���́@���b�Z�[�W
��1�́@���S�̌o�c�j�]�Ǝ������B�X�L�[��
��2�́@�S�����݂̎������B�X�L�[��
��3�́@JR�����{�Ɍ�������Ƃ̋���
��4�́@�h�C�c�̓S�����v�Ǝ������B�X�L�[��
��5�́@�r�W�l�X�Ƃ��Ă̎��_
���Ƃ���
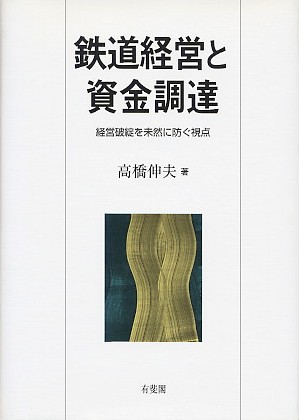
�@�����S���ɂ��Čo�ϊw�I�ȋc�_������̂ł���A�S���V�X�e���̂����炷�։v���Ƃ������o�ϓI�Ȍ��ʂ��Ƃ��������o�����ƂɂȂ�̂ł��낤��S���V�X�e���̔g�y���ʂ��l������A��ʂɂ��̌o�ϓI���ʂ͑傫�Ȃ��̂ł���A���������̋c�_�́A�f�l�������̂ł͗���s�\�Ȃقǂɍ��x�ŁA�����ۓI�ł��顂��������̖{�ł́A���̂悤�ȍ����ȋc�_�����̋�_�������o������͖ѓ��Ȃ�����̖{���͂����ƕʂ̏��ɂ���
�@�S�����Ǝ҂̎������B���ׂĂ݂���������v�������Ē��������ɒ��肵�Ĉȗ��A���̓��̒��ɂ́A������̋^�₪���邮��ƉQ�������Ă�������Ȃ킿�A
�@������ɐڐG���Ă�����Ђ������A���ڂ̒����ΏۂƂȂ����S�����Ǝ҂́A�����S�EJR�����{�A���{�S�������c�A�s�c�n���S�A�c�c�n���S�ł��������A���̓�̋^��Ɋւ��ẮA�������������Ƃ�������Ƃ��l�̏Z��[������{�I�ɕς��Ƃ���͂Ȃ��
�@�����̖ڐ��̍����œS���o�c�����߁A�����̎��Œ��ڊW�҂̘b�����ƂŁA�S���o�c�̕�������̖{�������ݎ�肽������ꂪ���̒��������̖ړI�ł�������������A���̓�̋^��ɑ��铚���͂܂��f�ГI�ɂ����������Ă��Ȃ���Ђ���Ƃ���ƁA������T���Ă��f�Ђ���������Ȃ��̂�������Ȃ���܂��͂��̏��͂ŁA�S���o�c�̕����Ă�����̑S�̑���f�`���Ȃ���A�E���W�߂������̒f�Ђ��͂ߍ���ł݂邱�Ƃɂ��悤����傤�ǔ��@���ꂽ�y��̔j�Ђ���y�������Ƃ��̂悤�ɡ�����������e�f�Ђ̏ڍׂȌ����͑�1�͈ȍ~�̖{�҂ōs�����Ƃɂ���
�@�o�c�w�҂ł���u���v�́A���݂̓S���o�c���l�@���邽�߂̏�����ƂƂ��āA�܂��́A���Ɍ��ʂ̏o�Ă��܂��Ă���u���ށv�Ƃ��āA���S�̎����I�����A�Ȃ����S���j�]�����̂���ǂ������邱�Ƃ���n�߂��B�Ƃ��낪���������ƂɁA�S���̒n�ʒቺ��l����c���A�����ĐԎ����[�J�����̑��݁\�\����܂ō��S�̌o�c�j�]�̌����Ƃ��ċ������Ă����v���́A���͒��ڂ̌����ł͂Ȃ������̂ł���B���ڂ̔j�]�����́A���S��1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v��̎������B�X�L�[���̎��s�ɂ������B
�@�܂�A�킩��₷�������ƁA���ǍH����ݔ��X�V�ɕK�v�Ȏ����������̍��Œ��B�������߂ɁA��B�����ɕ����c��݁A���������N�ł������Ȃ��o�c���j�]���Ă��܂����̂ł���B�������A���������K�v�����������̍��Œ��B����Ƃ��������ꒃ�Ȏ������B�X�L�[���ł́A�����Ɍo�c���j�]���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A�����̍��S���g�����O�Ɍx�����Ă����ɂ�������炸�
�@�������āA�o�c���e�ɗ������炸�Ƃ��A�������B�X�L�[�������ŁA���S�̌o�c�j�]�̃V�i���I�͂ł��Ă����Ƃ��������ׂ������B�S���̒n�ʒቺ��l����c���ȂNjN����Ȃ��Ă��A�����ĐԎ����[�J���������݂��Ȃ��Ă��A���S�̌o�c�͔j�]���Ă����Ƃ��������ׂ������ɁA�o�c�w�҂Ƃ��Ă̎��̖ڂ́A�ۉ������ɁA�������B�X�L�[���Ɍ������邱�ƂɂȂ�B�j�]�����͎������B�X�L�[���Ƃ������t���瑶�݂��Ȃ������̂ł���B
�@�����āA������i�߂Ă��������ɁA����ɋ������̂́A���݂ł��e�S�����(���m�ɂ͓S�����Ǝ�)�ŁA�������B�X�L�[����c�����Ă���l���ق�̐��l�������Ȃ��Ƃ��������ł���B���\���~�`���S���~�P�ʂ̋��z����������I�ɓ����Ă���ɂ�������炸�A��ʂ̐E����]�ƈ��́A�����̉�Ђ��ǂ̂悤�ɂ��Ď������B�����Ă���̂����m��Ȃ���A�����łǂ�ȗ��s�s�ȗ��������������Ă���̂����m��Ȃ��B�����āA���č��S���A���ꂪ�����Ŕj�]�������Ƃ��m��Ȃ��̂ł���B
�@�����Ŏ��́A�S�����݂ɓI���i���Ď������B�X�L�[���ׂ邱�Ƃɂ����B���S�̕������c���Ŏ����̗���͕��G�ɂȂ������A���{�ł́A�S�����݂̂��߂̎����͓�̑g�D���o�R���ė���Ă���B��͍��S�������c���̗����q�̖���ł���^�A�{�ݐ������ƒc�A�����Ă�����͓��{�S�������c�ł���B���̓�̑g�D��ʂ����⏕���A��t���A�����q�ݕt���A���������̗�������Ĕc������A�������B�X�L�[���̂��Ȃ�̕����͉���������B��������ς���ƁA�S�����݂̎������B�X�L�[���́A�������킸�A���Ȃ�̕��������̎��ƒc�ƌ��c�A���Ȃ킿���{�ɂ���Č��߂��Ă��܂��Ă���̂ł���B
�@���̌��ʁA���������ƂɁA�L���q�̋����S����ԍς���̂ɓ��Ă���ׂ������AJR�����{�EJR���C�EJR�����{��������Ă�����ݐV�������n����A�N�z7,424���~�̂����A����1,059���~���A�u��t���v���邢�́u�����q�ݕt���v�Ƃ��Đ����V�������̌��ݎ����ɒ������܂�Ă��邱�Ƃ��킩����(1997(����9)�N�x���Z)�B���S�������c���܂ł̊Ԃɐ�B�����ɖ�20���~�ɂ��c����S�̒������̗��q����d���Ȃ���Ԃł���̂ɁB
�@�����S�֘A�̘b�����ł͂Ȃ��B�s�c�n���S�̌��݂̂��߂ɔ��s����錚�ݍł́A���̗��q�����̎x�������扄���ɂ���A���̊Ԃ����Ƃ����L���q�����łȂ��ł���B���̂��߁A���ǁA���q���B�����ɓ]�����Ėc��܂��Ă��獑�ɂ������s�̈�ʉ�v�Ŏx�����Ƃ�������X�������Ȃ�s�ׂ��J��Ԃ���Ă���B�ǂ������������s���x�����̂ł���A���q�Ŗc��ޑO�Ɏx�����Ă��܂����������オ�肾�Ƃ����̂��Љ�I�ȏ펯�ł͂Ȃ����낤���B��́A���̍��ŁA���S�̌o�c�j�]�̋��P�͐�������Ă���̂��B��́A�ǂ�ȃ|���V�[������Ƃ����̂��낤���B
�@���ہA�������B�X�L�[���̉��p���Ƃ��āA�P�[�X�E�X�^�f�B�[�I�ɉc�c�n���S�Ɠs�c�n���S�̒n���S���ݔ�̎������B�X�L�[�����r���Ă݂�ƁA�����悤�ȋƑԂɂ�������炸�A�c�c�̕��������������ł̎������B���������Ă�����������c�c��k���̌��݂ł́A���ݍH�����n�܂�������A���x�ƂȂ��������B�X�L�[�����ύX����Ă��������ł͂Ȃ��A�⏕�����̂��̂�8�N�Ԃɂ��킽���ē�������Ă���������ɍ��̗\�Z�͒P�N�x��`���Ƃ����Ă��A�ւ�������Ǝ����J��ɂ����肩�˂Ȃ����Ԃł͂Ȃ����B���̑��ɂ��A�⏕���̏o�����́A����̈�ѐ��ɋ^�����������悤�ȕϓ]���߂܂��邵�������Ă���
�@���{�ƍD�ΏƂ��Ȃ��Ă���̂��h�C�c�ł��顃h�C�c�ł́A���{�̍��S�������c�������f���ɂ��Ă���Ƃ�������S�����v(Bahnreform)��1994�N�ɍs���āA�������h�C�c�̍��S�̓h�C�c�S���������(DBAG)�ɐ��܂�ς������������h�C�c�ł́A�S�������ł͂Ȃ����H���܂߂���т�����ʐ����c�_���S�����v�O���瑶�݂��Ă����B�h�C�c�ł̃C���^�r���[�����ɂ����āA�S�����v�Ɏ�����̃h�C�c�̓S������A�ߋ��̎������s���̏W�ςƂ��Ăł͂Ȃ��A���ꂼ��̒����I�Ȑ���Ƃ��Č���Ă������Ƃ͐V�N�ȋ����ł������B�������S�����v�O�ɂ́A���������������̒����c��(����т�������)���A���S�Ƃ������іڂŕ��G�ɗ��ݍ����Ă��܂��Ă������߂ɁA�S�����v�ɂ���āA���̌��іڂ𓌐��h�C�c���S���ĕ҂��邱�Ƃʼn����ق����A���ꂼ��̏c���ɐ���Ƃ��Ă̈�ѐ����m�ۂ����̂��ƍl����Ɨ��������₷���B
�@���̌��ʁA�h�C�c�ł́A�S�����݂ɔ���Ȑݔ����������𓊓����邽�߂̎������B�X�L�[���́A�S�����v��ʂ��āA���V���v���Ȃ��̂ɐ����������B�A�M���{�̊W�����ȕ⏕���A�����q�ݕt����GVFG�ADBGrG�ABSchwAG�ȂǂƁA���̍����@�̗��̂ŌĂ�Ă��邱�Ƃ͈�ۓI�ł���B����Ɣ�ׂē��{�ł́A���S�������c���͍��S�́u���Z�v���Ӑ}�������̂ł���A�i�i�ɊȒP�ȍ�Ƃ������͂��ɂ�������炸�A�������c����A���[�����ꓖ����I�ɃR���R���ς��A�������B�X�L�[�����������ĕ��G�����Ă��܂�����܂��ɍD�ΏƂł���B
�@�������B�X�L�[�����d�v�ł���̂́A�S�����݂��S���o�c����{�I�ɂ͋����Ƃ̋����ł���Ƃ������������R�Ƃ��ė����͂������Ă��邩��ł���B���ݎ��������ꂾ�����z�ɂȂ�ƁA�J�Ǝ��_�܂łɗݐς���L���q���z��������E���Ă��܂��A���͂�ǂ�ȂɊ撣���Ă��A�c�Ɨ��v�͗��q�̎x�����ɂ��ǂ����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂���������Ďx�������ʼnc�Ɨ��v��������Ԃ悤�ȏ��ɒu����Ă��ẮA������c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă����ꂸ�A�؋��͐�B�����ɖc���ŁA�������c�Ɠw�͎��̂��Y�ꋎ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B���̂��Ƃ������͍��S�Ƃ����u���ށv�Ŋw��ł����͂��ł͂Ȃ������̂��B
�@�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ́A�܂����ɁA�����̂Ȃ��������B�X�L�[�����ŏ��ɍH�v����K�v�����顂܂�A�@�ł��邾���⏕���△���q�ݕt�������ē������ۂŎ������B���A�A�L���q���͂ł��邾��������̂��̂ɂ��āA�B�⏕���A�����q�ݕt���A�������ۂ��ł��邾���������_�œ������A�L���q�����̓������ł��邾���x�点��K�v�����顂������ĊJ�Ƃ܂ł̊Ԃɂǂ����Ă��c���ł��܂��L���q�̕��z���ł��邾�����k����̂ł���
�@���ɁA���x�́A���H����J�Ƃ܂ł̊��Ԃ��ł��邾�����k���邱�Ƃł��顊J�Ƃ���܂ł͎������Ȃ��킯�ł��邩��A���R�����Ƃ��ɕԍς��ł���킯���Ȃ��A���̊Ԃ̗����ŗL���q���̊z�͐�B�����ɖc���ł����Ă��܂�����ɁA���ݎ�̂��o�c��̂ƕʂɂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�v���ӂł��顒��H����J�Ƃ܂ł̊��Ԃ����т�A�u�Ȃ������v�̗L���q������B�����ɖc��ނ��A���̃��X�N�����ݎ�̂ƌo�c��̂��V�F�A����悤�Ȏd�g�݂��܂��Ȃ�����̂��ߗp�n��������n�܂�H�����Ԃ����тĂ��A���ݎ�̂ɂ͉��̒ɂ݂�����Ȃ��̂ŁA�H�����Ԃ̉����Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ顂��ꂪ�����߂��ł���A���Ȃ��Ƃ������J�Ƃ�ڎw���ӋC���݂��Ⴄ���������Ėc���ł��܂������z�̗L���q���̂��߂ɁA�J�ƑO�Ɂu�j�]�v������I�ɂȂ����o�c��̂̃P�[�X������ƋƊE�ł͉\����Ă��顓S���̌��݁E���ǂƌo�c�������㉺�������������ł͉��̖������ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B���X�N�E�V�F�A�����O�̎d�g�݂����Ȃ���A�ނ��뎖�Ԃ�����������\���̕����傫���B
�@���̃|�C���g�A�����̂Ȃ��������B�X�L�[�����ŏ��ɍH�v����K�v������A�Ƃ������Ƃ������ɗᎦ���Ă���̂��A�n���S���݂̎������B�X�L�[���ł��顂��Ēn���S���݂ւ̕⏕���́A�v�z�ł͌��ݔ�p�̔����ȏ���o���Ă��邱�ƂɂȂ��Ă�����Ƃ��낪�A�^�c��⏕�Ƃ���10�N�ȏ�ɂ킽���Ă��炾��ƌ�t����Ă������߂ɁA��Ԏ������K�v�Ȍ��ݎ��ɂ͂قƂ�ǎ������Ȃ��A���ǁA�S�����Ǝ҂��A���ݎ����̑������u�Ȃ��v�Ƃ��Ďs����s����̗L���q���Œ��B����������Ȃ��������������ĊJ�Ƃ܂ł̌��ݒi�K�Ő�B�����ɖc��ޗL���q���̊z�����܂�ɋ��z�ɂȂ��Ă��܂����߂ɁA���ǂ́A���̂��Ƃ��炾��ƌ�t�����⏕���͗��q�⋋�ɂ����Ȃ�Ȃ������̂ł���B
�@������1992(����4)�N�ȍ~�̃��[���ŁA���ݎ��ꊇ��t�̎��{��⏕�����ɕύX�ɂȂ�A���Ԃ͍D�]���題��ݎ��̈ꊇ��t�ŁA�J�Ƃ܂ł́u�Ȃ��v�̗L���q���̊z���ȉ��Ɉ��k�ł��A�Ђ��Ă͗��q�̊z�������ȉ��Ɉ��k�ł���悤�ɂȂ����̂ł���B���̂��߂ɁA�����⏕�����ቺ�����ɂ�������炸�A�n���S���Ǝ҂̎������S�͑啝�Ɍy�����A���v�\���̉��P�ɑ傢�ɍv�����邱�ƂɂȂ�B�܂蒲�B����鎑���̊z�����ł͂Ȃ��A�����B����X�L�[���ɂ���Ă��A�J�ƌ�̓S���o�c�͌���I�ȉe������̂ł���B
�@�S�����݂ɕ⏕���𓊓�����ꍇ�A���̂悤�ɁA�⏕�������{��⏕�Ƃ��Č��ݎ��ɏW���������A�L���q���z�ƍH�����Ԃ̗������ł��邾�����k���邱�Ƃ��̗v�ł���B����قǗL���q���̑��݂͏d���ł���A�⏕���𔖂���T�����Ƃ̓h�u�ɋ����̂Ă�悤�Ȃ��̂ł��顂����Ď��́A�L���q�����B���Ȃ���S�����݂��s�����Ǝ��̂��A���܂⍑�۔�r�㓖����O�̂��Ƃł͂Ȃ��B
�@�Ⴆ�h�C�c�ł��顃h�C�c�ł͓S�����v�����A�S���ɑ��锜��Ȑݔ�������K�v�Ƃ���Ɋׂ��Ă����B���Ƃ��Ƌ����h�C�c���ł����H��A�E�g�o�[�����D�悳��A�S���ւ̐ݔ��������x��Ă������A����ɋ����h�C�c�̍��S�̐ݔ��͗ŁA���f����Ă��������h�C�c�����ԘH�������}�ɐ�������K�v���������B�������Ԏ������ŋ��z�̗ݐϐԎ�������鍑�S������ȃC���t�������S�ł���킯���Ȃ��A����ɘA�M���{���������S���邱�ƂɌ��߂��̂ł���B1999�N����n�܂����S�����v�̑��i�K�ł́A�V�����݂͂��ׂĘA�M���{�̕⏕���ŁA���ǍH���͘A�M���{����̖����q�ݕt���ƓS�����ƎҎ��g�̓������ۂŘd�����ƂƂ����B���{�̂悤�ɁA�S�����݂̎������B�����ՂɗL���q���ɋ��߂��A�S�z��⏕�����ō������S����o������߂��Ƃ������Ƃ͒��ڂɒl����B
�@����ł́A���ɋ��z�̎؋������Ă��܂��Ă���ꍇ�ɂ͂ǂ�����̂������́A�����ł�������̃��[���Ɏ芷����Ƃ����̂��A�Љ�I�펯�ł��낤����ہAJR�����{�́A���������̒ǂ����𗘗p���Ē���������B���A���̎����ō��S����̍������̓S�����J�グ�ԍς��邱�ƂŁA�������c���O���7.13%���������������̕��ϗ������A���̌�10�N��5%�ȉ��ɂ܂ŗ}���邱�Ƃɐ��������JR�����{�̒������̊z��5���~�߂��̂ŁA2%�̈Ⴂ�͔N��1,000���~�ɂ��Ȃ�
�@�Ƃ��낪�A����������J��Z���͌J�グ�ԍς𐧓x�I�ɋ����Ă��Ȃ��������A�V�������Ȃǂ́A�K���͌J�グ�ԍς��\�������ɂ�������炸�A���ۂɂ͂���u�����v�܂ŌJ�グ�ԍς�F�߂Ă��Ȃ�������ł��邾���������ő݂��t�����܂܂ɂ��Ă����������{����JR���Ƃ̉��x���͍L�������ł��顔�r�I������Ƃ͂����A�J�グ�ԍς��ł��Ȃ����������ɂׂ����藊���āA�P�N�x��`�̏ꓖ����s���ɖ|�M�������́A���Ђ̌o�c���e�ɒ��ӂ��Ȃ���s��ł̍����i�t�����ێ����A������̂Ƃ��Ƀ^�C�����[�Ɏs��Ŏ������B����������A��ƂƂ��Ăǂꂾ�����S�Ȃ��Ƃ��JR�����{�Ɍ��炸�A�����E�p�ɂ�鎑�����B�̎����������A�^�̖��c���̎p�Ȃ̂ł���
�@�����Ă�����A�������B�̎����ł����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A�S�����ƎҎ��g�ɐݔ��X�V��V�K�����̂��߂̓������ۂ������Ɋm�ۂ����邩�Ƃ������Ƃł��顏��Ȃ��Ƃ��������B�X�L�[���Ɋւ��ẮA�S�����Ǝ҂́u���Ȍ��茴���v���т�����ׂ��ł��顊�Ƃ́A���炠�������v�ɑ��āA������������錠���������Ă�������A���͑����䖝���Ăł����v�������A�����Ɠ������ۂ̌`�ŁA�����̊g�哊���̂��߂ɒ�����̂ł���B���ہA���c����̋����Ђ̃p�t�H�[�}���X����ɖ{���I�ɏd�v���������̂́u���Ȍ���v�ł������B�o�c�w�I�ɂ́A�������ۂ��܂߂��������B�X�L�[���̎��Ȍ��茴���̊m���������]�܂����B
�@������x�A���S�̒��ڂ̔j�]�����ƂȂ�����O�������v��ɂ��ĐU��Ԃ��Ă���������͂��̎����A���S�́A�V�����݂ł͂Ȃ��A���ǍH����ݔ��X�V�̕K�v�����������̍��Œ��B�������߂ɁA��B�����ɕ����c��݁A���������N�ł������Ȃ��o�c���j�]���Ă��܂��Ă����̂ł���B����ł́A�Ȃ����S�́A���ǍH����ݔ��X�V�̕K�v�������炢�A�������ۂ̌`�ŗp�ӂ��Ă����Ȃ������̂��낤������̌����́A���\�Ȍ�����������ƁA���S�̓������ە��ɑ��鐭�{�ƒn�������̂́u������v�ɂ������1949(���a24)�N�̍��S�����ȗ��A���̎Љ�E�����E�Y�Ɛ���Ƃ̊֘A�ŁA�ʋE�ʊw����A���ʈ��V�����E�G�����̌`�ŁA���̌������������ꂽ�^����̌������S��1967(���a42)�N�x�܂ł̗v��9,514���~�ɒB���顂����1956(���a31)�N�x����n���������S���̂��߂ɉۂ��ꂽ�s�����[�t����1967(���a42)�N�x�܂ł̗v��997���~�ɂȂ額��v�����1��0511���~���̎������A����n�������̂̎�ō��S����ނ���Ƃ��Ă������ƂɂȂ顂��̋��z���A1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v��̍ŏ���3�N�ԂɁA���S�����B�����ݔ����������̍��v�z1��0204���~�ƂقƂ�Ǔ��z�Ȃ̂́A����Ȃ���R�ł��낤����������ꂾ���̎������������ۂ���Ă���A���S�͌o�c�j�]���Ȃ��Ă��ς͂��Ȃ̂ł��顂��ꂪ�������B�����Ɏ؋���20���~�ɂ��c��ނ��������ƂȂ����̂�����A�����ƍ����������̂ł��顂��̏ꂵ�̂��Ŗڐ�̋��ɌQ����A������͂���ɍ������ƂȂ��Ē��˕Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ�
�@�Љ�I�펯�ł́A�S���Ɍ��炸�A�{�݂̌��݂͒����̃g�[�^���E�R�X�g�ōl����ׂ��ł���B���݃R�X�g�̑��ɁA���Ȃ��Ƃ������e�i���X�E�R�X�g��x���������v�Z�ɓ����ׂ��ł���B���̓�����O�̂��Ƃ����H�����邽�߂ɍ����ɋ����ꂽ�����Ƃ��L���ȑI�����́A��v�����@�������̎��_��ς��邱�Ƃł��顏]���̉�v�����@�̌����́A��ʂɖڂ̑O�́u���m�v�Ɏ��삪���肳�ꂪ���ł������B�������A�����Ȃ錟���Ώۂ��u�r�W�l�X�v�Ƃ��Ă̍L����������Ă���B�g�[�^���E�R�X�g�̎��_����A��v�����@���������B�X�L�[���̎��O�������s���悤�ɂȂ�A���S�̗�ɂ�����悤�ɁA�e�ׂȌo�c���e�ɗ������炸�Ƃ��A��r�I�e�Ղɋ��z�̍����𖢑R�ɉ�����邱�Ƃ��ł���B�o�c�j�]�܂ōs���Ȃ��Ƃ��A�ŏ��ɓ�������⏕���E�����q�ݕt���̊z���o���ɂ��݂��Ă���ƁA���̕��������L���q�����̂����ŁA�����I�Ɍ���ƍ������������đ傫�ȕ��S���������邱�ƂɂȂ�̂͌��R���鎖���Ȃ̂ł���B
�@���Ȃ��Ƃ��A���S�o�c�j�]�O��̂悤�ɁA�����Ҏ��g���댯�M�����Ă���ꍇ�ɂ́A��v�����@�͎��O�����𗦐悵�čs���ׂ��ł���B���̍ۂ̃|�C���g�́A���炩�ɍ��K���ł͂Ȃ��B���@�I�Ȏ������B�X�L�[���ł��A���������܂߂����̕ԍόv�悪�j�]���Ă���A�펯�I�ɍl���ăi���Z���X�Ȃ̂ł���B�ǂ�Ȃɔ�펯�Ȃ��̂ł��A�@����������Ă��܂��Εs�������Ƃ��Ďw�E����邱�Ƃ͂���܂��Ƃ����u�m�M�Ɓv�ɑ��āA��v�����@�͎���̌����}�C���h�ɗ����Ԃ��ăN���[��������ׂ��ł���B���O�����������ł��A���߂Ď������B�X�L�[�����g�[�^���E�R�X�g�̎��_���玖�㌟������Ɛ錾���ׂ��ł���B������A�⏕���△���q�ݕt���A����ɂ͗L���q�̍����������g�����������B�X�L�[�����ς�炴������Ȃ��Ȃ�͂��ł���
�@���{���L�S��(�ȉ��u���S�v�Ɨ��L)�̌o�c�j�]�̌����Ƃ��āA����܂ł́A�Ⴆ�A�S���̒n�ʒቺ��l����c�����������邱�Ƃ����������B���������̏͂ł́A���S�̌o�c�j�]���������B�X�L�[���̑��ʂ��瑨���������Ƃɂ��悤�B���S��1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v��́A���������������B�X�L�[���̒i�K�Ŕj�]���Ă����̂ł���B
�@1963(���a38)�N5��10���ɍ��S����ψ�����S���قɒ�o�����u���S�o�c�݂̍���ɂ��āv�́A1970(���a45)�N�x�̌o�c��Ԃ����Z���A�ؓ����̏��ҁE�������Ȃǂɂ��u�o�c�̊��S�j�]�v���x�����Ă����B�w���{���L�S���S�N�j�x(�ȉ��w���S�j�x�Ɨ��L)�̑�12��(1973, p.161)�ɂ��ƁA�u����̗A�����v�́A�\���Ɖ]���Ȃ��܂ł��T�˖����ł��邱�Ƃ�ڂǂɁA���̏����A���Ȃ킿�^�����x���͌�����ێ����A�x�[�X�E�A�b�v���͌�����ێ��������͌��݂܂ł̐�����H����̂Ƃ��āv�o�c��Ԃ̎��Z���s���ƁA1970(���a45)�N�x�ɂ́A
�Ƃ��āA�u����͌o�c�̊��S�j�]�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��v�ƌ��_�����̂ł���B
�@���ہA���̂���3�ɂ��ẮA��ł��G��邪�A���S�����B�����ݔ����������́A1965(���a40)�N�x����3�N�Ԃ́A3,266���~�A3,304���~�A3,634���~�Ƃقڗ\�z�ʂ�ɐ��ڂ��A�S�z���L���q���ł���ؓ����ƍ��ɂ����̂ł������B����͓���1965(���a40)�N�x����1971(���a46)�N�x�܂ł�7�N�Ԃ�\�肵�Ă�����O�������v��Ɋ�Â������̂��������A���̒����v��͂킸�����N�Ŕj�]���A1969(���a44)�N�ɂ́u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�����肳��A����ɂ��1968(���a43)�N�x���̐��{�Ǐ����ɌW�闘�q�̍Č����Ԓ��ɂ����鎖����̒I�グ���̍����[�u���Ƃ�ꂽ�B������1969(���a44)�N�x����͍����Č��v��ɕύX���ꂽ�̂ł���B
�@���Z�̌��ʂƎ��ۂ̐����Ƃ��r���Ă݂悤�B�w���a45�N�x ���{���L�S���č����x�ɂ��ƁA1970(���a45)�N�x���Z�́A
�ł������B�r���ʼn^���l�グ�������āA1�̎������������Ȃ��Ă͂�����̂́A2, 4�́u�o�c�̊��S�j�]�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��v�ƌ��_�������Z���ʂ�������Ɉ������e�ł������B
�@��O�������v��́A����1965(���a40)�N�x����1971(���a46)�N�x�܂ł�7�N�Ԃ�2��9000���~�̋K�͂��v�悵�Ă����B������v��܂ł͍��S�Ǝ��ɍ��肵�����̂������̂ɑ��āA��O�������v��́A���{�^�}�̍��S��{��蒲�����ѐ��{�̍��S��{��荧�k��ŐR�c����A1964(���a39)�N12���̌o�ϊW�t�����k��y��1965(���a40)�N1���̊t�c�����ċ��͂ɐ��i���邱�ƂƂȂ��Ă���(�w���S�j�x1973, Vol.12, p.646)�B�Ƃ��낪�A��O�������v��͂킸�����N�Ŕj�]���A1969(���a44)�N�ɂ́u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�����肳��A1969(���a44)�N�x����͍����Č��v��ɕύX����Ă��܂��̂ł���B
�@���̊ԁA���S�͈�̉��ɐݔ����������Ă����̂��낤���B������1965(���a40)�N�x�`1968(���a43)�N�x�̍H����Z�z�ł݂Ă݂�ƁA�S�̂�1��3411��6000���~�̂����A���H���ݔ�3238��1000���~�A�ԗ���2903��2000���~�A��ԏ�ݔ���2114��7000���~�ƑS���Z��70%���߂Ă����B��s�s�ʋΒʊw�A���́E�����A���͂̑����A�ԗ�����A�d���A�d�ԉ��ADC������ш��S�m�ۂɏd�_���u����Ă����Ƃ�����(�w���S�j�x1973, Vol.12, p.701)�B���́A1963(���a38)�N�x���ɓ��{�S�������c�ɐV�����ݍH�����ڍs���A���C���V������1964(���a39)�N�x�ɂ͊J�Ƃ��Ă���A�R�z�V�������ݍH�����J�n���ꂽ�̂�1967(���a42)�N�x����ł���(�w���S�j�x1973, Vol.12, p.696)�B�܂�A����قǂ̐ݔ������K�͂ɂ�������炸�A�ӊO�Ȃ��ƂɁA���̎����̍��S�͐V�����݂����܂肵�Ă��Ȃ������̂ł���B���������āA���̎����̍��S�̌o�c�j�]�̌�����Ԏ����[�J�����ƂȂ�V�����݂ƌ��ѕt���邱�Ƃ͐������Ȃ��B
�@�w���S�j�x(1973, Vol.12, pp.164-166)�ł́A�����������S�̌o�c�����̌����̈�Ƃ��āA��ʋ@�ւƂ��Ă̓S���̒n�ʒቺ�ŁA�^���l�グ�ɂ��v���悤�Ɏ������m�ۂł��Ȃ��Ȃ������Ƃ������Ă���B���̊ԁA���ɐG�ꂽ�悤�ɁA�^���̒l�グ�ɂ��������������A1966(���a41)�N3���ɂ́A��O�������v��̐��s�ɕK�v�Ȏ������m�ۂ��邽�߂ɁA���q31.2%�A�ݕ�12.3%�A�b�v�̉^���������s���Ă���B���������̎��́A���p���Ȃǂ̂��߂ɁA8,239���~�Ɨ\�肵�Ă����^�A�����͎���7,684���~�ɂƂǂ܂�A�\���傫����������Ƃ�����(�w���S�j�x1973, Vol.12, p.162)�B�܂�A���͂�^���̒l�グ�ɂ���Ď������m�ۂ��邱�Ƃ͍���ȏɂȂ��Ă����̂ł���B
�@����́A�S���̒n�ʒቺ�A���Ȃ킿�A����i�Ԃ̋����������������߂ł���B�w���S�j�x(12��, pp.164-166)�ɂ��A���ۂɂ́A��㒼��A��Ђɂ���ē��q�C�^���قƂ�lj�ł��A�����Ԃ���������̉����Ă�������Ȏ����ɂ����A�S���������V�F�A���ւ��Ă������̂́A���̌�A���������A����i������ɂ��������āA�V�F�A���ቺ���Ă������B1955�N�x�`1965�N�x�ŁA�������ݕ��A����(�L���g��)���N����8.6%�����������ŁA�S���͎��S���܂߂ĔN����2.8%�����������Ȃ������B���̊ԁA���q�C�^��10.8%�A�����Ԃ�17.7%���̐����𐋂����̂ƍD�ΏƂ��Ȃ��Ă���B�������āA���q�ɂ��܂��ĉݕ��A���̕���ō��S�̐��ނ͒����������̂ł���B���̂悤�ȑ��l�Ȍ�ʎ�i�̋����I�����̎���f���āA1966�N3���ɗ��q31.2%�A�ݕ�12.3%�A�b�v�̉^�������������ۂɂ́A�Ƃ��Ƃ��\�肵�Ă����^�A�������m�ۂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B
�@�ʂ̌����Ƃ��ẮA�l����̋}���Ȗc������������(�w���S�j�x1973, Vol.12, pp.168-170)�B���̊Ԃ̒��ٍْ�̃x�[�X�E�A�b�v����6�`10%�̍����������A���������̗��͎���ɍ����Ȃ��Ă������B���ٍْ�̊��S���{�̂��тɁA���S�����̏��v�z���\�Z�ł͘d������Ȃ��قǂł������B�������x�[�X�E�A�b�v�ŐE����l������̐l����啝�ȏ㏸�������������ł͂Ȃ��A���S�̐E���̔N��\�����u���Ԃ���`�v�����Ă������߂ɁA���̒��Ԃ��ꕔ���ɓ�����6�����߂�E���w���A1967(���a42)�N���ɂ�35�Έȏ�50�Ζ����ɓ��B���A�N���������Ől�������ɋ}���ɖc�������̂ł���B���v����ɂ�����l����́A1960(���a35)�N�x��1,863���~���A1967(���a42)�N�x�ɂ�3,849���~�ɔ{������B
�@�������A���Z���ʂ����������S�́u�o�c�̊��S�j�]�v�̌�����S���̒n�ʒቺ�Ɛl����c���ɋ��߂�̂͐������Ȃ��B�����������Z�́A�ؓ����̏��ҁE�������Ȃǂɂ��u�o�c�̊��S�j�]�v���x���������̂Ȃ̂ł���B����x�A���Ӑ[�����Z�̏������������ė~�����B�u����̗A�����v�́A�\���Ɖ]���Ȃ��܂ł��T�˖����ł��邱�Ƃ�ړr�ɁA���̏����A���Ȃ킿�^�����x���͌�����ێ����A�x�[�X�E�A�b�v���͌�����ێ��������͌��݂܂ł̐�����H����̂Ƃ��āv���Z���Ă���̂ł���B�܂莎�Z�̍ۂɂ́A�^���ƃx�[�X��A�b�v�͏����Ƃ��Č���ŌŒ肵���܂܂Ōv�Z���Ă���A����ł����Z��A�o�c�͔j�]����ƌ��_���o���Ă������ƂɂȂ�B
�@���ہA�S���̒n�ʒቺ�̖��́A�m���ɐ[���Ȗ��ł͂��邪�A���Z�̎��ɂ͑z�肵�Ă��Ȃ������^�������̑������͎̂����ł����킯�ŁA1�̔N���͎��Z����3,000���~�ȏ�����Ă���B������̗v���ł���1963(���a38)�N�̎��Z��ɐ[���������l����̖c���́A2��1,549���~�̑����̔����Ƃ����\����������Ɉ������������o���v���ɂ͂Ȃ������A���Ƃ���1963(���a38)�N�̎��Z�i�K�ł͑z�肳��Ă��Ȃ��������ԂȂ̂ł���B
�@�܂�A�����Ŏ��Z����Ă����o�c�j�]�Ƃ́A����I�ɕ\�ʉ������S���̒n�ʒቺ�̂����ł��A�l����̖c���̂����ł��Ȃ��A�������B�X�L�[���̎��s�ɂ��j�]�̂��Ƃ������̂ł���B�A�����v�ɒǂ������߂Ƃ�����`�����̉��ɁA�������B�̌��E���āA3�ɂ���悤�ɔN��3,300���~���̐V�K�������ؓ����Ŏ������B���Ȃ��瑱�������Ɍ}����ł��낤���������Z�������̂������̂ł���B���z�̗L���q�����B�������ʁA4�̂悤�ɋ��z�ɖc�����������琶���闘�����܂��c��ނ킯�ŁA����2�̂悤�Ȃ��肬��̎��x�ɂ��钆�ŁA���ɗ�������x��������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ԃ��o������A�������x�������߂ɂ���Ȃ�ؓ������B���J��Ԃ���A������B�����ɖc��ވ��z�Ɋׂ�̂ł���B�S���̒n�ʒቺ��l����c���Ƃ������o�c���e�ɗ�������Ȃ��Ă��A�������B�X�L�[���̎��s�����ŁA���S�̌o�c�j�]�̃V�i���I�͂ł��Ă������ƂɂȂ�B
�@����ł́A�����̍��S�́A�����������ǂ̂悤�ɒ��B���Ă����̂ł��낤���B���́A���݂̓S�����Ǝ҂̎������B�X�L�[���̏펯����͑z�����ɂ������ƂȂ̂����A�����̍��S�ɂ́A�����Ƃ��ĕ⏕���͌�t����Ă��Ȃ������B�⏕������t�����悤�ɂȂ����̂́A���S�̌o�c������������̂��ƂŁA1969(���a44)�N�́u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�Ɋ�Â��āA���v�⏕��ړI�ɁA���a43�N�x����J�n���ꂽ�u�H����⏕���v���ŏ��ł���B�܂�A���̎��Z���s��ꂽ�����̍��S�́A�⏕�����Ȃ��ɁA�������ۂƗL���q�������������Ƃɂ��ēS�����݂��s���Ă������ƂɂȂ�B
�@���������āA�����̍��S�ł́A�T�˕\1-1�̂悤�ɐ�������钷�������̒��B���@���p�����Ă����B����́A���S�̌o�c���j�]�������Ƃō��̒I�グ�̂悤�Ȏ��Ԃ��}����܂ł͕ς�肪�Ȃ��B���������̒��B���@�Ƃ��ẮA�`�ԓI�ɂ́A�ؓ����ƍ�(�S����)�̓�ɕ������A����ɒ��B��ɂ���č��������Ɩ��Ԏ����̓�ɕ�������B���������������B�̘g�g�݂́A��{�I�ɁA���c���㐔�N�ʂ܂ł�JR�e�Ђ��͂��߂Ƃ��āA���݂̓S�����Ǝ҂̈ꕔ�ɂ������p����Ă���B
�\1-1. ���S�̒��������̒��B���@
| �`�Ԃɂ�镪�� | ���B��(�ؓ���E�����)���猩������ | |
|---|---|---|
| �������� | ���Ԏ��� | |
| �ؓ��� | �������Z���ؓ��� | ���ԋ��Z�@�ւ���̎ؓ��� |
| �S���� | ���{����� | ���{�ۏ؍A���ʍ�*�A���p��*�A���̍�* |
�@�����Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂́A���{�ۏ؍͒��B��ōl����Ζ��Ԏ����ł͂��邪�A�������Z��(����)�̘g���Ƃ��Ĉ�����Ƃ������Ƃł���B�������Z���Ƃ́A���̐��x�E�M�p��w�i�Ƃ��ďW�߂���e��̌��I�����������ɂ��čs���鐭�{�̓��Z�������̂��Ƃł���A�Ώo�̂悤�Ɏg�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A������Z�ʂ��ċ�����t���ĕԍς��Ă��炤�L���q�����̊��p���w���Ă���B�������Z���v��́A
�Ƃ������������Ƃ�[1]�A�e�N�x�̗\�Z�̈ꕔ�Ƃ��č���̐R�c�A�c�����o�Č��߂��Ă���B���̂����A4 ���{�ۏ؍E���{�ۏ؎ؓ����́A���S�̂悤�ȍ����Ώۋ@�ւ����疯�Ԏ����B����̂ł͂��邪�A���̍ہA���{(��ʉ�v)�����̌���������ۏ��A�����ʁA���s�������̌������{���ꊇ���Ă���ɓ����邱�ƂŐM�p�͂����߂Ă�����̂ł���B���{�́A���N�x�A�\�Z�ɂ����Ē�߂�ꂽ���z�͈͓̔��ŁA�����邢�͎ؓ����̍��ۏ��s���Ă���B����������������āA���{�ۏ؍͒��B��ōl����Ζ��Ԏ����ł��邪�A�������Z���̘g���Ƃ��Ĉ�����̂ł���B
�@���ɏq�ׂ��悤�ɁA1969(���a44)�N�ɐ��肳�ꂽ�u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�ɂ��A1968(���a43)�N�x���ɍ����[�u���Ƃ��Ă���̂ŁA���̑O�N�܂ł̃f�[�^���������Ƃɂ���ƁA�\1-2�Ɛ}1-1�̂悤�ɂȂ�B���ꂩ����킩��悤�ɁA���a30�N��ɂ͐ݔ������̑唼���������Z���ɂ���Ęd���Ă������̂��A���Z���s��ꂽ������2�N��A1965(���a40)�N�x���獑�S�����肵����O�������v��ł́A���̏��N�x����n�߂�ꂽ���ʍ̔��s�ɂ���āA�������Z���̔�d���ꋓ�ɒቺ�����̂ł���B
�\1-2. ���S�̊O������̐ݔ��������B��(����)*�@�@�@�@�@�@�@(�P��: ���~)
| �N�x(����) (���a) |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| �� �� �� �� | �������Z�� | �ؓ��� | 115 | 55 | 80 | 200 | 265 | 250 | 70 | 626 | 509 | 675 | 435 | 281 | 445 |
| ����؊� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 127 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ���{����� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 | 200 | 420 | 230 | 160 | 100 | 463 | ||
| �� �� �� �� | ���{�ۏ؍� | 125 | 240 | 158 | 142 | 240 | 300 | 330 | 360 | 550 | 630 | 1,255 | 1,540 | 1,407 | |
| �������Z�� �ȊO | ���̍� | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 70 | 55 | 120 | 110 | 100 | 145 | 138 | |
| ���p�� | 3 | 13 | 18 | 84 | 60 | 69 | 110 | 76 | 100 | 143 | 140 | 135 | 141 | ||
| ���ʍ� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 1,103 | 1,040 | ||
| ���B���z | 243 | 308 | 256 | 461 | 610 | 739 | 805 | 1,444 | 1,776 | 1,788 | 3,266 | 3,304 | 3,634 | ||
| ���q�y�э��戵���� | 97 | 116 | 136 | 156 | 178 | 240 | 229 | 252 | 252 | 386 | 646 | 835 | 1,012 | ||
| ���������̐�߂銄�� | 47% | 18% | 31% | 43% | 43% | 50% | 37% | 66% | 57% | 51% | 18% | 12% | 25% | ||
| �������Z���̐�߂銄�� | 99% | 96% | 93% | 74% | 83% | 91% | 78% | 91% | 88% | 86% | 57% | 58% | 64% | ||
�}1-1. ���S�̐ݔ������ɐ�߂�������Z���̊���
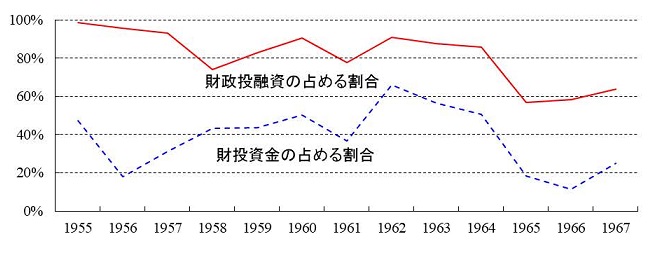
�@�������A�������Z���̔�d���ቺ�����Ƃ����Ă��A���̐�Ίz�͂ނ��둝���Ă���Ƃ������Ƃɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����́A�}1-2���悭�\���Ă���悤�ɁA1965(���a40)�N�x�ɑ�O�������v��̒���ɂƂ��Ȃ��A����܂ŁA���N1,800���~�ɂ��B���Ă��Ȃ������ݔ��������B�K�͂̂Ƃ���ɁA�ꋓ��1,000���~�ȏ�̓��ʍ������̘g�O�Ŕ��s���Ď�����lj����B�������߂ɍ����̔�d���ቺ�����̂ł���B�w���S�j�x (1973, Vol.12, pp.688-691)�ɂ��A��O�������v��̏��N�x�ɓ�����1965(���a40)�N�x�̗\�Z�v���ɍۂ��āA���S�͍������Z���̑啝���z��v���������A�呠�Ȃ͓�F�������A���{�ۏ̂Ȃ��V�����S�����A���Ȃ킿���ʍ̔��s�ɂ���Ď������B�����邱�ƂɂȂ����Ƃ����B
�}1-2. ���S�̊O������̐ݔ��������B��
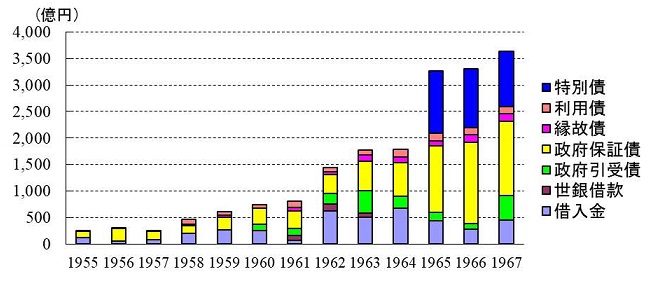
�@�������āA���{�ۏ̂Ȃ���荂�����̓��ʍ������̘g�O�ő�ʂɔ��s�����悤�ɂȂ������ƂŁA1967(���a42)�N�x�ɂ́A�����R�X�g�͔N������7.1%�ɂ��y�сA�x��������1955(���a30)�N�x�̂Ȃ��10�{���ɂ��B����̂ł���B���̊Ԃ̗��q�����̐L�т�4.4�{�A�ݕ������̐L�т�2�{�ł��������Ƃ��l�����킹��ƁA���Ԃ̐[�������킩��(�w���S�j�x1973, Vol.12, pp.162-163, p.167)�B���̌��ʁA���q�y�э��戵����͋}���ɑ������A1967(���a42)�N�x�ɂ�1,012���~�ƂȂ�A���ʍɂ�钲�B�z1,040���~�Ƃقڌ�����ׂ�܂łɂȂ����B�������A�\1-3�Ɛ}1-3������킩��悤�ɁA���̊Ԃɋ}���������q�y�э��戵����̑������̂قƂ�ǂ́A�S�����̗��q�������̂ł���B�܂�A���ʍ̔��s���n�߂����X�N�x�ɂ́A�������ɓ��ʍ͓S�����̗��q���x�������߂ɔ��s���Ă���悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă��܂����̂ł���B�������č��S�́A���O�Ƃ��Ă͐ݔ������̂��߂ɍs���Ă����͂��̒��������̒��B�����ݎ����̒��B�Ƃ͌�����Ȃ��Ȃ鎖�ԂɊׂ���[2]�B���̂��߁A���c���̎��ɂ́A�ȑO�u���p�v�����n�������̂���A�v�悳��Ă����d���H���╡�����H�����������̂܂܂ł��������Ƃ��w�E����A���̎����͂ǂ��Ȃ����̂��Ƃ����ᔻ���������Ƃ����Ă���[3]�B
�\1-3. ���S�̗��q�y�э��戵����̐���
| �N�x(����) (���a) |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| �����ؓ������q | 8,176 | 8,451 | 9,163 | 9,620 | 10,240 | 12,355 | 12,231 | 13,701 | 13,982 | 16,899 | 23,436 | 23,197 | 23,266 |
| ����ؓ������q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 1,582 | 1,524 | 1,457 |
| �S�������q | 1,214 | 2,879 | 4,123 | 5,507 | 6,939 | 11,490 | 10,603 | 11,405 | 11,088 | 20,569 | 38,321 | 57,179 | 74,891 |
| ���戵����* | 289 | 314 | 283 | 428 | 599 | 170 | 91 | 91 | 97 | 301 | 1,229 | 1,570 | 1,602 |
| ���v | 9,679 | 11,643 | 13,570 | 15,555 | 17,778 | 24,015 | 22,925 | 25,197 | 25,168 | 38,582 | 64,569 | 83,470 | 101,216 |
�}1-3. ���S�̗��q�y�э��戵����̐���
(���~)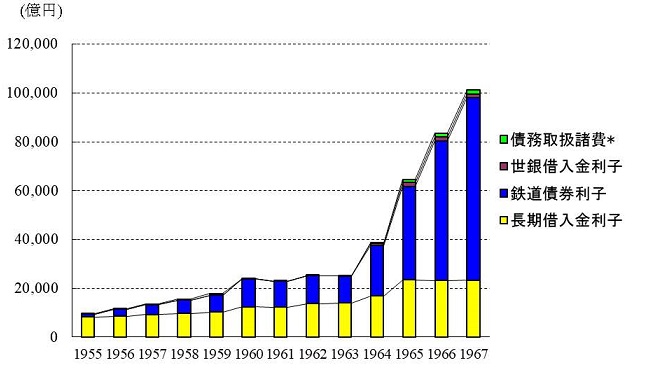
�@�Ƃ���ŁA1965(���a40)�N�x�ɑ�O�������v�悪�n�܂�܂ł́A���S�̐ݔ������̑唼�͐��{�ۏ؍��܂߂������̘g���Œ��B����Ă����B���ꂪ�傫�������̂́A���ɏq�ׂ��悤�ɁA�S�����̈��ŁA���{�ۏ̂Ȃ��u���ʍv�������̘g����O��đ�ʂɔ��s�����悤�ɂȂ��Ă���ł���B���́A�\1-4�̂悤�ɐ������Ă݂Ă��킩��悤�ɁA1965(���a40)�N�x�ɓ��ʍ��V�݂��ꂽ�ȍ~�A�D�ꎮ�ɔ��s�������ʍ̂��߂ɁA�S���̎�ނ͕��G�ȕϑJ�𐋂��邱�ƂɂȂ�A���ʍ��l�X�Ɏp��ς��Ă������̂ł���B
�\1-4. ���ʍ��V�݈ȍ~�̓S�����̎�ނƕϑJ
| �������� | 1965�N�x���s���� | 1987�N�x��c�� | ����擙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ����(%) | ���Ҋ���(�N)* | ��� | ����(%) | ���Ҋ���(�N)* | ||
| ���{�ۏؓS���� | ���{�ۏ؍� | 7.0 | 7(2) | ���{�ۏ؍� | 5.1�`8.8 | 10(3) | �l���̑��y�ѓs�ⓙ���Z�@�ւ��Ȃ����V���W�P�[�g�c |
| ���{�ۏؓS���� | �| | �| | �ϓ�, 6.04, 6.23 | 15(5) | �_�ђ������ɁA�S�M�A�A�M�� | ||
| �͍����ʓS���� | ���{����� | 7.0 | 7(2) | ���{����� | �| | �| | �����^�p���y�ъȈՕی��� |
| �ʍ����ʓS���� | �| | �| | 5.2�`5.6 | 10(3) | �����^�p�� | ||
| ���ʓS���� | ���p�� | 6.7 | 10(5) | ���̍� | 6.0�`8.0 | 10(5) | �n�������c�́A���ԉ�Г��H���̎�v�� |
| �덆���ʓS���� | ���̍� | 7.3 | 7(2) | �| | �| | ���S���ϑg���A�����ɑ��� | |
| �ɍ����ʓS���� | ���ʍ� | 7.3 | 7(2) | �| | �| | �n�������̓� | |
| �ٍ����ʓS���� | 7.5 | 5(0) | �| | �| | �ԗ���ЁA���݉�ЁA���S���ϑg���� | ||
| �֍����ʓS���� | 7.3 | 7(2) | 5.3�`8.9 | 10(3) | ���Z�@�ցA�ƍ��V�݈ȍ~�́A�֘A��� | ||
| �ƍ����ʓS���� | �| | �| | 5.4�`8.7 | 10(3) | ���Z�@�ցA1968�N�V�� | ||
| �������ʓS���� | �| | �| | 5.4�`7.6 | 7(2) | �S�����ϑg���A�덆�ɑ�����1970�N�V�� | ||
| �荆���ʓS���� | �| | �| | 5.8�`8.7 | 10(3) | �S�����ϑg���A1971�N�V�� | ||
�@�w���{���L�S���S�N�j�x(�ȉ��w���S�j�x�Ɨ��L)�̑�12��(1973, pp.688-691)�ɂ��ƁA���ɏq�ׂ��悤�ɁA��O�������v��̏��N�x�ɓ�����1965(���a40)�N�x�̗\�Z�v���ɍۂ��āA���S�͍������Z���̑啝���z��v���������A�呠�Ȃ���F�����������߂ɁA���{�ۏ̂Ȃ��V�����S�����̔��s�ɂ���Ď������B�����邱�ƂɂȂ����킯�����A���ꂪ�A�u�ɍ��v�u�ٍ��v�u�֍��v��3��̓��ʓS�����ł���B���ꂪ�����u���ʍv�ƌĂ�Ă������̂������B�������������ɁA���ʓS�������͕̂ʂɑ��݂��Ă����̂ŁA�u���ʍv�����ʓS�����@�ł͂Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ��v��B��̓I�ɂ́A�\1-4�ɂ���悤�ɁA���{����́A�͍����ʓS�����ł��������A���̍��A�덆���ʓS�����ł������B���̂悤�Ȓ��ŁA�u�ɍ��v�u�ٍ��v�u�֍��v��3��̓��ʓS���������������u���ʍv�ƌĂ�Ă����̂ł���B���̓��ʍ͐��{�ۏ��Ȃ��A������悪�\�肳��Ă��炸�A�����������̂��߂Ɏs�ꐫ�ɖR�����Ƃ���������ŁA���S�����̏������i�̂��߂ɕ\1-4�ł��킩��悤�ɁA�������̔��s����������҂ɂƂ��ėL���Ȃ��̂ɂ�����Ȃ������B���̂��߁A����������1965(���a40)�N�x������1�N�x����̍����[�u�Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�̂ł���B�Ƃ��낪�A���̓��ʍ�1966(���a41)�N�x�ȍ~���A���s��������ꂽ�B�����ĕ��G�ȕϑJ�𐋂���B
�@���̂����A�ԗ���ЁE���݉�ЁE���ރ��[�J�[���̊֘A��ЁA�y�э��S���ϑg����ΏۂƂ��Ĕ��s���ꂽ�u�ٍ��v�́A�֘A��Ђ̎����J����l���������߂ɗ����������Ȃ��Ă����B�����ŁA���q���S�̌y���̂��߂�1966(���a41)�N9���ɁA�֘A��Ђۗ̕L�����z�ʂŔ������p���Ă���B1967(���a42)�N�x�ȍ~�A�u�ٍ��v�͔��s���Ȃ��A1971(���a46)�N�x�ł��̑S�z�̏��҂��I����Ă���B
�@�������A1966(���a41)�N9���ɁA�֘A��Ђ́u�ٍ��v���z�ʂŔ������p������A�֘A��Ђɑ��锭�s�́A���Ƃ��Ƌ��Z�@�����������u�֍��v�����Ă��A����ɋN���̈����̒��ŁA���s���z�������ĉ���җ����������グ���u�ƍ��v��1968(���a43)�N6���ɐV�݂����ƁA���Z�@�ւ́u�ƍ��v�̈���ɉ��A�u�֍��v�̈����͊֘A��В��S�ɂȂ����B
�@����ɏ]���A���̍ƌĂ�Ă������S���ϑg�������́u�덆�v�ɑ����āA1969(���a44)�N�x����X�^�[�g���������Č��v��ɋ��͂��āA1970(���a45)�N1���V�݂Ő��{�ۏ؍Ɠ������́u�����v�����S���ϑg����������悤�ɂȂ����B�����Ƃ��A1971(���a46)�N7����������Z����啝�Ɋɘa���A�S�������������������s��ꂽ�ۂɂ́A���S���ϑg������̌����̂����A�����o���ɂ��Ă͒����������������߂ɁA�u�����v�ł͋t����ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�V���ɁA���s���z�����������ĉ���җ����������グ���u�荆�v���o��������1971(���a46)�N12���ɐV�݂��Ă���B���̒��������̒ቺ�X����1972(���a47)�N�ɓ����Ă��������̂ŁA7���ɂ͐��{�ۏ؍A8���ɂ́u�֍��v�u�ƍ��v�u�荆�v�̏��Ҋ�����10�N�ɉ�������Ă���B
�@�������āA�����u�ɍ��v�u�ٍ��v�u�֍��v��3��̓��ʓS����������1�N�x����̍����[�u�������͂��́u���ʍv�́A�l�X�ɔh�����p��ς��Ă����A�������c���̍��ɂ́A���p��(���m�ɂ́u���ʓS�����v)�Ɓu�֍��v�u�ƍ��v�u�����v�u�荆�v���u���̍v�Ƒ��̂���悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B
�@�����āA���S�̖����A1986(���a61)�N�x���ɂ́A���̍̊����c����7��1389���~�Ƒ傫���c��݁A���S�̒�����(�������ؓ����y�э�)�̊����c���̖�36%�ɂ��B���Ă����̂ł���B�����������ʍ̔h���̉ߒ������Ă���ƁA�����̘g�̂悤�Ȏ��~�߂���E���āA��荂�����ŋ��z�̗L���q���������S���g�Ɏ��Ȓ��B������悤�Ȃ��Ƃ����Ղɑ����Ă����ƁA�������B�̖��́A�o�ϐ��Ƃ͖����̒P�Ȃ鎑���J��̖��Ɖ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�����Ē��ڂ��ׂ��́A�֘A��Ђ̎����J����l�����āu�ٍ��v�̗����������ݒ肵����A������ŋt������N�����Ă������S���ϑg���̒����o�������ɗ����������グ���u�荆�v��V�݂�����ƁA���͂�o�ϐ��Ƃ͕ʂ̘_���������悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă����Ƃ��������ł���B
�@���������傫�Șg�g�݂܂��āA���S����̒��������̂���̓I�Ȓ��B���@������ƕ\1-5�̂悤�ɂȂ�B����͈�ʊ���ƌĂ����̂ŁA���̑��ɂ��A���S�̌o�c������́A�o�c���������U�����߂̕⏕������ʊ��肪���݂��Ă����B�t�̌�����������A���݂̓S�����Ǝ҂̎������B�X�L�[���̏펯����͑z�����ɂ������ƂȂ̂����A���S�̌o�c����������܂ł́A�����Ƃ��č��S�ɑ��ĕ⏕���͌�t����Ă��Ȃ��������A��ʉ�v����̎ؓ������Ȃ������̂ł���B
�\1-5. ���S�̒����������B(��ʊ���)�@�@�@1984(���a59)�N�x������
| ��� | ����(%) | ���Ҋ���(�N)* | ���ҕ��@�^������ | |
|---|---|---|---|---|
| �� �� �� �v | ��������� | 4.0 | 36(0) | |
| 7.966 | 10(0) | |||
| 8.328 | 10(0) | |||
| �n����ʐ����ʑݕt�� | �����q | 25(3) | �N2���ϓ� | |
| �� �� | �����^�p�� | 6.5�`8.5 | ||
| �ȈՕی��� | 6.2�`8.7 | |||
| ���Ԏؓ��� | 7.2�`8.0 | 7�`10(0.5) | �_��ɂ���ĈقȂ� | |
| �S �� �� �� | ���{�ۏ؍� (�����̘g��) | 6.6�`7.4 | 10(3) | �l���̑��y�ѓs�ⓙ���Z�@�ւ��Ȃ��W����c�� |
| 7.18, 7.31 | 15(5) | |||
| ���p��** | 6.5�`7.3 | 10(5) | �n�������́A���ԉ�Г��H���̎�v�� | |
| �֍���** | 6.6�`7.4 | 10(3) | �ԗ���ЁA���݉�Г��֘A��� | |
| �ƍ���** | 6.7�`7.5 | 10(3) | �s�⥒���A�n�⥑���A�M���A���ہA�_�ы��Z�@�֓� | |
| ������** | 6.5�`7.4 | 7(2) | ���S���ϑg�� | |
| �荆��** | 6.6�`7.4 | 10(3) | ||
�@���S�ɑ���⏕���́A1969(���a44)�N�́u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�Ɋ�Â��āA���a43�N�x������ꂪ�J�n���ꂽ�u�H���⏕���v���ŏ��ł���B����͖��̂ɂ�������炸�A���v�⏕��ړI�Ƃ��Ă���A�ݔ����������̈ꕔ�ɌW��ؓ����̗��q�⋋�̂��߂̕⏕���ŁA���v��̎����Ƃ��Ď�����Ă����B�ݔ������ɑ���⏕���́A1977(���a52)�N�x�����t����Ă���B
�@�����A���̈�ʉ�v����̎ؓ����Ƃ��āA��ʊ���ł́A�Ⴆ�A1951(���a26)�N12��20���Ɏԗ���(�ݎԐ���)�[���̂��߂ɐ��{(�^�A��)����̎ؓ���(�����q������)��20���~������B�������A���̈�ʉ�v����̎ؓ����͂��̂قƂ�ǂ����ʊ���(������������ʊ���)�ł������B����͍��̒I�グ�W�̂��̂ŁA���̑��z��5��3,221���~�A����Ƃ��ẮA��ʉ�v����̍����Č��ؓ����̎c����2,622���~�A�����^�p������̓��蒷���ؓ����̎c����5��599���~�ł������B���̎c���́A���u���ԂƂȂ��Ă���1980(���a55)�N�x����1984(���a59)�N�x�܂ŕϓ����Ȃ������ł͂Ȃ��A�������c���̒��O1986(���a61)�N�x���܂ŕϓ����Ȃ��B���̒I�グ�́A���̂悤�ɂ��čs��ꂽ�B
�@���S�̌o�c������������́A���S�ɑ��鍑�̑����ƕ⏕����t���n�܂�A�����͍��S�̎������B�ɂ����Ė����ł��Ȃ��K�͂ɒB���Ă����B�܂��A���S������������r�₦�Ă��������́A1971(���a46)�N�x�`1975(���a50)�N�x�̊ԁA���N�x�s����悤�ɂȂ����B����́A�\1-6�Ɏ�����Ă���悤�ɁA1973(���a48)�N�x�ɂ́A1,950���~�ƃs�[�N���}����B���̂Ƃ��͍H����800���~�A���v�Ή�1,150���~�Ƃ�������ł��������A�\������킩��悤�ɁA���̎��X�̍��̗\�Z�̐���������A�H����̏[����ړI�Ƃ����P�[�X���قƂ�ǂł������B
�\1-6. ���S�ɑ��鐭�{�o���̌o��
| �N�x | �o���z(���~) | �E�v |
|---|---|---|
| 1949(���a24) | 49* | ���S�������̍��L�S�����Ɠ��ʉ�v����̏��p |
| 1950(���a25) | 40 | �H����** |
| 1971(���a46) | 35 | �H����(��{�ݑ�����) |
| 1972(���a47) | 656 | �ݗ����H����556���~�A���k�V����100���~ |
| 1973(���a48) | 1,950 | �H����800���~�A���v�Ή�1,150���~ |
| 1974(���a49) | 1,130 | �H����650���~�A���v�Ή� 480���~ |
| 1975(���a50) | 700 | �H���� |
| �v | 4,560 | ���S���Z���ƒc���{���� |
�@�������I�������ɂ́A1977(���a52)�N�x���番�����c�����O��1986(���a61)�N�x�܂ŁA���x�͍��S�̐ݔ������ɑ��鍑�̕⏕�������N�x��t����邱�ƂɂȂ�B�\1-7�A�}1-4�Ɏ������悤�ɁA�⏕���̊z�͑S�̂�1978(���a53)�N�x�`1981(���a56)�N�x��4�A5�S���~�K�͂ɒB���Ă���[4]�B�⏕���̑ΏۂƂ��ẮA���ʎ{�ݐ�����A�����V�������ݒ�����Ƃ��������Ə�����A�����Ėh�Ў��Ɣ�A���C��������S���Z�p�J������������A�}1-5�ł����炩�Ȃ悤�ɁA�Ώێ��Ƃɂ���āA�⏕���͈قȂ��Ă����B
�\1-7. ���S�̕⏕���ΏۍH���̔N�x�ʐ���(���уx�[�X*)�@�@�@(���z�P��: ���~)
| �N�x(����) (���a) | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | �v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||
| �� �� �� �� �� | ���ʎ{�� ������ | �ΏۍH���� | 625 | 1,132 | 1,171 | 1,354 | 1,542 | 546 | 310 | 119 | 53 | 59 | 6,911 |
| �⏕�� | 169 | 311 | 380 | 288 | 327 | 88 | 78 | 49 | 37 | 37 | 1,764 | ||
| �⏕�� | 27.0% | 27.5% | 32.5% | 21.3% | 21.2% | 16.1% | 25.2% | 41.2% | 69.8% | 62.7% | 25.5% | ||
| �����V���� ���ݒ����� | �ΏۍH���� | 20 | 18 | 19 | 11 | 7 | 13 | 15 | 15 | 118 | |||
| �⏕�� | 20 | 18 | 19 | 11 | 7 | 13 | 15 | 15 | 118 | ||||
| �⏕�� | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
| �h�Ў��Ɣ� | �ΏۍH���� | 158 | 162 | 163 | 169 | 164 | 156 | 138 | 120 | 214 | 1,444 | ||
| �⏕�� | 87 | 99 | 97 | 98 | 95 | 90 | 81 | 68 | 110 | 825 | |||
| �⏕�� | 55.1% | 61.1% | 59.5% | 58.0% | 57.9% | 57.7% | 58.7% | 56.7% | 51.4% | 57.1% | |||
| ���C��������S�� �Z�p�J���� | �ΏۍH���� | 2 | 20 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | |||
| �⏕�� | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||
| �⏕�� | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | ||||
| �S�� | �ΏۍH���� | 625 | 1,290 | 1,355 | 1,555 | 1,740 | 733 | 479 | 276 | 194 | 294 | 8,541 | |
| �⏕�� | 169 | 398 | 500 | 413 | 449 | 200 | 178 | 146 | 123 | 165 | 2,741 | ||
| �⏕�� | 27.0% | 30.9% | 36.9% | 26.6% | 25.8% | 27.3% | 37.2% | 52.9% | 63.4% | 56.1% | 32.1% | ||
�}1-4. ���S�ɑ���⏕��
(���~)
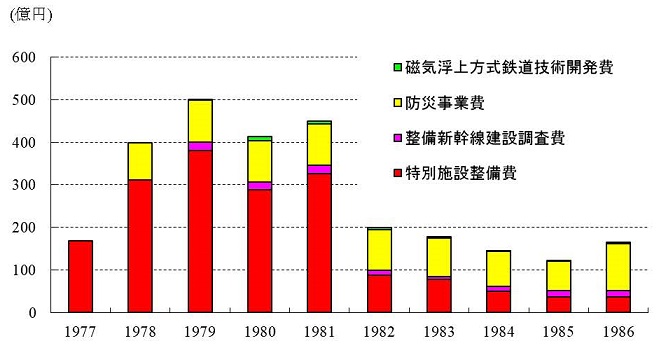
�}1-5. ���S�̕⏕���ΏۍH���̕⏕��
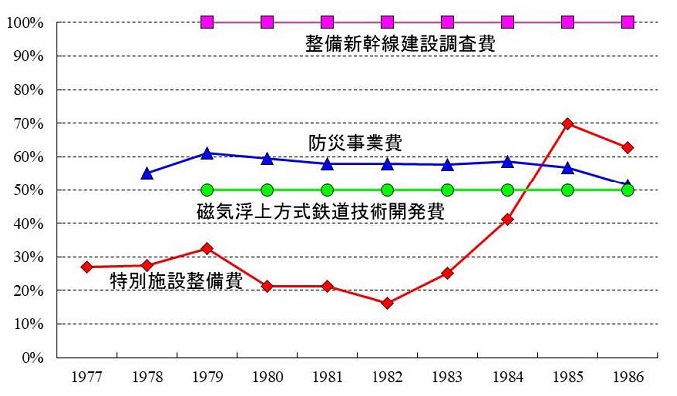
�@�����Łu���ʎ{�ݐ�����⏕���v�Ƃ͎��̎l�̕⏕�������������̂ł���B
�@���̂���2�`4�̕⏕����50%���������A1�͍��̍����̓s���ɂ��A�N�x�ɂ����27%�A30%�A35%�ƕω����A���r���N�x����u������t�v�ɂȂ�A�⏕�ΏۍH���������k�������Ȃǖ��N�x�̂悤�ɕύX���������B���̑��́u�h�Ў��Ɣ�⏕���v�̕⏕���͍H�����e�ɂ����1/3�`2/3�A�u���C��������S���Z�p�J����⏕���v�̕⏕����1/2�������B
�@�Ƃ���ŁA�����V�������ݒ�����Ȃǂ͕⏕��100%�ł��������A���S�ɑ���⏕���͑S�̂ł�32%�ɂ����Ȃ�Ȃ��B�����A���̕⏕���ɂ��ẮA50%����⏕���Ƃ����̂́A�{���A�����s���ׂ����Ƃ��̂��̂ɋ߂��Ƃ������ƂɂȂ�A�⏕�����x�Ƃ��Ă͂��������Ƃ����c�_���s���Ă����Ƃ�����B
�@���������o�߂����ǂ��āA1965(���a40)�N�x����X�^�[�g������O�������v��́A1969(���a44)�N�x����X�^�[�g���������Č�10���N�v��ɋz�������B�������A���̂悤�Ȏ������B�̌��E�����ݔ������́A1964(���a39)�N3���ɓS�����c���ݗ�����A�S�����c���g���L���q�����B�ł���悤�ɂȂ�A�����̌㉟���̒��ŐV�����݂��ϋɓI�ɐ��i�����悤�ɂȂ�ƁA���ǂ͎��~�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�����A���݂ɂ������ėL�������𓊓����鍑�S�V���ɂ��ẮA1964(���a39)�N3��23���̑呠�Ȏ�v�ǒ��E�呠�ȗ����ǒ��E�^�A�ȓS���ēǒ��Ԃ̊o���Ɋ�Â��A���Y�S���{�݂̌��ݒ��H�O�ɁA�����̍��S�ƓS�����c�Ƃ̊Ԃŕ����Ŋm�F����Ă���B�����̊m�F���ɂ�茈�肳�ꂽ���Ɍ��肵�ėL���������������ꂽ�B�L�������������������ɂ��ẮA1978(���a53)�N�x�܂ł͐��{�o�����A1979(���a54)�N�x�ȍ~�͍��ɕ⏕�������Ă��Ă����B���̂��߁A���S�͖{���A�A�����v���猩�č̎Z�I�Ɏ����o�c���\��(�c�ƌW��100�ȉ���)��������̗��v�����S�S�̂̐Ԏ���U�ɉH�ڂɂȂ�A���l�Ȍ�ʋ@�ւ̋����I�����̎���ɂ����āA�����n����ł̋����͂��܂��܂����ނ����錋�ʂƂȂ����̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȍl�@����A�{���ł́A�S�����Ǝ҂̎������B�X�L�[���ɒ��ڂ��邱�Ƃɂ����B���ɏq�ׂ��悤�ɁA�o�c���e�ɗ������炸�ɁA�������B�X�L�[�������ł��A���S�̌o�c�j�]�̃V�i���I�͂ł��Ă����̂ł���B�܂�A��B�����ɕ����c����ڂ̌����́A�������B�X�L�[���̎��s�ł���A����܂ł̎������B�̌��E�������z�̐ݔ������ł������B���S�̏ꍇ�A���́u���E�����v���Ƃ̏ے����A�����̘g���āA��ʂ̎������������̍������ʍŎs�����B����悤�ɂȂ������Ƃ������̂ł���B
�@�����\�Z�ɏ]���A���̘g��(�u�x�o���v)�Œ��B�����������e�͓I�ɑ��̖ړI�Ɏg�p����邱�Ƃ������Ɉ�@�s�ׂ������킯�ł͂Ȃ�(���S�@��39����14)�B�N�x�̎����v���́A���Ƃ��ΐݔ������ɑ��Ē����ؓ����Ƃ����������̐����ɉ������Ή��W�����邱�Ƃ��o���邪�A�����͍��S�S�̂Ƃ��ĉ������̂ł���A�����̎��ۂ̎����J��̒��ł́A�ݔ������̕⏕�����E���̃{�[�i�X�x�����ɏ[�Ă��邱�Ƃ��A�t�ɑ��v�⏕���̎���z�����߂̍H����̎x�����ɏ[�Ă��邱�Ƃ������Ă����̂ł���B
�@���̑��ɂ��A1953(���a28)�N�̍��S�@�̑�����Łu�\�Z�̒e�͐��v������������(�w���S�j�x1973, Vol.12, pp.604-605)�A���S�@��39���ɂ́u���{���L�S���̗\�Z�ɂ́A���̎��Ƃ���ƓI�Ɍo�c���邱�Ƃ��ł���悤�ɁA���v�̑����A�o�ώ���̕ϓ����̑��\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ԃɉ����邱�Ƃ��ł���e�͐���^������̂Ƃ���B�v�Ƃ���������B���l�̏́A���{�d�M�d�b���Ж@��40���A���{�ꔄ���Ж@��34���ɂ������A��3���Ђɋ��ʂ̂��̂ł������B��������ʓI�ɂ́A�\�Z�̒e�͏����Ƃ́A�Ώo�\�Z�̋��z���Γ��̑������̑����̏����̉��ő������邱�Ƃ�F�߂�\�Z�����̋K��������̂ł����āA�ʏ�A�\�Z�̋c���͌��x�z�̋c���ƍl������̂ŁA�Ώo�̌��z�ɂ͂��������K��͕s�v�ł���A�e�͏����͍Ώo�̑��z���K�肵�����̂ł���Ƃ���Ă���(���, 1985, p.83)�B�����Ƃ��A1953(���a28)�N�̍��S�@�̑�����Łu�\�Z�̒e�͐��v�ɂ��Ă̑�39�����V�݂����ȑO����A�\�Z�����ɂ͍��S�\�Z�́u�e�͏����v�͑��݂��Ă����B�܂��A�ݗ��@�ɂ����āA���S�@��39���̂悤�ȁu�\�Z�̒e�͐��v��^�����Ă��Ȃ��������Z���ɁA���{�J����s�Ȃǂ̓���@�l�ɂ��Ă��A�\�Z�����ɂ́u�e�͏����v���u����Ă���B���̂��Ƃ���A���S�@��39���̒e�͐��̓��e�́A�\�Z�����̒e�͏����Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��A�\�Z�̑S�ʂɋy�Ԃ��̂��Ƃ������߂�������(���{���L�S���@������, 1973, pp.153-154)�B
�@�����č��S����́A���m�Ɍ����A�H�����Ԃ��Ƃɒ��B�����R�X�g����肵���R�X�g�v�Z���s���Ă����킯�ł͂Ȃ������B����ʂɍs���Ă���������c�ƌW���̌v�Z�����S�S�̂ɂ������Ă������q�����炩�̊�Ŕz���������̂ŁA���̈Ӗ��ł͘�����ł������B�w���S�j�x(1973, Vol.12, pp.623-626)�ɂ��A���S�́A1949(���a24)�N6���Ɍ������Ƒ̂Ɉڍs���������11���ɂ͓Ɨ��̎Z�����i�ψ����݂��A��1950(���a25)�N3���ɂ́A�o�όv�Z�K���Ă��쐬���Ă���B�o�όv�Z�́A����2��ɕ�����Ă����B
�@�������������̂��߂ɁA�����͌o�c��v�Z�͐摗�肳��A�^�������v�Z�݂̂����s���ꂽ�B���̌�A1953(���a28)�N4���ɂȂ��āu���{���L�S���o�όv�Z�K���v�����肳��A1953(���a28)�N�x����S�ʓI�Ȏ��{�ƂȂ����̂ł���B�^�������v�Z�͐��ʁE�S���Ǘ��Ǖʂ���щ^�A�ʂ̌����v�Z���s�����̂ł��邪�A���̂������ʌ����v�Z�ɂ����āA�A���ʁE��������щ^���������א��ʂɌv�Z���A���ʂ̌Œ莑�Y�̉�]���A�c�ƌW���A�A���ʁA�ԗ��L�������茴���A�^�A���x�ƌ����̊֘A����c�����邱�ƂɂȂ��Ă����B���̂������q�̔z����́A�����͎ԗ��ȊO�̏��p���Y�̒��뉿�z����ɔz�����Ă������A����ł́A���̓����z�̑傫������͍����z���ƂȂ�Ƃ��āA1954(���a29)�N�x�̉����ŁA���Z�ԗ��L������Ƃ���悤�ɉ��߂�ꂽ�B�������A���̕����ł́A�ԗ��̉^�p�������グ��Ώグ��قǗ��q�̕��S�z���������Ă��܂��̂ŁA����ɁA1961(���a36)�N�x����́A(i)���p���Y�ɂ��Ă͎��Y�擾������藦�Ō������p���s�������̂Ƃ݂Ȃ��ĎZ�o�����c���z�A(ii)��֎��Y�ɂ��Ă͒��뉿�z��2����1�A(iii)�i�v���Y�ɂ��Ă͒��뉿�z�A�����ꂼ�ꐳ�����Y�Ƃ��āA�������ɐ���ʂɔz�����邱�Ƃɉ��߂�ꂽ�B�������āA���{���L�S���o�όv�Z�K���͉������J��Ԃ������߂ɁA��������������1964(���a39)�N5���Ɂu�o�όv�Z�����K���v�����肳��A����ɓ��N7���Ɂu�o�όv�Z������K���v�Ɖ��̂��ꂽ�B�����āA�R���s���[�^�ɂ��v�Z�\�͂̌���𗘗p���A����ɋ��͂Ȉӎv���莑���Ƃ��Ă̌o�c�v��̍���y�ѐݔ������o�όv�Z�ɗ��p���邽�߁A1966(���a41)�N5���ɓS���^�������v�Z������ݒu����A���N12���ɕ��ꂽ�������ʂ����N�x�̌����v�Z���x�Ɏ�������Ă���B
[1]�����͌��݂ł��A�������킸�S�����Ǝ҂ɂƂ��ďd�v�ȍ����ł��邪�A�������̂̍���(����)�͎��̎l����\������Ă���(�呠�ȗ�����, 1993, ch.1)�B
[2]�������u���{���L�S���@�v(�ȉ��u���S�@�v�Ɨ��L)�ł́A���S�̗\�Z�͍���F�����������̂ŁA�\�Z�A���ƌv�悾���łȂ��A���v����A���{������킸�A�x�o�\�Z�z��d�����߂̎��Ȏ������܂߂��u�����v��v���\�Z�̓Y�t���ނƂ��č����o����Ă���(���S�@��39����2)�B�������A����̋c�����o���\�Z�Ɋ�Â��āA�l�������ƂɎ����v����߁A������^�A��b�A�呠��b�A��v�����@�ɒ�o���Ă���(���S�@��39����16)�B�܂��⏕���Ɋւ��ẮA�⏕���K�����@(�u�⏕�����ɌW��\�Z�̎��s�̓K�����Ɋւ���@���v)�ŁA�K������Ă���A�ړI�O�g�p�͍ō�����3�N�̌Y���ɂȂ�B�������A�����\�Z�ɏ]���A���̘g��(�u�x�o���v)�Œ��B�����������e�͓I�ɑ��̖ړI�Ɏg�p����邱�Ƃ������Ɉ�@�s�ׂ������킯�ł͂Ȃ�(���S�@��39����14)�B����ɂ��Ă͕t�^���Q�Ƃ̂��ƁB
[3]�������A�H�������������Ƃ������ƂŁA���p����c�̂Ƃ̊Ԃő����ɂ܂Ŕ��W�����P�[�X�͂Ȃ������B���������w�i�ɂ́A�u���������������������v�Ƃ��������p�̈���c�̂̑������A�n�������̂̎��\�Ƃ����i���I�Ȃ��̂��������ƁA�܂��A���q�x���⌳�����Ҏ��̂͂�����ƍs���Ă����Ƃ����悤�Ȏ�����������ƍl������B �@�w�ɂ�d�����̍H���́A�H�����P�N�x�������Ă�2�`3�N���قƂ�ǂ������Ƃ����邪�A���H���݂͗p�n�̔��������Ƃ������Ē����Ԃ�v����ꍇ�������A���̊Ԃ̐�����߂���o�c���̕ω�������H���̌p��������ƂȂ�A�������̂܂܂ɂȂ�P�[�X���o�Ă����ƍl������B���S���c�������̐����ł́A���p���W�����H���Ŗ��������������̂Ƃ���13�����������Ă��邪�A�����͂��ׂĐ��H����(������)�W�ŁA�H�������Ƃ���JR�ɏ��p���ꂽ���̂�10���A�p��3���ƂȂ��Ă����B��b�F��������H���ݍH���́A�H�������̌p�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�H���ĊJ�̏ꍇ�ɂ͍ēxJR�ɂ��F�\�����K�v�ƍl�����Ă������߂ɁA���S�����Ɏ�����H�������f���Ă��������ɂ��Ă��A�ł��邾�����p��������Œ������s��ꂽ�Ƃ����Ă���B�H���������Ƃ̐����ł́A������̏ꍇ�����p�̋N�z�����H�����ё��z�̕��������Ă��邪�A���p���ꂽ�����̂�����3���Ɣp3���ɂ��ẮA���R�͕s�������H�����т��s�����Ă���Ɛ�������Ă����B
[4]���S�̐ݔ������ɑ���⏕���́A�H�����тɂ��������Č�t����(�㕥��)�A�܂����̗\�Z�̌J�z���x�̑��݂ɂ��A�\�Z�Ɍv�コ�ꂽ�N�x�Ǝ����N�x������邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ�����B�����Ŏ�����Ă��鐔���͎��уx�[�X�̐����ł���B
�@��1�͂Ř_�����悤�ɁA���S�̎������B���́A�S�����ݎ��������ł͂Ȃ��A�S���ێ��������܂߂��ݔ����������̒��B���ł������B�������A�V���{�݂̎�ւ���S�E����A����̂��߂̐ݔ������́A�{���͌������p��͈͓̔��ōs����ׂ����̂ł����āA�������B�X�L�[���̋c�_�ɂ͓���݂ɂ����B�����ŁA�{���ł͂���ȍ~�A�S�����ݎ����ɓI���i���āA���{�̓S�����Ƃ̎������B�X�L�[���ɂ��čl�@��i�߂邱�Ƃɂ��悤�B
�@�����ŁA���̏͂ł́A�����_�ł́A�S�����݂̍ۂ̎������B�X�L�[���̌���Ɩ��_��T�邱�Ƃɂ������B�܂���2�߂ł́A���݁A���Ԃ��܂߂ē��{�ł̓S�����ݎ������B�X�L�[���ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���^�A�{�ݐ������ƒc�Ɠ��{�S�������c(�ȉ��u�S�����c�v�Ɨ��L)��ʂ��������̗��������B����܂����������B�X�L�[���̉��p���Ƃ��āA��3�߂ł́A�P�[�X�E�X�^�f�B�[�I�ɉc�c�n���S�Ɠs�c�n���S�̒n���S���ݔ�̎������B�X�L�[�����������B���̏�ŁA��S�߂ł́A�n���S���ݔ�̎������B�X�L�[���̔�r���s���A�^�c��⏕���������ǂ͗��q�⋋�ɂ����Ȃ�Ȃ��������ƁA����ɔ�ׂāA�ꊇ��t�̎��{��⏕�����̕����A��菭�Ȃ��o�����z�E�⏕���z�ɂ�������炸�A�n���S���Ǝ҂̎������S��啝�Ɍy�����A���v�\���̉��P�ɍv�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B
�@�����������ʂ́A�S�����݂��S���o�c����{�I�ɂ͋����Ƃ̋����ł���Ƃ������ƂɋN�����Ă���B���ہA�������c����̓����{���q�S���������(�ȉ��uJR�����{�v�Ɨ��L)�́A�����S����w�����������Ƃ̋����̒��ŁA���z�ƕ��ϋ����̈��k�ɐ������Ă���(����, 2000)�B�{�e�̎咣�͒P���ł�������O�̂��Ƃł���B���_�I�ɂ����A�������킸�A���z�̗L���q�����𗘗p���čs����S�����݂Ƃ��̌�̓S���o�c�́A�����Ƃ̋����ł���B���ɁA�⏕�������������ꍇ�ɂ́A�D�揇�ʂm�ɂ��āA�⏕�������{��⏕�Ƃ��Č��ݎ��ɏW���������A�L���q�����z�ƍH������(���m�ɂ͒��H����J�Ƃ܂ł̊���)�̗������ł��邾�����k���邱�Ƃ��̗v�ł���B�����Ȃ��A�S�����Ƃ̎��v�\�����̂��������Ă��܂��A���������̕⏕�����������q�⋋�ɂ������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�ɂ�������炸�A����܂ł͍����⏕�����L�͂������ɂ킽���Ĕ�����܂��Ƃ����t�̂��Ƃ����Ă����悤�Ɍ�����B�������B�X�L�[���Ƃ������t���̂��قƂ�LjӖ��������Ă����ꓖ����I�s�����ڂɕt���B���̂����`�ŁA�S�����ݔ�̕s������q��������S�����ƎҎ��g�ɗL���q�����Ƃ��Ď��Ȓ��B������Ƃ������Ƃ����Ղɑ��������Ă���ƁA�J�Ƃ܂ł̍H�����Ԃ̊Ԃɗ��q�ł���ɗL���q���̊z���c��݁A�S�����Ƃ��̂��̂̎��v�\���̈������J�ƑO�Ɍ���I�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��B�x�������ʼnc�Ɨ��v��������Ԃ悤�ȏ��ɒu����Ă��ẮA������c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă����ꂸ�A�������c�Ɠw�͎��̂��Y�ꋎ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@���݂̓��{�ŁA���Ԃ��܂߂ēS�����Ǝ҂̓S�����݂̎������B�X�L�[���ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂��A�^�A�{�ݐ������ƒc�Ɠ��{�S�������c(�S�����c)�ł���B���̗��҂�ʂ��ē��������⏕���A��t���A�����q�ݕt���A�������Z�������A�����Ďs�����B���������{�̓S�����݂̎������B�X�L�[���̊�{�I�Șg�g�݂��`�����Ă���B
�@�S����������́A���S�������c�����ɐݗ����ꂽ�V�����S���ۗL�@�\�����U���鎞�ɁA���@�\�̈�̌����y�ы`�������p������̂Ƃ���(�V�����S���ɌW��S���{�݂̏��n���Ɋւ���@����5���A�y�ѓS����������@ ������4��1��)�A1991(����3)�N10��1���ɐݗ����ꂽ�B����ɁA1997�N10��1���ɂ� �S����������ƑD���������c����������ĉ^�A�{�ݐ������ƒc���ݗ����ꂽ���A1998�N9��1�����݂̐E������134�l�ŁA���S����������̎��Ƃ͂��̂܂܌p������Ă���A���҂͕ʉ�v�ɂȂ��Ă���B�S������������ݗ����ꂽ���Ƃɔ����A����܂ʼn^�A�Ȃ��璼�ڌ�t���Ă����e��⏕���́A��U�A�S������������o�R���Č�t�����悤�ɂȂ����B���̈Ӗ��ł́A�⏕���̃g���l����ГI�ȑ��݂ł���B���̑��ɂ��A�S������������ォ��AJR�{�B3�Ђ�������Ă�����ݐV�������n���������ɐ����V�����̌��ݎ����Ɍ�t���Ƃ��Č�t������A���邢�͒n���S���݂Ȃǂɖ����q�ݕt���Ƃ��đ݂��t����������Ă���B
�@���ɂ���̕⏕���͉^�A�{�ݐ������ƒc(���S���������)���o�R���ēS�����c���ɗ����悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�������B�Ɠ����Ƃ��������A�P�Ɏ����̗��o���Ɍg����Ă���Ƃ������������Ԃɋ߂����A�^�A�{�ݐ������ƒc�̎����̏o����͕\2-1�̂悤�ɐ��������B���̏����Ɩ��̑������S�����c����݂ł��邱�Ƃ͈�ڗđR�ł���B���z�I�ɂ����A�S�����c�ɑ��鏕���Ɩ��ɒn���S�ɑ��鏕���Ɩ������������̂����S�ƂȂ�B
�\2-1. �^�A�{�ݐ������ƒc(�S���W�����S���������*)�̎����̗��o��(1997(����9)�N�x���Z)
| �����Ɩ��E�⏕������(�����̋�����) | �S�����c�̎��Ɩ� | �⏕�� ��t�� �ݕt�� (%) | �����̒��B�� | �v | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� ���� (���� �⏕��) | ������� (�{�BJR3�� ����� ���ݐV���� ���n���) | �� �� �q �� �t �� �� �� �� | �^ �p �v | �ؓ��� | |||||||
| �� �� ** | �� �t �� | �����q �ݕt�� | ���Ԏؓ��E �O���o�c ������ | ||||||||
| �����V���� ���ݏ����Ɩ� | �V�����S���������ƌ�t�� | �V���� | ��z | 724 | 1,043 | ||||||
| �V�����S���������Ɣ�⏕ | �V���� | ��z A | 277 | ||||||||
| �����V�������ݐ��i���x�������Ɣ�⏕�� | �V���� | 100 | 35 | ||||||||
| �����V�������ݐ��i�������Ɣ�⏕�� | �V���� | 100 | 5 | ||||||||
| �����V�����w�����������Ɣ�⏕�� | �V���� | 100 | 3 | ||||||||
| ��v�����S�� ���������Ɩ� | �V�����V��������⏕�� | �V������ | 100 | 4 | 179 | ||||||
| �����S����������q�ݕt�� | ��v�����S���� | B | 15 | ||||||||
| �����S�������������Ɣ�⏕ | �����S�����K�i������ | 20 | 4 | ||||||||
| �n���J�����y�n���������ݔ�⏕�� | �n���S���V��(AB��) | 100 | 156 | ||||||||
| �s�s�S�� ���������Ɩ� | �ݕt���y���n�����ݔ���q�⋋�� | ���S���E�ݕt��(CD��) | C | 13 | 965 | ||||||
| �s�s�S����������q�ݕt�� | �s�s�S����(�c�c�����܂�) | 40 | 319 | ||||||||
| �j���[�^�E���S���������Ɣ�⏕ | 18 | 27 | |||||||||
| �����S�������������Ɣ�⏕ | 20 | 1 | |||||||||
| �n�������S���������Ɣ�⏕ | 35 | 605 | |||||||||
| ���j�A���S���Z�p�J�����i�����Ɩ� | 25��50 | 46 | 46 | ||||||||
| ���S�E�h�Б��������Ɩ� | ���� | 38 | 38 | ||||||||
| �������̌v | 1,213 | 724 | 335 | 2,272 | |||||||
| �����ҁE������ | 2 | 6,365 | 16 | 6 | 2,412 | 8,801 | |||||
| �Ǘ�� | 4 | 9 | 2 | 15 | |||||||
| ���������z�v | 1,217 | 11 | 7,424 | 16 | 8 | 2,412 | 11,088 | ||||
�@����A�S�����c��1964(���a39)�N3��23���ɐݗ�����Ă���B1998�N9��1�����݂̐E������1,790�l�����A������y�؉������ڍH�������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�{�s�Ǘ��ɓ������Ă���B�S�����c�͉^�A�{�ݐ������ƒc���痬��Ă���⏕���A��t���A�����q�ݕt���ɉ����āA�Ǝ��̃��[�g�ŁA�\2-2�ɐ�������Ă���悤�Ȗ����q�ؓ����A�����E���Ԃ���̗L���q�ؓ����A�����ēS�����ݍ��ɂ�鎑�����B�����Ă���B�S�����c�́A�����̒��B���������Ƃ���(�H���E��Ԃ���)�ɓ���̎������B�X�L�[���ɑ����ă~�b�N�X���A���ݍH�������Ƃ��ē������Ă���̂ł���B���̗l�q�́A�S�����c�̎��Ƃ��ƂɁA�\2-3�̂悤�ɐ��������B�������A1955(���a30)�N�ɐ��肳�ꂽ�n�������Č����ʑ[�u�@��24��2���̋K��ɂ��A�ʂɖ@���Œ�߂��ꍇ(�Ⴆ�A�����V�����̂悤�ȏꍇ)�������āA�n�������̂����c�ɑ��āA���ځA�⏕�������o���Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B������������w�i�ɂ��邽�߂ɁA���ړI�E�`���I�ɂ͑�O�Z�N�^�[�̂悤�ȓS�����Ǝ҂��������o���Ă���悤�Ɍ�����P�[�X�ł��A���ۂɂ͂��̓S�����Ǝ҂��o�R���Ēn�������̓����������o���Ă���ꍇ������B���������ꍇ�ɂ́A���̕\2-3�ł́A���̋��ɓI�Ȏ������A�܂�n�������̓��̕����L�ڂ��Ă���B
�\2-2. �S�����c�̎������B
| ���B�� | ���� | ���ҕ��@ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���Ҋ���(�N)* | �����ϓ�(����) | ||||||||
| �� �� �� |
�L �� �q |
(a)�����^�p�� | �ݕt�� | �ݗ���(1964�N3��) | 15(3) | ��(���N��) | |||
| 1965�N4���`73�N5�� | 25(3) | ��(���N��) | |||||||
| 1973�N6���` | 30(5) | ��(���N��) | |||||||
| ���n�� | 1972�N9���` | 25(3) | ��(���N��) | ||||||
| (b)���� | 1978�`80�N�x | 1(0) | �����ꊇ | ||||||
| 1979�`83�N�x | 7(3) | ��(���N��) | |||||||
| 1980�N�x | 10(0.5) | ��(���N��) | |||||||
| 1981�N�x�` | 10(3) | ��(���N��) | |||||||
| �� �� �q |
(c)�Y�Ɠ������ʉ�v | 1989�`92�N�x | 10(5) | ��(���N��) | |||||
| (d)�^�A�{�ݐ������ƒc �@(�� �S���������) |
1991�N�x�` | 15(5) | ��(���N��) | ||||||
| 1997�N�x�`** | 16(6) | ��(���N��) | |||||||
| (e)�s�s�S���������Ǝ��� | 1992�`96�N�x | 15(5) | ��(���N��) | ||||||
| 1997�N�x�` | 18(8) | ��(���N��) | |||||||
| (f)�n���S���������i���� | 1993�N�x | �ݕt�̗��N�x���� 2�N�ȓ��ɖ��N�x�̗\�Z�Œ�߂��z�ȓ� | |||||||
| 1994�N�x�` | �ݕt�ŏI�N�x�̗��N�x���� 3�N�ȓ��ɖ��N�x�̗\�Z�Œ�߂��z�ȓ� | ||||||||
| �S �� �� �� �� �� |
(g)���{�ۏ؍�(����) | 1967�N�x�`72�N6�� | 7(2) | �N2��e3%�ȏ� | |||||
| 1972�N7���`87�N3�� | 10(3) | ||||||||
| 1987�N4���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
| (h)���{����� | �����^�p�� | 1967�N�x�`72�N6�� | 7(2) | �N2��e3%�ȏ� | |||||
| 1972�N7���`87�N3�� | 10(3) | ||||||||
| 1987�N4���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
| �ȕێ��� | 1989�N�x�`97�N�x | 10(0) | �����ꊇ | ||||||
| (i)���ʍ�(���c��) | �n�����͒c�� | (�덆��) | 1965�N�x�`70�N6�� | 7(2) | �N1��e6%�ȏ� | ||||
| 1970�N7���`72�N7�� | 7(2) | �N2��e3%�ȏ� | |||||||
| 1972�N8���`92�N4�� | 10(3) | ||||||||
| 1992�N5���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
| �H���֘A�ƊE | (������) | 1965�N7���`67�N8�� | 5(0) | �N1��e6%�ȏ� | |||||
| (�͍���) | 1965�N�x�`72�N7�� | 7(2) | �N2��e3%�ȏ� | ||||||
| 1972�N8���`87�N4�� | 10(3) | ||||||||
| 1987�N5���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
| ���Z�@�� | (�ɍ���) | 1968�N�x�`72�N7�� | 7(2) | �N2��e3%�ȏ� | |||||
| 1972�N8���`87�N4�� | 10(3) | ||||||||
| 1987�N5���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
| (�ٍ���) | 1972�N11���`87�N4�� | 10(3) | �N2��e3%�ȏ� | ||||||
| 1987�N5���` | 10(0) | �����ꊇ | |||||||
�\2-3. �S�����c�̎���(1997(����9)�N�x���Z)
| ���Ɩ� | �H�����E������ | �H���E���������̒��B���@ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ��� | ���c ���B | �^�A�{�ݐ������ƒc | �n�������� | �S�� ���� �ғ� | |||||
| ���� �⏕�� | �� �t �� | �����q �ݕt�� | �⏕�� �o���� ���S�� | �����q �ݕt�� | ||||||
| �V���� | �k���V���� | ����E����� | �� �t �� �� | 2/3* (������t�� �v�͒�z�� 724���~) |
1/3* | |||||
| ���E����� | ||||||||||
| ������E���� | ||||||||||
| ����E��z�� | ||||||||||
| ���k�V���� | �����E���ˊ� | |||||||||
| ���ˁE�V�X�� | ||||||||||
| ��B�V���� | ����E���������� | |||||||||
| �D�����E�V����� | ||||||||||
| �� �s �s �� �� �� |
�s�s�S���� | ��V��** | �H�t���E���Ί� | 6% | 40% | 14% | 10% | |||
| �D����** | �����E�����̗������� | 50% | 4% | |||||||
| �}���** | ���R��E�}�O�O���� | 51% | 3% | |||||||
| ���S�� | ����8���� | ���n�E���|������ | �u���S���H���ɂ݂�S�����c�� �t�@�C�i���X�@�\�v�̖{���Q�� | |||||||
| �����r�ܐ� | ���n�E�ΐ_������� | |||||||||
| �����ɐ���� | �|�m�ˁE�k�z�J�� | |||||||||
| �����ɐ����(2) | �g�M�E�ƕ����� | |||||||||
| ���������(2) | �X�ь����E���쒬�� | |||||||||
| ���c�}���c����(2) | ���k��E�a����� | |||||||||
| ������ | ��ˁE�O������� | |||||||||
| ������ڰىH�c�� | ������E�V������� �� | |||||||||
| �݂ȂƂ݂炢21�� | ���l�E������ | |||||||||
| ��ʍ����S���� | �����J�����E�Y�a���� | |||||||||
| �ՊC���s�S����� | �������߰āE���� | |||||||||
| ��v���� �S���� |
���C����(�ݕ�) | �����ݕ�����فE ���ݕ�����ي� | 70% | 30% | ||||||
| ������ | �����E������ | 50% | 50% | |||||||
| �n���S�� �V��(AB��) |
�h�ѐ�*** | �h�сE������ | 100% | |||||||
| �䌴��*** | ���ЁE�_�ӊ� | |||||||||
| ������*** | ��ƁE�ޔ����� | |||||||||
| �����S�� ���K�i������ | �k�z�k�� | �Z�����E�Ҋ��� | 20% | 20% | 60% JR�����{ | |||||
| �V������ | �����V���� | �����s�E���s�� | 100% | |||||||
| �l���V���� | �{�B�E�W�H���� | |||||||||
| �������(�H���E����) | 100% | |||||||||
�@�S�����c�̎������B���\2-2�Ɋ�Â��ĉ������ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@�����̂����A�L���q�ݕt���ƓS�����ݍ��ɂ��ẮA�S�����c��1998(����10)�N3�����B�ł̋����͕\2-4�̂悤�ɂȂ��Ă��āA���s�җ����Ō���ƁA���{����Ǝ����^�p�������ؓ���(���������������)�̎������B�R�X�g���������Ƃ��킩��B
�\2-4. �S�����c�̒��B���� 1998(����10)�N3�����B��
| �z�ʋ��� | ���s�җ���� | |
|---|---|---|
| �����^�p�������ؓ��� | 2.1% | |
| ���{�ۏ؍� | 2.0% | 2.152% |
| ���{����� | 2.0% | 2.077% |
| ���ʍ� | 2.0% | 2.133% |
| ���Ԏؓ��� | 2.25% | |
�@�\2-3�ɐ�������Ă����悤�ɁA�V���ɘH�������݂�����A���ǍH�����s�����肷�鎞�ɂ́A�S�����c�́A�H���̎{�s�Ǘ��Ɠ����ɁA���⎩���̂̕⏕���△���q�ݕt���A���������A�����Č��c�ɂ��s�����B�ȂǂŎ������W�߁A�H��������q�������B����Ƃ����t�@�C�i���X�@�\���ʂ����Ă���B���������t�@�C�i���X�@�\�̏ے��I�Ȏ��Ƃ��A�\2-3�̒��́u���S���v�H���ł���B���S���H���́A���c�H���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ă��A��莄�S�̏ꍇ�͊e�Ђ����ЂŎ{�s�Ǘ����Ă���A���c���{�s�Ǘ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@���S���H���́A1972�N(���a47�N)�Ɍ��c�@�̒��Ɏ���(P��; Private���̈Ӗ�)�Ƃ��ĉ�����ꂽ�B���Ƃ��ƓS�����Ƃ̍H���ɓ������ẮA�S�����Ǝ҂͓S�����Ƃ̖Ƌ�����(�Ƌ������ɂ���ꍇ�͕s�v)�ɁA�S�����Ɩ@��8���1���ɒ�߂�H���̎{�s�̔F�\����������B�����āA�^�A��b�̔F��A�S�����Ǝ҂����c�H���̐\���o(���c�@��22��)���s�����ꍇ�ɂ����āA�S�����c���s�����Ƃ��K���ł���ƔF�߂鎞�́A�^�A��b�́A�H�����{�v����߂āA�����S�����c�Ɏw������B�������A���̂��Ƃ́A�S�����c���H���̎{�s�Ǘ����s�����Ƃ��Ӗ����Ă��Ȃ��B�S�����Ǝ҂ƓS�����c�̂ǂ��炪�{�s�Ǘ����s���̂��́A���҂̊Ԃŋ��c���Č��߂邱�ƂɂȂ��Ă���A���ہA1997(����9)�N�x�ł́A�����A�����A���c�}�́A���ЂŎ{�s�Ǘ����Ă���B
�@���ɖ��S�������ЂŎ{�s�Ǘ�����ꍇ�ł����Ă��A�^�A��b���H�����{�v����߂āA�����S�����c�Ɏw�������ۂɂ́A�S�����c���͂��̎w�����āA�H�������S�z��L�����B�����Ƃ��Ď����^�p�������ؓ���(���u����3�N�A���Ҋ���25�N)�ƓS�����ݍ��Œ��B����B�S�����ݍ���10�N�����ꊇ���҂ŁA���{�ۏ؍A���{����A���ʍ�3��ނ�����B������u���c�v�Ƃ�����͓̂��ʍ̂��Ƃł���B3��ނ̓S�����ݍ��̒��B�����͕\2-5�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���x�����x���ύX�ɂȂ��Ă��Ă���B
�\2-5. P���̗L�����B�����̒��B����
| �����̘g�� | �����̘g�O | ���B�����̊ | ||
|---|---|---|---|---|
| �����^�p�� �����ؓ��� | ���{�ۏ؍� ���{����� | ���ʍ� (���c��) | ||
| 1972�N�x�`1978�N�x | 40% | 0% | 60% | �L�����B���� |
| 1979�N�x�`1981�N�x | ���҂̂��߂̎؊��[�������������L�����B���� | |||
| 1982�N�x�`1983�N�x | 40% | 60% | ||
| 1984�N�x�`1986�N�x | ���Ԏؓ����A���҂̂��߂̎؊��[�������������L�����B���� | |||
| 1987�N�x | 60% | 40% | ||
| 1988�N�x�`1997�N�x | ���҂̂��߂̎؊��[�������������L�����B���� | |||
| 1998�N�x�` | 40% | 60% | ||
�@������A�S�����c���́A���n���s���u�H���E��ԁv���ƂɁA���ݗ����{�Ǘ���A���R�X�g�v�Z���A���n���z�ɂ��ĉ^�A��b�̔F��(���c�@��23��)�B���S���́A��������n���Ă���A25�N50�������ŕԍς��A���c���́A���̏��n�������ؓ����̕ԍςƓS�����ݍ��̏��҂̍����ɓ��Ă邱�ƂɂȂ�B
�@���̍ہA���S�����ԍς���ۂ̋����͌����Ƃ��ė���5%���Ȃ��悤�ɂ���^�A�{�ݐ������ƒc���o�R�������q�⋋���x(�\2-1�́u�ݕt���y���n�����ݔ���q�⋋���v)���p�ӂ���Ă���B���Ȃ킿�A5%���镪�ɂ��ẮA���̒����镪��1/2�������A1/2��n�������̂����n��25�N��(�j���[�^�E������15�N��)���q�⋋���s���B���̗��q�⋋���x�́A��{�I�ɗL���q�����݂̂ŏ[�����Č��݂��ꂽ����(�����S���ォ���CD��(��3�͂ŐG���)�y��P��)�ɌW��ݕt���͏��n��̓S�����Ǝ҂̕��S���y�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��鏕�����x�ł���B
�@�������A���S���̏ꍇ�ɂ́A���̂悤�ɓS�����c�����B����P�������ƕ����āA���S�������B���������p���邱�Ƃ��i��ł���(�w���{�S�������c�O�\�N�j�xpp.199-227)�B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��ẮA
�Ȃǂ����p����Ă���B�\2-3�ł����A����8�����A�����r�ܐ��A�����ɐ�����A�����ɐ����(2)�A���������(2)�A���c�}���c����(2)�́A1 ����s�s�S���������Ǝ����A���c�}���c����(2)�A������(���s�����S��)�A�݂ȂƂ݂炢21���A��ʍ����S�����A�ՊC���s�S������́A2 ���S�����莖�Ǝ����𗘗p���Ă���B�Ⴆ�A1992(����4)�N�H������݂̂ȂƂ݂炢21���́A���l�s����O�Z�N�^�[�ł��鉡�l�����S�����ɑ��Č�t�����J���ҕ��S��������Ў����̌`�Ŏ���Ă���A�S�����c�̖��S���H���Ƃ��Ă͏��߂�P�������ȊO�̎��В��B�������������ꂽ�P�[�X�ł���B
�@�����������S���H���̏ꍇ�́A���c�H���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ă��A��莄�S�̘H���͊e�Ђ����ЂŎ{�s�Ǘ����Ă���̂ŁA���̏ꍇ�́A�S�����c�̓t�@�C�i���X�@�\�����ʂ����Ă��Ȃ��ƍl������B����ɑ�3�͂ŐG��鋌���S���ォ��̗L���ݕt�����Ƃ̑��݂Ȃǂ��l����ƁA����Ӗ��ł́A�S�����c�́A�H���̎{�s�Ǘ��\�͂������đݕt���Ȃǂ̃��[�X������Ă���m���o���N�I�Ȗ�����S�����Ǝ҂ɑ��ĉʂ����Ă���Ƃ����A�^�A�{�ݐ������ƒc�ƂƂ��ɓ��{�̓S�����݂̎������B�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@����܂ŁA�^�A�{�ݐ������ƒc(���S���������) �ƓS�����c���`��鎑�����B�̘g�g�݂ɂ��ďq�ׂĂ������A���悢�掑�����B�̉��p���Ƃ��āA����̓I�ɒn���S���ݔ�̎������B�X�L�[�����P�[�X��X�^�f�B�[�Ƃ��Ď��グ�邱�Ƃɂ��悤�B�����ł́A�n���S�̒��ł������s�𑖂�n���S�ł���c�c�n���S�Ɠs�c�n���S�A���m�Ɍ����A��s�����x��ʉc�c(�ȉ��u�c�c�v�Ɨ��L)�Ɠ����s��ʋǍ����d�Ԏ���(�ȉ��u�s�c�v�Ɨ��L)�ɂ�����V�����ݔ�̎������B�X�L�[���ɂ��Đ�������B
�@1998�N3�������݂œS�����݂��i�s���̎�Ȃ��̂́A�S�����c�̂Ƃ���ŐG�ꂽ�����V�����A���S�����܂ޑ�s�s��ʐ��A�����Ă��ꂩ����グ��n���S�ł���B�c�c���s�c���S�����c�𗘗p���Ă��Ȃ��̂ŁA�������B�X�L�[���͂��P���Ȍ`�Ŏ������Ƃ��ł���B�܂��A�n���S�ł͌X�̘H���E��Ԃ��Ƃ̎������B�X�L�[�������Ȃ�͂����肵�Ă���B�����������R����A��قǁA�n���S���݂͎������B�X�L�[���̏d�v�����l��������i�D�̍ޗ�����Ă���邱�ƂɂȂ邪�A�܂��́A�c�c�Ɠs�c�̊T�v�ƊW�ɂ��Đ������邱�Ƃ���n�߂悤�B
�@�����ŏ��߂Ēn���S���J�Ƃ����̂́A1927(���a2)�N12���A�����n���S��������Ђ̐E����2.2km (���݂̉c�c������̈ꕔ)�ŁA���ꂪ���{�ōŏ��̒n���S�ł��������B���̌�A1941(���a16)�N7��4���ɒ�s�����x��ʉc�c�@�Ɋ�Â��āA�c�c���ݗ�����A���N9���A����܂łɊJ�Ƃ��Ă��������n���S��������ЁA���������S��������Ђ̉c�ƘH��(�O�҂͐E�V����8.0km�A��҂͐V���E�a�J��6.3km)�y�іƋ����A�Ȃ�тɋ��l�n���S��������Ћy�ѓ����s�̖Ƌ���������āA�c�c�͉c�Ƃ��J�n�����̂ł���[5]�B�ݗ����̎��{����6,000���~�ŁA�������{�o��4,000���~�A�����s�ƊW�d�S�A���S���ϑg�������킹��2,000���~�ł������B1998�N3�������݂̉c�c�̎��{����581���~�A�������{����310���~(53.4%)�A�����s����271���~(46.6%)�ł���[6]�B
�@����A�s�c�́A1911(����44)�N8��1���ɁA�����s�������S��������Ђ����āA�����s�d�C�ǂ�n�݂��ĘH�ʓd��(�s�d)���ƂƓd�C�������Ƃ��J�n�����̂��n�܂�ł���B���̌�A1924(�吳13)�N�̊֓���k�Ђő��Q�����s�d�̉��}�[�u�Ƃ��Ďn�߂��捇�o�X(�s�o�X)���ƂȂǂ������A1943(���a18)�N7��1���̓s���{�s�ɂ��A�����s�d�C�ǂ��瓌���s��ʋǂւƖ��̂�ς��Ă���B�c�c���ݗ����ꂽ���_�ł́A��������͉c�c�ɖƋ��������n�������̂́A�c�c�����ł͒n���S���݂��x���Ƃ��āA1954(���a29)�N3��29���ɓs�c��s�c�n���S���݂����c���A�Ăђn���S���݂ɏ��o�����B1958(���a33)�N3��1���ɒn���S1�����̖Ƌ��E�����擾���A���N8��31���ɒ��H�A1960(���a35)�N12��4���ɁA���߂Ă̓s�c�n���S�ł���n���S1����(���݂̐�)�̐��E����Ԃ��J�Ƃ��Ă���B�����������j�I�o�܂����邽�߂ɁA1998�N3�������݁A�����s��ʋǂ�
�̌܂̎��Ƃ��o�c���Ă���B��v��ł��A��ʎ��Ɖ�v(1, 2, 3)�A�����d�Ԏ��Ɖ�v(4)�A�d�C���Ɖ�v(5)�̎O�ɕ�����Ă���̂ŁA�����ł͓����s��ʋǑS�̂ł͂Ȃ��A�����d�Ԏ��Ƃ��������グ�āu�s�c�v�ƌĂԂ��Ƃɂ����̂ł���B
�@1998�N3�������݂ŁA�c�c�n���S�̑��c�ƃL������171.5km�A�s�c�n���S�̑��c�ƃL������77.2km�ƂȂ��Ă���B
�@�c�c�Ɠs�c�̒n���S���ݔ�̎������B�X�L�[���͋��ʓ_�������B����́A��ɂ́A�^�A�{�ݐ������ƒc�Ɠ����s�̒n���S���݂ɑ���⏕�����x�̘g�g�݂����ʂ��Ă��邩��ł���A������ɂ́A�c�c���s�c�����͂ō��ɂ�鎑�����B���\�ɂȂ��Ă��邩��ł���B
�@����ł́A�ŏ��ɓs�c�̒n���S���ݔ�̎������B�X�L�[���ɂ��Ă݂Ă݂悤�B����͍����Ƃ����`�ŕ\2-6�̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B
�\2-6. �s�c�̒n���S���ݔ����(�u��4���[���v)
| ���� | �v�Z��* | �\���䗦 |
|---|---|---|
| (1)���ɕ⏕�� | (1)��(�����ݔ�\���W��\�ԗ���\���ݗ��q) �@�~�@�@1.02�@�@�~�@�@80%�@�@�~�@35%�@�~�@90% �@�������悹�@�o�����T���@�@�⏕���@1�����k |
19.79208% |
| (2)��ʉ�v�⏕�� �@(�����s) |
(2)��(�����ݔ�\���W��\�ԗ���\���ݗ��q) �@�~�@�@1.02�@�@�~�@�@80%�@�@�~�@35% �@�������悹�@�o�����T���@�@�⏕�� |
21.9912% |
| (3)��ʉ�v�o���� �@(�����s) |
(3)�������ݔ�@�~�@20% �@�@�@�@�@�@�@�@�o���� |
20% |
| (4)���c��ƍ�(�n����) | (4)�������ݔ�|{(1)�{(2)�{(3)} | 38.21672% |
| �v | 100% |
���̒n���S���ݔ�����́A���ɇ@�ƇA�̖Ԋ|�������Ɋւ��ẮA�s�c�ł��c�c�ł��u��4���[���v(�u����4�N�x���[���v�̈Ӗ�)�ƌĂ�Ă���⏕�����x�Ɋ�Â������̂ł���[7]�B
�@���́u��4���[���v�́A��q����悤�ɁA�n���S���݂ɂƂ��āA����Ӗ��ł͉���I�ȕ⏕�����x�ł��邪�A1992(����4)�N�x�Ɉ�Ăɏo���オ�����̂ł͂Ȃ��A���N�������āA�������̉����_��ςݏグ�āA����������̃��[���̂悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ͒��ӂ�����B�܂��A(1)�̍��ɕ⏕����1990(����2)�N�x�܂ł́A���ډ^�A�Ȃ��c�ƊO���v�Ŏ����^�c��⏕�������������A1991(����3)�N�̓S����������̐ݗ��ɔ����A�S�����������ʂ��Ď��{�I�����Ŏ���鎑�{��⏕�����Ɉڍs���Ă���B����͎��v�I�����y�юx�o�ɓ��Ă���u3��⏕���v���玑�{�I�����y�юx�o�ɓ��Ă���u4��⏕���v�ւ̐��x�ύX�Ƃ������Ƃ��ł���[8]�B�܂��⏕���̌�t�̎d�����A1991(����3)�N�x�ɂ����ẮA�܂��e�N�x�̕⏕����7%�ŁA5�N������t(�v35%)�Ƃ���Ă������A1992(����4)�N�x�ɂ͈ꊇ��t�ɂ��⏕���x�ɕς�����B�����������ɕ⏕���̐��x�ύX�ɍ��킹�āA�����s��ʉ�v�⏕���̐��x�����߂��Ă���B����ɁA���ɕ⏕���̔�ڂ́A1994(����6)�N�x�\�Z����A�u���̑��{�ݔ�v�������I�ȍ������m�ۂ����u�������ƊW��v�ւƈڍs���Ă���B
�@�c�c�ł��⏕���̐��x�͊�{�I�ɓ����ŁA�u��4���[���v�ƌĂ�Ă���B�������A�������̑���_������B�܂��c�c�ł́A�u��4���[���v�̎������B�X�L�[���ɂ����āA�\2-6�̒���(3)�����s�̈�ʉ�v����̏o���������݂��Ȃ�[9]�B�܂����ݗ��q�ɂ��ẮA�s�c�ł͌��ݗ��q���������B�X�L�[���̒��ōl���Ă��邪�A�c�c�ł͌��݂͌��ݗ��q���������B�X�L�[���̒��ł͍l�����Ă��炸�A�c�Ǝ��v���Řd�����ƂɂȂ��Ă���B���������āA�}2-1�̂悤�ɁA���ݗ��q���������s�c��(3)��(4)�ɊY�����镔�����A(5)�����ؓ�����(6)�c�c�����s��������ʍ���(��s�ؓ������܂ޏꍇ������)�Œ��B���邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̕�����7���͍����ؓ����Ƃ��Ē��B�ł��邱�ƂɂȂ��Ă���A3���������ʍ��Ŏs�����璲�B�����B�s�c�̏ꍇ�����c��ƍ̈ꕔ�͍����Œ��B����Ă���B���ݗ��q�̕��������A(1)���ɕ⏕����(2)�����s�⏕���Řd����䗦�͓s�c���c�c�������ɂȂ�B
�}2-1. �n���S���ݔ�����̔�r(�u��4���[���v)*
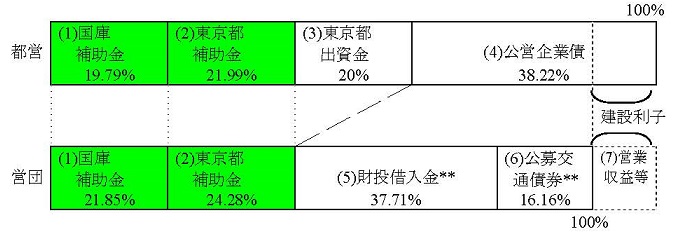
* ���W��5%�A�ԗ���6%�A���ݗ��q12%�Ɖ��肵�Ď��Z�������̂ł���B
** �c�c�ł͒n���S���ݔ�̍����̂����A(1)�����s�̈�ʉ�v�⏕����(2)���ɕ⏕�����������c���7���������ؓ����Œ��B�ł��邱�ƂɂȂ��Ă���A3���������ʍ��Ŏs�����璲�B���Ă���B
�@�s�c�ɂƂ��Ă��c�c�ɂƂ��Ă��A���̔��s�͌��ݎ������B�̂��߂̏d�v�Ȏ�i�ł���B�s�c�̏ꍇ�A���c��ƍ�(�ȉ��u��ƍv�Ɨ��L)�͌��݉��Ǎ�(�ȉ��u���ݍv�Ɨ��L)�ƌ��ݍ̗��q���x�������߂̓���Ƃɕ������邱�ƂɂȂ�B����́A1970(���a45)�N�x���甭�s����Ă��邪�A���ݍ̊e�N�x�̎x�����q�����z�ɑ��Ă̂ݔ��s����Ă���B
�@��ƍ̂��ׂ��ȕ��ނ͕\2-7�̂悤�ɂȂ邪�A���ԍ̒��̌���͈���V���W�P�[�g�c��������s���Ă���B��ƍ̂����A���ݍ̒����̗����͐}2-2�̂悤�ɐ��ڂ��Ă���B1990�N��ɓ����āA���������f���A�����͂ǂ�ǂ�ቺ���A1997(����9)�N�x���̎����ł̐��{�̗�����2.1%�ł�����[10]�B
�\2-7. �s�c�̌��c��ƍ�(1997(����9)�N�x)
| ����� | �������ݍ�(�~) | ���ϗ��� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ���ݍ� (���݉��Ǎ�) |
�Z���� | ���{�� | �ȈՕی��� | 5,267,000,000 | 2.0% |
| �����^�p�� | 8,827,000,000 | 2.0% | |||
| �Z���S�� | 14,094,000,000 | 2.0% | |||
| ������ | ���{�� | �ȈՕی��� | 85,946,518,376 | 4.9% | |
| �����^�p�� | 156,477,266,341 | 5.7% | |||
| ���c��Ƌ��Z���� | 12,821,330,420 | 6.0% | |||
| ���ԍ� | ����(�s������) | 57,366,700,000 | 4.0% | ||
| ���ϑg�� | 21,189,000,000 | 3.6% | |||
| ��s(���̍�) | 61,433,500,000 | 3.8% | |||
| �O��(�O�ݍ�) | 160,290,713,019 | 4.6% | |||
| �����S�� | 555,525,028,156 | 4.8% | |||
| ���݉��ǍS�� | 569,619,028,156 | 4.7% | |||
| ����� | ������ | ����(�s������) | 3,388,400,000 | 4.8% | |
| ��s(���̍�) | 63,459,500,000 | 4.7% | |||
| ���c��Ƌ��Z���� | 25,252,266,901 | 4.3% | |||
| ����S�� | 92,100,166,901 | 4.6% | |||
| ��ƍS�� | 661,719,195,057 | 4.7% | |||
�}2-2. �s�c�̌��݉��Ǎ�(������)�̕\�ʗ����̐���
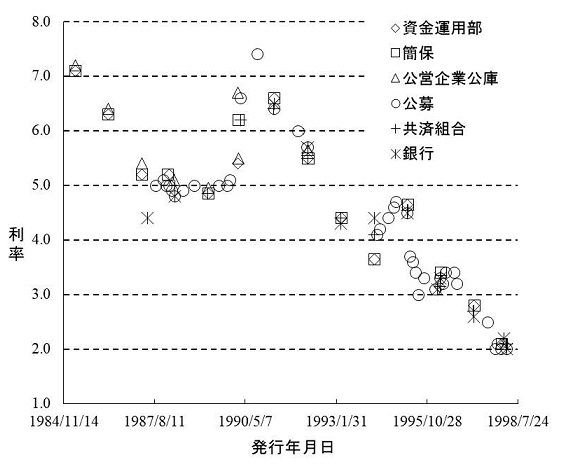
�@�s�c����ƍ𐭕{�Ɩ��ԍɕ��ނ��Ă���悤�ɁA�c�c�̏ꍇ�A��ʍ��͎����^�p���ƊȈՕی��ǂ�������u���{������v�ƈ���V���W�P�[�g�c��������s���Ă���u�����ʍ��v�Ƃɕ��ނ���Ă���B�������A���ݎ��̐V�K�̐��{������́A�^�p�������ɂ��Ă�1981(���a56)�N�x�ȍ~�A�ȕێ����ɂ��Ă�1990(����2)�N�x�ȍ~���s����Ă��炸�A�؊����݂̂����s��F�߂��Ă���B���������ĉc�c�̏ꍇ�A�ݔ����������ɌW�����������́A1990(����2)�N�x�ȍ~�͂��ׂĎؓ����̌`�Ŏ���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɋ��ʓ_�̑����s�c�̌��ݍƉc�c�̌�ʍ��ł͂��邪�A���Ҋ����ɂ��Ă͈Ⴂ������B�s�c�̐��{�̏��Ҋ����͈�т���30�N�ł���̂ɑ��āA�c�c�̐��{������́A1988(���a63)�N�x�܂ł�12�N�A1989(������)�N�x�ȍ~��10�N�ł���B�����Ƃ��A�c�c�̐��{������́A��{�I�ɏ��Ҋ���10�N�ł��A�芷����2��\�ł��������߁A�v30�N�܂Ŏ�Ă����邱�ƂɂȂ��Ă����ƌ����[11]�A���̈Ӗ��ł͎����I�ɓ����Ƃ�����̂�������Ȃ��B�������A1990�N��㔼����̍����ᔻ�̒��ŁA�c�c�̐��{������ɂ�钲�B������Ȃ�A1998(����10)�N�x�ȍ~�́A�芷��������F�߂��Ȃ��Ȃ��Ă���B���݂̂悤�Ȓ��������ɂ����ẮA���̏��Ҋ����̈Ⴂ�́A�c�c�ɑ��Ă͕s���ɓ�����������Ȃ��B�������A����������ɁA�s�c�̂悤��30�N�Ƃ����������̐��{����Ŏ����B����ƁA�J�グ���҂��ł����ɍ������ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�B���̈Ӗ��ł́A�c�c�̐��{������̂悤�Ɋ�{�I�ɏ��Ҋ���10�N�ŁA�芷����2��\�Ƃ������V�X�e���̕����A�������B���X�N�̉���ɂ͗L����������Ȃ��B
�@�܂�����̏ɍ��킹�ď��Ҋ����̐ݒ���l����ׂ��Ȃ̂ł���B�������̎��ɂ͒����ؓ����Ƃ����Ă��ł��邾���Z���Œ��B���ׂ��ł��邵�A������̎��ɂ́A�ł��邾�������Ŏ������B�����ׂ��Ȃ̂ł���B���{����ł͂Ȃ��Ȃ������@���I�ɔ��s���ł��Ȃ��̂ł���A���ԍ��邢�͌���ł��̓���T��ׂ����낤�B���ہA�c�c�̌�ʍ��̗����͐}2-3�̂悤�ɂȂ邪�A�s�c�̌��ݍ̗����������}2-2�Ɣ�r����ƁA�����̓����͂قڏd�Ȃ��Ă�����̂́A1995(����7)�N�x�ȍ~�A�c�c��������ŏ��Ҋ���20�N�̂��̂̔��s���n�߂����߂ɁA20�N���̂̌������10�N���̂̐��{������Ɣ�ׂāA������0.6%���x�����Ȃ��Ă���B����́A������̊Ԃɑ��������������Ȃ��Ă��A�o���邾�������̍��s���Ă������Ƃ����c�c���̈Ӑ}�ōs���Ă���A�d�͊e�ЂȂǂ����l�̂��Ƃ��n�߂��Ƃ����s�ꓮ���܂��Ă̂��Ƃł������B����ɑ��āA�s�c�͈�т��Ė��ԍ̏��Ҋ�����10�N�ł���A���̓_�ɂ��Ă͎������B�ɑ���s�c�Ɖc�c�̎p���̈Ⴂ��������B
�}2-3. �c�c�̌�ʍ��̕\�ʗ����̐���
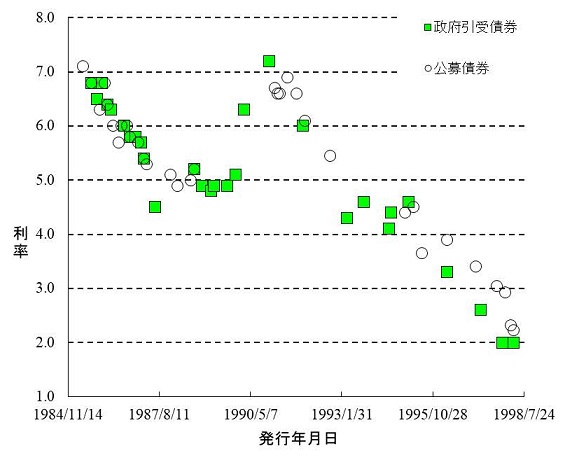
�@�Ƃ���ŁA�s�c�̌��݉��Ǎ̔��s�ɂ͓����̊ԁA�����Ȃ̋����K�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B1993(����5)�N�x�`1997(����9)�N�x��5�N�Ԃ̕��ςł́A���݉��Ǎ̋N���z�̊����͐��{��34%�A���ԍ�66%�ƂȂ��Ă����B����ɑ��āA�������̉c�c�̌�ʍ��̔��s���z�̊����́A���{�����26%�A�����74%�ł��������A���̎������s���ꂽ���{������͂��ׂĎ芷�����Ȃ̂ŁA�n���S���ݎ����̒��B�����Ƃ͈قȂ邱�Ƃɂ͒��ӂ�����B���ۂɂ́A���ɏq�ׂ��悤�ɁA�c�c�̏ꍇ�A�}2-1�̒n���S���ݔ�̍����̂����A1.���ɕ⏕����2.�����s�̈�ʉ�v�⏕�����������c��������ʍ��ƍ����ؓ����Řd���Ă���킯�����A7���������ؓ����Œ��B�ł��邱�ƂɂȂ��Ă���A�c���3���������ʍ��Ŗ��Ԃ��璲�B���Ă���B
�@�n���S���ݔ�⏕���x�͂���܂łɉ��x�����x�ύX���s���Ă��Ă��邪�A�s�c���Ɏ��A�n���S�̌��ݔ�ɑ�������⏕����1978(���a53)�N�x�`1982(���a57)�N�x��59.85%(���Ɏ����⏕����29.93%)���s�[�N�ɂ��ĉ����葱���A1991(����3)�N�x�ȍ~��41.78%(���Ɏ����⏕����19.79%)�ƂȂ��Ă���B����͐}2-4�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA1978(���a53)�N�x�ȍ~�A���ڕ⏕������70%�ň��̂܂܂����A�\2-6�̒��ŋ������悤�Ȕ�ڂ�lj��I�ɕ⏕���̑Ώی��ݔ��T������悤�Ȑ��x�ύX���s���Ă������߂ł���B1991(����3)�N�x�ȍ~�́A�����⏕����41.78%(���Ɏ����⏕����19.79%)�ɂ܂Œቺ���Ă��܂����B���̂��߁A�u��4���[���v�ł�38.21672%����ƍɂ���Ęd�����ƂɂȂ��Ă���B
�}2-4. �s�c�̒n���S���ݔ�⏕��
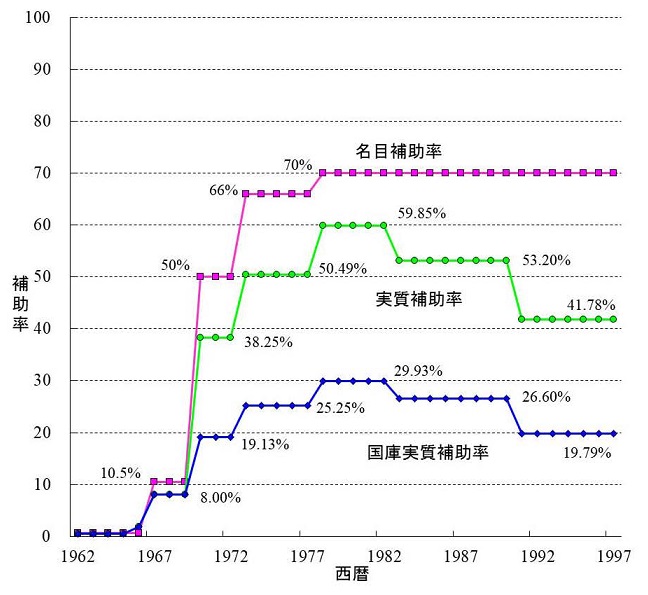
�@����������͕\�ʏ�̂��Ƃł���A���ۂɂ́u��4���[���v�̗̍p��1991(����3)�N�x����͎��{��⏕�ƂȂ邱�ƂŁA���ݔ�ɒ��ڕ⏕���������ł���悤�ɂȂ�A�����1992(����4)�N�x����́A���̕⏕�����ꊇ��t�����悤�ɂȂ������ƂŁA���ꂩ�猩��悤�ɁA���s����N�z���i�i�ƌ������A����܂Œn���S���Ƃ̎��x���������Ă����x�������̌y�����}���邱�ƂƂȂ����B����Ȃǂ́A�����⏕���̍��Ⴞ���ł͂Ȃ��A�������B�̎d�����̂����͏d�v�ȗv���ł��邱�Ƃ�@���Ɏ������Ⴞ�Ƃ����邾�낤�B
�@�u��4���[���v���ł���O�܂ł�(���O�́u53���[���v�܂菺�a53�N�x���[��)�A�����⏕���͕\�ʓI�ɂ͍����Ɍ����Ă������A�n���S���ݎ��ɕ⏕����̂ł͂Ȃ��A10�N�Ԃ̕����Ō��݂̎��̔N���班�����⏕������t�����Ƃ������̂�����[12]�B���̊Ԃɂ��A���ݎ��ɂ܂Ƃ߂Ĕ��s����Ă�����ƍ���́A����ȗ��q�������������邱�ƂɂȂ�B
�@���̂��Ƃ�s�c���ɂ��āA���Z���Ċm�F���Ă������B���܉��ɒn���S���ݔ1,000���~�ł������Ɖ��肵�悤�B�����ŁA
�Ƃ������Z������ŁA�⏕���̕�����t�����Z���Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B���̏����̂���2��3���u53���[���v�ł���A�������ċ��߂��e�N�x�̕⏕�����v�z�͍��ɂƓ����s��ʉ�v��1/2�����S���邱�ƂɂȂ�B
�@���Z���ʂ͕\2-8�Ɛ}2-5�Ŏ������B����ł킩��悤�ɁA�u53���[���v�ł́A1,000���~�̑����ݔ�ɑ��āA���݊J�n2�N�ڂ���15�N�ڂ܂łɕ⏕����������t����A��ԑ���6�N�ڂł�72���~���x�����x�����Ȃ��B�܂葍���ݔ�1,000���~�ɑ��āA�s�[�N���ł�7.2%�����⏕������t����Ȃ��̂ł���B����͎�����̗��q�⋋�ɂ����Ȃ��Ƃ����Ă������낤�B
�\2-8. �u53���[���v�ł̕⏕��������t���@�@�@�@�@�@�@(�P��: ���~)
| �N�x | A���ݔ� | B�⏕�Ώۊz (A��85.5%*) | C�⏕�����v (B��70%**) | ��t�N�x*** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1�N�� | 2�N�� | 3�N�� | 4�N�� | 5�N�� | 6�N�� | 7�N�� | 8�N�� | 9�N�� | 10�N�� | 11�N�� | 12�N�� | 13�N�� | 14�N�� | 15�N�� | �v | ||||
| 1�N�� | 200 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 2�N�� | 200 | 171 | 119.7 | 20.52 | 17.10 | 13.68 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 6.84 | 119.7 | |||||
| 3�N�� | 200 | 171 | 119.7 | 20.52 | 17.10 | 13.68 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 6.84 | 119.7 | |||||
| 4�N�� | 200 | 171 | 119.7 | 20.52 | 17.10 | 13.68 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 6.84 | 119.7 | |||||
| 5�N�� | 200 | 171 | 119.7 | 20.52 | 17.10 | 13.68 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 6.84 | 119.7 | |||||
| 6�N�� | 171 | 119.7 | 20.52 | 17.10 | 13.68 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 6.84 | 119.7 | ||||||
| �v | 1,000 | 855 | 598.5 | 0 | 20.52 | 37.62 | 51.30 | 61.56 | 71.82 | 61.56 | 54.72 | 51.30 | 51.30 | 47.88 | 37.62 | 27.36 | 17.10 | 6.84 | 598.5 |
�}2-5. �u53���[���v�ł̕⏕��������t��
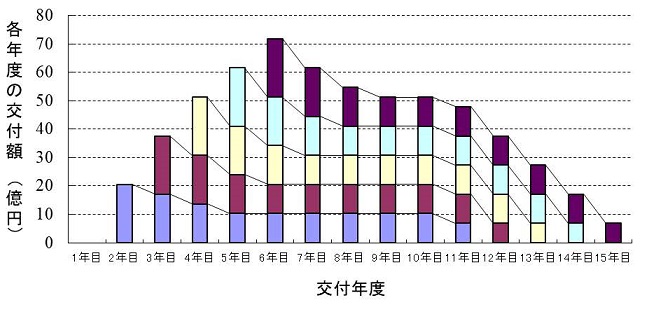
�@�����A�u53���[���v�̂��Ƃł́A�s�c���n���S���݂��Ă��鎞�_�ł́A�����s�̈�ʉ�v�⏕�����A���ɕ⏕������t����Ă��炸�A�����ݔ��10%�ɑ������铌���s�̈�ʉ�v�o�����ȊO�̕����A���ɑ����ݔ��90%����ƍɂ���Ē��B���āA�L���q�����Ŏ������q���ł��������Ȃ������B�܂�A�����ɂ���ƍ̗��q���⏕���̊z���x�͔����������Ă����̂ł���B
�@�c�c�����㔭�̓s�c�̏ꍇ�A�V���̌��݂��������s���Ȃ���A�u53���[���v�̂悤�Ȑ��x�̉��ŁA���̌��ݔ�p�̂��Ȃ�̕�����L���̊�ƍɗ����Ă������߂ɁA�c��Ȏx�������ƌ������p��������A�n���S���Ƃ̎��v�\�����ꂵ�����̂ɂ��Ă���B1997(����9)�N�x�̍����d�Ԏ��Ƒ��v�v�Z���ɂ��A�c�ƊO��p�́u�x�������y��ƍ戵����v��281���~�A�u�������p��v��278���~�ɂ̂ڂ�A���҂����킹��ƁA�������p����������c�Ɣ�p544���~�����̂��c��Ȋz�ɂȂ�B
�@���Ƃ��ƒn���S���ݔ�̕⏕���x�́A1962(���a37)�N�x�̔������ɂ́A���q�⋋���x�Ƃ��ăX�^�[�g���Ă���A���̌�⏕�������z����A�⏕�����㏸�����ȍ~���u53���[���v�܂ł́A�呠�Ȃ͒n���S�⏕�����ݔ�⏕�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��Ȃ������Ƃ�����(�ɓ�, 1996, pp.162-164)�B�������\�ʓI�Ɍv�Z���Ă݂�ƁA�u53���[���v�ł́A�s�c�ł��c�c�ł����ڕ⏕����70%�ł���A���ɓs�c�̏ꍇ�ɂ́A�����x�[�X�Ō��Ă��A�����⏕���ɓ����s����̏o����10%���������69.85%���������̂ł���B���ꂾ���̕⏕���ł���Ȃ���A���ǂ͗��q�⋋�ɂ����Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ƃ́A�⏕���̍���̖��Ƃ��������A�u�^�c��⏕�����v�Ƃ����������̂ɖ{���I�Ȗ��_���������ƍl����ׂ��ł��낤�B
�@����ɑ��āu��4���[���v�ł́A�����⏕����41.78%�ŁA�����s����̏o������20%�ɑ������ɂ�������炸�A����������Ă�61.78%�ɂ����Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���q���S�܂ł𑍌v����Ɠs�c�̎������S�́u��4���[���v�̕����͂邩�Ɍy������Ă���̂ł���B�܂�A�u��4���[���v�Ɣ�ׂāA�u53���[���v�̕������z�̏o�����E�⏕���𓊓����Ă����Ȃ���A���������̎d�����K�łȂ���������ɁA�s�c�̎������S���������đ��₵�Ă��܂��Ă������ƂɂȂ�̂ł���B�܂��Ɏ������B�X�L�[���̏d�v����Ɋ�������B
�@���̂��Ƃ𓌋��s��ʋǂ̎��Z�����Ƃɂ��Ċm�F���Ă������B��قǂƓ��l�ɁA���ɒn���S���ݔ1,000���~�ł������Ɖ��肵�悤�B�\2-9�Ŏ������悤�ɁA�u53���[���v�ł�900���~�A�u��4���[���v�ł�382���~�̊�ƍs����K�v������B
�\2-9. �����ݔ�1,000���~�̒n���S���ݔ�̍���(�s�c�̃P�[�X)
| ���ݎ��̎������B�z(���~) | ||
|---|---|---|
| �u53���[���v | �u��4���[���v* | |
| (1)���ɕ⏕�� | �| | 198 |
| (2)��ʉ�v�⏕��(�����s) | �| | 220 |
| (3)��ʉ�v�o����(�����s) | 100 | 200 |
| (4)��ƍ�(�n����) | 900 | 382 |
| �v | 1,000 | 1,000 |
�@�����ŁA
�Ƃ������Z������ŁA��ƍ��s��30�N��(���݊��Ԃ��܂߂��34�N��)�̌����̏��ҋ��z���z�����߁A�u53���[���v�̏ꍇ�͂��ꂩ��⏕���̍��v�z(�\2-8����A�����599���~�ɂȂ邱�Ƃ��킩��)�����������̂��u�������S���z�v�ƌĂсA��������߂邱�Ƃɂ��悤�B
�@�u��4���[���v�ł́A�⏕���͍ŏ��̒i�K�Ō�t����Ă��܂��Ă���̂ŁA��ƍ̔��s�z�̈��k�ɍv�����Ă��邾���ŁA��ƍ̏��Ҏ��ɂ͕⏕���͎p�����킳�Ȃ��B����ɑ��āu53���[���v�ł́A�⏕���͂�����u3��⏕���v�ƌĂ�A���v�v�Z���̉c�ƊO���v�Ɂu���ɕ⏕���v�u��ʉ�v�⏕���v�Ƃ��Čv�コ���B�c�ƊO��p�ɂ́u�x�������y��ƍ戵����v���v�コ���̂ŁA�`���I�ɂ��A�c�ƊO���x�̂Ƃ���ŕ⏕�������q�⋋�ɓ��Ă��Ă���\�}�������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������āu53���[���v�ł́u3��⏕���v�̌`�ŕ⏕���s������̂́A�ŏ��̌��ݒi�K�ł̊�ƍ̔��s�z��900���~�Ɩc��ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
�@��ƍ̗�����2%�`6%�܂�1%���݂ŕς��Ȃ���A�����s��ʋǂ����Z�����Ƃ���ɂ��ƁA�\2-10�Ɛ}2-6�̂悤�ɂȂ�B�����I�ɂ��A��ƍ̗���������������قǁu53���[���v�ł͗��q�̕��S�����d���̂��������Ă��邱�Ƃ��킩�邪�A���ۂɂ͊�ƍ̗�����2%�Ƃ���������ł��A�u��4���[���v�̕����A�o�����E�⏕���̍��v�����z�����Ȃ��ɂ�������炸�A�s�c�̎����I�ȕ��S���y�����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�����ݔ�1000���~�ɑ��āA����6%�ł͂��̍��z��563���~�ɂ��Ȃ�B�ʂ̌���������A����6%�̂Ƃ��A�����ݔ�1,000���~�ɑ��āA���q�܂œ��ꂽ�s�c�E���ɁE�����s��ʉ�v�̎x�o���v�z�́A�u��4���[���v�Ȃ��1,475���~�ōςނ̂ɁA�u53���[���v�ł͎���2,119���~�ɂ܂Ŗc��ނ̂ł���B
�\2-10. �����ݔ�1,000���~�̏ꍇ�̊�ƍ��ҏI�����܂ł̎������S���z�̔�r�@(�P��:���~)
| ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | ||
| 53���[�� | ��ƍ��s�z | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ���q | 338 | 521 | 712 | 912 | 1,119 | |
| 3��⏕��(���q�⏕) | -599 | -599 | -599 | -599 | -599 | |
| �������S���z | 639 | 822 | 1,013 | 1,213 | 1,420 | |
| ��4���[�� | ��ƍ��s�z | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| ���q | 144 | 221 | 302 | 387 | 475 | |
| 3��⏕��(���q�⏕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| �������S���z | 526 | 603 | 684 | 769 | 857 | |
�}2-6. �����ݔ�1,000���~�̏ꍇ�̊�ƍ��ҏI�����܂ł̎������S���z�̔�r
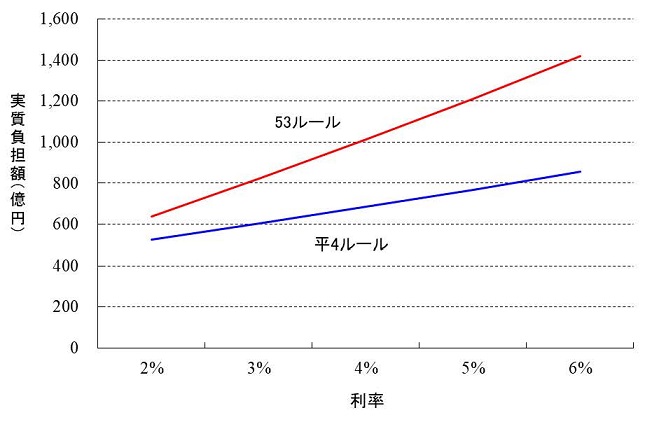
�@���̏͂���߂�����ɓ������āA�L���q���������ɁA�S�����Ǝ҂̎������B�X�L�[���̂�������ȒP�ɐ������Ă������B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�����ł̎咣�͒P���ł�������O�̂��Ƃł���B���_�I�ɂ����A���z�̗L���q�����𗘗p���čs����S�����݂ƓS���o�c�́A�����Ƃ̋����ł���B�⏕�������{��⏕�Ƃ��Č��ݎ��ɏW���������A�L���q���z�ƍH�����Ԃ̗������ł��邾�����k���Ȃ���A�S�����Ƃ̎��v�\�����̂��������Ă��܂��B�ɂ�������炸�A����܂ł͍����⏕�����L�͂������ɂ킽���Ĕ�����܂��Ƃ����t�̂��Ƃ����Ă����悤�Ɍ�����B���q�⋋�I�ȉ^�c��⏕���ő����̐V�����݂����H����Ă����B����ǂ��납�A�������B�X�L�[�����̂��L�������������͖������ꂽ�ɓ������P�[�X���������̂ł���B
�@�Ⴆ�A�c�c�̓�k���́A�⏕���𗘗p������ԁu�ԉH�╣�E��ԁv�Ɖ^�A�{�ݐ������ƒc(���S���������)�̖����q�ݕt�����x�𗘗p������ԁu��E�ڍ��ԁv�Ƃ���Ȃ��Ă��邪�A�T�ˁA�\2-11�̂悤�ȍ����̊����ɂȂ��Ă����B���̕\������킩��悤�ɁA��k���̌��ݔ�̍����́A�ڂ܂��邵���ς���Ă���B���Ɂu��E�ڍ��ԁv�́A�傫�ȕύX���������Ă��A�ŏ��́u53���[���v�̕⏕���𗘗p���Ă������A1991�`1998(����3�`10)�N�x�͖����q�ݕt�����x�𗘗p���A1999(����11)�N�x�ɂ͍��x�́u��4���[���v�̕⏕�����x�𗘗p����`�ɖ߂��Ă���B
�\2-11. �c�c��k���̌��ݔ����(�v�掞)*
| ��� | �ԉH�╣�E��� | ��E�ڍ��� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �J�Ǝ��� | 1991(����3)�N11��29�� | ��E�l�b�J�ԁ@1996(����8)�N3��26�� �l�b�J�E���r�R���ԁ@1997(����9)�N9��30�� ���r�R���E�ڍ��ԁ@2000(����12)�N�H�\�� | ||||||||
| �N�x | 1985�`1986 | 1987�`1991 | 1992�`1997 | 1998�` | 1985�`1986 | 1987�`1990 | 1991 | 1992�`1998 | 1999�` | |
| ���a60�`61 | ���a62�`����3 | ����4�`9 | ����10�` | ���a60�`61 | ���a62�`����2 | ����3 | ����4�`10 | ����11�` | ||
| �� �� |
���ɕ⏕��** | 25.34% | 21.41%*** | 25.05% | 21.80% | |||||
| ��ʉ�v�⏕��(�����s)** | 25.34% | 23.79%*** | 25.05% | 24.22% | ||||||
| �����q�ݕt��(���ƒc) | 34.60% | |||||||||
| �����q�ݕt��(�����s) | 34.60% | |||||||||
| �������Z���ؓ��� | 24.66% | 29.59% | 34.53% | 38.36% | 24.95% | 29.94% | 18.48% | 21.56% | 37.79% | |
| �����ʍ� | 24.66% | 19.73% | 14.80% | 16.44% | 24.95% | 19.96% | 12.32% | 9.24% | 16.19% | |
�@�����������̂́A�c�c�̏ꍇ�A�u��4���[���v���K�p�ɂȂ�̂́A1998(����10)�N�x����ŁA1991(����3)�N�x�����k���u��E�ڍ��ԁv�Ŗ����q�ݕt�����x�����p�����悤�ɂȂ������Ƃ𗝗R�ɁA�����q�ݕt�����x�𗘗p���Ă��Ȃ���k���̑��̋�Ԃ�11�����ɂ��Ă܂ł��u��4���[���v�͓K�p�ɂȂ�Ȃ������̂ł���B1998(����10)�N�x����c�c�ɑ���u��4���[���v�̓K�p���n�܂邪�A���̔N�x��1985(���a60)�N�x���H�̓�k���u�ԉH�╣�E��ԁv�̊��J�Ɛ��c�H��(���H�̖{�����H��)��1993(����5)�N�x���H��11�����ɂ��ēK�p���n�߂��Ă���B��k���u��E�ڍ��ԁv�ɂ��Ă͗�1999(����11)�N�x����u��4���[���v�̓K�p���n�܂�B
�@����܂ł́u53���[���v�̉��ł́A�⏕���͌��݂������͊J�Ƃ̗��N�x����x������Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͌��ݎ��ɂ́A���������Ɩ��Ԏ���(�����ʍ��E��s�ؓ���)�����Ŏ������B�����邵���Ȃ��A�⏕���͌ォ�痈����̂������̂ł��邪�A���ۂɂ́A�X�L�[���ƌĂԂ̂��͂����悤�ȁA�͂邩�ɕs���肩�s�m���ȍ����ł������B���́A1991(����3)�N�x�����k���́u��E�ڍ��ԁv�Ŗ����q�ݕt���̐��x�𗘗p����悤�ɂȂ�ƁA��������߂��ۂ́u�����q�ݕt���s���Ă���Ԃ́A�⏕���̌�t��ۗ�����v�Ƃ����呠�Ȏ�v�ǒ��Ɖ^�A�Ȓn���ʋǒ��̊o���Ɋ�Â��A����Ԃ̍��ɕ⏕���E�����s��ʉ�v�⏕���܂ł�����������Ă��܂����̂ł���B�܂�A���݊J�n�����ɍ����Ƃ��ė\�肳��Ă����͂��̕⏕���͌ォ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���̏�Ԃ́u��4���[���v���K�p�ɂȂ�1998(����10)�N�x�܂ő������̂ł������B���������āA�\2-11�̍����Ƃ��Ă̕⏕���́A���ǁA�Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@�܂�A�u53���[���v�̉��ł͕⏕���͂������������q�⋋���x�ł���ɂ�������킸�A����ƂĂ��m���ȍ����ł͂Ȃ��A�{���̈Ӗ��ł́u�������B�X�L�[���v�����Ă��A������Ԃł͂Ȃ������̂ł���B�����̉c�c�̎��Ԃ́A���{�����߂��������Z����������{�ɂ��Ēn���S���ݔ�B���A�s�����������ʍ����s�ؓ����Ŗ��Ԃ��璲�B����Ƃ����\�}�����Ȃ��������ƂɂȂ�B���ہA�u��4���[���v�△���q�ݕt�����x���o�ꂷ��ȑO�́u53���[���v�̎���܂ł́A�u�������B�X�L�[���v�Ƃ������t���̂��g���Ă��Ȃ������Ƃ������Ă���B
�@����ɁA���Ƃ��A�\2-11�́u��|�ڍ��ԁv�̍����̊���������ƁA�^�A�{�ݐ������ƒc(���S���������)�̖����q�ݕt�����x�𗘗p����Ɩ����q�Ō��ݔ��70%�߂������B�ł���̂ŁA�L���ł��邩�̂悤�ȍ��o���o���邪�A�����͂���قNJÂ��͂Ȃ��B�����q�Ƃ͂����A�ݕt���͕ԍς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA5�N���u��A10�N�ŏ��҂��邱�ƂɂȂ��Ă���B���ǁA���̖����q�ݕt���͍����ւ̎؊����ł��Ȃ����ƂɂȂ����̂ŁA����͍��������������̖��Ԏ���(�����ʍ��E��s�ؓ���)�Ŏ芷������������Ȃ��Ȃ����B������ɂ���A�����̍���̈Ⴂ�͂����Ă��A�������Č��ݔ�̑S�z���L���q���ɉ����邱�ƂɂȂ�B���ǁA���{�������q�ݕt���ɂ��n���S���݂�U���E���i�������ƂŁA�c�c�̗L���q���ւ̈ˑ��x�����߂Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł���B
�@�m���ɁA�S�����c�A�c�c�A�s�c�Ȃǂ̌��ݍH����̂����ɂ�鎑�����B�\�͂������Ă��邱�Ƃ͕֗��ł���B�������A�n���S���݂ɂ����āA�q�������̑��݂����Ăɂ����^�c��⏕�����̕⏕���ł́A70%�ɂ܂ŕ⏕�����グ�Ă��A���ǂ͗��q�⋋�ɂ����Ȃ�Ȃ������Ƃ��������͏d���~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������⏕�����L�͂������ɂ킽���Ĕ�����܂��Ƃ������z�̉��ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�������B�X�L�[�����A���ʓI�ɁA�ǂꂾ���̗��q���S��S�����Ǝ҂ɋ����Ă��������v���N�����K�v������B�⏕����������܂���邱�ƂŁA���ݍH���̃y�[�X�͒x���Ȃ邩�A���邢�͌��݂��}���Α��z�̎�����L���q���Ƃ��Ď��Ȓ��B������Ȃ��Ȃ�B������̏ꍇ���A�������܂߂��L���q�����𗘗p���Ă���ꍇ�ɂ́A��葽�z�̗��q�̔����ɒ�������B�S�����ݔ�̕s������Ȃ�������S�����ƎҎ��g�ɗL���q�����Ƃ��Ď��Ȓ��B������Ƃ������Ƃ����Ղɑ��������Ă���ƁA�J�Ƃ܂ł̍H�����Ԃ̊Ԃɗ��q�ł���ɗL���q���̊z���c��݁A�S�����Ƃ��̂��̂̎��v�\���̈������J�ƑO�Ɍ���I�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ����ǂ͒����I�Ɍ��āA���̂܂܍����̕��S�ɂȂ�̂ł���B
�@���̂��Ƃ͊��ɕ����Ă��܂������̏����ɂ����Ă͂܂�B�����ł��邾���Z���Ԃɕԍς���Ƃ������z���������ɁA���܍��킹�����Ă���ƁA���ǂ́A�����̕��S���傫���Ȃ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�s�c�̓���̌������ҋ�(�������{����)�ɑ��ẮA���ɂ��邢�͓����s�̈�ʉ�v����̕⏕������t����Ă��邪�A�\2-12�Ŏ�����Ă���悤�ɁA���̕⏕���̐��x�͉ߋ��ɉ��x���ύX����Ă��Ă�����̂́A����̌��������ɂ��Ă͈�т��āA�S�z�������s�̈�ʉ�v����⏕������t����Ă����̂ł���B����̗��q�����ɂ��ẮA1993(����5)�N�x�ȍ~�́A�N����4%�����z�����ɂƓ����s�̈�ʉ�v��1/2���⏕���邱�ƂɂȂ��Ă���B�܂�A���ݍ̗��q�����́A������͍��ɂ������s�̈�ʉ�v�Ŏx�������ƂɂȂ�̂ɁA���̎x������扄���ɂ��A���̊Ԃ����Ƃ����L���q�����łȂ����ƂŁA���ǂ͎x���������]�v�ɂ����ތ��ʂƂȂ��Ă���̂ł���B
�\2-12. �����d�Ԏ���(�s�c)�̓�����x�̐���
| �N�x | ���s���ꂽ����� | �⏕�Ώ� | �⏕���e | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������s�Ώ� | ��� | ������� | ������q | ||||
| �����s��ʉ�v | ���� | ||||||
| 1970�`1972�N�x | 1968�N�x�ȑO���s �̌��ݍ̗��q |
���{�� | ������� | ������� | �S�z | �| | �S�z |
| ���ԍ� | �| | �| | �| | �S�z* | �| | ||
| 1973�`1982�N�x | 1971�N�x�ȑO�ɔ��s �������ݍ̗��q | ������� | ������� ������� | �S�z | �| | �S�z | |
| 1983�`1985�N�x | 1972�`1976�N�x�ɔ��s �������ݍ̗��q | �V����� | ������� | �S�z | �| | 1/3 | |
| �V����� | �| | �N����4% ������ | |||||
| 1986�`1992�N�x | ������� | �S�z | 1/3 | �| | |||
| �V����� | �N����2% ������ | �N����2% ������ | |||||
| 1993�`2002�N�x | 1977�`1982�N�x�ɔ��s �������ݍ̗��q | �V�V����� | �V����� | �S�z | |||
| �V�V����� | |||||||
�@���������������B�X�L�[���̍l�@�����Ƃɂ���A�t�@�C�i���X�@�\���g�ݍ��܂�Ă���S���̌��ݎ�̂��A�S�����Ƃ̉c�Ǝ�̂ƑS���������Ă��܂��Č��݂ɓ������Ă���ꍇ�̖��_�����炩�ɂȂ�B���ɁA���ݍH�����x��ė]�v�ɔ�p�◘�����������Ă��A���ݎ�̑����A���̕��͍��s���Ď������Ȃ��ŁA���̒lj��z�����̂܂܃v���X���āA�S�����Ǝ҂ɏ��n����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă����(���������āA���ݎ�̑��ɐԎ����o�邱�Ƃ͂Ȃ�)�A�H���̎{�s�Ǘ��ɓ����錚�ݎ�̑��ɂ́A�H�����Ԃ��ł��邾���Z�k���A�L���q�����̊z�����炻���Ƃ����C���Z���e�B�u���Ȃ��A�댯�Ȃ̂ł���B���������ꍇ�A�Ⴆ�ΓS�����c�ł̈ꕔ�̖��S���H���̂悤�ɁA�S�����ƎҎ��炪�{�s�Ǘ����s�����Ƃ͊댯����Ɍ��ʓI�ł���B���ہA��3�͂ŐG���悤�ɁA�H�c�V�����̏ꍇ�ɂ́A���c�H���ł͂��������AJR�����{���g���{�s�Ǘ��ɓ�����A10%�ȏ�̃R�X�g�팸���ʂ������Ă���B
�@����ɁA�����V�����ōs���Ă���S�����Ǝ҂̎��x�͈͓̔��őݕt�������߂�ݕt�����́A�S�����c���ɂ����X�N�E�V�F�A�����O�������Ă���Ƃ����_�Œ��ڂ����B�����V�����̑ݕt���̌v�Z�����́A���Y�V�����������ꍇ�̎��v�Ɠ��Y�V���������Ȃ��ꍇ�̎��v�Ƃ̍�(��z)�ɑd�łƊǗ���̍��v��������Ƃ������̂ŁA���̕����ł���A�S�����Ǝ҂́A�x�������⌸�����p��Ƃ��������{�W��p�̏d���ƃ��X�N����������āA�c�Ƃɐ�O���邱�Ƃ��ł���B���ɖk���V�����̍���E����Ԃ̑ݕt�������N�x175���~�ƒ�z�Œ�߂��Ă���B���̌v�Z�����ł���A���ݍH�����x��ė��q��������ŗL���q�������c���ł��܂������̃��X�N��S�����c�����w�������ƂɂȂ�̂ŁA���R�A�L���q�����z�ƍH�����Ԃ̗��������k���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���b�V���[�ɂȂ�͂��ł���B�����Ƃ̋����𑱂������ŁA���������������X�N���̂�}���鐧�x�A������͍������ׂ��Ȃ̂ł���B
�@�S�����݂��S���o�c���A�����Ƃ̋����ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�S�����݂ɓ������ẮA�⏕�������{��⏕�Ƃ��Č��ݎ��ɏW���������A�L���q�����z�ƍH�����Ԃ̗������ł��邾�����k���āA�S�����Ƃ̎��v�\�����̂̈�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�������ʼnc�Ɨ��v��������Ԃ悤�ȏ��ɒu����Ă��ẮA������c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă����ꂸ�A�������c�Ɠw�͎��̂��Y�ꋎ���邱�ƂɂȂ�̂�����B
[5]�����ł����Ƌ����Ƃ͌��ݗ\����̂��Ƃł���B
[6]���̊Ԃ̌o�܁A���邢�͏o�������̈Ӗ��A���{�Ɠ����s���o���҂ɂȂ�������ɂ��ẮA�Γ�(1997)���Q�Ƃ̂��ƁB
[7]1999(����11)�N�x�ɁA�s�c�ɂ����āA�u��4���[���v�ɏ������⏕���x���K�p����Ă���H���́A���̒ʂ�B (a) 12�������˕� (b) �V�h�� (c) 12������s�������(1999�N3���ɖ؏�Ԍɂ��s�������) ����ȑO�Ɍ��݂��J�n���ꂽ�O�c���́A1990(����2)�N�x�ɓK�p���ꂽ10�N�����̕⏕���x���K�p����Ă���B���Ȃ킿�A�e�N�x�̕⏕���́A���N�x1%�A����ȍ~��2%, 3%, 4%, 4%, 5%, 5%, 4%, 4%, 3% (�v35%)��10�N������t�ł���B12�����̌ď̂͂��̌�u��]�ː��v�Ɍ��܂����B
[8]�n�����c��Ɩ@�{�s�K���̑�12���ɂ́A�\�Z���̗l������߂��Ă��邪�A���̈�Ɍf�����Ă���ʕ\��5���Ɏ�����Ă���\�Z�l���̒��Łu��3���@���v�I�����y�юx�o�̗\��z�v�u��4���@���{�I�����y�юx�o�v�Ƃ��č��ڂ��������Ă��邱�Ƃ���A���ꂼ��u3��⏕���v�u4��⏕���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����B
[9]�c�c�ł́A�u��4���[���v�̒n���S���݂̎������B�X�L�[���ɂ����Ă͏o�������܂܂�Ă��Ȃ����A1951(���a26)�N�x�`1986(���a61)�N�x�܂ŁA�����s�ƍ��S����̑���(�o��)��1953(���a28)�N�x�������Ė��N�s���Ă������Ƃɂ͒��ӂ�����B����ȍ~�̑����͍s���Ă��Ȃ��B�������A����ɂ́A��s�����x��ʉc�c�@(�ȉ��u�c�c�@�v�Ɨ��L) ��20���Ŏ��{����10�{�̊z�܂ł͌�ʍ����s�ɂ�鎑�����B���\�Ƃ��Ă������߂ɁA���{���̑��傪���߂��Ă����Ƃ������ʂ�����B���̕ӂ̎����Γ�(1997)�ɂ��������Đ������Ă������B���A���ݎ������B��i�Ƃ��Ă̌�ʍ��̏����ɂ͌��E�����������߂ɁA�����A���@�����i�߂��Ă��������^�p�������@�ɂ��������Z�������ݎ����̗L�͂ȍ����ƍl�����A���̍ۂ̗Z���K�i�v���Ƃ��āA�c�c�̌��@�l�Ƃ��Ă̐��i�̖��m���A���Ȃ킿�A�\�Z�A���ƌv�擙�ւ̐��{�̊ē̎���Ɩ��ԏo���̔r�������߂��A���̎�|�ɉ������c�c�@�̉����ƍ��S�y�ѓ����s�ȊO�̏o���̏��p���s���āA1951(���a26)�N�x�Ɏ����^�p������8���~�̗Z�������������B���Ȃ݂�1951(���a26)�N1���ɋN���ꂽ��㏉�̌�ʍ��̔��s�z���A1���~�ɂƂǂ܂��Ă������Ƃ���A�����̑��݂̑傫�����킩��B���̌��ʁA1951(���a26)�N4��1�����_�ł̏o����(�v�������{)�́A���S1,300���~�A�����s325���~�A���S��325���~�ł��������A1951(���a26)�N�ɖ��S���̏o���������p����A����ȍ~�A���S�Ɠ����s�ɂ�鑝���������̂ł���B����ɁA1950(���a25)�N����́u��s���ݖ@�v�ɂ��ƂÂ�����@�ցu��s���݈ψ���v��1952(���a27)�N�ɒ�o�����u(�c�c��)�s���̌�ʋ@�ւ��鐫�i�ɂ��݁A�����ɂ������Ă͓����s�����đ������z�̏o�����Ȃ����ނׂ��ł���v�Ƃ����ӌ���w�i�ɂ��āA���S�Ɠ����s�̑����z�͓��z�Ƃ���A���̌��ʁA���҂̗v�o���z�͏��X�ɐڋ߂��Ă����B����1959(���a34)�N�x�`1965(���a40)�N�x�̊Ԃ́A���ҋ���5���~���v10���~�A1966(���a41)�N�x�`1986(���a61)�N�x�̊Ԃ́A���ҋ���10���~���v20���~�N�x�������Ă����B1987(���a62)�N4��1���A���S�������c���ɔ����c�c�@�̈ꕔ�����ɂ��A�c�c�̏o���҂̂������S���u���{�v�ɉ��߂�ꂽ�B�������A�b��[�u�Ƃ��āA���{���L�S�����Z���ƒc��������t���Ōp�����A1991(����3)�N3��29���������āA�c�c�ɑ���o�����́A�S�z���{�ɏ��n���ꂽ�B1987(���a62)�N�x�ȍ~�A���Ȃ��Ƃ�1998(����10)�N�x���܂ł͑����͍s���Ă��Ȃ��B
[10]�ŋ߂ł́A�����1.1%�ɂ܂Œቺ���Ă�������(1998(����10)�N10��16���`12��15���̊�)���������B
[11]�����ł������̎芷���Ƃ́A�Ⴆ�u���Ҋ���10�N�A�������u����3�N�̍��v���芷����ꍇ�ɂ́A3�N�����u������A7�N�Ԃɂ킽���Ė��N8%���v56%�����҂��Ă��܂��̂ŁA�c��44%������Ɏ��̍��Ŏ芷���邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���������āA�u���Ҋ���10�N�̍���2��芷����v�Ƃ������Ƃ́A�ŏ��̔��s�z�̂܂�30�N�Ԏ�Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��A�ŏ��̎芷�����ɂ͓������s�z��44%�A2��ڂ̎芷�����ɂ͂���ɂ���44%�ƁA�芷���̓x�ɍ��̔��s�z���قڔ������Ă������ƂɂȂ�B
[12]�u53���[���v�ł̕⏕���̌�t�J�n��1985(���a60)�N�x�܂ł́u���݂̗��N�x����v�A1986(���a61)�N�x�ȍ~�́u�J�Ƃ̗��N�x����v�������B1990(����2)�N�x����́u���݂̓��N�x����v�ɕύX�ɂȂ��āA�����Ɋ����݂̍��ɕ��ɂ��Ă��u���݂̗��N�x����v�����ɕ��A�����B
�@���z�ȗL���q�����B���čs����S�����݂��A���z�ȗL���q��������Ȃ���i�߂���S���o�c���A��{�I�ɂ͋����Ƃ̋����ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B1987(���a62)�N4���Ɏ��{���ꂽ���S�̕������c���ɂ���āA���������̒��B���@�����R�ω������B���́A���S���������c�����ꂽ�O��́A����������Ѝ��s�̖ʂł����x�ύX������A���̂��Ƃ�JR�̒����������B�̎d���ɉe����^���Ă���B�����ł��̏͂ł́A�������c����̓����{���q�S���������(�ȉ��uJR�����{�v�Ɨ��L)�𒆐S�Ɏ��グ�āAJR�����{�������ɂ��ċ����Ƌ������A���z�ƕ��ϋ����̈��k�ɐ������Ă����̂����T�ς�����ŁAJR�����{���������������Ƃ̋�����W�J���Ă������ʁA���{����{�S�������c(�ȉ��u�S�����c�v�Ɨ��L)�Ƃ̊Ԃŋ������o�ɑ傫�ȉ��x�����������邱�Ƃ��w�E����B���̂��Ƃ͓����ɁA���݂̎������B�X�L�[������������_�����w�E���邱�ƂɂȂ�B
�@���S����Ɣ�r�����ꍇ�AJR�����{�̎������B�X�L�[����̑傫�ȕω��́A���Ƃ����Ă��A�������c���ɂ���āA���x�I�ɍ����𗘗p�ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��낤�B�������AJR�����{������5�N�Ԃ�1991(����3)�N�x�܂ł́A�u���q�S��������Ћy�ѓ��{�ݕ��S��������ЂɊւ���@���v�Ɋ�Â����̗\�Z�[�u�āA���{�ۏؓS������V�K���s���Ă����B�������A����ȍ~�̓S�����̐V�K���s�͂Ȃ��B�����ēS�����Ɠ���ւ��ɁA1992(����4)�N�x����i�t�����擾���Ĕ��s���n�߂��Ѝ�(�������ʎЍA�O��)�������������B�̒��S�ɂȂ�̂ł���B
�@���������ω��́A�\3-1�A�}3-1�A�}3-2�ɂ����邱�Ƃ��ł���B�����AJR�����{�ɂƂ��ẮA�����S���������Ɍ��炷��������ł������B���c���̎��_�ŁA��ʉ�v�ƍ������Z���̍��͍��S���Z���ƒc�ɏ��p����AJR�e�Ђ͖��Ԏؓ����ƓS����(���{�ۏ؍A���{����A���̍�)�̍��S���ď��p���Ă����B1991(����3)�N�x�ɐV��������������ꂽ���ƂŁA�V�������ȊO�̒������̌����X�s�[�h�͓݂邪�A����Ȓ��ł��AJR�����{�́A�����S�������炷���Ƃɓw�߂��B
�\3-1. ���S��JR�����{�̒����ؓ����y�э��̊����c���@�@�@�@�@(���z�P��: ���~)
| �N�x | ���{���L�S��(���S) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | ||
| ���a50 | ���a55 | ���a56 | ���a57 | ���a58 | ���a59 | ���a60 | ���a61 | ||
| �����ؓ��� (��ʊ���) |
��ʉ�v | 350 | 1,048 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 803 | 778 | 768 |
| �����^�p�� | 40,384 | 28,888 | 35,833 | 44,178 | 53,707 | 60,969 | 67,922 | 71,966 | |
| �ȈՕی��� | 3,229 | 6,388 | 7,069 | 7,618 | 7,429 | 7,358 | 6,925 | 6,621 | |
| ���ە����J����s | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���{�J����s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���Ԏؓ���(JR��) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���Ԏؓ���(���S��) | 0 | 1,365 | 2,847 | 3,782 | 4,535 | 5,490 | 5,851 | 6,646 | |
| �n�������� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| �S���� | ���{�ۏ؍�(JR��) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ���{�ۏ؍�(���S��) | 5,110 | 13,788 | 16,293 | 19,286 | 23,075 | 28,060 | 33,171 | 3,8102 | |
| ���{����� | 419 | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959 | |
| ���̍� | 18,195 | 39,204 | 45,166 | 51,360 | 56,854 | 62,368 | 67,762 | 71,389 | |
| �Ѝ� | ������ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �O�� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| �v* | 67,793 | 90,770 | 108,294 | 127,235 | 146,611 | 165,048 | 182,409 | 197,451 | |
| �V������(�^�A�{�ݐ������ƒc) | |||||||||
| �H�c�V����(�S�����c) | |||||||||
| �������z���v* | |||||||||
| �\�ʗ���(�����q�ݕt�����܂�) | 7.13%** | ||||||||
| �N�x | �����{���q�S��������Ёi�i�q�����{�j | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
| ���a62 | ���a63 | ����1 | ����2 | ����3 | ����4 | ����5 | ����6 | ����7 | ����8 | ����9 | ����10 | ||
| �����ؓ��� (��ʊ���) |
��ʉ�v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �����^�p�� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| �ȈՕی��� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���ە����J����s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���{�J����s | 420 | 861 | 1,371 | 1,708 | 2,132 | 2,471 | 3,041 | 3,433 | 3,755 | 4,003 | 4,112 | 3,992 | |
| ���Ԏؓ���(JR��) | 0 | 2,978 | 7,078 | 7,078 | 7,078 | 7,468 | 8,498 | 8,863 | 9,413 | 10,453 | 10,297 | 10,037 | |
| ���Ԏؓ���(���S��) | 3,709 | 3,220 | 2,709 | 1,950 | 1,426 | 963 | 585 | 293 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| �n�������� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 130 | 223 | 325 | 335 | 387 | |
| �S���� | ���{�ۏ؍�(JR��) | 528 | 1,013 | 1,494 | 1,965 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,135 | 470 | 470 | 470 |
| ���{�ۏ؍�(���S��) | 8,332 | 7,361 | 6,394 | 5,446 | 4,072 | 2,062 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ���{����� | 529 | 1,015 | 1,498 | 1,971 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 1,972 | 623 | 0 | 0 | |
| ���̍� | 16,785 | 10,276 | 4,818 | 4,230 | 3,823 | 3,386 | 3,020 | 1,670 | 333 | 0 | 0 | 0 | |
| �Ѝ� | ������ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,700 | 3,700 | 5,100 | 5,800 |
| �O�� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 879 | 879 | 879 | |
| �v* | 30,305 | 26,726 | 25,363 | 24,351 | 23,090 | 22,122 | 21,292 | 20,848 | 20,633 | 20,454 | 21,194 | 21,566 | |
| �V������(�^�A�{�ݐ������ƒc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,691 | 30,217 | 29,698 | 29,121 | 28,513 | 27,846 | 26,869 | 25,852 | |
| �H�c�V����(�S�����c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 268 | 257 | |
| �������z���v* | 30,305 | 26,726 | 25,363 | 24,351 | 53,782 | 52,340 | 50,990 | 49,969 | 49,147 | 48,580 | 48,332 | 47,676 | |
| �\�ʗ���(�����q�ݕt�����܂�) | 6.91% | 6.47% | 6.22% | 6.20% | 6.35% | 6.13% | 5.90% | 5.64% | 5.50% | 5.10% | 4.84% | 4.62% | |
�}3-1. ���S�̒����ؓ����y�э��̊����c��
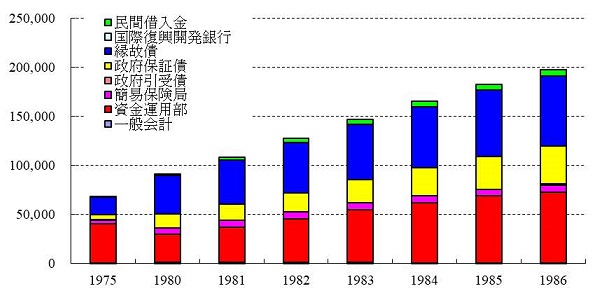
�}3-2. JR�����{�̒����ؓ����y�э��̊����c��(�V�����̍�������)
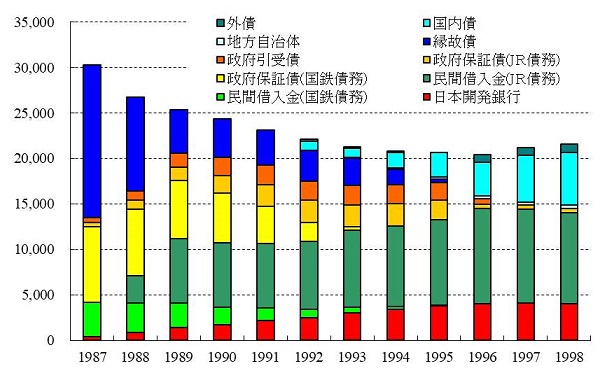
���̌��ʁA�����N�x�ł���1987(���a62)�N�x���A�������̎���84.6%(=2��5,645���~/3��305���~)���߂Ă����S�����́A���N�x�A���ҁE�Վ����҂�i�߂����ƂŁA���S����̓S���������Ė��Ԏؓ����̏��p�����Ƃ��ɁA1996(����8)�N�x���܂łɕԍς��I���B����ȍ~�Ɏc���Ă���S�����̎c���́A���c����̐V�K���ł��邪�A����ƂĂ��A1998(����10)�N�x���ɂ́A�r���t���̐V����������������������2.2%(=470���~/2��1,566���~)�ɂ܂Ō������Ă���B���������l�q�͕\3-1�Ɛ}3-1������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B
�@�������Č��������S�����̑���ɁA1988(���a63)�N�x����n�܂�������(�s�s��s�A�M����s�A�����M�p��s)����̎ؓ����ƁA1992(����4)�N�x����i�t�����擾���Ĕ��s���n�߂��Ѝ�(�������ʎЍA�O��)�������������B�̒��S�ɂȂ����B1997(����9)�N�x���ŁA���Ԏؓ���48.6%(=1��297���~/2��1,194���~)�A�Ѝ�28.2%(=5,979���~/2��1,194���~)�ƂȂ��Ă���B
�@�܂��AJR�����{�́A�����N�x�ł���1987(���a62)�N�x����A���{�J����s(�ȉ��u�J��v�Ɨ��L)�̗Z������悤�ɂȂ�B���S����̖���(�s�s��s�A�M����s�A�����M�p��s)����̎ؓ����̏��p���ƊJ��Z���̍��v�z�́A���c����A�ق�4,000���~���x�ň�肵�Ă���A�\�ʓI�ɂ́A�J��Z�������Ԏؓ����̏��p���Ɏ���đ���`�ɂȂ��Ă���B
�@�������A����ɂ͕ω��̒�����������B1990�N��㔼�ɓ����āA�呠�Ȃ̍������Z������ɔᔻ���W�����āA�����S���Z���ƒc�y�ы��S������������ɑ��Ă������̊ԁA������݂��Ȃ����j�ƂȂ����B�J��Z���Ɋւ��Ă��A�W�e�Ȓ��ł́A(a)����Ƃ�1,000���~�߂��̌o�험�v���o����Ђɑ��č�����������Ƃ����ᗘ�Z�������Ă��悢�̂��A(b)���{�J����s���̐��{�n���Z�@�ւ̓��p���A(c)������Ƃ�ΏۂƂ�����������̊����O�ԍρA(d)����Ƃō����i�t���ō������N�̉�Ђɑ���Z�������̃J�b�g�A�����c�_���ꂽ�B����f���āAJR�����{�̑ΏۍH���z�ɑ���Z�����́A1995(����7)�N�x50%�A1996(����8)�N�x45%�A1997(����9)�N�x40%�A1998(����10)�N�x30%�ƒቺ���Ă���B����A��q����悤�ɁA�Ѝ��s�̖ʂł����x�ύX�����������ŁAJR�����{�͍����i�t�����ێ����邱�ƂŁA�Ѝɂ��s�ꂩ��̒��B�����ጸ�ɐ������A����1999�N2�����s��10�N���̂̎Ѝł́A�J��Z���̓��ʋ���2.2%�����Ⴂ����2.18%�Œ��B�ł���悤�ɂȂ����B���̂悤�ȏ�̒��ŁAJR�����{��1999(����11)�N�x����́A�J�₩��̐V�K�Z���͎Ȃ����j�ŁA����A�J��Z���c���͏��X�Ɍ������錩���݂ł���B
�@�������āA���B���@��ω������邱�ƂŁAJR�����{�͒��������̕������܂��Ƃ炦�āA�����������������������ւ̎؊���i�߂��B���̂������ŁA�������̕\�ʋ����́AJR�����{��������1987(���a62)�N�x�����7.13%����1998(����10)�N�x������4.62%�ɂ܂Œቺ�����邱�Ƃɐ������Ă���B
�@���S���ォ��A�m���ɍ�����J��Z���͖��Ԏؓ��������������Ⴉ�������A���͍̏����Ɏ���܂ŕς���Ă��Ȃ��B�������A���{�ۏ؍��܂߂č������Z�������p�ł��Ȃ��Ȃ�A�J��Z�����������������Ȃ����ɂ�������炸�AJR�����{�͍��S�Ɠ����������ł���悤�ɂ͌����Ȃ��B���̗��R�́A���ꂩ���������悤�ɁA1996(����8)�N�ɎЍ��s�̖ʂł̐��x�ύX������A���̂��Ƃ�JR�����{�ɂ��J��Z�����݂̒�����ŎЍɂ���Ď������B�����铹���J���ꂽ���ƁA�����Č�̐߂ŐG���悤�ɁAJR�����{���ߓx��������ݔ�����������Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B
�@�܂�JR�����{������e���v�����̓����ɂ��ĊT�ς��Ă������B�}3-3�ł��킩��悤�ɁA�������N�̌X���Ƃ��āA������10�N���̍��̕\�ʋ�����+0.2�`0.3%�A�J��Z���͍����̋�����+0.1�`0.2%�Ƃ����邪�A���������������͍����̎d�g�݂��痈����̂ł���B�����^�p�����A�X�֒����A�����N���E�����N�����̗a�����ɑ��Ďx�������q�̗����͗a�������ƌĂ�邪�A���S�̕������c���̒��O�A1987(���a62)�N3���Ɏ����^�p�������@����������A�a�������̖@�萧�����߁A���߂Œ�߂邱�Ƃɂ��A����ȍ~�͎s��ɂ����钷�������̑�\�I�w�W�ł���10�N���̍��̕\�ʋ�������ɂ��Ēe�͓I�Ɍ��߂��邱�ƂɂȂ����B�����^�p���ł́A���̗a�������ŗa�����ꂽ�������T������炸�ɓ���̗����̍��������Ŋe�����Ώۋ@�ւɑ݂��t���Ă���B�܂����{�J����s�̂悤�Ȑ�����Z�@�ւ̏ꍇ�́A��{�I�ɖ��Ԃ̒����v���C�����[�g��������Ƃ��A�����I�ȕK�v���ɉ����āA���������ƒ����v���C�����[�g�̊ԂŗD��������݂��āA�����A�ᗘ�̗Z�����s���Ă���(�呠�ȗ�����, 1993, p.20; ����, 1998, p.101)�B�������āA�����ƊJ��Z���Ƃ̊Ԃɋ������������邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�}3-3. �e������̐���
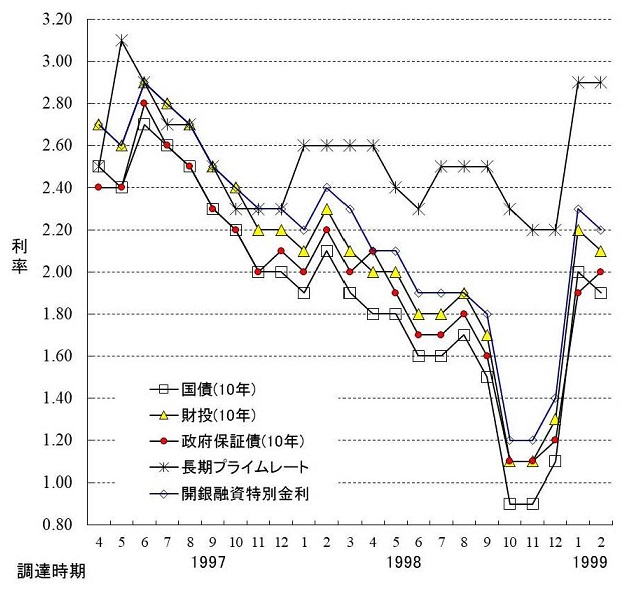
JR�����{�̏ꍇ�A���ɏq�ׂ��悤�ɁA���������͒��ڗ��p�ł����A�J��Z���̌`�ł������p�ł��Ȃ��B�������J��Z���Ƃ͂����Ă��A��{�I�ɍ����������ł���ȏ�A���̗\�Z�ɂ����邽�߂ɁA�������������ɂ��A�\�Z�v�サ�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂������O�ԍς��ł��Ȃ����Ƃ���[13]�A�������ቺ�����ꍇ�ł����̋����ቺ�̃����b�g�����Ȃ��B���������āA���ϋ����Ō������ɂ́A�K�������J��Z���̋������Ⴍ�Ȃ�킯�ł͂Ȃ��̂ł���B����ɑ��āAJR�����{�̏ꍇ�ɂ́A�\3-2�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�Ѝ̊i�t�����������߂ɁA�Ѝ̋����͒Ⴍ�A1996�N�x�ȍ~�A�s�ꂩ��ł����Ă��A�J��Z���̓��ʋ������݂��邢�͂���ȉ��̒�����Œ��B���邱�Ƃ��\�ɂȂ����̂ł���[14]�B�������Ѝ̏ꍇ�ɂ́A���̗\�Z�ɔ����Ȃ��̂ŁA���̕��A�@���I�ɒ��B�A���҂��\�ł���B�����������Ƃ�JR�����{�̎��Ȓ��B�u�������߂錋�ʂƂȂ��Ă���B
�\3-2. JR�����{�̎Ѝ̔��s����
| ���s�N���� | ���� | ���s�z (���~) | �N�� (�N) | �i�t�� | ���s����(%) | �e�����(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | ���[�f�B�[�Y | S&P | ����(10�N) | ���{�ۏ؍�(10�N) | �J��Z�����ʋ��� | |||||
| 1992�N10��5�� | ��1�ʎЍ� | 1,000 | 12 | AAA | Aa2 | AA | 5.550 | 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| 1995�N3��6�� | ��2�ʎЍ� | 700 | 20 | AAA | Aa2 | AA | 4.900 | 4.400 | 4.500 | 4.650 |
| 1996�N3��11�� | ��3�ʎЍ� | 1,000 | 20 | AAA | Aa2 | AA | 3.950 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 1997�N2��25�� | ��4�ʎЍ� | 600 | 12 | AAA | Aa2 | AA | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.900 |
| ��5�ʎЍ� | 400 | 20 | AAA | Aa2 | AA | 3.300 | ||||
| 1997�N8��12�� | ��6�ʎЍ� | 400 | 12 | AAA | Aa2 | AA | 2.875 | 2.500 | 2.500 | 2.700 |
| ��7�ʎЍ� | 300 | 20 | AAA | Aa2 | AA | 3.300 | ||||
| 1998�N2��25�� | ��8�ʎЍ� | 400 | 12 | AAA | Aa2 | AA | 2.650 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| ��9�ʎЍ� | 300 | 20 | AAA | Aa2 | AA | 3.075 | ||||
| 1999�N2��10�� | ��10�ʎЍ� | 400 | 10 | AAA | Aa2 | AA- | 2.180 | 1.900 | 2.000 | 2.200 |
| ��11�ʎЍ� | 300 | 20 | AAA | Aa2 | AA- | 2.970 | ||||
�@�]���A���{�ł́A�i�t���Ƃ͊W�Ȃ��A�����Y�z�Ȃǂ̍����I�Ȑ��l��ɂ���Ĉ��S�Ǝv�����ƂɌ��肵�ĎЍ��s���F�߂��Ă����B�������A���S�̕������c���̒��O�A1987(���a62)�N2���ɁA�]���̐��l������Ȃ��Ă����i�ȏ�̊i�t���������̔��s���\�ɂȂ�A���l��ƕ��p���Ċi�t�����K��Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����̂ł���B���̌�A1990(����2)�N6���ɂ͐��l����p�~����āA�K��͊i�t����Ɉ�{�����ꂽ(����, 1999, pp.116-117)�B
�@�������A����ł��܂��Ѝɂ�鎑�����B�ɂ͑傫�ȏ�ǂ��������B����́A���s��f�t�H���g(���s���s)���������Ă��A���͎Ѝ��s����舵���������s���z�ʂňꊇ���Ĕ������Ƃ������s���������̂ł���B���m�Ɍ����ƁA�L�S�ی����ƌĂ�A�Ѝ��s�ɍۂ��āA�N�҂͉c�Ɨp���Y�ł���y�n�⌚���Ȃǂ̕s���Y��S�ۂƂ��Ď����s�ɒ��Ȃ���Ȃ炸�A����A�ԍϕs�\�ɂȂ������́A�����s���ԍϕs�\�Ѝ����ׂĔ����グ��Ƃ������̂ł������B���������̈��S���m�ۂ̂��߂̕ی������������A����萔���Ƃ��āA���s�҂̐M�p�͂ɊW�Ȃ��ꗥ�ɏ�悹���ꂽ���߂ɁA�M�p���X�N���Ȃ�����ɁA�Ѝ͐M�p�͂̍������s�҂ɂƂ��Ă��܂薣�͓I�ȑ��݂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���(���{�i�t�������Z���^�[, 1998, pp.56-59; ����, 1999, p.105)�B
�@�������A1996(����8)�N1���ɓK����p�~����Ă���A�i�t���͑傫�ȈӖ��������n�߂�B���̊i�t���́A���������̈��S���A���Ȃ킿���ԍς̈��S�x��]���������̂ŁA�Ⴆ��R&I�ł�[15]�A�����̏ꍇ�A���S�x�̍��������珇�ɁAAAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C�ƒi�K�I�ɕ\���Ă���킯�����A���̊i�t���ɂ���č����s�̍ۂ̗���肪���܂�悤�ɂȂ����̂ł���B�������A�\3-3�Ɏ������悤�ɁA1996(����8)�N�H�ȍ~�A�s��S�̂ɒ�����X�����������ɂ����Ă����AAAA�i�ЍƑ��̊i�t���̎ЍƂ̗����i���͊g�傷��X���ɂ���(���{�i�t�������Z���^�[, 1998, ch.2)�B�����āA1998(����10)�N10��16�����݁AR&I�̊i�t���ʂ̎c��4�N�̎Ѝ̗����́A�\3-4�̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B
�\3-3. R&I��AAA�i�ЍƂ̗��ʗ����i��(�c���N��3�N)�@(�P��: %�|�C���g)
| R&I�i�t�� | AAA�i�ЍƂ̗��ʗ����i�� | ||
|---|---|---|---|
| 1997�N6��30�� | 1997�N12��29�� | 1998�N10��16�� | |
| AA | +0.104 | +0.264 | +0.376 |
| A | +0.346 | +0.621 | +0.928 |
| BBB | +0.956 | +1.485 | +1.797 |
�\3-4. R&I�̎Ѝi�t���ʗ��ʗ����(1998�N10��16�����݁A�c���N��4�N)
| R&I�i�t�� | ������ | ���ʗ���� |
|---|---|---|
| AAA | 46 | 1.117% |
| AA | 47 | 1.466% |
| A | 95 | 1.989% |
| BBB | 28 | 3.015% |
| BB | 6 | 6.761% |
| B | 1 | 31.665% |
�@�����̔����Ɋւ��Ĕ��������肩��\���������̊i�t���́A��������Z���I�Ȏ��v�ϓ��ɕ]���̏d�_������B�������Ѝ̏ꍇ�́A�������̍���(�����Ȃ��Ƃ��ꎞ�I�ɂ͎��v�͂̑傫��)������u�D�NJ�Ɓv�����̍����i�t���������Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�Ѝ̊i�t���ɍۂ��ẮA���v�͂�L���b�V���t���[�̈��萫�A�����Ď��Y���e�̌��S�����d�������B���������āA���v�������Ⴍ�A�ݔ������̕��S���d�����߂ɍ����\��������肷��悤�ȓd�͉�Ђł��A����d�͂��܂߂�10�БS�����A�n��Ɛ�Ƒ���������`�ɂ���āA���v�̈��萫�Ⓤ���̉�������x�I�Ɋm�ۂ���Ă���Ƃ������R�ŁAR&I��AAA�̊i�t�����擾���Ă���(���{�i�t�������Z���^�[, 1998, ch.5)�B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA�d�͉�ЂƓ��l�̎�����������S�����Ǝ҂́A�����͎Ѝ̊i�t���ɂ����Ă͗D�ʂɗ�������̂ł���B
�@���ہAJR�����{���܂߂��{�B3�Ђ�R&I�̊i�t�����Ƃ��Ă���B���ɁA1992(����4)�N�ɍ����y�ъC�O�̊i�t�����擾����JR�����{�̏ꍇ�ɂ�[16]�AJR�e�Ђ̒��ŗB��A�O�̔��s�ɕK�v�ȃ��[�f�B�[�Y��S&P�̊i�t�������Ƃ�[17]�A�������c���ȗ��A���������m���Ɍ��������A�o�c��Ղ��������钆�ŁA�����i�t�����ێ����邱�ƂŁA���������Ѝ��s�̊��ω����v���X�̕����ɐ��������Ƃɐ������Ă����B
�@�\3-2�ɂ�JR�����{�����s���Ă������ʎЍ̔��s������������Ă��邪�AJR�����{�̎Ѝ̊i�t���́A���{��Ƃ������݊i�t���𗎂Ƃ��Ă���1998�N�x�̔N�x���ł��AR&I��AAA�A���[�f�B�[�Y��Aa2�AS&P��AA-�A�ƍ����B���̍����i�t�����ێ����Ă��邨�����ŁA1996�N�x�ȍ~�A�s�ꂩ��ł����Ă��A�J��Z���̓��ʋ������݂��邢�͂���ȉ��̒����(�d�͉�ЂƂقړ����x�̋���)�ł̒��B���\�ɂ��Ă����̂ł���B
�@���c�����JR�����{�́A�������ċ����Ƃ̋����𑱂��Ă����B���̌��ʁA�������o�̓_�ł́A���܂�{�Ƃ̊ԂŖ��炩�ɉ��x��������B���̂��Ƃ����݉��������Ⴊ�A�����Ŏ��グ��V�������̑����ٍϐ��x�Ǝ����Ŏ��グ�閳���q�ݕt�����x�̂��ꂼ��^�p�Ɋւ���Η����ł���B�ǂ���̐��x���^�A�{�ݐ������ƒc(�� �S���������)���֗^���Ă���B
�@���ɏq�ׂ��悤�ɁA�S����������́A�V�����S���ۗL�@�\�̉��U���ɂ����āA���@�\�̈�̌����y�ы`�������p������̂Ƃ���1991(����3)�N10��1���ɐݗ�����A����ɁA1997(����9)�N10��1���ɂ� �S����������ƑD���������c����������ĉ^�A�{�ݐ������ƒc���ݗ����ꂽ�B�^�A�{�ݐ������ƒc��JR�{�B3�Ђ�������Ă�����ݐV�������n������A����ɐ����V�����̌��ݎ����Ɍ�t���Ƃ��Č�t������A���邢�͒n���S���݂Ȃǂɖ����q�ݕt���Ƃ��đ݂��t����������Ă���B���z�ł��L���q�̋����S��������Ă���ɂ����āA�ꍏ�������V�������n��������ԍςɉȂ���A�������S�ō����N�X��B�����ɑ������Ă��܂��̂ɁA�Ȃ����V�������n����͌�t���△���q�ݕt���ɉ�Ă���̂ł���B�����������Ǝ��̂������ɑ���w�C�s�ׂƂ��v����̂����A���̂悤�Ȑ��{�̋������o�Ɋ�Â��āA�^�A�{�ݐ������ƒc�̏����x���^�p����Ă��邱�Ƃ�JR���Ƃ̑Η��̍���ɂ���B
�@���S���㖖���̓��ʍ��s�̎d���ɂ́A�����������{���̋��K���o�Ɠ����悤�ȓ������Y���Ă����킯�����A���c�����JR�͖��炩�ɈقȂ�s�����Ƃ�n�߂Ă���B���́AJR�����{�AJR�����{�AJR���C��JR�{�B3�Ђ́A�V�������̊����O�ԍ�(������^�A�{�ݐ������ƒc�ł́u�����ٍρv�ƌĂ�ł���)�ɂ͐ϋɓI�Ȃ̂ł���B�����A����܂łɎ��������V�������̊����O�ԍς́AJR�{�B3�Ђ̋��������|���ɂ����̂ł������B
�@��̓I�ɂ́A�V�������̕ϓ���(25.5�N���ҁA����10�N�x�K�p����5.02%)�ɂ���[18]�A���������Ŏ����̉^�p�悪�����炸�ɍ����Ă���o�c������(�O�����)�Ƃ̊W�ŁA1997(����9)�`2001(����13)�N��JR�����{��1400���~�AJR�{�B3�Ђ�4000���~�𑁊��ٍςł��邱�ƂɂȂ����̂ł��邪�A���̌o�܂͎��̂悤�ł������Ƃ�����B
�y1996(����8)�N8��27���^�A�Ȃ̃v���X(�L��)���\�̓��e�z
�@JR�k�C���AJR�l���AJR��B�ɑ���x����̈�ŁA�o�c������(�O�����)�̉^�p�v���m�ۂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A1997(����9)�N�x�ȍ~5�N�ԁA�S���������(�� �^�A�{�ݐ������ƒc)�����̒��B�����̂����A�]���̖��Ԏؓ����y�ѐ��{�ۏ؍���������3�Ђ̌o�c����������4.99%�̌Œ藘��(�ߋ�10�N�Ԃ̒��������ϗ����)�Ŏ����邱�Ƃɂ��A3�Ђ̌o�c�������̉^�p�v�̊m�ۂ�}��B
�@���̂悤��2, 3�̂悤�ȏ��ŁA���܍��킹�I�ɏ����̋������S���l������4�z���鐭�{���̋������o�ɂ͋�������邪�A����ɑ��āA���c������JR�{�B3�Ђ̎������B�Ɋւ��閯�ԓI���o�A���ɋ����ɑ��銴�o���ΏƓI�ɍۗ����Ă��ċ����[���B���Ȃ݂ɁA6�ɂ���悤�ȔN�x���̕ԍϊ����ɑ��āAJR���́A�N�x���ɂ�����炸�ɁA�����ł������Ԃ����̕��̋��������������Ă��炦��̂ł͂Ȃ����ƌ��������A�f��ꂽ�Ƃ����Ă���B
�@���ɖ����q�ݕt�����x�̘b�Ɉڂ낤�B�����q�ݕt���Ƃ�1991(����3)�N10���̓S����������̐ݗ��ɔ����n�݂��ꂽ���x�ł��顂Ƃ��낪�A�S�����c�̐��x�Ƃ̐��������������߂ɁA�u�����q�v���L�����������Ă���B����̓I�ɂ́A�S����������������q�ݕt���̏��ҕ��@��5�N���u��10�N�����ϓ����N�����҂Ƃ��Ă���̂ɑ��āA�S�����c�����n�Ή��̉�����@��25�N�����ϓ����N�����҂Ƃ��Ă��邽�߂ɁA�����I�ɖ����q�ݕt�����x���u�����q�v�ł͂Ȃ��Ȃ�Ƃ������ۂ������Ă���̂ł���
�@���݂ł��^�A�{�ݐ������ƒc�̖����q�ݕt���̏��ҕ��@��5�N���u��10�N�����ϓ����N�����҂Ƃ���Ă���B�Ƃ��낪�A���Y���x�n�݂ɓ������Ẳ^�A�Ȃɂ����錟���ߒ��ɂ����ẮA���Y�����q�ݕt���Ƃɂ�茚�ݓ����Ȃ��ꂽ�S���{�݂̑Ή��̉�����@�́A���s�̓S�����c��P��(Private��; ���S���̈Ӗ�)���x�Ɠ��l�A25�N�����ϓ����N�����ҕ����ɂ����@��O���ɂ����Ă����Ǝv����B���ہA���Y�����q�ݕt���Ƃ̑n�݂Ɠ����ɁA���Y���Ƃɂ��S���{�݂̏��n�̕��@�ɂ��Ă̋K�肪�S�����c�@�{�s�߂ɒ�߂��Ȃ��������A����͌��s��P���Ɠ��l�̏��n�Ή��̉�����@�A���Ȃ킿�S�����c�@�{�s�ߑ�9���ɂ�錳���ϓ����N���x���̕��@�ɂ����̂Ƃ����l�������������߂Ɛ��������[19]�B
�@���̂悤�Ȕw�i����A�����q�ݕt���Ƃɂ�茚�ݓ����s�����S���{�݂̏��n�ɔ������n�Ή��̌v�Z���@�Ƃ��āA1994(����6)�N11��8���ɉ^�A��b����S�����c�ɑ��āA�S�����c�@�{�s�ߑ�9���2���Ɋ�Â��u�^�A��b���w�肷����ԁv���u�S���{�݂����n�����͈��n������25�N�ԁv�Ƃ��A�u�^�A��b���w�肷�闘���v���u�S���{�݂̌��ݖ��͑���ǂɌW��ؓ��ɌW�闘���v�Ƃ���|�̎w�����o���ꂽ�B����́A
�@���̂悤�ɁA���̐��x�͂��Ƃ��Ƒ�O�Z�N�^�[�̂悤�Ȍo�c��Ղ̐Ǝ�ȓS�����Ǝ҂ɓK�������x�ł���AJR�����{�̂悤�Ȏ��O�̎������B�\�͂ɂ��D�ꂽ�D�NJ�ƌ�����K�������Ӑ}�������̂ł͂Ȃ������Ƃ�����̂�������Ȃ��B���̂��Ǝ��̂����������ǂ����́A��4�͂̃h�C�c�̗�Ȃǂ��l����Ƌ^�₪�c�邪�A���Ȃ��Ƃ��A�������������q�ݕt�����x��������ɂ�������炸�A�S�����c���ɂ���ɍ��킹�����n�Ή��̉�����@���K�肵�Ȃ��������߂ɁA�u�����q�v���䖳���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B���̂��Ƃ́AJR�����{�̖����q�ݕt�����x�̓K�p���߂��鎖������邱�ƂŁA���炩�ɂȂ�
�@JR�����{�̏H�c�V�����̍H���A���m�ɂ́u�c��ΐ������E��Ȋԋy�щ��H����ȁE�H�c�Ԃ̑���ǍH���v�́A�����̓S����������̏����Ώێ��ƂƂȂ邱�Ƃ���AJR�����{�́A1992(����4)�N2��5���t���ŏ��������ł���S�����c�H���̐\���o�����A6���t���ŋ�����@�Ɋ�Â����ƔF��\�����s�����B���H����598���~�̂���490���~�ɂ��ẮA�����q�ݕt���Řd���邱�ƂɂȂ����B�������A�������̖����q�ݕt���𗘗p����ۂ̎��ƔF��̑O������Ƃ��āA����̖����q�ݕt���Ɠ��z�������̖����q�ݕt�����W�����̂���o����邱�ƂɂȂ��Ă������߂ɁA�����q�ݕt�Ώێ��ƔF��z490���~�̔��z245���~�͊������S�����c�ւ�5�N���u��10�N���҂̖����q�ݕt���ŁA�c��245���~�͏H�c���E��茧�����5�N���u��10�N���҂̖����q�ݕt���Řd��ꂽ�̂ł���[20]�B�������āA��̓I�ȓS�����c�̎{�ݍH��������B�͕\3-5�̂悤�ɂȂ����B
�\3-5. ���{�S�������c���猩���H�c�V�����̎{�ݍH��������B�@�@(�P��: ���~)
| ���B | �g�r | ||
|---|---|---|---|
| ���� | ���z | ���� | ���z |
| ��(50%) | 245 | �{�݉��ǔ� | 598 |
| �n��(50%) | 245 | ||
| �ؓ��� | 108 | ||
| �v | 598 | �v | 598 |
�@�������āA���Ɗ�{�v��ύX�F�\���y�ю��ƔF��\���̍ۂɁA490���~���镔���̎������B�́A�S�����c�̒��B����L���q�����ɂ����̂Ƃ��Č����ςł��邱�Ƃ���A���Y�H���̎��{�̌��ʁA�����q�ݕt�Ώێ��Ɣ���������ɂ��ẮA�S�����c�̓��ʍ�(������u���c�v)�s���邱�Ƃɂ��蓖�Ă���邱�ƂɂȂ����B
�@1992(����4)�N8��3���ɍH���͒��肳��A�����E���n��1997(����9)�N3��21���������B���������ۂɂ́A�R�X�g�팸���ɂ��A���H����͏���ł��܂߂�531���~(�����ݔ�p516���~�{�����15���~)�ł������B���̂��ߌ��ʓI�ɁA���ݔ�p516���~�̓��A490���~�������q���ŁA�c���26���~�͓S�����c�����c�Œ��B�����L���q�����ƂȂ����̂ł���B���m�Ɍ����A���c�[���z��2,634,500��~�A����2.9%�ł������B
�@��������JR�����{�̏H�c�V�����̏ꍇ�A�����̍H�����{�v��̍ۂ���A�K�v�ȑ����Ɣ�Ɩ����q�ݕt���Ƃ̑Ώێ��Ɣ�Ƃ̊Ԃɂ͊J��������A�c��̎��Ɣ�ɂ��ẮAJR�����{���ŏI�I�ɕ��S���邱�ƂɂȂ��Ă������߂ɁA���ʓI�ɁA���n����26���~�́A�S�����c�����c�Œ��B�����L���q�����ƂȂ��Ă������ƂɂȂ�B�܂薳���q�ݕt���ł̌��݂Ƃ͂����Ă��A�������畽�ϋ���0.02%�Ƃ͂����A�L���q�����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B�������A�{���ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A���̕��ϋ���������ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����A������S�z���L���q�����ɉ����Ă��܂����̂悤�ȃ��J�j�Y���𐧓x���̂�����Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@�܂�A�Ή��̉�����ԂƑݕt���̏��p���Ԃ̕s��v�A���Ȃ킿�A�����q�ݕt�������Ҋ���15�N�ł���̂ɑ��āA�S�����c�ƓS�����Ǝ҂Ƃ̊Ԃɂ́A25�N���҂̌_�����ׂȂ����Ƃ��甭�����閳���q�����̗L���q���Ȃ̂ł���B
�@���̎����ɋC������JR�����{���́A�H�c�V�����̏��n��4�����قǑO����A15�N�ԍς���]���ēS�����c�ƌ��������A����Ȃ������Ƃ����Ă���B�S�����c�Ƃ��ẮA���x�͈�ł���A���������n�Ή��̉�����@��S�����c���Ǝ��Ɍ��肷�邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂�[21]�AJR�����{�̂悤�ȗD�NJ�Ƃ݂̂ɓ��ʂȏ��n�Ή��̉�����@��F�߂邱�Ƃ͕s�\�ł���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��낤���A���{�́A�����Ə_��Ȑ��x�ɂ��Ă����i���͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B �H�c�V�����̏��n�ɓ������ẮA�S�����c��JR�����{�ɑ��āA�������������������āA1996(����8)�N12��3���Ɂu�c��ΐ��E���H���̑���Njy�я��n�E���n�����������菑�v���������Ƌ��ɁA25�N�Ԃ̏��n�Ή��̉���V�~�����[�V�������쐬�����Ă���B
�@JR�����{�͂���ɒ���āA�R�`�V�����̎R�`�E�V����Ԃ̉��L�H���̍ۂɂ́A�^�A�{�ݐ������ƒc�̖����q�ݕt�����x�𗘗p����(���Ȃ킿�S�����c���o�R����)�A�n���̎R�`�� (���m�ɂ́A�R�`�J������)����10�N���u��10�N���҂܂���5�N���u��10�N���҂̖����q�ݕt����JR�����{�����ڎāA�H�����s���Ă���[22]�B
�@����܂Ō��Ă����悤�ɁAJR�����{�͋����Ƃ̋����̒��ŁA�������o���Ȃ���A����܂ł̍����������玩�Ȓ��B�����ւƎ������B�̕��@���ւ��A���������̕������܂��Ƃ炦�āA�������B�R�X�g��啝�ɒቺ�����邱�Ƃɐ������Ă����B���̂��Ƃ͍��S���Z���ƒc���͂��߂Ƃ��鋌���S������������̓���@�l�Ɣ�r����ƑΏƓI�ł���B�����āAJR�����{�̋����Ƃ̋����𐬌��ɓ������w�i�ɂ́A�ߓx��������ݔ���������̑��݂����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���S�̌o�c�j�]�̋��P��̌����������̂Ƃ��āAJR�����{�̐ݔ���������͒��ڂɒl����B
�@�܂��AJR�����{�ɂ́A�S���̎��v�������傫���L�т邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ�����{�F��������B�ɂ�������炸�A�V�����݂��}���A�S�����Ƃ́A�ݔ������z�����z�Ȃ��߂ɁA�������甭�����镉�z���������p������z�ƂȂ�B�������p��ɂ���ĉc�Ɨ��v���o�Ȃ��Ȃ���肩�A���ɉc�Ɨ��v���o���Ƃ��Ă��A�����L���q���ł���A�����̕ϓ������ŁA�c�ƊO���x�̎x���������ϓ����A�o����x���傫�����E����Ă��܂����ƂɂȂ�B�܂�S���Ƃ��琶�ݏo���ꂽ�c�Ɨ��v���A�����̕ϓ��Ő�����Ԃ��Ƃ��\���ɂ��肤��B����ł͂�����c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă��Ă�����Ȃ��B�������đ�1�͂ł��݂��悤�ɍ��S�̌o�c�͔j�]�����̂ł���B
�@����ɑ��āAJR�����{�́A�������p��͈͓̔��ł����ݔ��������s��Ȃ����j���̂��Ă���B�����̘H���̉��ǂɂ��A���͂�L���H�����͍s���Ă��邪�A�ݔ�����(�����ݍH����A�ꕔ�Ԍɗp�n���̓y�n�w�����܂�)�͌����I�Ɍ������p�� (JR�����{�̏ꍇ�́A�N��2,200�`2,300���~) �͈͓̔��Ƃ���Ă���B�������p��͈͓̔��łƂ������Ƃ́A��������ς���A�ݔ��X�V�̂��߂̓������ۂ͈͓̔��łƂ������Ƃł���B�����������~�߂����炩�������ƂŁAJR�����{�ł́A���c����A�S���V���̌��݂͍s���Ă��Ȃ����A���݂̂Ƃ���V�����v����Ȃ��B
�@�V�����݂��s��Ȃ��Ƃ������ƂɊւ��āAJR�����{���������������Ă��邱�Ƃ��������Ⴊ����������B�Ⴆ�A�������Ȃ͓̂��k�V�����̏ꍇ�����A���S����A�S���~�ݖ@�ɌW��錚�݂Ə�z�V�����̌��݂͓S�����c���H����̂ƂȂ�A���k�V�����̌��݂͍��S���H����̂ł������B���k�V�����̓����E���Ԃ̍H���͖��c���ゾ�������A�����̐V�����ۗL�@�\����JR�����{��������Ď{�s�Ǘ��������̂������̂ŁA���c�����JR�����{�ɂ��V�����݂͂Ȃ������Ƃ����̂��AJR�����{���̌����ł���B�܂�JR�����{���o��������Ђ��V���H�����s�����Ƃ��Ȃ��B��O�I�ɁA�����ՊC�����S��������Ђɂ͏o�����Ă��邪(�o���䗦4.91%)�A�����ɂ͉����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B�������āA�g���͂߂Đݔ��������������Ă��邱�Ƃ��A���S����Ƃ̈Ⴂ�̍���ɂ���[23]�B
�@����ɉ��ǍH��������ꍇ�ł����Ă��A���Ӑ[���������B�X�L�[����I�����Ă��Ă���BJR�����{�ł́A�R�`�V�����A�H�c�V�����̏ꍇ�ȂǁA�����H���̉��ǂ̍ۂɂ́A�H�����ƂɌo�c�Ǘ����Ⓤ���v�敔�������̗\���Ȃǂ��s���A�̎Z���̌������s���Ă���B�������A���̏ꍇ�ɂ́A�������B�R�X�g�͌v�Z�ɓ���Ă��Ȃ��B���̗��R�́AJR�����{�̏ꍇ�A�����������ݍH����͂��ׂĒn�������̓�����̖����q�ݕt����O��Ƃ��Ă��邩��ł���A�����Ƃ��Ă���ȊO�̃P�[�X�ł́A�H���͍s���Ȃ�����ł���B���̔w�i�ɂ́A�������B���X�N���������Ƃ����l����������B���Ƃ����Ҋ��Ԃ������ł����Ă��A�L���q�����ł̓��X�N���傫���B���Z�@�ւł����A����ł͒����ł�5�N���x�݂̑��o�����ʏ�ł���A���\�N�ɂ��y�ԁu�������v�݂̑��o���͍s���Ă��Ȃ��Ƃ��������́A�����������X�N�ɋ��Z�@�ւł���Ή�������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���Ƃ����̂ł���B�����ŁA�������B���X�N���ɗ͉�����钲�B���@������Ă���̂ł���B
�@�܂�����Ƃ̋����𑱂������ŁA�������X�N���̂�}������̂��Ă���̂ł���B�������āA�S�����Ǝ҂͎������B�R�X�g��X�N�����Č������p��Ƃ��������{�W��p���ł��邾���}���A�c�Ƃɐ�O���ׂ��ł���Ƃ������z���琶�܂ꂽ���[�����AJR�����{�̂悤�ɁA�������p��͈͓̔��A���Ȃ킿�������ۂ͈͓̔��ł����ݔ��������s��Ȃ����A���ɁA�H�c�V������R�`�V�����̂悤�Ȋ����H���̉��ǂ̍ۂɂł��A���ݍH����͂��ׂĖ����q�ݕt����O��Ƃ���Ƃ������ƂȂ̂ł���B�����Ɉ�̓S�����Ǝґ��������яオ���Ă���B
�@�S�����ƂɂƂ��ďd�v�Ȃ͓̂S�����{�݂̎��Y���l�ł͂Ȃ��B�m���ɁA�S�����{�݂����L�ł���A���̕����]�܂����B�������A���L���邽�߂ɗv���鎑�����B�R�X�g��X�N�����Č������p��Ƃ��������{�W��p�͓S�����Ƃ̏ꍇ�ɂ͔���Ȃ��̂ɂȂ�B��������ׂĉ^�������ł܂��Ȃ����Ƃ͂܂����������I�ł͂Ȃ��BJR�����{�̏ꍇ�ł��A��������V�������n����Ă��܂��ƁA���̌�͔���Ȍ������p��������āA�������p��͈͓̔��ɐݔ���������������Ƃ������~�ߎ��̂��Ӗ��������\�����\���ɂ���B
�@�����������n�����ɑ��āA�V���̏ꍇ�ɂ́A�̎Z�͈͓̔��ɒ��ؗ��������߂�̂ł���A���ؗ������͌��ʓI�ł���B�Ⴆ�ΐ����V�����̏ꍇ�́A�S�����c�����݂��A����������L���͓S�����c�Ɏc��AJR�e�Ђ͏��n�����ɁA��āA���ؗ����x�����Ȃ���c�Ƃ����邾���ł���B���̍ۂ̒��ؗ��́A���x�͈͓̔��ɐݒ肳��Ă���B���́A���������ݕt�����͍��S���ォ�瑶�݂��Ă����ʓI�ȕ��@�Ȃ̂ŁA���̂��Ƃ����Ă������B
�@�����S�̐V���̋敪�Ǝ������B�E�ݕt�E���n�͕\3-6�̂悤�ɐ����ł���B���S�̐V�����݂ɓ������Ă����S�����c�́A1964(���a39)�N3��23���̌��c�ݗ������ɂ����ẮA�L���܂��͖����̑ݕt���̌��݂����邱�ƂɂȂ��Ă����B�����ł����L���̑ݕt���Ƃ́ACD���AE���̒Ìy�C�����AG���ł���V�����̂��Ƃł���A�����̑ݕt���Ƃ�AB���̂��Ƃł���[24]�B
�\3-6. �����S�̐V���̋敪�Ǝ������B�E�ݕt�E���n
| �敪 | �ړI | ���ݎ��� | �ݕt | ���n | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB�� | �n���J���� �y�ђn������ | ��Ƃ��Ēn��i���̐����Ɏ������ | ���������̂� | ���� | JR�e�ЁA���S�� �Z���ƒc�ɏ��p |
| C�� | ��v���� | ��v�s�s�Ԃ̗A���͑�������}����� | �����̗A�����v�������߂邽�߁A �L���q����(���������Ɩ��Ԏ���) ���[������A�J�ƌ�A���S���� ���c�ɏ��҂���� | �L�� | �ݕt���Ԍo�ߌ�� ���n |
| D�� | ��s�s��ʐ� | ��s�s�̗A���͂̑�����}��� | |||
| E�� | �C���A���� | �Ìy�C�������͂��߂Ƃ���� | ���c�̉i�v�ۗL | ||
| F�� | �lj����ݐ� | �S���V�����ݒ����v��(1966�N12��)�ɂ���������̉����Ȃ����� | |||
| G�� | �V���� | �S���V�����S�������@(1970�N5�����z6���{�s)���āA1971�N4���� �^�A��b�������v������肵�A��z�A���c���V�����̌��݂����c�ɁA ���k�V�����̌��݂����S�Ɏw���������ƂŁA���c�����߂ĐV������ ���݂Ɍg��邱�ƂɂȂ��� | �L�� | 1989�N�ȍ~�Ɍ��� ���������V������ ���c�̉i�v�ۗL | |
�@1970(���a45)�N3���Ɍ��c�@�{�s�߂������ɂȂ�A���݂����S���{�݂́A1969(���a44)�N4��1���ȍ~�A���ׂĈ�U�݂��t������A���̑ݕt���Ԃ��o�߂������̂ɂ��ď��n���邱�ƂɕύX�ɂȂ����B���s�ł́A40�N�ԍ�(80������)�ŁA���ό�ɏ��n����邱�ƂɂȂ�B���S�̖��c���ɔ����A�ݕt���̑�����JR�e�Ћy�э��S���Z���ƒc���ɏ��p����A���L�����ڂ��Ă��邪�A�܂��S�����c�ݗ����琔���Ă�40�N�����Ă��炸�A���ς�����͂Ȃ��BJR�e�Ђ͕ԍς𑱂��Ă���B�Ⴆ�A�傫�ȗA�����v�������߂邽�߂ɁA�����S��CD���̂����A���ݐ��E��������E���t�����́A���݂��S�����c�̑ݕt�����ƂƂȂ��Ă���B���������ς����JR�����{���ɏ��n�����B
�@����ł́A�ݕt���͂ǂ̂悤�ɂ��Čv�Z�A�ݒ肳��Ă���̂��낤���B�ݕt���̌v�Z�́A�\3-7�̂悤�ɍs���Ă���B�\3-7(A)�̇@�̕����ł́u�^�A��b���w�肷����ԂƗ����v�́A��ɗ��q�⋋�̑Ώۋy�ъ�����肳��邱�Ƃɔ����A���т��щ��肳��Ă����B���̌��ʁA�u��z�V�����v�u�ΐ����v�u���ݐ��v�u���̑��v�̂��ꂼ��ɂ��Ċ��ԂƗ������w��E���肳��Ă��Ă���B������4.5%�`6.5%���������A�ݕt���ɑ��ẮA���q��5%���镪�ɂ��Ă͂��̑S�z���A������^�A�{�ݐ������ƒc(�� �S���������)��ʂ��ēS�����c�ɑ��ė��q�⋋���s���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�\3-7. �ݕt���̌v�Z
(A)�ݕt���̗v�f
| ���݂ɗv������p (���݊��Ԓ��̗��q ���Ƒd�ł��܂�) | �ؓ����� | �^�A��b���w�肷����ԂƗ����ɂ�錳���ϓ� ���N���x���̕��@�ɂ�菞�҂�����̂Ƃ��� �ꍇ�ɂ����铖�Y�N�x�̔��N�����̍��v�z | (1) |
| �ؓ������ȊO | �������p��̊z | (2) | |
| �S�����ݍ��̍����s��ƍ����s���� | (3) | ||
| �d�łƊǗ���̍��v | (4) | ||
(B)�ݕt���̌v�Z��
| �敪 | ���N�x�̑ݕt�� | ���l |
|---|---|---|
| CD�� | (1)�{(2)�{(3)�{(4) | 1969�N�x�` |
| (2)�{(4) | ���ݐ����ؒ��E��q�� | |
| E�� (�Ìy�C����) | (4) | 1988�N3���` |
| G�� (�����V����) | ���Y�V�����������ꍇ��
���v�Ɠ��Y�V���������ȁ@�{(4) ���ꍇ�̎��v�Ƃ̍�(��z) |
�Ⴆ�A����E����� �͖��N�x175���~ |
�@�����������ŁA���ڂ����̂́AG���̐����V�����̑ݕt���̌v�Z�����ł���B���Y�V�����������ꍇ�̎��v�Ɠ��Y�V���������Ȃ��ꍇ�̎��v�Ƃ̍�(��z)�ɇC�d�łƊǗ���̍��v��������Ƃ��������ł���A�S�����Ǝ҂́A�x�������⌸�����p��Ƃ��������{�W��p�̏d���ƃ��X�N����������āA�c�Ƃɐ�O���邱�Ƃ��ł���B���ɖk���V�����̍���E����Ԃ̑ݕt�������N�x175���~�ƒ�z�Œ�߂��Ă���B�����Ƃ̋����𑱂������ŁA���������������X�N���̂�}���鐧�x�A������͍������ׂ��Ȃ̂ł���B
�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA���c����AJR�����{�͋����Ƌ������A���z�ƕ��ϋ����̈��k�ɐ������Ă����B�������A�@����������Ƃ����_�ł́A���c������܂����_���c���Ă���B����́AJR�e�Ђ̏ꍇ�A��Ж@�̒��ŁA�Ѝ��s�����ł͂Ȃ��A1�N�ȏ�̒����ؓ����ɑ��Ă��A�^�A�Ȃ̔F���K�v�ɂȂ��Ă���_�ł���BJR�����{�̏ꍇ�A�����ؓ�����1��̒��B��500�`600���~���x�̎������B�����邪�A����ɂ͎��O�������܂߂ĔF��2�������x���������Ă���Ƃ�����B������������ł́A�@���I�ɋ����̕ϓ��ɑΉ��ł��Ȃ��B�Ⴆ�A1998(����10)�N��10������12����{�܂ł́A�ؓ����̒��B��Ѝs����̂ɁA���ɗǂ����ł������B���̎�����10�N���̍��̕\�ʋ�����1%�O�ゾ�������A���̌�12�����{�ɂ�10�N���̋�����2%���鐅���ɂȂ��Ă���B�����F�\�������Ȃ��Ă�JR�����{�����R�ɋN��ؓ����s�����Ƃ��ł���̂ł���A���̐�D�̋@��������Ƃ��ł����͂������A����͂ł��Ȃ������B���̋������ł́A���B�z1,000���~�ŁA10�N�ԂŖ�100���~�̎x�������̍����o�邱�ƂɂȂ�B�@���������邽�߂ɂ́AJR�S�ЂƂ͂���Ȃ����A���߂Ċ����s��ɏ�ꂵ����Ђɂ��ẮA���������F���x���͂����Ă����������]�܂����B
�@�܂��A���Ɍ����悤�ɁA�H�c�V�����̏ꍇ�ɂ́A���c�H���ł͂��������AJR�����{���{�s�Ǘ��ɓ�����A10%�ȏ�̃R�X�g�팸���ʂ������Ă���Ƃ��������͒��ڂɒl����B�Ȃ��Ȃ�A�S�����c���ɂƂ��ẮA�S�����Ǝ҂قǂɂ͗L���q���������炻���Ƃ����C���Z���e�B�u���Ȃ�����ł���B
�@�������A�S�����Ǝ҂ɓS���{�݂����n������A�S�����Ǝ҂̌o�c�������s���Ȃ��Ȃ�A�S�����c�ɏ��n�Ή����x�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�S�����c���Ɍ����������邱�ƂɂȂ�B�܂��A�S�����c���A�S���{�݂̌��݃R�X�g�k���Ɏ�����悤�ɂƁA�Z�p�J�����ȉ�A���ݔ�z�Ǘ��ψ���A���݃R�X�g�ጸ�������ʈψ����ݒu���ēw�͂��Ă��邱�Ƃ������ł���B�������A����ł��Ȃ���������H�������̍H�����p�n�����̒x�ꂩ�痈�錚�݊��Ԃ̑啝���߂ɔ��������̑啝�������ɂ��ẮA���̔�p���������S�����c���̑����ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��B���ݍH�����x�ꂽ��A�v������]�v�ɔ�p���������Ă��A���̕��͌��c�s���Ď������q���ŁA���̒lj��z�����̂܂܃v���X���āA�S�����Ǝ҂ɏ��n�ł���Ƃ����\�}���A�S�����c���Ɏc����Ă������A��͂�S�����Ǝ҂قǂɂ͐ϋɓI�ɗL���q���������炻���Ƃ����C���Z���e�B�u�͐��܂�Ȃ����낤�B�H���x����H����̍ۂɁA�S�����c���S�����Ǝ҂ɑ��Ď��O���������邱�ƂɈ�̂ǂ�قǂ̈Ӗ�������̂��낤���B
�@���������S�����c�̂悤�ȑ��݂́A�t�@�C�i���X�@�\�Ƃ����_�ŕ֗��ł͂��邪�A�����ɁA�S�����c���g���H���̎{�s�Ǘ��ɓ��������ꍇ�ɂ͗L���q���������炻���Ƃ����C���Z���e�B�u�����Ȃ��Ƃ����_�ł͊댯�ł�����A�܂��ɗ��n�̌��Ƃ�����B�p�n�����ȂǂɎ��Ԃ�������߂��A���݊��Ԃ��啝�ɉ��т邱�ƂŗL���q�����̊z���c���ł��܂����Ƃ��A�S�����c���͐Ԏ��ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����\�����̂��A���Ƃ��\�ʉ����Ă��Ȃ��Ă����Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��ł́A�ꕔ�̖��S���̍H����H�c�V�����̍H���̂悤�ɁA���c�H���ł����Ă��S�����c�Ɏ{�s�Ǘ���C������ɂ����ɓS�����ƎҎ��炪�{�s�Ǘ����s�����Ƃ́A�S�����ݎ��ɂ�����L���q�����̈��k�ɂ͌��ʓI�ł���B
�@���邢�͊��ɐG�ꂽ�悤��G��(�����V����)�ōs���Ă���ݕt�����́A�S�����c���ɂ����X�N�E�V�F�A�����O��������Ƃ����_�ŁA���ʂ����邩������Ȃ��B���Y�V�����������ꍇ�̎��v�Ɠ��Y�V���������Ȃ��ꍇ�̎��v�Ƃ̍�(��z)�ɇC�d�łƊǗ���̍��v��������Ƃ��������ł���A���ݍH�����x��ė��q��������ŗL���q�������c���ł��܂������̃��X�N��S�����c�����w�������ƂɂȂ�B��������A���R�A�L���q�����z�ƍH�����Ԃ̗��������k���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���b�V���[�ɂȂ�͂��ł���B
�@���āA���{���L�S�����Z���ƒc�̍����҂̂��߂ɂƂ�ׂ����{���������1989(������)�N12���̊t�c����Łu���ƒc�̍������́A��������Ƃ̋����ł���v�Ƃ����\�������������A���̌�̎��ƒc���̑����́A���ƒc�̎��Y���p�������A�����{���甭�����闘�q�Ƃ̋����ɍŏI�I�ɕ��������Ƃ������Ƃ�������(�Γ�, 1999)�B���S�̋��P�������߂ɂ́A������ɂ���A�S�����݂��S���o�c���A�����Ƃ̋����ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�S���H���ɓ������ẮA�L���q�����z�ƍH�����Ԃ̗������ł��邾�����k���āA�S�����Ƃ̎��v�\�����̂̈�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�������ʼnc�Ɨ��v��������Ԃ悤�ȏ��ɒu����Ă��ẮA������c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă����ꂸ�A�������c�Ɠw�͎��̂��Y�ꋎ���邱�ƂɂȂ�̂�����B
[13]�������A�J��Z����1997(����9)�N�ɂȂ��āA���̔N�x�ȍ~�̎ؓ��_��ɂ��ď��߂ČJ��グ�ԍς��ł���悤�ɂȂ����B
[14]���́A���j��A���i�t���̍ŏ��̑ΏۂƂȂ������̂��A�܂��ɓS�����������̂ł���B���݂̕č��ɂ�����2��i�t���@�ւ̈�A���[�f�B�[�Y�E�C���x�X�^�[�Y�E�T�[�r�X(Moody�fs Investors Service, Inc.)�́A�n�Ǝ҃W�����E���[�f�B�[(John Moody)��1900�N�ɓS����Ђ̓��v�����o�ł̂��߂ɐݗ�������Ђł������B���Ђ�1909�N�ɔ��s�����w���[�f�B�[�Y�S�����������́x�̒��ŁA�S����Ђ̔��s�����250��1500�����̓��������Ƃ��Ă̗D���Aaa����C�܂ł̋L����9�i�K�Ɋi�t�������̂��A�ŏ��̊i�t���������Ƃ����Ă���(����, 1999, p.87)�B
[15]���{�ł́A1975�N�ɓ��{�o�ϐV���Ђ��Г��Ɍ��Ѝ������ݒu���Ď����I�Ȋi�t�����n�߁A1979�N4���ɂ͓��{�o�ϐV���Ђ̓����g�D�̂܂ܓ��{���Ѝ�����(JBRI)�ɉ��g�����B1985�N4���ɂ��̌������͓��{�o�ϐV���Ђ�����Ƃ��銔����ЂƂ��čăX�^�[�g�������A�����ɐ����ۂȂǂ̋@�֓����ƌn�i�t���@�ւƂ��ē��{�i�t������(JCR)�A��s�E�،��n�i�t���@�ւƂ��ē��{�C���x�X�^�[�Y�T�[�r�X(NIS)���ݗ����ꂽ�B�����O�̖����n�i�t���@�ւ̂����AJBRI��NIS��1998�N4���ɍ������āA���{�i�t�������Z���^�[(R&I)�ƂȂ����B�������āAR&I�Ɠ��{�i�t������(JCR)�̖����n2�Ђƕč���2�Ђ̊i�t�����A���{�Ŏ�Ɏg����悤�ɂȂ����̂ł���(���{�i�t�������Z���^�[, 1998, p.45; ����, 1999, p.114)�B
[16]�i�t����Ђ́A�ʏ�͍����s��(�N��)����̈˗����A�_�������Ŋi�t�����s���B�N�҂͊i�t���@�ւ̒����ɉ����A������A�i�t���萔�����x����(�N�҂̊i�t���L�����ɐ��������̂́A1968�N��S&P���ŏ��ł�����(����, 1999, p.89))�A�i�t���@�ւ͌��\�ɓ������Ď��`�����Ƃ����_��ł���B���̑��ɂ��u����i�t���v�Ƃ����A���s�҂���̈˗��Ȃ��Ɋi�t�����s�����\���邱�Ƃ�����B����i�t���ɂ��ẮAR&I�ł�op (official publications)�AS&P�ł�pi (public information)�A�Ƃ����L����t���Ă��邪�A���[�f�B�[�Y�̏ꍇ(�u�����i�t���v�ƌĂ�ł���)�͋�ʂ��Ă��Ȃ��B
[17]���[�f�B�[�Y��1962�N�ɑ��M�p������Ѓ_���E�A���h�E�u���b�h�X�g���[�g�ɔ�������A���݂�100%�q��ЂƂȂ��Ă���B����A���[�f�B�[�Y�ƕ��ԕč���2��i�t���@�ւ̈�A�X�^���_�[�h�E�A���h�E�v�A�[�Y(Standard & Poor�fs Corp; S&P)�̕��́A1860�N�ݗ��̃v�A�[�Y�Ђ�1920�N�ݗ��̃X�^���_�[�h�Ђ�1941�N�ɍ������Ăł����i�t���@�ւł��邪�A�v�A�[�Y�Ђ�1922�N����A�X�^���_�[�h�Ђ�1924�N���炻�ꂼ��i�t�����s���Ă��Ă����BS&P��1966�N�ɑ��o�ŎЃ}�O���[�q���ɔ�������A100%�q��ЂɂȂ��Ă���(����, 1999, p.89)�B
[18]�V�������ɂ́A���̑��ɐ����V�������ɗ��p���Ă����悹��(60�N����6.55%)������B
[19]1972(���a47)�N��P���Ɩ����n�݂��ꂽ�ۂɂ́A�����ɓS�����c�{�s�ߑ�9����3�Ƃ���P���̏��n�Ή��̉�����@���K�艻����Ă���B
[20] JR�����{���A�S�����Ɩ@(���a61�N�@����92��)��7���1���y�ѓ��@�{�s�K����7���̋K��Ɋ�Â��A1992(����4)�N1��28���ɉ^�A��b���ɐ\�������u���Ɗ�{�v��̕ύX�F�\�����v�́u���ݔ�T�Z���v�ɂ��A�H����́u��598���~(����3�N�x���i)�v�Ƃ���A���\�����́u���Ƃ̊J�n�ɗv���鎑���̑��z�y�ђ��B���@�v�ɂ��A�u�{�ݍH����ɂ��ẮA�S����������̕⏕���x��K�p���A���͍H�����1/2���q�Z���A�n�������Ɠ����Ƃ��H�����1/2���q�Z������v�Ƃ���Ă���B�������A1992(����4)�N2��6���ɓS����������@(����3�N�@����46��)��22���1���Ɋ�Â��\�������u���ƔF��\�����v�ɂ����ẮA����F��\���z�́u490���~�v�Ƃ��A���̒��B���@�́u�S�������������̖����q�ݕt���A�n�������c�̖̂����q�ݕt���v�ƂȂ��Ă���B ����28���ɉ^�A��b������c�ɑ��āA�H�����{�v��̎w���y��JR�����{�ɑ��鎖�ƔF�肪�o���ꂽ�̂ŁA���c��JR�����{�͓����t���œc��ΐ��E���H���̑���Njy�я��n�E���n����{�������������B���H����͓���598���~�Ƃ���A���c���ڎ{�s�̍H�����25.6���~�AJR�����{�ւ̈ϑ��{�s�̍H�����572.4���~�Ƃ���Ă����B�����āA���̌��c�ɑ���H�����{�v��̎w���̍ۂɂ́A�u�K�v�ȑ����Ɣ��598���~�Ƃ��A�����S�������������̖����q�ݕt���Ƃ̑Ώێ��Ɣ��490���~�v�Ƃ��A�u�c��̎��Ɣ�108���~�ɂ��ẮA�����{���q�S��������Ђ��ŏI�I�ɕ��S����v�Ƃ����|�̒ʒm���A�ʓr�A���c�ɏo����Ă���B
[21]�S�����c�����݂����S���{�݂�S�����Ǝ҂ɏ��n���悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A�^�A��b����߂��ɏ]���Čv�Z�������n���z���A�^�A��b���w�肵�����ԋy�ї����ɂ�銄���x���̕��@�ɂ����邱�ƂƂ���Ă���(���{�S�������c�@23���y�ѓ��@�{�s��9��)�A�S�����c�Ǝ��ŏ��n�Ή��̉�����@�����肷�邱�Ƃ͕s�\�ł���B
[22]�������A�^�A�Ȃ͌����������o���Ă��Ȃ����A���ƒc�̖����q�ݕt�����x�́A��V�����Ō�̓K�p�Ƃ��\����Ă���A����JR�����{���]�Ƃ��Ă��A���ƒc�̏����Ώێ��ƂƂȂ�\���͒Ⴉ�����Ƃ������Ă���B
[23]�S�����Ƃł́A�V�����݂̏ꍇ�������A�ݔ������͔���̑����ɂ͌��т��Ȃ��Ƃ������F������B�w�̎{�݂��ǂ�Ȃɍ��ɂ��Ă��A�ԗ������ǂ��Ă��A��q�ɑ���T�[�r�X����ɂ͂Ȃ邪�A��{�I�ɏ�q����������킯�ł͂Ȃ��B���������āA�V�����݂��s�킸�ɁA�������p��͈͓̔��Őݔ��������s���Ƃ������Ƃ́A�T�[�r�X����ɐ�O����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂�������Ȃ��B�������A�ȃG�l�^�̐ݔ������Ȃǂ��s���A���̂Ƃ��́A���㍂�͑������Ȃ��Ă��R�X�g�팸�ɂ͂Ȃ���B
[24]�\3-6�����Ă���ƁA�������B�I�ɂ�AB�����]�܂����悤�Ȉ�ۂ��邪�A���_������B���́A���������������g���Č��݂���AB���́A�⏕�����𔖂���T���Ă������͎����������Ăǂ����Ă��������x���Ȃ�̂ł���B�����ł��т��炵�āA����������ڎw�����Ƃ���ƁA���ݔ�̍����Ƃ��Ē��B�̗e�ՂȗL���ؓ����𓊓�����K�v��������B�����ŁAAB���ł�����������(����E�k������)�ƎI����2�H���ɂ��ẮA���S����̗v���ɂ��A1965(���a40)�N����ؓ������������ꂽ�B�ؓ������̈����͑���CD�����݂̑ݕt�����ɍ��킳�ꂽ���A�ؓ������ȊO�̕����̑ݕt��̈����͑���AB���Ɠ�������(���Y�����ɔ������錸�����p����z���u�⏕���v�Ƃ��č�������c�Ɍ�t)�ɍ��킳�ꂽ�B�����悤��AB���Ƃ��Ē��肳�ꂽ�Ďq��(���̏����E���Ê�)�ɂ��ẮAAB������CD���ւ̕ύX�[�u���m�F�̏�A1982(���a57)�N�x�Ɍ��ݔ�̍����Ɏؓ������������ꂽ�B������́A����CD���Ɠ���ݕt�����ő݂��t�����Ă���(�w���{�S�������c�O�\�N�j�xp.646)�B
�@�h�C�c�ł́A1994�N�̓S�����v(Bahnreform)�ɂ��A�������h�C�c�̍��S�͓����̏�A������Љ�����āA�h�C�c�S���������(DBAG: Die Deutsche Bahnen Aktien Gesellschaft)���a�����A���c����ڎw�����v���Z�X���n�܂����B�S�����v�O�A�������h�C�c�̍��S�͎����ԂƂ̋����Ŏs��������Ȃǂ��Čo�c���������A�S�����v�̍ۂɁA�A�M���{�������������h�C�c���S�̗L���q���̊z(1993�N��)��660���}���N(1�}���N����74�~���Z�Ŗ�4.9���~)�ɂ��B����[25]�B �h�C�c�̓S�����v�́A1987�N�̓��{�̍��S�������c���ɑ傫�ȉe�����čs��ꂽ�Ƃ�����B�����������ɓ��{�Ƃ̑���_�����݂��A���Ƀh�C�c�ł́A�V���DBAG�������S������؈����p���ł��Ȃ��_�A�A�M���{���z���ł̈����グ�������̗�������n�����̐Ԏ���U�ɂ��Ă�Ƃ����悤�ɋ����S���̕ԍόv��ƍ�������̓I�ɒ�߂Ă���S�����v�ɗՂ�ł���_�����{�Ɣ�ׂėD��Ă���[26]�B
�@�h�C�c�̓S�����v�Ɏ���v���Z�X�ɂ��ẮA���ɖx(1994)�A��(1994)�A����(1996)�Ƃ������ڍׂȌ��������邪�A�����ł͓S�����v�Ƃ��̌�̓�����ʂ̊p�x����Ƃ炦�邱�Ƃɂ��悤�B�h�C�c�̓S�����v���A���{�̍��S�������c���Ɠ��l�ɁA�c��ȍ��S�Ԏ���w�i�ɂ��čs��ꂽ���Ƃ͎����ł��邪�A�{�e�ł́A���Ȃ��Ƃ�����4�_�ɂ����āA���{�ɂ͂Ȃ����������I�ȕ��������������Ƃ𖾂炩�ɂ������B
�@�܂����ɁA1990�N�̃h�C�c����̑O��ɂ́A�h�C�c�͓S���ɑ��锜��Ȑݔ�������K�v�Ƃ���Ɋׂ��Ă����B���Ȃ킿�A
�@���������C���t�������̂��߂̔���Ȑݔ������́A�����ł����Ԏ��̑������S�ɕ��S�ł�����̂ł͂Ȃ��A����ɘA�M���{���������S���邱�Ƃ����߂��Ă����B
�@���ɁA���������q�A�ݕ��ɂ��ẮA���Ƃ��Ɨ������ł��郈�[���b�p�S�̂ł̓S���Ԃ̍\�z�̒��Ōo�c�`�Ԃ��l�����Ă��Ă����B���[���b�p�S�̂̓S���ԍ\�z���ɂ�ŁAEU�����ȑO����EC�w�߂ŏ㉺�����̕��������ł��o����Ă���A����Ɋ�Â��A�h�C�c�̓S�����v�ł͉��������q�A�ݕ��̃I�y���[�V�������s���S�����Ǝ҂��C���t����������͕�������A�����I�y���[�V�����S���̓S�����Ǝ҂ւ̐��{�̏����͈�؍s���Ȃ����ƂɂȂ����B
�@��O�ɁA�ߋ������q�ɂ��ẮA�����h�C�c��1960�N�ォ��n����ʂɂ�����u���H������H�ցv�̐����]�����s���A���̗���̒��ŁA�S�����v�ɂ���āA�ߋ������q�S����A�M���{����B���{�ֈڊǂ��邱�Ƃ��s��ꂽ�B���������āA�ߋ������q�S���ɂ��ẮA����̓S�����v�̃v���Z�X�̒��ł��A�㉺�����ł͂Ȃ��A�ނ���n��Ƃ��Ă܂Ƃ܂��ăC���t�������ƈ�̉����ēS���o�c�����Ă������Ƃ������������������Ă���B
�@��l�ɁA���{�̍��S�ɂ͌������͂��Ȃ��������A���h�C�c�̍��S�ł͌����������������Ă���A���̂��Ƃ���������⋣���͌���̑������ɂȂ��Ă���Ƃ����F�����������B���{�̍��S���Z���ƒc�ɂ��Ƃ�����h�C�c�̘A�M�S�����Y�@�\(BEV)�́A���h�C�c���S�̌o�c�̑������������Ă�����̃}�C�i�X�v��: ���z�L���q���Ɩc��Ȍ������������邱�Ƃ�ړI�ɐݗ����ꂽ���A�S�����v�̑��i�K�ŕ��ԍς̔C�������ꂽ����������A���̌��ʁABEV��DB�O���[�v (DBAG�����Љ����Ăł�����Ђ̃O���[�v)�̕��������ƌ������̐l���E�N���̂��߂̋@�ւƂȂ�A���S���Z���ƒc�Ƃ͑S�����i�̈قȂ���̂ƂȂ����B
�@���̂悤�ɓ��{�Ƃ̈Ⴂ�͑傫�����̂́A���{���h�C�c�Ɋw�Ԃׂ����Ƃ͑����B�܂��A�h�C�c���S�����v�ɂ���Ă��N���ɑł��o�����ƂɂȂ����������B�X�L�[���́A���{�Ɣ�r���đ傫�ȓ���������B�h�C�c�ł͓S�����v�̑�2�i�K���@�ɁA�S���ݔ��ւ̔���ȓ������A�V�����݂ɂ��Ă͂��ׂĘA�M���{�̕⏕���ɂ���Ęd���A���ǍH���ɂ��Ă͘A�M���{����̖����q�ݕt���ƓS�����ƎҎ��g�̓������ۂɂ���Ęd�����ƂƂ����B���{�̂悤�ɁA�S�����݂̎������B�����ՂɗL���q���ɋ��߂��A�S�z��⏕�����ō������S������o������߂��Ƃ������Ƃ͒��ڂɒl����B��1�͂ł������悤�ɁA���ē��{�ł́A���{�����S�̐ݔ��������������S���g�ɏꓖ����I�ɗL���q�Œ��B���������Ƃɂ���āA���̌�A������B�����ɑ����A�S���o�c���\���I�ɔj�]���Ă��������A��2�͂Ő��������悤�ɁA���̎������B�X�L�[���́A���݂̓��{�ɂ����Ă����܂��Ă���Ƃ͌�������������ł���B
�@�����āA��������{���h�C�c�Ɋw�Ԃׂ����Ƃ́A����̈�ѐ��ł���B��2�͂ł��������悤�ɁA�����������{�ł́A����̓S�����Ƃł����Ă��A���Ǝ҂ɂ���ĕ⏕�����̏o�������قȂ�����A���݂̓r���ŕ⏕�����������ꂽ��ƁA����̑��ݎ��̂��^�������Ȃ�悤�ȏꓖ����I�ȍs�����s���Ă����B����ɑ��āA�h�C�c�ł́A�S�������ł͂Ȃ����H���܂߂���т�����ʐ����c�_���S�����v�O���瑶�݂��Ă���[27]�B�������S�����v�O�ɂ́A���������������̒����c��(����т�������)���A���S�Ƃ������іڂŕ��G�ɗ��ݍ����Ă��܂��Ă����̂ł���B�h�C�c��1994�N�̓S�����v�́A���̌��іڂ𓌐��h�C�c���S���ĕ҂��邱�Ƃʼn����ق����A���ꂼ��̏c���ɐ���Ƃ��Ă̈�ѐ����m�ۂ��邽�߂̍�Ƃł��������ƍl����Ɨ��������₷���B�P�X�^�E��(2000, p.19)���咣����悤�ɁA1990�N��Ɏ��{���ꂽ����́A���ׂĂ���܂łɐ��h�C�c���S�̉��v�ĂƂ��ċc�_����Ă������e�ł���A�^�C�~���O�̖���1994�N�ɂȂ��Ĉ�C�Ɏ��{���ꂽ�Ƃ����Ă��悢���̂Ȃ̂ł��顂��̌��ʂƂ��āA�h�C�c�ł́A�S�����݂ɔ���Ȑݔ����������𓊓����邽�߂̎������B�X�L�[�����A�S�����v��ʂ��āA���V���v���Ȃ��̂ɐ������ꂽ�̂ł���B�h�C�c�̓S�����v�ɔ�ׂ�A���{�̍��S�������c���͍��S�́u���Z�v���Ӑ}�������̂ł���A�i�i�ɊȒP�ȍ�Ƃ������͂������A�ɂ�������炸�A���{�ł͍��S�̕������c����A�������B�X�L�[�����������ĕ��G�ɂȂ��Ă���A�ΏƓI�Ƃ�����B
�@����ł́A�܂��ŏ��ɁA�h�C�c�̓S�����v�Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂����ȒP�ɐ������Ă������Ƃ���n�߂悤�B
�@���h�C�c�̍��S�A�h�C�c�A�M�S��(DB: Deutsche Bundesbahn)�̗��q�A���V�F�A(�l�L��)��1950�N�ɂ�34.4%�����������A���̌�A�����ԂɃV�F�A��D���A1970�N�ɂ�8.4%�A������1990�N��6.0%�ւƋ}���ɃV�F�A���ቺ�����B�ݕ��A���V�F�A(�g���L��)�ɂ��Ă����l�Ɏ����ԂɃV�F�A��D���āA1950�N��55.3%�A1970�N��32.7%�A1990�N��20.5%�ƒቺ�X����������(����, 1996, pp.132-133) [28]�B
�@��������DB�̒n�ʒቺ�̔w�i�ɂ́ADB����������������������Ă���(���������ł���������������������)���߂ɁA�����ԂƋ����ł���悤�ȃT�[�r�X��ł��Ȃ��������ƁB����ɁA1960�N��ȍ~�A�n���ł̑��̊m�ۂ�D�悵���H���g�����s��ꂽ���̂́A���v��������悤�ȓ����͍s���Ȃ��������ʁA�������ۂ��m�ۂł����ɂ܂����̐ݔ��������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ������z�������āA���̓S���ߑ㉻���x�ꂽ���Ƃ���������[29]�B
�@��������DB�͔����ȗ���т��ĐԎ��o�c�𑱂��Ă���[30]�B1973�N�ȍ~�͐��h�C�c���{�ɂ��DB�ɑ��闘�q�⋋�[�u���������ɂ�������炸�A�ݐύ��z��1990�N�ɂ�440���}���N[31] (��3.3���~[32])�ɑ������Ă�����(�^�A��, 1996)�B1980�N��A�����h�C�c���{�̘A�M�S���ւ̏������͔N��100���}���N(��7,400���~)�ȏ�ɂ̂ڂ�A�A�M�\�Z��3�`4%���߂Ă����Ƃ�����(��, 1994)�B���̂悤�ȏ��ɂ����āA1990�N�̃h�C�c�̓���ŁA����ɓ��h�C�c���S�Ƃ����d�ׂ������邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̓��h�C�c�̍��S�A�h�C�c�鍑�S��(DR: Deutsche Reichsbahn)�́A�ꎞ�A�������q�A���ʂ�1/2�A�ݕ��A���ʂ�2/3�̃V�F�A���ւ��Ă���(�x, 1994)�B�������A����͋����h�C�c����ɂ͎����Ԃ����荢��ŁA����Ɍv��o�ϑ̐��̉��ł̈��̓S�����v�̕ۏ����������߂ɁA�S���ˑ��x�����������̂ł���B1990�N10���̃h�C�c������o�āA���R�o�ϑ̐��ֈڍs����ƁA���h�C�c�n��͌o�ϊ�@�ɂ��o�ϊ������̂�����������߂ɗA�����v���S�ʓI�Ɍ���������ɁADR�͎����ԂƂ̋����ɂ��炳��āA�s��V�F�A���}���ɒቺ���A1991�N��DR�̗A���ʂ́A���q�A�ݕ��Ƃ���1990�N����قڔ������A43���}���N(��3,182���~)�̌������o���Ɏ�����(�^�A��, 1996)�B
�@�������A���̂悤�ȓ����h�C�c�̍��S�̒u���ꂽ�𗝉�����ɂ́A���{�Ƃ̈Ⴂ�ɁA����Ȃ钍�ӂ��K�v�ł���B���́A�\4-1�ɂ���悤�ɁA�h�C�c����ɂ���āA�h�C�c�̍��y�ʐς͓��{�̍��y�ʐςƂقړ����ɂȂ����B�Ƃ��낪1990�N�̒i�K�ŁADB��DR�̍��v�ƁA���{��JR�e�Ђ̍��v(���q�S����Ђł���JR6�ЂƓ��{�ݕ��S��(JR�ݕ�)�̌v7�Ђ̍��v)���r����ƁA�\4-1�̂悤�ɁA�����h�C�c���S�̉c�ƃL�����̍��v�́AJR�e�Ђ̍��v�̂ق�2�{���������̂ł���B�������A�����h�C�c���S�̗A���ʂ�JR�Ɣ�r����ƁA���q�A���l�L����25%�����Ȃ��A���q�̗A���ʂ�JR�����i�i�ɏ��Ȃ��̂ł���B�ݕ��A���g���L���ł�JR��3.8�{����A�����h�C�c���S�́A���q�A�������ݕ��A�������S�������Ƃ������ƂɂȂ�B
�\4-1. 1990�N�̃h�C�c�Ɠ��{�̓S��
| �h�C�c | ���{ | |
|---|---|---|
| �@�@�ʐ�(��km2) | 357 | 378 |
| �@�@�l��(�S���l) | 79.1 | 123.6 |
| �@�@�l�����x(�l/km2) | 220 | 330 |
| �S�� | DB+DR | JR* |
| �@�@�S���c�Ƌ���(km) | 40,989 | 20,175 |
| �@�@�@�@���q�c�Ƌ��� | 33,480 | 20,175 |
| �@�@�@�@�ݕ��c�Ƌ��� | 39,892 | 10,136 |
| �@�@�@�@�����ȏ��� | 16,599 | 5,953 |
| �@�@�@�@�d������ | 14,718 | 9,601 |
| �@�@�H�����x(m/km2) | 115 | 53 |
| �@�@�E���� | 462,235 | 192,000 |
| �@�@�L��������E���� | 11 | 10 |
| �@�@�S�����q�A���l�L��(��) | 600 | 2,377 |
| �@�@���q�A�����x | 5,041 | 32,279 |
| �@�@�S���ݕ��A���g���L��(��) | 1,013 | 267 |
| �@�@�ݕ��A�����x | 6,957 | 7,217 |
�@���̂��Ƃ́A���{�Ɣ�ׂāA�h�C�c�̗��q�S�������������ɒu����Ă��邱�Ƃf���Ă���Ƃ�������B���{�ł́A�{�B�̓����A���É��A���ɖ�6100���l�A�܂���{�̑��l���̔��������Z���Ă���A���ɐl�����W�����Ă����ԂŁA���q�S���ɂƂ��Ă͗��z�I�Ƃ������邪�A�h�C�c�ł͓s�s�ߍx�ɂ����镪�U�I�ȏZ��݂��s���Ă������߂ɁA��s�s��l���̑����n��ł����A�l���W���x�͓��{��菬�����A���q�S���ɂ͌����Ȃ��\���ɂȂ��Ă����̂ł���(�����N, 1999)�B���̌��ʃh�C�c�ł́A�s�s���ł�DB�̋ߋ������q�A���̎����̓R�X�g��7�����J�o�[����ɂ������A����ȊO�̒n���Ɏ����ẮADB�̎����ł̓R�X�g��1�`2�������J�o�[���Ă��Ȃ������Ƃ�����(��, 1994)�B
�@�������āA���̂܂܂ł́ADB�����DR�̍��́A1994�N�ɂ�700���}���N(��5.2���~)�ɒB���A����ɂ��̌�10�N��3,800���}���N(��28���~)�ȏ�ɒB����ł��낤�Ƃ��������݂̒��ŁA�S�����v[33]�����{���ꂽ�̂ł���(�^�A��, 1996)�B�����ŁA�h�C�c�̓S�����v�̃v���Z�X��DBAG���g�̐������x�[�X�ɁA�x(1994)�A��(1994)�A����(1996)�A�Z�c(1998)�A�P�X�^�E��(2000)�œ��t�����Ȃ��琮������ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@1990�N10���̃h�C�c�����O�ɂ��āA1989�N2��1���ɂ́A���h�C�c���{�����C�j�V�A�`�u���Ƃ��āA�����Ɨ��̈ψ���Ƃ��ĘA�M�S�����{�ψ���(RKB: Regierungskommission Bundesbahn)�̐ݒu�����߂Ă���BRKB��1991�N6��21���ɒ��ԕ����A1991�N12��21���ɍŏI����A�M��ʑ�b�ɒ�o���Ă���(����, 1996, p.224)�B
�@�����āA1993�N12���Ƀh�C�c�̓S�����v�@�Ă͐������A��{�@(���@)�ƓS���@�������ɂȂ����B������āA��1994�N1���ɓS�����v�̑��i�K���n�܂�A�����h�C�c�A�M�S��DB�Ƌ����h�C�c�鍑�S��DR �̓������s��ꂽ�B���̏����́A�܂�1994�N1��1���ɓ��ʍ��Y[34]DB��DR��P��̓��ʍ��Y�A�A�M�S�����Y(BEV: Bundeseisenbahnvermogens)�ɕғ�����B������1��5���ɂ́A�S�z�A�M���{�o���̃h�C�c�S���������(DBAG: Die Deutsche Bahnen Aktien Gesellschaft)��o�L���āABEV�̊�ƕ��������B�܂������S�������Ă����s������̂����A�S���̊ēE�F�Ȃǂ̍����I�C�������ĘA�M�S����(EBA: Eisenbahn-Bundesamt)��ݗ�����B���������āA�A�M�S�����YBEV�ɂ́ADBAG��EBA�Ɍp������Ȃ��E���A���A�s���Y���c�邱�ƂɂȂ�A���̊Ǘ����s�����Ƃ��d���ƂȂ����B�܂�A
�@�@�@DB+DR �� BEV+EBA+DBAG
�ƂȂ����̂ł���B
�@DBAG�AEBA�ABEV�ɂ��đ����⑫��������ƁA�܂�DBAG�͓S�����Ǝ҂ł���B���̓����́A����ɒʘH����ƗA������ɑg�D��̏㉺����(organisational separation)���}���Ă����B�ʘH����͎Љ�{����S�����H�̈ێ��Ǘ��Ƃ������ƓI�ȔC����^�����Ă���B����ɑ��ė��q�A������E�ݕ��A������́A���ꂼ��v���t�B�b�g�E�Z���^�[�Ƃ��ċ@�\���邱�ƂɂȂ����B
�@�A�M��ʏȂ̊O�ǂƂ��Ĉʒu�t�����Ă���A�M�S����(EBA)�̎�v�ȔC���́A�V�������݂������̂��܂߂ēS���{�݂̊ē���ь������s���A�Z�p�����ɒB���Ă��邱�Ƃ�ۏ��邱�Ƃɂ��顂܂�EBA��DBAG�̐��H�̎g�p�Ɋւ����O�҂ւ̖Ƌ��̌�t���S�����Ă���(�P�X�^�E��, 2000)��S�����݂ɂ��������������̓I�Ɍ����A��q����悤�ɁA�A�M���{�̕⏕���E�����q�ݕt����z�����A�V�����݁E���ǍH���̎{�H�Ǘ����s���ē����ł���Ƃ�����B
�@DBAG��EBA�Ɍp������Ȃ��E���A���A�s���Y���c���ꂽ�A�M�S�����Y�@�\(BEV)�́A1993�N���Ŗ�660���}���N(��4.9���~)�̗ݐύ�[35]�Ƌ��ɁADBAG�̉c�Ə�s�v�ȕs���Y�����p�����邱�ƂɂȂ���[36]�BBEV�����p�����ߋ����͘A�M���{���������̐ӔC���A���̏��ҍ����Ƃ��ẮA��ʍ����x�o[37]�̂ق�BEV�̕s���Y�̔��p�����Ă邱�Ƃ��v�悳��Ă����B
�@���̂���BEV�͓��{�̍��S���Z���ƒc�Ɨގ������g�D�ł���(��, 1994)�Ƃ����Ă������A��ŏڂ����_����悤�ɁA������(Beamte)�����ׂĈ������Ƃ����_�ŁA�傫�ȈႢ������B�����E���E�J���E���͒���DBAG�Ɉڍs���邪�A�������͑S����BEV�Ɉٓ����ABEV����DBAG�ɏo������`���Ƃ�B���̌������̋��^��BEV���x�����ADBAG�͂��̋��^��90%�S���邱�ƂɂȂ�B�������̔N����������ȊO�̐E���ɑ���t���N��������BEV�������A�ŏI�I�ɂ͘A�M���{�����S���邱�ƂƂȂ���(��, 1994)�BBEV�͂�������U����^���ɂ���A�u�A�M�̓S���̍����ƐV�Ґ��Ɋւ���@���v(Gesetz zur Zusammenfuhrungund Neugliederung der Bundeseisenbahnen) [38]�ł́A�������2004�N�܂ł�BEV�����U�����錠�����A�M���{�ɗ^�����Ă���B���������āA2004�N�܂łɂ͉��U�̐���̌������s���邾�낤�B
�@1997�N12��4���A1998�N12��2���ɂ��ꂼ��DBAG�̎������J����A��2�i�K�����肵�A1999�N1��1���ɑ�2�i�K���n�܂����B��2�i�K�ł́ADBAG�͎�����ЂƂȂ�A���ƕ��������5�Ђɕ��Љ������B
�@�����̉�Ђ͌��݁uDB�O���[�v�v(DB (Deutsche Bahn) Gruppe: �h�C�c�S���O���[�v)�Ƒ��̂���Ă���B�����ADBAG�̗��q�A��������������E�ߋ����ɕ����邩�ǂ��������ɂȂ������A���ǁA�A�ƇB�ɕ����邱�ƂɂȂ����B�܂��ADBAG�̒ʘH���傪�����ꂽ�C�ƇD�͓����̌v��ł͓S�����H���Ɗ�����ЂƂ��Ĉ�̉�ЂɂȂ�͂����������ADBAG���C�������邱�Ƃ����߂Ă���B�����̊�����Ђ̓o�L���1999�N7��1��������͂��邱�ƂɂȂ����B�����5�Ђ̂����ADB Netz�͂�����ȑ��݂ŁA���̉�Ђ�������100%���p���Ă��\��Ȃ��̂ɑ��āADB Netz�͔��p��49%�܂łƌ��߂��Ă���B
�@��������DBAG��1999�N�ɁA���ƕ����5�Ђɕ��Љ����Ď�����ЂƂȂ����킯�����A���̎�����Ђ�2002�N1��1���ɉ������邱�Ƃ��ꉞ�\�肳��Ă���B�������ABEV���U�Ƃ͈قȂ�ADBAG���U�Ɋւ���@�������ɂ͑S�B�̓��ӂ��K�v�ɂȂ�̂ŁA�����̎����A�d���͂܂��m�肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@�S�����v���������Ƃ����Ă��A���݂̃h�C�c�̗��q�S���̑̌n�́A�����h�C�c�̍��SDB (�h�C�c�A�M�S��)���ォ����ɕς�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��BDB���邢�͓S�����v���DBAG�ADB(�h�C�c�S��)�O���[�v�𒆐S�Ƃ������q�S���̑̌n�́A��܂��ɂ͕\4-2�̂悤�ɐ����ł���[39]�B
�\4-2. �h�C�c�̗��q�S���̑̌n
| �^�c | ���� ���� | �T�[�r�X���e | |
|---|---|---|---|
| �C���^�[�V�e�B �G�N�X�v���X (ICE: InterCity Express) | DB | �K�v | 1991�N6������c�Ƃ��J�n�����ō�����280km�́u�V�����v�B �������AICE��p���ȊO�ł́AIC/EC�Ɠ��l�ɉ^�s�����B |
| �C���^�[�V�e�B (IC: InterCity) | DB | �K�v | �����̎�v�s�s�Ԃ����ԓ��}�B1�`2���ԊԊu�Œ莞�Ɋe�w�� �o������B |
| �I�C���V�e�B (EC: EuroCity) | DB | �K�v | �������z���ĉ^�s����鍑�ۗ�ԂŁA�h�C�c�����ł̓C���^�[ �V�e�B�Ɠ��l�Ɉ����A�����_�C���ʼn^�s�����B |
| �C���^�[���M�I (IR: InterRegio) | DB | �K�v | �C���^�[�V�e�B�Ԃ̌��Ԃ߂Ēn��Ԃ𑖂�}�s�B���悻 2���ԊԊu�ŏo���B |
| �V���l���c�[�N (D: Schnellzyg) | DB | �K�v | �n���̈�艻�Ǝԗ��̋ߑ㉻�ƂƂ��ɃC���^�[���M�I�ɒu�� ����������B |
| �V���^�b�g �G�N�X�v���X (SE: Stadt Express) | DB | �s�v | ��v�w�ɂ̂ݒ�Ԃ�������B�]���̉����A�C���c�[�N(Eilzug) �ɒu�������ē������i�ށB�����ɓ������āA�n���E�I���n�� �K�肵�ĉ^�s�n�������ɂ��A���S��1���ԊԊu�̉^�s�Ƃ����B |
| S�o�[�� (S-Bahn) | DB | �s�v | �����d�̂悤�ȓs�s�S���Ŋe�w��Ԃ������B���M�I�i���o�[�� (RB: Regional Bahn)��S�o�[�������i��ł���B |
| U�o�[�� (U-Bahn) | ���c | ��{�I�ɒn���S�����A�s�S���ł͒n���A�x�O���ł͐�p�O�� (DB�ȊO)�ŗ��҂���̘H���Ƃ��ĉ^�s����Ă���ꍇ���قƂ�ǁB | |
| �H�ʓd�� (Strasenbahn) | ���c | �s�S���̂ݒn���𑖂��Ă���ꍇ�����邪�A���̏ꍇ���n���S �ɂ͕��ނ��Ȃ��B |
�@�����h�C�c�ł́A��q����悤�Ɋe��v�s�s���ɂ͋ߋ������q�A����S�������ʎ��Ǝ҂ɂ��^�A�A�����ݗ�����Ă���ADB�̃V���^�b�g�G�N�X�v���X��S�o�[��������ɑg�ݍ��܂�Ă����B�����āA������v�s�s���̊Ԃ����Ԍ`�ŁADB��ICE�AIC/EC�A�C���^�[���M�I�A�V���^�b�g�G�N�X�v���X�Ȃǂ��A�������1�Ȃ���2���ԊԊu�ʼn^�s����Ă���̂ł���[40]�B
�@�S�����v�O����i�s���Ă����V���^�b�g�G�N�X�v���X���AS�o�[�����ɂ́A�����������Ԋu�^�s�̎����Ɠ����ɁA��Ԃ̎ԑ̂̎��̌���Ƃ����Ӗ������߂��Ă��邱�Ƃɂ͒��ӂ�����B���́A���̂��Ƃ��������Ă���悤�ɁA�h�C�c�ł́A�S�����v�ŏ㉺�������X�^�[�g����ȑO����AICE�AIC/EC�A�C���^�[���M�I�A�V���^�b�g�G�N�X�v���X�AS�o�[�����͏��i���������̂ł�����[41]�A�H�����ł͂Ȃ������̂ł���B��Ԃ̎ԑ̖̂��̂Ƃ������������m��������Ȃ��B
�@�Ⴆ�A�h�C�c�́u�V�����v�ƌĂ��ICE�́A���{�̐V�����̂悤�ɁA�ݗ����Ƃ͕ʂɌ��݂��ꂽ�V���𑖂��Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�������V���������ő����Ă���ꍇ�����邪�A��O�����ICE�ł���ICE3�����邱�Ƃ��\�肳��Ă���P�������t�����N�t���g�ԂɌ��ݒ��̘H��[42]�́AICE3��p���ł͂�����̂́A�H�����̂ɂ͓��{�́u���C���V�����v�̂悤�Ȗ��O�͕t�����Ă��Ȃ�[43]�B���́A���݂��P�������t�����N�t���g�Ԃ̃��C���쉈���̘H��(���{���Ɍ����ݗ���)��ICE�́u�ԑ́v�������Ă��邪�AIC/EC�Ɠ������v���Ԃʼn^�s����Ă��顂ɂ�����炸�A�ԑ̂�ICE�Ȃ̂�ICE�ƌĂ�ł��āA�^����IC/EC�Ɣ�ׂĊ����Ȃ̂ł���B
�@���̂悤�ɋ����h�C�c�ł́A�S�����v�̂����ƈȑO����A�H���Ƃ͓Ɨ��������i�������݂��A��������v�s�s���ɂ�����ߋ������q�S���Ɖ��������q�S���Ƃ͋�ʂ���āA���ꂼ��ʂ̕������ő̌n�����s���Ă����B����ɉݕ��A���́A��������Ƃ͑̌n���قȂ�B�S�����v�̑��i�K�A���i�K�ŐV���x�╪�Љ��Ƃ��Č��݉��������̂́A�S�����v�ɂ���ēˑR�o�������킯�ł͂Ȃ��̂ł���B�����ŁA���̂悤�ȓS���̑̌n���ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������A�����Ă��ꂪ�S�����v�ɂ���Ăǂ̂悤�ɕω����Ă����̂������Ă݂悤�B
�@���h�C�c�ł�1960�N��ɋc�_�������āA���������鎩���ԂɑΉ����āA�K�v�ƂȂ铹�H��n������葱���Ă������Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA���H������H�ւƌ�ʂ̏d�S���ڂ��Ă������Ƃ����߂�ꂽ�B���̂Ƃ�1967�N�Ɂu�s�s��ʉ��P�����@�v(GVFG)���ł��āA���łł���z���ł������グ�A���̕����ߋ�����ʂ̌��݂ɓ��Ă邱�Ƃ����߂�ꂽ�B���̍����ŁAS�o�[���AU�o�[���A�H�ʓd�Ԃ̌��ݔ��60%���d���A�c���40%���B���{�ƒn�������̂����S���邱�Ƃ����@�ɒ�߂��Ă���B�����āA�Ⴆ��S�o�[���ɂ��邩U�o�[���ɂ��邩�́A�R�X�g�v�Z���s���āA�L���ȕ���I�����邱�Ƃɂ����̂ł���B
�@���������̈���ŁAS�o�[���H��������DB�̋ߋ����H���A�܂�n�����͔p�~���i��ł������B1970�N�`1990�N�̗v�ł́A���q�ł�5684km�A�ݕ��ł�3244km���p�~����Ă���B���������Ԏ��n������p�~���A�d�_����v�s�s���̐l���f���n����ł̋ߋ������q�A���Ƃ����̊Ԃ����ԉ��������q�A���Ɉڂ��Ƃ����l������1983�N11��23���̘A�M���{�K�C�h���C���ɂ�菳�F���ꂽ�o�c�헪DB�f90�ł��咣����Ă���(����, 1996, pp.155-159)�B����ł����v���O�ɂ́A�ߋ������q�S���ɂ�����R�X�g��100%�Ƃ���ƁA������65%���x�����Ȃ����悤�ȐԎ���ԂɊׂ��Ă����Ƃ�������[45]�B
�@��v�s�s���̋ߋ������q�A���̏d���Ƃ����_�ŁA1967�N��GVFG�Ƃقړ������ɃX�^�[�g�����̂��^�A�A���ł���B�^�A�A��(Verkehrsverbund)�Ƃ́A�����̎����̂���\���������n����̓s�s��ʂ���薣�͓I�Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɁA���̒n��Ɋ܂܂��S���A�o�X�̎��Ǝ҂��A���ʉ^���̐ݒ�A�^�s�v��̒����A�ꕔ�̕⏕���̓S�����Ǝғ��ւ̔z�������s���@�\�ŁA�L����Ђ̌`�Ԃ��Ƃ��Ă���B1966�N�ȍ~�A�n���u���N�A�~�����w���A�t�����N�t���g[46]�A�V���c�b�g�K���g�A���C�������[��(���[���H�ƒn��)�A���C�����W�[�N(�{���A�P����)�A�j�������x���N�A���C�����l�b�J�[(�}���n�C���A�n�C�f���x���N)�Ƃ������K�͂̑傫���s�s�𒆐S�Ƃ����s�s���ʼn^�A�A������������(��, 1994; �Z�c, 1998)�B
�@�^�A�A���́A���̂悤�ȓ����������Ă���(�y�J, 1997)
�@����ɁA�����\�̕Ґ��ɂ��ẮA���������Ԋu�����\(ITF; Integraler Taktfahrplan)�����A���ׂĂ̘H���ɂ��āA�������������A�Ⴆ��5���A20���A35���A50���ɗ�Ԃ��^�s����悤�ɓ��ꂷ�邱�Ƃ��i��ł���(�P�X�^�E��, 2000, p.40)��^�A�A���́A���Ƃ��Ɛ��h�C�c�Ŕ��B���Ă������̂����A�h�C�c�����́A��s�x�������ł�1997�N�Ƀx�������^�A�A�����ݗ�����Ă���(�Z�c, 1998)�B
�@�^�A�A���ݗ��̓����́A�h�C�c�̓S�����v�ɂ���Ă���ɉ��������B�S�����v�ɂƂ��Ȃ��āA�����ߋ������q�A���̈ꕔ�ł���u�ߋ����S�����q�A���v�̉^�c�ӔC���n������������A������B�ւƈڊǂ��ꂽ���Ƃʼn^�A�A�����}�����A�ߋ������q�A���̒����Ɋ֘A�����Ђ́A�^�A������(Verkehrsgemainschaft)�Ȃǂ��܂߂āA1997�N6�����݂܂ł�59�Аݗ�����Ă���(�P�X�^�E��, 2000, p.38)�B�܂��t�����N�t���g(�w�b�Z���B)�ł́A���Ƀt�����N�t���g�^�A�A�������݂��Ă������A�w�b�Z���B�̏B�s�r�[�X�o�[�f�����܂ޓs�s���S�̂��T�[�r�X�̑ΏۂƂ���悤�ɁA���C���E�}�C���L��^�A�A���ւƍL�扻����Ă���(��, 1994)�B
�@��������1970�N��ɂ�����^�A�A�����x�̔��B��A1980�N��ɂ�����S�o�[���̒������H������̕����ɒn�����{�����͂������Ƃ́ADB��n��̌�ʌv��ɑg�ݍ��ނ��߂̍����Ƃ�������(��, 1994)�B��������DB��S�o�[���A�V���^�b�g�G�N�X�v���X�͉^�A�A���̒��ɑg�ݍ��܂�Ă������B�]���A�h�C�c�̓S�����v�̏Љ�ł͏㉺�������肪��������Ă������A���́A�ߋ����Ɋւ��ẮA������������܂ł̃h�C�c�̌�ʐ���̗��ꂪ����A�㉺�����Ƃ͕ʂ̕��������_�Ԍ�����̂ł���B
�@�Ⴆ�A�x��������S�o�[���ɂ��ẮADBAG��100%�q��ЂƂ��Đݗ����ꂽ�x������S�o�[���L�����(S-Bahn Berlin GmbH)���A�S�����v���1995�N1��1������^�c���Ă���(�Z�c, 1998)�B����͓S�����v���i�K�ȍ~��DB Regio�̎q��ЂƂȂ�A�㉺���������Ɉ�̂Ƃ��Čo�c����Ă���B���������[�u�̓x�����������̗�O�[�u�ł͂Ȃ��B�n���u���N�ł��n���u���NS�o�[���L�����(S-Bahn Hamburg GmbH)���ݗ�����ADB Regio��100%�q��ЂƂȂ��Ă���BDBAG�Ƃ��ẮAS�o�[���ɂ��ẮA���H�E�w�Ƃ������C���t�������������ɁA��̉�ЂƂ��Čo�c����K�v������ƍl���Ă��āADB Netz�����̍l�������L���Ă���B���̂��߁ADB Regio�͏����I�ɂ͂��������n�悲�ƂɁA�㉺��̉�����S�o�[���̎q��Ђ����X�ƕ����E�ݗ����Ă����\��������B
�@1994�N�̓S�����v�ɂ��AICE�̂悤�ȉ���������A�����ĉݕ�����ɑ��ẮA��؏����͂��Ȃ����ƂɂȂ����B����ɑ��ċߋ�������ւ̏����͑������A���̐ӔC�͏B���{�Ɉڊǂ���邱�ƂɂȂ����B���������S���ߋ������q�A���̒ӔC�ƍ����ӔC���B�⎩���̂Ȃǂ̒n��c�̂Ɉڊǂ��邱�Ƃ͒n�扻�ƌĂ�AEC�̗�����(EEC)�K��No.1893/91�̒�Ăɉ��������e�ł�����(����, 1996, p.245)�B
�@�h�C�c�̏ꍇ�A��������EC�̓������d�v�ȗv���ł���B�k��A1958�N1��1�������̃��[���b�p�o�ϋ�����(EEC: European Economic Community)�̐ݗ����ɂ���āA�A���T�[�r�X�̂��߂̋K���𐧒肷�邱�Ƃ��K�肳�ꂽ�B�����ŋK���Ƃ́A�S���͂������A���ׂẲ������ɓK�p�������̂��w���Ă���B���̌�1967�N7��1���ɔ����������[���b�p������(EC: European Community)�̗�����(EEC)�ł́A���ۂɁA���ʉ^�A�{����������邽�߂̑O��������Ƃ��āA1969�N���玟�̂悤�ȋK�������肳��Ă���(�Z�c, 1998)�B
�@���́A���ɐ��h�C�c�ł͂���ȑO��1961�N����A�����I�����^�����啝�ȐԎ��ݏo���Ă���Ƃ��āA���ʂȎZ���Ȃ��ɖ��N1.2�`1.7���}���N���A�M���{����x�����Ă���A1967�N�ɂ͎Z���m�ɂ��āu�Љ���I�����^���ɂ�闷�q�A���̌o���U�̂��߂̐��o���v�Ƃ������̂ɂȂ��Ă����B�������A���̋��o���͇@EEC�K��No. 1191/69�ɂ���āA1970�N��1971�N�ɂ�8.9���}���N�܂ő��z����A1972�N����́u�S���ߋ������q�A���̕⏞�v�Ƃ������ڂɂȂ��āA�ߋ������q�S���S�̂��⏞�̑ΏۂƂ��ꂽ�̂ł���B���̊z�́A1981�N��32.8���}���N�A1991�N��36.6���}���N�ɂ��Ȃ�ADB�ɑ���A�M���{�̏������z�̂��ꂼ��28%�A31%���߂Ă���(��, 1994)�B
�@�������A1994�N�̓S�����v���i�K�ł́A�^�A�A���ɂ�����Ԏ��E�����̕�U�̎d���͕��G�Ȃ܂܂ł������BS�o�[�����ɂ��Ă͘A�M���{���Ԏ���U�����AU�o�[���A�H�ʓd�ԂƂ��������c��ʊ�Ƃɂ��Ă͌S�E�s�������Ԏ���U�����A�^�A�A�������ɂ���Ĕ�������R�X�g�ɂ��Ă͏B���{�����S���邱�ƂɂȂ��Ă���(��, 1994)�B
�@1996�N1��1���ɋߋ������q�S���̉^�c�ӔC���A������B�Ɉڊǂ���Ă���A����Ӗ��ŐԎ���U�̎d���̓V���v���ɂȂ����B�ڊǂɂƂ��Ȃ��A�Ԏ���U�̐ӔC���A�M���{����B���{�Ɉڂ�A�B���{��DBAG�̌_��ɂ���āAS�o�[���̉c�Ɣ�p�ɑ���^�������̕s�����ɑ��āA�B���{���������邱�ƂɂȂ���[47]�B
�@�������A�^�c�ӔC���A�M���{����B���{�Ɉڊǂ��ꂽ�Ƃ����Ă��A���ǂ͘A�M���{�������̃o�b�N�A�b�v���Ă���A���̓�̍������p�ӂ��ꂽ(��, 1994)�B
���̊z��1999�N�ŔN��120���}���N���x�ɂȂ��Ă���[48]�B
�@�܂��B���{�ւ̈ڊǂɂ��A�ߋ������q�S���̐Ԏ��H����p�~���邩�ǂ����̍ŏI���茠���n���Ɉڂ������ƂɂȂ�B���ɃI�y���[�V�����̉�Ђ��Ԏ��œP�ނ��Ă��܂����ꍇ(���ɂ��������P�[�X�͂���)�A���D�ɂ���ĐV���ȃI�y���[�V�����̉�Ђ��邱�ƂɂȂ邪�A����ł�������Ȃ������ꍇ�ɂ́A�H���p�~�Ƃ������Ƃ��z�肳��Ă���B
�@�ߋ������q�A���Ƃ͑ΏƓI�ɁA1994�N�̓S�����v�ȗ��A���������q�Ɖݕ��ɑ��ẮA��ؐԎ��E������U���s��Ȃ����ƂɂȂ����B�������A�㉺�������s��ꂽ�̂ł���B���������S�����v���̕������́A���[���b�p�S�̂̓S���ԍ\�z�̒��ōl�����Ă������̂ł���B
�@���ɋߋ������q�S���̂Ƃ���ŁA���[���b�p������(EC)�Ő��肵���K���ɂ���āADB�ւ̕⏕�̌`���Ɗz���ς�������Ƃ��q�ׂ����A�O�q�̘A�M�S�����{�ψ���(RKB)�̍ŏI��(1991�N12��21��)�ɂ́u�ψ���́A���v�Ă�EC�̌�ʐ���̓W�J��e��̎w�߂ƍ��v����悤�ɂȂ邱�Ƃ��d�������v�Əq�ׂ��Ă���(����, 1996, p.231)�B���̉��v�ẮA���N6��20�����\��EC������(EEC)�K��No.1893/91[49]�A���N7��29�����\��EC������w��(91/440/EEC)�Ɣ�r����ƁA���ԕ��̔��\������1991�N6��21���Ƃقړ����Ƃ��������ł͂Ȃ��A���e�I�ɂ��قړ���ŁAEC�̗�����w�߁E�K���͉��v�Ăɍ�����^�����Ƃ�����(����, 1996, pp.224-226)�B
�@���Ɍ�ҁA�u�����̂̓S���̔��W�Ɋւ���t��������w�߁v(91/440/EEC)�͓S���Ɋւ���w��[50]�ōł��d�v�Ȃ��̂��Ƃ����A���̎w�߂̒��ł́A
���K�肳��Ă���(�Z�c, 1998)�B
�@���̂����A2�ł����S���^�����ƂƓS�����H���Ƃ̌o�c�̕����́A���{�́u�S�����Ɩ@�v�ɋK�肷�����S�����ƂƑ�O��S�����Ƃ̂悤�ȊT�O�ɑ���������̂̕������Ӗ����Ă���(�Z�c, 1998)�B�܂��o�c��������@�Ƃ��āA��v�݂̂̕���(��v����; separation of accounts)�A����S�����Ǝғ��ɂ�����g�D�̕���(�g�D����; organizational separation)�A�S�����ƌo�c���̂�ʁX�̓S�����Ǝ҂ɕ����镪��(���x����; institutional separation)������A��v�����͕K�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���(�x, 1996; �Z�c, 1998)�B��v�����Ƃ́A�S����Ɖ�v��A������ƒʘH�����2����̉�v�P�ʂɋ敪���Ď������̂ŁADB�ɂ����ẮA�o�c���v�̎��݂̈�Ƃ��āA����1980�N�ȍ~�́w�c�ƕ��x�ŁA�敪��v(Trennungsrechnung)�Ƃ��Ď����I�ɍ̗p����Ă���(����, 1996, p.153; �x, 1996)�B
�@��ʂɂ�����㉺�����́A����(1989)�ɂ��A���H��q��A�C�^�Ȃǂ̂悤�ɒʘH�{�݂̌��݂Ƃ��̗��p����������邱�Ƃ��w���Ă���BEC�ł́A�C���t���Ǘ��ƗA�����Ƃ̕���(separation between infrastructure management and transport operation)�Ƃ��Ă��(����, 1996, pp.38-39)�B�����ăh�C�c�ł́A�㉺�����Ƃ́A�S�����H��ۗL���A���̈ێ��Ǘ����s���u�ʘH��́v�ƓS���A�����Ƃ݂̂��ƂƂ���u�A����́v�ƂɓS�����Ǝ҂����邱�Ƃ������B
�@���͐��h�C�c�ł́A���Ȃ葁���i�K����㉺�����Ɋ֘A�����c�_���J��Ԃ���Ă�����S���̒ʘH��S���ߏd�ł���Ƃ����c�_���ʋ@�֊Ԃ̒ʘH��S�̌����������߂�c�_�́A1961�N�̌�ʉ��v(Verkehrsreform)��1967�N��Leber�A�M��ʑ�b�����\�������[�o�[�E�v�����ł����ɍs���Ă���(�P�X�^�E��, 2000, pp.15-17)�����ɁA1979�N�ɂ͘A�M���{�����H(Fahrweg)�Ɨ�ԉ^�s(Betrieb)�̕����`�Ԃɂ��Ă̌������ʂ���A��I�Ȗ@�������̕K�v������{�͍���Ƃ������̂́A���ɐG�ꂽ�悤��DB���g��1980�N�ȍ~�́w�c�ƕ��x��3�̈�ɕ������敪��v�ő��v�v�Z���s���A��ƌo�ϓI�̈�ł͗��v�������Ă��邱�Ƃ������A�����A���ƓI�̈�(�ʘH)�ƌ����o�ϓI�̈�(�����T�[�r�X�`��)�ɂ��ẮA�A�M���{��n�������̂ɂ�銮�S�ȕ⏞�����߂��̂ł���(�P�X�^�E��, 2000, p.19)�
�@�������A�S�����v�̒i�K�őł��o���ꂽ���������q�Ɖݕ��ɂ��Ă̏㉺�����́A����Ƀ��[���b�p�S�̂̓S���ԍ\�z���w�i�ɂ��������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ�����Ȃ킿�A�㉺�����͓��Y�ʘH�ɑ��鏊�L���Ȃ����x�z����A����̂���ړ]���邱�ƂɂȂ�̂ŁA���H�̃��[�U�[����͗��p�x�ɉ��������H�g�p�������邱�ƂŁA���ʓI�ɂ́A�@�I�ɑ�O�҂��鎖�Ǝ҂ɂ����H���J�����A���Y���H�ɂ�����S���A�����Ƃւ̎Q����F�߂�I�[�v���E�l�b�g���[�N�����ւƂȂ���B�������邱�ƂŁA�O���Ђ̓S�����Ǝ҂ł����Ă��A���Y���ɂ����ĉc�Ɗ������\�ɂȂ�̂ł���(�x, 1994; 1996)�B����́A��茻���I�ɂ́A���[���b�p�S�̂Ƃ��Ă̓S���A���ԁA���ɍ����S���Ԃ��\�z���Ă̐��ƍl������B�����A�㉺������ł��o�����O�q�́u�����̂̓S���̔��W�Ɋւ���t��������w�߁v(91/440/EEC)��1991�N7���ɏo���ꂽ���A���̑O��1991�N6���ɂ̓h�C�c��ICE�̉c�Ɖ^�]���J�n����Ă���[51]�B�����Ă��̔��N�O��1990�N12���ɂ́uEC�̃��[���b�p�����S���Ԍv��v��EC�t��������ŏ��F����Ă���B�܂�A���������@�^���n����������EC�w�߂��K�肳��Ă���̂ł���B
�@���̌�A1993�N11��1���Ƀ}�[�X�g���q�g��������āAEC�����[���b�p�A��EU (European Union)�ƂȂ�A1995�N�ɂ̓I�[�X�g���A�A�t�B�������h�A�X�E�F�[�f����������������������15�J���̐��ɂȂ邱�Ƃ���A�O�q�̍����S���Ԍv��ɂ͌����C�����������A1995�N1���ɂ́u���[���b�p�����S���Ԍv��v���܂Ƃ܂��Ă���B�����ł�2010�N��ڕW�N���Ƃ��āA12,500km�̍����V���̌���(�ō�����250km�ȏ�)�A14,000km�̍ݗ����̉���(�ō�����200km�ȏ�)�A2,500km�̑��ݘA�����̌��݂܂��͉��ǂ��������Ă���(�Z�c, 1998)�B
�@�������A������EC�w�߂��������Ƃ͂����A�����āA�ȑO��胈�[���b�p�̍��X�̊ԂŁA�����͓S�����ꏏ�ɂ�낤�Ƃ����b���������Ƃ͂����A�h�C�c���㉺�������s���ADB Netz���g�p��������悤�ɂȂ������Ƃɑ��ẮA���̍��̍��S����ᔻ���o�Ă���Ƃ�������BEC�w�߂̓K�C�h���C���Ƃ��������x�[�V�b�N�E���C���Ƃł��ĂԂׂ����x�̂��̂Ȃ̂ŁA����Ȃ鍇�ӂ����߂āA1999�N���݁A�u�����b�Z���̈ψ���Ő��H�̎g�p���Ɋւ��錟�����n�܂��Ă���[52]�B���������ɂ���ēS���̌o�c���e���قȂ�A���c���̃��x�����قȂ�A�����EU�����Ŋe���̕��z�����炷���߂ɁA�S���ւ̏������팸���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ȂǁAEU�S�̂ł̏㉺�������߂����Ă͂܂��܂��������ׂ���肪�����B
�@�������������S���Ԍv��̂悤�ɖ��邳�̌����闷�q�S���ɔ�ׂāA�ݕ��͓S�����Ǝ҂ɂƂ��ĔY�݂̎�ł���[53]�B�������A�S���̍��ۉݕ��A���ʂ́A1975�N��120���g���L������A1985�N�ɂ�165���g���L���A1990�N�ɂ�183���g���L���Ƒ������Ă���(����, 1996, p.138)�B�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�������x�ł���B�ݕ��ɂ��ẮAEU�ł͓��H������H�ւƂ�������ł͍��ӂ��ł��Ă�����̂́A���ʂɂ��ꂼ�ꔭ�B�����̂ŁA�������x�����̂܂܂ł���B���̂��Ƃ͉��������q�ɂ��Ă����l�ł͂��邪�A����قǐ[���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���[���b�p���c�f����悤�ȉ��������q�Ƃ����̂́A�H���Ƃ��Ă͑��݂��Ă��Ă��A���ۂɂ͍q��H��������̂ŁA�S���H���̒[����[�܂ł���l�̏�q�������Ə�葱���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ�����ł���B�������A�ݕ��̏ꍇ�ɂ͂��ꂪ���肤��B�����Ńh�C�c���{�́A�ݕ��ɂ��Ă�EU�S�̂�1�ЂƂ��āA��̃^���t��EU�S�̂̉ݕ��A�����s�����Ƃ��Ă��Ă���[54]�B
�@�A�M�S�����Y(BEV)�ɂ��ẮA�]���A���{�̍��S���Z���ƒc�Ƃ̑Δ�ŁA���̏�������������Ă����B�����ABEV���������́A����N�X�ԍς���̂�BEV�̎d���ɂȂ��Ă����B���h�C�c���SDB�ɂ͌��s���č��������ȗL���q��������[55]�A1994�N�̓S�����v�̍ہABEV�������p�������̑��z��660���}���N�A���̎x�������͔N��50���}���N�ɂ��Ȃ��Ă����̂ł���B�������A�s���Y�p���邱�Ƃŕ���ԍς���Ƃ����A�C�f�A�͔��I�ł������B�Ⴆ��1998�N��BEV�̑�����250���}���N�̂����A�s���Y���p�ɂ������́A������14���}���N�����Ȃ��B����ł́A���̔N�̎x������50���}���N�����Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�����1994�N�A1995�N��BEV�͒P�Ƃ�200���}���N����s�ؓ����Ƃ��Ē��B�������̂́A�A�M���{�����������BEV���P�ƂŎ�������������������A��v�����@�̃A�h�o�C�X��������[56]�A1996�N�A1997�N�͘A�M���{�Ƌ����Ŏ����邱�ƂɂȂ����B�������s���Y���p�������x�ł͏Ă��ɐ��ŁA�ԍς͓���A���̊z�͑��������A1998�N����780���}���N�ɖc���ł����B�������ēS�����v�̑��i�K�ŁABEV�͕��ԍς̔C��������A����BEV����A�M���{�Ɉڂ��ꂽ�̂ł���B
�@����ł́ABEV�̖����͏I������̂ł��낤���B���́A�d�v�Ȗ������c���Ă����B�S�����Ƃ��������@(offentlichen Dienstrechts)�̐��������āA�������I�ł�苣���͂̂���S���ɂ��āA�S���̌�ʎ��v�𑝂₷���Ƃł���[57]�B���́A�S�����v�O�ADB�E���̐g���ɂ́A������(Beamte)�Ǝ����E���E�J���E��(Arbeiter)��2��ނ�������[58]�B�S�����v���O��1993�N���ł�DB�̐E������21��7725�l���������A���̂�������12��4447�l�A57.2%���������������̂ł���(����, 1996, p.227)�����́A�����E���E�J���E���Ɣ�ׂāA�������̕��������Ȏd�������Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���j�I�Ȍo�܂���A�Ⴆ�Ήݕ��A���ȂǂŃX�g���C�L���̂Ȃ���������z�u����K�v�̂������|�W�V�����ɂ͌��������̗p���ꂽ�̂ł���[59]�B
�@BEV��1994�N1��1���ɖ�11��5,000�l�̌������ɑ��鋋�^�x���ƁA24���l�ȏ�̔N���҂ɑ���N�����t�������p���Ŕ������Ă���[60]�B����́A���̒����DBAG�������ݗ����ꂽ��ł��ς��Ȃ��BEV�ň���������������͏�����BEV�ł��邪�A���ۂɂ�DBAG(1999�N�ȍ~��DB�O���[�v)�œ����Ă���[61]�B��������������V�K�ɍ̗p���邱�Ƃ́A���͂�s���Ȃ���S�����v�O�܂łɍ̗p���Ă��܂���������������BEV �����DBAG�ADB�O���[�v�ɑ��݂��邱�ƂɂȂ題������̏��i����DBAG�����o���ꂽ�����Ɋ�Â���BEV�̐l����(�������̂́u��ꕔ(Abteilung 1)�v)�����߂Ă���B�������̋��^�̌n�͘A�M���{�̌������Ɠ����ł���B�������̋��^��BEV����x�����邪�A���̂���90%��DBAG��BEV�Ɏx�����Ă���B���Ȃ킿�ADBAG��10%�������������ق��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@BEV����������֎x�����鋋�^�̔N�ԑ��z�́A1998�N�Ŗ�50���}���N�ɂȂ�B�����1998�N�ɂ́A�ސE������������24��3000�l�ɖ�80���}���N�̔N�����A�⑰�ɂ͖�20���}���N�̔N����BEV����x�����Ă���B���������������W�̎x�o�͔���ł���B1998�N�͓S�����v���i�K���O�ŁA�܂��L���q��������Ă������A���́A�x�������͖�50���}���N�ŁA���R�ɂ��������ւ̎x�����^�z�Ƃقړ��z�ABEV�̑��x�o��250���}���N�̂���2�����x�����Ȃ������B�c��8���͌������̐l����ƔN�����ɓ��Ă��Ă����̂ł���B
�@1998�N���ł���������7��1008�l���āADBAG�̑��]�ƈ�25��2468�l[62]��28.1%���߂Ă���B�������̗̍p�́A�S�����v�̑O�N1993�N�܂ōs���Ă����̂ŁA������5���l�͂܂�50�Έȉ��ł���B���h�C�c���SDB�͂��̂悤�ɑ����̌�����������Ă������߂ɍ̎Z���A�������̓_�Ŗ��[63]���������Ƃ����A���̌������̎M�Ƃ��Ă�BEV�����ꂽ�̂ł���B
�@BEV���g�ɂ���Ă��ABEV�͌��������l�������������������ɑ��ĕۏ���@�ւ��Ƃ���Ă���[64]�B�S�����v�̑��i�K�ŕ��ԍς̔C�������ꂽ���ƂŁA����������������Ƃ��Ă�BEV�̑��݂���蕂������ɂȂ����Ƃ�������B�����ABEV�ɍŌ�܂Ŏc��d���́A�������̐l���̎d���ł���BBEV���U���������邱�ƂɂȂ��Ă���2004�N�ɂ͌�������4��5000�l���x�ɂȂ��Ă��邾�낤�B2036�N�ɂ͍Ō�̌��������ސE���A2060�N�܂łɂ͓S�����v�̊W�҂����ׂđސE���邱�ƂɂȂ�B�������A����ł����������W�̎��Ƃ�N���͌p�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������BEV�����U��������A��DB��DR�̕����������p��������d�g�ݍ������邱�Ƃ��A���݂�BEV�̏d�v�Ȗ����ł���B�Ⴆ�ADB�O���[�v�S�̂̕�������[65]�ɂ��ẮADBAG�̎����ō��c�@�l���ݗ�����ABEV�����̊Ǘ���S�����Ă���B�܂��ADB�O���[�v�̖�13���˂̎Б�����L�Ǘ����Ă���Z���Ђ��ABEV��18�Ђ����Ă��邪[66]�A���p���l���Ă���B���邢�͏]�ƈ��̂��߂ɐΒY(�����Ƒ�������)�E�Ζ��Ƃ������R���̈����ȋ������s���Ă���A�����34���l�̂���7���l(����������ł͂Ȃ�)�����p���Ă��邪�A������ł���ΓƗ������Ĕ��p��������BEV�͍l���Ă���B�܂�BEV�Ƃ��ẮA���������W�̎d���͑g�D�Ƃ��ēƗ������āA���X�ɔ��p���Ă������j�Ȃ̂ł���[67]�B�������邱�ƂŁABEV���U����A���������̃T�[�r�X�𑱂��邱�Ƃ��ł���
�@�S�����v�̍ۂ�BEV�����^���ꂽ�s���Y�̂����A�S�����ƂɕK�v�̂Ȃ��s���Y[68]�͓S���s���Y�}�l�W�����g�L�����(Eisenbahnimmobilien Management GmbH)�ɂ���ď��ƊJ�����s����B����͕K���������p���Ӗ����Ă��Ȃ��B�ނ���ĊJ���ɂ��t�����l��t���āA���݂ɏo�����Ƃ����S�ł���[69]�B���������ĊJ���ɂ���Ċm�ۂ������v�́A�����I�ɂ�BEV�����S���邱�ƂɂȂ��Ă���ސE�����������̔N���ɓ��Ă��邱�Ƃ��\�肳��Ă���BBEV���U����ADB�O���[�v�̕��������W�̎��Ƃ�N�����p���ł���悤�ɁA����BEV�̎��Ƃ͐����E�ĕҁE�Ɨ����}���Ă���A���̂��߂̍����Ƃ��ď��p���Y�̎g�������l�����Ă���B
�@�S�����v���5�N�ԂŁADBAG�͏]�ƈ����̂ق�1/4�ɂ������8���l�̍팸�ɐ������Ă��邪�A����͉��قɂ����̂ł͂Ȃ��A�Z�p�v�V�ɂ��Ԍɂ̏ȗ͉���}������A�E����g�D�̍ĕҐ��ɂ���ė]�����l���̑�����]�ސE��������A�����鎩�R���ɂ���Č��������̂��Ƃ���Ă���B���̂��ƂŁA1998�N�̏]�ƈ�1�l������̗��q�g��km�Ō������Y���́A�S�����v�O(1993�N)��94.1%���ƁA�قڔ{�ɂȂ��Ă���B
�@�������A�m���ɏ]�ƈ����̍팸�ɂ�藘�v���o��悤�ɂȂ������A�����Œ��ڂ��ׂ��́A���̓����z�����z�Ȃ��Ƃł���B���40�N�ɂ킽���āA�S���ߑ㉻�̂��߂̓�����ӂ��Ă������͏d���̂ł���B�\4-3�ł��킩��悤�ɁA1998�N��DBAG�̗��v�͑����㍂�̖�1%�ɂȂ邪�A�������z�͑����㍂�̖��ɂ��Ȃ��Ă���[70]�B�S�����v�ȍ~�A���N�̑������z�͂ق�140�`150���}���N�Ő��ڂ��Ă���B
�\4-3. �S�����v���DBAG�̌o�c�w�W�@(���z�̒P�ʂ͕S���}���N)
| 1994�N | 1995�N | 1996�N | 1997�N | 1998�N | |
|---|---|---|---|---|---|
| �����㍂ | 28,933 | 29,824 | 30,221 | 30,466 | 30,018 |
| �ň��O���v | 491 | 553 | 721 | 359 | 394 |
| �������z | 13,942 | 14,334 | 15,199 | 13,957 | 14,982 |
| �������z* | 10,822 | 9,988 | 9,889 | 12,172 | 5,946 |
| ���O�L���b�V���E�t���[ | 2,888 | 2,826 | 3,475 | 3,585 | 3,882 |
| �]�ƈ���(�N��)(�l) | 331,101 | 312,579 | 228,768 | 268,273 | 252,468 |
�@�����������z�����̍����́ADBAG�̓������ۂ����Řd����킯�ł͂Ȃ��B�h�C�c�̌��@�ł����{�@��87 e���ɁA�S�����݂͘A�M���{���⏕����Ə����Ă���قǂŁA�@���Ɋ�Â��ĘA�M���{�E�B���{�E�n�������̂����ݕ⏕���A�����Ė����q�ݕt�����o���Ă���B
�@�\4-3��1997�N��DBAG�̑������z�͂ق�140���}���N�ɂȂ邪�A���̂����A���s�H���̈ێ��A���s��Ԃ̊g�[�A�V��Ԃ̌��݁A�Ԍɂ̋ߑ㉻���̍�������ȂǂƂ�������2�i�K���DB Netz AG���NJ����邱�ƂɂȂ����悤�ȕ����̓����z��86���}���N�ɂȂ顂��̂����A�M���{����̖����q�ݕt����41���}���N�A�A�M���{�ƏB���{����̕⏕����25���}���N�̍��v66���}���N���O�ҋ@�ւ���9���}���N�A�c���11���}���N��DBAG�̓������ۂƂ������ƂɂȂ�[71]�B
�@���̂����A�M���{�̊W�����ȕ⏕���A�����q�ݕt���ɂ��ẮA�A�M��ʏȁAEBA�ADBAG�́A�������GVFG�ADBGrG�ABSchwAG�ƁA���̍����@�̗��̂ŌĂ�ł���B
�@���ɏq�ׂ��悤�ɁA�h�C�c�ł�1960�N��ɋc�_�������āA���������鎩���ԂɑΉ����āA�K�v�ƂȂ铹�H��n������葱���Ă������Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA���H������H�ւƌ�ʂ̏d�S���ڂ��Ă������Ƃ����߂�ꂽ�B1971�N�Ɂu�s�s��ʉ��P�����@�v(GVFG: Gemeindeverkerkehrsfinanzierungsgesetz)���ł��āA���łł���z���ł������グ�A���̕����ߋ�����ʂ̌��ݍ����Ƃ��邱�Ƃ����߂�ꂽ�B1999�N���݁A1���b�g��������5.4�y�j�q(��0.054�}���N)�������ƂȂ��Ă���[72]�B
�@��̓I��1998�N�̐����ł́AGVFG�̍�����32��8000���}���N�ł��顂�������\4-4�Ɏ������悤�ɁA�܂���������ъJ����620���}���N��������顎c���32��7380���}���N�ɂ��āA�����h�C�c���̏��B�̕��Ƌ����h�C�c���̏��B�̕��Ƃɂ܂��������顂���ɂ��̂��ꂼ��ɂ��āA20%��A�M���{�̃v���O����(Bundesprogramm)�ɁA80%���B���{�̃v���O����(Landerprogramm)�ɓ��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�\4-4. GVFG�ɂ��A�M�����x��(1998�N)
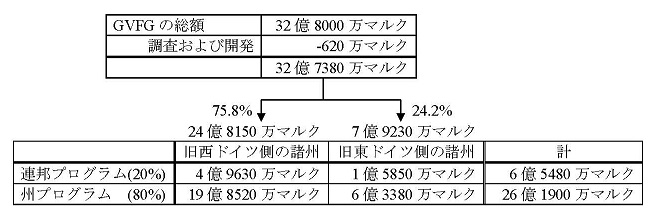
�@���̌��ݍ����ŁAS�o�[���AU�o�[���A�H�ʓd�Ԃ̌��ݔ��60%���d���A�c���40%���B���{�ƒn�������̂����S���邱�Ƃ����@�ɒ�߂��Ă���B�Ⴆ�x�������^�A�A�����ł́AS�o�[���AU�o�[���̐V�����݂̌��ݔ�́A����60%�A�x�������s��40%�S���邱�ƂɂȂ��Ă���B�V���c�b�g�K���g�^�A�A������S�o�[���̐V�����݂ł��A����60%�A�c��͏B��28�`34%(������28%���ł�����)�A�S��12�`6%(��12%)�ƂȂ��Ă���(�Z�c, 1998) [73]�B�����āAS�o�[���ɂ��邩U�o�[���ɂ��邩�́A�R�X�g�v�Z���s���āA�L���ȕ����I�������B
�@�u�h�C�c�S��������Ђ̐ݗ��Ɋւ���@���v(Gesetz uber die Grundung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft)��1993�N12��27���ɐ��肳�ꂽ�S�����v�֘A�@�̒��̈�ł���B���̖@���̓h�C�c�ł͗����Ɂu�h�C�c�S��������Аݗ��@�v(DBGrG: Deutsche Bahn Grundungsgesetz)�Ƃ��Ă�A����ɂ͌������̏�����S�����v�܂łɗݐς������̈����ɂ��Ē�߂Ă���ƂƂ��ɁA���̓���̈�Ƃ��āA�����h�C�c�n��̓S���{�݂������h�C�c�n��̐����Ɉ����グ�邽�߂ɐV���Ȏ{�ݓ��ւ̕K�v�ȓ���(1994�`2002�N��330���}���N������Ƃ��Ă���)�����������邱�ƂƂ��A���̈�ʍ�������[�����邱�ƂƂ���Ă���B�@���̒��ɋ��z�����L����Ă���̂͂���DBGrG�����ł���
�@�u�A�M�̓S���ʘH�̊g���Ɋւ���@���v(Gesetz uber den Ausbau der Schienenwege des Bundes)��1993�N11��15���ɐ��肳�ꂽ�S�����v�֘A�@�̈�ł���B���̖@���́A�h�C�c�ł͗����Ɂu�A�M�S���H���g���@�v(BSchwAG: Bundesschienenwegeausbaugesetz)�Ƃ��Ă�A�����S���̐����͈̔͂Ƃ��ċ�̓I�ȘH���̃��X�g�������āA����ɓS���ʘH�̌��݁A��������эX�V�����ɑ��āA�A�M���{���\�Z�͈͓̔��Ŗ����q�ݕt���܂��͕⏕�����o�����Ƃ���߂��Ă���B���݁A�N�Ԗ�90���}���N�قǂɂȂ��Ă���
�@�ȏ�̎O�̖@��GVFG�ADBGrG�ABschwAG����v�ȍ����ɑΉ����Ă��邪�A���̑��ɂ��ADBAG�������������͎O����̂ňꉞ�����͂��Ă����
�@BSchwAG�Ɋ�Â��⏕���Ɩ����q�ݕt���̎g�����Ƃ��ẮA�����A���ǍH���ɂ��Ă�100%�����q�ݕt���Řd���A�V�����݂ɂ��ẮA�����q�ݕt���ƕ⏕���̊�����A�M���{�ƓS�����Ǝ҂����c���Č��߂邱�Ƃɂ��Ă����̂ŁA�V�����݂̃v���W�F�N�g���Ƃɖ����q�ݕt���ƕ⏕���̊������قȂ邱�ƂƂȂ����B��萳�m�Ɍ����A���̊����͋�Ԃ��ƂɌ����_��ɂ���ĈقȂ��Ă�����Ⴆ�AA�s��C�s�����Ԕ�r�I�Z����Ԃ̐V�����ݍH���̌_���ł́A���z1��2440���}���N�̓����ɂȂ邪�A���̂����A�M���{����1��1400���}���N���A�M���{����o����邱�ƂɂȂ��Ă���A���̍������\4-5�̂悤�Ɏ������[74]�B
�\4-5. �S�����v��1�i�K�ł̐V�����݂̍��������̗��@(���z�̒P��: �S���}���N)
| ���� | �@���z�@ | |
|---|---|---|
| ���݂Ɠy�n���� | BSchwAG�Ɋ�Â��������q�ݕt��(a)�@�@ | 30 |
| BSchwAG�Ɋ�Â����⏕�� | 20 | |
| DBGrG�Ɋ�Â����⏕�� | 50 | |
| �b��I�ɍ������������z�̍��v* | 100 | |
| �v�您��ъǗ��̔�p(b) | 14 | |
| ���z | 114 | |
�@�_�ɂ͂��̂悤�ȋ�̓I�Ȕ�p�̕��S���z���L�ڂ���Ă��顂��������_��́A�S�����v��A�S���̌��݁A���ǍH���͘A�M���{(���m�ɂ́A�A�M��ʏȁA�A�M������)��DBAG�Ƃ̊Ԃł̌_��̌`���Ƃ��čs���顑��i�K�ȍ~�́ADBAG�̑���ɁADB Netz AG��DB Station & Service AG���_������邱�ƂɂȂ� �_��ɂ���ĕ⏕���△���q�ݕt���̊������قȂ�̂ŁA�Ⴆ�A�V�����݂̘H�����X�g�̒��ɋ������Ă����P�������t�����N�t���g�Ԃ�ICE��p���́A2001�N���ɂ͊����A2002�N5���J�Ɨ\�肾���A���v���\���Ɍ����܂�邱�Ƃ���A���ݔ�p��S�z��77.5���}���N�ƍŏ��Ɍ��߁A���̂���67.5���}���N��A�M���{�̖����q�ݕt���A10���}���N��A�M���{�̕⏕���Řd�����ƂƂ���Ă���B���ۂɍH�������Ă��̊z���I�[�o�[�����ꍇ�ɂ́A���̍��z��DBAG(���i�K�����DB Netz)�����S���邱�ƂɂȂ��Ă���[75]�B
�@�������A���̕����͗�O�I�ł���A���ʓI��DB Netz���ɉߑ�ȕ��S�������邱�ƂɂȂ�ƍl�����Ă���[76]�B���̂悤��1994�N�̓S�����v����̌o���ƌ��y�ёË��̌��ʂƂ��āA1998�N���玟�̂悤�ɕύX�ɂȂ����B
�@�����q�ݕt���́A�S�����Ǝ҂��J�ƌ�A�������p����������ɕԍς��邱�ƂɂȂ��Ă���[78]�B��2�i�K��DB Netz���������ꂽ���Ƃɂ��A�V����DB Netz �̏��L�ƂȂ�ADB Netz�����H�g�p��(1km������)�����邱�ƂɂȂ�B���̎g�p���̊z�́A�������p��ɑ��R�X�g(���l����A�������܂�DB Netz�̏��o��)���������z�ɂȂ�̂ŁA���̎g�p���̒��̌������p��������q�ݕt���̕ԍςɓ��Ă��AEBA�ɕԂ���邱�ƂɂȂ�B
�@����ł́A�h�C�c�ł͂ǂ̂悤�ȃv���Z�X�ŐV�����݂����肳���̂ł��낤���B���h�C�c�ɂ����ẮA����E���ōr�ꂽ���y�̕�����}�邽�߂ɁA�A�M��ʘH�v�悪���т��э��肳�ꂽ�B�O�a��ԂƂȂ������H������H�ւƂ����A�M���{�̐��������A�V���̌��ݏꏊ��A�M���{�����X�g�A�b�v���Ă����̂ł���B
�@�h�C�c�����̏��̑S���I�Ȍv��́A1992�N7��15���Ɂu�S���\�����v�̂��߂̊�{�����̌���v�Ɠ����Ɋt�c���肳�ꂽ�u�A�M��ʘH�v��1992�v�ł��顂����1990�N�ɐ��肳���͂��ł������u�A�M��ʘH�v��v���h�C�c����ɂ��啝���������K�v�ɂȂ������߂ɒx�ꂽ���̂�[79]�A1993�N�H�ɘA�M�c��Ō��c���ꂽ��u�A�M��ʘH�v��1992�v�ł́A�A�M��ʘH�v��j�㏉�߂ēS��(DB+DR)�ւ̓����\�葍�z���A�M���������H�ւ̓����\�葍�z���Ă���(����, 1996, p.237; �P�X�^�E��, 2000, p.61)�B���̌v������{���邽�߂ɁA�O�q�́u�A�M�S���H���g���@�v(BSchwAG)���S�����v��(1993�N11��)�ɐ��肳�ꂽ�Ƃ����(�Z�c, 1998)�ABSchwAG�ɂ́u�A�M��ʘH�v��1992�v�̃��X�g�̂����A����Ɋm���Ȍv��H���̃��X�g���܂܂�Ă���B
�@���X�g�ɋ�����ꂽ�v��H���ɂ͘A�M���{���K�v�x�ɉ����Ēi�K�����Ă��������A���Ƃ��Ɓu�A�M��ʘH�v��1992�v�̃��X�g�͍���20�N�ȓ��Ɍ��݂��ׂ��H���̃��X�g�ł���A���̍������キ�A5�N���ƂɘA�M���{���K�v�x�̌������Ƒ����̕ύX���s���Ă������Ƃ����߂��Ă���B�������̓��e�͂��������邪�A�܂��R�X�g�v�Z�̊�b���Â��Ȃ�̂ł��̍X�V���s���B���ɗ��p�x�̌������ŁA����̓R�X�g�v�Z�ɔ�ׂē���B��ʂɂ͊J�ƌ㎞�Ԃ������Ȃ��Ɨ��p�x�͏オ��Ȃ�����ł���B�܂����p�x�͗����̐ݒ�ɂ���ĉe������\��������̂ŁA�����ݒ�ŐF�X�ȃV�i���I���l����B����ɉ����āA�ٗp�����Ȃǂ̒n��ւ̕։v����j��Ȃǂ̌���[80]�ADBAG�̌o�c�ɑ���e���̌���[81]���K�v�ɂȂ�B
�Ⴆ�A2002�N�J�Ɨ\��̃P�������t�����N�t���g�Ԃ�ICE��p���ɂ��ẮA���ӂ̏B���{���A�ߋ����H�����P������t�����N�t���g�ɏ�����邱�Ƃ��������Ă���A�\���ȗ��p�������܂�Ă���B�������A�P�������t�����N�t���g�Ԃ̍q��H���������Ă��郋�t�g�n���U�q��́A���̘H�����Ԏ��H���Ȃ̂ŁA���܂ł̔����̎���50���Ō��Ԃ��Ƃ��ł���ICE��p���J�ƌ�͓P�ނ���\��ŁA�P�������t�����N�t���g�Ԃ̍ݗ�����ICE��p�������킹����q���͑����������܂��B��ԓ�����̗��p�҂����Ȃ��낤���A�g�p���͗�Ԃ̖{���Ō��܂�̂ŁADB Netz �͒��Ԃ�1���ԓ�����㉺���ꂼ��5�{�^�s�ł���ΐ������ƍl���Ă���[82]�B
�@�������ĕK�v�x�̂����H�����X�g�͑��݂��邪�A�ǂ��̘H���𒅍H���邩�́A1994�N�̓S�����v�ȍ~�A�A�M���{�ƓS�����Ǝ҂Ƃ̊Ԃ̌��ɂ���Č��߂���悤�ɂȂ����B�@����́A�ǂ̘H���𒅍H���邩��DB Netz������ł��邱�ƂɂȂ��Ă��āA�A�M���{��DB Netz�ɋ����͂������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���X�g�̒��łǂ��̘H���𒅍H���邩�́AEBA��DBAG(1999�N1�������DB Netz)�Ƃ̊ԂŌ����Č��߂�̂ł���B�������s������ꍇ�ɂ́A���̉ߒ��ŏB���{�ɕ⏕�������߂����������[83]�B
�@�������������o�āA�H���_�����킯�����A���i�K�ȍ~�͑呠�ȁA�A�M��ʏȁADB Netz�ADB Station & Service�̎l�ҊԂ̌_��ɂȂ��Ă���B�H���_��̒��ɂ́A�ړI(�ꏊ�A�V�����݂����ǍH����)�A�\�Z���ρA�A�M���{�̕��S�A�����E�J�Ǝ����Ȃǂ����L����Ă���B�������A���̌_��ł́A100%�S�����߂Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�V�����݂ɂ��Ă�[84]�A��ԕʂ̌v���EBA�ɒ�o���āAEBA���v���W�F�N�g�ʂɌ������邱�ƂɂȂ�[85]�B���̃v���Z�X�́A
�@�����v�悵�Ă������݃R�X�g�ɂ��Ă�100%�x�����邪�A���R�A�H���̉ߒ��̒��Ō��ݔ�c��ރP�[�X���o�Ă���B���������ꍇEBA�́A���ݔ�I�[�o�[���镪���K���ǂ�����������[86]�B���������菇�ނ��ƂŁA����܂ł̂Ƃ���A�������ς�����I�[�o�[�����P�[�X���܂߂āA���тƂ���100%�⏕���Řd���Ă��顂������A����������ł��₦�Ȃ��قǂɌ��ݔ�I�[�o�[�����Ƃ��ɂ́A�H�����Ԃ��������Ƃ�A�V�������v��̒��H�𓀌����邱�ƂȂǂ����������Ƃ���[87]�B
�@��ʂɉ��B�̓S���͓��{�Ɣ�r���Đ�Ύ��v�ɖR�����A�S�����Ǝ҂��ʘH�܂ŕۗL���Ă̌o�c�͒���������ł���Ƃ�����B�����ŁA�㉺�����ɂ���āA�S�����Ǝ҂��o�c��̍ő啉�S�ƂȂ��Ă����S�����H�{�݂ۗ̕L�Ǘ��ӔC����������A�A�����Ƃɂ̂ݐ�Ɖ����A��Ɛ����ő���ɔ������邱�Ƃ́A�A����̂ɂƂ��Ă͖]�܂������ƂƂ����(�x, 1994; 1996)�B�������A�ʘH��������t����ꂽ�ʘH��̂͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B
�@�h�C�c�o�ό�������1987�N�ɂ��čs���������I�ȒʘH��p�v�Z�ɂ��A���̓����ł��A����(�S���c�Ǝ����ƘA�M���{�̕⏞)�͒ʘH����J�o�[����̂ɂ͏\���łȂ������Ƃ����B���̏�Ԃ́A�ݕ��A���ɂ�����DBAG�̔̔��ʂ��ቺ���Ă������ƂŁA����Ɉ������Ă���(�����N, 1999)�B
�@�S�����v��ADBAG�̒ʘH����y�ё��i�K�ȍ~��DB Netz���o�c�I�Ɉ��肵�Ă���̂́A1994�N1��1���̓S�����v�̍ۂ̎��Y�]���̑啝�艺���ŁA�������p��啝�Ɍ��������������ł���B�����ADB+DR�ŗL�`�Œ莑�Y��992���}���N���������̂��ADBAG��253���}���N��BEV��32���}���N�̌v285���}���N�ɁA�Ȃ��707���}���N71.3%�����z���Ă��܂���(����, 1996, p.279)�B���̂������ŁA�\�ʓI�ɂ͌o�c�����肵�Ă�����킯�ł���B�������A�������p��̑啝�Ȍ����ɂ���ĒZ���I�ɂ͗��v���o�邩������Ȃ����A�����I�ɂ̓����e�i���X���̍X�V�̂��߂̐ݔ�������}�����Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤��[88]�B
�@����ɁA��ʂɒʘH��̂����ݍς݂̓S���̈ێ��Ǘ������ɓ������Ă���ꍇ�ɂ͖��͂Ȃ����A�h�C�c�̏ꍇ�ɂ́A�I�y���[�V���������Ȃ�DB Netz��ICE��p���̂悤�ȐV�����݂��S�����邱�ƂɂȂ�B�Ԏ��H�������X�ƍ�葱�������{�S�������c�̂悤�ȑ��݂ɂȂ�Ȃ��̂��S�z�ł͂���B���c���ݗ������́A���H��ۗL���āA�����݂��t���邱�Ƃ��l���Ă����̂ł���B�������I�y���[�V���������Ȃ��ƂȂ�ƁA���ݔ�k�̃C���Z���e�B�u�͏��Ȃ��Ȃ�B�h�C�c�̏ꍇ�A�~���͗L���q�������g���Ă��Ȃ��Ƃ����_�����A����ł������̗͂ō̎Z�������H���̓S�����݂�h���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤��[89]�B
�@EU�����ŁA�e���̓��H�A�S���̌o�c�`�Ԃ̈Ⴂ�����ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�h�C�c�̗�Ԃ��t�����X�ɓ���ƁA�h�C�c�̗�Ԃł��t�����X�̗�ԂƂ��Ĉ����顂������A�����Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�������z����Ƃ��Ƀp�X�|�[�g���o�������ŁA�h�C�c�̎����Ԃ͂����܂ł��h�C�c�̎����ԂƂ��ă��[���b�p���𑖂��邱�ƂɂȂ顂��܂�h�C�c�S�̂𑖂��Ă���g���b�N��30�`40%�͊O���̃g���b�N���Ƃ�������[90]�B�h�C�c�ł́A�A�E�g�o�[���̗��p�͌������������A�A�E�g�o�[���ɂ������p�̂��߂ɍz���ł��g���Ă���A���̂��߃h�C�c�����Ŕ̔�����Ă���K�\�������͑��̍��ɔ�ׂāA�����ɂȂ��Ă���B�O���Ԃ̓h�C�c�����̂����O���ŃK�\���������������ăA�E�g�o�[���ɓ����Ă��邽�߂ɁA�t���[���C�_�[�Ɖ����Ă��邪�A���Ƃ����āA���̍��ł́A���H����Ђ�����Ă����������āA�������͓��[91]�B���H�ݕ��A��(�g���b�N�A��)�̏ꍇ�A�h�C�c�ł�1993�N6���ɃJ�{�^�[�W��[92]�K�����P�p����Ă���A���ɑ���EC�������������ڂ̍z����(����, 1996, pp.200-202)������ɍ����Ȃ�A�h�C�c�̃g���b�N�A���Ǝ҂ɕs�����ɂȂ邩������Ȃ��B
�@����ɁA�q��H���Ƃ̊W���d�v�ł���[93]�B�h�C�c�����̍q��H����S���ɒu�������Ă������Ƃ��������������B�h�C�c�̍����q��H���́A�R�X�g�������A���i���Ⴍ�}�����Ă��邽�߂ɐԎ��ƂȂ��Ă���B���̂��߁A���������Ă��郋�t�g�n���U�q������͓I�ł���B�Ⴆ�A�t�����N�t���g��`�ɂ́A����܂ł��n����S�o�[���̉w�͂��������A1999�N5���ɁA�n���ICE��IC/EC�Ƃ��������������q�H���p�̉w���J�Ƃ����B���̂悤�ɁA��ʎ�i�̊Ԃł̋����Ƌ������A�܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă���Ǝv����[94]�B
[25]�������S�����v�̍ۂɁA�A�M���{�������������h�C�c���S�̗L���q���̊z(1993�N��)�ɂ��ẮA�����ɞB�������c���Ă��顂����ł�BEV�ł̃C���^�r���[�Ŋm�F��������660���}���N�ɂ��Ă���A���{�̉^�A�Ȃ́w�^�A�o�ϔN���x(1996)�ł�660���}���N(p.83)�Ƃ��Ă��顂Ƃ��낪BEV�̃p���t���b�g�u�S�����v�̊�b�v(Fundamente zur Bahnreform, �S�����v�̏����ɍ��ꂽ�Ǝv����)�ł�670���}���N�Ƃ���Ă���A�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�ł�670���}���N�Ƃ���Ă�������̑��A704���}���N�Ō��\�l680���}���N�Ƃ�����(����, 1996, p.281)������A�����DBAG�ł̃C���^�r���[�ł�700���}���N�Ƃ����������������Ă����
[26]�w�����V���x�Ƃ̃C���^�r���[�L��(1994�N2��11���t)�ŁA������DBAG��Heinz Durr��́A�h�C�c�̓S�����v�͓��{�̍��S���c���̐����ɉe�����čs��ꂽ���A�㉺�����₱���ɋ������悤�ȍ��̏��p�Ə��҂̕��@�Ȃǂő��Ⴊ����Ǝw�E���Ă���B
[27]�h�C�c�ł̃C���^�r���[�����ɂ����āA�S�����v�Ɏ�����̃h�C�c�̓S������A�ߋ��̎������s���̏W�ςƂ��Ăł͂Ȃ��A���ꂼ��̒����I�Ȑ���Ƃ��Č���Ă������Ƃ͐V�N�ȋ����ł������B
[28]�������A�V�F�A�͒ቺ���Ă��A�A�����т��������Ă������Ƃɂ͒��ӂ�����B���q�A����1960�N��400���l�L��(�V�F�A��16%�A�ȉ����l)����1992�N�ɂ�460���l�L��(6%)�ցA�ݕ��A����1960�N��530���L���g��(37%)����1992�N�ɂ�560���L���g��(18%)�ɑ������Ă���(�����N, 1999)�B
[29]������DBAG���̎咣�ł���B���ɁA�ߑ㉻���x�ꂽ�����ɂ��āA�����̉e���Ń~�X��}�l�W�����g���s���A�^�����Ⴍ�}�����Ă������߂ɁA���������邾���̓������ۂ��m�ۂł��Ȃ����������ł͂Ȃ��A���������Ă������̂���DBAG�͐������Ă���BDBAG�́A������x�̉^���l�グ�͌o�c��K�v���Ɣ��f���Ă���悤�������B�^�����グ��ƒ���͗��p���������邪�A�͑����A�����A�S�����v��A�^���l�グ�����Ă��邪�A�q�̗��p�L�����͑������Ă���Ƃ����B�������A���{�̍��S�̔��Ȃ܂���A��������x���Ƃ������ƂɂȂ낤�B�x���z���ĉ^����l�グ����A��͂�q���͗���Ă������낤�B
[30]��(1994)�́ADB���u1948�N�̔����ȗ�1951�N�������Ĉ�т��ĐԎ��v�ł���A1951�N��7,000���}���N�̍����������Ƃ��Ă���B������DB�̔�����1948�N�Ƃ��Ă��鍪���͕s���B����(1996, ch.4)�ɂ��A����E���s���̘A���R��̉��ł́A�č��E�p����̒n��(�����o�ϒn��)�ƁA�t�����X��̒n��ł͌o�c�����Ⴕ���B1949�N5��23���̊�{�@���z�ɂ��h�C�c�A�M���a�������̌�A���N9��7������č��E�p����̒n��ł́u�h�C�c�A�M�S���vDB�Ƃ������̂��g���A���N10��11���ɘA�M��ʏȂ͂����P�ꖼ�̂Ƃ��邱�Ƃ����肵�����A��̌o�c�g�D�́u�����o�ϒn��h�C�c�A�M�S���v�u�h�C�c�A�M�S���쐼�h�C�c�S���o�c�A���v�ɕ����ꂽ�܂܂ł������B���g�D�̍����́A1951�N3��2���́u�h�C�c�A�M�S���̏��L���̊W�ɂ��Ă̖@���v�A1951�N12��13���́u�A�M�S���@�v�̌��z�Ƃ��̎��{(���N12��18��)�܂ő҂��˂Ȃ炸�A�����ɂ́ADB�̐�����1951�N12���Ƃ������ƂɂȂ�B���������Ă����ł́uDB�͔����ȗ���т��ĐԎ��o�c�𑱂��Ă����v�Ƃ����\���ɉ��߂��B
[31] DBAG�̐����ł́A1990�N�̕��z��470���}���N�B
[32]1�}���N����74�~�Ŋ��Z�B�ȉ����̐߂͓��l�B
[33]�h�C�c�̓S�����v��Bahnreform�Ƃ����p�ꂪ�p�����Ă���A���{�̂悤�ɍ��S���c���Ƃ͌Ă�Ă��Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ�����B�����Ɍ����A���c��(Privatisierung)�͉��v�̎d�グ�̒i�K�Ƃ��āu�\�ȏꍇ�ɘA�M�ۗL�̊��������J����v�i�K���w���Ă���(��, 1994)�B
[34]���h�C�c�ł́A�A�M���x���ŁA��ʉ�v���ƂƂ��Ă̐��{���c���ƁA���ʉ�v���ƂƂ��Ă̐��{���c���Ƃ̑��ɁA�ŗL�̌o�c�Ɖ�v��L���邪�@�l�i�������Ȃ����ʍ��Y(Sondervermogen)�Ƃ������@�`�Ԃ�����A�h�C�c�A�M�S���̑��ɂ��h�C�c�A�M�X�ւ����ʍ��Y�̌`�Ԃ��Ƃ��Ă�������́A��O�̃i�`�X�������œ����o�ς��i�ޒ��A1937�N���狌�h�C�c�鍑�S���͓��ʍ��Y�̌`�Ԃ��Ƃ��Ă���A�Ɨ��̎Z�I�ł͂�����̂́A�c�Ɨ��v�̈ꕔ���A�E�g�o�[���̌��݂ɉ��Ȃǎ���������߂��Ă����o�܂�����(����, 1996, p.51; pp.100-104)�
[35]���̐����ɂ��ẮA���̖̏͂`���̒�25���Q�Ƃ̂��ơ
[36]���{�̉^�A�Ȃ́w�^�A�o�ϔN���x(1996, p.83)�ɂ��ƁADBAG�̉c�Ə�s�v�ȕs���Y���]���z�Ŗ�133���}���N(��9,842���~)���p���������ƂɂȂ��Ă���B�������ABEV�̃p���t���b�g�u�S�����v�̊�b�v(Fundamente zur Bahnreform)�ɂ��ƁABEV���ݗ����_�ŋ����S��������p�����s���Y�́A�A�M�S�̂Ŗ�225,000�ӏ��A150,000�w�N�^�[���ɂ̂ڂ�A��������ADBAG�̊J�ƑݎؑΏƕ\�ł́A���Ȃ��Ƃ�50���}���N�����̕s���Y���ڊǂ���邱�ƂɂȂ��Ă�������ꂾ���̗ʂɂȂ�ƁA�����̕s���Y�̓o�L�A�ڊǂ���C�ɕЕt�����̂ł͂Ȃ��A���X�ɁA�S���ɕK�v�ȕs���Y��DBAG�Ɉڊǂ��A�S���ɕs�v�ȕs���Y�͎s��Ŕ��p����Ȃ�ABEV�����p����Ȃ肪�s���Ă��Ă��顂��̍�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ�1999�N�̃C���^�r���[���_�ł��������Ă���̂ŁA�p�����Y�̋��z�ɂ��Ă͞B�������c��
[37]�ߋ����̏��ғ��ň�ʍ������v�����傷�邽�߂ɁA�K�\����1���b�g���ɂ�16�y�j�q(=0.16�}���N)�A�y��1���b�g���ɂ�7�y�j�q(=0.07�}���N)�ւƍz���ł̈����グ���s���A1994�N�x�Ŗ�77���}���N(��5,698���~)�̑����ɂȂ���(�^�A��, 1996; ����, 1996, p.293)�B
[38]1993�N12��27���ɐ��肳�ꂽ�S�����v�֘A�@�̒��̈�B
[39]�\4-2�̒���DB�́A���m�ɂ́A�S�����v�O�̓h�C�c�A�M�S��(Deutsche Bundesbahn)���Ӗ����Ă������A�S�����v���i�K��͕��Љ����o��DB�O���[�v���Ӗ����Ă���(���������x��Deutsche Bahn�h�C�c�S���̈Ӗ�)�BDB�O���[�v�ł́A���S�Ƃ��č��ł���ԓ���DB��t���Ă���B���ɍ������Ȃ�����́A�S�����v�O�����DB�ƌĂԂ��Ƃɂ���B
[40]�������q�A���̊ϓ_����́A���̑��ɓs�s�����o�X���d�v�Ȗ�����S���Ă���B�y�J(1997)�ɂ��ƁA�h�C�c�̌�ʖԂ́A�e��v�s�s�����̃l�b�g���[�N�Ƃ����𑊌݂Ɍ��ѕt���鍂�����(Schnellverkehr)�Ƃɕ��ނ���A������ʂ�S���Ă���̂�DB�̊e�H���Ɠs�s�����o�X�ł���B�s�s�����o�X(Stadteschnellbus) �́A�قƂ�ǂ�1���ԊԊu�̉^�s�ŁADB��1���ԊԊu�̗�ԃ_�C���ƑΉ����Ă���B�啝�ȘH�������ɂ��ADB�̘H���Ԃ̌��Ԃ߂Ă���B
[41] DBAG�ł�Produkt�ƌĂ�Ő������Ă����B
[42]219km�B2001�N�������A2002�N5���J�Ɨ\��B
[43] DB Netz�̐����ł́AICE3��p���Ƃ����Ă��ADB�O���[�v��������Ԃ𑖂点��킯�ł��Ȃ��A�����炭�I�����_��ICE3���w�����āA���̘H�����g�p���邱�ƂɂȂ�Ƃ����B
[44]���������ċߋ������q�A���ƌ����̂��ɂ��ẮA�����ނˏ�ԋ���50km���邢�͏�Ԏ���1���Ԃ��ڈ��ɂȂ��Ă��āA�H���ł͂Ȃ���ԑ̌n�Ɋւ��镪�ފT�O�ł���(����, 1996, p.267; �Z�c, 1998)�B�S�����v�֘A�@�̓S���V�����@�Ƃ��āA����1993�N12��27���ɐ��肳�ꂽ��̖@���ɂ��A �@�u�����ߋ������q�A���̒n�扻�Ɋւ���@���v(�n�扻�@)�ł́A��ɓs�s�A�s�s�ߍx����ђn��̌�ʎ��v�������߂̂��̂��u�����ߋ������q�A��(OPNV)�v�Ƃ����A��ʂ����ɂ����ꍇ�ɂ́A��̌�ʋ@�ւ�1��̏�ԋ����������ނ�50km�܂��͏�Ԏ��Ԃ�1���Ԃ��Ȃ��ꍇ�Ƃ���Ƃ���Ă���B�A�u��ʓS���@�v1��5���ł́A��Ԃ̏�q�̑����̑S�̂̏�ԋ�����50km���Ȃ����A�܂��͏�Ԏ��Ԃ�1���Ԃ��Ȃ����̂��S���ߋ������q�A���ƋK�肳��Ă���B
[45]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[46]�����h�C�c���[�̏����Ȓ�Frankfurt an der Oder�Ƌ�ʂ��邽�߂ɁA���m�ɂ�Frankfurt am Main (�}�C���쉈���̃t�����N�t���g)�ƌĂ�Ă���h�C�c�̏��ƁE���Z�̒��S�s�s�B�h�C�c�̋�̌��փt�����N�t���g��`��i���Ă���B�{���Ńt�����N�t���g�Ƃ����A����Frankfurt am Main ���w���Ă���B
[47]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[48]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[49]�ߋ������q�A���̂Ƃ���œo�ꂵ��EC������(EEC)�K��No.1191/69���C�����ꂽ����(����, p.206; p.228)�B
[50] EC�ł́A�������̂�������̉������ɍS���͂������A���̎��{���@�ɂ��ẮA�������������@�𐧒肷��u�w�߁v(Directive)���o���Ă���B
[51] ICE�̓n�m�[�o�[���r�����c�u���N��(327km)����у}���n�C�����V���c�b�g�K���g��(99km)��1991�N6������ō�����280km�ʼnc�Ƃ��J�n����(�Z�c, 1998)�B
[52]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[53]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[54]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[55]���Ƃ��ƌ���DB�����s���Ă������A�u�A�M�̓S���̍����ƐV�Ґ��Ɋւ���@���v�ł́A1994�N��1995�N�Ɍ����āA�e�N95���}���N�����x�Ƃ��ċN���F�߂��Ă���(����, 1996, p.290)�B������BEV�̐����ł́A���i�K�Ő��x���ς��1999�N7��1���ȑO��BEV�����s�ł��A���ہA1994�`1999�N�܂�BEV�͌��s���Ă����Ƃ����B�����DB�̔��s���Ă������̎؊��ł���
[56] DBAG�̓C���t�����݂������A�M��v�����@�̌����ΏۂɂȂ邪�ABEV��100%�����Ώۂł���B���̗�ł́A�����@�́A�ؓ�����BEV�P�ƂŎ���������A�A�M���{�Ǝ���ꂽ�ق������q�������͈����Ȃ�̂ŁA����ŔN��2700���`3000���}���N�ߖ�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�܂�����Ƃ͕ʂɁABEV�̕s���Y�̊Ǘ��̎d�����H�v���邱�ƂŁA���l�R�X�g��ŋ����N��2���}���N�ߖ�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B
[57] BEV�ł̃C���^�r���[�Ǝ����ł́A�h�C�c�̓S�����v�̗��R�E�ړI�Ƃ��ē��������ꂽ�B���̗��R�E�ړI�����̌������Ɋւ�����̂ŁA���̗��R�E�ړI�́A�A�M���{��\�Z��̃��X�N����~�����ƂƂ���Ă����B
[58]�����h�C�c���S�ŁA�������������̂�DB�����ŁADR�ɂ͌������͂��Ȃ������B
[59] BEV�ł̃C���^�r���[�B
[60] BEV�̃p���t���b�g�u�S�����v�̊�b�v�ɂ��
[61] BEV�̐����ɂ��ƁA���m�ɂ́A1998�N�����݂̖�7��1000�l�̌������̂����A��6��8000�l�͂����ł����悤��BEV�����̌������ł��邪�A�c��̖�3000�l�́ABEV���璷���̋x�ɂ��o�����`��DBAG�Ŏd�������ADBAG���������x�����Ă���B
[62]���̑��ɁA�P������1��6275�l����B������������26��8743�l�ɂȂ�B
[63]���̖��́A���܂��ɉ��������Ƃ͌����������B�Ⴆ�AICE��IC/EC��10�`30���̒x�ꂪ��ԉ����Ă��邪�A�����������Ԃ�DBAG�͂��Ȃ�C�ɂ��Ă���BDB Netz�̌��ւɂ����l�̂��̂����������A�t�����N�t���g�����w�ł͌f���Ŗ����̒x��̏���ʏ�~�q�ɂ悭������ꏊ�Ɍf������Ă����B����ɂ��ƁA1998�N1�N�ԂŃh�C�c�A�M�S�̂ŁA�荏�ɉ^�s���Ă����̂́A������(Fernverkehr)��86.7%�A�ߋ���(Nahverkehr) ��92.5%�AS�o�[����97.9%�Ƃ������Ƃ������B���������x��́A�ŋ߂ނ��눫���������Ă���B�t�����N�t���g�����w�̌f���ɂ́A1999�N10��17���̒荏�^�s���A�h�C�c�A�M�S�̂ŁA������(Fernverkehr)69.2%�A�ߋ���(Nahverkehr) ��86.2%�AS�o�[����98.3%�A�t�����N�t���g�����w�ŁA������(Fernverkehr)65.7%�A�ߋ���(Nahverkehr) ��82.0%�AS�o�[����97.8%�ł������Ə�����Ă����B���̂悤�ɒx�ꂪ��ԉ����Ă��闝�R�Ƃ���DBAG���������̂́A���H�ɍH�����̉ӏ����������ƁA�h�C�c�̓V��͍r���Ƒ�ςȂ��Ƃł������B�����āA�������͑ӂ��Ă��Ă��N�r�ɂł��Ȃ��̂ŁA�K��������Ă��邽�߂Ƃ����w�E������Ƃ̍J�̉\���Љ�ꂽ�B��Ԃ̒x��̏��킴�킴��q�����Ɍf�����邱�Ƃ��A�������ɑ����팩�����ߓI�ȕ��͋C���Y���Ă���B���������������ɑ���s�M�����S�����v�̒ꗬ�̈���Ȃ��Ă������Ƃ͊m���Ȃ悤�ł���B
[64] BEV�̃p���t���b�g�u�S�����v�̊�b�v�ɂ��
[65]�a�@�A�z�e���A���W���[�{�݁A�����500�قǂ̎�̃T�[�N���܂ł���B
[66]�Z���Ђ͗L����Ќ`�ԂŁA�S�����v�O���瑶�݂��Ă���B�]�ƈ��ɂ͌������͂��Ȃ��B���Ă�20�Ђ������Ƃ������邪�A���p�������Ǝv����B
[67] BEV�ł̃C���^�r���[�
[68]����Ԃ��ƁABEV�����^���ꂽ�s���Y�̒��ɂ́A�S�����ƂɕK�v�ȕs���Y���܂��܂܂�Ă��邱�ƂɂȂ�BBEV�̐����ł́A���m�Ɍ����ƁADBAG��������DB�O���[�v���g�p���Ă��邪�@����A�o�L��͂܂�BEV�̏��L�ƂȂ��Ă���S���W�s���Y���c���Ă���B�����͏������o�L���i�߂��Ă��Ă��邪�A�����DB�O���[�v�e�Ђɖ����ŏ��n�����\��ł���B1999�N�̃C���^�r���[���_�ł���Ƃ͐i�s���ł������B���������o�L�Ɏ��Ԃ�������̂́A���Ƃ��ƍ��S�����L���Ă������ɂ͈ꊇ���Ďg���Ă����̂ŁA���E���ʐς������܂��ŁA���ʂ�������Ƃ��Ă��Ȃ��ȂǁA�o�L�ɕK�v�ȃf�[�^�������Ă��Ȃ����߂ł���B���ʓ��̍�Ƃɂ͎v���̊O���Ԃ�������B���l�̌��ۂ́A���{�̍��S���Z���ƒc�ł������Ă���B
[69]�Ⴆ�A�t�����N�t���g��BEV�{��(1999�N12���Ƀ{���Ɉړ]����O)�̗���ɂ́A�t�����N�t���g�ݕ��w�Ղ̍L��ȓy�n���L�����Ă��邪�A���̓y�n��BEV��DBAG���������ď��L���Ă���B���̂����t�����N�t���g���S���ɋ߂��ă��b�Z���ɗאڂ��Ă���y�n��BEV�����L���Ă���B���̐Ւn�͔��p�����ɁABEV���͂��߂Ƃ��ăJ�i�_��ƂȂǂ̊O������̓������܂߁A��60���}���N�B���čĊJ����Ђ����A����80m���̓��H�𒆐S�Ƃ��������{�݂̊X�ɍĊJ�����ł���B
[70] DBAG�̐����ł́A���̂�����90���}���N��BSchwAG�Ɋ�Â����A�M���{�̕⏕���ŁA�C���t���ɓ��Ă��Ă��邪�A�c��͎�Ɏԗ��̋ߑ㉻�����ɓ��Ă��Ă���Ƃ����B
[71] DBAG�ł̃C���^�r���[�
[72] EBA�̐����ł́A�N�Ԋz�͌i�C�̗ǂ��������ɂ��܂�W�Ȃ���r�I���肵�Ă���Ƃ����
[73]�x�������s�͖ʐ�889km2�A�l��347���l�ŁA�x�������^�A�A����1997�N�ɐݗ��B�V���c�b�g�K���g�^�A�A����1977�N�ݗ��ŁA�V���c�b�g�K���g�s�Ƃ��̎���4�S���܂ޖʐ�3000km2�͈̔͂ŁA�l��230���l�B
[74] DBAG�ł̃C���^�r���[�
[75]�A�M��ʏȂ�EBA�ł̃C���^�r���[�B
[76] EBA�ł̃C���^�r���[�B
[7]�����EBA�̐��������ADB Netz�̐����ł́A����ɐ��������肳��A���ݔ��37%��DB Netz�����S���A�c��63%��A�M���{�̖����q�ݕt���Řd���Ƃ���Ă����B
[78]�������AEBA�̐����ł́A�������p�̊z�͏ꏊ�ɂ���ĈႤ�̂ŁA������S�����킹�ĕ��ω����Čv�Z���Ă���Ƃ����
[79]�u�A�M��ʘH�v��1992�v�ł́A�x���������ӂ̒������H�������S�o�[���H���̐������d�_�I�Ɉ����A�S������̍���10�N�Ԃ̌v��K�͖�2,000���}���N�̂����̖�10%�A200���}���N���߂Ă���(�P�X�^�E��, 2000, pp.61-62)�
[80]���j��ɔz������ƁA�R�Ԓn�Ńg���l���⋴�������Ȃ�A���݃R�X�g�������Ȃ�̂ŁA���j��̖��̓R�X�g�v�Z�Ƃ����ڂɊW���Ă���B�A�M��v�����@�̐����ł́A���ɍŋ߁A���j��ւ̔z���œS�����݃R�X�g���c��ތX���ɂ���B
[81]�Ⴆ�A�X�E�F�[�f���̃X�g�b�N�z�����ƃC�^���A�̃{���[�j�������ԘH�����v�悳��Ă��āA�h�C�c�����ł́A�x�������A���C�v�`�q�A�G�A�t���g�A�j���[�����x���N�A�~�����w���Ƃ������s�s��ʂ邱�ƂɂȂ�B�������A���̌v��ł̓G�A�t���g�ƃj���[�����x���N�̊ԂɐV�������݂���K�v������B���ꂾ���������ɂȂ�ƁA���p�͗��q�Ƃ��������ݕ����S�ɂȂ邪�A�A�M��v�����@�̌v�Z�ł��ADBAG�̌v�Z�ł��Ԏ����m���ł���A���݂̂Ƃ���V�����݂͓�������Ă���B���[���b�p�S�̂̓S���Ԃ�����Ƃ����ϓ_����V�����݂̕K�v�x����������Ƃ����l���������邪�A�S�����v��́A�o�ϐ��̌��������d�v�ɂȂ����Ƃ�����B
[82] EBA�ł̃C���^�r���[�B
[83] EBA���g�̐����ł́AEBA�̖ړI�́A���������������̍�������̎��������ׂĎg�����āA�V�����݂Ɖ��ǍH���ɓ������邱�Ƃɂ���Ƃ����B�����������ɁA�A�M���{�̗\�Z���������ꍇ�ɂ́A�S�����ƎҎ��g�Ɏ������B������̂ł͂Ȃ��A�H�����Ԃ���������A�V�K�H���̒��H�𓀌�����A�v���W�F�N�g�̈��N�x�r���œ�������Ƃ��������ƂɂȂ�Ƃ����B
[84]�������A�V������(100%�⏕)�����ɂ��Ă�EBA��DB Netz���������邪�A���ǍH���ɂ��ẮAEBA�̌����͂Ȃ��A���F��v�m���č����s���Ă���B���F��v�m�́A���ނȂǂ��ړI�ʂ萳�����g���Ă��邩���`�F�b�N���邪�A�o�ϓI�Ɏ��{���Ă��邩�ɂ��Ă͌������Ȃ��B����́A���ǍH���ɂ�DB�����玑�����o���Ă���̂ŁA���̖ʂ͒S�ۂ���Ă���͂��Ƃ̍l������ł���B������������������q�ݕt�����o�Ă���̂ŁA���ǍH���ɂ��ẮA�A�M��v�����@(Bundesrechnungshofes�ȉ��u�����@�v�Ɨ��L) ���o�ϐ��ɂ��Č������Ă���B�����Ƃ������Ƃ͂����Ă��A�`���I�ɂ͌����@��EBA����������`���Ƃ��Ă���ADB Netz �ɑ��ẮA�����@�͕s�����鎑���𐿋����邱�ƂɂȂ�B
[85]���������u�����v�́A�S�����v�O��DB���g���s���Ă������̂ŁA�����@�̌����Ƃ͈قȂ�B�����@�́AEBA�̌������s�����ADBAG�ɂ��Ă͈ꕔ�����AEBA�̌����ŕs�\���łȂ������Ƃ��낾�����������Ă���B�����@�́A�S�����v�O�ɂ�DB�ɑ��ĕ��ʂ̖����ɑ���̂Ɠ������������Ă������A�h�C�c�����́ADR�ɂ��Ă����������Ă����B�������A�S�����v�ɂ���āA
�@�@�@DB+DR �� BEV+EBA+DBAG
�ƂȂ�ƁABEV��EBA�͌����@�̌����Ώۂ����ADBAG�͌����Ώۂ���O����Ă��܂��B����͍���@91���ƃh�C�c�S��������Аݗ��@DBGrG�ɁA�⏕������ꍇ�ł��ADBAG�̗\�Z�Ǝx�o�ɂ��Č����@�͌������Ȃ��Ă����ƒ�߂��Ă��܂�������ł���B�����Ȃ����̂́AEBA���u�����v���Ă��邩��Ƃ������R�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�����@�̌�����������DB�̈��̃��r�[�����̉e���ł������Ƃ������Ă���B�������A�V�����݂Ɖ��ǍH���ɂ͘A�M���{���⏕�����o���Ă���̂ŁA�C���t�������ɂ��ẮA�����@��EBA���������AEBA�œ���ł��Ȃ����������ɂ��ẮADBAG�܂ōs���ē��肷��Ƃ������Ƃ����Ă���B�܂茟���@�́AEBA��DBAG�𐳂��������������ǂ�������������̂ł����āADBAG�ɑ��Ă͎������������ƂȂ��Ă���B�������ADBAG�ɑ���EBA�̌����͑S���ł͂Ȃ�������茟���Ȃ̂ŁA���̔�����茟���Ŗ�肪���������ꍇ�ɂ́AEBA�����������Ƃ���ȊO�������@���������邱�ƂɂȂ�B�����������ԂɂȂ�Ȃ���A�����@��DBAG�̌������n�߂Ȃ��B
[86] EBA�̐����ł́A����܂ł͗Ⴆ�g���l���̃T�C�Y�̐v�ύX���p���������Ƃ͂���B�������A���ǍH���̏ꍇ�͕ʂ̗v��������ł���B�h�C�c�ł͕⏕���̊�����25�N�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ŁA���̊����O�ɁA���̕⏕�������炤�悤�Ȏ��ԂɂȂ����ꍇ�ɂ́A�����@���⏕���̃J�b�g���w�����邱�ƂɂȂ�B���������l���Ɋ�Â��āA���H���C���t���̊Ǘ���DBAG�A���݂�DB Netz �̎d���Ȃ̂ŁA�C���t���̃����e�i���X��ӂ�����s�K�������肵�āA�ݔ��̍X�V���K�v�ɂȂ����ꍇ�A�����@�͕⏕���̎x�o����߂����邱�Ƃ��ł���B
[87] EBA�ł̃C���^�r���[�B
[88]�A�M��ʏȂ́A���Y�]���̐艺�����̂͌����I�Ȋz�ɂȂ����Ƃ̗��ꂾ���A�����e�i���X���̍X�V�̂��߂̐ݔ������̗}�����ʂɂ��ẮA���l�̊뜜�������Ă����B
[89]����ɑ��āAEBA�Ƃ��ẮA�S�����v�̍ŏ���5�N�Ԃ͐V�����݂Ɖ��ǍH���̗����Ɏ������g���Ă������A����͐V�����݂������ǍH���ɏd�_��u�����j���Ƃ����B
[90]�A�M��ʏȂł̃C���^�r���[�B
[91]�����ŁA�A�M��ʏȂɂ��A���݁A�A�E�g�o�[���͏d�ʃg���b�N�������Ă͖��������A2002�N�ɏd�ʃg���b�N�ɂ��ė����������グ��ۂɁA���̎Ԏ�ɂ��Ă��L������}�邱�Ƃ��l���Ă���B�������A�A�E�g�o�[��������������ݒu����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ̂悤�Ȍ`�ŗ���������̂��ɂ��ẮA���������ł���B
[92]�h�C�c��ł�Kabotage�A�p��ł�cabotage�B���Ƃ��Ƃ͊O���D�E�O���@�̋ߊC�E�����^�s(��)�̂��ƂŁA�����ł̓h�C�c�Z�҂̃h�C�c�����̒ʍs���Ӗ����Ă���B
[93] DBAG�ł̃C���^�r���[�B
[94]��c��(1997)�ɂ��A�h�C�c�ɂ����ẮA�A�M�S��ɂ킽�鑍����ʌv��̍���Ɋւ��āA�ΏۂƂȂ��ʃv���W�F�N�g��I�ɕ]�����邽�߂̎w�j�uRAS-W�v(Richtlinien fur die Anlage von Strassen Teil: Wirtchaftlichkeitsuntersuchungen)���K�p����A���H�A�S���A���q���^�ɑ����ʓ����Ɋւ��āA��т�������I�Ȏ�@�̉��Ɍo�ϕ���(��p�E�։v����)�ƍ������͂̎��{���@�I�ɋ`���Â����Ă���B�A�M������ʌv��͘A�M�c��̏��F���o�Ď��{�Ɉڂ���邪�A���̍ہA���H�A�S���A���^�̊e���傲�Ƃɂ��ׂĂ̌��v���W�F�N�g�̗D�揇�ʂ������L���O����A�]�����ʂƃ����L���O�͘A�M�c��ɒ�o�����B���������Ƃ�܂Ƃ߂͘A�M��ʏȂɂ���čs���Ă���Ƃ���Ă���B�������A�A�M��ʏȂ�EBA�Ɋm�F�����Ƃ���ł́ARAS-W�̓K�p�Ώۂ͓��H�����ł���A�S���␅�^�ɓK�p���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����ł������B
�@�S�����Ǝ҂̃C���^�r���[������i�߂Ă����ۂɁA����S�����Ǝ҂ŕ������b����ۂɎc���Ă���B�H���A�S���̓g���l���Ȃǂɔ���Ȏ��{�𓊉����Č��݂����̂ŁA�J�Ɠ����͌������p��ŗ��v���o�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邪�A�������p���ς߂Η��v���o��悤�ɂȂ�A�Ƃ����̂ł���B��v��͏��p���I����Ă��܂����{�݂ł��A���ۂɂ͂���ȍ~�������Ԏg�p���邱�Ƃ��\�Ȃ̂ŁA�����Ȃ�ƌ������p��������Ȃ���������R�X�g�ɂȂ��ė��v�ނ悤�ɂȂ�̂��A�Ƃ����킯�ł���B
�@���������Ă����̂�1998�N�㔼����1999�N�O���ɂ����ĂŁA���̎����ɂ́A���̉�b�͒P�Ɍ`���I�Ȍ������p�ƌ����̎��Y���l�̍��ق̘b�Ƃ��Ă̈Ӗ����������Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪1999�N�㔼�ɓ���ƁA�R�z�V�������͂��߂Ƃ���S���̃g���l���̕������̂��������B�K���A�����ΏۂƂ��Ă����S�����Ǝ҂ł͂����������͔̂������Ȃ��������A���S�m�ۂ̂��߂̔���ȃ����e�i���X�E�R�X�g�̕K�v���������̂��̂ƂȂ��Ă���ƁA�����̖{�����p�������n�߂�B���Ȃ킿�A�S���Ɍ��炸�A�{�݂̌��݂͒����̃g�[�^���E�R�X�g�ōl����ׂ��ł���A����ɂ͏��Ȃ��Ƃ��u���݃R�X�g�{�����e�i���X�E�R�X�g�{�x�������v�ōl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���������O�̎����ł���B���Ƃ����݃R�X�g�������ς�ł��A����̃����e�i���X�E�R�X�g��������A�g�p���Ԃ������ɂȂ�Ȃ�قǃg�[�^���E�R�X�g�͒��ˏオ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�����āA���������̂悤�ȗL���q�����̔�d���傫���Ȃ�A�x�������͔���Ȃ��̂ƂȂ邾���ł͂Ȃ��A������E���Ă��܂��A�ǂ�Ȃɉc�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă��A�L���q���͐�B�����ɖc��オ���Ă������ƂɂȂ�B
�@�����e�i���X�E�R�X�g��L���q���̔䗦�̍����{�݂ɂ��ẮA����̈ێ��Ǘ���ؓ����ԍςɏd�_��u�������Ƃ̃p�b�P�[�W�Ƃ��ăr�W�l�X�ōl����K�v�����邩������Ȃ��B��������A���������{�݂̌��݁E�^�c�͖��Ԃɂ܂����Čo�ϐ���Nj������������悢�Ƃ����悤��PFI (private finance initiative)�I�ȃA�C�f�A�����܂�Ă���[95]�B���邢�́A�⏕�����g���Č��݂��ꂽ�{�݂��A�����\�肳��Ă����������������X�V����K�v�ɔ���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����e�i���X���s�K��������A�����ӂ����肵�����ʂ��Ƃ��āA�lj��I�ȕ⏕���̎x�o�����ۂ��邱�Ƃ��l������[96]�B
�@�����ł̎咣�́A����Ӗ��ł͑S��������O�̂��Ƃł���B����͉�v�����@�̌����Ώۂ��A���́A�����I�ɑ��݂��鎑�Y�ł���u���m�v�����ł͂Ȃ��A�{���I�ɂ́A���݁E�擾����n�܂��Ē����I�Ȉێ��Ǘ������Ď��x�܂ł��܂߂����ƁA�܂�u�r�W�l�X�v�Ƃ��Ă̍L����������Ă���Ƃ������Ƃł���[97]�B�Ƃ��낪��2�߂Ō���悤�ɁA�]���̉�v�����@�̌����́A��ʂɁA�ڂ̑O�̃��m�Ɏ��삪���肳�ꂪ���ł������B��O�I�Ȃ̂͋�3���Ђ̌����ŁA���c���O������Ɍ����̒��Ɂu�r�W�l�X�̌����v�I���z��f�ГI�ɂł͂��邪���o�����Ƃ��o����B��3���Ђ̌������@�͕č�GAO (General Accounting Office)�^�̗L�����������ƌ^�������u���������̂ł͂Ȃ��A�ނ��낱��܂ł̉�v�����@�̌����\�͂ƌ����}�C���h���ێ��������ōs���Ă������̂ł���B��3�߂ł́A���̉�������Ńr�W�l�X�̌����̖G�肪�����邱�Ƃ��������B
�@�r�W�l�X�̌����́A��v�����@�̌����}�C���h�̉�������Ɉʒu����ɂ�������炸�A�����Ώۂ��r�W�l�X�Ƃ��ĂƂ炦��ɂ́A����܂ł� (1)���m���A(2)���K���A(3)�o�ϐ��E�������A(4)�L�����Ƃ����������̊ϓ_�Ƃ͈قȂ�ϓ_�E���_���K�v�ɂȂ�B���ꂪ�u�g�[�^���E�R�X�g�̎��_�v�ł���B�g�[�^���E�R�X�g�̎��_���猩��A����܂łƂ͑S���قȂ錟���̃|�C���g�������яオ���Ă���͂��ł���B�Ⴆ�A�{�݂̌��݂��̃g�[�^���E�R�X�g�ōl����ƁA���Ȃ��Ƃ��u���݃R�X�g�{�����e�i���X�E�R�X�g�{�x�������v���܂߂ăg�[�^���E�R�X�g���l����K�v���o�Ă���B���������Ȃǂ̗L���q�����𗘗p�����ꍇ�ɂ́A�ʏ�l�����Ă���ȏ�Ɏx���������傫�ȃR�X�g�v���ɂȂ�̂ł���B����͒P�� (3)�o�ϐ��E������ ���l����ۂ̃^�C���E�X�p������蒷���ɐݒ肷��Ƃ������x�̈Ⴂ�����ɂ͂Ƃǂ܂�Ȃ��B�������B�X�L�[���̐�����܂߂����f���v�������B�����ő�4�߂ł̓r�W�l�X�̌����̃|�C���g�Ƃ��āA���S�̌o�c�j�]������Ƃ��Ď������B�X�L�[���̏d�v����_���A����Ƀr�W�l�X�̃��C�t�E�T�C�N�����ӎ������V�����r�W�l�X�����̃X�^�C���ɂ��Ă��l�@�������B
�@�]���̉�v�����@�̌����́A��ʂɁA�ڂ̑O�̃��m�Ɏ��삪���肳�ꂪ���ł������B�Ⴆ�A���c(1995)�́A1968(���a43)�N�x����1993(����5)�N�x�܂ł�26�N�Ԃ̌��Z�����̑S�f�L����(3853��)���ϓ_�ʂɕ��ނ��Ă��邪[98]�A���̌��ʂ́A�u���K���v(2920�� 75.8%)�A�u�o�ϐ��E�������v(780�� 20.2%)�A�u�L�����v(153�� 4%)�ƈ��|�I�ɍ��K�����������������̂ł���B�܂�A�����H���̃n�[�h�ʂŎ{�H��o�������_�E�v���E�d�l���ʂ�ł��邩�ǂ����Ƃ����s�������̒��o�����S���������ƂɂȂ�B
�@�����������ɕ\5-1�̂悤�ȌX�������炩�ɂ����B�܂�A���{�̉�v�����@�̌��������ł́A1980�N��ȍ~�ɁA���K����������o�ϐ��E�����������ւ̈ڍs���N����A���̌��ʁA���݂ł́A���n�����ɂ���ċɗ͎{��ɑ��錴�f�[�^�����W���Ď��ԉ��P�̂��߂̏��u��v������悤�ɂȂ����Ƃ����̂ł���B
�\5-1. ���������ɂ�����ϓ_�̔�r
| ���{�̉�v�����@ | �č���GAO | ||
|---|---|---|---|
| 1960�N��̍��x�������܂� | 1980�N��ȍ~ | 1974�N�ȍ~ | |
| ��Ȍ����Ώ� | �����H���̃n�[�h�� | �Љ�ۏ�̃\�t�g�� | �A�M���{�̃v���O���� |
| �ϓ_ | ���K������ | �o�ϐ��E���������� | �L�������� |
| �d�������@�\ | �ʕs���������o | ���u�v��(���Ɖ��P) | ���� |
| �������e | ���z�̑傫�����̂�I�сA�����H���̎{�H��o�������_�E�v���E�d�l���ʂ�ł��邩������ | �N���Ɍ�����1�N�Ԏ��{���錟���e�[�}�⎖�Ǝ�ڂȂǂ�ݒ肵�āA���n�����Ŗ��_���W�� | GAO�łȂ���Γ���ł��Ȃ��悤�Ȗc��ȃf�[�^����F����q�A�����O���s���āA���ɐM�ߐ��̍����f�[�^����� |
�@���������ϓ_�ʂɌ��������̎d���́A��v�����@���g�ɂ���Ă��s���Ă���B1997�N�ɏo���ꂽ�w���{�����@���̉�v����50�N�̂���݁x(�ȉ��w����݁x�Ɨ��L)�ɂ��A�����̊ϓ_�́A�����E���Ƃ̕�����v�o���̓��e���ɉ����ėl�X�ł��邪�A�����̌ʋ�̓I�Ȋϓ_�����ʂɔF�߂��鐫���ɂ���ʂ���ƁA(1)���m���A(2)���K���A(3)�o�ϐ��E�������A(4)�L�����̎l�ɕ��ނł���Ƃ���Ă���B���̂����A�o�ϐ�(economy)�A������(efficiency)�A�L����(effectiveness)�̊ϓ_����̌����́A���̓��������Ƃ���3E�����Ƃ��Ă�Ă���B�����Đ��́A�����ނˁA���K���𒆐S�Ƃ��錟������A�o�ϐ��E�������ɂ������ɒ��ӂ������ցA�����Ă���ɂ͌o�ϐ��E�������ɗL������������3E�������d�����錟���ւƓW�J���Ă���Ƃ����傫�ȗ��ꂪ���Ď���Ƃ���(p.47)�B
�@�������A�o�ϐ��E�������̌����ւ̓W�J�ɂ��Ă͔[���������邪�A�ʂ����ē��{�̉�v�����@��GAO�^�̗L�����������u�����Ă����̂ł��낤���B�č��ł́A1974�N�̋c��\�Z���ۓ����@�ɂ���āA�A�M���{�̃v���O������]�����A���̌��ʂ��c��Ɋ�������@�I������������GAO�ɗ^����ꂽ�B���̌��ʁAGAO�łȂ���Γ���ł��Ȃ��悤�Ȗc��ȃf�[�^����F����q�A�����O���s���āA���ɐM�ߐ��̍����f�[�^�����Ƃ������@�\���d�������L�����������s����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���B���{�ł́A�L���������ɒ��ڑΉ����Ă���̂́u���L�����v�ł���Ƃ������邪�A���������Ƃ炦���ɂ͌�q����悤�ɋ^�₪����B�܂����L�����́A�ߔN�ނ��댏���ł͌����X���ɂ���A�ƂĂ��u�W�J���Ă���v�ƌ`�e�ł���قǂɂ͏\���ɗ��p����Ă��Ȃ��B
�@�����ŁA���ɋ�3���Ђ̗�������A3���Ђ̌������@��GAO�^�̗L�����������ƌ^�������u���������̂ł͂Ȃ��A�ނ��낱��܂ł̉�v�����@�̌����\�͂ƌ����}�C���h���ێ��������ōs���Ă������ƁA�����Ă��̉�������ŁA���c���̑O�ɂ����Ă����A����3���Ђ̌����̒��Ɂu�r�W�l�X�̌����v�I���z��f�ГI�ɂł͂��邪���o�����Ƃ��o����Ƃ������Ƃ��������B
�@���ɂȂ��āA����܂ō��̎��ƂƂ��č��̓��ʉ�v�ɂ��^�c�`�Ԃōs���Ă����ꔄ����(�呠�Ȑꔄ��)�A�S������(�^�A��)�A�d�M�d�b����(�d�C�ʐM��)�́A���ꂼ��1949(���a24)�N6���ɓ��{�ꔄ����(�ȉ��u�ꔄ�v�Ɨ��L)�A���{���L�S��(�ȉ��u���S�v�Ɨ��L)�A1952(���a27)�N8���ɓ��{�d�M�d�b����(�ȉ��u�d�d�v�Ɨ��L)�Ƃ��Č������Ƒ̂̎��ƂɈڍs�����B
�@�����3���Ђ́A���{���S�z�����̏o���ɂ����̂ł��������Ƃ���A�K�v�I�����Ώےc�̂ƂȂ����킯�����A���Љ�����s�������S�Ɛꔄ�ɑ��鏑�ʌ����ɂ��ẮA���S�Ɛꔄ���������Ƒ̂Ɉڍs���钼�O�A1949(���a24)�N5���ɒʒB���ꂽ�v�Z�ؖ��Ɋւ���w��ŁA�u���̍s���@�ւƂ��ď]���̂Ƃ���v�Z�ؖ���v����v���̂Ƃ���Ă����B�Ƃ��낪��1950(���a25)�N�ɁA��v�����@�ɑ���GHQ����A��v�����ɂ���Č��Ђ̔\���I�ȉ^�c��j�Q���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�č��ɂ�����������Ƒ̂̌����̕��@�P���邱�Ƃ��������ꂽ�B���ꂪ�u��ƌ^�����v�ƌĂ����̂ŁA��Ƃ̌o�����x�y�ѓ����������x���ᖡ���A�������\�����ԑ��v�ƍ�����Ԃ�K���ɕ\�����Ă��邩�ۂ��ɂ��Ĉӌ���\�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B�܂�A���F��v�m������Ƃɑ��čs���č��Ɠ��l�̂��̂ł���B���̏ꍇ�A�X�̎����A�x�o���̎���ɂ��Ă͒��o�����ɂƂǂ߁A�����̐����ȋᖡ�͓����č��Ɉς˂邱�ƂɂȂ�B����GHQ�̎������āA��v�����@��1951(���a26)�N4���ɁA���S�Ɛꔄ�ɂ��āu��ƌ^�����v�̓��������߂��̂ł���[100]�B
�@���̊Ԃ̌o�܂Ɋւ��āA���S�ɂ��Ắw���S�j�x�ɂ���ė��t���邱�Ƃ��ł���B���S���̋L�q�ɂ́AGHQ�͓o�ꂵ�Ȃ��B���S���́A�Ɨ��̎Z�����Ƃ������Ƒ̂Ƃ��Ă̋Ɩ��^�c�̎��含���d�����A��Ɣ\������э��������ɂ��̏d�_���u�����ׂ��ł���Ƃ������_�Ɋ�Â��A1950(���a25)�N3��7���Ɍo���ǒ����������āu��v�����@�̌������j�̉�������]����v��������v�����@�ɒ�o���A�v�Z�ؖ�������\�Z�W���ށA�����S�s�v�Z���A�����v�揑�A�����������Z�\�A���Z�A�������\(���v�v�Z���E�ݎؑΏƕ\����э��Y�ژ^)����ѓ���̉�v�s�ׂɊւ���؋����ނɌ��肷��悤�ɗv�]�����B����ɑ��āA��v�����@����A1950 (���a25) �N4��1���́u���a25�N�x�ȍ~�̌v�Z�ؖ��ɂ��āv�������č��S���̎�|�ɂ��v�Z�ؖ��̎w����s���\��ł���Ƃ̒ʒm���Ă���(�w���S�j�x��12��p.927)�B
�@�����������ŁA��v�����@�́A���S�̍������\�̐M�ߐ��ɏd��ȊS�������A����������A�n���ɂ����鎎�Z�\�̋L�^�v�Z�ɂ��āA���̐��m�x�𑪒肷����j�𗧂āA1950(���a25)�N11�����{�����1�T�Ԃɂ킽��A���É��n���o������������т��̌��Z�����̊e�@�ւɑ��āA���Љ���ŏ��̉�v���������{���ꂽ�B���̉�v�������s�̌��ʂ��āA��v�����@�����1951 (���a26) �N4��25���Ɂu���a26�N�x�ȍ~�̌v�Z�ؖ��ɂ��āv�ŁA1951(���a26)�N�x����A�����銯����v�ɂ����錻������ѕ��i�̏o�[�𒆐S�Ƃ��錟���ł͂Ȃ��A�������\�Ƃ��̎�������ьo�����ړI�Ƃ����Ɖ�v�I�Ȍ����ɐ�ւ���|�̒ʒm���������B�����⑫����`�łقړ������A1951(���a26)�N5��15���ɉ�v�����@�����������獑�S���ق��ĂɁu�����č����x�̋����[���Ɋւ��錏�v�Ƃ��āA���̗v�����������B
�@�u���S�ɑ��錟���ɂ��Ă̌v�Z�ؖ��ɂ��ẮA���a26�N4���Ɏw�肵���ʂ�ł��邪�A����͍��S�����ɂ���������č����x����щ^�p�������̌��ʂ������邱�Ƃ�O��Ƃ��ďؖ����@���ȈՉ����ꂽ���̂ł���B�������A���Јڍs��A���S�̓����č����x�̐����E�m���ɓw�͂����Ă��邱�Ƃ͗��m����Ƃ���ł��邪�A���݂ɂ����Ă͊č����̈����E�f�{�E�����e���ʂ̋��͂̓_���ɂ��āA�Ȃ��\���łȂ��_��������̂ŁA�����̎����ɂ��āA�����E�n���Ƃ���w�̔z�����]�܂����B�v
�@�������A���̗v���ƍ��S�Ď@�����҂̓w�͂ɂ�������炸�A���̓����č��@�\���[�����邱�Ƃ͂ł����A�킸��1�N���1952(���a27)�N7��1���Ɂu���{���L�S���̌v�Z�ؖ��Ɋւ���w��ɂ��āv����v�����@�����獑�S���قɎ��B����A�����E�x�o�Ɉ����z�ȏ�̏؋����ނ̒�o���߂����ƂŁA�����č��̋�����O��Ƃ�����Ɖ�v�I�Ȍ����͂����ɏI�~����ł����̂ł���(�w���S�j�x��12��pp.927-929)�B
�@�������č��S���̐����ɂ��A�����č��@�\�̏[���Ɏ��s�������ƂŊ�ƌ^�����͂����ɏC������Ă��܂��̂����A��������̉�v�����@���́A��ƌ^�����̏C���̗��R�Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���[101]�B
�@2��3�ɂ��Ă͍��S���Ƃ̃j���A���X�̍��������邪�A������ɂ���A����������A�̗��R����A��ƌ^�����͏C������A1953(���a28)�N2���ɂ́A��������c�Łu���̉�v�Ɠ��l�ɕs�������̌������s���A����ɉ����č������\�̊č��y�ьo�c�\���č����s���v���Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂�A���c���Ɠ����Ɠ��l�̕����̌������s���������A�������\�̌�����o�c�\���̌������s�����ƂɂȂ����̂ł���B���̕��j�́A1985(���a60)�N�ɐꔄ��JT�ɁA�d�d��NTT�ɖ��c������A1987(���a62)�N�ɍ��S�����q�S����Ђł���JR6�ЂƓ��{�ݕ��S��(JR�ݕ�)�̌v7�Ђɕ������c�������܂ł́A�����ɂ͊�{���j�̒��Ō�������邱�ƂɂȂ�B
�}5-1. �S�̂̕s�������̌����̐���
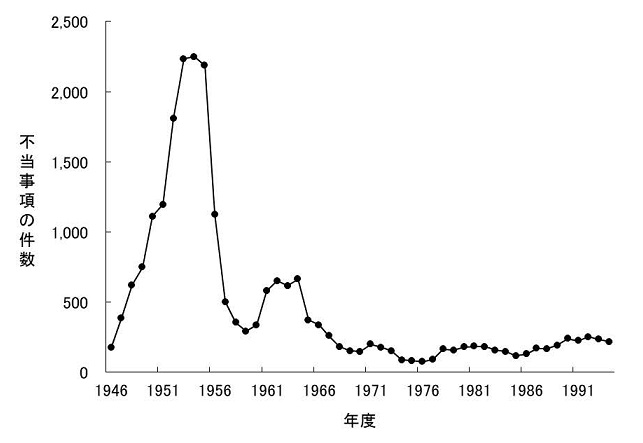
�@�������A�������������̎d���ɂ͋^����c��B��ƌ^��������߂����R�Ƃ��ĉ�v�����@���������Ă��闝�R�͔[�����ɖR�����̂ł͂Ȃ����낤���B���R��2�Ŏw�E���Ă���悤�ɁA�����A���F��v�m�Ɠ����̍������\�č��\�͂̂��钲���������������������Ȃ������Ƃ����͎̂����Ƃ��Ă��A��v�����@�����̌�����������l�ނ��̗p�������͈琬���悤�Ƃ����`�Ղ��Ȃ�[103]�̂͂Ȃ����낤���B����������ƌ^������������肪�Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���ہA���R��3���������͂��̖��c���ȍ~���A��ƌ^�������̗p���钛������݂��Ȃ��B3���Ђ̖��c���܂��āA1987(���a62)�N5���ɁA��v�����@�ŁA�����Ђ̌����͂ǂ�����ׂ����̌������s��ꂽ�ۂɂ́A���c���̎�|��F�����A�o�ϐ��E�������̊ϓ_����̌����A�Ƃ�킯��Ќo�c�������I�ɍs���Ă��邩�Ƃ����_�ɏd�_��u���Č������邱�ƂƂ��ꂽ�Ƃ�����B�����Ė��c����́A�o�c��̌����������߂�w�E���قƂ�ǂɂȂ�ƂƂ��ɁA�����i�K�ł��A���Ƃ��ƂɎ��v���𖾂炩�ɂ���悤�Ȏ����̒�o����v�����@�������߂邱�Ƃ������Ȃ��Ă��Ă���Ƃ͂����Ă���B�������A���ۂɏo���������̂́A�Ⴆ�A���S�̏ꍇ�A���c������JR�ɂȂ�������Ɍ���ꂽ�A���̂悤�Ȏ��S�Ƃ̔�r���x�[�X�ɂ����w�E�ł���B
�@���̂���1��JR 6�Ђɑ��āA2��JR�����{�ɑ��Ă̂��̂ł���B���̂悤�ɑ��ЂƂ̔�r�ɂ���ĉ��P���T��Ƃ������@�̓x���`�E�}�[�L���O�ƌĂ�A���Ԋ�Ƃł͈�ʓI�ɗp�����Ă����@�ł���B���������F��v�m���s���悤�Ȋ�ƌ^�����ł͂Ȃ�[104]�B ��v�����@������������ƌ^������������肪�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ́A���R��1�ɂ��Ă���������B�m���Ɍ��Д��������́A�w�E�̂悤�ɁA���̓I�ɐ�����v�����v�o�����������Ă����B������1962(���a37)�N�ȍ~�A����܂ł̕s���o���E����ӓ|�̌�������A���L���A�s�K�ؕs�����ȉ�v�o���ɂ��āA���̔���������T�����āA���P��}�邽�߂̈ӌ��\���E���u�v�����w�������������ϋɓI�ɍs����悤�ɂȂ��Ă������Ƃ��w�E����Ă���(�w����݁xp.48)�B���̂��Ƃ͐}5-1�ɂ������Ɍ���Ă����B
�@�������{���ɁA�s�����������ɑ����������߂Ɋ�ƌ^���������Ȃ������̂ł��낤���B�m���ɐ}5-1�Ɛ}5-2���r����ƁA3���Ђ̕s�������̌����̃s�[�N�́A�S�̂��������A���S�A�ꔄ�ɂ��Ă͌��Љ��������N�x��1950(���a25)�N�x�A�d�d�ɂ��Ă͌��Љ�����2�N���1954(���a29)�N�x�ɂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A���̌�A�s�������̌������������Ă����Ă��A���K����������o�ϐ��E�����������ւƂ����P�Ȃ�ϓ_�̈ڍs�����N����Ȃ������̂ł���B��ƌ^�����ւ̈ڍs�͋N����Ȃ������B�Ȃ��s�������̌������������Ă����ɂ�������炸�A3���Ђɂ��Ċ�ƌ^�����Ɉڍs���Ȃ������̂ł��낤���B��ƌ^�������C�������̂́A�s�������������������߂Ƃ��������A�ނ���A��v�����@���ݗ��������玝���Ă���ӔC�Njy��`������Ƃ��Ẳ�v�����@�̌����}�C���h�Ɗ�ƌ^�����Ƃ����e��Ȃ��������߂Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�}5-2. 3���Ђ̕s�������̌����̐���
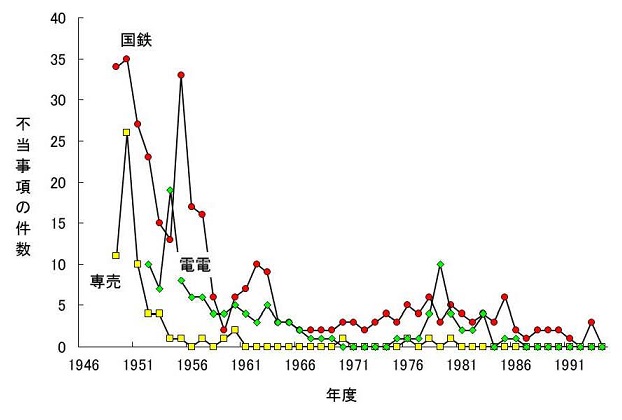
�@�����A���̌�A���R��2,3���Ȃ��Ȃ����킯�ł��Ȃ��̂ɁA���ۂɂ́A���Љ������25�N���o�߂��������疯�c���܂ł̊Ԃɂ́A�������\��̌o�c���т������Čo�c�\���肷�邱�Ƃ��s���Ă����̂ł���B���̊Ԃ̂ق�10�N���炢�̊��Ԃł́A��ƌ^�����̌`���܂��ɁA���v���A��萳�m�ɂ͒����I�Ȏ��x�̌o�ϐ�������Ă���A�u�r�W�l�X�̌����v�I���z�Ŋe���Ђ̌o�c�S�̂��Ƃ炦�Ă��̂������Ƃ����p��������n�߂Ă���B
�@�Ⴆ���S�ɂ��Č����A
�Ƃ����A������u�V���[�Y�v���o������B����3, 4, 5�́u�O����v�Ƃ��Ă�A���N�v��I�ɉݕ��A�ו��A���q�ƕ�����ڂ��Ȃ�����L�������f�L����Ă���B
�@�܂��ꔄ�ɂ��ẮA
�@�����āA�d�d�ɂ��Ă��A
�Ƃ����w�E���s���Ă���B���̑��A3���Ћ��ʂ̂��̂Ƃ��āA3���В��c�a�@�̉^�c�ɂ���(1977(���a52)�N�x���Z������, pp.213-216, ���L)�̎w�E���Ȃ��ꂽ�B
�@����ɂ́A1975(���a50)�N�x���Z����������L�����Ƃ��Ė���N���邱�Ƃ��n�܂����Ƃ����w�i������B���̑S�̓I�ȗ�����āA3���Ђɂ��Ă��A���̍�����A��������悤�ɁA���L�������o�ꂵ�������̂ł���B�������A������ϓ_�̐��ڂƂ��ĂƂ炦�A���L������L���������ɑΉ������邱�Ƃɂ͋^�₪����B�č��ł́AGAO�łȂ���Γ���ł��Ȃ��悤�Ȗc��ȃf�[�^����F����q�A�����O���s���āA���ɐM�ߐ��̍����f�[�^�����Ƃ������@�\���d�������L�����������s����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���B�������A��������GAO�̒����^�̗L���������ɑ��āA���{�̉�v�����@�̓��L�����́A�Njy�^�̌����}�C���h�����̂܂ܔ��f�������̂�����ł���B
�@�܂�A���n�����ɂ���ċɗ͌��f�[�^�����W���悤�Ƃ��Ă���ۂɑ��������l�X�ȁu�����Ȃ����Ɓv�u�������Ɓv�A�Ⴆ�A���S�ł́A�����g�������d�ŁA��������ɂ����ꋦ�c����K�v������A�@�B���w�����Ă����ꋦ�c������Ȃ��ē������Ȃ��悤�ȏ��p�ɂɌ���ꂽ�B�������A�����������Ƃ͍��S���ǂ̓w�͂����ł͉����ł�����̂ł͂Ȃ��A�ʂ̕s�������Ƃ��Ă͐��藧���ɂ����B�܂�Njy���Ă����Ă��A���Z�����ɂ͌f�L���邱�Ƃ��o���Ȃ��B�����ŁA�������ʂ̔����Ƃ����ϓ_����A����܂łɑ������Ă����l�X�ȁu�����Ȃ����Ɓv�u�������Ɓv����L�����Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă������Ƃ������ʂ��������̂ł���B���������Ċ�ƌ^�����Ƃ������^�̗L���������Ƃ����z��A�v���[�`�̎d�����܂������قȂ���̂��������ƂɂȂ�B
�@�����ɂ́A�s��������₤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����I�Ȏ��x�̌o�ϐ���₤�Ƃ������ƂɎp��ς����Njy����p��������A��v�����@�̌����}�C���h�f�����u�r�W�l�X�̌����v�I���z�̂��̂ł��������Ƃ��킩��B�����āA�����Ɋ�ƌ^�����̓���������߂��ő�̗��R���������Ǝv����B��v�����@���|���Ă��������\�͂��R�A�\�͂Ƃ��čl�����Ƃ��A��v�����@�̌����}�C���h�̉�������ɂ́A��ƌ^�����͑��݂��Ȃ��BGAO�^�̗L�������������݂��Ȃ��B�{�e�Ŏ咣����悤�ȃr�W�l�X�̌��������������Ă���̂ł���B
�@������������܂���ƁA�č�GAO�^�̗L�����������ƌ^�����Ƃ͈�����������������Ă���B���̂��Ƃ����Ċm�F���Ă������B
�@�܂��ŏ��ɁA��v�����@�̌����Ώۂ́A�����I�ɑ��݂��鎑�Y�ł���u���m�v�����ł͂Ȃ��A�{���I�ɂ́A���݁E�擾����n�܂��Ē����I�Ȉێ��Ǘ������Ď��x�܂ł��܂߂����ƁA�܂�u�r�W�l�X�v�Ƃ��Ă̍L����������Ă���̂��Ƃ������Ƃł���B���́A���K����������̂ƂȂ��Ă�������H���ł����A�m���Ɍ��Z�����Ɍf�L����Ă���̂̓��m�̖��ł��A���Ӑ[���ώ@����A�ӔC��Njy����Ă���͎̂��Ǝ�̂̑g�D�ł���A���m�Ɍ�������܂ł̎��ƑS�̂̃v���Z�X�����Ƃ���Ă��邱�Ƃɂ����ɋC�����B�ɂ�������炸�A�����̌��Z�����ł́A�����Ώۂ����m����r�W�l�X�ւƍL���邱�Ƃ��S�O�������A��3���Ђ̎���̂悤�Ȉꕔ�̗�O�������āA���I�؋��������邱�ƂɏI�n���Ă����̂ɉ߂��Ȃ�[105]�B
�@���ɁA�u�r�W�l�X�Ƃ��Č�������v�Ƃ��������������A���́A��v�����@�ɂƂ��đS�����m�̗̈�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�ނ���A���n�����ɂ���Č��f�[�^�����W���āA���ԉ��P�̂��߂̏��u��v������Ƃ����A����܂Ŕ|���Ă�����v�����@�̌����}�C���h�̉�������Ɉʒu������̂ł���[106]�B���ɉ�v�����@�̈ꕔ�ł́A���̌o���ƃm�E�n�E��~�ς�����悤�ɂ�������B�������A���m�̌������K�v�s���ȃT�u�v���Z�X�Ƃ��Ă��̒��ɑg�ݍ��܂�Ă���ׂ��ł���B���������u�r�W�l�X(�Ƃ���)�̌����v���A�x���`�E�}�[�L���O�I�Ȏ�@����Ƃ��Ă��A���F��v�m������悤�Ȋ�ƌ^�����Ƃ͖{���I�ɈقȂ邱�Ƃɂ͒��ӂ�����B
�@��O�ɁA���m�̌����ɏI�n����p���́A�s�����������ɑ������������ɂ́A����Ȃ�ɐ��������邱�Ƃ��ł������낤���A�}5-2�ł�������Ă����悤�ɁA1970�N��ȍ~�A���̎��Ƃ�����Ӗ��Ő��n���̎������}���A�s�������̌������̂����������������Ă�����ł́A�čl��v����Ƃ������Ƃł���B�܂�A���m�̌�������r�W�l�X�̌����ւƑ傫�����ݏo�������ɗ��Ă���ƍl������B���܂������m�̌����ɕ�������p������E�炵�āA�r�W�l�X�̌����ւƓ��ݏo���A���W������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�r�W�l�X�Ƃ��Č������邱�Ƃ������A����ȁu�����Ȃ����Ɓv�u�������Ɓv�ɑ��āA������ۂ��ĉ�v�����@�̌����}�C���h��������B��̕��@���ƍl������B
�@���̂悤�ɁA�r�W�l�X�̌����́A��v�����@�̌����}�C���h�̉�������Ɉʒu���錟���ł���B��������ς���A���m����r�W�l�X�Ɍ����Ώۂ��L��������Ƃ����āA��v�����@�̌����}�C���h�ɓ��ɕω������߂���킯�ł͂Ȃ��B�������A�ɂ�������炸�A�����Ώۂ��r�W�l�X�Ƃ��ĂƂ炦��ɂ́A�O�q��(1)���m���A(2)���K���A(3)�o�ϐ��E�������A(4)�L�����Ƃ����������̊ϓ_�Ƃ͈قȂ����ϓ_�E���_���K�v�ɂȂ�B���ꂪ�u�g�[�^���E�R�X�g�̎��_�v�ł���B
�@�g�[�^���E�R�X�g�̎��_���猩��A����܂łƂ͑S���قȂ錟���̃|�C���g�������яオ���Ă���͂��ł���B�Ⴆ�A�{�݂̌��݂��̃g�[�^���E�R�X�g�ōl����ƁA���Ȃ��Ƃ��u���݃R�X�g�{�����e�i���X�E�R�X�g�{�x�������v���܂߂ăg�[�^���E�R�X�g���l����K�v���o�Ă���B���Ƃ����݃R�X�g�������ς�ł��A����̃����e�i���X�E�R�X�g��������A�g�p���Ԃ������ɂȂ�Ȃ�قǃg�[�^���E�R�X�g�͒��ˏオ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�����āA���������Ȃǂ̗L���q�����𗘗p�����ꍇ�ɂ́A�ʏ�l�����Ă���ȏ�ɋ������傫�ȃR�X�g�v���ɂȂ�̂ł���[107]�B
�@�������A���̋������S�́A�������B�X�L�[���������`�F�b�N����A��r�I�e�ՂɎ��O�Ɏ��Z���邱�Ƃ��ł��A���z�̍����𖢑R�ɉ�����邱�Ƃ��\�ł���B�����ŁA�܂��͑�1�͂Ŏ��グ�����S�̌o�c�j�]�̎���ɖ߂��āA�������B�X�L�[���̏d�v���Ǝ��O�����̉\�����w�E���A�g�[�^���E�R�X�g�̎��_�̈Ӌ`���咣�������B���̏�ŁA�r�W�l�X�̃��C�t�E�T�C�N�����ӎ������V�����r�W�l�X�����̃X�^�C������邱�Ƃɂ��悤�B����́A�X�̎��Ɩ��ɁA������x�����I�Ȏ��Ԃ��l���������O�̌����v�����b�Ƃ���悤�Ȍ����X�^�C���ł���B
�@���S�̌o�c�j�]�̌����Ƃ��Ă͗l�X�ȗv�����������Ă���B��������1�͂ł��w�E�����悤�ɁA���ڂ̔j�]�����́A���S��1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v�悪�A���������������B�X�L�[���̒i�K�Ŕj�]���Ă������Ƃł������B���������̂��Ƃ����S���g���F�����Ă������Ƃ������ł���B���Ȃ킿�A1963(���a38)�N5��10���ɍ��S����ψ�����S���قɒ�o�����u���S�o�c�݂̍���ɂ��āv�ł́A1970(���a45)�N�x�̌o�c��Ԃ����Z���A�ؓ����̏��ҁE�������Ȃǂɂ��u�o�c�̊��S�j�]�v���x�����Ă����̂ł���B
�@�ɂ�������炸�A��v�����@�͍��S�ɑ��Ĉ�̂ǂ̂悤�Ȍ��������Ă����̂ł��낤���B���͑�1�͂Ő������Ă݂����̂́A���ɏq�ׂ��悤�ɁA1970�N��㔼������L�����ō��S�̃V���[�Y���n�܂�ȑO��1973(���a48)�N�ɔ��s���ꂽ�w���S�j�x(��12��pp.161-173)�̒��ŁA���S���g�̎�ɂ���ċL�q����Ă������̂Ȃ̂ł���B����ǂ��납�A�w���S�j�x�̌������́A����ɂ���10�N�O��1963(���a38)�N5��10���ɍ��S����ψ�����S���قɒ�o�����u���S�o�c�݂̍���ɂ��āv�ł���A���ɂ��̒i�K�ŁA1970(���a45)�N�x�̌o�c��Ԃ̎��Z���s���A�u�o�c�̊��S�j�]�v���x�����Ă����̂ł������B�Ȃ���v�����@�͌o�c���j�]���Ă��܂������Ƃ��N�̖ڂɂ����炩�ɂȂ�܂ŁA�����w�E���Ȃ������̂��낤��[108]�B����ǂ��납�A���S�̃V���[�Y�̓��L�����ɂ����Ă����A��v�����@�͖c��ȍ��S�Ԏ��̍��{�����Ƃ������鎑�����B�X�L�[���̂ł���߂��ɑS�����y���炵�Ă��Ȃ��B1963(���a38)�N�ɂ́A���S���g���������B�X�L�[���̔j�]���w�E���Ă���ɂ�������炸�A�ł���B
�@�����ɁA�r�W�l�X�Ƃ��Ă̌�����������ă��m�̌����ɏI�n����Ƃ�����v�����@�̏]���̎p���̖��_�����m�ɂȂ�B�Œ���A�����@�́A�������B�X�L�[���̎��O����������ׂ��ł���B���{�̉�v�����@�ł́A�Ȃ������O�����͍s���Ă��Ȃ����A��4�͂ł��G�ꂽ�悤�ɁA�h�C�c�ł́A�������R�ɉ�v�����@���v��i�K�ł̎��O�������s���Ă���B���{�̉�v�����@�������邱�ƂȂ����O�������s���ׂ��ł���A���ɁA�����Ҏ��g����댯�M�����o����Ă���ꍇ�ɂ́A�����@�͎��O�����𗦐悵�čs���ׂ��ł���B���̍ۂ̃|�C���g�́A���炩�ɍ��K���ł͂Ȃ��B�������B�X�L�[���������ɍ��@�I�Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A���q�x�������܂߂����̕ԍόv�悪�j�]�������ƌv��Ȃǂ͏펯�I�ɍl���ăi���Z���X�Ȃ̂ł���B�ǂ�Ȃɔ�펯�Ȑ���ł��A�@����������Ă��܂��Εs�������Ƃ��Ďw�E����邱�Ƃ͂���܂��Ƃ����p���ɑ��āA��v�����@�͎���̌����}�C���h�ɗ����Ԃ��Č������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@�������B�X�L�[���̔j�]�����S�ɂ����炵�����̂́A�P�Ȃ�����I�Ȕj�]�ɂƂǂ܂�Ȃ������B��3�͂ł��݂��悤�ɁA�������킸�A���z�̗L���q�����𗘗p���čs����S�����݂Ƃ��̌�̓S���o�c�́A�����Ƃ̋����ł���B�L���q�����z�ƍH������(���m�ɂ͒��H����J�Ƃ܂ł̊���)�̗������ł��邾�����k���邱�Ƃ��̗v�ŁA�����Ȃ��A��2�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�S�����Ƃ̎��v�\�����̂��������Ă��܂��A���������̕⏕�����������q�⋋�ɂ������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B���S���o�c�j�]���������܂��ɂ������������A�S�����ݔ�̕s������Ȃ�������S�����ƎҎ��g�ɗL���q���Ƃ��Ď��Ȓ��B������Ƃ������Ƃ����Ղɑ��������Ă���ƁA�J�Ƃ܂ł̍H�����Ԃ̊Ԃɗ��q�ł���ɗL���q���̊z���c��݁A�S�����Ƃ��̂��̂̎��v�\���̈������J�ƑO�Ɍ���I�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��B�x�������ʼnc�Ɨ��v��������Ԃ悤�ȏ��ɒu����Ă��ẮA������c�Ɠw�͂�ςݏd�˂Ă����ꂸ�A�������c�Ɠw�͎��̂��Y�ꋎ���邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�@��v�����@�ɂł��邱�Ƃ́A���������X�L�[���̎��O��������ł͂Ȃ��B�g�[�^���E�R�X�g�̎��_�ɗ��Ȃ�A�r�W�l�X�̃��C�t�E�X�^�C���ɉ����������I�Ȍ����v���O���������ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���S�̂悤�ɁA�N���猩�Ă����z�̐Ԏ����o�������A�o�c���j�]���Ă��܂����悤�ȃP�[�X�����ł͂Ȃ��A���Ƃ��o�c�j�]�Ƃ������Ԃɂ͗�������Ȃ��Ă��A�r�W�l�X���ӎ�����������Ȃ��Ȃ�悤�Ȓi�K�͓����悤�ɂ���Ă��邩��ł���B���̂��Ƃ�d�d�ɂ��Č��Ă݂悤�B
�@�d�d�ł́A1977(���a52)�N�x�ɑ�5��5���N�v����I�����A������u�������d�b�v�Ɓu�����Ȃ���d�b�v��ڕW�Ƃ��������d�b�̐ϑ؉����ƑS��������������2��ڕW�����ꂼ��1977(���a52)�N�x��1979(���a54)�N3��14���ɒB�����ꂽ�B���̌��ʁA1982(���a57)�N5��17���̗Վ��s��������(�ȉ��u�Ւ��v�Ɨ���)��l����u�O���ЁA����@�l���݂̍���ɂ��āv�ɂ��w�E�����悤�Ȏ��̂悤�ȏ��o������(����, 1989a)�B
�@���Ȃ킿�A�d�d�̓d�b���Ƃɂ�����x�o����̌����̈�́A�o��̖�1/3���߂�l����ł���A1965(���a40)�N�x�ɂ͖�24���l�������v���K�͂��A1980(���a55)�N�x�ɂ͖�33���l��40%���������Ă���B����́A�����d�b�̐ϑ؉������߂����āA1970�N��O���̔N����300�������ɂ���ʉːݎ���ɑ啝�ɑ��������ێ畔��̗v������15���l�̑��݂��傫���B�Ւ��͂��̕ێ畔��̗v�����̏k���ƑS�������������B���ɂ���ĕs�v�ɂȂ�����蓙�̉^�p�v����6��6000�l�̏k�����K�v�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�����ėՒ��̎w�E��҂܂ł��Ȃ��A�d�d�̐l���������͗Ւ��ȑO����d�d�̎�ɂ���Ē��X�Ɛi�s���������̂ł���(����, 1989a)�B
�@�����������������i�s���Ă������ŁA1978(���a53)�N�x���Z�����̓d�d�̃J���o���E�J����c���̕s���o�������A������1979(���a54)�N�x���Z�ł̗\�Z�����A���Ђ̋K�����Ɉᔽ�������^�Ɋւ��镲�����Z����������B���̂��Ƃ́A���͐��n���ɓ����āA�o�c�`�ԂƎ��ƂƂ̊Ԃŕs�K�����N�����n�߂Ă���Ƃ�������߂ďd��ȃV�O�i���ł������B��v�����@���Ƃ��ẮA�s���o�������╲�����Z�́A�܂��ɔƍߍs�ׂł��낤�B�������A�����A�d�d��������s���o���Ɋւ����������Ƃ��������́A�P�ɘJ�g�W�̕s���f���Ă��邾���ł͂Ȃ��A�d�d�̏�����S�z���Ă����d�d�̐l�Ԃ��A�N����������đ�|�������Ăق����Ɗ���Ă����Ƃ������ʂ����肤��B�����āA���������s���̍������ɂ́A�u�d�d���Ђ̗��j�͍������̗��j�v�Ƃ����g�����ɂ���߂��悤�Ȋ��o�Ōo�c�������Ɗi�����Ă��������̓d�d�̎��g�݂ɑ��āA���ǂ͍��̉�v�Ɠ����g�g�݂ʼn�v�������Ă��܂����Ǝ��̂̌��E���������̂ł���B
�@�d�C�ʐM�Y�Ƃ̂悤�ɋZ�p�v�V�̌���������ɂ����ẮA�{�����Ԋ�Ƃł���A�������ɂ���ē���ꂽ���ʂ́A��Б��������̓����̂��߂ɓ������ۂ��邾���ł͂Ȃ��A�]�ƈ��̑��ɂ��A�x�[�X�E�A�b�v���ŊҌ����Ă����Ȃ���A�o�c�������ւ̏]�ƈ��̗����͓����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�d�d�ł͍������͗Վ����ɔ[�t���ƂȂ��Ă��܂��A�o�c���ɂ��E�����ɂ��Ȃ��Ҍ�����Ȃ������̂ł���B�����̌��А��x�̒��ł����E�����ɊҌ����悤�Ƃ���ƁA����͕s���Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�������A������Ƃ����ĕs���������������킯�ł͂Ȃ����A���А��x�ɂƂǂ܂����́A���������s���o�������͉��x�E������Ă��J��Ԃ���邱�ƂɂȂ�B���������F���́A���c�������̓d�d�̊����ɂ͋��L����Ă����悤�Ɋώ@���ꂽ�B
�@�����ɂ��A���c���ȑO��1982(���a57)�N2��26���̗Ւ���l����q�A�����O�ɂ����āA�d�d�́A���̌o�c�`�Ԗ��Ɋւ��āA���А��x���������A�����Е����A���c��Е�����3��������Ă���B���̓��e����������ƁA�d�d�́A���А��x���������ɂ����Ă����A�\�Z�����ɂ�鋋�^���z����p�~���邱�Ƃ����߂Ă���B�����āA����܂ŁA30���~�܂Ŗ����q�A������z���镔���ɂ̂�3%�̗��q�Ƃ������ɗa������߂Ď����^�p�̎��R�x���g�債�Ă����悤�ɋ��߂Ă���̂ł���B(����, 1989a)
�@���̂Ƃ��A���̗Ւ���l����q�A�����O�ł̌o�c�`�Ԃ̒쐬�Ɍg������d�d�̊����̈�l�́A���́A�s���o�����������A���܂��܋ߋE�d�C�ʐM�ǂɋΖ����Ă��Č��@�̎�蒲�ׂ��A���А��x�̌��E��Ɋ������Ƃ�����B�����āA���܂Ƃ߂��O��A���Ђ̗\�Z������̋c�����o�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ȏ�A����ȏコ��Ȃ鍇������i�߂邽�߂ɂ́A���͂���А��x�͎̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ɗo�債���Ƃ����B�������āA�d�d�������Љ��Ƃ����I��������_�@�Ƃ��āA���́A�����̉�v�����@�̌������A�����@�����F�����Ă���ȏ�ɔ��ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����̂ł���B
�@���̂悤�ȁu�Ǐ�v�̌����鐬�n���ɑ��āA�ɂ̗����グ���ł́A�ʂ̋����[���u�Ǐ�v������ꂽ�B���́A���S�E�ꔄ�Ɠd�d�́A���Љ��̎�����3�N�قǂ���Ă���ɂ�������炸�A�}5-1�ł����炩�Ȃ悤�ɁA���Љ������ŏ���2�`3�N�ɕs�������̌����̃s�[�N���}���Ă����̂ł���B�܂�A�����Љ������Ƃ��������ɂ͂�����炸�A�ǂ��ł��ŏ��̐��N�Ԃ͍������Ƃ�����悤�ȏɒu�����炵���B
�@���ہA1949(���a24)�N6���Ɍ��Љ��������S�̏ꍇ�A���������́A������Ƒ̂ɂӂ��킵����v���x�̊m���͏����Ɉς˂��A���ʂ̑[�u�Ƃ��đS���]�O�̒ʂ�̖@�߂��K�p����Ă���B���̔N12���̍��S�@�ꕔ�����̍ۂɉ�v���x�̕s���͐�������Ă��邪�A1953(���a28)�N8���̍��S�@������ʼn�v���x�̑�������s����܂ŁA�b��[�u�Ƃ��āA���L�S�����Ɠ��ʉ�v�@�A�����@�A��v�@����э��L���Y�@���K�p����Ă����̂ł���B���ۂɁA���S�@������ɂƂ��Ȃ��č��S�@�{�s�߂���������ꂽ�̂�1953(���a28)�N10���A���{���L�S����v�K������������ꂽ�̂�1954(���a29)�N10���A�����o���W�e�K�����������ꂽ�̂͂���ɂ��̌�Ƃ������ƂɂȂ�B�����܂łŊ���5�N���o�߂��Ă���B�����āA���S���e��̕W���E�v�̓����߂邱�ƂŁA�ώZ�̓���A���葱�̋ψꉻ���̌��ʂɂ���ĉ�v�����@�̎w�E��������������̂́A�����10�N���o�߂���1964(���a39)�N�x�ȍ~�̂��ƂɂȂ�̂ł���(�w���S�j�x��12��pp.589-591; pp.929-930)�B
�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ���A��3���Ђɂ��ẮA�Ǝ�⎖�Ɠ��e�A���Љ�����܂ł̗��j�Ƃ����_�ňقȂ��Ă���ɂ�������炸�A�������e���������A���̂悤�ȋ��ʂ������C�t�E�T�C�N��������Ƃ������Ƃ��w�E�ł������ł���B
�@���̂悤�ɁA��3���Ћ��ʂɃ��C�t�E�T�C�N���̂悤�Ȃ��̂�������Ƃ������ۂ́A�����Ώۂ��A�P�ɕ����I�ȃ��m�����������ꍇ�ɂ͋N���肦�Ȃ��B���Z�����Ɍf�L�������̂����m�̖��ł������Ƃ��Ă��A�����̑Ώۂ����L���r�W�l�X���邢�͎��Ƃ����������߂ɋN���肤�錻�ۂȂ̂ł���B
�@�����������C�t�E�T�C�N���S�̂��l���Č�������ɂ́AGAO�^�̗L���������Ƃ���ƌ^�����Ƃ��قȂ�u�g�[�^���E�R�X�g�̎��_�v����̃r�W�l�X�̌������K�v�ɂȂ�B�����Ē����I�ȃg�[�^���E�R�X�g�̎��_����l����A�r�W�l�X���邢�͎��Ƃ̃��C�t�E�T�C�N���̊e���C�t�E�X�e�[�W�ɉ��������̂悤�Ȓ����I�Ȍ����v���O���������z����Ă�����ׂ��ł���B
�@��������A��v�����@�̖����́A������ʂ��āA�����Ԃ̊ԂɎ��Ƃ𗧂��グ�邱�Ƃ���������̂ւƎ��I�ɕω�����\��������B
�@����ł́A�����グ�ɐ����������Ƃɑ��錟���͂ǂ̂悤�ɂȂ�̂��낤���B��3���Ђ̏ꍇ�ɂ́A���n�����}����ƁA���Ǝ�̂̐ӔC��₢�ɂ����O�I�v���ɋN�������肪�����Ă������߂ɁA�s�������̎w�E�Ƃ����`�͂Ƃ�ɂ����Ȃ�A�������ʂ̔����Ƃ������ϓ_����̓��L���������o�����̂ł���B����͊�{�I�ɓ����Ҕ\�͂�����Ă��邽�߂Əq�ׂ����A��萳�m�ɂ͎��Ȍ���̌���������Ă��Ȃ��������߂ɔ����������̂ł���B
�@��Ƃ́A���炠�������v�ɑ��āA������������錠���������Ă�������A���͑����䖝���Ăł����v�������A�����Ɠ������ۂ̌`�ŁA�����̊g�哊���̂��߂ɒ�����̂ł���[110]�B�����āA�Z���I�ɂ͑����̉䖝�����Ăł��A�����ł݂��Ƃ��̎����B�̗��v���ő剻���悤�Ƃ�����̂ł���[111]�B���ہA���c����̋����Ђ̃p�t�H�[�}���X����ɖ{���I�ɏd�v���������̂́u���Ȍ���v�ł������B
�@��3�͂ł��݂��悤�ɁA���c�����JR�����{�ɂ��Ă����̂��Ƃ͂����邪�A����Ɍ����ȗ��NTT�ł���BNTT�͓����Љ��ɂ���āA���v�E�����̏����E�^�p�Ɋւ��Đ��x�I�Ɏ��Ȍ���I�ł��邱�Ƃ�ۏ��ꂽ�̂ł���B����͎��̂悤�ɖ��c���O��őΏƓI�ɐ����ł���(����, 1989c)�B���Ȃ킿�A���c���O�܂ł́A
�@���ꂪ�A1985(���a60)�N�̖��c���ȍ~�́A
�Ƃ����悤�ɕς��B����͑傫�ȈႢ�ł���B
�@���Ƃ��A���^�̌����ɂ��Ă��A���c���O�́A�\�Z������̋c�����o�Ă����ɁA�\�Z�����ɂ�鋋�^���z�������������߁A���Ƃ��o�c�w�͂������āA�����ɗ]�T���o���Ă��A�]�ƈ�(�����͐E���ƌĂ�ł���)�̋��^����グ���Ȃ������̂ł���B���Ȃ݂ɁA�]�ƈ��̋��^�܂�l����͐��m�ɂ͗��v�̏����ł͂Ȃ��A���v���v�Z����O�̒i�K�̌o��Ȃ̂ŁA���^�̌���͒ʏ�̊�����Ђł͊��呍��̏��F����K�v�̂Ȃ������ł���B���c�����NTT�͂悤�₭���ꂪ�����ꂽ���ƂɂȂ�B�]�ƈ��͓d�C�ʐM�T�[�r�X�̋@�B���A�������Ɏ��g�݁A���̂��Ƃɂ���Đ������]�T�̈ꕔ�����݂̋��^�Ƃ��Ď�邾���łȂ��A�ꕔ�������B�̖����̓����̂��߂ɒ����邱�Ƃ̂ł��錠�����̂ł���B
�@���̗]�T�����◘�v�����ɓ������A���邢�͂ǂ̂悤�Ɏ����^�p����̂��ɂ��Ă��A���c����͂��Ȃ莩�Ȍ���I�ɂȂ����B1�̎��ƌv��ɂ͏o���E�����ɂ��Ă̋L�q�͊܂܂ꂸ�ANTT�����ł��o���E�����̗\�Z�g�Ƃ������͍̂��Ȃ������B�܂�A�L�]�ȓ����悳������A�\�Z�g�ɂƂ��ꂸ�^�C�~���O���̂������o���E�������ł���悤�ɂȂ�A�����̎��v����������x�m�ۂł���悤�ɂȂ����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A1985(���a60)�N�Ɂu���c���v���A�����Љ�����NTT���A1986(���a61)�N�ɏ�ꂷ��܂ł�100%���{�o���̌���Ƃł���A���݂�50%�ȏ�𐭕{���o�����Ă������������ƂȂ̂ł���B���́A�{���A����Ƃ�����Ƃ��͊�Ƃ̒����I�p�t�H�[�}���X�ɂƂ��Ă͂��܂�{���I�ł͂Ȃ��BNTT�̂悤�ɁA���v�E�����̏����E�^�p�Ɋւ��Đ��x�I�Ɏ��Ȍ���I�ł��邱�Ƃ�ۏ���邱�Ƃ������{���I�ɏd�v�Ȃ̂ł���B���v���z���グ��̂����Ƃł���A����ł���A����͌��Ǔ������ʂ������炷�B1960�N��㔼����̊��唽�v���ŕč��̌o�c�Ҏx�z�������Ƃ��̂��Ƃ��v���N�����悢(����, 1995)�B���Ȍ���I�ł��邱�Ƃ��A���{���I�ɏd�v�Ȃ̂ł���B�o�c�҂�����̐ӔC�ɂ����Đ헪�𗧂āA�g�D�����o�[�����ϓ��ɉE���������邱�ƂȂ������I�ɒ����I����ɗ����čs���ł��邱�Ƃ�ۏ���̂ł���B���{��`�Љ�ɂ����Č���ꂽ�o�c�Ҋv���A���Ȃ킿�o�c�҂Ƃ��ėL�\�ł���A���o�c�҂ł����Ă����ȉi���I�ł��肤��Ƃ������Ƃ��A���̂��Ƃ̏ے��I�o�����̈�������̂ł���B
�@�����āA���Ȍ��茴�����m�����ꂽ��ł��A�r�W�l�X�̌����͗L���ł���B���ɏq�ׂ��悤�ɁA��v�����@�ł�3���Ђ̖��c���܂��āA1987(���a62)�N5���ɁA�����Ђ̌�������Ќo�c�������I�ɍs���Ă��邩�Ƃ����_�ɏd�_��u���Č���������j��ł��o���Ă���B�����Ď��ۂɁA�Ⴆ���S�̏ꍇ�A���c������JR�ɂȂ�����ɂ́A���S�Ƃ̔�r���x�[�X�ɂ����x���`�E�}�[�L���O�̎�@�Ō������o����Ă����B����͖��炩�Ɋ�ƌ^�����Ƃ͈قȂ�B�����グ�ɐ����������ƁA�r�W�l�X�ɑ��āA�č�����č��@�l�̂悤�ɐڂ���̂ł͂Ȃ��A�ЊO�����I�ɃA�h�o�C�X�𑱂��Ă����Ƃ����̂��u�r�W�l�X�̌����v�̂���ׂ��p�Ȃ̂ł���B�����ɁA��ƌ^�����Ƃ̖{���̈Ӗ��ł̗���̈Ⴂ�A�����}�C���h�̈Ⴂ���ے��I�Ɍ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ŁA�ŏ��̖��ɋA�낤���1�͂Ŏ��グ���悤�ɁA���S�̒��ڂ̔j�]�����ƂȂ���1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v��̍ŏ���3�N�ԂɁA���S�����B�����ݔ����������́A3,266���~+3,304���~+3,634���~�̍��v1��0204���~�ł�������S�z���L���q���ł���ؓ����ƍ��ɂ����̂ł���B����͓���1965(���a40)�N�x����1971(���a46)�N�x�܂ł�7�N�Ԃ�\�肵�Ă�����O�������v��Ɋ�Â������̂��������A���̒����v��͂킸�����N�Ŕj�]���A1969(���a44)�N�ɂ́u���{���L�S�������Č����i���ʑ[�u�@�v�����肳��A����ɂ��1968(���a43)�N�x���̐��{�Ǐ����ɌW�闘�q�̍Č����Ԓ��ɂ����鎖����̒I�グ���̍����[�u���Ƃ�ꂽ�B������1969(���a44)�N�x����͍����Č��v��ɕύX���ꂽ�̂ł���
�@�Ƃ��낪�A��1�͂ł��q�ׂ��悤�ɁA����قǂ̐ݔ������K�͂ɂ�������炸�A�ӊO�Ȃ��ƂɁA���̎����̍��S�͐V�����݂����܂肵�Ă��Ȃ������B1965(���a40)�N�x�`1968(���a43)�N�x�̍H����Z�z�ł݂�ƁA�S�̂�1��3411��6000���~�̂����A���H���ݔ�3238��1000���~�A�ԗ���2903��2000���~�A��ԏ�ݔ���2114��7000���~�ƑS���Z��70%���߂Ă����B��s�s�ʋΒʊw�A���́E�����A���͂̑����A�ԗ�����A�d���A�d�ԉ��ADC������ш��S�m�ۂɏd�_���u����Ă����Ƃ�����(�w���S�j�x1973, Vol.12, p.701)�B�܂�A���S�͉��ǍH����ݔ��X�V�ɕK�v�Ȏ����������̍��Œ��B�������߂ɁA��B�����ɕ����c��݁A���������N�ł������Ȃ��o�c���j�]���Ă��܂����̂ł���B�������Ȃ����S�́A���ǍH����ݔ��X�V�ɕK�v�Ȏ������炢�A�������ۂ̌`�ŗp�ӂ��Ă����Ȃ������̂��낤����������p�̍l�����͂�����S�ɂ��������̂ł���
�@���̓����́A���\�Ȍ�����������ƁA�������o�Ă������̍��S�̗��v�ɑ��鐭�{�ƒn�������̂́u������v�ɂ��顁w���S�j�x(1973, Vol.12, pp.170-172)�ɂ��ƁA���S��������Ƒ̂Ƃ��Ĕ�������1949(���a24)�N�ȗ��A���̎Љ��E��������E�Y�Ɛ���̌������������ꂽ�^����̌������S�́A1967(���a42)�N�x�܂ł̗v�ŁA�ʋE�ʊw�����6,915���~���܂ޗ��q7,424���~�A�ݕ�1,578���~�A���ʈ��V�����E�G��512���~�̍��킹��9,514���~�ɂ̂ڂ顂���ɁA1956(���a31)�N�x����u���L���Y�����ݒn�s������t���y�є[�t���Ɋւ���@���v�ŁA�������R���Ă����n�������̌��S���Ɏ����邽�߂ɉۂ��ꂽ�s�����[�t�����A1967(���a42)�N�x�܂ł̗v��997���~��܂荇�v1��0511���~���̎������A����n�������̂̎�ō��S����ނ���Ƃ��Ă������ƂɂȂ顂��̋��z���A1965(���a40)�N�x���璅�肵����O�������v��̍ŏ���3�N�ԂɁA���S�����B�����ݔ����������̍��v1��0204���~�ƂقƂ�Ǔ��z�Ȃ̂́A����Ȃ���R�Ȃ̂ł��낤����������ꂾ���̎������������ۂ���Ă���A���S�͌o�c�j�]���Ȃ��čς͂��Ȃ̂ł���
�@�ēx�J��Ԃ�����{���A����Ƃ�����Ƃ�����Ƃ̒����I�p�t�H�[�}���X�ɂƂ��Ă͂��܂�{���I�ł͂Ȃ��B���v�E�����̏����E�^�p�Ɋւ��Đ��x�I�Ɏ��Ȍ���I�ł��邱�Ƃ�ۏ���邱�Ƃ������{���I�ɏd�v�Ȃ̂ł���B���v���z���グ��̂������E�n�����{�ł���A����ł���A����͌��Ǔ������ʂ������炷�B�o�c�w�I�ɂ́A�������ۂ��܂߂��������B�X�L�[���̎��Ȍ��茴���̊m���������]�܂����B
[95] PFI���邢��BOT (build operate transfer)�ɂ��ẮA�w��w�I�y���[�V�����Y�E���T�[�`�x1998�N9����(Vol.43, No.9)�����W���s���Ă���B���̒��ł�����(1998)�́A�L���b�V���E�t���[�̊ϓ_����BOT����������t����ƂƂ��ɁA�����̏Љ���s���Ă���B
[96]��4�͂ł��G�ꂽ���h�C�c�ōs�����S���̎������B�X�L�[���̃C���^�r���[�����ɂ��ƁA�h�C�c�ł͕⏕���̊�����25�N�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ŁA���̊����O�ɑ��̕⏕�������炤�悤�Ȏ��ԂɂȂ����ꍇ�A�S���C���t���̃����e�i���X���s�K��������A�����ӂ��Ă����肵�����Ƃ������Őݔ����̍X�V���K�v�ɂȂ����Ƃ��ɂ́A�h�C�c�A�M��v�����@�͕⏕���̎x�o����߂����邱�Ƃ��ł���B
[97]�{�e�ł͒����I�Ȏ��x�̌o�ϐ������ɂȂ�Ƃ����Ӗ��Ńr�W�l�X�Ƃ����p���p���邱�Ƃɂ��悤�B�����ăr�W�l�X�Ƃ����p���p����̂́A���̎��Ƃɑ��āu���v���v�̊ϓ_�������o�����Ƃ͂Ȃ��݂ɂ������A�����ŁA�P�ɋ����ʂ�́u�o�ϐ��E�������E�L�����v�ł͈ӂ�s�������Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B
[98]�������A���c(1995)�̕��͂ɂ��ẮA���̂悤�Ȗ��_�����邱�Ƃ�O���ɂ����ė�������K�v������B�@���Z�����̌f�L�����́A�����Ȓ��Ɋ֘A��������̕s�����������ɑ������o���ꂽ�ꍇ�ɂ́A������1���Ƃ��Ă܂Ƃ߂Čf�L����X��������A�����𐔂��邱�Ǝ��̂ɂ��܂�Ӗ����Ȃ��\��������B�A���Z�����Ɍf�L����Ȃ��Ă��A���K��������o�ϐ��E�����������Ɋւ��ẮA���u���v������A�������̂���[�u������Ă��邪�A�����A�L���������Ɋւ��ẮA���Z�����Ɍf�L���ꂸ�s��ɂȂ�A����������̂���[�u���Ƃ��Ȃ��\�����傫���B�܂�A���Z�����̌f�L�����̌X���́A��v�����@�̌��������S�̂̌X����\���Ă���Ƃ��������A���Z�����ւ̌f�L��̌X����\���Ă���ƍl�����������m�ł��낤�B
[99]�ȉ��̂��̐߂Ǝ��̑�3�߂ōs���镪�͂́A�{�c�ĕF��(��܋ǓS�������� ����������)�Ƃ̃C���^�r���[(1998�N6��12��)�A������j��(���nj����������� ����)�Ƃ̃C���^�r���[(1998�N9��10��)�A�����1987�N2��20���Ɂu���Ќ���������ꊔ����Ќ����ցv�Ƒ肵�čs��ꂽ������OB�̍��k��̋L�^�����Ƃɂ��āA�w����݁x�ŕ⑫���Ȃ���܂Ƃ߂����̂ł���B
[100]�w����݁xp.25, p.48�ł͍��S�����������̑ΏۂƂ��ċ������Ă��邪�A�ꔄ���ΏۂɂȂ��Ă����B
[101]���̎O�̗��R�ɂ��Ă͕⑫�������K�v�ł��낤�B�܂��A(a)1�̋L�q�́A�P�ɕs�������������������߂ɁA�]���^�����ɑ�����v���������Ƃ������Ƃ��w���Ă���݂̂ŁA��ƌ^�������s���ɂ͎��@�����ł������Ƃ����悤�ȃj���A���X�͊܂܂�Ă��Ȃ��B(b)2�ł����u�l���v�Ƃ͌��F��v�m�Ɠ����̍������\�č��\�͂̂��钲�������Ӗ����Ă���A�����ɂ͂��̂悤�Ȓ������͂��������������Ȃ������B���F��v�m�̎��i�������Ă����������́A����܂łł����ɑފ�����2���ƌ�����1��(1998�N�x����)�������Ȃ��B����Ƃ͑ΏƓI�ɕč��ł́A���c(1995)�ɂ��A1950�N���GAO��100%���F��v�m�ɂ���č\������Ă����Ƃ�����B�������A���̌�15�`20�N�����ē����̐l�Ԃ̍ċ��炪�s���A����GAO�ł͌��F��v�m�̊�����20%���x�ŁA�命�������I�o�������X�^�b�t�ō\�������悤�ɂȂ��Ă���Ƃ����B(c)��v�����@���s���������\�̌����Ƃ͊�ƌ^�����̂悤�ȑg�D�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ʓI�U���I�Ȃ��̂ł���A�������\�̓K�ۂ�S�̂Ƃ��Ĕ��f���邱�Ƃ�ڎw�����̂ł͂Ȃ��B(d)�o�c�\���ɂ��Ă̌����Ƃ́A�������\�ł͕K�������킩��Ȃ�����̎��Ƃ��邢�͋Ɩ��ɂ��Ă̑��v�𖾂炩�ɂ��A���̌������@�艺���ĕ��͂��錟���ł���B
[102]���̂������S�ɂ��ẮA1964(���a39)�N3��23���ɓ��{�S�������c(�S�����c)�������������߂ɁA���̕����܂߂ďW�v���Ă���B��̓I�ɂ́A���S�ɕ��ނ���Ă���1967, 70, 71, 73, 76, 80�N�̊e1���A1978, 79�N�̊e2���͓S�����c�̕��ł���B
[103]��101��(b)���Q�Ƃ̂��ƁB
[104]���������w�E�̎d���͖��c���O�ł����Ă��\�������͂������A���c���O�ɂ́A�֘A���Ƃ���ӋƖ��Ɍ��y���邱�Ƃ����Ƃ��������鋰�������A�������Ă����Ǝv����B���������c�����_�@�ɂ��āA�����A��v�����@�̓����ŁA���c�������̂�����A���܂�����ė��v�������Ă��鎄�S�Ƃ̔�r�����Ă݂悤�Ƃ����C�^������オ��A�����Ɍ��т������̂��ƌ����Ă���B�����������̌������܂Ƃ߂�ɓ������ẮA�u���v���v�Ƃ����ӎ��͂��܂�Ȃ������ƌ����A�����Č����A���c���O�̎x�o�ʂł̌o�ϐ���{�����������̂��A���S�Ƃ̔�r��ʂ��Ď����ʂł̌o�ϐ��ɂ��S�������悤�ɂȂ����Ƃ���������������x�ł��낤�B�x�o�����ł͂Ȃ��������l����悤�ɂȂ����Ƃ����Ӗ��ł́u�r�W�l�X�̌����v�I���z�������Ă��邪�A��ƌ^�����Ƃ͖��炩�ɈقȂ���̂Ȃ̂ł���B
[105]���ۂ̌����̏�ʂł́A��3���Ђ̂悤�ȁA��薯�ԓI�ȑg�D�ł���A����Ƃ����s���_�ɊÂĂ��A�����I�Ɏ���̗��v�ƂȂ�\���������w�E�ł���Ύ���₷�����A�t�ɁA�������I�ȑg�D�ł́A����Ή��������āA�s�m�������w�E�ɂ��ẮA������˂��ċ��₷��Ƃ������ʂ��������ƍl������B����������͌��Z�����ɂǂ��܂ŏ������Ƃ������ł����āA�����Ώۂ����ł��邩�Ƃ͕ʎ����̖��ł���B���́A�����������┽�����́A��҂̖����I�ȑg�D�ł����Ă��A�ӔC�Njy�����m�̃��x�������ł͍ς܂Ȃ��Ȃ�Ƃ����F�����琶���Ă���ƍl������B���Ȃ킿�A�^�̌����Ώۂ́A���ł����m�ł͂Ȃ��g�D�ł���A���̌o�c�E�^�c�E�Ǘ��E���j�Ƃ������r�W�l�X������Ă��邩�炱��������g�D�h�q�I�����Ȃ̂ł���B
[106]���ہA1998(����10)�N�x���Z�����ł́A�u�{�B�l���A�����H�̌v��y�ю��тɂ��āv(pp.525-539)�̂悤�ɁA�������x�A���Ҍv��A��ʗʂȂǂ̌����ɂ��A�x����������d���Ȃ��悤�ȏ��w�E������̂�����Ă��Ă���B
[107]�Ⴆ�A�O�q�̍��S�̃V���[�Y��2 (1977(���a52)�N�x���Z������)�ł́A1,582���]�~�̓����Ō��݂��ꂽ�{�݁A�ݔ��܂��͔z�����ꂽ�@�B�A���u�������̌��ʂ����Ȃ��܂܂ɂ�������ɔN�����o�߂��A�����̓����z�ɌW�闘����1977(���a52)�N�x���܂ł̗v���Z�z�ŁA�Ȃ�Ɩ�432���~�ɂ��Ȃ�Ƃ��Ă���B
[108]�����̌��Z�����ł́A���S�ɂ��ẮA�u���ƊT�v�ɂ��āv�u���v�ɂ��āv�ȂǂƂ������`�ŁA���̋Ɩ��E�����̏ɂ��ĒW�X�ƋL�q����Ă��������ł������B
[109]���ƊJ�n����20�`30�N���x�o�߂����i�K�ŁA��v�����@���u�������v���s���A���c�����[�h�ɓ��邩�A���Z���[�h�ɓ��邩�A���邢�͂��̂܂܂���ɐ��\�N�A���̎��ƂƂ��Čp������̂��A�Ƃ���go or no-go�̊ϓ_(�K��, 1999)����̌������s�����Ƃ��`���Â���ׂ���������Ȃ��B�]�����̎�̔��f�⊩�����Ƃ��Ȃ��������͍s���Ă��Ȃ����A�Ⴆ�A�O�q�������S�̃V���[�Y�̏ꍇ�A���̂悤�Ȏ��Ԃ���u���Ă���ƁA�����̍��S�̂��߂ɂ͔��Ɋ댯�Ȃ��ƂɂȂ�B���S�̊F����͂����������Ԃ��ǂ��l���A�ǂ̂悤�ɔ��f���܂����B�����Ώ����Ȃ�������܂���˂Ƃ�����v�����@������̃��b�Z�[�W�����߂��Ă����Ƃ�����B�����H���̏ꍇ�ł��A1993(����5)�N�x�̗r�p�p�y�n���ǎ��ƁA1994(����6)�N�x�̑��ړI�_�������ݎ��Ƃ̓��L�����ł́A�X�ɓ��ݍ���ŁA���ʖ������̎��Ԃ�����ȏ�g�傳���Ȃ����߂Ɏ��Ƃ̌��������܂߂��ϓ_�������N���Ȃ���Ă���B�܂����ƌp�������߂�ۂł��A���Y���Ƃł̏����҂͉ߋ��ɑk�y���ĐӔC���Ƃ点�A�������̑ΏۂƂ��ׂ���������Ȃ��B���݂ł��s�������Ƃ��č����s�ׂ��s�����ꍇ�ɂ́A��������������s���Ă���B�w��v�������x1998�N5��28�����ɂ��A1996(����8)�N�x���Z�����̏������u�ł́A�W�Ȓ��Ɛ��{�W�@��(����)��1998(����10)�N3�����܂łɏ������u���s���������ґ�����1,619�l�A����ɉ����ďo���@�l��36�l�ƂȂ��Ă���B�������u�����v�u���d���Ӂv�u���Ӂv���x�ŁA�����҂ɂƂ��Ď����I�ɂǂ̂悤�ȃf�����b�g�ɂȂ�̂��K���������炩�ł͂Ȃ��A����m�ɂ���ɂ͗ǂ��@�������Ȃ��B
[110]��Ƃ����炠�������v�ɑ��āA������������錠���������Ă���Ƃ������ƁA�܂�A�g�D�ɂ����Ď��Ȍ���I�ł��邱�Ƃ��d�v�ł��������̑��ʂ́A���Ȍ���I�ł��邱�Ƃ��ꎩ�̂��A���͐E�������̌���ł���Ƃ������[�N�E���e�B�x�[�V�����̑��ʂł���B�ڂ����́A����(1993a; 1993b; 1997)���Q�Ƃ̂��ƁB
[111]���āA���c���O�̓d�d�ŁA���Ԋ�Əo�g�̐^���P���ق́A1981(���a56)�N�ĂɁu�Г��I�ɂ͗\�Z�Ƃ����������g���ׂ��炸�v�Ƃ��������w�����o�����Ƃ�����B�u�\�Z�v�ƂȂ�Ɗ����^�ɍl���āA�ǂ����Ă������܂ł͎g�p�ł���x�o�g�Ƃ��āA����Ɉ���i�ނƁA�����܂ł͖������Ɏg���Ă����A�g��Ȃ���Α��Ƃ������ƂɂȂ��āA�{���Ȃ�A���v�̑㏞�ƂȂ�ׂ��o��A�K�v���Ȃ���Ύg��Ȃ��Ƃ������{�I�ȗ������Ȃ��Ȃ��Z�����Ȃ����ƂɁA���Ԋ�Ƃ̏o�g�҂Ƃ��ċƂ��ς₵�Ă����̂��Ƃ����B�������A�d�d�͖��c���̑O�ォ��A���������ӎ����v���\�z�O�ɑ����A���L�͂ɐi�݁A�e���ꖈ�ɒ��߂Ă݂�ƁA�]���Ă��g��Ȃ��A���邢�͌v��ύX���Ă�葽���̊z��v�����Ďg���Ƃ������ۂ�����ꂽ�ƁA��v�����@���ł��q������Ă���B
�@���̖{�́A�M�҂���v�����@�̓��ʌ��������߂Ă����Ƃ�(1998�N4������2000�N3���܂�)�ɁA��v�����@���[�R�c�������ǂ̃����o�[�ɏ������Ȃ���i�߂Ă��������E���������ƂɂȂ��Ă���B���ɁA����A�����Ԓ���������̋c�_�̑�������Ă����������͖k���Y��Ȓ�����(����)�A�h�C�c�ł̌��n���Ԓ����̌����I�ȃX�P�W���[����g��ł�����������ɓ��s�܂ł��Ă�����������y��������抯�A��v�����@�Ȃ�ł͂̎������W�ŋ��͂ȃT�|�[�g�����Ă�����������{������(����)�A�r�c�������A�����Ċ��R�I�q�������ق��̒������̕��X�ɂ͉��߂Č��\���グ�����B�����ǂ̏����Ȃ��ɂ́A�{���͉e���`���Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@�������A���R�̂��ƂȂ���{���ł̎咣�͕M�҂̐ӔC�ɂ����ĂȂ���Ă��邵�A�����A�Ō�܂Ō����ǂ̃����o�[�ƈӌ��̈�v���݂Ȃ��������������݂���B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�ӌ��̑���́A��v�����̌����m��Ȃ��M�҂̌�����痈����̂ł��������A���܂��v�����@�ƊW�̂Ȃ�������o�c�w�҂́u�펯�v�����킹����̂ł��������B�������A���������{���̈ӌ��������炱����łԂ��荇���Ă���ԂɁA�{�����`���傫�Ȗ��ӎ��Ə������������Ă����̂������ł���B
�@���́A��A�̌����́A�{����5�͂ɓ����镔���̘_���������قǏ����オ����1998�N�H����n�܂��Ă���B�����ŐE�ƕ��A�f�B�e�[���ɂ���������M�҂��A���������̘_����I�グ�ɂ��āA���ۂ̓S�����Ǝ҂̎������B�X�L�[���ׂ����Ƃ킪�܂܂������o�����B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���ꂾ�����z�̎��������B����Ă���ɂ�������炸�A�������B�X�L�[���ɂ��ẮA���Y��Ƃ̂����ꈬ��A���l�̐l�����m��Ȃ����E�Ȃ̂ł���B�����ŁA�����ǂ̃����o�[�Ɏ������B�S���҂̃A�|������Ă����悤�ɍ��肵���킯�����A���ꂪ�\�z�O�ɏ����ɐi�݁A1998�N�H����1999�N�t�ɂ����ẮA���T�̂悤�ɕM�҂��C���^�r���[�ɔ�щ�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���ׂ�Β��ׂ�قNj����̘A���ł��������A�������W��C���^�r���[�����ŋ��͂��Ă��������������{���q�S���������(JR�����{)�A���{�S�������c�A�����s��ʋǁA��s�����x��ʉc�c�ɂ́A�����ɋL���Ďӈӂ�\�������B���ɍ��S����̋M�d�Ȏ������E���Ă���������JR�����{�̐Γ����M���ɂ́A���̏�����肵�Ċ��Ӑ\���グ�����B
�@�������āA���{�̓S�����݂ɂ����鎑�����B�X�L�[�����悤�₭�����肩���ė���ƁA���x�́A�����ǂ̑�����A���{�̍��S�������c�������f���ɂ����Ƃ�������h�C�c�̓S�����v�ׂĔ�r���ׂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ���A1999�N10���ɁA�h�C�c�ł̘A�M��ʏȁA�A�M�S����(EBA)�A�h�C�c�S���������(DBAG)�A�A�M�S�����Y(BEV)�A�A�M��v�����@�̃C���^�r���[���������E���{���ꂽ�B�����̏��@�ւɂ����Ӑ\���グ��������̃h�C�c�ł̒����̂������ŁA���{�̕����Ă�����_�����Ȃ�N���ɂȂ����B
�@���̂悤�Ȍo�߂łق�1�N���A�I�グ��Ԃɂ����������̘_���ɂ悤�₭�߂��Ă��āA�ēx�A�����ǂ̃����o�[�ƔC�����肬��܂ŋc�_���J��Ԃ��āA�Ȃ�Ƃ��{���S�̂̍\�����o���オ�����̂ł���B���̊ԁA��A�̌������ʂ́A����Ȃ���`�ɂ��āA����ɓǎғ�����̔ᔻ�����Ƃ����v���Z�X��ʂ��Ă����B���\���ɏ��o�ꗗ�Ƃ����`�Ōf����ƁA
�Ƃ������ƂɂȂ�B�{����1�́`��3�͂�1��2���ĕ҂������̂ŁA��4�͂�4��5���܂Ƃ߁A��5�͂�3�����Ƃɂ��āA���ꂼ����M���Ă���B
�@�M�҂̏������铌����w��w�@�o�ϊw�����Ȃ̌o�c�O���[�v�ł́A21���I�Ɍ����āA(1)���ꂩ��{�������ݏo��(field)�A(2)�����_���I�ɐ����E���͂�(logic)�A(3)��̓I�Ȗ������Ɍ��т���(action)�A�Ƃ������t�B�[���h�E�x�[�X�g(field-based)�ȃA�v���[�`����Ă���̂����A�{�����t�B�[���h�E�x�[�X�g�Ȍ������ʂƈʒu�t���Ă��炦��A�]�O�̊�тł���B
�@�ŏ���1�{�̘_���ɂȂ�͂����������̂��A���̊Ԃɂ�1���̖{�ɉ����Ă��܂��A��v�����@�̌����ǂ̃����o�[�͑��������Ă��邩������Ȃ��B���̖{�̓��e��ǂ�ŁA����ɋ�����邱�Ƃ𖧂��Ɋ��҂��Ă���B���̊ԁA�u�S���v�u�S���v�ƌ�����Ȃ���A�˔@�A�S���}�j�A�Ɖ����������Ƃ��Z�������ɓS����ǂ��Ĕ�щ���Ă����M�҂����b�����Ȋ�Œ��߂Ă������̗͂F�l�A�m�l�����́A�����[�����邩������Ȃ��B�h�C�c�ł͂��y�Y��I��ł���ɂ��Ȃ������Ƙb���Ă��M�p���Ă��炦�Ȃ������ȓ֎q�Ƒ��q�L�V�ɂ͑����̌�����ɂȂ邩������Ȃ��B�낭�ȃh�C�c�y�Y�������Ȃ��������A���X���ӂ��Ă���B�����āA�ǎ҂���̍ŏ��̔ᔻ�ɑ��鎄�̕Ԏ�:
�ٍe�̎咣�ɑ����a���Ƃ��{��͗����ł������ł͂���܂��B�������A�S������Ɍ��炸�A�e���ʂŐςݑ�����A���͂�c��������ʂقǂɌ�̐���ɑ��ĕ���w���킹�Ă��܂��Ă��錻����ӂ܂��āA�@����{�ӔC����̂ǂ�قǂ̖ƍߕ��ɂȂ肦��̂�����ƌ������̈�l�Ƃ��Ċ뜜�������Ă���܂��B������w���߂������A�����悤�ȋǖʂɑ�������ł��낤�Ƃ��������̗\���Ɗo��̒��ŁA���͂��̌����ɒ��肵�܂����B���́A������w�̈ꋳ���ł���O�ɁA����{�����Ƃ��āA��w�̖]�܂�������ׂ��p��͍����A��ɓ����҈ӎ������������Ă��������Ɗ���Ă���܂��B
�@�Ō�ɁA�{������N3���ɋ}�������ł����h���鋳�t�̈�l�ł��镃�A���o�v�ɕ�����B
2000�N3���@���̖���
�����L�v