第1部 未来傾斜原理
第1章 意思決定原理と協調行動の進化
第2章 未来係数と参加の意思決定
第3章 終身コミットメントと未来係数
第2部 未来傾斜型システムの成長志向
第4章 期待効用原理とチャレンジ
第5章 ぬるま湯的体質とチャレンジ・成長
第3部 未来傾斜型システムの育成志向
第6章 近代組織論とゴミ箱モデル
第7章 やり過ごしと人材育成
第8章 尻ぬぐいと育てる経営
結章 「未来の重さ」と経営者の仕事
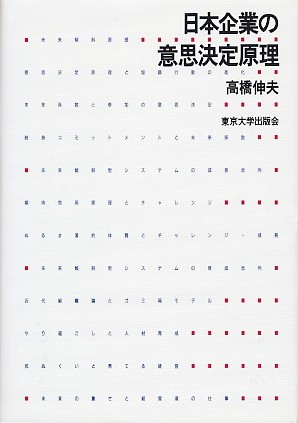
数年前、近代組織論の体系をその源流である決定理論、さらにゲーム理論にまで遡って位置付けてみようという意図から、『組織の中の決定理論』(朝倉書店, 1993年)という本を書いたことがある。きれいで美しいゲーム理論の世界、決定理論の世界、近代組織論の世界。それは、この本の第1部、第2部、第3部のそれぞれ冒頭の章でも、その一端をのぞくことができる。私もかつてはその美しさに魅せられた人間の一人だった。
ところが、日本に暮らすわれわれ、特に日本企業とそのメンバー達は、それらの理論では説明のつけられない世界に生きているように見える。それらの理論から見ると一見不合理な世界に生きているように思える。実際の日本企業を調べて、その行動の理不尽さ、合理性のなさをことさら強調することはたやすい。欧米型の理論に立脚してそれを行なえば、なおさらそれはたやすいことだ。しかし、われわれの生きている世界は本当に不合理、不条理の支配する世界なのだろうか?
そんなはずはない。なぜなら、もし本当に不合理ならば、われわれは互いの行動の予想も全くつかず、社会生活など不可能で、われわれの目の前には支離滅裂でばらばらな光景が展開しているはずだからである。しかし、そんなことはない。何か筋が通っているような気がする。はっきりとはしていないが、われわれは何かに導かれて行動しているように感じられる。それでは、一体何に導かれているのだろうか?
以前から気にはなっていたが、その本を書いたことで、この疑問が余計鮮明になり、脳裏にこびりついて離れなくなってしまった。そして気がついてみると、10年以上も続けていたことになる調査データとの格闘、あるいは理論との葛藤を経て、ようやく私は、この課題に対する私なりの答えを整理し、提示するところまでこぎつけた。それがこの本である。
手探り状態で始めた研究だったが、答えのヒントはモデルに埋めこまれた未来の取り扱い方の中にあった。はっきり言ってしまえば、私もそうだが、多くの日本企業とそのメンバー達にとって、割引いて現在価値に直すことで清算してしまうような未来なんかに意味はないのである。現在よりも未来の方が大切なのだ。未来がどこかに収束しなくてはならない必要などどこにもない。目先の選択肢の最適性をとやかく言うよりも、未来に向かってチャレンジすることの方が、ずっと大きな意味を持つ。そして、自ら成長し、育てることの中にこそ、未来の本当の意味があるのである。未来は残すことにこそ価値がある。
ただ、そうなってしまうと、今までゲーム理論や決定理論をはじめとする経済学系の分野で何のためらいもなく使ってきた、最適な選択肢を選ぶというアプローチが使えなくなってしまうという大きな問題が発生する。均衡も安定ももはや魅力的で説得的なアイデアとはいえなくなる。そこで私は、自分の悪戦苦闘の成果を1冊の書物としてまとめるに当たって、少しでもスマートに整理するために、意思決定原理という切り口から斬り込んでみることにした。例えば、日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、一体、どのような意思決定原理に則ったものなのだろうか。
私はそれを「未来傾斜原理」と呼んでみた。過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現に寄り掛かって意思決定を行なう原理である。未来が確かなものであれば、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながることが想像できるが、それこそが自然に発露した未来傾斜原理に則った行動である。しかも、自分が定年退職を迎えるまで自分の会社が存続しているかどうかもわからない場合でさえ強い成長志向を持ち続けていることがあるように、未来傾斜原理自体は、未来の確かさとはかかわりなく、意思決定原理として機能しうるものなのである。
この意思決定原理がどのように形を変え、われわれの前に姿を現すのか。この本を読み進むうちにわかってくるだろう。そうしてから、また最初の問いに戻ることにしよう。われわれは一体何に導かれて行動しているのだろうか?
私の答えだけを手軽に知りたい読者のために、「結章」に結論があるということだけはお知らせしておこう。しかし、その結論に到達する道筋をできるだけ理論的に、かつ調査データに基づいて示すために、この本は書かれている。この本の試みは果たしてうまくいったであろうか。「結章」を先に読んでしまった人も、そこだけで本書の試みの成否を判断せずに、できれば、最初から読み直して、この本の議論が納得のいくものかどうかを自分自身の頭と感性で判断して欲しい。
人は、何かものごとを決める際に、意識している意識していないにかかわらず、何らかの原理・原則に則って意思決定を行っているものである。それをここでは意思決定原理(decision principle)と呼ぶことにしよう。例えば、選択肢の種類や内容について一切考えず、取り敢えず一番手近な選択肢を選ぶというのも立派な意思決定原理であるし、でたらめに選択肢を選ぶというのは、むしろ代表的な意思決定原理の一つであるといっていい。
意思決定原理は、明示的あるいは暗黙のうちにさまざまな分野で登場してくるが、ここで関心があるのは、企業、組織、経営といった分野における意思決定原理である。この分野でよく知られたものは、主に決定理論と呼ばれる分野で考えられたものがルーツになっている。決定理論の中では、原理(principle)とは呼ばずに、規則(rule)や基準(criterion)と呼ぶ言い方もあるが、rule は後述するゲームのルールとして使うこともあるし、また criterion になると単なる選択基準に限定されたイメージになってしまうので、そうではなく、自らの行動を律する原理になっているという意味も込めて、principle を使うことにする。
ところで、決定理論自体、もともとはゲーム理論から派生して生まれたものであるが、ゲーム理論では、ゼロ和2人ゲームであれば、数ある意思決定原理の中でも、マクシミン原理と呼ばれる意思決定原理に導かれて均衡点に到達することがわかっている。言い換えれば、ゼロ和2人ゲームの世界では、それを採用すれば均衡点に到達できるという意味で、マクシミン原理は説得的でありかつ魅力的な意思決定原理である。しかし、非ゼロ和2人ゲームになると、均衡点は存在するものの、もはやマクシミン原理でそこへ到達できる保証はなくなる。マクシミン原理は均衡点を指し示すものではなくなるのである。
しかも非ゼロ和ゲームでは、その均衡点自体、実際上、どれだけの意味があるものかも怪しくなってくる。例えば、ゲーム理論で考えれば、裏切り合いの共倒れで均衡するはずの囚人のジレンマ・ゲームであっても、ゲームが長期間にわたって行われた時には、実験でもシミュレーションでも協調関係が現れるようになる。これはわれわれの日常感覚にも合致している。つまり、均衡点は現実的には意味を失ってしまっているのである。均衡に代わって進化論的な状況で用いられる集団安定の概念を使っても、均衡の時と同様に、裏切り合いの共倒れで集団安定することが理論的に証明されるのだが、実際には、ゲームが長期間にわたって行われた場合には、現実的に無意味であることが明らかになる。
こうして、ゼロ和ゲームでは、均衡点を指し示してくれるという点で、マクシミン原理は説得的でかつ魅力的な意思決定原理だったのに、非ゼロ和となると、マクシミン原理がもう均衡点を指し示さないどころか、均衡も安定も現実的な意味を失ってしまっているのである。もはや均衡や安定を指し示してくれるという観点から意思決定原理を評価すること自体に意味がない。しかし、もしわれわれが、どんな形であれ、筋の通った行動をとっているとすれば、そして、それに何らかの意味があるとすれば、われわれは全く異なる別の観点から見て説得的で魅力的な意思決定原理に則って意思決定を行い、行動しているはずである。
そこで、反復囚人のジレンマ・ゲームのシミュレーションの結果を検討してみると、実はシミュレーションの結果から、
という性質をもった戦略が高得点を挙げていることがわかる。この1、2が示唆していることは、目先の利益や過去への復讐を選択してはいけないということである。将来の協調関係をこそ選択すべきなのである。
しかし、よく考えてみると、これはあまりにも当たり前のことである。シミュレーションなどやってみるまでもない。いまもし、
とが競争すれば、短期的には「a. 刹那主義型システム」が羽振りをきかせる時期があったとしても、結局、何十年か後をみてみると、生き残っているのは「b. 未来傾斜型システム」に違いないからである。ゲーム理論や決定理論では、均衡や安定の観点から意思決定原理を見てきたために、未来傾斜型システムは見逃されてきたのである。
そこでこの章では、こうした議論を整理した上で、未来傾斜型システムのエッセンスを「未来傾斜原理」と呼ぶ意思決定原理で要約することにしよう。未来傾斜原理とは、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来を残すことを選択し、その実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという原理である。均衡や安定へのパスを指し示すからではなく、まさに未来そのものへのパスを指し示すという点で、未来傾斜原理は説得的である。そして、日本企業でごく普通に観察される意思決定原理が、この未来傾斜原理なのである。例えば、日本企業のもつ強い成長志向などはその典型的な発露である。
議論を始めるに当たって、意思決定原理を概念的にはっきりさせておく必要があるので、ゲーム理論を使って、戦略との違いをきちんと説明しておこう。
もともと軍事用語であった戦略(strategy)をゲームの各プレイヤーのとる手を意味する学術用語として使用したのは、ゲーム理論を体系化したフォン・ノイマン(John von Neumann)とモルゲンシュテルン(Oskar Morgenstern)の有名な『ゲームの理論と経済行動』(Theory of Games and Economic Behavior, 1944)である。ゲーム理論は、戦争であろうと政治やビジネスであろうと、争いごとの存在するゲーム的状況に対する統一的な分析枠組みを提供しているが、実は、このゲーム理論が社会的な問題、特にビジネスについての考え方に革命をもたらし、その結果として、1950年代の後半から、戦略という用語が経営学の分野で本格的に使われるようになったともいわれる(Ansoff, 1965, p.94 邦訳p.128; p.105 邦訳p.147)。
しかし、ここではそこまで幅広く取り扱うわけではないので、一般的なゲームの構成要素を考えていくことにしよう。ジャンケンをはじめとする将棋、チェス、トランプなどの様々なゲーム(game)は、形式的には、複数のプレイヤーが、各々の行動を規定する一組の規則、ルール(rule)に従ってプレイするものである。たとえば、2人で行なう最も基本的な1回限りのジャンケンでは、2人のプレイヤーがグー、チョキ、パーという3種類の手の中から一つの手を選択し、その選択の結果を文字どおり「手」で表現して提示するという動作から成り立っている。そして、手の組合せによって2人のプレイヤーの勝敗がどう定まるのかが事前に取り決められている。つまり、こうしたゲームのルールは次のような基本的な要素から構成される。
これは抽象的にいえば、意思決定をし、行動する主体のことである。ジャンケンでいえば、出す手を自分で考え、そして実際に自分で決めた手を「手」で表現して、対戦相手に提示する人がプレイヤーである。ゲームは形式的には2人以上のプレイヤーが存在してはじめて成立することになる。
これは、各プレイヤーのとりうる行動計画のことである。各プレイヤーは通常は複数の戦略をもっており、そのために各プレイヤーは戦略の選択の問題に直面する。ジャンケンでは各プレイヤーは、グー、チョキ、パーの三つの戦略の中から一つの戦略を選択することになる。より一般的には、プレイヤー1、プレイヤー2のもつ戦略の集合は、それぞれ Π1、Π2 と表され、集合として、次のように表現される。
Π1={i: i=1, 2, ..., m}, Π2={j: j=1, 2, ..., n}
ただしここでは、各プレイヤーのとりうる戦略の数は有限と考えている。
各プレイヤーが何らかの戦略をとることによってゲームは終了し、ある結果が定まるが、この結果について各プレイヤーがもっている評価値を利得と呼ぶ。一般的には、とりあえず金銭のようなものであると考えておこう(このことについては、詳しくは、第4章で触れる)。プレイヤー1が戦略 i、プレイヤー2が戦略 j をとったときの戦略の組 (i, j) に対して、プレイヤー1とプレイヤー2の利得は、それぞれ次のように表わす。
f1(i, j)=aij, f2(i, j)=bij
あるいは (プレイヤー1の利得,プレイヤー2の利得) という組の形で
( f1(i, j), f2(i, j))=(aij, bij)
と表してもよい。いずれにせよ、ゲームにおいては、どのプレイヤーも自分の利得は自分の戦略だけではなく、他のプレイヤーの戦略との組合せによって定まるというところが重要なのである。
さて、このようなルールの基本的要素によって記述されるゲームにおいては、ゲーム理論では、まず各プレイヤーは自分の受け取る利得を最大にしようとして戦略を選択すると考える。この前提に立った上で「ゲームを解く」ことを考えるのである。ゲームを解くというのは、簡単にいうと、ゲームの均衡点とそのときの均衡利得(これをゲームの値と呼ぶ)を求めることをさしている。このように定式化した場合には、ゲームの均衡点は次のように定義される。
f1(i*, j*)=maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1)
f2(i*, j*)=maxj∈Π2 f2(i*, j) (1.2)
このとき、戦略の組 (i*, j*) を均衡点(equilibrium point)またはナッシュ均衡点(Nash equilibrium point)と呼ぶ。そして、この均衡点での利得 ( f1(i*, j*), f2(i*, j*)) を均衡利得というのである。
いまナッシュ均衡点に双方のプレイヤーがいるとしよう。仮に片方のプレイヤーがそのままで、もう一方のプレイヤーが戦略を変えるとすると、ナッシュ均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らし、損をすることになる(少なくとも利得が増えることはない)。したがって、この均衡点からどちらのプレイヤーも離れようとはしない(このことを自己拘束的(self-enforcing)と呼ぶ)。つまり、つりあいがとれ、安定していることになる。だから均衡点と呼ばれるわけである。たとえば、表1.1のような利得表を考えれば、戦略の組(2,2)がナッシュ均衡点であり、ゲームの値は(4,4)となることがわかる。
表1.1 ナッシュ均衡点
| プレイヤー1 | プレイヤー2 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | (2, 2) | (0, 6) |
| 2 | (6, 0) | (4, 4) |
| (注) | はナッシュ均衡点 |
以上のように、均衡点がどれかはわかったものの、その均衡点はプレイヤーがどのように考えて行動したときに達成可能なのだろうか。そこでここでは、どのような意思決定原理に則って行動したときに達成されるのかについて考えてみることにしよう。
意思決定原理の説明を簡潔にするために、これ以降この節では、ゼロ和ゲームに限定して話を進める。いま2人ゲームのうち、特に2人のプレイヤーの利得 f1(i, j)、f2(i, j) の和が常に0であるような場合、すなわち、
f1(i, j)+ f2(i, j)=0
であるとき、このゲームはゼロ和2人ゲーム(zero-sum two-person game)と呼ばれる。ゼロ和2人ゲームの場合には、
f1(i, j)=−f2(i, j)
と一方のプレイヤーの利得は、他方のプレイヤーの利得の符号をひっくり返したものになる。このため、2人の利得を両方とも併記して書く必要はない。そこで、
aij= f1(i, j)=−f2(i, j)
とおいて、プレイヤー1の方だけを考えて、戦略と利得との関係を次のような行列の形で表現することができる。
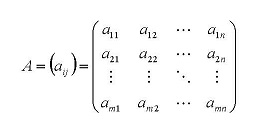
この行列は利得行列(payoff matrix)と呼ばれる。利得をこのような行列の形で表現できることから、ゼロ和2人ゲームは行列ゲーム(matrix game)とも呼ばれる。
こうしておいた上で、ゲームをする際にプレイヤーが依拠するであろう意思決定原理について考えてみよう。これについては、既に先人達が知恵を絞って考案しているので、ここではその中でも有名ないくつかの意思決定原理について紹介しておこう。なお説明の便宜上、ここではプレイヤー1の意思決定原理を考えることにする。ゼロ和2人ゲームなので、プレイヤー2の意思決定原理は式の中の大小関係を逆にしたものになる。
もともとゲーム理論で考えられていたもので、後にワルド(Abraham Wald)が決定理論を構築する際に取り上げたために(Wald, 1950)、ワルドのマクシミン原理(Wald's maximin principle)とも呼ばれるようになった。この意思決定原理では、戦略 i をとったときの最悪の可能な結果、つまり利得が一番小さくなる結果
si=minj aij
を考える。これは戦略 i の保証水準(security level)と呼ばれ、戦略 i は少なくともこの
si の利得を保証していることになる。このとき、マクシミン原理は
sk=maxi si=maxi minj aij
のように最大の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。
マクシミン原理が各戦略をとったときに起こりうる最悪の事態を考えて戦略をとるという意味では、悲観的な(pessimistic)意思決定原理であるのに対して、マクシマクス原理(maximax principle)は、各戦略をとったときに起こりうる最良の事態を考えて戦略をとるという意味で、楽観的な(optimistic)意思決定原理である。つまり、まず戦略 i をとったときの最良の可能な結果
oi=maxj aij
を考える。これは戦略 i の楽観水準(optimism level)と呼ばれる。このとき、マクシマクス原理は
ok=maxi oi=maxi maxj aij
のような最大の楽観水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。
マクシミン原理は悲観的すぎるし、マクシマクス原理は楽観的すぎると思われる人のためには、ハーウィッツ(Leonid Hurwicz)によって楽観・悲観指数原理(Hurwicz's optimism-pessimism index principle)が1951年に提案されている。これは、マクシミン原理で出てきた保証水準 si とマクシマクス原理で出てきた楽観水準 oi の加重平均
αsi+(1−α)oi, 0≦α≦1
を考え、これを最大にする
αsk+(1−α)ok=max i {αsi+(1−α)oi}
となるような戦略 k を選ぶという意思決定原理である。ここで登場するαは楽観・悲観指数(optimism-pessimism index)とよばれる。
「逃した魚は大きい」「後悔先に立たず」などとよくいわれるが、このような後悔(regret)を決定に先だって考え、それから意思決定を行おうというのが、サベージ(Leonard J. Savage)が1951年に提案したミニマックス・リグレット原理(Savage's minimax regret principle)である。いまプレイヤー1は相手のプレイヤー2がどんな戦略をとるかわからないので、仮に、プレイヤー2がある戦略 j をとると仮定しよう。その戦略 j に対して最良の戦略をプレイヤー1がとっていれば得られたはずの利得 maxi aij と実際にとってしまった戦略 t の利得 atj との差をリグレット(regret)と定義する。すなわち、
rtj=maxi aij−atj
そこで、利得行列の各 atj をこのリグレット rtj で置き換えた利得行列を考え、これについてワルドのマクシミン原理を適用することを考えるのである。ただし、リグレットは利得でなく、「損失」なので、最小ではなく、最大のリグレット
ρi=maxj rij
を保証水準と考え、
ρk=mini ρi=mini maxj rij
のような最小の保証水準をもたらす戦略 k を選ぶという意思決定原理である。
実際に数値例を使って戦略の選択をしてみると、表1.2(A)の例では、プレイヤー1はどの意思決定原理にしたがっても、結局は同じ戦略1を選ぶ結果になる。しかし、常にそうなるとは限らない。それぞれの意思決定原理がそれぞれ全く異なる戦略の選択に導くこともある。例えば、表1.2(B)の利得表について、これまで扱ってきた4種類の意思決定原理に則ってプレイヤー1の戦略を選択してみると(ただし、楽観・悲観指数は0.7とする)、意思決定原理によって異なる戦略が選択される(表1.2(A)(B)の実際の解法は難しくないが、必要な読者には、高橋(1993c, ch.1)に解説がある)。すなわち、
表1.2 意思決定原理とプレイヤー1の戦略の選択
(A)意思決定原理によらず同じ戦略1が選択される利得表(プレイヤー1の利得のみ表示)
| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 0 |
(B)意思決定原理によって異なる戦略が選択される利得表(プレイヤー1の利得のみ表示)
| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 0 |
こうなってくると、どの戦略が選択されるかは、採用される意思決定原理によってまったく異なるわけで、どの意思決定原理を採用するか、それ自体が大問題となる。そして、ある意思決定原理に則ってある戦略を選択したプレイヤーにとって、相手プレイヤーが予想外の戦略を選択したときに、それがいかなる意思決定原理に則って行われたものであるかを想像し、理解することは至難のわざということになる。
おそらくそういう場合には、相手プレイヤーの意思決定原理を徹底的に追求し、理解しようとするような努力は放棄され、「彼らは意思決定原理もなしに意思決定を行っている」と断定して次のステップに進んでしまうだろう。それが繰り返されると、米軍の意思決定原理のように、敵の意思ではなく、敵の対抗する能力を評価し、それに基づいて司令官は行動を決める(Haywood, 1954)というパターンが定着してしまうことも考えられる(詳しくは第6章で触れる)。これはマクシミン原理に通じており、これから述べるように、ゼロ和ゲームの世界に限れば、確かに望ましい結果をもたらすので、ゼロ和状況での最適な意思決定原理として生き残ってきたとしても不思議はない。
しかし、よく日本人はプリンシプル(=原理)がないと言われるが、これは本当にプリンシプルがないのかどうか、実は大いに疑問なのである。むしろ、多くの日本企業で普通に観察される意思決定原理は、ここで紹介したゲーム理論や決定理論に登場する代表的な意思決定原理とは系統の異なる別種のものだと考える方が妥当なのではないだろうか。それが本書の主張であり、後ほどより詳細に述べられる。
既に触れたように、ゲーム理論においては、ゼロ和2人ゲームではマクシミン原理が望ましい意思決定原理とされるのだが、その理由を明らかにしておこう。
ゼロ和2人ゲームは2人ゲームの特殊な場合であるから、ナッシュ均衡点の定義をそのまま適用することができる。f2(i, j)=−f1(i, j) のとき、ナッシュ均衡点の定義式(1.1)式、(1.2)式は、(1.2)式だけを変えれば
f1(i*, j*)=maxi∈Π1 f1(i, j*) (1.1)
f2(i*, j*)=minj∈Π2 f1(i*, j) (1.2')
となるから、この両式を満たす (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの均衡点ということになる(ここでは、とりあえず均衡点の存在を仮定しておこう)。
このとき(1.1)式と(1.2')式とを f1(i*, j*) で結合すると、任意の i∈Π1, j∈Π2 について、
f1(i, j*)≦f1(i*, j*)≦f1(i*, j)
となる。実は、行列 A において、任意の i, j について、
aij'≦ai'j'≦ai'j
が成立するとき、(i', j')をこの行列の鞍点(「あんてん」と読む; saddle point)とよび、ai'j' を鞍点値(saddle point value)という。したがって、ナッシュ均衡点 (i*, j*) はゼロ和2人ゲームの利得行列の鞍点となっていることになる。いま
v1=maxi minj aij
v2=minj maxi aij
とすると、もし鞍点 (i*, j*) が存在すれば、そのときに限って v1=v2=ai*j* となることが証明できる。
定理1.1 (鞍点定理). v1=v2 となる必要十分条件は、この利得行列が鞍点をもつことである。
《証明》まず、次の補題を証明しておこう。
補題.
《証明》まず任意の i', j' について
minj ai'j≦ai'j'≦maxi aij'
したがって、任意の j' について
maxi minj aij≦maxi aij'
がいえるので
maxi minj aij≦minj maxi aij
定理の証明に戻る。
(十分性) いま (i*, j*) を鞍点とすると、定義から、任意の i, j について
この定理1.1の証明から、v1=v2 ならば v1=v2=ai*j* と、鞍点 (i*, j*) での利得の値に等しくなることがただちにわかる。すなわち、こうした鞍点は、実はマクシミン原理によって達成されているのである。なぜなら、マクシミン原理とは、自分が戦略 i をとったときに、最悪の場合でも得られる利得(=戦略 i についての保証水準)を考え、この利得が最大となるような戦略を選択する意思決定原理であった。したがって、ゼロ和2人ゲームに均衡点が存在しているときには、各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択すると、プレイヤー1の利得は v1、プレイヤー2の利得は v2 となり、それが均衡利得となっているからである。
このように、均衡点を指し示すという点で、マクシミン原理は説得的で魅力的である。しかも、マクシミン原理で意思決定原理も均衡する。より正確に言えば、ゼロ和2人ゲームでは、一方のプレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択している限り、もう一人のプレイヤーにとっても、マクシミン原理が最適な意思決定原理となる。なぜなら、マクシミン原理から逸脱することは、均衡点から逸脱する可能性を意味し、均衡点の定義から、戦略を変えたプレイヤーの方が利得を減らすことになる(少なくとも増やすことはできない)からである。したがって、マクシミン原理は、どちらか一方のプレイヤーが意思決定原理として採用を決めると、他のプレイヤーも採用せざるを得なくなる性質をもち、しかもその際には均衡点に達するというきわめて安定性の高い意思決定原理であるということができる。つまり戦略といういわば行動や決定のレベルで均衡点が存在しているだけではなく、その意思決定に至る手前の意思決定原理のレベルでも均衡が存在していることになる。
このことは常に成り立つ。これまでは、とりあえず均衡点の存在を仮定してきたが、一種の拡張を行い、これまでのように、Π1、Π2 の中からどれか一つの戦略を選択する(これを純戦略(pure strategy)と呼ぶ)のではなく、Π1、Π2 上の確率分布 p=(p1, ..., pm), q=(q1, ..., qn) で表されるような、どれか一つの戦略の当たる「くじ」(これを混合戦略(mixed strategy)と呼ぶ)を一つ選択することを許すことにする。そうして、第4章で登場する期待効用を使えばミニマックス定理が証明される。つまりゼロ和2人ゲームには均衡点が必ず存在すること、そしてここで扱った純戦略の場合と同様に、その均衡点は各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択したときに達成されることが証明できるのである(詳しくは、例えば高橋(1993c, ch.2))。
これまではゼロ和2人ゲームの話だった。ところが、表1.3の例を見るとわかるように、ゼロ和の制約がはずれて、非ゼロ和2人ゲームになると、2人のプレイヤーがマクシミン原理にしたがって戦略を選択しても、ナッシュ均衡点にならないこともある。非ゼロ和では、マクシミン原理はもう均衡点を指し示さなくなるのである[1]。つまり、マクシミン原理の説得力や魅力は失われる。
表1.3 非ゼロ和2人ゲームの均衡点とマクシミン原理
| プレイヤー1の戦略 | プレイヤー2の戦略 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | (3,2) | (4,4) |
| 2 | (2,3) | (6,6) |
| ←マクシミン原理に則ったプレイヤー1の戦略 |
↑
マクシミン原理に則ったプレイヤー2の戦略
| (注) | はナッシュ均衡点 |
それでも均衡の概念だけは、非ゼロ和ゲームでもまだ非常にすっきりしたものにも感じられるが、実は非ゼロ和ゲームになった途端、個々のケースではどうもすっきりとは納得のできない場合も出てくるのである。そのうち特に有名なのが囚人のジレンマ(prisoner's dilemma)のケースである。
いま、共犯の2人の容疑者、囚人1と囚人2とが逮捕され、分離された上で別々に尋問を受けている。もし2人とも自白した場合には、懲役8年の刑になるが、2人とも自白しなければ、検察側も微罪しか立証できないので、懲役1年の刑で済むことになる。検察側は、2人の容疑者に自白を促すために、どちらか1人だけが自白した場合には、自白しなかった1人には、この罪での最高刑の懲役10年を求刑するが、自白した1人は検察に協力したということで懲役にはしないという司法取引を提示した(もともと米国で考えられた話なので、司法取引が許される)。さて、囚人1と囚人2はどのような行動をとるのであろうか。この場合、刑期は負の利得なので、刑期にマイナスをつけて利得表を作成すると、表1.4のようになる。
表1.4 囚人のジレンマ
| 囚人1 | 囚人2 | |
|---|---|---|
| 自白しない | 自白する | |
| 自白しない | (-1, -1) | (-10, 0) |
| 自白する | (0, -10) | (-8, -8) |
| (注) | はナッシュ均衡点 |
この利得表からもわかるように、均衡点は(自白する,自白する)という戦略の組で、ゲームの値は(-8,-8)ということになる。つまり共倒れで均衡する。囚人1にとっても囚人2にとっても、相手が自白しようがしまいが、自分は自白した方が常に刑期は短くてすむのである。
このようにゲーム理論では確かに共倒れで均衡になるが、実際にゲームをした場合でも、本当に、均衡点である(自白する,自白する)という戦略の組をとることになるのだろうか。実は(自白しない,自白しない)をとることができれば、利得は(-1,-1)となって、2人の囚人にとってはるかに望ましいはずなのである。もし共倒れで均衡するとすれば、なんとも愚かしい状況ではないか。そう思うのは私だけではあるまい。実際、本当に共倒れになるのだろうかということに関して、多くの心理学者がその研究意欲をかきたてられたと言われている。1959年の囚人のジレンマに関する最初の実験結果(Scodel et al., 1959)が発表されてから、20年間に、約1000点もの論文、著書が発表されたという(Pruitt & Kimmel, 1977; 佐伯, 1980)。そして実は「反復囚人のジレンマ・ゲーム」では、必ずしも共倒れの裏切り合いにはならないということがわかってきたのである。
その話に入る前に、この「囚人のジレンマ」状況をもう少し一般化しておこう。まず2人のプレイヤーの戦略についてだが、より一般化して「自白しない」は「協調」を意味し、「自白する」は「裏切り」を意味していると考えると、囚人のジレンマ状況のイメージはぐっとふくらむ。つまり、ここで考える「囚人のジレンマ」ゲームは次のような「協調・裏切り」ゲームなのである。
この3がジレンマというわけである。2人のプレイヤーについて対称になるように、表1.5(A)のような利得表を使ってみよう。
表1.5 囚人のジレンマ
(A)標準的な書き方の表 (B)これから使う書き方で書いた表1.4
| プレイヤー1 | プレイヤー2 | |
|---|---|---|
| 協調(C) | 裏切り(D) | |
| 協調(C) | (R, R) | (S, T) |
| 裏切り(D) | (T, S) | (P, P) |
| C | D | |
|---|---|---|
| C | R=-1, R=-1 | S=-10, T=0 |
| D | T=0, S=-10 | P=-8, P=-8 |
(注) (A)の書き方は非ゼロ和ゲームの利得表の一般的な書き方に則っているが、この章では今後、囚人のジレンマしか扱わないので、わかりやすさを重視して、(B)の書き方をとることにする。
表1.5では
を意味している。これを使って先ほどの3を数式により表現してみると、次のようになる。
仮定1.1 T > R > P > S
つまり、一方的な裏切りに成功したときの誘惑 T が一番大きく、逆に、お人好しにも相手に一方的に裏切られてしまう S が一番小さい。そして、協調し合った時の報酬 R よりも裏切り合った時の P は小さく、罰になっている。囚人のジレンマとは、このように裏切り合うよりも協調し合う方が利得が大きくなっているにもかかわらず、一方的な裏切りで相手を出し抜く誘惑に負けてしまい、結局は裏切り合いの共倒れに終わるという状況を指しているのである。そして、反復囚人のジレンマ・ゲームとは、同じ相手との間で囚人のジレンマ・ゲームを何回も反復し、各回、それまでの試合経過を利用して(つまり、相手の選択パターンを研究しながら)、次回、協調するか否かを選択するゲームである。
ところで、反復囚人のジレンマ・ゲームとはいっても、有限回数の反復囚人のジレンマ・ゲームで、しかもその回数をプレイヤーが知っている場合には、たとえ反復囚人のジレンマ・ゲームになったとしても、結局は1回限りの囚人のジレンマ・ゲームと同じで、それより以降の回のゲームの存在もむなしく、協調行動を引き出すことはできないというのがゲーム理論の結論である。なぜなら、いま最終回を考えてみると、もはや後々のことを考えて行動する必要がないので、1回限りのゲームと同じ理由で裏切り合うことになる。するとその前の回でも、最終的に相手が裏切るのを見越しているために、どちらも協調せず、裏切り合いになる。こうして、その前の回も、そのまた前の回も・・・・・・、と裏切り合うことになり[2]、どんなに回数が多くとも有限回である限り(つまり最終回がある限り)、この論法で最終回から逆に遡っていくと、最初の回でも裏切り合うことになるからである(Luce & Raiffa, 1957, pp.98-99; Axelrod, 1984, p.10 邦訳pp.9-10)。つまり、有限回の反復囚人のジレンマ・ゲームでは、回数がどんなに多くとも、裏切り合いの共倒れで均衡するというのが、ゲーム理論の結論なのである。
こうしたゲーム理論上の結論を理解した上で、反復囚人のジレンマについてのラパポート(Anatol Rapoport)とチャマー(Albert M. Chammah)の実験結果を見ると、実に興味深い(Rapoport & Chammah, 1965)。彼らはミシガン大学の男子学生ペア、70組を実験対象として、囚人のジレンマ・ゲームを300回続けてプレイさせた。ごくまれな例外を除いて、各ペアの2人は互いに知り合いではなかった。ゲームの結果は各プレイの後に知らされた。
ゲームには、表1.6のような7タイプの利得表が用意されていた。各ペアは七つあるタイプのゲームの内の一つのタイプのゲームをプレイした。つまり、各タイプのゲームに10組ずつのペアが割り当てられたことになる。彼らがこの実験で興味を持っているのは、「協調」がとられる頻度である。
表1.6 実験に用いられた7タイプの利得表
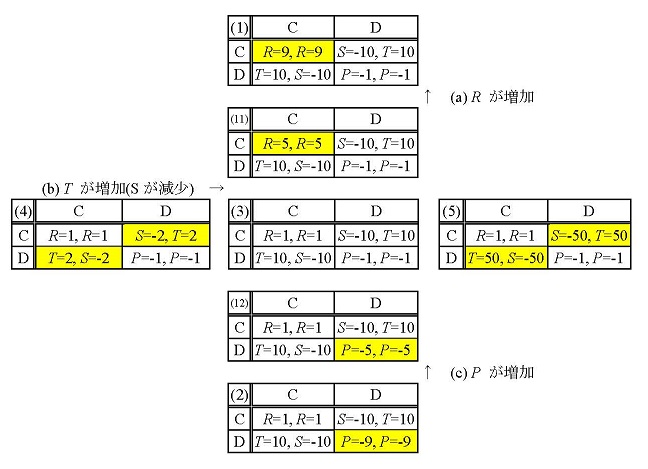
(資料) Rapoport & Chammah (1965, p.37 邦訳p.32) にある利得表をわかりやすく整理したもの。表(3)が基本になって、上・下・左右に網掛けのセルの部分だけが値を変えられている。いずれの表も S = -T, R >0, P <0 となるように単純化されている。表の番号は彼らにしたがったが、表(6)〜(10)は他の実験に使われたとされて、原典でも掲載されていない。
ただしここで注意がいるのは、本来は、プレイヤー間のあらゆる形態の協調行動が問題となるはずだが、この実験で注目されているのは各プレイヤーが、CCCCCC・・・・・・ と協調し続けるタイプの協調行動だったということである。実は、反復囚人のジレンマ・ゲームでは、別のタイプの協調行動も考えられる。それは例えば一方のプレイヤーがCDCDCD・・・・・・、もう一方のプレイヤーがDCDCDC・・・・・・というように、2人のプレイヤーがしめし合わせて、交互に裏切りに成功し合うような協調行動である。こうしたタイプの協調行動自体も本来は興味の対象であるはずだが、しかし、協調行動のタイプを複雑化することは研究上得策ではないので、単純化のためにもう一つ次のような仮定をしておくのが慣例になっている(Rapoport & Chammah, 1965, pp.34-35 邦訳pp.29-30)。
仮定1.2 R > (T+S)/2
こう仮定することで、2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合っても(例えば1回ずつ交互に裏切りに成功し合ったときの利得は T, S, T, S, T, S, ・・・・・・ あるいは S, T, S, T, S, T, ・・・・・・ となる)、その平均利得は協調しあった時の利得R を下回るようにしておくのである。これで2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合うような協調行動を考えることを排除できる。この条件を満たす囚人のジレンマ・ゲームは、(反復かどうかにかかわらず)標準的囚人のジレンマ・ゲームとも呼ばれる(鈴木, 1994, p.6)。
実は表1.6の各利得表もこの条件を満たしており、ラパポートとチャマーの実験は、正確に言うと、標準的囚人のジレンマ・ゲームの反復を行ったことになる。つまり、2人のプレイヤーが交互に裏切りに成功し合うような協調行動を事前に排除したことで、この実験では「協調」がとられる頻度だけを集中して調べればよいことになったのである。その実験の結果は図1.1のようになった。
図1.1 実験の結果として得られた「協調」の頻度
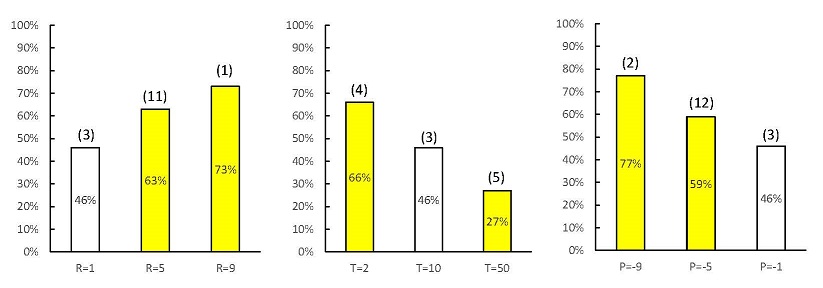
(資料) Rapoport & Chammah (1965, Figure 1)。
図1.1でもわかるように、実験をしてみると、反復囚人のジレンマ・ゲームでは、裏切り合って共倒れになるとは限らないのである。むしろ「協調」はかなりの頻度で出現する。図1.1の実験結果を彼らは次のように整理する(Rapoport & Chammah, 1965, p.38 邦訳p.32)。もし他の利得が一定に保たれるならば、
これらの結果はもっともなことであろう。そして注目されるのは、各ペアでは相互作用が強くて、2人のプレイヤーがお互いに相手の行動を真似るという傾向が見出されたことである。いまある回で、2人のプレイヤーがとる行動の間の相関係数を r0 とする。さらに、ある回で、各プレイヤーの行動と、その1回前に相手のとった行動との相関係数を r1 とする。同様に、ある回で、各プレイヤーの行動と、その i 回前に相手のとった行動との相関係数を ri とする(i=1, 2, ...)。こうして定義した相関係数を求めると、表1.7のようになった。
表1.7 お互いの行動を真似る傾向を示す相関係数
| r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相関係数 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
これからわかるように、r1 が 0.51 と一番大きく、各ペアではプレイヤーは前回の相手の行動を真似る傾向がある。つまり、前回、相手が「協調」をとった場合には「協調」で恩返しするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には「裏切り」でし返しをするのである。ちなみに、ここで扱っているデータは「協調」(C)と「裏切り」(D)の二つの値しかとらない質的データであるので、ここで言っている相関係数は正確には表1.8のようなクロス表の相関係数である。もっともこれは、Cに1、Dに0の値を形式的に与えて計算した通常の相関係数(正確にはピアソンの積率相関係数)の値と一致する。量的データで計算する相関係数と比べると、0.51 という相関係数はあまり大きくないように感じられるかもしれないが、クロス表では一般的に相関係数は低めになる傾向があるので注意がいる(高橋, 1992, ch.5)。例えば、表1.8は20,000回のプレイ(300回×70組でほぼ2万回)をクロス表にした例で、相関係数が 0.5 になっているが、目で見てもはっきりとした相関関係が認められる。つまり表1.8を例にすれば、前回、相手が「協調」をとった場合には75%の確率で「協調」で恩返しするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には75%の確率で「裏切り」でし返しをするような場合、相関係数は 0.5 になるのである。
表1.8 相関係数 0.5 のクロス表の例(20,000回のプレイ)
| プイレヤー1 | プレイヤー2 | ||
|---|---|---|---|
| C | D | 計 | |
| C | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
| D | 2,500 | 7,500 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
またこのようにプレイヤー間での相互作用が強いことから、(C, C) (プレイヤー1もプレイヤー2も「協調」(C)を選択している意味)で協調し合っている期間が長くなるか、(D, D)で裏切り合っている期間が長くなるという傾向も見られた。しかし、特に、各ペア300回のプレイのうち最後の25回に注目し、そのうち23回以上(C, C)反応がある場合を「(C, C)封じ込め(lock-in)」、23回以上(D, D)反応がある場合を「(D, D)封じ込め」と呼ぶと、(D, D)封じ込めは17%で、これは共倒れ状態の(D, D)で安定してしまって終わるが、(C, C)封じ込めは53%にのぼり、半数以上は協調し合う共生状態で安定してゲームを終了していたのである(Rapoport & Chammah, 1965, Table 6)。
これは驚くべき結果であった。なぜなら、この実験のように、有限回数の反復囚人のジレンマ・ゲームで、しかもその回数が300回であることをプレイヤーが知っている場合には、たとえ反復囚人のジレンマ・ゲームになったとしても、結局は1回限りの囚人のジレンマ・ゲームと同じで、それより以降の回のゲームの存在もむなしく、協調行動を引き出すことはできないというのがゲーム理論の結論だったからである。それなのに、「協調」が見られるというだけではなく、最終回が近づいてきてもなお半数以上は協調し合う共生状態で安定してゲームを終了していたのである[3]。
こうして、彼らの実験から、利得表によって協調行動が誘導されたり、阻害されたりすることはあるものの、ゲーム理論の結論に反して、囚人のジレンマ状況でも必ずしも共倒れ均衡に終わるわけではなく、協調行動はとられること。そして、前回、相手が「協調」をとった場合には「協調」でお返しをするが、前回、相手が「裏切り」をとった場合には「裏切り」でお返しをするという行動をとるプレイヤーが多かったこともわかったのである。いまや、均衡の概念の現実性に対しては大きな疑念が生じてきたのである。
ラパポートとチャマーによる反復囚人のジレンマの研究は、心理学的な実験によるものだった。それに対してアクセルロッド(Robert Axelrod)は、コンピュータ選手権によって反復囚人のジレンマを研究することを考えついた(Axelrod, 1980a)。これは、各回に「協調」か「裏切り」のどちらかを選択するコンピュータ・プログラムを競技に参加する人に作ってもらい、そのプログラム同士でコンピュータ上で総当たりのリーグ戦をやってもらおうというものである。
アクセルロッドは、反復囚人のジレンマ・ゲームのコンピュータ選手権に、心理学、経済学、政治学、数学、社会学の五つの分野に属するゲーム理論の専門家14人を競技参加者として招待した。そのうちの一人として、ラパポートは「お返し」プログラムで競技に参加する。このときの「お返し」は正確には、最初は「協調」、その後は、前回相手がとったものと同じ行動をとるという戦略であった[4]。これは競技に参加したプログラムの中で最も短いプログラムであり、Fortran言語でわずか4行のプログラムだったと言われる。
アクセルロッドのコンピュータ選手権では、この14のプログラムに、「協調」と「裏切り」を同じ確率で、でたらめに(=ランダムに)選択する「ランダム」というプログラムを加えて、15のプログラムが、それぞれ自分自身との対戦も含めて総当たりで対戦することになった。各対戦組合せで5試合ずつの対戦で、各試合は200回の反復プレイからなっており、ゲームの利得表は表9のようになっていた。その結果は、なんとラパポートの「お返し」プログラムが優勝したのである。
1試合で200回プレイするのであるから、毎回協調し合って、3点ずつ得点すると600点になる。同様にして、毎回裏切り合って、1点ずつ得点すると200点ということになる。理屈の上では最低点は0点、最高点は1000点になるはずであるが、大部分のプログラムの得点は200点から600点の間にあり、優勝した「お返し」の平均点は504点であった。
表1.9 コンピュータ選手権で用いられた利得表
| C | D | |
|---|---|---|
| C | R=3, R=3 | S=0, T=5 |
| D | T=5, S=0 | P=1, P=1 |
アクセルロッド(Axelrod, 1980b)はこうしたコンピュータ選手権の結果とその分析をフィードバックした上で、第2回のコンピュータ選手権を企画した。第1回のコンピュータ選手権への参加者が再招待されたのに加え、パソコン・ユーザー向けの雑誌に案内を出して一般からも参加者が募集された。その結果、6カ国から62人がコンピュータ選手権に参加することになった。そんな中で、ラパポートは今度もまた、ただ一人「お返し」プログラムで参加してきたのである。そして「お返し」は連続優勝を遂げることになる。
第2回選手権も第1回選手権とほぼ同じ方式で行われたが、ただし第1回選手権では各試合を200回の反復プレイと決めていたものを、第2回の選手権では、図1.2のように、ある回が終わるごとに、次の回もやるかそれともその回で試合を終了するかを確率で決めることにし、次回も続ける確率(これを未来係数と呼び w で表す)を0.99654とした。これは1試合の反復プレイ回数の中央値が200回になるように設定されたものである(ちなみに、1試合の平均回数を200回にするのであれば、確率は w =0.995 にしなくてはならない)。
図1.2 未来係数
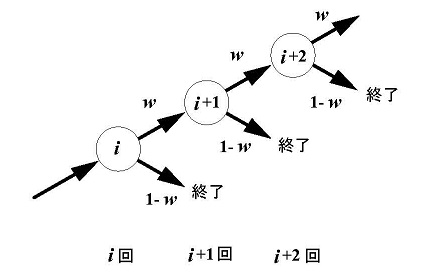
ここで後で重要になってくる未来係数について説明しておこう。次回の対戦が行われる確率である未来係数 w は、アクセルロッド(Axelrod, 1984)では discount parameter と呼ばれている。割引率と訳す方が正確であろう。しかし、現在(正確には今回の対戦)と比較した未来(正確には次回の対戦)の重さ(あるいは重みづけ; weight)(Axelrod, 1984, p.13 邦訳p.12)という意味を汲んで、ここではあえて邦訳で意訳されているように、「未来係数」(英語にすると future coefficient ということにでもなろうか)と呼ぶことにしよう[5]。未来係数が大きいということは、未来が現在同様に重要であり、あまり割引かれないことを意味している。
アクセルロッド(Axelrod, 1980b)は、この大会をさらに続けていくとどうなるかと考えた。あまりに成績の悪かったプログラムは挑戦をやめ、成績の良かったプログラムはさらに挑戦を続けるに違いないと考えたのである。人間は学習もするし、最も良いと思われるプログラムを模倣するかもしれない。それに、うまくいかないプログラムは淘汰されるだろう。
そこで、アクセルロッドはコンピュータ・シミュレーションを行った。第2回選手権への参加プログラムはそれぞれ一つずつが参加したわけであり、いわば均等なシェアを持っていたわけだが、これを第0世代とし、各プログラムが第 i 世代同士の試合で挙げた総得点に比例して、第 i+1世代のシェアが決まると設定したのである。つまり、例えば第0世代での試合でプログラムAがプログラムBの2倍の総得点を挙げたのならば、第1世代では、プログラムAはプログラムBの2倍のシェアをもつようにしたのである。同様にして、第2世代は第1世代での各プログラムの総得点に比例して、参加プログラムのシェアを決める。このように順々に第3世代、第4世代、・・・・・・ と世代を重ねていくようにしてシミュレーションが行われた。
このシミュレーションの結果、50世代を経過すると下位3分の1のプログラムはほぼ消滅し、中位3分の1のプログラムは衰退を始めていたが、上位3分の1のプログラムは増殖していた。上手な裏切りによって相手から搾取するようなプログラムは、しばらくは調子が良いように見えていても、そのうち自らが食い物にしてきたプログラムが絶滅してくると自らも絶滅していったのである。そして、シミュレーションを続けた1000世代の間、「お返し」はずっと1番の成績を挙げ続け、シェア1位を守り、最後まで最大の増加率を示してシェアを伸ばし続けていたのである。ラパポートとチャマーの実験結果にみられた「お返し」と (C, C) 封じ込めの現象は、こうした学習や模倣、あるいは淘汰の結果として出現したのかもしれない。
ところで、あるプログラムが別のプログラムによって置き換えられる時、それが模倣(学習)によるものなのか、それとも淘汰によるものなのかは、シミュレーション・モデル上は違いはなく、形式的には全く同じものとして扱っていることになる。しかし、両者の間には本質的な違いがある。それはプログラムがもっている慣性力(inertia)の大きさの違いである。慣性力が弱い時には、プログラムは変化しやすく、学習も容易である。しかし、慣性力が強い時には、プログラムが学習によって変化することはなく、別のプログラムによってそっくり置き換えられる以外に変化の方法はない。つまり淘汰以外に変化の方法はないのである。
しかし淘汰によるものでも、厳密には2種類の淘汰がある。ここで取り上げられているシミュレーションは、世代進行に伴って新しいプログラムが加わってくるわけではないので、厳密に言えば、突然変異を考慮した進化論的なシミュレーションというよりも、生態学的シミュレーションということになる。したがって正確に言えば、ここでの結果は、生態学的なシミュレーションの結果ということになる。それでは、突然変異を考慮した進化論的な状況の下では、この1000世代を経過しても、かなり安定しているように見えたという生態学的なシミュレーションの結果はどうなっていくのであろうか。
突然変異を考慮した進化論的な状況の下で、この生態学的なシミュレーションの結果がどうなっていくのか。アクセルロッド(Axelrod, 1984, ch.3)にしたがって理論的に考えてみることにしよう。
それには集団安定性という概念が用いられる。いま、ただ1種類の同じプログラムをもった個体からなる集団があるとする。そこに突然変異によって1個体だけが別のプログラムを持つに至ったと考えてみよう。もし、この突然変異個体が集団内の他の個体よりも高い得点を挙げることができれば、この突然変異プログラムは集団に侵入できるといわれる。いかなるプログラムも侵入可能でないならば、その集団がもっていたただ一つのプログラムは集団安定(collectively stable)であるという。アクセルロッドは次のような定理を証明している(Axelrod, 1981, Theorem 6) [6]。
定理1.2 「全面裏切り」プログラムはいつも集団安定である。
アクセルロッドの証明は手が込んでいるが、考え方としては、ある一つのプログラム以外は「全面裏切り」プログラムただ1種類からなる集団の中では、そのプログラムが「裏切り」をとっている間は、「全面裏切り」プログラムと同じ利得 P を挙げていられるが、「協調」をとる度に、自分の利得は S に減少し、「全面裏切り」プログラムの利得は T に増加することになるので、「協調」を一度でも選択するプログラムが侵入することができないと考えるのである。
この定理から、均衡の代わりに集団安定性という概念を用いても、やはり均衡の時と同様に、裏切り合いの共倒れが集団安定だったことがわかる。しかしここで注目しておかねばならないことは、集団安定という概念自体、実際上、一体どれほどの説得力をもっているのか疑わしいということである。つまり理論的には「全面裏切り」プログラム100%の集団には「協調」は入り込めないことになるのだが、それでは、一体、何%くらいまで「全面裏切り」プログラムのシェアが低下したら他のプログラムの侵入を許すようになるというのだろうか。
そこで試しに、「お返し」対「全面裏切り」の場合を考えてみよう。この場合、清水(1996)によると、最終的には、
の3通りのケースのうちのどれか一つになるのだが、それは未来係数の大きさと、初期状態の構成比率によって決まる。アクセルロッドがコンピュータ選手権で用いた利得表(表1.9)、未来係数 w =0.99654 の場合で計算してみると、その境界は「お返し」の構成比率わずか0.17% (つまり「全面裏切り」の構成比率は99.83%)になるという。これよりも「お返し」が多ければ「お返し」一色に、少なければ「全面裏切り」一色に最終的にはなってしまう。0.17%ちょうどであれば、この初期状態から全く構成比率が変化しないことになる(清水, 1996, pp.40-45)。
たったの0.17%である。つまり「全面裏切り」が理論的には集団安定だとはいっても、「お返し」プログラムの侵入を防ぐことは「全面裏切り」の構成比率が99.83%を超える時でなければ実現しない話なのである。0.17%をわずかでも超えて「お返し」プログラムが混じっていれば、「お返し」プログラムは「全面裏切り」に侵入できることになる。そして、いずれは「お返し」一色になってしまうのである。このような「安定性」に一体どれほどの意味があるのか、大いに疑問である。
この0.17%という境界比率は決して特殊な数字ではない。いまこの境界比率を c とし、表1.5(A)の一般の利得表の場合で求めてみると、
c=(P−S)/{(R−P)/(1−w)−(S+T−2P)} (1.3)
となる。つまり「お返し」の構成比率が、この c の値よりも大きくなると、最終的には「お返し」一色になるのである。この(1.3)式から、未来係数 w の値が十分に1に近ければ、境界比率 c の値は十分に小さくなることがわかる。したがって、未来係数がほとんど1であれば、「全面裏切り」プログラムの集団安定性は無意味になるのである[7]。
こうして、ゼロ和の制約をはずして考えた囚人のジレンマ・ゲームの裏切り合いの共倒れ均衡は、理論的には有限反復ゲームでも維持されるはずだったのに、実験ではあっさりと崩れてしまった。しかもこの裏切り合いの共倒れは、進化論的な状況でも集団安定性が理論的には証明されるものの現実的にはほとんど無意味である。ここまで来ると、もはや均衡や集団安定が本当に魅力的で説得的なアイデア、コンセプトなのかどうか疑ってみる必要がある。
わかっているのは、ゼロ和2人ゲームの美しい均衡の世界はとうに崩れ、もうここには存在しないということである。マクシミン原理はゼロ和ゲームでは均衡点を指し示してくれるという点で魅力的で説得的だったが、日常的な世界に生きているわれわれにとって、均衡や集団安定とは違う観点から見て、魅力的で説得的な別系統の意思決定原理はないのだろうか。
その点で第1回コンピュータ選手権の際にアクセルロッドが行った分析は、実に示唆に富んでいる。アクセルロッドによると、好成績をもたらしたプログラムの特徴を分析すると、おおむね次のような2点に整理されるという(Axelrod, 1984, ch.2)。
まず驚いたことに、高得点のプログラムと低得点のプログラムを分けていたのは、たった一つの性質であった。それが
【1】紳士的(nice)であること=姑息でないこと・・・・・・自分からは決して裏切らないこと
である。15プログラム中成績上位8位までのプログラムはどれもが紳士的なプログラムであった。その他のプログラムはどれも紳士的ではなかった。紳士的なプログラムは472点から504点までの平均得点を挙げていたのに対して、紳士的でないプログラムの最高得点は平均401点どまりで、得点上のギャップがあった。つまり、相手を試したり、時折つまみ食いをしたりして一時の利益を求めると、それから後の協調関係が崩れてしまい、結局は長期間協調関係を維持し続けていたよりも得点が低くなってしまったのである。
それに対して紳士的なプログラム同士は、相手が裏切らない限りは協調し続けるので、互いの平均得点を高め合った。そして裏切られた時の対応の仕方によって、それぞれの紳士的なプログラムの全体的な平均点が決まった。好成績を挙げた紳士的なプログラムがもっていた性質とは、
【2】容赦すること(forgiveness)=根に持たないこと・・・・・・相手が裏切った後でも、再び協調すること
である。教訓風に言えば、過去の裏切りをいつまでも根に持たずに水に流し、将来の協調関係を選択すべし。さもなくば、相手の一度の裏切りが果てしない報復合戦を呼び起こしてしまい、長期間その泥沼から抜け出せなくなって共倒れになってしまうということである。
つまり、【1】【2】が示唆していることは、「【1】現在の目先の利益や【2】過去の裏切りへの復讐を選択してはいけない」ということである。現在でも過去でもないとすると、残っているのは未来である。未来についてはどうしろと言っているのだろうか。結論から言ってしまえば、「【3】これからの将来の協調関係をこそ選択すべきである」ということになる。
コンピュータ選手権でも、長期的な協調関係を維持し続けることに成功したプログラムが、結果的に地道に協調の得点を積み上げ、好成績を挙げて勝ち残って繁栄していった。そのもっともシンプルな代表例が「お返し」プログラムだったのである。
「現在の目先の利益や過去の裏切りへの復讐を選択してはいけない。これからの将来の協調関係をこそ選択すべきである。」本書ではこうした理論的エッセンスを「協調・裏切り」ゲームの枠内にとどまらず、広く「未来傾斜原理」(leaning on future principle)と呼ぶことにしよう。日本企業では、多くの経営現象をこの未来傾斜原理で説明することができると考えられる。未来傾斜原理とは、わかりやすく言えば、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来を残すことを選択し、その実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという原理である。未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながることは容易に想像がつくが、これこそが未来傾斜原理に則った行動である。
しかし、よく考えてみると、この意思決定原理が生き残って繁栄していくのはあまりにも当たり前のことではないか。シミュレーションなどやってみるまでもない。いまもし、
とが競争すれば、短期的には「a. 刹那主義型システム」が羽振りをきかせる時期があったとしても、結局、何十年後かをみてみると、生き残っているのは「b. 未来傾斜型システム」に違いないからである。それはまさに、イソップの「アリとキリギリス」の寓話そのものではないか。未来係数が高ければ、この当たり前のことが実感できる。未来を実感できるのである。
ただし、一つ注意がいるのは、確かに未来係数の大きな場合には、未来傾斜原理が有効性を発揮しやすいことは容易に想像できるが、未来傾斜原理自体は、未来係数の大きさに依存するものではないということである。未来係数の大きさにかかわらず、すなわち、未来係数があまり大きくないと思われる場合にも、意思決定原理として機能しうるし、実際にも機能している。
日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、未来傾斜原理の典型的な発露である。少なくとも自分が定年退職を迎えるまで、自分の会社が存続しているかどうかわからない場合でさえ、こうして未来傾斜原理に則った意思決定が行われる[8]。
こうした事例は実にたくさん存在しており、高橋(1996b)にもそのいくつかが挙げられている。しかも、アクセルロッドの理論研究が明らかにしているのは、実は生き残るのは未来傾斜原理に則ったシステムの方だということである。進化論的な言い方をすれば、長期的パフォーマンスの点から、他の意思決定原理に則ったシステムは淘汰され、やがて未来傾斜原理に則った未来傾斜型システムが繁栄するようになる。この本でこれから観察される事実は、この理論的予想が日本企業においてはほぼその通り実現されつつあることを示しているのにすぎない。
ところで、実は、ペンローズ(Edith Penrose)は、専門経営者は、1959年に、企業内で資金を留保・再投資できれば得るところが大きいし、オーナー経営者ですら、企業から引き出される所得よりも、企業の成長にもっと関心をもっていると指摘した上で(Penrose, 1995, p.28 邦訳p.37)、こうした企業の全体的な長期利益を増加させようとする傾向を仮定すれば、企業内での再投資のために、できるだけ多くの利益を漠然と留保しておくという際立った傾向が期待できると考えていた(Penrose, 1995, p.29 邦訳pp.38-39)。こうした当時の欧米の企業に対する観察はまことに鋭いというほかない。
ただし、ペンローズは、こうした成長それ自体を目的とするような行動を、結局のところ長期的利益を目的とすることと同じだとして合理化してしまった。しかし、両者は本当に本質的に同じものなのだろうか。実は、長期的利益の最大化というアイデア自体が、割引率の大きさによってはまったく無意味になるのである。つまり、割引率が1で、全く割引かなければ、長期的利益は発散し、最大化の議論は用をなさない。しかし、成長率を大きくする、あるいは維持するという議論は依然として意味を持ち続ける。言い方を変えれば、結局のところ「利益」に回帰して行く議論と、本質的に「成長」にこだわり続ける議論とでは、実は基礎となっている意思決定原理、世界観が違うのである。その違いが、割引率1のときにはっきりするだけのことなのである。そして、後者の場合を、本書では未来傾斜原理と呼んでいる。したがって、長期的利益対短期的利益のような比較の次元や程度の問題を超えたところに、意思決定原理の違いがあると考えるべきなのである。
アクセルロッドに言わせると、一般的には、未来は現在ほどには重要ではない。繰り返しゲームの状況で言えば、プレイヤーは、利得の獲得が未来に遠退くほど利得への評価を下げる傾向があるし、未来の対戦は来ないかもしれないからである(Axelrod, 1984, p.12 邦訳p.12)。そのために、次回の対戦が行われる確率 w を discount parameter と呼んで、未来を割引くわけである。
しかし、本当にそうだろうか。そもそも、なぜ未来は割引かなくてはならないのだろうか。未来係数 w <1 は、基本的に、未来の利得よりも現在の利得の方が選好されるということを表しているのにすぎない。はたして本当に、未来は現在ほどには重要ではないのだろうか。本当にわれわれは、未来にいくほど、利得への評価を下げる傾向があるのだろうか。ひょっとすると、われわれは、現在よりも未来の方が大切だと思っているのではないだろうか。少なくとも私はそう考えているし、多くの日本企業とそこに勤める従業員はそう考えている可能性が高い[9]。仮にそうだとすると、w =1 でもいいことになる。未来係数 w が停止ルールの一種であることを思い起こせば、w=1 は終わりのない世界を表していることがわかる。この世界では、後方帰納法は意味を失っている。そして、未来傾斜原理のように未来を残す系統以外の意思決定原理はそもそも説得的ではないのである。
[1] ナッシュ均衡をめぐるこれまでの経済学の流れに関しては、神取(1994)の整理がわかりやすい。最近になって、複数均衡が存在するような場合に、進化ゲーム的なアプローチを採用することで、局所的な漸近安定性をもつ点を進化的均衡点として、歴史的経路依存性を分析しようとする試み(青木・奥野, 1996)も見られるようになってきた。ただし、ナッシュ均衡がどうやって実現するのか、ということを経済合理性だけで説明する試みはこれまでのところ失敗している(Kandori, 1997)。本書ではこうした経緯をふまえた上で、均衡を分析の中心に据えるこうした経済学分野でのアプローチとは距離を置いて、意思決定原理を分析の中心に据えた日本企業の行動分析が展開されていく。
[2] このような考え方は、後方帰納法(backward induction)と呼ばれ、もともとは統計的決定理論の逐次分析(sequential analysis)の分野で使われ始めたものである(例えば、Blackwell & Girshick, 1954, ch.9)。その後、動的計画法(dynamic programming)では、ベルマン(Richard E. Bellman)によって後方帰納法の考え方が最適性の原理(principle of optimality)に一般化された。すなわち、最適政策とは、最初の状態や決定がどうであっても、ある時点以後の決定は、その時点における状態から新しく始めた場合の最適政策となるように構成しなければならないということである(Bellman, 1957, ch.3)。この原理を数学的に翻訳することで関数方程式が導出されるが、動的計画法では、広範囲の逐次決定問題がこの関数方程式の形に定式化されて解かれることになる。経営組織論の分野でも、組織設計問題にそうした分析方法が用いられることがある(Takahashi, 1983; 1987a; 1988)。
[3] このように後方帰納法によって解かれた均衡が現実の実験データと一致しない理由として、青木・奥野(1996, ch.11)は、①人間は合理性だけではなく、ある種の感情をともなってプレイしているし、②ゲーム理論家がゲームを合理的に解く時と同じ様な合理性を持ってゲームをするわけではないからとしている。ということは、後方帰納法によって得られた均衡は非現実的だと判断していることになる。ただし、実は近代組織論では、後方帰納法に限らず、合理的思考は組織の中でこそある程度実現可能になると考えているし、それが組織の存在意義であるとも考えているので注意がいる(詳しくは第6章を参照のこと)。もっとも、実際には日本企業の場合、むしろ逐次的な意思決定プロセスをとらない方が多数派であるようなケースも調査結果からわかっているので(Takahashi & Takayanagi, 1985)、そうなると常に後方帰納法を考えることは、それ自体が現実的ではない可能性もある。
[4] 「お返し」の原語は tit for tat で、日本語では、普通「しっぺ返し」と訳され、これがほぼ定訳になっている。しかし、やっかいなのは「しっぺ返し」という日本語から、われわれは報復のみを連想してしまうということである。ここでいう tit for tat は確かに「裏切り」に対しては「裏切り」でお返しし、報復するのだが、「協調」に対しては「協調」でお返しして、恩返しするように設計されたプログラムなのである。正しい日本語としては、中立的な「お返し」を訳語に当てるべきであろう。ここでは、tit for tat を「お返し」と呼ぶことにする。
[5] この未来係数を一般化して、それまでに得られたデータによって確率が決まるようにしたものを統計的決定理論の分野では停止ルール(stopping rule)と呼んでいる。通常は決定ルール(decision rule)と対で使われ、逐次決定過程が定式化される(Ferguson, 1967, ch.7; DeGroot, 1970, ch.12)。未来係数は確率であるが、経済学的には割引率として解釈することも可能である(Axelrod, 1981)。
[6] これはメイナードスミス(John Maynard Smith)によって提唱された「進化的に安定な戦略」(evolutionarily stable strategy; ESS)をもとにして考えられたものである。ESSは、もし集団の全員がその戦略を採用していれば、自然淘汰により、どんな突然変異戦略もその集団に侵入できないような戦略を指していた(Maynard Smith, 1982, p.10 邦訳p.11)。ただし、集団安定とESSは似て非なるものである。事実、アクセルロッド自身が、この定理1.2で「全面裏切り」プログラムはいつも集団安定であると証明する一方で、それ以前の論文では、未来係数 w =1 のときは「全面裏切り」はESSではないということも証明している。ESSについて、詳しくは Kandori (1997)を参照のこと。
[7] 事実、次の定理が証明できる(Axelrod, 1981; 1984)。
「お返し」が集団安定⇔ w≧max{(T−R)/(T−P); (T−R)/(R−S)}
ただし、アクセルロッドによる十分条件の証明は不完全である。完全な証明は、清水・高橋(1996)によって行われている。
[8] もともと個々の企業の長期的な健全性や成長に興味のない機関投資家は、こうした日本企業の行動に対して、株主に還元されるべき利益が企業や系列の成長のために温存されていると批判するが、いかにも刹那主義を絵に描いたような主張でわかりやすい。このような刹那主義型システムが1960年代後半以降の米国の多くの資本集約型産業に一体どれだけのダメージを与え続けたのかを思い起こす必要がある(Chandler, 1990; 高橋, 1995b)。たとえそれが均衡や安定そして経済学的な合理性を楯にして擁護されていたとしても、企業の長期的な健全性や成長よりも短期的な株主の利益を優先させるようなシステムが生き残ることは、この章でも見てきたようにまったく現実的ではない。株式市場の好調さが企業や経済の健全性を必ずしも反映していないことは、バブル期の日本経済が立証済みである。それでもなお未来傾斜型システムが現行の株式会社制度やいわゆる「資本主義的制度」になじまないとの主張もありうるが、生き残るために変えるべきは、むしろ制度の方だろう。
[9] 実際、1992年8月〜9月に実施された日本の非金融系上場企業632社と外資系35社の投資決定方式に関する調査では、回収期間法や収益性指標を用いる企業が63%を占めており、内部収益率法や正味現在価値法といった割引率を用いた方法で設備投資を決定している企業は17%しかない(『企業の財務活動に関するアンケート調査報告書』日本生産性本部, 1993)。米国で1979年に『フォーチュン』誌上位1000社の内200社を調べた同種の調査で、割引率を用いた方法をとる企業が68%にもなるのとは対照的である(Kim & Farragher, 1981)。ただし、米国で割引率を用いた評価方法が急速に普及するのは1960年代に入ってからで、別の調査(184社)では、1959年段階で採用していた企業は19%にしかすぎなかったのが、1970年には57%にも達する(Klammer, 1972)。1960年代の合併・買収ブーム以降、米国では株主の短期的利益のために企業の長期的な能力・健全性や成長の維持が犠牲にされ、その結果、市場で競争する上で不可欠な組織能力は破壊され、米国の多くの資本集約型産業は、国内・国外市場でのシェアを急速に失うことになったが(Chandler, 1990, pp.621-627 邦訳pp.537-542)、割引率を利用する方法の普及と同時進行していることは、単なる偶然ではなかろう。こうした事態の経営学的意味については、高橋(1995b)で論じている。
日本企業では、従業員は未来傾斜原理に則って行動しているのではないだろうか。そのことを直接的に検証するために、この章では、組織に参加し続けるか、あるいは組織を離れるか、という参加の意思決定に焦点を当て、その要因を未来係数の観点から解明することにしよう。あわせて、その組織論的な意義についても探りたい。
そのために、まずはこれまで全く取り扱われてこなかった「見通し」の概念に着目し、職務満足も退出願望も、新たに開発した「見通し指数」によって、ほぼ説明可能であることを約4,500人分の調査データから明らかにする。そして、見通し指数が高いほど未来傾斜原理が機能していることを示唆している分析結果も得られる。この見通し指数は、協調行動の進化を議論する際に用いた未来係数の一種と考えられるものである。
また、未来係数は、理論上は定数なので、試みにパーソナリティーを表しているはずの「未来傾斜指数」を計算してみると、見通し指数と同様の傾向が見出せることが約23万人分の調査データによって明らかになった。そこで、企業内の従業員だけではなく、企業外の組織参加者である内定者(大学生)までも調査対象に含めて、見通し指数、未来傾斜指数を同時に調べて、その比較を行ってみた。その結果、未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まり、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されるので、見通し指数と同様の傾向が未来傾斜指数でも見られることがあるが、個人レベルで両指数の相関が高いわけではないので、例えば、退出願望については、説明力があるのは見通し指数に限られるということがわかった。しかも退出願望と見通し指数の関係は従業員も内定者もほとんど同じであることもわかったのである。
なお、この章以降、JPC調査のデータが頻繁に用いられるが、JPC調査の調査方法等については巻末付録を参照のこと。各章でその都度説明することは省略する。
動機づけ理論ではあいまいになっているが、マーチ(James G. March)とサイモン(Herbert A. Simon)は、組織のメンバーが行なう次の2種類の意思決定について、明確に区別して議論する必要があると指摘している(March & Simon, 1958, p.48 邦訳pp.74-75)。
ブルーム(Victor H. Vroom, 1964)は、文献レビュー(例えば、Brayfield & Crockett (1955) 等)もふまえた上で、職務満足と職務遂行との相関についての20の研究をレビューして、職務満足と生産性の間の相関関係自体には疑問があるものの、職務満足と離職率、欠勤との間には一貫した負の関係があると結論づけている。要するに米国では、職務に対する不満足は、生産の意思決定とは結び付かなくても、離職や欠勤という参加の意思決定とは結び付くことがわかっているのである。それでは、日本では一体どのようになっているのであろうか。この章では参加の意思決定に絞って考えてみることにしよう。
離職率の統計としては、労働省政策調査部が出している『雇用動向調査報告』のものがよく用いられる。それによると、1975〜1995年の間、離職率は13〜16%の間を推移しており、そのうち1992年は14.5%、1993年は14.0%、1994年は13.8%、1995年は14.3%だった[10]。
しかし実際には、個別の企業は離職率の数字をなかなか表に出したがらず、特に、職務満足などと一緒にその実態を調べることは非常に難しい。そこで、表に出しにくい会社全体の離職率ではなく、会社の一部の部門の離職率を調べることにした。具体的には、JPC93調査で調査対象となったA〜F社各社の組織単位において、調査時(1993年)から遡って最近の過去数年間に自己都合で実際に退職した人数を年平均で求め、それを組織単位構成人員総数で割ったものを離職率として求めることにした[11]。その結果は表2.1に示されている。JPC調査では、調査対象が大企業のホワイトカラーに限定されていることもあって、先ほどのほぼ同時期の労働省の数字と比べると、1社を除いて低めではあるが、平均して考えると特異なケースではないことがわかる。
さらにJPC93調査では、これらの各社の各組織単位における全数調査を行ない、
といった質問に答えてもらっている[12]。
ところが、質問Q2.1、Q2.2に対する各社でのYes比率をそれぞれ「満足比率」「退出願望比率」と定義した上で、実際の離職率との関係を調べてみても、表2.1に示されているように、離職率と満足比率、退出願望比率との間には明示的な関係は見出せないのである。表2.1の会社別のデータをもとにして相関係数を計算してみても、満足比率と退出願望比率との相関係数は-0.87で5%水準で有意であるが、実際の年間離職率と満足比率および退出願望比率との間の相関係数はそれぞれ-0.68, 0.47であり有意な相関は見られなかった。こうした結果は、この調査だけではない。坂下(1985, pp.205-206)の日本企業を対象とした調査研究でも、JDI系の職務満足と欠勤率、離職率との間には有意な関係は見出せていない。
表2.1 実際の離職率と他の要因(JPC93調査)
| 満足比率 | 退出願望比率 | 実際の年間離職率* | |
|---|---|---|---|
| A社 | 60.9 (110) | 25.7 (109) | 5%程度 |
| B社 | 31.2 (109) | 59.8 (107) | 20%程度 |
| C社 | 62.2 (143) | 28.7 (143) | 1%以下 |
| D社 | 48.1 ( 27) | 59.2 ( 27) | 5%程度 |
| E社 | 41.8 (553) | 54.1 (549) | 1%以下 |
| F社 | 60.1 (213) | 40.3 (211) | 5%程度 |
この事実はどのようにして説明されるのだろうか。大まかにいえば、参加の意思決定は、組織を移動する願望にだけ関係しているのではない。移動する願望に加えて、知覚された移動の容易さとも関係しているのである。より正確にいえば(March & Simon, 1958, ch.4)、
これを図式化すると図2.1のようになる。実際、米国のように組織間を移動する知覚された容易さがある程度存在するとされる社会では、組織間を移動する知覚された願望が、参加の意思決定にストレートに結び付くために、ブルームが結論したように、職務満足と欠勤、離職が相関するであろうことは容易に推測できる。しかし、日本は米国に比べれば、組織間を移動する知覚された容易さは低いレベルにあると考えられ、そのため、日本企業を対象とした調査では、職務満足と欠勤率・離職率との間の相関関係を見出すことが難しくなると推測されるのである。
図2.1 参加の意思決定の諸要因
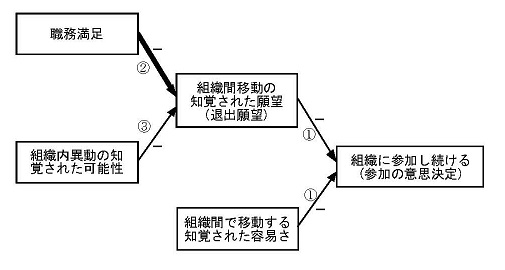
実際、日本においても、離職といった実際の行動や意思決定のレベルの事象ではなく、組織を退出したいという願望について調べるのであれば、職務満足との関係(図2.1の太い矢線で示した関係)は、比較的ストレートに確認、検証することができる。そこで1992〜1996年に行ったJPC調査のデータを用いて、先ほどの二つの質問Q2.1、Q2.2の間でクロス表をつくってみることにしよう。このクロス表は表2.2のようになるが、これから、職務満足と退出願望との間には有意な負の相関関係があり、職務満足を感じている人はその約66%が転職を考えていないが、逆に職務満足を感じていない人はその約59%が転職を考えていることがわかる。しかし、必ずしも強い相関というわけではない。これはどうしてなのだろうか。
表2.2 職務満足と退出願望(JPC92〜JPC96調査)
| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 |
Q2. チャンスがあれば転職または独立したいと思う。 | Yes | No | 全体 |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 1992年 | 138 | 198 | 336 |
| 1993年 | 180 | 377 | 557 | |
| 1994年 | 129 | 270 | 399 | |
| 1995年 | 189 | 332 | 521 | |
| 1996年 | 109 | 272 | 381 | |
| 小計 | 745 (33.96) | 1449 (66.04) | 2194 (100.00) | |
| No | 1992年 | 254 | 135 | 389 |
| 1993年 | 350 | 235 | 585 | |
| 1994年 | 259 | 166 | 425 | |
| 1995年 | 307 | 229 | 536 | |
| 1996年 | 223 | 191 | 414 | |
| 小計 | 1393 (59.30) | 956 (40.70) | 2349 (100.00) | |
| 全体 | 2138 | 2405 | 4543 | |
一つの説明の仕方としては、図2.1で示された因果関係を見ると、「退出願望」には「職務満足」だけではなく、「組織内異動の知覚された可能性」も影響を与えているため、その分、相関が弱められるという考え方である。ところが、表2.1で実際の離職率の特に低かったC社、E社については、JPC93調査の事後ヒアリング調査の結果、「社内転職」とでもいうべき、組織内での他部門への大規模な、しかも3年前後という比較的短いサイクルでの定期的な人事異動が常態化しており、その見通しが立っているおかげで、たとえ退出願望があったとしても、それは実行には移されないということがわかった。つまり、たとえ現在、職務に対する不満があり、退出願望があったとしても、「社内転職」の見通しさえ立っていれば、参加し続けるというのである。したがって正確には、「職務満足」が低ければ「退出願望」が高まり、会社を辞めたいと感じるが、その時、社内外に「転職」先があるかどうかで実際の離職行動が決まってくるということになる。もちろん、気に入った「社内転職」先があれば、離職には至らない。事実、実際の離職率が20%程度と高いB社では、こうした定期的な部門間あるいは職場間の異動はほとんど行われていなかった。異動する見通しは立たないのが普通だという。ただ、こうなってくると、図2.1は、図2.2のように太い矢線を描き直し、改訂しなくてはならない。つまり「組織内異動の知覚された可能性」は「参加の意思決定」に直接働くので、「退出願望」は「職務満足」だけからしか影響を受けないようになってしまうのである。これでは、相関は弱まらない。
図2.2 参加の意思決定の諸要因の改訂版
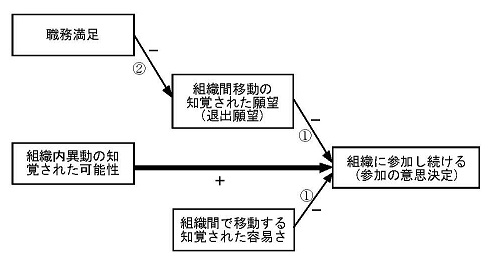
そこで、さらにもう一歩踏み込んで考えれば、不満足ならば退出することを考えるという関係自体が、果たして、マーチ=サイモンが言うように自明のことなのだろうかという疑問が湧いてくる。この章では、この疑問に対して、未来傾斜原理の観点から光を当てることにしよう。実は、ここに至って、事後のヒアリングを通して、「見通し」という用語が登場してくるようになり、しかも、実は「社内転職」の見通しだけではなく、自分と会社とのかかわりについてのあらゆる意味での社内での見通しが参加の意思決定には重要であるということもヒアリングの結果から明らかになってきたのである。この見通しこそが、未来係数の一種と考えられるのであり、職務満足、やりがいそれ自体に対しても、見通しが決定的に重要だということが、これから徐々に明らかになってくる。結論を先取りして言えば、実は見通しさえ立てば、不満足は必ずしも退出には結びつかないのである。
それでは、「見通し」という概念にはどのような要素が考えられるだろうか。実際のヒアリング調査で言及される場合、企業において従業員が「見通し」という用語を用いる際には、未来における自分と会社とのかかわり方とその程度に対する一種の重みづけが行われていると考えられる。実は、JPC93調査の前年に行われたJPC92調査においては、「見通し」とは何かという問題意識に基づいて、45問のYes-No形式の質問項目の中から、見通しに関係していると思われる次のような五つの質問項目が拾い上げられていた。
これらの質問項目に対する回答は「Yes」または「No」を選択する形で行なわれた。このうち、P1、P3、P5についてはYesと答えた方が見通しが良いと考えられ、P2、P4についてはNoと答えた方が見通しが良いと考えられる。そこで各質問について、P1、P3、P5についてはYesならば1点、Noならば0点を与え、P2、P4ついてはYesならば0点、Noならば1点を与えることにしよう。このように、二つのカテゴリーのうちどちらかに属することを0か1で表すように定義した変数はダミー変数と呼ばれるが、これらのダミー変数の単純統計と相関係数行列は表2.3のようになる。
表2.3 変数P1〜P5の単純統計と相関係数(JPC92調査; N=710)
| 単純統計 | 相関係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | P1 | P2 | P3 | P4 | |
| P1 | 0.4042 | 0.4911 | ||||
| P2 | 0.5648 | 0.4961 | 0.1731*** | |||
| P3 | 0.5634 | 0.4963 | 0.1696*** | 0.1150** | ||
| P4 | 0.2521 | 0.4345 | 0.1232** | 0.1760*** | 0.2103*** | |
| P5 | 0.2930 | 0.4554 | 0.3022*** | 0.2030*** | 0.1673*** | 0.2035*** |
そこで各変数を標準化した上で主成分分析を行なうと、各主成分に対する固有値は 1.74427, 0.92843, 0.87202, 0.77690, 0.67837 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトル
(0.467, 0.413, 0.407, 0.430, 0.511)
から、各変数の標準偏差も考慮に入れた上で各質問項目に対する重み係数を求めると、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができる。つまり、単純に合計して合成得点を作ってもよさそうだ。そこで、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点を「見通し指数」(perspective index)と定義し、これによって、組織の中での見通しの良さをみることにしよう。定義から、見通し指数は0から5までの整数値をとることになる。
そこで、先ほどと同様に、質問Q2.1、Q2.2に対する、あるグループでのYes比率をそれぞれ「満足比率」「退出願望比率」と定義する。具体的には、「見通し指数が0の人のグループ」「見通し指数が1の人のグループ」……「見通し指数が5の人のグループ」という6グループのそれぞれについて、満足比率、退出願望比率を求めることで、見通し指数との関係を調べてみた。その後のデータの蓄積も生かし、JPC92〜JPC96調査の合併データを使うことにすると、表2.4と図2.3、表2.5と図2.4を作成することができる。これらの図表から、この見通し指数が高くなるほど、満足比率が上がり、退出願望比率が低下するという、きれいな、ほぼ完全な線形の関係のあることがわかる。決定係数はそれぞれ、0.9991, 0.9975 という驚くべき高さであった。
表2.4 見通し指数と満足比率(JPC92〜JPC96調査)
(A)見通し指数の値ごとの満足比率
| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 見通し指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| Yes | 1992年 | 19 | 53 | 86 | 73 | 59 | 38 | 328 |
| 1993年 | 22 | 80 | 126 | 142 | 119 | 60 | 549 | |
| 1994年 | 17 | 44 | 65 | 83 | 99 | 86 | 394 | |
| 1995年 | 26 | 70 | 129 | 122 | 101 | 65 | 513 | |
| 1996年 | 13 | 54 | 69 | 73 | 86 | 79 | 374 | |
| 小計 | 97 | 301 | 475 | 493 | 464 | 328 | 2158 | |
| No | 1992年 | 75 | 122 | 106 | 49 | 26 | 4 | 382 |
| 1993年 | 100 | 199 | 143 | 98 | 26 | 14 | 580 | |
| 1994年 | 55 | 78 | 103 | 83 | 72 | 29 | 420 | |
| 1995年 | 127 | 162 | 108 | 82 | 44 | 4 | 527 | |
| 1996年 | 66 | 114 | 118 | 62 | 36 | 11 | 407 | |
| 小計 | 423 | 675 | 578 | 374 | 204 | 62 | 2316 | |
| 全体 | 520 | 976 | 1053 | 867 | 668 | 390 | 4474 | |
| 満足比率(%) | 18.65 | 30.84 | 45.11 | 56.86 | 69.46 | 84.10 | 48.23 | |
(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 見通し指数 | 12.996 | 0.190 | 68.481 | 0.0001 |
| 定数 | 18.346 | 0.575 | 31.931 | 0.0001 |
図2.3 見通し指数と満足比率(JPC92〜JPC96調査)
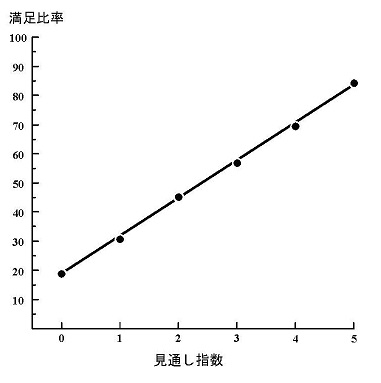
表2.5 見通し指数と退出願望比率(JPC92〜JPC96調査)
(A)見通し指数の値ごとの退出願望比率
| Q2. チャンスがあれば転職 または独立したいと思う。 | 見通し指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| Yes | 1992年 | 72 | 110 | 96 | 66 | 33 | 8 | 385 |
| 1993年 | 90 | 170 | 123 | 86 | 38 | 16 | 523 | |
| 1994年 | 60 | 119 | 104 | 55 | 33 | 13 | 384 | |
| 1995年 | 99 | 130 | 111 | 85 | 47 | 13 | 485 | |
| 1996年 | 50 | 90 | 92 | 50 | 33 | 14 | 329 | |
| 小計 | 371 | 619 | 526 | 342 | 184 | 64 | 2106 | |
| No | 1992年 | 21 | 63 | 95 | 56 | 52 | 33 | 320 |
| 1993年 | 31 | 107 | 143 | 155 | 106 | 58 | 600 | |
| 1994年 | 44 | 86 | 97 | 79 | 71 | 44 | 421 | |
| 1995年 | 54 | 102 | 125 | 119 | 98 | 55 | 553 | |
| 1996年 | 29 | 78 | 96 | 87 | 88 | 76 | 454 | |
| 小計 | 179 | 436 | 556 | 496 | 415 | 266 | 2348 | |
| 全体 | 550 | 1055 | 1082 | 838 | 599 | 330 | 4454 | |
| 満足比率(%) | 67.45 | 58.67 | 48.61 | 40.81 | 30.72 | 19.39 | 47.28 | |
(B)退出願望比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 見通し指数 | -9.484 | 0.237 | -39.966 | 0.0001 |
| 定数 | 67.986 | 0.718 | 94.624 | 0.0001 |
図2.4 見通し指数と退出願望比率(JPC92〜JPC96調査)
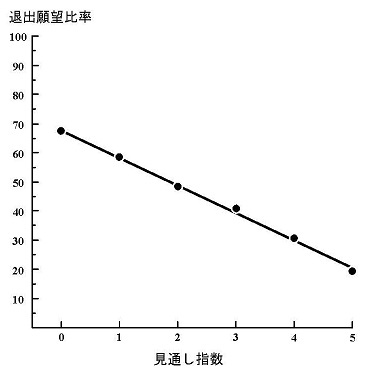
さらに、同じJPC92〜JPC96調査の合併データを使って、3重クロス表を作ると、表2.6のようになった。見通し指数の各値ごとに職務満足と退出願望のクロス表を作って比較してみると、見通し指数の値の小さいときの各クロス表は強い相関関係が認められるが、見通し指数の値が大きくなると、相関係数である Cramer's V の値が小さくなる傾向がある(図2.5)。つまり、見通し指数が大きくなるほど、現在の職務満足は退出願望に影響しなくなるのである。後述する追試、CC&C95調査の場合には、この傾向はさらに鮮明に現れる(図2.11)。こうしたことは一見奇妙に思えるかもしれないが、見通し指数が未来係数の一種だと考えれば、未来傾斜原理に則ると当然のことなのである。
表2.6 見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(JPC92〜JPC96調査の合併データ)
| 見通し指数 | 現在の職務に満足感を感じる | 相関係数 Cramer'sV |
χ2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Yes | 2. No | |||
| 0 | 43.88( 98) | 72.57(452) | -0.234 | 30.194*** |
| 1 | 42.28(324) | 65.84(729) | -0.221 | 51.318*** |
| 2 | 40.72(501) | 55.61(579) | -0.149 | 23.851*** |
| 3 | 35.09(493) | 49.27(341) | -0.142 | 16.759*** |
| 4 | 28.38(437) | 37.27(161) | -0.085 | 4.367* |
| 5 | 17.71(288) | 30.95( 42) | -0.112 | 4.113* |
図2.5 見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(JPC92〜JPC96調査の合併データ)

前章で指摘したように、未来が実現する確率、つまり未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながる。そして過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという未来傾斜原理が機能しやすくなる。個人の場合で考えれば、たとえ現在、職務に対する不満があったとしても、その会社での未来への見通しさえ立っていれば、それに寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながり、退出行動はおろか、退出願望にも至らないのである。見通し指数が大きければ、現在の職務満足は退出願望に影響しないという表2.6と図2.5の関係は、見通し指数が未来係数の一種であると考えると、まさに未来傾斜原理そのものであり、うまく説明することができるのである。つまり調査データでは、見通し指数が高いほど、未来傾斜原理が機能するようになることを示唆している。
そこでいま一度、表2.2に見られるような職務満足と退出願望の間の相関関係を再考してみると、これは両変数とも見通し指数との間に強い線形の関係があるために現れる疑似相関であると説明することもできることになる(安田・海野, 1977)。ところが、職務満足の研究において注目されてきたのは、職務満足と退出願望等との相関関係だけであり、これまで「見通し」や未来係数は重要視されてはこなかった。例えば、第4章でも取り上げるが、ブルームの期待理論(Vroom, 1964)では、ゲーム理論や決定理論で考えられている期待効用原理ときわめて近い形で外的報酬による動機づけを扱っている(高橋, 1993b)。また、ローラー=ポーター(Lawler & Porter, 1967)は、職務遂行と職務満足との間に、第3の変数である報酬(rewards)を入れて、高い職務遂行はある場合には報酬を生み出し、報酬は職務満足を引き起こすと主張する。しかしこれでは、職務満足の概念は職務遂行や報酬に対する「過去から現在に至るまで」のいわば後向きの評価の産物ということになる。果たして、職務満足は単に後向きの評価の産物なのだろうか。根拠はなかったのである。
ところで、見通しと未来係数との間には、違いがあるということも考えておかねばならない。それは、見通しが自分と会社のかかわりという比較的変動しやすい「変数」として考えられているのに対して、アクセルロッドの考えた未来係数は、モデル上は変数ではなくて「定数」だったということである。もちろん、モデルを簡単にするための仮定だったのであるが、仮に未来係数が実際上も定数であるならば、それはおそらくパーソナリティーに近い性格をもっていることになろう。もしそうだとすると、見通し指数よりも、よりパーソナリティーに近い未来係数的な指数であったとしても、職務満足や退出願望を見通し指数同様にうまく説明できる可能性がある。
そこで実際に、そのことを確かめてみよう。利用したデータは社会経済生産性本部のメンタル・ヘルス研究所が実施している「JMI(Japan Mental Health Inventory)-心の健康診断」の調査(以下「JMI調査」と略記)で収集されたデータの一部である。JMI調査では596項目から構成される質問調査票に従業員個人が答える。今回利用したのは、見通し指数と調査時点、調査対象を揃える意味もあって、1992〜1994年にJMI調査を受けた企業のうち、大企業67社の全従業員(ただし、非常に規模の大きな企業については1事業所のみとなっている企業もある)、実に232,957人分のデータである。
JMI調査では個人毎に596項目の質問から職場領域、精神領域、性格領域、身体領域の4領域の55尺度が求められる。今回はこうしたJMI調査の既存の尺度とは別に、未来係数及び未来傾斜原理の概念的吟味に基づいて、性格領域のパーソナリティーに分類されている項目の中から、次の5項目を選びだした。
そして、それぞれの質問で「はい」ならば1点、「いいえ」ならば0点を与え、5項目の合計点数を求めて、それを未来傾斜指数と定義した。そこで見通し指数のときの満足比率、退出願望比率と同様に、次の質問
表2.7 未来傾斜指数と生きがい比率(JMI調査)
(A)未来傾斜指数の値ごとの生きがい比率
| Q3. 今の仕事に生き がいを感じている。 | 未来傾斜指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| はい | 4,489 | 12,307 | 18,868 | 21,434 | 19,702 | 13,857 | 90,657 |
| いいえ | 28,699 | 37,631 | 34,567 | 23,877 | 12,810 | 4,716 | 142,300 |
| 全体 | 33,188 | 49,938 | 53,435 | 45,311 | 32,512 | 18,573 | 232,957 |
| 生きがい比率(%) | 13.53 | 24.64 | 35.31 | 47.30 | 60.60 | 74.61 | 38.92 |
(B)生きがい比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 未来傾斜指数 | 12.151 | 0.335 | 36.310 | 0.0001 |
| 定数 | 12.289 | 1.013 | 12.129 | 0.0003 |
図2.6 未来傾斜指数と生きがい比率(JMI調査)
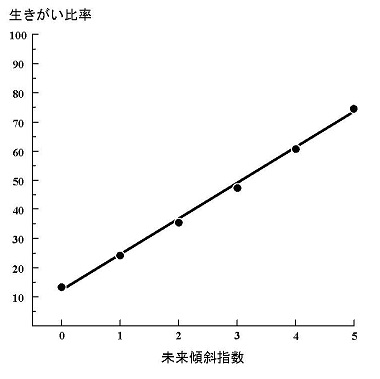
表2.8 未来傾斜指数と勤続願望比率(JMI調査)
(A)未来傾斜指数の値ごとの勤続願望比率
| Q4. 私は今後ともこの 会社で働き続けたい。 | 未来傾斜指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| はい | 19,361 | 34,590 | 39,557 | 35,537 | 27,060 | 16,387 | 172,492 |
| いいえ | 13,827 | 15,348 | 13,878 | 9,774 | 5,452 | 2,186 | 60,465 |
| 全体 | 33,188 | 49,938 | 53,435 | 45,311 | 32,512 | 18,573 | 232,957 |
| 勤続願望比率 | 58.34 | 69.27 | 74.03 | 78.43 | 83.23 | 88.23 | 74.04 |
(B)勤続願望比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 未来傾斜指数 | 5.592 | 0.510 | 10.973 | 0.0004 |
| 定数 | 61.274 | 1.543 | 39.711 | 0.0001 |
図2.7 未来傾斜指数と勤続願望比率(JMI調査)
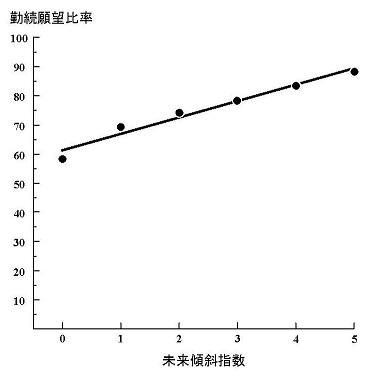
既に述べたように、未来傾斜指数の5項目は、いずれもJMI調査のパーソナリティー項目に含まれている。実際、今回の利用データでは、未来傾斜指数とJMI調査の「目標遂行性」との相関係数は0.8760と高い。そして、この目標遂行性はJMI調査では性格領域のパーソナリティーと位置付けられている。そのことは5つの質問項目をもう一度見てみると良くわかる。このことから、職務満足や退出願望は、見通し指数という変数で説明できるだけではなく、長期にわたって安定しているはずのパーソナリティーつまり定数である未来傾斜指数でも説明ができるのかもしれない。しかし、実際にはJPC調査での見通し指数、職務満足、退出願望の質問項目はJMI調査の調査項目には入っていないし、逆に、JMI調査での未来傾斜指数、生きがい、勤続願望の質問項目はJPC調査では調べられていない。したがって、本当に、職務満足や退出願望が、見通し指数だけではなく未来傾斜指数でも説明ができるのかどうかを検証する必要がある。また見通し指数と未来傾斜指数のどちらが説明力があるのかも見極める必要がある。
前章で指摘したように、未来が実現する確率、あるいは未来に対する重みづけである未来係数が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながる。そして過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという未来傾斜原理が働く。日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、未来傾斜原理の典型的な発露である。同様にして、個人の場合でも、たとえ現在、職務に対する不満があったとしても、その会社での未来への見通しさえ立っていれば、それに寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながり、参加の意思決定を促すだろう。
しかし、これは見通し指数についての話である。未来傾斜指数の場合はこうはいかない。仮にパーソナリティーとしての未来傾斜指数が高かったとしても、どんな会社に対しても長く勤めようとする一般的な傾向があるとは考えにくい。むしろ、未来傾斜指数が高いからこそ、将来性など未来のことを考え、長期の勤続に値しない会社だと判断するケースもありうる。そうだとすると、おそらく未来傾斜指数が見通し指数と同様の性質をもっているのは二次的な理由によるものだろう。それには次の二つの可能性が考えられる。
いずれにせよ、こうして考えると、変数としての見通し指数も、定数としての未来傾斜指数も同様の傾向をもっていることを矛盾なく説明できる。この際、1と2のどちらが正しいかという議論は、学問的にはともかく、実際上はあまり重要な問題ではないだろう。なぜなら、パーソナリティーとしての未来傾斜指数の高い人は、既に従業員になっている場合でも、これから新規になろうとする場合でも、変数としての見通し指数を高くするような経営を常日頃から選好していると考えられるからである。つまり企業の内側に入っているのか、それともまだ外側にいるのかの違いはあっても、両者は表裏一体というわけである。言い方を変えれば、企業の境界をまたいで連続性があるはずである。
このことは大学生を考えるとよりはっきりする。大学生は親からはかなりの独立性をもって一消費者、一顧客として行動している。同時に大学生は、現在の日本ではほとんどが卒業とともに就職するわけであるが、大学の4年生ともなると、今度は企業を就職の対象として考え始める。そして卒業すると、今度は企業という境界を踏み越えて内側に入り、従業員として組織に参加するわけである。しかし、その前の就職活動の段階では、
このことを確かめるためには、従業員だけではなく、大学生、特に就職が内定している大学生をも調べてみる必要がある。
そこで、こうしたことを検証するために、「大学生」「内定者」「従業員」の3グループを対象としたCC&C95 (Corporate Communication and Culture 1995)調査が企画、実施された。このCC&C95調査では、
の3群を調査しているが、A群の大学生調査の結果については、ここでは取り上げない(高橋(1996b)で分析を行なっている)。今回取り上げたB、Cの2群の間では、できるだけ共通の質問調査票を用いた調査が行われた。
A群で東京大学経済学部及び経済学部進学内定者を調べたために、それとの接続を考えて、B群、C群は過去3年間に東京大学経済学部の卒業生の採用実績のある民間企業から選ばれている。手順としては、まず該当する63社の人事部長宛に1995年8月1日付で「CC&C調査への参加のお誘いとお願い」を送付し、そのうち8月中に反応のあった15社と調整を行い、実施条件などで調整のついた9社が調査対象となった。各企業において、B群については全員、C群については、入社1年目の新入社員全員と約100人規模のホワイトカラー部門を対象にして、10月から12月にかけて、質問調査票を配布・回収してもらう方法で調査が行われた。このうちB群の「内定者」については、10月2日(月曜日)の「内定式」の際に実施されたケースが多かった。
ここで分析に用いたのは、CC&C95調査の調査対象9社のうち、B群、C群の2群が両方とも調査できた7社に限定している。7社全体では、B群: 配布530人; 回収451人; 回収率85.1%、C群: 配布1603人; 回収1168人; 回収率72.9%となり、両群合わせると、配布2133人; 回収1619人; 回収率75.9%であった。ほとんど無回答の調査票は未回収扱いとした。
まず、満足比率と見通し指数、未来傾斜指数の関係を確認してみよう。職務満足についての質問は、本質的に「内定者」には答えられない質問なので、ここでわかるのは「従業員」群についての関係のみである。表2.9と図2.8から明らかなように、JPC調査同様に、かなりきれいな線形の関係がある。決定係数は0.9911という高さである。しかし、JPC調査と比べると、上方に10ポイント近く平行にシフトしている。これは東大生が就職するような企業を調査対象にしたことにより、その社会的ステータスの高さが、生きがいや満足感を押し上げているからかもしれない。こうした傾向はこれまでにも指摘されていた(高橋, 1994)。CC&C調査の対象企業は就職人気ランキング上位に名を連ねるような企業だけに事実上限定されてしまっている。JPC調査の対象企業も大企業には違いないが、知名度、大きさなどの点で、必ずしもすべての調査対象企業が、CC&C調査の対象企業に比肩するほどではない。
表2.9 見通し指数と満足比率(CC&C95調査)
(A)見通し指数の値ごとの満足比率
| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 未来傾斜指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| 従業員 | はい | 38 | 87 | 141 | 188 | 193 | 115 | 762 |
| いいえ | 60 | 87 | 93 | 64 | 34 | 11 | 349 | |
| 全体 | 98 | 174 | 234 | 252 | 227 | 126 | 1,111 | |
| 満足比率(%) | 38.78 | 50.00 | 60.26 | 74.60 | 85.02 | 91.27 | 68.59 | |
(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | 見通し指数 | 10.910 | 0.516 | 21.163 | 0.0001 | 0.9911 | 0.9889 | 447.873 |
| 定数 | 39.380 | 1.561 | 25.230 | 0.0001 |
図2.8 見通し指数と満足比率(CC&C95調査; JPC調査)
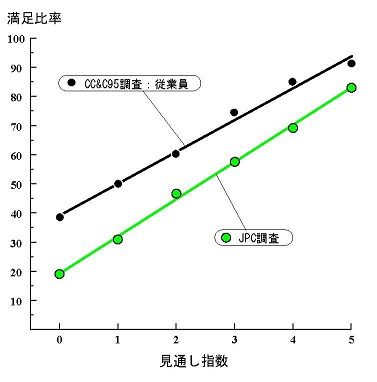
また、JPC調査では調べていなかったが、未来傾斜指数と満足比率の関係を調べると、表2.10と図2.9のようになり、線形の関係はあるものの、決定係数は0.8743で、満足比率については、見通し指数の方が、説明力が高いことがわかる。
表2.10 未来傾斜指数と満足比率(CC&C95調査)
(A)未来傾斜指数の値ごとの満足比率
| Q1. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 未来傾斜指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| 従業員 | はい | 27 | 71 | 148 | 171 | 170 | 182 | 769 |
| いいえ | 36 | 45 | 77 | 84 | 65 | 48 | 355 | |
| 全体 | 63 | 116 | 225 | 255 | 235 | 230 | 1,124 | |
| 満足比率(%) | 42.86 | 61.21 | 65.78 | 67.06 | 72.34 | 79.13 | 68.42 | |
(B)満足比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | 未来傾斜指数 | 6.172 | 1.170 | 5.274 | 0.0062 | 0.8743 | 0.8429 | 27.819 |
| 定数 | 49.300 | 3.543 | 13.915 | 0.0002 |
図2.9 未来傾斜指数と満足比率(CC&C95調査)
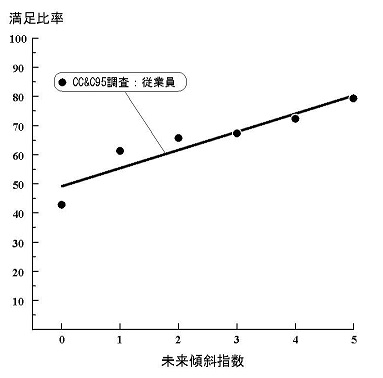
次に、見通し指数と退出願望比率の関係を調べてみよう。「内定者」「従業員」の各群について、見通し指数と退出願望比率の関係を調べてみると、表2.11と図2.10のようになった。いずれもJPC調査ほどにはきれいではないが、線形の関係を示している。しかも、見通し指数0のところを除いて両群ともほぼ同じ退出願望比率を示している。見通し指数0のところで「内定者」の退出願望比率が極端に高いのは、該当者が3人しかいなかったための標本誤差と考えられ、本質的なものではない。つまり企業外であっても、「内定者」は見通しに基づいて、企業内の「従業員」とほぼ同程度の退出願望をもつことがわかった。JPC調査と比べると、全般的に直線の傾きが幾分小さく、見通し指数の値の割には退出を考えないという傾向が見られるが、JPC調査とほとんど同じ直線を描いているといっていいだろう。
表2.11 見通し指数と退出願望比率(CC&C95調査)
(A)見通し指数の値ごとの退出願望比率
| Q2'. チャンスがあれば 転職したいと思う。 | 見通し指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| 内定者 | はい | 3 | 5 | 13 | 32 | 44 | 29 | 126 |
| いいえ | 0 | 6 | 19 | 46 | 98 | 62 | 231 | |
| 全体 | 3 | 11 | 32 | 78 | 142 | 91 | 357 | |
| 満足比率(%) | 100.00 | 45.45 | 40.63 | 41.03 | 30.99 | 31.87 | 35.29 | |
| 従業員 | はい | 58 | 87 | 97 | 89 | 76 | 37 | 444 |
| いいえ | 40 | 84 | 137 | 164 | 152 | 89 | 666 | |
| 全体 | 98 | 171 | 234 | 253 | 228 | 126 | 1,110 | |
| 満足比率(%) | 59.18 | 50.88 | 41.45 | 35.18 | 33.33 | 29.37 | 40.00 | |
(B)退出願望比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | R2 | Adjusted R2 | F(1,4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内定者 | 見通し指数 | -10.961 | 4.242 | -2.584 | 0.0611 | 0.6253 | 0.5316 | 6.675 |
| 定数 | 75.730 | 12.844 | 5.896 | 0.0041 | ||||
| 従業員 | 見通し指数 | -5.942 | 0.722 | -8.230 | 0.0012 | 0.9442 | 0.9303 | 67.725 |
| 定数 | 56.420 | 2.186 | 25.809 | 0.0001 |
図2.10 見通し指数と退出願望比率(CC&C95調査; JPC調査)
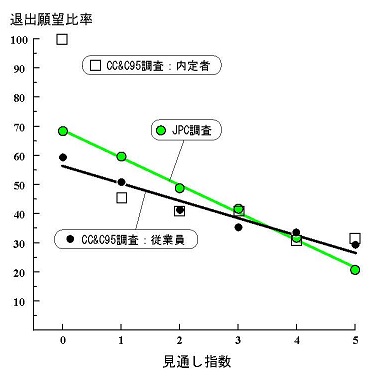
ところで今回のCC&C調査では、勤続願望は退出願望の裏返しと考え、勤続願望についての質問は入れずに、退出願望についての質問だけを入れている。ところが、JMI調査で従業員に見られた未来傾斜指数と勤続願望比率の線形の関係は、今回の未来傾斜指数と退出願望比率の間には見出せなかった。「従業員」の決定係数は 0.1078 ( p=0.5253)しかなかった(同時に調べた「内定者」は決定係数 0.7509 ( p=0.0255)で、有意であった)。退出願望を未来傾斜指数で説明することは難しいようだ。
さらに、JPC調査のときと同様に、「従業員」群について3重クロス表を作ってみると、表2.12のようになった。「内定者」については職務満足について聞いていないので、クロス表は作れなかった。見通し指数の各値ごとに職務満足と退出願望のクロス表を作ると、見通し指数の値の小さいとき、各クロス表の相関係数である Cramer's V の値は大きいが、見通し指数の値が大きくなると、相関係数が小さくなる傾向が見られる。図2.11でも示されているように、職務に満足している人の退出願望比率はほぼ29〜39%の範囲内で安定しているのに比べて、満足していない人は、見通し指数が大きくなると急速に退出願望が低下する傾向がある。そして、見通し指数が大きくなると、両者の差はほとんどなくなり、見通し指数が5に至ると、職務満足と退出願望の間に有意な相関は消失する。つまり、見通し指数が大きければ、現在の職務満足は退出願望に影響しなくなるのである。このことは既にJPC調査の所で、未来傾斜原理によってうまく説明できるとしていた通りである。しかもJPC調査よりも、さらに鮮明にその関係が現れている。つまり、見通し指数が高いほど、未来傾斜原理が機能していることが、このことからわかるのである。
表2.12 「従業員」の見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(CC&C95調査)
| 見通し指数 | 現在の職務に満足感を感じる | 相関係数 Cramer's V | χ2 | |
|---|---|---|---|---|
| はい | いいえ | |||
| 0 | 39.47 ( 38) | 71.67 ( 60) | -0.319 | 9.981 ** |
| 1 | 35.29 ( 85) | 66.28 ( 86) | -0.310 | 16.422 *** |
| 2 | 29.79 (141) | 59.78 ( 92) | -0.297 | 20.614 *** |
| 3 | 30.32 (188) | 50.00 ( 64) | -0.179 | 8.096 ** |
| 4 | 32.12 (193) | 41.18 ( 34) | -0.068 | 1.064 |
| 5 | 28.95 (114) | 27.27 ( 11) | 0.010 | 0.014 |
図2.11 「従業員」の見通し指数・職務満足ごとの退出願望比率(CC&C95調査)
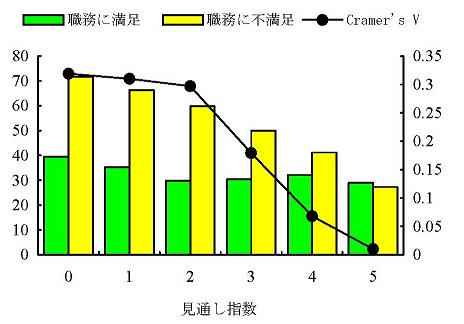
それでは、見通し指数と未来傾斜指数の関係はどうなっているのだろうか。両者の間の相関係数は0.327 (N=1464; p=0.0001)となっている。データ数が多いので統計的には有意になっているが、相関関係自体は弱い。それに対して、会社別に「内定者」と「従業員」に分けて見通し指数・未来傾斜指数の平均を求め、プロットしてみると、図2.11のような相関係数0.8795の強い相関関係が見出される。データ数14個でも統計的に有意である( p=0.0001)。図を見ればわかるように、「内定者」は高見通し・高未来傾斜で「従業員」は低見通し・低未来傾斜だが、各点はどれもほぼ同じ直線にのりそうに見える。つまり、見通し指数と未来傾斜指数の相関は、個人レベルでは低いが、企業レベルでは高いのである。未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まっていると考えられるし、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されていると考えられる。
図2.12 会社別に見た内定者・従業員の見通し指数・未来傾斜指数(CC&C95調査)
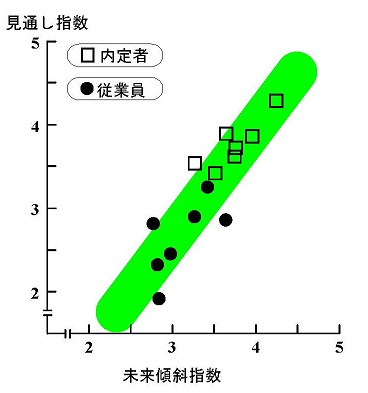
これまでの調査結果をまとめると、次のようになる。
要約すれば、未来傾斜指数の高い内定者は見通し指数の高くなるような企業を選んで集まり、未来傾斜指数の高い従業員が多く集まった企業では見通し指数を高く導くような経営施策やビジョンが選択されるので、見通し指数と同様の傾向が未来傾斜指数でも見られることがあるが、個人レベルで両指数の相関が高いわけではないので、例えば、退出願望については、説明力があるのは見通し指数に限られるということになる。しかも退出願望と見通し指数の関係は「従業員」も「内定者」もほとんど同じであることがわかったのである。
それでは、こうした結果に、一体どのような組織論的意義があるのだろうか。 もともと企業は外部環境から内部環境を隔離する「境界」の概念である。それに対して、組織はそれとは異質な、独立に定義される要素間の関係、結合といった「システム」の概念なので、その関係が企業という境界からはみ出していても一向にかまわない(高橋, 1995b)。事実、もともと近代組織論では、組織は企業という境界を超えて広がっていると考えられていたのである。例えばバーナード(Barnard, 1938)とサイモン(Simon, 1947)によって探究された組織均衡(organizational equilibrium)の概念では、組織は参加者と呼ばれる多くの人々の相互に関連した社会的行動のシステムとされ、「参加者(participants)」(バーナードに言わせると「貢献者(contributors)」)の範囲として、通常、われわれが組織メンバーと考える従業員に加えて、投資家、供給業者、顧客といった、今言うところの、いわゆるステークホルダー(stakeholder)まで含めて考えられていたのである(cf. March & Simon, 1958, p.84 邦訳p.128)。
ところが、1970年代以降、内部組織の経済学が隆盛を迎える頃には、経済学者だけではなく、経営学者によっても、組織概念は企業の内部に封じ込められ、「組織」といえば、まさに企業の内部組織だけを指すようになっていた。つまり、いつしか組織均衡論のもっていたステークホルダーまで含めるという組織の広がりは失われてしまっていたのである。
近年になって、マーケティングの分野で注目される関係性マーケティングの考え方(嶋口, 1994, ch.8)では、ステークホルダーまで含めて組織を考え、その組織の均衡を考えているので、まさに組織均衡論は蘇りつつある。しかも、こう考えると、企業外の市場においてリピーターのような特定の顧客層に対するマーケティング活動で最近話題になる顧客満足(customer satisfaction; CS)と、企業内の従業員に対するモティベーション管理で扱われてきた職務満足とは、企業という境界の外と内の違いはあっても、両者ともちょうど同じ組織均衡を扱っていることになる。このことは先ほどの大学生の例でもよくわかる。
ただしCC&C調査でも大学生を調べる時に苦労したように、職務満足はその企業に勤めるまでは生まれないし、顧客満足だって製品・サービスを試用するまでは生まれない。つまり、顧客満足や職務満足が存在しているのは限定された状況下だけなのである。だとすると、「満足」によって、企業を超えた広がりをもつ組織への参加の意思決定を扱うこと自体が、理屈の上で無理があったことになる。言い換えれば、組織均衡論的な視点に立てば、満足と参加の意思決定の関係を調べるという課題設定自体が、論理的に無意味なのである。事実、組織均衡概念では、各参加者が組織を去るか否かについて無差別になるとき、誘因の効用と貢献の効用とのバランスがとれていると考えるわけだが、この誘因・貢献効用スケール(inducement-contribution utility scale)を満足スケールで代替することには論理的に問題があるとされていた(March & Simon, 1958, ch.4)。
正確に言えば、誘因・貢献効用はそもそも操作的な概念ではなく、構成概念にすぎなかったのかもしれない。その意味では、退出願望と見通し指数の関係が、企業内の「従業員」にとっても、企業外の「内定者」にとってもほとんど同じであったという事実は、未来係数が誘因・貢献効用の実体であった可能性を示唆していて注目される。実際、図2.12で示したように、CC&C調査では、組織に参加している「従業員」も「内定者」も、彼らの未来傾斜指数は組織がもたらす見通しとバランスがとれていた。しかも「見通し」は顧客に対しても有効である。例えば、リピート購入するような消費者の場合には、その企業の行動に対して、ある種の「見通し」をもっていると考えた方が自然である。パーソナル・コンピュータの機種の選定やソフトの選定に際しても、消費者は現在の製品の品質や価格だけをもとにして選んでいるわけではない。むしろ、今後もより高機能の新機種を出し続け、ソフトのバージョン・アップをし続けるという「見通し」の高い企業のものを選んでいると考えられる。
そしてなんといっても、第1章でも述べたとおり、未来係数が大きいことは、囚人のジレンマ状況でも全面裏切りが集団安定になることを阻止し、協調行動を引き出すことにつながるのである。これは、未来係数が大きければ組織均衡が維持されるということを直接的に意味している。つまり、組織均衡論は、見通し指数という未来係数の一種を得たことで、企業という境界を超えて広がっている組織への参加の意思決定を現実的に説明できる理論として再構築される可能性が出てきたことになるのである。
[10] ただし、これは発表されるのが翌年末と遅い。そのためJPC93調査のときは、当時バブル崩壊直後ということもあり、変動も予想されたために、より近い時点の統計数字として、別の統計も参考にした。それは労働省の労働市場センター業務室が毎年、雇用保険被保険者の記録から新規学校卒業者の就職・離職状況をまとめたもので、毎年8月発行の『労政時報』にその紹介が掲載される。後ほどの参考のために、1989〜1992年の数字を挙げておくと、例えば、『労政時報』(1993年8月20日) No.3128, pp.36-38 によれば、全国の新規学校卒業就職で雇用保険適用事業所に雇用されて新規に被保険者資格を取得した者、1989年3月卒27,292名、1990年3月卒25,873名、1991年3月卒23,241名を対象として、1992年10月31日現在で就職・離職状況を取りまとめると次のようになるという。
[11] 『雇用動向調査報告』でいう離職者とは「調査期間中に雇用関係が終了した者及び系列企業への移動者(移籍出向を含む)」であり、離職理由別に離職者をみると、1993年は個人的理由71.6%、契約期間の満了9.0%、経営上の都合7.0%、本人の責5.0%、定年4.5%、死亡・傷病2.8%となっている。これらのうち、参加の意思決定と関係しているといえるのは、個人的理由による離職だけなので、JPC93調査では、自己都合による退職者だけをカウントすることを考えたのである。ちなみに、1992年は個人的理由が77.0%を占めていたが、1994年には71.5%、1995年には68.2%であり、1993年以降はほぼ7割前後だったことがわかる。こうしたことからバブル崩壊後の自己都合だけを考えた離職率は『雇用動向調査報告』の離職率、約14%よりも3割程度低い値、つまりほぼ10%程度になっていたと考えられる。
[12] 職務満足については、多元的概念として扱う研究者が多いが、それがどんな次元から構成されているのかということについては、多くの研究者の間で合意があるわけではない。しかも代表的なコーネル系のJDI (Job Descriptive Index)やミネソタ系のMSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire)のように、幅広く職務要因の種類ごとに多くの質問項目を用意し、それをもとにして合成得点として職務満足を求めてしまうと(坂下, 1985, pp.140-142)、本書のように、多くの質問項目を探索的に分析に用いる場合には、分析の過程で、説明変数側と被説明変数側とで質問項目が実際上重なるケースも出てくる可能性がある。しかし、それを事前に回避して職務満足を定義するのでは、かえって恣意的で客観性に欠ける。したがって本書では、あえて合成得点を用いずに、質問Q2.1でストレートに職務満足を表すことにする。
[13] ただし、未来傾斜指数と未来係数の厳密な意味での違いには注意しておく必要がある。未来傾斜指数は、そのもとになった質問を見てもわかるように、一定時間(たとえば3年)たった後の未来と現在の重みの比較を行ったものである。それに対して、アクセルロッドが繰り返しゲームの状況で考えていた未来係数は、次回と今回の重みの比較である。つまり、対戦を頻繁にすることで、一定時間内の対戦回数を増やすことができれば、次回と今回の時間間隔は短くなり、未来傾斜指数は一定のままでも、未来係数は向上させることができる。そしてそのことで、協調行動は生まれやすくなるのである(Axelrod, 1984, p.130 邦訳p.137)。
日本企業とその従業員のもつ未来係数の高さは、未来係数という用語こそ存在しなかったが、実は、従来より日本的経営論の中で繰り返し、かつ一貫して主張されてきているものである。日本企業では、雇い主は従業員の解雇や一時解雇をしようとしないし、また従業員も辞めようとしないということを指して用いられている終身コミットメントの指摘は、その典型であろう。
戦後、比較的早い時期から、進んだ米国の経営に対比して、遅れた前近代的な経営というニュアンスを込めて「日本的経営」という言葉が日本国内で使われていたといわれている。このころの議論の中心は、日本の労使関係であった。後に、日本的労使関係の「三種の神器」として有名になる終身雇用、年功賃金、企業別組合なども、1960年代までは、欧米の労使関係研究者の間でも、欧米の労使関係制度の枠組みを大きく逸脱する前近代的で家父長主義的な枠組みを引きずるものであり、後進性の現れととらえられていたのである。
それが1950〜1960年代の日本経済の復興と高度成長を経て、1970年代になると、欧米の学者によって「日本的経営」が評価されるようになる。さらに、1980年代に入ると、米国企業の生産性の伸びの低下と日本企業の躍進を背景に、米国企業では日本的経営の長所を見習って、それを取り入れようという動きまでが見られるようになる。このように日本経済と日本企業の活躍の度合によって、日本的経営に対する評価は大きく振れ、評価が右往左往する。それでも、終身「雇用制度」であったかどうかはともかく、終身「コミットメント」は戦後、一貫して指摘されてきたのである。しかし、従来、これと年功賃金(それと企業別組合)をワン・セットにして、日本的経営の中心に据えた議論が多かったが、両者が「日本的経営」という一つの実態の二つの側面なのだという捉え方には疑問がある。
そこでこの章では、こうした流れを整理した上で、バブル崩壊後「日本的経営の存亡の危機」説がマスコミ等で喧伝されるようになったインパクトを利用して、日本的経営の内部構造を探ってみることにしよう。1994年に実施した40歳代の管理職の調査では、終身雇用への態度と年功賃金への態度は、連動していないことが明らかになる。終身コミットメントを基本に考えると、年功賃金ではなく、生活費保障給が本来の姿なのである。
また、多国籍企業の文化的側面の研究として先駆け的な研究を参考にして、1996年に日本企業3社の国内の情報処理技術者について行った調査結果と、そのうち1社の9カ国の海外現地法人のエンジニアについて行った調査結果とをもとにして、日本の企業の位置付けも行ってみよう。こうすることで、バブル崩壊後も、依然として、日本における終身コミットメントは国際比較の点からも特徴的であることがわかってくる。
終身「雇用制度」ではなく、終身「コミットメント」こそが日本では企業の未来係数の高さを示唆している。そして、未来係数が高ければ、企業とその従業員が未来傾斜原理を意思決定原理として採用することは容易になるのである。
アベグレン(James C. Abegglen)は、非欧米国でしかも一貫してアジア的なものを残していながら、当時既に工業国といえるようになっていた日本で、1955年から1956年にかけて19の大工場と34の小工場を訪問調査し、その結果をもとにして、1958年に『日本の経営』(The Japanese Factory, 1958)を著わした。これは、日本的経営に関する海外の文献でこの本を引用しないものはほとんどないというほどの記念碑的業績である。その中でアベグレンは「米国式の組織および管理の制度は、工業化に対する数個の可能な方式の一つをなすにすぎない」(「日本語版への序」)と考え、当時、日本の工場では組織等が欧米とは著しく異なっているということにほとんど何の注意も払われないままに、欧米の生産において有益だった方法や機械がそのまま導入されていることに疑問を呈した。そして、日本の工業化の研究を通じて、欧米的な生産組織の方式の限界とその適応の限界を調べようとしたのである(1958, ch.1)。
アベグレンは、米国の工場との決定的な違いとして、日本で見られる終身コミットメント(lifetime commitment)に着目する。これは、日本の工場では、雇い主は従業員の解雇や一時解雇をしようとしないし、また従業員も辞めようとしないということを指している。実態から考えても、終身雇用というよりもこちらの方が正確だと思われるが、それ以上に、終身コミットメントの定義は未来係数の高い状態を直接的に指し示していて注目される。それに対して、アベグレンによれば、米国の会社では、逆に高い移動率は望ましいものと考えられていたというのである。
そして、終身コミットメントがあるために、そのままでは日本の工場では、景気変動や需要変動に適応できなくなってしまうので、環境の経済的・技術的変化に対するバッファーとして、日本の工場では、現在でも広く観察される次の二つの方法が既にとられていたという。
こうして、この終身的なコミットメントは、求人や採用の制度、動機づけと報酬の制度との間に相互に密接な関係をもっており、まさに日本の工場組織全体の基本的な部分をなしていると指摘するのである(1958, ch.2)。そのことをアベグレンの著書にしたがって、順に整理しておこう。
まず終身的であれば、採用時の選考の失敗はなかなか正せないし犠牲も伴うので、注意深く選考が行われる(1958, ch.3)。また、いくつかの工場での例を挙げて、職員と工員では賃金体系が違うものの、工員に対する生産性手当は、通常は生産高が標準生産高基準を超えているために、実質的には恒常的かつ安定的に支払われていることを指摘し、日本の工場では、給与制度が基本給の基準方式の上に立てられていて、勤続年数と入社時の教育程度によってのみ決まるとする(いわゆる年功賃金)。賞与もそれを当てにして従業員が生活水準を考えられるほどに定期的な賃金制度となっているが、この賞与のおかげで、経営者は基本的な賃金制度を改めることなしに、報酬に対する組合の要求に応えることができる。そして福利厚生費は直接労務費総額に対して20%の付加分をなしている工場もあった。
こうして、作業の成果に対する動機づけは、大部分、忠誠心と集団への一体感に依存しており、それはほとんど米国の家族集団に近いものであるとされる。日本の制度は家父長的な制度といっていいと主張する。それに対して、米国では、現金支払賃金は報酬のはるかに大部分を占めていて、従業員が会社に対する自分の価値や自分の職務に対する成功度を評価するのに用いられる。欧米の制度は職務と現金報酬との間の非人格的交換を強調し、生活水準や健康水準は個人の責任の問題となっていると対比されるのである。(1958, ch.4)
また日本の工場の管理組織は公式的には精巧であるが、機能的には不明瞭で、粗雑にしか定義されていない。決定に際して、直接にその個人的責任を負う危険にあえて一個人をさらすことをせず、能率を犠牲にしてでも会社内の人間関係を維持しようとする。また、通常、共通の大学の経験と背景を基礎にして、大会社にははっきりとした閥が作られており、それは昇進と成功に対してインフォーマルにではあるが、非常に重要な役割を果たす。訓練は主としてOJT (on-the-job-training)であり、先輩や上司から学ぶことである。こうして従業員と上司との密接な関係を促進することで、本質的に家父長的関係で従業員を会社に結び付けるきずなを強めているとされる(1958, ch.5)。実際、「良い職長は、父親が自分の子供を見るように、自分の工員を見る」という所見にすべてのグループから強い同意が得られたという。米国の大企業の比較的非人格的かつ合理化された生産方式・組織的制度と比較すると、日本の工場は家族的であるように思われるというのである(1958, ch.6)。
しかし、こうした日本の工場に対するアベグレンの評価は、特に生産性に関しては否定的である。第7章「日本の工場における生産性」では、生産性に関連して、終身雇用や年功賃金に対する否定的な見解が述べられていた。すなわち、日本の工場の生産性は、それと同等の米国の工場の50%もなく、多くは20%程度しかない。それは日本企業が終身的であるために、規模と費用の点で固定した非常に大きな労働力を維持しなければならないためである。非能率的な従業員を会社から除くことは非常に困難で、管理階層または現場で不適当と証明された人達のために害のない地位を見つけだすことになる。しかも、少なくとも欧米流の着実かつ効果的な生産に対するおもなインセンティブは取り去られる。また、生産における誤りや失敗の責任を特定の個人に帰することを習慣的に回避するために、米国では考えられないような品質管理上の問題が発生しているというのである。こうした主張は、40年を経たバブル崩壊後の日本で声高に主張されていることと全く同じで驚かされる。しかし、こうした生産性に関する見解は、その新版として1973年に『日本の経営から何を学ぶか』(Management and Worker, 1973)を著わした際には、章ごと完全に削除されることになる。
こうした中で、「日本的経営」を題に入れた日本で最初の書物といわれているのが、小野豊明の『日本的経営と稟議制度』(1960)である[14]。ただしその中では、「日本的経営」という用語は全く用いられず、山城章にしたがい、日本の企業経営を「稟議的経営」と呼んでいる。そして、日本的経営を理解するための中心的な概念として「稟議制度」が取り上げられる。小野は「業務の執行にあたって広く上長または上部機関の決裁または承認を受けることを定めている場合」(p.28)を広く稟議制度としてとらえているが、こうなると、1960年当時の日本企業の経営はまさに稟議的経営であった。つまり、前近代的な要素を多分にもっていて、職能分化が不十分で、スタッフも未発達で、責任体制も欠如しているということになる。
小野によれば、日本では、「封建的農村社会において長い伝統を持つ家族制度が、西欧から輸入された近代企業にそのまま移植され」(p.4)たのである。その原因は一つには、「近代企業の経営を担当したのが、主として封建時代から存在した同族的商人経営の専門家」(p.4)であったためで、もう一つには「近代企業が農村に近接して成立し、その労働力は農村からの出稼労働者によって満たされたため、伝統的な農業社会の家族制度的な考え方が、そのまま企業社会にもちこまれた」(p.4)ためだというのである。
しかし小野は、企業の近代化につれて、稟議制度はやがて発展解消し、廃止される運命にあるとしていた。それまでは、職位とその職務権限に関する概念がまだ確立しておらず、稟議書の立案者と決裁者・承認者を明らかにした稟議規定が、職位の権限に関する唯一のものだった。しかし、当時、企業経営の革新が進行中であり、稟議制度のもっていたマネジメント機能を他の制度の導入によって整備して、稟議制度の発展的解消をはかることこそが、まさに近代化の過程だというのである[15]。
一方同じ頃、日本の労務管理、労使関係について、その歴史的変遷を分析すると共に、比較的早い時期から「日本的経営」という用語を用いていた間宏は、その著書『日本的経営の系譜』(1963)で、戦前の日本的経営の特質を経営家族主義で要約してみせる。そしてこの戦前の経営家族主義を再編したものとして、戦後の日本的経営が位置付けられる。つまり管理施策の面では、戦前のものを引きずっていて、形式的には全く類似しているというのである。より具体的には
といったものがそれだとされる。戦前と戦後で変わったのは理念の面で、戦前の経営家族主義では(戦前の家族制度での)親子関係的な労使一体論で労使関係を考えていたものが、戦後は、労使協調論に立って、企業の繁栄、従業員の生活向上、社会への福祉へ向けての労使協力を考える(これを経営福祉主義と呼んでいる)というように転換されたというのである(pp.261-263)。
1960年代の日本経済の高度成長期を経て、1970年代になると、欧米の学者によって「日本的経営」の見直しが行われるようになった。つまり、日本企業の経営スタイルにも積極的に評価すべきところがあるというのである。それまでの日本的経営に関する否定的評価が肯定的評価に変わったターニング・ポイントともいえる論文がドラッカー(Peter F. Drucker)によって発表されたのが1971年だった。ドラッカー(Drucker, 1971)は、当時の米国の経営者の直面する最重要課題として三つを挙げ、日本の経営者がこれらの問題に対して欧米とは異なる対処の仕方をしていることが、日本の経済成長の重要な要因だとした。すなわち、
その翌年出版された『OECD対日労働報告書』(1972)では、時の労働事務次官、松永正男の寄せた「序」において「OECDが日本の労働力政策を検討するにあたっての中心的な関心と問題意識は、日本的風土のもとに形成された生涯雇用、年功賃金、企業別労働組合という雇用賃金慣行−報告書ではこれらを総称して「日本的雇用制度」(Japanese Employment System)といっている−が、いわゆる<三種の神器>として日本の経済成長にいかに貢献したか、それが現在どのように変貌しつつあり、労働力政策に対してどのような課題を投げかけているか、ということにあった」と肯定的な評価が与えられている。こうして、終身雇用、年功賃金、企業別組合などが日本的労使関係の「三種の神器」と呼ばれるようになったのも、ちょうどこの時期であった。戦後直後に発表されたGHQ労働諮問委員会(Labor Advisory Committee)の「恒久的賃金制度に関する勧告」では、当時の年齢、性、婚姻状態の相違に基礎を置く賃金給料制度は経済的に不健全であり、不公平であり、将来、排除されるべき雇用慣習の一部と考えられていた(高田, 1982)というから、まさに様変りである。
間と共同で日立製作所の日立工場・多賀工場を、そして英国のイングリッシュ・エレクトリック社の2工場を調査して比較したドーア(Ronald P. Dore)の『イギリスの工場・日本の工場』(British Factory-Japanese Factory, 1973)は、日本の工場について、間と類似した企業福祉集団主義を指摘した。しかし実は間もそうだったのだが、ドーアは日本的経営の集団主義的性格については、戦後の社会民主革命を経てもなお残る前近代的な家父長主義的性格のものという考えはとらなかった。それどころか、ドーアは逆に、産業社会が向かいつつある発展傾向の最も先端的な姿として捉えていたのである。
同じ1973年には、アベグレンが1958年の『日本の経営』(The Japanese Factory, 1958)の新版として『日本の経営から何を学ぶか』(Management and Worker, 1973)を著わし、旧版を第2部とした3部構成で出版している。その際、旧版で終身雇用や年功賃金に対して否定的な評価を与えていた第7章「日本の工場における生産性」については、これを章ごと完全に削除するとともに、新たに付加した第1部「70年代における日本の終身雇用制」では、「日本の終身雇用制が非常に大きな強みをもっているにもかかわらず、それは非能率的であり、実際にはうまく働かないと西欧では一般的に見られている」ために西欧中心主義に陥りやすいのだとしてしまう。そして、まず年功賃金であるために、学卒者を多数採用する成長企業は人件費を引き下げると同時に最新の技術教育を受けた人材を確保でき、しかも終身雇用のため、学卒者は慎重に成長企業を選択するというように、成長企業には有利なシステムになっているとする。さらに終身雇用と企業別組合のおかげで、日本企業は労使関係に破滅的なダメージを与えることなく、企業内の配置転換によって、急速に技術革新を導入できたというのである。
こうして、海外での見直しの動きに背を押されるように、1970年代半ばからは、日本の研究者にとっても、日本的経営のブームが到来することになる。代表的な論者としては、津田眞澂は、戦前の経営が家族的編成の原理に立っていたのに対して、戦後の経営はそれとは別の原理によって編成されていて、たまたまそれらが外形的に近似したに過ぎないとした『日本的経営の擁護』(1976)を序曲として、自身の日本的経営論の集大成と評する『日本的経営の人事戦略』(1987)まで、「日本的経営」をタイトルに入れたものだけでも8冊を著わしている。
これに対して、戦前、戦後を通じて日本的経営の根底にある一貫した編成原理が存在していたとする立場のものとしては、岩田龍子が『日本的経営の編成原理』(1977)で、日本的経営の背景を、日本の伝統的な社会や文化、あるいは日本人固有の心理特性として安定性志向の強いある種の集団主義に求める。他方、アベグレンの翻訳者でもある占部都美は『日本的経営を考える』(1978)において、終身雇用、年功昇進、年功賃金といった制度は、いずれも日本的経営の不変の要素というわけではなく、その根源に、経済合理的、適応的な側面があるのであって、低成長経済のもとでは、終身雇用には雇用調整、年功昇進には能力主義、年功賃金に対しては職務給という変化が現れてきているとする。
こうして日本企業の経営システムが国の内外で注目を集める中で、1980年代以降の日本的経営のブームの火付役を果たすことになる研究が、米国で伏流的に静かに進行していたことを指摘しておかなければならない。1970年代以降、日本企業の海外直接投資が本格化し始めたなかで、例えば、米国の日系企業と純粋な米国企業との比較研究が行われていたのである。パスカル(Richard Tanner Pascale)とオオウチ(William G. Ouchi)は、1973〜1974年に20社以上の日本と米国の企業を訪問調査した。その成果は1974年の共著論文 (Johnson & Ouchi, 1974)に著わされるが、その後、パスカルはさらに詳細なデータ収集に進み、一方、オオウチは「セオリーZ」的な米国企業の調査に進む。
パスカルによる米国の日系企業の研究によれば、ボトム・アップ・コミュニケーション、公式文書、協議による意思決定という点で、日本企業の特徴が指摘される(Pascale, 1978a)。さらに業種、組合組織化の程度、事業所の設立年、技術要因などをコントロールして、米国の現地企業と日系企業の各11社について、従業員に対するアンケート調査、管理者へのインタビュー調査、文書調査を行った。その結果、日系企業は従業員の交流、レクリエーションに米国企業の2倍以上の額を支出しているし、第一線管理者1人当りの作業員数は米国企業29.1人に対して日系企業14.8人、20分間に同僚と話す頻度も米国企業44%に対して日系企業66%、といったようにコミュニケーション面では違いが見出された。しかし、仕事の満足度については両者に差は見られず、また日系企業の方が欠勤、遅刻、離職が多いというように、必ずしも、日系企業のパフォーマンスが良かったわけではない(Pascale, 1978b)。
米国では、1980年に『ビジネス・ウィーク』誌(Business Week, October 27, 1980, pp.148-160)が、1983年には『フォーチュン』誌(Fortune, October 17, 1983, pp.66-72)が企業文化の特集を組んだことで、「企業文化」(corporate culture)という用語が急速に普及したといわれている。学術誌でも1983年には『アドミニストレーティブ・サイエンス・クオータリー』誌(Administrative Science Quarterly: ASQ, Vol.28, No.3, 1983)が「組織文化」の特集を行い、日本では組織学会編集の『組織科学』誌(Vol.17, No.3, 1983)が「コーポレート・カルチャー」の特集を行っている。
こうした流れの背景には、1980年代に入ると目立ってきた米国企業の生産性の伸びの低下がある。そんな米国企業に取って代わって躍進してきた日本企業を目の当たりにして、文化という言葉がキーワードになってきたのである。それは、企業の活動が国境を越えて行われるようになり、米国企業だけではなく日本企業も多国籍企業化して米国をはじめとする世界中に生産拠点等をもつようになったという時代の反映でもあった。
このような米国企業の生産性の伸びの低下を嘆く論調は、米国で「企業文化」「組織文化」をブームにしただけではなく、それと同時並行する形で、日本的経営の長所を見習って、それを取り入れようという動きにつながった。その代表的存在が、オオウチのベスト・セラー『セオリーZ』(Theory Z, 1981)なのである。
そこではまず、日本企業の組織の理念型としてタイプJ、米国企業の組織の理念型としてタイプAを考える。タイプJの終身雇用、遅い人事考課と昇進、非専門的なキャリア・パス、非明示的な管理機構、集団による意思決定、集団責任、人に対する全面的な関わりという特徴とは対照的なものとして、タイプAの短期雇用、早い人事考課と昇進、専門化されたキャリア・パス、明示的な管理機構、個人による意思決定、個人責任、人に対する部分的関りを挙げている。例えば、米国では経営幹部ですら離職率が高い。管理職は3年間も重要な昇進がないと失敗したという気持ちになり、早期に昇進しないと企業をすぐに変えてしまうというヒステリックな症状を示す。その結果、短期雇用となり、早い人事考課と昇進が必要になると指摘する。1960年には4,000人ほどしかいなかったMBA新規取得者が1980年には45,000人にもなったことも火に油を注ぐ結果となっているというのである[16]。
ところが、オオウチは米国企業の中にもタイプJと類似した特徴をもっている企業があることに気がつく。IBM、ヒューレット・パッカード、インテルなどの企業である。これらの企業は日本の真似をしたわけではなく、米国で独自の発展をしてきた企業なのである。そこでオオウチはこれをタイプZと呼び、このタイプZによる経営が米国においても可能であり、このことで生産性が左右されることを主張したのである[17]。
これに対して、オオウチと共同研究していたパスカルも、エイソス(Anthony G. Athos)との共著『ジャパニーズ・マネジメント』(The Art of Japanese Management, 1981)を同じ年に発表する。こうしてオオウチの『セオリーZ』は、翌1982年のピーターズ(Thomas J. Peters)=ウォーターマン(Robert H. Waterman, Jr.)の『エクセレント・カンパニー』(In Search of Excellence, 1982)、ディール(Terrence E. Deal)=ケネディー(Allen A. Kennedy)の『企業文化』(Corporate Cultures, 1982)といった日本企業を意識した一連の企業文化ものの先駆けとなったのである。
ただし、後者の2冊は、日本企業を見習えと主張したわけではないことには注意がいる。例えば、ディール=ケネディーの主張は米国企業はNCR, GE, IBM, P&G, 3Mといった米国の偉大な会社を作り上げたオリジナルの概念やアイデアに帰る必要があるというもので、1960年代後半からのM&Aブーム、コングロマリット・ブームが始まる前の米国の企業を見習えというものだった。そしてその頃の米国企業は出版当時の日本企業と同じ様な企業文化をもっていたのである。例えば、「マサチューセッツ工科大学を卒業したてのエンジニアの卵が、真新しい計算尺をもって、新調のスーツを着て、ゼネラル・エレクトリック社(GE)に初出社したときの話。出迎えた無愛想な年配の上司に、いきなりほうきを渡されて床を掃けと言われる。しばしぽかんと口を開けて突っ立っていたものの、新入社員ということもあり、言われた通りにしたけれど、あれは自分の人生でまたとない最良の教訓だった……。」(Deal & Kennedy, 1982, p.65 邦訳pp.107-108)というように。
しかし、オオウチの議論については、そのモデルを日本の経営に求めていることは明白である。オオウチやパスカルの著書の出現により、日本的経営の見直しの動きは新しい局面を迎えた。この時期のメイン・テーマはなんといっても生産性であり、その源泉として、当初は企業文化的なものが注目され、1980年代半ば頃からはより直接的に、自動車産業を中心とする日本企業の生産システムが注目を浴びることになる。それは、日本経済がバブル景気に浮かれていた1990年前後には最高潮に達する。
トヨタの生産方式に焦点を当てた門田安弘の『トヨタシステム』(Toyota Production System, 1983)は、数ヵ国語に翻訳され、読まれた。ここでトヨタ生産方式あるいはジャスト・イン・タイム生産システム(JIT生産方式)とは、必要な物を必要な量だけ必要な時に生産することで、過剰在庫や過剰な人件費を排除して、コストを低減させるシステムである。そのための手段として、後工程で使った部品を定期的に前工程に引き取りに行き、前工程は引き取られた量だけ生産するという「かんばん方式」がとられる。こうした生産システムであれば、文化とは異なり、日本以外の国でも導入可能なはずで、実際に、こうした生産方式を採用した日本の自動車メーカーの米国進出工場が成功をおさめている様子は、島田晴雄の『ヒューマンウェアの経済学』(1988)でも紹介された。
そして、こうした関心は、製造工程だけにとどまらず、自動車の製品開発プロセスにまで向けられる(Clark & Fujimoto, 1991)。1990年には、MITが中心になってそれまで5年間続けてきた自動車産業に関する大規模な国際研究プロジェクトの最終報告書が出される。世界の優れた自動車生産システムの主流はかつて米国が誇っていた大量生産方式ではなく、日本企業がとっている企画、製品開発、製造、さらには部品業者、販売業者に至るまでの無駄なく柔軟な「リーン(lean=痩せた)生産方式」に移行したと指摘するのである(Womack et al., 1990)。
また、こうした動きは生産システムだけに限ったことではない。雇用システムでも同様の動きが指摘されている。もともとドーア(1973)は、英国など先発先進国が市場志向型から日本的な組織志向型雇用システムへ移行していると仮説を出していた。つまり、雇用の期間と条件は、労働者の熟練が他の雇主から外部市場においていかなる対価を受け取るかということから影響される度合をますます弱めていき、各企業独自の相対的ランク付けの内的構造に適した比較的安定的な長期雇用の存在を予想するものへと移行するとしていたのである。
しかし出版当時(1973年)は、英国の学会でそのようなことを発表すると、「とんでもない」と退けられるのが普通だったという。ところが、やはり1980年代後半になると、事情はかなり変わってくる。当時、日本語版(1987年)に寄せられた「日本語版への序」によれば、英国では、
1992年にバブルが崩壊すると、経営環境や制度的制約の変化によって、日本的経営の要素として「三種の神器」にも数えられていた終身雇用と年功賃金はその存亡の瀬戸際に立たされていると論じられることが多くなってきた。具体的に言えば、本来、年功賃金であれば、昇給の続くはずの40歳代の管理職で、年収が頭打ちになったり、あるいは減収に追い込まれる可能性が出てきたり、あるいは終身雇用を標榜することをやめ、40歳代の管理職にまで早期退職勧奨を制度化する動きなどが、景気低迷の中で進行し、マスコミでしきりに取り上げられるようになってきたのである。
このマスコミ等で喧伝される「日本的経営の存亡の危機」説は、そのインパクトを利用して、日本的経営の内部構造を探る絶好の機会を提供してくれた。というのも、従来、終身雇用と年功賃金(それと企業別組合)をワン・セットにして、日本的経営の中心に据えた議論が多かったのだが、本当に両者が「日本的経営」という一つの実態の二つの側面なのかについては疑問があったからである。アベグレンの主張していたように、終身雇用、正確に言えば終身コミットメントこそが、日本的経営の本質で、年功賃金は別なのではないだろうか。だとすれば、終身雇用への態度と年功賃金への態度は、必ずしも連動していないはずである。
そこで、終身雇用と年功賃金がゆらぐ中での従業員側の態度を調べるため、1994年5月に実施された「高齢化時代に適合した人事管理モデルに関する調査」(これ以降「AGE94調査」と略称する; 翌1995年にも第2回調査が行われているが、調査項目が異なるので、ここでは取り上げない)のデータを使って、そのことを検証してみよう。このAGE94調査は『ダイヤモンド会社職員録上場会社版』に掲載されている役員・管理職約25万人のうち、40歳代のいわゆる団塊の世代とその前後の世代から、5,000人をランダム・サンプリングして、郵送法によって質問票の配布・回収を行ったものである。このうち1,519人から回答が得られた。回収率は30%ということになる。
AGE94調査では、次の質問によって、百万円単位の「現在の年収」額と「転職しないかわりに受け入れる減収」率を聞いている。
調査結果は図3.1に示されている。まず現在の年収にかかわりなく、ほぼ一定に10%前後の人が、減収よりは転職を選ぶとしていることが注目される。逆に言えば、転職よりも減収を選ぶ人がほぼ一定で90%前後いるということになる。つまり、90%程度の人は、賃金よりも雇用の安定を求めていたことになる。
図3.1 現在の年収と転職しないかわりに受け入れる減収率
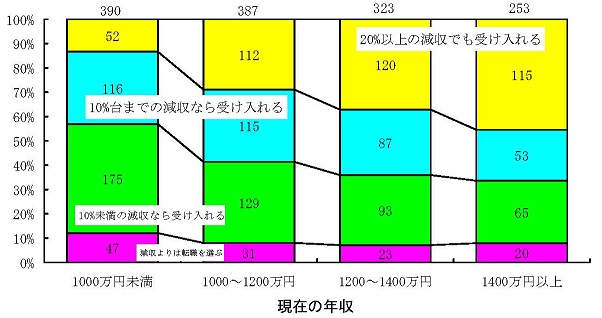
(AGE94調査; Cramer's V=0.153, χ2=95.575, p<0.001)
そして、一見してわかるように、転職しないかわりに(=会社に残れる代わりに)20%以上の減収を受け入れる人の割合は、現在の年収が増えるにしたがって増えてくる。10%以上の減収を受け入れる人の割合で見てもこの傾向は同じで、現在の年収が1000万円未満の人では57%の人が10%以上の減収を受け入れないが、現在の年収が1400万円以上の人では、逆に66%の人が10%以上の減収を受け入れるとしていて、多数派が入れ代わる。すなわち、会社に残るという人は、年収が高いほどより大幅な減収を受け入れるが、年収が低いと大幅な減収を嫌がる傾向があり、給与の額に対する生活費保障給的な意識が強いことがわかる。
次に「早期退職勧奨への対応」について質問してみた。
表3.1でもわかるように、早期退職勧奨を断ることと、会社に残る代わりに10%以上の減収を受け入れることとは関係がなく、この両者の分類は無相関で、表3.1の四つのセルはほぼ4分の1ずつに均等に割られている。つまり、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動していないことになる。
いま、表3.1の各セルに「柔軟姿勢派」「強硬姿勢派」「賃金重視派」「雇用重視派」というラベルをつけた上で、現在の年収階層別に分布を調べたのが図3.2である。この図で示されるように、現在の年収が増えるほど、「賃金重視派」が減り、「雇用重視派」が増えるという傾向があることがわかる。しかし、各年収階層別に、表3.1のようなクロス表を作ってみても、図3.2の下にも示されているように、早期退職勧奨を断ることと、会社に残る代わりに10%以上の減収を受け入れることとは、現在の年収1000〜1200万円の階層でやや負の相関が見られるもの、各年収階層別に見てもほぼ無相関なのである。つまり、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動していない。
ということは、現在の年収が減るほど「賃金重視派」が増えるという傾向は、もともと低収入の人が、これ以上収入が減っては暮らしていけないと考え、それならば金銭的な優遇措置で早期退職・転職に踏み切らざるをえないということを示しているといえよう。つまり、賃金が年功ベースで上昇し続けるという理由で年功賃金が重要視されていたわけではなかったのである。年齢に応じた生活費を保障するような賃金水準を維持することこそが重要なのである。したがって、日本の大企業では、経営環境が悪化した時に、従業員も労働組合もある程度、賃金や配属などでじっと我慢をしようという態度が現れるし(例えば、1996年秋に三井金属がべア廃止を打ち出したように)、企業側もまずは雇用保障をしようという判断につながるのである。
以上のことから、これまで終身雇用と年功賃金をワン・セットで日本的経営の柱に据える論調が多かったものの、実は、終身雇用への態度と年功賃金への態度は連動しておらず、両者は「日本的経営」という一つの事象の二つの側面というより、高度成長期にたまたま同時に観察されてきた別々の事象だったことになる。こうして、終身雇用と年功賃金をワン・セットにして考えるという呪縛から抜け出し、あくまでも、終身コミットメントを基本に考えると、重要なのは賃金が年功ベースで上昇し続けることではなく、年齢に応じた生活費を保障するような賃金水準を維持できるかどうかなのだということが、より明確になってくる。つまり、終身コミットメントの帰結は、年功賃金ではなく、生活費保障給なのである。このことは歴史的経緯としても確認できる。
表3.1 日本的経営の存亡に直面した対応の4モード(AGE94調査)
| 会社に残れるなら10%以 上の減収でも受け入れる | 早期退職勧奨への対応 | ||
|---|---|---|---|
| 受けてもよい | 断りたい | 計 | |
| 受け入れる | 柔軟姿勢派 380(27.64) | 雇用重視派 405(29.45) | 785( 57.09) |
| 受け入れない | 賃金重視派 305(22.18) | 強硬姿勢派 285(20.73) | 590( 42.91) |
| 計 | 685(49.82) | 690(50.18) | 1,375(100.00) |
図3.2 現在の年収と日本的経営の存亡に直面した対応の4モード(AGE94調査)
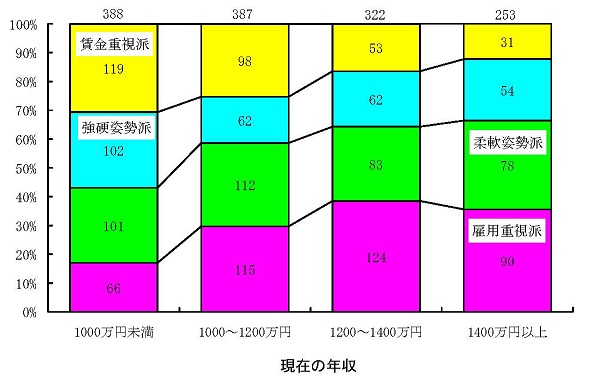
| Cramer's V | 0.066 | -0.118 | -0.058 | 0.095 |
| χ2 | 1.705 | 5.365 | 1.087 | 2.282 |
| p | 0.192 | 0.021 | 0.297 | 0.131 |
日本の大企業では、戦後直後の労働組合による「経営民主化」「身分制撤廃」運動の結果として、ホワイトカラーとブルーカラーの間に、基本的に同じ賃金制度が適用されるようになった。準戦時体制、戦時体制のもとで確立した大企業の賃金カーブは、戦後直後の生活給的賃金制度に受け継がれ、さらに春闘方式のもとで「年齢別生活費保障型」の賃金カーブが定着する。その結果、日本のブルーカラー労働者とホワイトカラーのスタッフとは、年齢・賃金プロフィール、勤続年数別構成、企業福祉費の割合等において、マクロ・データのレベルで近似することになるのである(小池, 1981)。
したがって、こうした傾向は賃金だけにとどまらなかったことになる。ドーアは産業化の進展につれて、人々の社会的な平等への欲求が強まり、日本の大企業では「英国ならばミドル・クラスの職員に限られている特権である年金や疾病手当のような付加給付、かなりの程度の雇用保障、家族生計費の出費増に応じた賃金の上昇などを、現場労働者にまで与えている」と日英間の雇用システムの違いを指摘している(Dore, 1973, p.264 邦訳p.293)。
ドーアが研究対象に選んだ日立製作所について、菅山(1995)をもとにして見てみよう。1920年に久原鉱業から独立した株式会社日立製作所は、1939年に至るまで、「社員」の規則と「職工」の規則が全く別立てであった。社員は新規学卒者の定期採用により採用され、すべて年給、月給の定額給で定期昇給する制度になっていた。1930年代の離職率は年平均3%程度と、ほとんどの者が永年勤続する現象が見られた。まさに「社員」は年功賃金で終身雇用だったのである。
しかし、職工は定額の日給をもらっている者も少数派で、多くは出来高払制度が適用されていた。定期昇給は期待できず、職長や現場の係員の恣意的な査定で昇給、昇進が決められることに対して、不平不満が強かったという。1930年代半ばに採用された「定傭工」のうち定期採用者は7%程度で、ほとんどは定期採用者ではなく、最初は「日雇工」として入所して、1年以内に定傭工となった者だった。日雇工の数は定傭工の約半数にのぼっていたという。しかし、1939年、日立工場では「職工」という呼称が「工員」に改められ、戦争経済の破綻が進む中で、生活程度を考慮しない出来高払制の不合理が指摘され、1940年には、標準的労働者のライフサイクルと能力曲線に基づき、単価請負から時間請負への切り換えが行われた。1943年には、固定給部分が設定され、日給の半額に相当する額が事実上の固定給部分となった。こうして、第二次世界大戦末期には、ブルーカラー労働者の賃金のホワイトカラー化はかなりの進展をみせたのである。
日本全体で見ると、労働組合は、終戦から1年半の間に約500万人、雇用労働者の4割を組織したが、1947年8月に実施された調査によれば、そのほとんどすべてが企業単位に組織されており、工員・職員一本の混合組合の比率が8割を超え、職長や係長にも、そして3分の1の組合では課長にまで組合員資格を与える「従業員組合」となっていた。日立工場でも、従業員の間では、工員層でも、優遇されている社員層でも、社員・工員の身分制度撤廃を望む声が強く、1946年5月には工員が組織する組合と社員が組織する組合が合併して「日立工場労働組合」が誕生する。1947年1月には、社工員の身分を撤廃し新たに所員とする協定が成立し、日立製作所の経営陣は身分制度の撤廃に同意する。
1947年5月には、年齢を重視する生活給的色彩の強い新基本給が労使間で合意され、これによってかつての社員・工員間の賃金格差は一挙に消滅した。それでも、直接現業職については基本給に対する加給の比率が高かったが、実績においてあまり大幅には変動せず、能率給はインセンティブ・システムとしては有効に機能しなかった。
このことは他の企業でも同様で、日経連が能率給制度の宣伝に努めたにもかかわらず、製造業で能率給制度を適用されている労働者の比率は1950年の46%から、1965年には17%にまで大幅に低下する。こうして、ホワイトカラーとブルーカラーの間に、実質的にも同じ賃金制度が適用されるようになったのである。そして、1960年代に入ると、日本経済の高度成長に伴う深刻な労働力不足と高校進学率の急速な伸びで、企業はそれまで下級のホワイトカラー職として雇っていた高卒を現場労働者として採用するようになった。このことで、高卒者に対してとっていた定期採用方式が、ブルーカラー労働者に対しても見られるようになり、ブルーカラー労働者の雇用制度面でのホワイトカラー化はほぼ完成を見ることになる。こうして、生活費保障型賃金が、ホワイトカラー、ブルーカラーを問わず、日本企業に定着するのである。
ところで、こうした終身コミットメントは、本当に日本企業にとってある程度共通の特徴なのであろうか。仮にそうだとして、それは日本国内だけでの特徴なのだろうか、それとも多国籍企業としての日本企業の企業文化の特徴なのだろうか。そこでここでは、1970年前後に行われた調査をもとにして、1980年に発表され、多国籍企業の文化的側面の研究として先駆け的な存在となったホフステッド(Geert H. Hofstede)の研究をとりあげる。さらに独自の最新データを使って日本企業3社の企業文化との比較も行ってみよう。
ホフステッドの『経営文化の国際比較』(Culture's Consequences, 1980)は、多国籍企業における文化の国際比較を40ヶ国にわたって行なったという点で注目すべき研究である。そこでさっそく、ホフステッドの行なったIBMを対象としたといわれる調査の概要をまとめておこう(Hofstede, 1980, ch.2)。ホフステッドの調査は1967〜1973年に行われたもので、66ヶ国、延べ約117,000人からデータが集められたという。調査は第1次調査と第2次調査とからなり、表3.2のようなスケジュールで行われた。
表3.2 ホフステッドの調査の概要(Hofstede, 1980, ch.2)
| 第1次調査 | (1967〜1970年、53ヶ国(18ヶ国語)、約6万人) |
|---|---|
| 1967年6月 | 製品開発部門(6ヶ国(5ヶ国語)) |
| 1967年11月 | アジア、ラテン・アメリカ、太平洋諸国の全社員(26ヶ国(4ヶ国語)) |
| 1968〜69年 | ヨーロッパ、中東諸国の全営業・管理部門 |
| 1970年 | 全製造工場(13ヶ国) |
| 第2次調査 | (1971〜1974年、66ヶ国(18ヶ国語)、約6万人*) |
| 1971年 | 製品開発部門の再調査……古い項目と新しい項目からなる過渡的な調査票 |
| 1971〜73年 | 営業・管理部門の再調査…新しい調査票 |
| 第1回 1967〜1969年 31,218人 | |
| 第2回 1971〜1973年 40,997人 |
第1次調査のうち、1967年6月の調査データはそれ以後の調査とは異なる質問が非常に多かったので用いられなかった。第1次調査の結果、新しい調査票が作られた。新調査票はすべての第2次調査で用いられる60問の中核的質問(A1〜A60)と、使用が推薦される66問のオプション質問(B1〜B66)とから構成されていたとされる。
第1次・第2次調査のデータのうち、国間の比較のための国別得点は、営業部門、管理部門のデータが用いられ、製品開発部門、製造部門のデータは用いられなかった。したがって、具体的に特定すれば、国間比較に用いられたのは、表3.2のうち網掛け部分の調査で収集されたデータということになる。
職種カテゴリーのいくつかで欠けているデータは、他の職種カテゴリーから推測したとされる。1回だけ欠けている場合には、第1次・第2次の2回の調査の間にその国の他の職種で生じた平均の変化を用いて推測し、2回とも欠けている場合には、全世界データでの職種間差異で修正した上で、その国の他の職種のデータから推測されているという。この結果、39ヶ国のデータが利用可能となり、うち30ヶ国が第1次・第2次と調査を2回実施した国である。これにIBMの支社ではないが、旧ユーゴスラビアで他の製品とともにIBM製品の販売・サービスをしている労働者自主管理の輸出入組織のデータが1971年に得られたので、この旧ユーゴスラビアを40番目の国として加えている。
こうして第1次調査から1967〜1969年にかけて集められた31,218人分のデータ、第2次調査から1971〜1973年にかけて集められた40,997人分のデータが分析に用いられたことになる。つまり、ホフステッドの分析は1967年〜1973年に行われた40ヶ国のIBMの営業部門、管理部門の延べ72,215人の回答をもとにして行われたということになる。
分析には、第1次・第2次の2回の調査で比較的安定していたスピアマンの順位相関係数ρ>0.5の質問が使用されたが、ρ≦0.35 の該当5問は除き、0.39≦ρ≦0.49 の該当5問は当分残すことにして分析が始められる(うち2問は後で除かれた)。
ホフステッドによって、IBMデータに現れたとされる国民文化の四つの次元、(a)権力格差、(b)不確実性の回避、(c)個人主義化、(d)男性化、が具体的にどのように調査され計算されたものかを順に見ていくことにしよう。ただし、このうち(c)(d)については、指標の具体的な算出方法がブラック・ボックスで(高橋, 1995b, ch.5)、(3)節で取り上げる独自の調査にも使われなかったので、ここではふれない。
権力格差とは、上司と部下の間の権力格差のことで、「上司が部下の行動を規定することができる程度と部下が上司の行動を規定することができる程度との差である」と定義されている(Hofstede, 1984, p.72 邦訳p.78)。実際の分析では、
がそれぞれ大きいほど大きな値をとるようになっている権力格差指標(power distance index; PDI)が用いられる。
権力格差指標PDIは値が大きいほど権力格差が大きいとされ、具体的には、定数項135でレンジを調整して、次のように算出される。
| PDI=135−25 | ×B46(平均) | −A54(3の%) | +A55(1+2の%) |
| しりごみ | 相談的管理者 を選好する% | 上司を独裁的か説 得的と知覚する% |
実際の値は 11≦PDI≦94 であったが、理論的には -90≦PDI≦210 の値をとりうることになる。またPDIは職種によって非常に異なり、教育レベル、地位レベルの低い職種ほどPDIは高くなる傾向がある(決定係数 R2=0.88)。PDI算出のもとになっている質問項目は次のとおり[19]。
A54 & A55. ここに次のような4人の異なるタイプの管理者がいます。この文章をよく読んで、質問に答えてください。
不確実性の回避については、
がそれぞれ大きいほど大きな値をとるようになっている不確実性回避指標(uncertainty avoidance index; UAI)が用いられている。このうち3でストレスが取り上げられるのは、不確実性を回避する二つの方法である1、2との間に、不安水準と安全への欲求とを挟んで次のような関係があるためとされている。
こうして求められた不確実性回避指標UAIの値が大きいほど、不確実性回避の傾向が強いとされ、具体的には、定数項300でレンジを調整して、次のように算出されている。
| UAI=300 | −30×B60(平均) | −A43(1+2の%) | −40×A37(平均) |
| 規則への志向性 | 長くてあと5年し か勤務しない% | 仕事で神経質、緊張 |
実際の値は 8≦UAI≦112 であったが、理論的には -150≦UAI≦230 の値をとりうることになる。UAIは回答者の平均年齢との間に相関があった。算出のもとになっている質問項目は不確実性を回避する二つの方法である規則への志向性(質問B60)と雇用の安定性(質問A43)、そしてこの2変数と関連のあるストレス(質問A37)についての質問項目で、次のとおり。
ディール=ケネディーに言わせると、文化がいかにして人々を結び付け、日々の生活に意味と目的を与えているのかについて、先人の教訓を学び直す必要がある。米国企業の創立者達は強い文化(strong culture)が成功をもたらすと信じていた。従業員が生活の不安を感じることなく、それゆえ事業の成功に必要な仕事ができるような環境つまり事実上の文化を社内に作り出すことが自分達の役割であると考えていた。これら初期のリーダーたちの教訓は社内で代々の経営者に受け継がれ、彼らが注意深く築き、育んだ文化が、景気の浮沈を乗り越えて、組織を維持してきたというのである(Deal & Kennedy, 1982, p.5 邦訳pp.16-17)。
ホフステッドのいう4指標のようなものが、仮に何らかの意味で文化を見る指標として有効であるならば、これらの指標が40ヶ国でどの程度の値の散らばり、分散になるかを見ることで、まさにディール=ケネディーの言う「企業文化の強さ」を測定することができるのかもしれない。あるいは逆に、ある国の中で、いくつかの企業でこれらの指標の値の散らばり、分散がどの程度であるのかを見ることで、国民文化の強さを見ることもできるのかもしれない。そこで、その後者の試みを次に見てみることにしよう。
ホフステッドのIBM調査との比較を目的として、1996年1月から3月にかけて、コンピュータの分野で日本を代表する大手電機メーカーF社、N社、T社の3社でIT96 (Information Technology 1996)調査が行われた(高橋, 1997b, ch.1)。対象は各社の情報処理部門及び各社が日本国内にもっている情報処理関連子会社に所属する情報処理技術者である。調査は質問調査票を用い、留置法によって行われた。調査対象になっている情報処理技術者とは具体的には、次のような職種についている者である。
これら以外の職種に就いている者からの調査票も若干名から回収されたが、集計、分析からは除外されている。
調査対象に情報処理関連子会社の従業員まで含めたのは、日本のコンピュータ・メーカーは、そのソフトウェア開発のかなりの部分を本体から分離して子会社や関連会社に切り出しているためであり、実際F社、N社の場合には、会社本体で実際に情報処理技術に携わっている者の数は驚くほど少なくなっている。またIBM調査では多国籍企業としてのIBM全体を調査対象としているために、米国本国を除いては、現地法人すなわち現地子会社が調査対象であったことを考えると、子会社を含めることは、比較の際にはむしろ適切に思われる。
調査対象となったのは、F社285人、N社630人、T社399人の計1,314人で、回収されたのはF社215人、N社438人、T社369人の計1,022人、全体の回収率は77.8%であった。
今回、分析に用いられるのは、権力格差指標PDIと不確実性回避指標UAIの二つで、ホフステッドの質問がそのまま調査票で用いられた[20]。そこで、さっそくF社、N社、T社の3社(正確には3グループ)について、それぞれ権力格差指標PDIと不確実性回避指標UAIを求め、ホフステッドのIBM調査の結果と重ね合わせてプロットしてみると、図3.3が得られる。
図3.3 不確実性回避指標と権力格差指標(IT96調査)
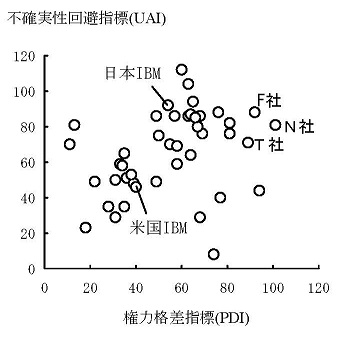
(出所) Hofstede (1980, Figures 7.2)を簡略化した上にIT96調査の日本企業3社(F社、N社、T社)を重ねてプロットしたもの。
一見してわかるように、日本企業の3社、F社、N社、T社は、互いに違いはあるものの、IBM本体・子会社の40ヶ国の分布の中にプロットすれば、ほとんど同じ所に位置付けられるということがわかる。3社全体の平均で、PDIが95、UAIが79であった。つまり、さきほどの言い方を借りれば、日本の国民文化の強さを表している調査結果だといえるのかもしれない。四半世紀前の日本IBMの調査結果と比べても、不確実性回避指標UAIではほとんど同じである。言い換えれば、日本企業の間には、組織文化的に見て類似点があると思われるのである。特に不確実性回避指標UAIが高い値をとる理由として重要なことは、「長くてあと5年しか勤務しない」人の比率が、3社全体の平均で20.85%しかないということである。そのことからすぐに連想されるのは「終身コミットメント」の存在なのである。
実は、F社、N社、T社のうちの1社についてだけは、まだ予備調査段階であるが、英語の質問調査票が使える国だけに限定した形で、米国、カナダ、英国、アイルランド、タイ、シンガポール、香港、マレーシア、フィリピンの9カ国の13現地法人のエンジニアを対象にして1996年12月から1997年1月にかけて、調査を行っているので(回収計770人、回収率53.4%)、調査の規模の点では必ずしも十分ではないが、参考のために、そのデータを使って比較をしてみよう。その結果は、まずPDIの平均は71、UAIの平均は28で、F社、N社、T社の日本国内の平均、PDIが95、UAIが79と比べて、かなり異なることがわかる。そして「長くてあと5年しか勤務しない」人の比率の平均は57.04%にもなっていたのである[21]。つまり、この質問の答えだけで、UAIの得点差51(=79-28)ポイントのうち、実に36ポイントも説明できてしまうことになる。やはり、日本における企業、特に大企業の企業グループにおける終身コミットメントは、国際比較上、まだ特徴的な存在なのである。しかも、それは多国籍企業としての日本企業の企業文化的特徴というよりも、日本国内での特徴らしい。
以上の分析から、終身コミットメントは、日本国内の企業、特に大企業では高い未来係数として一貫して観察されてきており、しかもそのことは日本国内ではある程度共通で、比較的安定しており、国際的に見ると特徴的であることがわかった。この未来係数の高さが、少なくとも日本では、企業とその従業員に未来傾斜原理を意思決定原理として採用することを容易にしてきたはずなのである。そして、この未来係数の高さは、アベグレン(1973)の説を待つまでもなく、成長企業にとって有利なのである。未来傾斜型システムは成長志向を内包している。
[14] 1960年に、日本経営学会編『日本の経営』(『経営学論集』第32集, 森山書店)が出版されているが、これはいわゆる日本的経営に関する書物ではない。この論集の題名は、前年(1959年)に開催された日本経営学会第33回大会の統一論題「日本における経営の諸問題」に由来するものだが、もともとこの統一論題は「経営組織の基本問題」「経営と地域開発」「ビッグビジネスとスモールビジネス」の三つからなるとされており、経営組織の基本問題と言っても、むしろ米国やドイツの話が主体であった。統一論題のみならず、自由論題や討論でも、今日言うところのいわゆる日本的経営に関する議論はない。あえて探せば、日本では責任、権限が不明確であるといった類の文章が見つけられる程度である。
[15] こうした見方は、1960年代に入って、日本経済の高度成長を目の当たりにしても、なおも支配的であった。吉野洋太郎は、驚異的な経済成長を非常な成功とするものの、日本の社会に基本的変化が生じつつあるために、稟議制度を含めた日本の伝統的な経営慣行には当時既にいくつかの変化が生じ、さらに次の10年間には日本の経営慣行の中に大きな革新が生ずるであろうとしていた(Yoshino, 1968)。
[16] 1960年代の合併・買収ブーム以降、1970年代にかけて、米国企業で未来係数が急速に低下していく様子と、その一因としてのMBAの急速な進出が挙げられていて興味深い。当時、こうした受け止め方をしたのはオオウチだけではなかった。1980年代に唱えられた企業文化論、組織文化論も基本的に同じ認識をしていたようである。例えば、後で登場するディール=ケネディーは、1960年代はM&Aによるコングロマリットの時代で財務部門の人達が昇進し、1970年代は戦略的計画の時代でMBA達が出世したが、その危険性は明白で、成功するためには、経営者は一時的流行につられて昇進させるのをやめさせ、その代わりに企業の中心的な価値を体現している人達を昇進させなければならないとしていた(Deal & Kennedy, 1982, p.49 邦訳p.84)。
[17] この『セオリーZ』の原型は、オオウチが1978年にジョンソン(Jerry B. Johnson)との共著で発表した論文 (Ouchi & Johnson, 1978)に遡ることができるが、そこでは米国企業の組織の理念型としてタイプA、日本企業の組織の理念型の米国版としてタイプZを考えているのみで、タイプJは登場していない。そこで挙げられているタイプZの特徴のうち、個人責任を集団責任に置き換えたものが『セオリーZ』ではタイプJとされているので、明言はされていないが、正確にはタイプZはタイプJとタイプAの中間型と位置付けられることになる。
[18] しかし驚くべきことは、アベグレン(1958)やパスカル=エイソス(1981)の描く日本企業の姿が、現在に至るまでの40年間、あまり変わっていないということである。少なくとも終身コミットメントは一貫してみられ、未来係数は高かったのである。対照的に米国企業の姿は、1960年代〜1970年代にかけて、すっかり一変してしまったとされている(Deal & Kennedy, 1982)。
[19] ただし質問A54&A55で、管理者1〜4についてつけられているラベル(独裁的)(説得的/温情主義的)(相談的)(民主的)(参加的)は、ここでは解説の便宜のためにつけているだけで、実際の調査の際にはもちろんつけられていない。
[20] 質問A54&A55については1970〜1973年版が用いられた。また、(c)個人主義化と(d)男性化については、ホフステッドは仕事の目標に関する14の質問に対して、因子分析を使って決めた重み係数で合成得点を計算しているのだが、その合成得点の正確な算出式は明らかにされていない(Hofstede, 1980)。そのため、この2指標についてはここでの分析から除かれている。
[21] ホフステッドの分析では、こうした各質問項目に遡った分析や結果の紹介は行われていない。ただし、邦訳の原典にもなっている1984年に出された要約版(Abridged edition)では割愛されてしまっているが、1980年版の Appendix 2 (Hofstede, 1980, pp.411-413)には、国別に各質問項目の単純集計が掲載されているので、それを利用することができる。それによると、「長くてあと5年しか勤務しない」人の比率は、IBMの場合、日本15%に対して、米国、カナダ、英国、アイルランド、タイ、シンガポール、香港、フィリピンの8カ国の国単位の平均で29%になる。比較のために、同様の計算を今回の調査データでもやってみると、日本とマレーシアを除いた8カ国の国単位の平均は62%になり、1970年前後のIBMの数字の約2倍になっていることがわかった。日本がさほど変動していないことと比べると特徴的であるが、理由についてはまだはっきりしていない。ここでマレーシアを除いて計算しているのは、もともと、Hofstede (1980)で分析対象となった40カ国の中にはマレーシアが含まれておらず、単純集計が不明なためである。ただし、Hofstede (1991)にはマレーシアのPDIやUAIなどの指標も計算されて載っている。
第1章でも見たように、非ゼロ和ゲームでは均衡も安定も現実的な意味を失ってしまっているが、ゼロ和2人ゲームであれば、マクシミン原理という特定の意思決定原理とそれが導く戦略で均衡してしまう。つまりゼロ和2人ゲームでは、均衡点へのパスを指し示すという点で、マクシミン原理は説得的で魅力的である。第1章では、とりあえず均衡点の存在を仮定してきたが、そこで予告した通り、このことは常に成り立つ。一種の拡張を行い、これまでのように、Π1、Π2 の中からどれか一つの戦略を選択する(これを純戦略(pure strategy)と呼ぶ)のではなく、Π1、Π2 上の確率分布で表されるような、どれか一つの戦略の当る「くじ」(これを混合戦略(mixed strategy)と呼ぶ)を一つ選択することを許すことにする。そうして、この章で登場する期待効用を使えば、2人ゲーム(もちろんゼロ和を含む)には均衡点が必ず存在することが証明されるのである。そして純戦略のときと同様に、その均衡点は各プレイヤーがマクシミン原理に則って戦略を選択したときに達成される。
しかし、本当にそうだろうか。何か大きなものを忘れてはいないだろうか。確率、より正確にいえば、未来がモデルに入ってきた途端、実は我々の仕事観、世界観は大きく変わるはずなのである。確率を期待効用を計算する際の単なる重み(ウェイト)としてのみ使っていていいのだろうか。第1章でも述べたように、未来傾斜原理で考えれば、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現の方が大切なのである。リスクや不確実性のある未来だからこそ、今は、多少無理をしてでもチャレンジして、成長することを考えるべきなのではないだろうか。
事実、ワーク・モティベーションの世界では、期待効用原理は色あせ、チャレンジの概念が大きな意味を持ち始める。未来はどこかに収束する存在などではなく、無限大に発散する存在なのだ。現在価値に直して清算してしまうような未来には意味がない。未来は残すことにこそ意味があるのである。チャレンジの概念が示唆しているように、自ら成長し、そして育てることの中に未来の本当の価値があるのである。そのことを個人の決定問題としての観点からとらえ直して考えてみよう。
個人の決定問題(decision problem)は、ゼロ和2人ゲームとして定式化することができる。いま、プレイヤー1が意思決定者(decision maker)(または統計家(statistician)とも呼ばれる)、プレイヤー2が自然(nature)(または環境(environment)とも呼ばれる)という設定のゼロ和2人ゲームを考えてみよう。
まず、プレイヤー1である意思決定者の戦略を行動(action)と呼び、意思決定者のとりうる行動の集合を
A={a1, a2, ..., am}
で表す。一方、プレイヤー2である自然の戦略を自然の状態(state of nature)と呼び、自然のとりうる状態の集合を
Ω={θ1, θ2, ..., θn}
で表す。そして、真の自然の状態(true state of nature)が θj のとき、意思決定者が行動 ai をとることによって引き起こされる結果(outcome)を oij で、そのとき得られる意思決定者の利得を
vij=v(oij)=V(ai, θj)
で表すことにしよう。このとき、v, V は利得関数と呼ばれる。もちろんゼロ和ゲームであるから、この意思決定者の利得にマイナスをつけたものが、自然の利得になるわけである。こうして、意思決定者の行動と自然の状態の組み合せによって決まる意思決定者の利得は、ゼロ和2人ゲームの利得表として、表4.1のように表され、これは決定表(decision table)と呼ばれる。このように定式化された意思決定者対自然のゼロ和2人ゲームで、自然または環境に対峙した意思決定者の決定問題を扱うのが決定理論である。
表4.1 決定表
| 行動 | 自然の状態 | |||
|---|---|---|---|---|
| θ1 | θ2 | ・・・・・・ | θn | |
| a1 | v11 | v12 | ・・・・・・ | v1n |
| a2 | v21 | v22 | ・・・・・・ | v2n |
| : | : | : | ・・・・・・ | : |
| am | vm1 | vm2 | ・・・・・・ | vmn |
ところで、プレイヤー2を自然や環境と呼んでいるのには理由がある。自然や環境は泰然として大きい存在なので、たとえプレイヤー1がプレイヤー2の戦略に関して情報収集をしたとしても、プレイヤー2は通常の人間のように、そんなことに影響されて戦略を変えたりしないし、それに対する防護策を講じたり、対抗策をちらつかせたりすることもないと仮定しているのである。
つまり環境は意思決定者からの影響を全く受けない。逆にいえば、環境は制御不能な要因(uncontrollable factors)の集合であると定義できることになる(例えば、Marschak & Radner, 1972, p.12)。しかし、だからといって、環境自身が自律的に変化していくこと(Takahashi, 1987a ch.4)や意思決定者が環境を「住み替える」ことまでも否定しているわけではない。単に環境が意思決定者に影響されないということを言っているだけで、環境が意思決定者にとって固定されたものである必要はない。例えば、意思決定者が対戦相手である環境を、状況を見ながら、やり過ごすこと(やり過ごしについては第6章と第7章を参照のこと)も許容している定義なのである。
しかし、このようにしてプレイヤー2を制御不能な自然と見ることで、この自然に対しては、どの程度制御できるかではなく、どの程度知ることができるかが重要になってくる。こうして、自然がどの状態をとるのかについての意思決定者の知識のレベルとして、次のような「不確実性」のレベルが考えられてきた(cf. Luce & Raiffa, 1957, p.13; March & Simon, 1958, p.137 邦訳pp.208-209)。
こうした事態がさらに進んで、自然の状態の集合 Ω も知らず、各行動によって引き起こされる可能な結果の集合についても定かではないケースも考えられるが、こうしたケースは、あいまい性(ambiguity)と呼ばれ、ここで扱われる決定理論系の決定問題とは別の枠組みで議論される(第6章を参照のこと)ので、ここではこのa、b、cの三つのケースを考えることにしよう。
このうちcの厳密な不確実性下の意思決定(decision under strict uncertainty)はゼロ和2人ゲームの理論で既に考察済みである。またaの確実性のケースは、bのリスクのケースの特別な場合である。なぜなら、もしリスクのケースである自然の状態 θt の生起する確率が1、他の自然の状態の生起する確率が0であるとき、つまり、
(p(θ1), ..., p(θt-1), p(θt), p(θt+1),..., p(θn))=(0, ..., 0, 1, 0, ..., 0)
のとき、リスクのケースは確実性のケースと同じことになるからである。そこで問題になるのは、bの「リスクをともなう意思決定(decision with risk)」ということになる。
ゼロ和2人ゲームが、勝った方が取るという約束で勝負事に金品を出すという意味での「かけ(賭)」を扱っていたのに対して、リスクをともなう意思決定では「くじ(籤)」を扱うことになる。くじとは、紙片、竹片、こよりなどに文句または符号を記しておき、その一つを抜き取らせ、吉凶、勝敗、等級などを決定する、あの「くじ」である。そこで、ここではリスクをともなう意思決定をくじの選択問題として定式化してみよう。
リスクをともなう意思決定では、意思決定者は Ω 上の確率分布 (p(θ1), p(θ2), ..., p(θn)) を知っているので、一つの考え方としては、確率を使って、これから述べるような期待金額を計算してみて、それをもとにして選択を考えるという方法がある。
くじの賞金 X は、それがとる各値
x1, x2, ..., xm
に対して、それぞれ確率
p(x1), p(x2), ..., p(xm)
が与られている変数であり、これを通常、確率変数(random variable)と呼び、大文字で表す。この確率変数である賞金 X の期待値は次のように定義される。
E(X)=Σi=1m p(xi) xi
このとき Σi p(xi)=1 であるから、これで確率による加重平均をとっていることになる。
つまり、各々の賞金額 xi は、それが得られる確率 p(xi) によって加重され、より得られやすい賞金額は、より大きい重みをつけられて平均が求められるのである。このように、確率変数のとりうる値を確率をウェイトとして加重平均して求めた値を期待値(expectation)という。この場合は、賞金額の期待値なので期待金額(expected monetary value)という。この場合は、賞金額の期待値なので期待金額(expected monetary value)というわけである。
それでは、期待金額にはどのような意味があるのだろうか。いま、くじを n 回引いたときの賞金額の平均を
Xn=(X1+X1+・・・・・・+Xn)/n
としよう。このとき、この平均賞金額も確率変数になる。確率論の大定理、大数の弱法則(weak law of large numbers)によると、任意の定数ε>0について、
P(|Xn−E(X)|>ε)→0, n→∞
がいえる。つまり、くじを n 回引いたときの平均賞金額 Xn は、くじを引く回数 n が十分に大きければ、期待金額 E(X) にいくらでも近い値をとることがきわめて確実なのである。逆に言えば、通常は、くじの期待金額 E(X) は、くじを何万回、何十万回も繰り返して行ったときに得られる金額の平均を表していると考えてよい。もっとも、通常は期待金額よりも、期待効用と呼ばれるものを使うことの方が一般的である。なぜそうなるのか、次にそのことを考えてみよう。
次のようなルールに基づく一種のくじを考えよう。
このくじでは理想的な硬貨を投げるので、1回目に表が出る確率は1/2、2回目に初めて表が出る確率は (1/2)2=1/4、3回目に初めて表が出る確率は (1/2)3=1/8、……、n 回目に初めて表が出る確率は (1/2)n となる。したがって、このくじから得られる賞金 X の期待値である期待金額は
E(X)=(1/2)・2+(1/2)2・22+(1/2)3・23+・・・+(1/2)n・2n+・・・
=1+1+1+・・・+1+・・・=∞
と無限大になってしまう。くじの期待金額が無限大ということは、このくじへの参加料がどんなに高くても、所詮、有限の額にすぎないはずだから、このくじに参加した方が得になるはずである。しかし、例えば、参加料が100万円とすると、220=1,048,576 であるから、少なくとも19回続けて裏が出なければ、参加料の元はとれないことになる。おそらく、まともな人ならば、参加料を100万円も支払って、このくじに参加するようなことはしないだろう。どうも期待金額だけでは説明がつかないようだ。これをサンクトぺテルブルクのパラドックス(St. Petersburg's paradox)という[22]。
それでは、くじの期待金額で説明できなければ、他にどのような説明が考えられるだろうか。「ベルヌーイの解決」として有名な説明によれば、簡単に言えば、くじによって金銭そのものを得るのではなく、金銭の効用(utility)を得ていると考えれば良いというのである。そして金額が1単位、例えば1円増えたときに、これにともなって増加する効用の大きさ(これを限界効用(marginal utility)という)が金額が大きくなるにしたがって逓減すると考えるのである。これを限界効用逓減の法則(law of diminishing marginal utility)ともいうが、具体的には次のような効用関数を考えてみればわかる。いま金額 x 円の効用を
u(x)=log10x
としよう。するとここでは常用対数をとっているので、金額 x が10倍になるごとに効用は1ずつ増えることになる。そこで、このくじから得られる金額の効用の期待値を求めると
E(u(X))=Σi p(xi) u(xi)
=(1/2)u(2)+(1/2)2u(22)+(1/2)3u(23)+・・・+(1/2)nu(2n)+・・・
=(1/2)log2+(1/2)2log22+(1/2)3log23+・・・+(1/2)nlog2n+・・・
=(log2){1・(1/2)+2・(1/2)2+3・(1/2)3+・・・+n・(1/2)n+・・・
=2log2=log4=u(4)
となる。これを期待効用(expected utility)と呼ぶわけだが、期待金額で考えるのとは違い、この期待効用で考えると、このくじのもたらす効用は、確実に得られるわずか4円の金銭が与える効用に等しくなってしまうのである。実は、この計算は対数の底が何であっても成立する。したがって、対数関数型の効用関数であれば、対数の底が何であっても、それをもつ人にとっては、このくじのもたらす効用は、確実に得られる4円の金銭が与える効用に等しいことになる。このように、リスクをともなう資産をリスクのない安全な資産に換算した場合の価値を確実同値額(certainty monetary equivalent)という。
ところで、なぜ効用関数として対数関数が登場したのだろうか。いま、ある個人の富の量が、 x から x+h へと増大したとしよう。このとき、この人の効用の増加分は、富の量の増加分 h に比例するが、初期所有量 x とは反比例する関係があると考えるのである。そのことを数式で書くと、k をある定数とすると、
u(x+h)−u(x)=k(h/x)
したがって
u'(x)=limh→∞ {u(x+h)−u(x)}/h=k/x
この微分方程式を満たす効用関数 u(x) は
u(x)=k log x+C
となる。ここで、k=1/log a, C=0 とおくと、u(x)=loga x という対数関数型効用関数が得られるのである。
もっとも、このサンクトぺテルブルクのパラドックスのくじで、実際にどのくらいの金額を平均的に獲得できるのかを調べるために、硬貨投げをパソコンでシミュレーションしてみると、くじ100万本を引き終わった段階で、平均賞金額は15円程度にすぎない(高橋, 1993c, pp.25-30)。理論上、期待金額が無限大になってしまうとはいっても、そのスピードはわれわれが想像するよりもかなりゆっくりなのである。平均賞金額が無限大になってしまうなどと想像させるような事態に遭遇することは、日常生活ではまずありそうにない。これぞまさに杞憂というべきだろう(これを「高橋の解決」と呼ぶことにしよう)。
しかし、たとえ確率がからんでこなくても、ベルヌーイが考えたような効用関数の存在を暗示する現象がわれわれの身の回りに多いのは事実である。いつでも誰でも、そしてどんないい加減な意思決定でも期待効用さえ用いれば必ず説明ができるというわけではない。しかし、人間の意思決定が「合理的」と思われるいくつかの要件を満たして行われるのであれば、そのときその「合理性」を体現するものとして何等かの効用関数のようなものが存在しているはずだと考えるのは自然な発想である。そして、その範囲においては、人間の合理的意思決定は、期待効用で説明することができるはずなのである。そのことが、これから述べる期待効用原理によって明らかにされる。
これから述べる考察は、すべて1個人の選好に基づいてなされる。その個人のことをここでは「あなた」と呼ぶことにしよう。このような選好が、どのような性質をもっているときに、合理的意思決定が行われるのだろうか。ここではルース(R. Duncan Luce)とライファ(Howard Raiffa)を参考にして(1957, ch.2)、これから述べる五つの仮定を満たすようなものを合理的と考えることにしよう。実は、仮定には様々なバリエーションがあるが(例えば、von Neumann & Morgenstern (1944); Blackwell & Girshick (1954); Ferguson (1967))、ここでは定理の証明ができるだけ簡単になるような仮定を設定してみた。
いま、獲得する可能性のある賞金の金額、A1, A2, ..., An の集合を A とする。このとき、A 上のくじ(lottery)とは、互いに排反で全てを尽くすような(mutual exclusive and exhaustive)不確実な事象の集合の一つが起こったときに、あなたの受け取る賞金額を決める装置ということが出来る。つまり簡単に言えば、ここでは、よくできたルーレットや硬貨のように、不確実な事象の各々に結びついて、ある既知の確率が存在しているくじ(正確にはルーレット型くじ(roulette lottery)と呼ばれるもの)を考えようというわけである。
いま賞金 Ai∈A が当る確率を pi とすると、当然、pi≧0, i=1, ..., n で、Σi pi=1である。このとき、くじを そこで、RL に属する任意のくじに対して、あなたは次の仮定にあるような二つの条件を満たす選好順序をもっているとする。いま L1 を L2 より選好するか、または無差別のとき、 L1  L2 で表すことにすると、
L2 で表すことにすると、
仮定4.1 (連結律と推移律) 任意の Li, Lj, Lk∈RL に対して、
 Lj または Lj
Lj または Lj  Li が成立する(両方を満たしてもよい)。
Li が成立する(両方を満たしてもよい)。 Lj かつ Lj
Lj かつ Lj  Lk ならば Li
Lk ならば Li  Lk。
Lk。 このうちaの連結律では両方を満たしてもよいので、 L1  L2 かつ L2
L2 かつ L2  L1 のとき、これを L1 〜 L2 で表わし、 L1 と L2 とは無差別であるという。また A ⊂ RL であるから、この仮定4.1から、賞金 Ai ∈ A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1
L1 のとき、これを L1 〜 L2 で表わし、 L1 と L2 とは無差別であるという。また A ⊂ RL であるから、この仮定4.1から、賞金 Ai ∈ A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1  A2
A2  ・・・
・・・  An という順序につけられているものとする。この A1 と An を使って、次の二つの仮定がおかれる。
An という順序につけられているものとする。この A1 と An を使って、次の二つの仮定がおかれる。
仮定4.2 (連続性(continuity)) 任意の Ai ∈ A に対して、
Ai〜(pA1, 0A2, ..., 0An-1, (1-p)An) (4.1)
となる実数 p (0≦ p ≦1)が存在する。
この(4.1)式は結局 A1 と An しか問題になっておらず、A2 から An-1 までは確率0で無視することになるので、これを便宜上
Ai〜(pA1, (1-p)An)
のように表すことにしよう。この記法をさっそく用いると、
仮定4.3 (単調性(monotonicity))
p≧q ⇔ (pA1, (1-p)An)  (qA1, (1-q)An)
(qA1, (1-q)An)
次に、単純くじの繰り返しで、単純くじの賞品が別の単純くじのくじ券になっているようなくじ
C=(p1L1, ..., pmLm)
を複合くじ(compound lottery)と呼ぶことにする。たとえば、年末ジャンボ宝くじのくじ券を景品にした商店街の歳末福引のようなものである。この複合くじに対して、次の二つの仮定がおかれる。
仮定4.4 (代替性(substitutibility)) 第 i 成分だけが異なり他が同じである任意の二つの複合くじ (…, piLi, …) と (…, piLi', …) について、Li 〜 Li' ならば、(…, piLi, …) 〜 (…, piLi', …)
仮定4.5 (複合くじの縮約(reduction of compound lotteries)) 複合くじは通常の確率計算にしたがって求められた、賞金に達する確率のみを考えた単純くじに評価することができる。
(q1(p11A1, ..., p1nAn), ..., qm(pm1A1, ..., pmnAn))
〜((p11q1+・・・+pm1qm)A1, ..., (p1nq1+・・・+pmnqm)An)
ここでは以上の仮定4.1〜4.5の五つの仮定を満たすような場合、効用関数が存在することをルース=ライファを参考にして、定理の形で証明しておこう。以上のような仮定を満たせば、合理的に効用関数に基づいて意思決定が行なわれていることになる。
定理4.1 (効用関数の存在) あなたが仮定4.1〜4.5に従うならば、任意の二つのくじ L1, L2 ∈ RL に対して、
U(L1)≧U(L2) ⇔ L1 L2
L2
であるような関数 U が存在する。
《証明》A ⊂ RL であるから、仮定4.1から、賞金 Ai ∈ A, i=1, ..., n については順序付けが可能なので、一般性を失うことなく、便宜上、賞金の添字の値は、A1  A2
A2  ・・・
・・・  An という順序につけられているものとする。仮定4.2から、任意の Ai ∈ A に対して、
An という順序につけられているものとする。仮定4.2から、任意の Ai ∈ A に対して、
Ai〜(uiA1, (1−ui)An) (4.2)
となる実数 ui (0≦ ui ≦1)が存在する。いま任意のくじ L1 ∈ RL を L1=(p1A1, ..., pnAn) とすると、仮定4.4を繰り返し用いることで、仮定4.1の推移律も用いれば
L1〜(p1(u1A1, (1−u1)An), ...,
pn(unA1, (1−un)An))
さらに、仮定4.5から、
L1〜((p1u1+・・・+pnun)A1, (1−(p1u1+・・・+pnun))An)
そこで、p=p1u1+・・・+pnun とおくと、
L1〜(pA1, (1-p)An)
で 0=p1・0+・・・+pn・0 ≦ p ≦ p1・1+・・・+pn・1=1 となっている。同様にして、任意のくじ L2 ∈ RL をL2=(q1A1, ..., qnAn) とすると、q=q1u1+・・・+qnun とおくと、
L2〜(qA1, (1−q)An)
で 0≦q≦1。したがって、仮定4.3から
L1  L2 ⇔ p ≧ q
L2 ⇔ p ≧ q
このとき、U(L1)=p, U(L2)=q とおけば、
L1  L2 ⇔ U(L1) ≧ U(L2)
L2 ⇔ U(L1) ≧ U(L2)
証明終
定理4.1の証明の中で、(4.2)式の
Ai〜(uiA1, (1−ui)An)
となるように選ばれた ui が、賞金 Ai の効用に当ると考えれば、例えば、くじ
L1=(p1A1, ..., pnAn)
に対応して与えられた
U(L1)=p=p1u1+・・・+pnun=Σi piui
は期待効用(expected utility)ということになる。つまり、定理4.1は、あなたが仮定4.1〜4.5を満たしているときには、くじの効用が賞金の効用の期待値と等しく置けることを示している。このように定義された効用概念は、一般に、基数的(cardinal)効用あるいはフォン・ノイマン=モルゲンシュテルン効用と呼ばれ、序数的(ordinal)効用とは区別されている。
ところで、この賞金 Ai の効用を、任意の実数 a>0 および b について、
vi=aui+b
と正の線型変換することを考えてみよう。この場合でも、任意の L について、
V(L)=p1v1+・・・+pnvn
とすると、
V(L)=p1(au1+b)+・・・+pn(aun+b)
=a(p1u1+・・・+pnun)+b
=aU(L)+b
ということになる。つまり、明らかに任意の二つのくじ L1, L2 ∈ RL について
V(L1)≧V(L2) ⇔ U(L1)≧U(L2) ⇔ L1  L2
L2
が成立し、V(L)もまた効用関数となる。このことは、ちょうど温度を摂氏で計っても、華氏で計ってもよいように、効用を測る効用関数にも色々なものがありうることを意味しているが、効用というものは実質的にはただ一つしかないないのである[23]。
定理4.1によって、リスクのケースでの効用が明確に定義され、期待効用を考えることの妥当性が明らかになった。意思決定者が期待効用を最大にするような戦略を選択する意思決定原理を期待効用原理(expected utility principle)と呼ぶことにしよう。期待効用原理は、リスクをともなう意思決定を考える上においては、これまでのところ、最も有力な意思決定原理であると考えられてきた。それは、働くことへの動機づけを扱うワーク・モティベーションの分野においても同様であった。
動機づけに関する代表的かつもっとも精緻な理論である期待理論(expectancy theory)は、基本的には打算的で合理的な人間を仮定し、そうした人間に、ある特定の行為を行わせようとする動機づけを定式化したものであるが、そこではやはり期待効用原理に近似した定式化が行われている。その原型は1930年代の研究にまで遡るといわれるが、現在のようなワーク・モティベーションの理論として比較的完成された形にまとめたのは、ブルーム(Victor H. Vroom)の『仕事とモティベーション』(Work and Motivation, 1964)である。
期待理論では、職務遂行によって獲得できる報酬の効用は誘意性(valence)と呼ばれ、その報酬獲得の主観確率は期待(expectancy)と呼ばれる。ブルームのモデルをV型モデルと呼ぶことにすると、V型モデルでは、ある人にとって、ある行為を遂行するように作用する力は、その行為がいくつかの結果をもたらすとの期待と、それぞれの結果がもっている誘意性との積の和(すなわち、誘意性の期待値のことで、期待効用に相当する)の単調増加関数で表される。このことから期待理論は「期待×誘意性」理論ともいわれ、ある職務を遂行するように作用する力は期待効用によって決まると考えるのである。
いま結果 j の誘意性すなわち効用を Vj とし、pi(j) を行為 i が結果 j をもたらす主観確率とする。このとき、ある人に行為 i (i =1, 2, ..., l )を遂行するように作用する力(force) Fi は、
Fi= fi (Σj=1m pi( j) Vj), i=1, 2, ..., l (4.3)
となるとされる(Vroom, 1964, Proposition 2)。ただし、fi'>0 で fi は単調増加関数である。
このモデルと期待効用原理との違いは、形式的には関数 fi が存在していることであるが、fi は単調増加関数であるから、結局、期待効用
Σj=1m pi( j) Vj
が大きくなるほど、「行為 i を遂行するように作用する力」もまた大きくなるので、遂行される行為は同じになり、実質的には違いはない。
そして、ブルームは、結果の誘意性はそれと結び付いた他の結果の誘意性から導き出されると考えていた(Vroom, 1964, Proposition 1)。例えば図4.1のように、(4.3)式の中にある誘意性第1次の結果 j (j=1, 2, …, m) の誘意性 V1j とすると、これは第2次の結果 k の誘意性 V2k とその結果 k の獲得に対する第1次の結果 j の手段性(instrumentality) Ijk から、次の(4.4)式のように求められると考えたのである。
V1j=gj(Σk=1n IjkV2k), j=1, 2, ..., m (4.4)
ただし、−1≦Ijk≦1。また gj'>0 で gj は単調増加関数である。
図4.1 ブルーム型の動機づけモデル
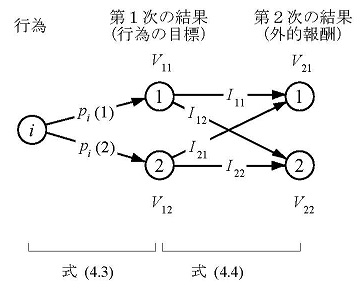
ブルーム理論に関する一般的な解釈に従えば、第1次の結果の複合体がいわゆる行為の目標に相当しており、第2次の結果は外的報酬に相当したものである(Deci, 1975, p.119 邦訳p.134) [24]。そして、図4.1にも示されるように、 (4.3)式の中の結果の誘意性は、その結果と結びついた他の外的報酬に相当する誘意性から、主観確率 pi(j) とは独立に導きだされると考えられているのである。したがって、ブルーム型モデルの、(4.3)式の中の誘意性は外的報酬によって決まるもので、期待効用原理での賞金の効用と実質的に同じである。つまり、ブルーム型のモデルでは、ある特定の行為への動機づけをくじと同様に定式化していることになる。
しかし、人にとっての仕事は、単にくじを引く以上の何かである。仕事がわれわれにもたらしてくれるものは、くじの賞金以上の何かなのである。事実、ブルーム型モデルでこそ、誘意性はくじの賞金の効用にすぎなかったが、後述するアトキンソン型モデルでは、誘意性はそれとは決定的に異なる別の概念として取り扱われるのである。
こんな違和感を裏付けるように、実はブルーム自身が、広範な調査研究のサーベイの結果を次のように発見としてまとめている(Vroom, 1964, ch.8):
そして、これらの発見は、職務遂行が目的達成の手段であるばかりでなく、目的そのものでもあることを示しており、個人は職務遂行に対する外的に媒介された結果とは無関係に、効率的遂行からは満足を引き出し、非効率的遂行からは不満足を引き出すことを示唆しているとしたのである(Vroom, 1964, pp.266-267 邦訳pp.304-305)。このように、外的には何も報酬がないのに、その行動それ自体から喜びを引き出しているような場合、内発的に動機づけられた行動と呼ばれる。
ところが、ブルーム型のモデルでは、個人がより困難なことにチャレンジするように動機づけられることはない。できるだけ容易な道へと向かってしまうのである。実際問題として、ブルーム型のモデルでは、職務誘意性は作業者が外的報酬を獲得できる程度の仕事をすることとは関係するかもしれないが、外的報酬さえ獲得できれば、それ以上のレベルの業績をあげる必要も理由も存在しない。たいていの場合、作業者の潜在的可能性をはるかに下回る業績レベルで十分に外的報酬を獲得できるので、その場合、とても効率的に生産活動を行っているとはいいがたいのである。
そもそも、あたかも職務遂行それ自体が目的そのものであるかのような行動を引き出せる外的報酬のシステムなどありうるのだろうか。テイラー(Frederick Winslow Taylor, 1911)の科学的管理法から考えても既に1世紀を費やしているのに、そのような外的報酬のシステムの設計には誰一人として成功していない。もう外的報酬による動機づけへの信仰を捨てるべき時が来ているのではないだろうか。もともと外的報酬の獲得だけが目的となっている世界では、その外的報酬を獲得することだけを狙った行動が出現するのは当然であり、事前にそうした行動の発生をすべて予測し予防措置をとっておくことは不可能なのである。
しかも、金銭や賞賛のような外的報酬はまさに「外的」存在である。たとえ満足をもたらすとしても、満足は報酬の後にやってくることになる。このように外的報酬には満足を後に押しやってしまう効果があるために、外的報酬が内発的動機づけを制約する大きな顕現性(salience)とインパクトをもっていることになる(Deci, 1975, Proposition I)。実際、内発的動機づけと外的報酬による動機づけとは付加的関係にはないということが、多数の実験研究から実証されている(Deci, 1975, ch.5)。これらの実験では、内発的動機づけの測度として、
を採用しているが(Deci, 1975, pp.148-149 邦訳pp.166-167)、どちらの測度であれ、多くの場合、外的報酬は内発的動機づけを低下させているのである。例えば、大学生に興味のもてるパズルを解かせたときに、金銭的報酬を与えた試験群の方が、金銭的報酬を与えなかった統制群よりも、1のパズルに費やした時間の量が減ってしまったことが報告されている。
つまり、人は期待効用原理で想定しているように、外的報酬という賞金のために、くじを引くがごとく仕事をし、働いているわけではない。いかに精緻な理論であっても、期待効用原理で、人の意思決定、特に動機づけを説明し尽くすことはできない。より高い目標に向かってチャレンジし、成長し、そして育てること、それ自体が喜びであり、仕事のやりがいなのである。かくして、期待効用原理で動機づけを定式化してしまおうとする試みは、一時的に多くの研究者をひきつけたものの、やはり、くじにたとえること自体に無理があった。
組織の中の日常的な意思決定、特にその大部分を占めているルーチンの意思決定が、決定理論的な意味で合理的に行われているために(ただしこれは、組織の中で問題を手頃な大きさに因数分解することに成功しているからである。詳しくは、第6章を参照のこと)、なかなか気づきにくいのだが、われわれを仕事に動機づけているのは、決定理論的な意味での合理的な判断ばかりではないはずである。人にとっての仕事は単にくじを引く以上の何かである。仕事によって成長し、仕事によって直接満足感を得る。
そこで、期待効用原理を単に書き換えただけと言ってもいいような外的報酬による動機づけを扱うこのブルーム型モデルではなく、チャレンジが意味を持っているような動機づけモデルについて考えてみよう。実は、ブルームの期待理論より以前に、アトキンソン(John W. Atkinson, 1957)の達成動機づけに代表される内発的動機づけ(intrinsic motivation)の理論の系統のモデルが既に存在していたのである。そこで、アトキンソン(1957)が定式化した動機づけモデルをここではアトキンソン型モデルと呼ぶことにし、ブルーム型モデルとの比較を行なってみよう。
実は、ブルームのいうところの誘意性つまり効用がどのように決められるかという点で、アトキンソンは別の考え方をしていた。ブルームの考えた効用は、期待効用原理で考えられていたくじの賞金の効用のようなものであるが、アトキンソンはそうは考えなかったのである。ブルームのモデルでは、期待効用原理と同様に、外的報酬の効用のように、効用はそれをもたらす確率とは独立に決められていたのに対して、アトキンソンは、効用はそれをもたらす確率と連動して決まると考えたのである。
まず、Isj を目標 j の成功の誘因価(incentive value of success)とし、Ifj を目標 j の失敗の誘因価(incentive value of failure)とする。ここで、成功の誘因価とは人が目標 j を達成した際に感じるプライドで、その目標が達成困難なほど高い誘因価をもつ。他方、失敗の誘因価とは失敗に伴う恥や困惑といった不快の情緒であり、負の値をとるが、その目標の達成が容易なものであったほど、失敗したときのダメージはひどく、失敗の誘因価の絶対値は大きくなる。誘因価は効用と同様のものと考えられる。
また、Ms を成功への動機(motive to approach success)とし、Mf を失敗回避動機(motive to avoid failure)とする。両方とも比較的安定したパーソナリティー的特性で、その値は各個人については状況にかかわらず定数であると考えられる。そして、成功の効用、失敗の効用は対応する誘因価 Isj, Ifj とパーソナリティー的特性である動機 Ms, Mf のそれぞれの積で決まると考えたのである。
以上のことから、あとは成功の確率と失敗の確率がわかれば、期待効用が求められるわけで、目標jの達成状況に接近したり回避したりする合成的モティベーション(resultant motivation) Rj は
Rj=p( j)Ms Isj+(1−p( j))Mf Ifj (4.5)
と表される。ここで、p( j) は目標 j の成功の主観確率である。
ここまではブルーム型のモデルつまり期待効用原理とほぼ同じである。ここから先の誘因価の定義つまり効用の定義が、ブルーム型のモデルとは本質的に異なる。これまでの話からもわかるように、成功の確率 p( j) は目標 j の成功の容易性を表していることになるし、他方、1−p( j) は目標jの成功の困難性と考えられる。アトキンソンは、成功の誘因価は達成が困難であった方が高く、失敗の誘因価は達成が容易だったはずのものほど負の低い値をとるという誘因価のもっている意味から、誘因価 Isj, Ifj がそれぞれこの目標 j の成功の困難性、容易性の線型関数になると仮定した。そして、その線型関数という関係をさらに単純化して、誘因価と目標 j の成功の確率 p( j) との間に次のような関係を仮定するのである。
Isj=1−p( j), Ifj=−p( j)
この関係を用いれば、合成的モティベーションを表す(4.5)式は
Rj=(Ms−Mf ) p( j)(1−p( j)) (4.6)
となり、成功への動機 Ms と失敗回避動機 Mf という二つのパーソナリティー的特性を表す定数と目標 j の成功の確率 p( j) によって、合成的モティベーション Rj が決まることになる[25]。
このモデルでは、誘因価が成功の確率によって決まるということを仮定したことで、「目標達成」ということのもたらす満足は、目標達成それ自体にのみ関係し、目標達成以外には明白な報酬がまったくないことになる。このことは、ブルーム型のモデルと比べて際だった特徴になっている。当該活動の他には明白な報酬がまったくないのに活動に従事するわけであり、期待効用原理で考えたように賞金目当てにくじを引くわけではない。あえて言えば、くじを引くこと自体が目的となっている。このように、アトキンソン型のモデルでは後述する内発的動機づけだけが問題になっていることになる。
外的報酬による動機づけを考えたブルーム型のモデルでは、もし同じ外的報酬 k をもたらすパスに、容易なパスと困難なパスの二つのパスがあるときには、人は容易なパス、すなわち、確率 pi( j) と手段性 Ijk の大きいパスを選ぶことになるだろう。なぜなら、外的報酬の期待値が高くなるからである。しかし、内発的な動機づけを考えたアトキンソン型のモデルでは、より困難なパスを選ぶかもしれない。なぜなら、合成的モティベーションを表す(4.6)式の Rj の式からも明らかなように、個人の変化性向が正、つまり、Ms−Mf >0 ならば、p( j)=1/2 のときに最大の内的報酬が得られるからである。したがって、外的報酬による動機づけは、目標成功の困難性が低いほど大きくなるが、他方、内発的動機づけは、目標の困難性が一定の最適水準に高まるまで増大するのである(Deci, 1975, p.117 邦訳p.132)。つまり、ブルーム型のモデルではできるだけ容易な道へと向かってしまうのに対して、アトキンソン型のモデルでは、個人がある程度は困難なことにチャレンジするように動機づけられることになると結論するのである。
このように、この2タイプの動機づけモデルによって導かれる結論は異なる。それでは、実際には、仕事をする際の満足感である職務満足は、一体どこから来ているのだろうか。ブルームの考えたように、くじの期待効用のごときものなのだろうか。それともアトキンソンの考えたように、くじの期待効用とは異なる内発的なものなのだろうか。
ハーズバーグ(Frederick Herzberg)の動機づけ衛生理論(motivation-hygiene theory)はそのヒントを与えてくれる。ハーズバーグらは、米国ピッツバーグ(Pittsburgh)市の企業9社の技術者と会計担当者、約200人を対象にした横断的な面接調査を行なった。この面接調査では、彼らの職務について例外的に良い感じをもった時、あるいは例外的に悪い感じをもった時を思い出してもらい、その時にどんな事象が起こったのかを詳細に話してもらうという方法がとられた(Herzberg et al., 1959, ch.3, pp.141-142)。その結果、次のような事実発見が得られたという(Herzberg et al., 1959, p.80)。
ハーズバーグ等(1959, pp.113-114)は、これらの2組の要因は二つの分離したテーマを有していると考えた。つまり、職務満足をもたらす1の満足要因(satisfier)は自分の行っている職務そのものと関係していると考えられるが、職務不満足をもたらす2の不満足要因(dissatisfier)は自分の職務ではなく、それを遂行する際の環境、条件と関係しているというのである。そして、1の満足要因は動機づけ要因(motivators)と呼ばれ、2の不満足要因は、もっぱら職務不満足を予防するための環境的要因なので、衛生要因(factors of hygiene)と呼ばれることになる。これが動機づけ衛生理論の概要である[26]。
この動機づけ衛生理論に対して、その後、ハーズバーグ自身のものも含め、多くの追試が行われ、多数紹介されている(Herzberg, 1966, chs.7-8)。そのうち、復元調査だけでも9研究が取り上げられており、もともとの調査も入れて、17母集団に対する10研究で、重複しているものも入れて100以上の要因が調べられ、そのうち、動機づけ衛生理論の予想と違う結果になったのはわずか3%にも満たないことが紹介されている(Herzberg, 1966, p.125 邦訳p.141)。以上のことから、ハーズバーグの動機づけ衛生理論はかなり真憑性が高いと考えるべきであろう。
動機づけ衛生理論の真憑性が高いとすると、ブルーム型の期待理論で第2次の結果(外的報酬)として動機づけ理論の中で位置づけられるべき給与や作業条件などが、実際には衛生要因にすぎなかったということになる。それに代わって見いだされた動機づけ要因について、ハーズバーグ等(1959, p.114)は、仕事において自らの先天的潜在能力に応じて、現実の制限の内で、創造的でユニークな個人として自分の資質を十分に発揮したいという自己実現(self-actualization)の個人的欲求を満たすからこそ満足要因になるのだと主張している。こうしたことを明らかにしてくれるのが、内発的動機づけの理論である。
内発的に動機づけられた活動とは、アトキンソン型のモデルのところでも触れたように、当該の活動以外には明白な報酬がまったくないような活動のことである。見た目には、つまり外的には何も報酬がないのに、その人がその活動それ自体から喜びを引き出しているようなとき、そう呼ばれる。ブルーム型のモデルで考えられていたように、その活動が外的報酬に導いてくれる手段となっているからその活動に従事するのではない。その活動それ自体が目的となって、その活動に従事しているような活動を内発的に動機づけられた活動というのである(Deci, 1975, p.23 邦訳p.25) [27]。
デシ(Deci, 1975, p.61 邦訳p.68)はこの内発的動機づけ(intrinsic motivation)を考察し、「内発的に動機づけられた行動は、人がそれに従事することにより、自己を有能(competent)で自己決定的(self-determining)であると感知することのできるような行動」であると定義した。アトキンソン(1957)の考えた達成動機づけも、環境との関係において自らが有能で自己決定的であることを感じたいという基本的な動機づけから分化したものであり、内発的動機づけの一つの特殊ケースとなる(Deci, 1975, p.107 邦訳p.120)。有能さと自己決定に対する内発的欲求は、出生時から既に存在しているのである(Deci, 1975, pp.82-84 邦訳pp.92-94) [28]。
有能さ(competence)の概念について説明を加えておこう。この概念はもともとはホワイト(Robert W. White, 1959)によるもので、日常的用法よりも広義に、生物学的意味で有機体がその環境と効果的に相互に作用する能力を指している。ホワイトは広範な文献サーベイを行い、見る、つかむ、はう、歩く、考える、目新しいものや場所を探求する、環境に効果的な変化を生み出すといった行動は、それによって、動物や子供がその環境との間に効果的に相互に作用することを学習するプロセスを構成するという共通の生物学的意味をもっていると考えた。この共通の性質を指すために、有能さという用語が選ばれたのである。
つまり、自己の環境を処理し、効果的な「変化」を生み出すことができたとき、有能さを感じるのであり、デシはホワイトの定義したこの有能さという用語を選ぶことで、変化性向の概念を考察していたことになる。人は自己の環境を自分で処理し、効果的な「変化」を生み出すことができるときに、有能であると感じるのであり、それはまさに自己決定的であると感じていることにほかならない(Deci, 1975, p.61 邦訳p.65)。そして、そうした有能さと自己決定(self-determination)の感覚に対する一般的欲求(Deci, 1975, p.62 邦訳p.70)こそが、個人の「変化」性向なのである。このように有能さはホワイトの定義まで遡れば、自己決定的であるということと同義になるが、有能さには日常の用法での意味が重ねられてしまうので、ここでは用いず、自己決定的という用語のみを用いることにしよう。
この変化性向がある程度の大きさでは存在しているために、人は、
という内発的に動機づけられた行動をとるのである(Deci, 1975, pp.61-63 邦訳pp.69-70)。そしてもし、ある人の自己決定の感覚が高くなれば、彼もしくは彼女の満足感は増加し、逆に、もし、自己決定の感覚が低くなれば、彼もしくは彼女の満足感は減少すると考えるのである(Deci, 1975, Proposition II)。内発的動機づけの理論が正しければ、次の仮説が検証されてしかるべきである(高橋, 1993a)。
仮説4.1 (自己決定仮説) 組織の中での個人の自己決定の感覚が高いほど、職務満足感は高くなる。
この仮説の検証を行うためには、自己決定の感覚がなんらかの形で測定されなければならない。論理的にこれらを表す質問項目と考えられるものの中から、さらに高橋(1993a)でも取り上げられているような主成分分析の結果も検討しながら絞り込みを行って、次の5問が選ばれた。
これらの質問項目に対する回答は「Yes」または「No」を選択する形で行なわれた。各質問について、Yesならば1点、Noならば0点を与え、ダミー変数化することにしよう。これらのダミー変数の単純統計と相関係数行列は表4.2のようになる。
表4.2 変数 D1〜 D5の単純統計と相関係数(JPC90調査; N=831)
| 単純統計 | 相関係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| D1 | 0.508 | 0.500 | ||||
| D2 | 0.531 | 0.499 | 0.371*** | |||
| D3 | 0.633 | 0.482 | 0.327*** | 0.327*** | ||
| D4 | 0.458 | 0.498 | 0.303*** | 0.216*** | 0.204*** | |
| D5 | 0.588 | 0.492 | 0.320*** | 0.273*** | 0.300*** | 0.320*** |
そこで各変数を標準化した上で主成分分析を行なうと、各主成分に対する固有値は 2.258, 0.919, 0.682, 0.644, 0.498 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトル
(0.464, 0.479, 0.476, 0.379, 0.430)
から、各変数の標準偏差も考慮に入れた上で各質問項目に対する重み係数を求めると、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができる。つまり、単純に合計して合成得点を作ってもよさそうだ。そこで、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点を自己決定度として定義することにしよう。定義から、自己決定度は0から5までの整数値をとることになる。
第2章でも述べた通り、職務満足については、ここでは次のYes-No二者択一形式の質問Q4.1で直接的に聞いてみることにする。
そこで、第2章の見通し指数等と同様に、質問Q4.1に対する、あるグループでのYes比率を「満足比率」と定義する。具体的には、「自己決定度が0の人のグループ」「自己決定度が1の人のグループ」……「自己決定度が5の人のグループ」という6グループのそれぞれについて、満足比率を求めることで、自己決定度との関係を調べてみた。その後のデータの蓄積も生かし、JPC90〜JPC96調査の合併データを使うことにすると、表4.3、図4.2のように、自己決定度が上がるにつれて、満足比率もまた上昇するというようなきれいな直線的関係が得られる。図4.2の直線は回帰分析で求めたもので、自己決定度3で満足比率はほぼ50%になり、自己決定度が1上がるごとに満足比率が約10%上昇する関係のあることがわかる。
表4.3 自己決定度と満足比率(JPC90〜JPC96調査)
(A) 自己決定度の値ごとの満足比率
| Q4.1 現在の職務に 満足感を感じる。 | 自己決定度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| Yes | 1990年 | 20 | 42 | 50 | 71 | 94 | 113 | 390 |
| 1991年 | 6 | 29 | 40 | 97 | 133 | 140 | 445 | |
| 1992年 | 8 | 32 | 51 | 74 | 80 | 86 | 331 | |
| 1993年 | 18 | 50 | 80 | 111 | 135 | 156 | 550 | |
| 1994年 | 17 | 44 | 65 | 83 | 99 | 86 | 394 | |
| 1995年 | 15 | 55 | 65 | 112 | 132 | 138 | 517 | |
| 1996年 | 13 | 21 | 35 | 84 | 110 | 112 | 375 | |
| 小計 | 97 | 273 | 386 | 632 | 783 | 831 | 3,002 | |
| No | 1990年 | 78 | 90 | 93 | 70 | 63 | 44 | 438 |
| 1991年 | 35 | 61 | 99 | 92 | 86 | 68 | 441 | |
| 1992年 | 40 | 67 | 110 | 98 | 47 | 22 | 384 | |
| 1993年 | 69 | 110 | 144 | 122 | 83 | 42 | 570 | |
| 1994年 | 55 | 78 | 103 | 83 | 72 | 29 | 420 | |
| 1995年 | 59 | 103 | 122 | 131 | 65 | 52 | 532 | |
| 1996年 | 59 | 103 | 122 | 131 | 65 | 52 | 532 | |
| 小計 | 386 | 598 | 760 | 665 | 491 | 291 | 3,191 | |
| 全体 | 483 | 871 | 1,146 | 1,297 | 1,274 | 1,122 | 6,193 | |
| 満足比率(%) | 20.08 | 31.34 | 33.68 | 48.73 | 61.46 | 74.06 | 48.47 | |
(B) 満足比率を被説明変数とする回帰分析
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 自己決定度 | 10.723 | 0.868 | 12.353 | 0.0002 |
| 定数 | 18.084 | 2.628 | 6.880 | 0.0023 |
図4.2 自己決定度と満足比率(JPC90〜JPC96調査)
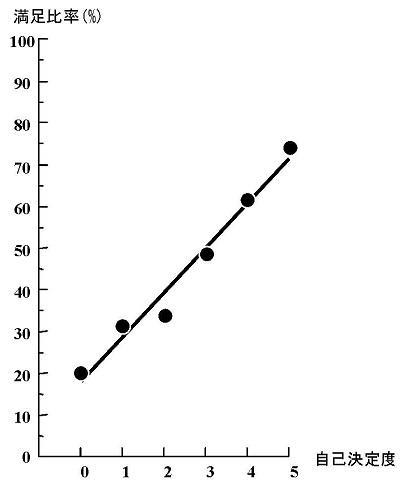
以上のことから、日本企業においては、自己決定仮説が成り立っていることがわかる。ということは、内発的動機づけの理論の帰結としても、日本企業では、(1)自らにとって効果的に変化を生み出すことができるという意味で、最適のチャレンジを与える状況を追求し、そしてまた、(2)自分が出会ったりまたは創り出しているチャレンジを征服しようとしているはずだ、ということになる。まさに、未来傾斜原理に則った意思決定が行われていることになる。
そして、もう一つ重要な可能性が指摘できる。実際に組織の中での個人の自己決定の感覚が高いほど、職務満足感は高くなっているということは、従来の外的報酬を基礎に置いたブルーム型の動機づけモデルでは説明の付けられないような現象が、日本企業では見られるはずだということである。その代表が、次の章で明らかにされる「ぬるま湯的体質」なのである。
この章の議論では、直接的には「見通し」の話は出てこないが、この章のしめくくりに、見通しの重要性について触れておこう。自己決定度と満足比率の図4.2は、第2章で示した見通し指数と満足比率の図ほどには、きれいな線形性が現れていない。これはどうしてなのだろうか。実は、これには、「見通し」が重大な影響を与えている可能性が考えられる。そのことを実際の調査事例を通して見てみよう。ここで取り上げる調査事例は、CALUTE (Climate Assessment of Lukewarm Units' Temperature)と呼ばれる組織風土の調査診断手法を社会経済生産性本部で開発した際に遭遇したものである。
CALUTE 開発に際しては、1992年に、トライアルとして、産業機器の大手メーカーI社のパートタイマーまで含めた従業員の全数調査を行なった(高橋, 1994)。これをCALUTE92調査と呼ぶことにしよう。I社は正社員約2,000名、パートタイマー約250名をかかえる東証一部上場の注文生産中心の産業機器メーカーである。質問票調査は、1992年11月25日(水曜日)〜30日(月曜日)にかけて行われた。質問調査票の回収2,128人、回収率は97.4%であった。この質問票調査を受けて、1993年1月19日(火曜日)には、I社の本社で社長以下、役員、事業所長に対して調査結果の中間報告が行われた。この段階では事後のヒアリング調査はまだ行われておらず、質問票を用いた統計調査データからの知見と推測だけが「中間」報告の形で述べられた。これによって、I社での事後ヒアリング調査が承認された。
中間報告の中でも用いられた図4.3で(この図では自己決定度はI社内での偏差値表現になっている)、事業所別の満足比率を見てみよう。これによるとS事業所の満足比率が23.3%と自己決定度により予想されるよりもかなり低水準であることがわかる。つまり、これまで自己決定仮説を構築、検証してきた際の企業間比較では現れなかった現象が、企業内比較では出たわけで、何か企業内比較に固有の特殊事情があるのではないかと考えられた。そこで、統計的分析の中間報告を経て、1993年6月18日(金曜日)に、S事業所で4名、K工場で8名をインタビューする事後のヒアリング調査が企画実施されたわけである。
図4.3 産業機器メーカーIの全従業員(2,128人)の事業所別満足図(CALUTE92調査)
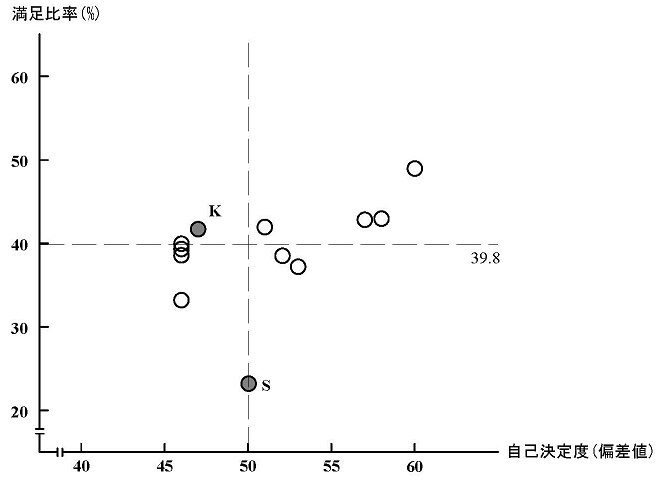
(満足比率39.8% 入社後5年の推定年間離職率12〜13%)
S事業所(約100名)はK工場(約350名)の分工場であり、正式名称は「K工場S事業所」という。しかし、K工場自体は、図4.3ではごく普通の位置にプロットされている。K工場は市の中心部に近い住宅地の中に立地しているが、S事業所はK工場から車で20分ほどの距離の海浜の工場地区にあり、手狭になったK工場を補うために1985年に開設された。I社は注文生産で、単品もしくは少数生産を行なっているため、その工程は大まかに次のようになる。
設計→資材調達→生産→調整検査
K工場で生産している代表的な製品では、設計から資材調達までに約2カ月、生産に約1カ月、調整検査に約1.5カ月を要し、注文から納入まで約6カ月を見込んで受注が行なわれる。K工場で扱っていた製品のうち、汎用機器について、工程の最初と最後、すなわち設計と調整検査の部分が順次S事業所に移された。そのためS事業所はI社の中では唯一、生産部門のない事業所となっているのであるが、I社の話によれば、生産よりも時間をかける調整検査の工程は、もの作りの現場的な色彩が強く、生産部門がないこと自体は、あまり気にならないということだった。
通常よく行われる非統計的な組織調査の方法である
では、S事業所の満足比率が予想される水準よりもかなり低い理由はわからなかった。そこでさらに、統計調査の結果を目の前に置いて、その理由を尋ねる形で、従業員へのインタビューを行った。
ここに至って、ようやくその理由が明らかになってきた。それはS事業所の社内的なステータスの低さである。社内ステータスが低い理由はいくつも存在していた。
社内ステータスによる影響は、企業間比較の場合には、各企業内で相殺されてしまうために問題にならないが、企業内比較の場合には非常に重要な要因となることが、統計調査の事後ヒアリング調査によってはじめて明らかになったのである。
さらに、S事業所の中でも特に満足比率が低く、S事業所全体の満足比率の足を引っ張っている満足比率10%にも満たない2部門については、これらのことを補強する特殊事情があった。
実際、両室はK工場の中では窓際族的かつ雑用係的印象が強く、K工場の中では最低の満足比率21.7%を記録している。つまり、K工場内部でも、ステータスの低さが満足比率を引き下げていると考えられるわけで、以上のようなことから、S事業所の社内的なステータスの低さが、そこへ異動させられた人間の不満を引き起こし、その不満が満足比率を引き下げていると考えられる。
しかし、ここで重要なことは、社内ステータスの低さが、なぜ満足の低下を引き起こしたのかということである。これは第2章での表現を用いれば、社内ステータスの低い部署に配属されたことで、社内での見通しが大幅に低下したためと考えられる。現に、K工場にとどまることは、I社では順当な出世コースに残ることを意味していたし、S事業所に異動させられることは、「島流し」という言葉そのままに、その出世コースから外れることを意味していた。このCALUTE92調査の調査項目には見通し指数は入っていないので、直接的には確認できないのが残念であるが、このCALUTE92調査で発見された社内ステータスの重要性は、とりも直さず、見通しの重要性を意味しているのである。
[22] このパラドックスは、もともとはアムステルダムからサンクトぺテルブルクまでの海上輸送の危険に対する保険の問題に端を発しているといわれるが、このパラドックスの解決に登場するのが、ダニエル・ベルヌーイ(Daniel Bernoulli)である。流体力学や気体運動論で有名なベルヌーイは1700年生まれで、1725年から1733年まで、ロシアのサンクトぺテルブルクの帝室科学アカデミーの数学の教授をしている。その間に「くじの計算に関する新理論」と題する論文を書き、スイスのバーゼルに帰った後、1738年に『ペテルブルク帝室科学アカデミー論文集』に発表したといわれる(鈴木, 1994, pp.397-399)。
[23] ちなみに、摂氏 C 度と華氏 F 度の間には、F=(9/5)C+32 という一次式で表される関係がある。つまり、摂氏の温度と華氏の温度の違いは、単なる温度計の目盛の付け方の違いでしかない。したがって、温度というものは実質的にはただ一つしかないと解釈していい。このことは、効用を測る効用関数にもそのままあてはまる。こうしたことから、効用関数については、「正の線型変換を除いて一意に定まる」という言い方もされる。
[24] 実は、ここでブルーム自身は第1次の結果と第2次の結果という区別をしていないが、両者を区別しておかないと、誘意性の間にはこの(4.4)式が与えられているために、誘意性はその連立方程式を代数的に解くことによって求められるべきものであるということになりかねない。そこで、一般には第1次の結果と第2次の結果とは区別して考えられている。ブルーム理論の解説や解釈も基本的にこの区別を行っている。
[25] この(4.6)式の中の個人ごとに定まる定数である Ms− Mf は、チャレンジの際の成功への動機から失敗回避動機を引いたものであり、この変化を求める傾向を第5章では個人の変化性向(propensity to change)と呼んでいる(高橋, 1989a; 1993a)。
[26] 動機づけ衛生理論に対しては、その調査方法も含めて批判があり(例えば、Vroom (1964, pp.126-129 邦訳pp.145-148))、ハーズバーグ論争にまで発展したが(坂下, 1985, pp.35-47)、これはむしろ衛生要因ばかり見てきた当時の動機づけ論者からの拒絶反応と考えた方が理解しやすい。実際、翌1960年にはマグレガー(Douglas McGregor)がX理論、Y理論を発表するが、当時、組織に関するたいていの文献や経営施策で、暗黙のうちに、普通の人間は生来仕事が嫌いで、責任を回避することを望み、強制、統制、命令、おどしが必要になると考えているとして、これをX理論(Theory X)と呼ぶことになる(McGreger, 1960, pp.33-34 邦訳pp.38-39)。それに対して、当時生まれつつあった動機づけ要因的な特性に着目する人事管理の新理論はY理論(Theory Y)と呼ばれる(McGreger, 1960, pp.47-48 邦訳pp.54-55)。つまり、ブルームの期待理論以前の1960年頃は、外的報酬による動機づけの発想が色あせ、内発的動機づけが見いだされつつある状況だったのである。
[27] デシ(1975)の記述の中には、この4.5項で引用している概念の定義部分に限定しても、行動(behavior)と活動(activity)が統一されないままに使われている。しかし、こうして集めて引用すると混乱を招くので、本書では「行動」に統一することにした。
[28] ここでの有能さと自己決定に対する内発的欲求の位置付けは、マズロー(Abraham H. Maslow, 1943)による自己実現の欲求の位置づけとはその位置づけが根本的に異なっていることには十分な注意が必要である。マズローは人間の欲求は最低次欲求から最高次欲求まで階層的に配列されていると仮定した上で、低次の欲求は満足されると強度が減少し、欲求階層上の1段階上位の欲求の強度が増加するというように、欲求の満足化が低次欲求から高次欲求へ、
前章で、日本企業においては、自己決定仮説が成り立っており、そのため、従来の外的報酬を基礎に置いた動機づけモデルでは説明の付けられないような現象が見られるはずとしていたが、その代表が「ぬるま湯的体質」である。
もともとは「組織が活性化していない状態」の典型として、いわゆる企業の「ぬるま湯的体質」に着目し、ぬるま湯の現象がどのような状態のとき発生しているのか、そして、ぬるま湯的体質が組織の活性化にどのような意味をもっているのかを明らかにするために、調査が行われた。これは、ぬるま湯的体質に関しての、いわば事実発見を主目的とした調査であり、この調査から、ぬるま湯感を説明するための枠組みとして「体感温度仮説」が立てられた。これは、湯温として組織のシステムの変化性向を表す指数である「システム温」を考え、これとメンバーの組織人としての変化性向を表す指数である「体温」との温度差によってぬるま湯感を説明しようとするものである。
日本企業のぬるま湯的体質を解明するために、高橋(1989a)において最初に提唱した「体感温度仮説」はその後、調査研究を積み重ねて『ぬるま湯的経営の研究』(高橋, 1993a)にまとめられた。そこで、この章では、まず同書に基づいて「体感温度仮説」の概説を試みた上で、同書から始められた体感温度測定尺度の改良作業を継続し、その後のデータの蓄積による「体感温度仮説」の検証を行う。そして、実際問題として、ぬるま湯感が発生する際には、企業の成長性が発生要因として大きな位置を占めることを明らかにする。また、ぬるま湯の状態は外発的には動機づけられていないのに、組織に貢献している状態だったことも明らかになる。
前章でも述べたように、変化性向の概念は、チャレンジの概念と密接に結び付いたもので、外発的には動機づけられていないのに、組織に貢献している「ぬるま湯」現象が日本企業で多く観察されるということは、まぎれもなく、日本企業に勤める多くの従業員が、少なくとも動機づけの場面においては、期待効用原理の世界ではなく、未来傾斜原理の世界に住んでいるということを示している。前章で、ワーク・モティベーションの世界では、期待効用原理は色あせ、チャレンジの概念が大きな意味を持ち始め、自ら成長し、そして育てることの中に未来の本当の価値があると指摘したが、「ぬるま湯」現象の出現に際して、リスクや期待効用ではなく、まさにチャレンジと成長性が大きな意味をもっているのである。
「ぬるま湯」現象とはどういった組織現象、特に職場内や個人の意欲上の現象を表しているのであろうか。また、そもそもぬるま湯的体質とは、組織が活性化していない状態の典型だと考えてしまってよいのであろうか。こうした一連の問題意識に基づいて、ぬるま湯感についての事実発見を主目的としてのJPC87調査が企画された。
そこで、このJPC87調査のデータを基にして、ぬるま湯現象について考察していくことにしよう。ぬるま湯感についての、いわば鍵となる質問:
については、55.4%がYes、44.6%がNoと答え、ほぼ半数の人がぬるま湯感を感じると答えている。ここで、この質問に対して、Yesすなわち「ぬるま湯」と感じることがあると答えた人の比率を「ぬるま湯比率」と呼ぶことにしよう。
この質問については、会社別には有意な相関が見られたが、性別、年齢階層別、既婚・未婚別、学歴別、職種別、職位別には有意な相関は見られなかった。また、この調査ではこの他に、質問Q5.1を含む「職場に関する」25の質問項目と後述する質問Q5.2を含む「個人の仕事に対する姿勢に関する」25の質問項目の計50問が同時に調べられていた。そこで、ぬるま湯感と他の質問項目との間の相関関係をみてみると、「職場に関する」質問項目との相関がまだ高いが、「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問項目との相関は全般的に低いという特徴のあることがわかった。このように、組織の不活性状態を表すと考えていた質問項目との間で相関があまり高くないということは、組織の不活性状態の代表的な現象としてぬるま湯現象を位置付けることに疑問を抱かせる。少なくとも典型的とはいえないのではないだろうか。
この疑問は、調査の第1段階のヒアリングで、組織のメンバーの活性化の重要な指標と見ていた質問:
との相関をみると、よりはっきりしてくる。この質問に対し、62.0%の人がYes、38.0%の人がNoと答え、ほぼ6割の人が仕事に充実感を感じていると答えていたが、この仕事の充実感はぬるま湯感とは異なり、会社別に有意な相関があるだけではなく、性別にみれば男性の方が、年齢階層別にみれば高い年齢階層の方が、既婚・未婚別にみれば既婚者の方が、学歴別にみれば高学歴の方が、職位別にみれば高い地位の方が、より仕事の充実感を感じているという有意な相関がみられるのである。しかも、この仕事の充実感は、職場に関する質問項目、個人の仕事に対する姿勢に関する質問項目との相関がともに高いという特徴のあることもわかった。
この質問Q5.2は、ぬるま湯感と有意な相関のあった、数少ない個人の仕事に対する姿勢に関する質問の一つで、なおかつその中では一番相関係数の高いものだったが、クロス表の形で示すと表5.1のようになり、ぬるま湯感と仕事の充実感の間には有意な負の相関関係があるものの、仕事に充実感を感じている人のほぼ半数がぬるま湯感も同時に感じており、両者の間にはかなりの重なりが存在していることがわかる。
表5.1 ぬるま湯感と充実感(JPC87調査)
| Q5.2 自分の仕事に 充実感を感じている。 | Q5.1 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 175 | 176 | 351 |
| No | 138 | 77 | 215 |
| 計 | 313 | 253 | 566 |
しかも、質問Q5.1、Q5.2に対して、Yesと答えた人の比率をそれぞれ「ぬるま湯比率」「充実比率」と呼ぶことにし、会社別に、両比率を求め、プロットしてみると、図5.1のようになる。この両者の間には、全体的には弱い負の相関関係があるが、C社については、こうした傾向からはずれる特性を示していることがわかる。C社は、71.7%がぬるま湯だと感じていて、ぬるま湯比率は調査対象企業11社中もっとも高くなっているが、一方、仕事に充実感を感じている者も72.9%もいて、充実比率も11社中3番目に高いのである。つまり、C社においては、まさに仕事の充実感とぬるま湯感が共存していることがわかる。同様に、職場別にみてみると、ぬるま湯感と仕事の充実感の共存する職場が、C社に限らず、かなり存在していることもわかった。つまり、ぬるま湯現象を単純に組織の不活性状態における典型的現象として考えることは、かえって不自然に思われるのである。
図5.1 会社別ぬるま湯比率・充実比率散布図(JPC87調査)
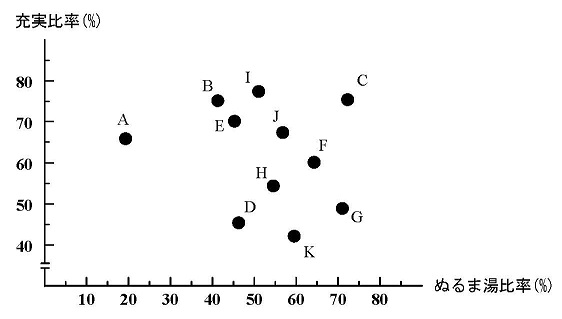
そこで、原点に戻って考えてみることにしよう。職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じるということはどういう現象なのであろうか。また、職場のぬるま湯感を表す際の「温度」とは何を意味しているのだろうか。高橋(1989a)は、そのヒントを「ぬるまゆにつかる」の意味の中に求めた[29]。 つまり、現状に甘んじることなく変化を求める傾向、現状を打破して変化しようとする傾向、これを「変化性向」と呼び、ここでは、組織のシステムとしての変化性向をまず考え、変化性向が大きければ、「温度」が高く、熱いと感じ、逆に、変化性向が小さければ、「温度」が低く、ぬるま湯と感じると考えるのである。
変化性向に関しては、既に前章においても、自己決定、有能さ、チャレンジの概念との関連について触れている。ここでは、JPC87調査の前述の50の質問項目のうち、「職場に関する」質問のなかから、基本的には論理的に考えて組織のシステムとしての変化性向を表すものと考えられる次の五つの質問を選び出した[30]。
この五つの質問のうち、S1〜S3についてはYes、S4、S5についてはNoと答えた方が、変化性向が大きいと考えられる。そこで、この五つの質問を基にして、各個人について、S1〜S3についてはYesならば1点、Noならば0点を与え、S4、S5についてはYesならば0点、Noならば1点を与えて、これらの5問の合計点をシステム温と呼び、定義し、これによって、組織のシステムとしての変化性向をみることにした。システム温は組織のメンバーがつかっている湯の温度を表しているものであるが、湯温という用語を用いると、システムの温度ではなく、回答者の周囲の人々の温度を表しているかのような誤解を与えるので、ここではあえてシステム温という用語を用いることにする。
そこで、このシステム温とぬるま湯感の関係をみるために、ぬるま湯感についての鍵となる前述の質問Q1で、職場の雰囲気をぬるま湯と感じている人を便宜上「ぬるま湯」群と呼び、そうではない人をやはり便宜上「非ぬるま湯」群と呼んで、その両者の間で、システム温についての平均値の差の検定を行ってみた。すると、全体でのシステム温の平均は3.05だったが、「ぬるま湯」群での平均は2.72、「非ぬるま湯」群での平均は3.46と、予想通り、「ぬるま湯」群の方が、システム温が0.1%水準で有意に低いことが確かめられた。
以上のことから、システム温によって、個人のぬるま湯感を説明することは有望そうである。それでは、このシステム温を使うことで、会社別にみたときのぬるま湯感を説明できるであろうか。つまり企業のぬるま湯的体質を説明することができるであろうか。会社別のシステム温については、表5.2に示してあるが、各社のシステム温の平均には0.1%水準で有意な差がみられるものの、11社中で最高のぬるま湯比率71.7%のC社のシステム温は2.73になっていて、システム温が特に低いということにはなっていない。したがって、ぬるま湯感を説明するためには、システム温だけではまだ不十分と考えた方がよいようである。そこで、ぬるま湯感を説明するための新たな枠組みが必要となってくる。
表5.2 会社別のシステム温・体温・体感温度(JPC87調査)
| 会社 | N | システム温 | 体温 | 体感温度 |
|---|---|---|---|---|
| A | 19 | 4.00 | 4.05 | -0.05 |
| B | 27 | 3.19 | 3.52 | -0.33 |
| C | 55 | 2.73 | 4.04 | -1.31 |
| D | 18 | 2.50 | 3.44 | -0.94 |
| E | 96 | 3.72 | 3.68 | 0.04 |
| F | 78 | 2.36 | 3.23 | -0.87 |
| G | 65 | 2.86 | 3.45 | -0.58 |
| H | 53 | 2.92 | 3.26 | -0.34 |
| I | 26 | 3.92 | 4.54 | -0.62 |
| J | 40 | 3.15 | 3.98 | -0.83 |
| K | 48 | 2.81 | 3.25 | -0.44 |
| 全体 | 525 | 3.05 | 3.60 | -0.55 |
C社のもつ特徴についてもう一度思い起こしてみよう。C社はぬるま湯比率が71.7%と11社中最も高い一方で、充実感比率も72.9%と11社中3番目に高かった会社である。そのことを考え合わせると、ぬるま湯感には、単に、組織のシステム側の要因だけではなく、人の側にも原因がありそうである。そこで、次のように考え、仮説を立ててみよう。
生物としての人間の体温は、誰でも約36〜37℃でほぼ一定している。だから、システム温という湯の温度を考えて、ぬるま湯感を説明することを自然に思いついたのである。しかし、組織人としての人間の体温は、果して、誰でも、いつでも一定なのであろうか。つまり、C社のメンバーのように仕事の充実感の高い人は、実は組織人としての体温も高いのではないだろうか。そして、ぬるま湯と感じるか熱湯と感じるかということは、組織人としての体温をベースとした体感温度の問題なのではないだろうか。
ここでいう「体温」とは、組織のメンバーの組織人としての変化性向であり、組織のメンバーが現状を打破して、変化をもたらそうとする意欲がどの程度あるのかを表す指数と考えられる。一方、「システム温」とは、既に定義したように、組織のシステムとしての変化性向であり、組織のシステムがメンバーの変化を受け止め、あるいは促す仕組み、制度にどの程度なっているのかを表す指数であった。そこで、組織人としての変化性向として体温を考え、思い切って単純化をして、この体温とシステム温との温度差で、ぬるま湯感を説明することを考えた(高橋, 1989a)。
仮説5.1 (体感温度仮説) 体感温度を
体感温度=システム温 − 体温
のように定義すると、ぬるま湯と感じる人の方が、熱湯と感じる人よりも体感温度が低く、ぬるま湯と感じる人と熱湯と感じる人の分布は図5.2のようになる。
図5.2 体感温度仮説
(A)システム温・体温と体感温度 (B)体感温度による相対度数折れ線
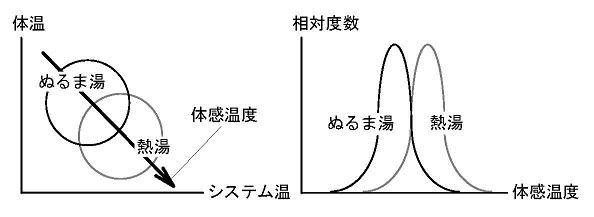
体感温度仮説を検証するためには体温について定めなくてはいけない。まず、システム温と同様にして、基本的には論理的に考えて、今度は「あなたの仕事に対する姿勢に関する」質問の中から組織人としての変化性向を表す質問項目と考えられる、次の五つの質問を選び出した:
このうち、B2についてはNo、他の4問についてはYesと答えた方が変化性向が大きいと考えられる。そこで、システム温と同様にして、この五つの質問を基にして、各個人について、B2についてはYesならば0点、Noならば1点、他の4問についてはYesならば1点、Noならば0点として点数を与え、この五つの質問について点数を合計したものを体温と呼び、定義し、これによって、組織人としての変化性向をみることにした。
各社の体温の平均は既に表5.2に示されているが、平均については0.1%水準で有意な差がみられた。予想された通り、C社はやはり体温の平均値も4.04と高く、充実比率と同様に、11社中3番目に高い値になっている。
それではさっそく、仮説5.1の検証にとりかかることにしよう。ただし、仮説5.1では、「ぬるま湯」と感じる人と「熱湯」と感じる人という分類を用いているが、今回の調査では質問Q5.1しか使うことができないので、「ぬるま湯」「非ぬるま湯」という分類しか用いることができない。そこで、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群とで、体感温度に差が認められるかどうかをみてみることにしよう。まず体温についてみてみると、全体での体温の平均は3.60だったが、ぬるま湯感と「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問との間に、あまり相関が高くなかったことを反映して、体温の平均は「ぬるま湯」群では3.64、「非ぬるま湯」群でも3.56と、両群の間には体温の平均値に有意な差はみられなかった。次に、体感温度を計算して求めると、全体での体感温度の平均は-0.55だったが、「ぬるま湯」群での平均-0.91、「非ぬるま湯」群での平均は-0.09と、両群の間には体感温度の平均値に0.1%水準で有意な差があり、仮説通りに、「ぬるま湯」群の体感温度の方が「非ぬるま湯」群の体感温度よりも低いことがわかった。以上のことは、図5.3のように、「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群両者の相対度数折れ線を描くとより明確になり、仮説の図5.2(B)とほぼ同じ図が得られる。
図5.3 相対度数折れ線(JPC87調査)
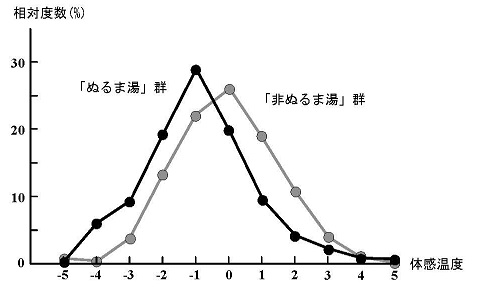
ところで、今回の調査では、「熱湯」ではなく「非ぬるま湯」のカテゴリーを使うことしかできなかった。このため「非ぬるま湯」の中に、熱湯だけではなく、他の「適温」なども入ってくることが考えられる。実際、体温を縦軸、システム温を横軸とする図5.2(A)上での分布を見てみると、図5.4の(A)(B)のようになった。傾向としては、仮説に近い傾向が現れたものの、図5.4(B)の「非ぬるま湯」群の分布は、仮説の中で「熱湯」としていた位置よりも、右上隅を中心に分布していて、「非ぬるま湯」群の大部分がいわば「適温」に分類すべきメンバーであったことを示唆している。
図5.4 体温・システム温散布図(JPC87調査)
(A)「ぬるま湯」群
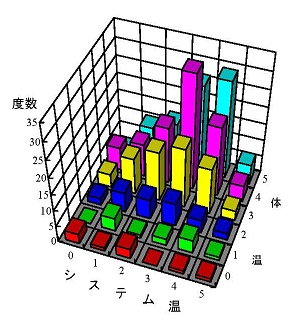
(B)「非ぬるま湯」群
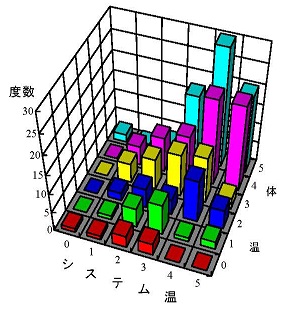
次に会社別の分析をしてみよう。会社別に体感温度の平均値を求めたものは既に表5.2に示してあるが、0.1%水準で会社によって体感温度の平均値に有意な差のあることがわかる。その中で、ぬるま湯比率が最も高かったC社の体感温度は一番低くなっている。また会社別にシステム温、体温の平均値を求め、散布図に会社をプロットしてみると、図5.5のようになり、C社が予想された高体温・低システム温の「ぬるま湯」領域にプロットされる。以上のことから、システム温と体温を使って、企業のぬるま湯的体質をかなり説明することができそうだということがわかった。
図5.5 会社別散布図(JPC87調査; 破線は平均値)
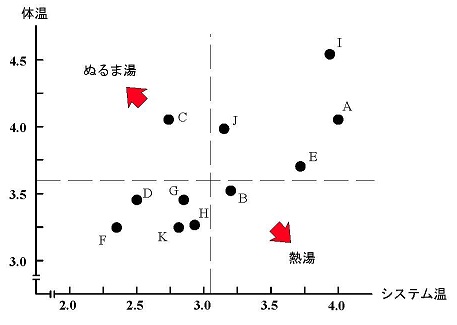
さらに同じ体感温度測定尺度を用いて、追試として、今度は調査対象者を中間管理職に限定してJPC88調査を行った。詳細については高橋(1990b)に詳しいが、JPC88調査では、ぬるま湯感についての質問Q5.1「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」に対しては、69.7%がYes、30.3%がNoと答えている。これはJPC87調査でYesが55.4%、Noが44.6%とほぼ半数がぬるま湯感を感じていたことと比べると、ぬるま湯比率が7割という高レベルになっている。ところが、JPC88調査のシステム温の平均値は3.06で、JPC87調査のシステム温の平均値3.05とほぼ同じであり、システム温だけによってJPC88調査での中間管理職の高水準のぬるま湯感を説明することはできない。しかし、体感温度仮説によれば、2回の調査でシステム温の平均はほぼ同じなのに、JPC88調査の中間管理職の場合には、体温の平均が4.09と、JPC87調査の3.60を大きく上回っていたために、体感温度が低下し、その結果、ほぼ7割がぬるま湯感を感じることになってしまったと説明することができる。
これとは逆に、低体温が引き起こす現象も報告されている。次節で後述する改良版の体感温度測定尺度を用いて、辻(1993)は1992年に3県1政令指定都市の計4地方自治体の職員の調査を行い、15の職場で331人からデータを得た(回収率は91.9%)。それによると、これらの地方自治体の職員での「ぬるま湯比率」は36.7%で、JPC調査のぬるま湯比率と比べるとかなり低い。しかし、地方自治体ではシステム温は高めではあるが、特に高いというわけではなかったのである。むしろ体温が低く、一つを除けば、すべての職場で体温はJPC調査の平均以下となっていたために、体感温度仮説の通りに「体感温度=システム温−体温」で体感温度が上がってしまい、ぬるま湯とは感じなくなっていると考えられた。こうして、調査結果を積み重ねることで、体感温度仮説の信憑性がより高まっていくことになる。
JPC87調査では一つの重要な事実発見、すなわち「非ぬるま湯」群の大部分が、実は「熱湯」ではなく、「適温」と呼ぶべき領域に属していたことがわかった。そこで、こうした事実発見をふまえて、「ぬるま湯」対「熱湯」という対立図式を体感温度によって説明するのではなく、「ぬるま湯比率」を体感温度で説明することを考えてみよう。そのためにまず、仮説5.1の体感温度仮説の次のようなぬるま湯比率版を考える。
仮説5.2 (ぬるま湯比率に関する体感温度仮説) ぬるま湯と感じる人の比率をぬるま湯比率と呼ぶと、体感温度が高くなるほどぬるま湯比率は低下する。
ところで、この仮説5.2を検証するには、JPC87調査の質問項目はあまり適しているとはいえない。つまり、単調性のあるきれいな関係が出てこないのである。この原因は、JPC87調査を実施してしまった後でシステム温や体温といった変化性向の概念に合いそうな質問項目を選んだために、採用された10の質問項目の中にやや問題のある質問項目も含まざるをえなかったことにある。具体的には、次のような問題点を指摘することができる。
以上のことから、ぬるま湯比率を説明するという観点から、改めて質問項目リストの吟味をする必要がある。
そのため、まずそれまでの質問票調査によって集積されたデータと経験をもとにして、質問項目の収集・整理と、それを基にした質問調査票の設計を行い、1990年に予備調査を行った(高橋, 1990c)。そしてJPC90調査を行い、質問項目リストの改善を図り、改良版体感温度測定尺度として、次の10問を選んだ(高橋, 1993a, ch.3):
システム温システム温については、問題のあった質問項目については結果的に除くことにした。代わりに、S7〜S9をまったく新たに加え、さらにS6についても、質問文S2よりも説明的な表現に改めた。体温についても、体温の平均を下げる必要もあって、全面的に見直しを行い、B1以外は質問項目を入れ替えることにした。これらの10の質問項目のうち、システム温の質問S6、S8、体温の質問B9については、Yesならば0点、Noならば1点、他の七つの質問項目については、Yesならば1点、Noならば0点を与えて、ダミー変数化することにしよう。質問項目 Si に対応するダミー変数を Si で表し、質問項目 Bi に対応するダミー変数を Bi で表すことにする。
まずシステム温に使われるこれらのダミー変数の単純統計と相関係数行列は表5.3のようになる。そこで各変数を標準化した上で主成分分析を行なうと、各主成分に対する固有値は 1.696, 1.104, 0.844, 0.712, 0.645 となり、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトル
(0.455, 0.452, 0.489, 0.405, 0.431)
から、各変数の標準偏差を考慮に入れても、システム温の各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができる。
表5.3 システム温系の変数の単純統計と相関係数(JPC90調査; N=830)
| 単純統計 | 相関係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | S1 | S6 | S7 | S8 | |
| S1 | 0.416 | 0.493 | ||||
| S6 | 0.410 | 0.492 | 0.201*** | |||
| S7 | 0.596 | 0.491 | 0.217*** | 0.131*** | ||
| S8 | 0.450 | 0.497 | 0.074* | 0.309*** | 0.160*** | |
| S9 | 0.264 | 0.441 | 0.219*** | 0.085* | 0.277*** | 0.063† |
次に体温に使われるダミー変数の単純統計と相関係数行列は表5.4のようになる。そこで各変数を標準化した上で主成分分析を行なうと、各主成分に対する固有値は 1.960, 0.980, 0.820, 0.659, 0.581 となり、第1主成分だけが約2で1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトル (0.515, 0.499, 0.509, 0.351, 0.322) から、各変数の標準偏差を考慮に入れても、B8、B9の重み係数は小さめであった。
表5.4 体温系の変数の単純統計と相関係数(JPC90調査; N=831)
| 単純統計 | 相関係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | B1 | B6 | B7 | B8 | |
| B1 | 0.721 | 0.449 | ||||
| B6 | 0.583 | 0.493 | 0.329*** | |||
| B7 | 0.616 | 0.486 | 0.383*** | 0.388*** | ||
| B8 | 0.537 | 0.499 | 0.231*** | 0.150*** | 0.165*** | |
| B9 | 0.627 | 0.484 | 0.174*** | 0.183*** | 0.111** | 0.190*** |
ところで、体感温度を「システム温−体温」として引き算をして求めることについてはどうだろうか。これについては、質問Q5.1を使って「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群に分けた上で、2群の判別分析を行なってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。
u=−0.414+0.097 S1+0.263 S6+0.653 S7+0.514 S8+0.711 S9
−0.254 B1−0.311 B6−0.022 B7−0.138 B8−0.191 B9 (5.1)
この線形判別関数を基にして u を計算し、u<0 のとき「ぬるま湯」、u>0 のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。線形判別関数を見ると、係数の大きさにはかなりのばらつきがあるものの、システム温系の変数の係数の符号はすべて正であり、体温系の変数の係数の符号はすべて負となっており、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした体感温度仮説を符号の点で明確に支持したものになっている。
そこでこうした主成分分析、判別分析の結果から、符号の点では一致しているので、重み係数の値の大小には振り回されずに、ダミー変数化した各5変数を単純に合計した合計点をシステム温、体温の値として定義することにした。このようにシステム温、体温の各変数の重み係数は一定としてしまうことの不利益は、実はほとんどない。例えば、この等ウェイトのシステム温、体温を使って、体感温度≦0 のとき「ぬるま湯」、体感温度>0 のとき「非ぬるま湯」と判別すると、誤判別率は最小の38.5%になるが、線形判別関数(5.1)式を用いた判別を行なったとしても誤判別率は38.0%で、ほとんど改善されないのである。
こうして定義すると、システム温、体温ともに0から5までの整数値をとることになる。したがって、体感温度は-5から5までの整数値をとることになる。そこで、第2章の見通し指数等と同様に、質問Q5.1に対する、あるグループでのYes比率を「ぬるま湯比率」と定義する。具体的には、「体感温度が-5の人のグループ」「体感温度が-4の人のグループ」……「体感温度が5の人のグループ」という11グループのそれぞれについて、ぬるま湯比率を求めることで、体感温度との関係を調べてみた。M
その後のデータの蓄積も生かし、JPC90〜JPC96調査の合併データを使うことにすると、その結果は表5.5のようになる。これはぬるま湯感と体感温度のクロス集計表であるが、仮説5.2では、ぬるま湯比率が問題になっているので、行ではなく、列で、つまり縦方向に百分率をとっている。この表5.5から明らかなように、仮説5.2の通り、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率は単調に低下していく。この様子は、図5.6にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。
表5.5 体感温度(改良版)とぬるま湯比率(JPC90〜JPC96調査)
| 質問Q5.1 ぬるま湯感 | 体感温度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | ||
| Yes | 1990年 | 14 | 34 | 68 | 98 | 98 | 82 | 46 | 18 | 3 | 1 | 0 | 462 |
| 1991年 | 17 | 52 | 84 | 133 | 121 | 101 | 60 | 26 | 9 | 1 | 0 | 604 | |
| 1992年 | 23 | 40 | 90 | 97 | 103 | 93 | 46 | 20 | 11 | 2 | 0 | 525 | |
| 1993年 | 24 | 64 | 125 | 136 | 132 | 113 | 62 | 30 | 8 | 4 | 0 | 698 | |
| 1994年 | 22 | 51 | 87 | 104 | 110 | 91 | 62 | 33 | 11 | 4 | 0 | 575 | |
| 1995年 | 45 | 87 | 126 | 152 | 149 | 104 | 74 | 35 | 7 | 6 | 1 | 786 | |
| 1996年 | 23 | 64 | 91 | 111 | 125 | 76 | 49 | 16 | 10 | 3 | 0 | 568 | |
| 小計 | 168 | 392 | 671 | 831 | 838 | 660 | 399 | 178 | 59 | 21 | 1 | 4,218 | |
| No | 1990年 | 3 | 12 | 31 | 51 | 80 | 69 | 61 | 31 | 8 | 7 | 1 | 354 |
| 1991年 | 1 | 8 | 20 | 34 | 55 | 59 | 53 | 27 | 8 | 8 | 0 | 273 | |
| 1992年 | 1 | 8 | 24 | 20 | 35 | 47 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 182 | |
| 1993年 | 1 | 14 | 31 | 60 | 75 | 90 | 77 | 50 | 16 | 8 | 2 | 424 | |
| 1994年 | 2 | 9 | 22 | 22 | 42 | 43 | 40 | 27 | 14 | 3 | 1 | 225 | |
| 1995年 | 0 | 9 | 13 | 51 | 44 | 54 | 41 | 31 | 6 | 6 | 1 | 256 | |
| 1996年 | 3 | 12 | 16 | 33 | 37 | 42 | 35 | 22 | 5 | 3 | 0 | 208 | |
| 小計 | 11 | 72 | 157 | 271 | 368 | 404 | 334 | 205 | 60 | 35 | 5 | 1,922 | |
| 全体 | 179 | 464 | 828 | 1,102 | 1,206 | 1,064 | 733 | 383 | 119 | 56 | 6 | 6,140 | |
| ぬるま湯比率(%) | 93.85 | 84.48 | 81.04 | 75.41 | 69.49 | 62.03 | 54.43 | 46.48 | 49.58 | 37.50 | 16.67 | 68.70 | |
図5.6 体感温度(改良版)とぬるま湯比率(JPC90〜JPC96調査)
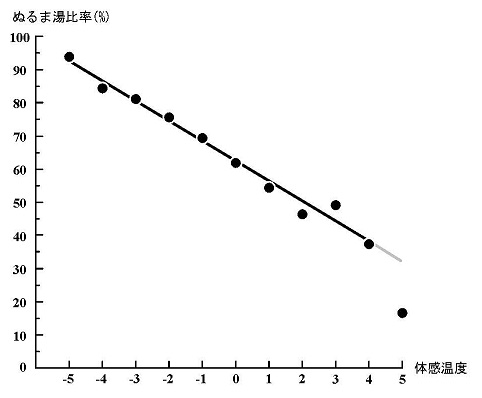
注)図示されている回帰直線は体感温度-5〜4についてのもので、体感温度5は6人(全体の0.1%)しか該当者がいなかったので、回帰分析から除いた。ぬるま湯比率を被説明変数とする回帰分析(体感温度-5〜4)の結果は次のようになる。
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 体感温度 | -6.028 | 0.290 | -20.814 | 0.0001 |
| 定数 | 62.415 | 0.844 | 73.919 | 0.0001 |
ただし、ここで注意を要するのは、体感温度5のところで、急にぬるま湯比率が落ちていることである。これは、体感温度5が6人しかいないため(これは全体のわずか0.1%にすぎない)、精度が落ちるためだと考えられる。そこで、体感温度5を除いて、最小2乗法で残りの10個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図5.6の注にあるような回帰直線となる。決定係数は0.9895となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この回帰直線によれば、体感温度0でぬるま湯比率はほぼ62%となり、体感温度が1高くなるごとに、ぬるま湯比率はほぼ6ポイント低下することになる。この図によって、体感温度のもつ意味はより明確に理解されるだろう。つまり、体感温度を測定することができれば、ある体感温度をもった人がどの程度の確率でぬるま湯感を感じるかを予測することができるのである。
また、体感温度が3以上の人は160人、全体の2.98%しかおらず、実際の組織の中では、熱湯と感じる人がごく少数しかいないこともわかる。これは、測定尺度の問題なのか、それとも実際に、熱湯と感じる人が組織を退出するなどして少ないためなのか、問題として残されるが、後の節である程度の結論が導き出される。
前章で、ワーク・モティベーションでは期待効用原理は色あせ、チャレンジの概念が大きな意味を持ち始め、自ら成長し、そして育てることの中に未来の本当の価値があると指摘したが、「ぬるま湯」現象の出現に際しては、まさに成長性が大きな意味をもっている。
ここで取り上げられる成長性は、一つは企業や産業の置かれた成長段階に関するものであり、もう一つは日本経済全体の成長性、つまり好不況である。いずれの成長性も、企業内にいる従業員に各人の成長の機会を与えるか否かという点で、きわめて重要である。つまりシステム温と密接に関係している。前章で述べたように、体温の高い人は、(1)自らにとって効果的に変化を生み出すことができるという意味で、最適のチャレンジを与える状況を追求し、そしてまた、(2)自分が出会ったりまたは創り出しているチャレンジを征服しようとする、という内発的に動機づけられた行動をとるはずで、成長性が高ければ、こうした行動には絶好の機会となるが、逆に成長性が低ければ、なかなか機会は訪れないことになる。そこに、ぬるま湯感が発生する。その意味では「ぬるま湯」現象は期待効用原理の世界ではなく、未来傾斜原理の世界の組織現象なのである。
ぬるま湯の現象は不活性状態の典型ではなかったということはわかった。それでは、なぜ、ぬるま湯感は好ましくないという印象をもたれているのであろうか。そこで、組織の活性化とぬるま湯感が、なぜいま問題になっているのかについて、改めて考えてみることにしよう。もし、企業が高成長を続けているのであれば、その組織のほとんどの特性、変数は、単調に大きく増加、もしくは単調に大きく減少しているだろう。十分な成長性は組織内部に高い変化率と変化の単調性をもたらすのである。このことは重要である。一つには、組織自体の変化率が大きいことから、組織が現状に留まることは、したくてもできず、組織のシステムとしての変化性向も大きなものとなり、そのため、ぬるま湯感は自然と低く抑えられることになる。それは言い換えれば、企業内にメンバー各自の成長の機会がころがっていることを意味している。企業の成長は、その内部にいるメンバーの成長の機会と表裏一体なのである。
もう一つには、単調性があれば、メンバーは、企業全体の方向性や戦略が明確に分らなくとも、自分の回りのごく狭い世界を構成する変数の過去から現在への動きを知っているだけで、その延長線上に、進むべき未来像を企業全体の方向性に反しない範囲で描くことができる。高橋(1987b)での組織の活性化された状態の定義の中の「組織のメンバーが (1)組織と共有している目的・価値を (2)能動的に実現していこうとする状態」のうちの(1)が容易に達成され、高成長のもたらす活気が(2)をも可能にし、比較的容易に「活性化された状態」が達成されうることになる[31]。
ところが、企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、こうした事態は一変する。単調性はあちらこちらで屈折し、混迷へと急速に推移する。企業全体の方向性や戦略が明確に打ち出されなければ、そして、それがメンバーの間にきちんと浸透しなければ、メンバーは自らの向かうべき方向を見失う。自分がいま何をなすべきかを見失うのである。暗闇の中では、積極的に動くことができない。こうして、活性化された状態は失われる。
しかも、組織自身の変化率が低下しているので、何か人為的に変化性向を高める努力をしない限りは、組織のシステムとしての変化性向も低迷し、低システム温のもとで、体感温度仮説の筋書き通りに、ぬるま湯感もまた進むことになる。もちろん各メンバーの成長の機会も狭められる。
以上のことから、活性化とぬるま湯感は、直接的には因果関係が存在しないにもかかわらず、成長性という先行変数があるために、見かけ上は疑似相関があると考えられるのである(高橋, 1989b)。そこで、この予想を次のような仮説の形に整理しておこう。
仮説5.3 (成長性先行仮説) (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、活性化された状態も比較的容易に達成されるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。
つまり、活性化とぬるま湯感は、成長性という先行変数があるために、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。そこで、JPC89調査の結果からこの仮説の妥当性を検証してみることにしよう。
仮説5.3の検証のために、第1段階のヒアリング調査の中で、ヒアリング対象者自身によって相互の比較が行われ、10社の調査時点での成長段階における位置付けが行われた。その上で、10社を次のように3グループに分けた。
A社は自動車部品メーカーで、売上高、販売台数ともに伸び、納入先も拡大して、工場も次々に増設されている。1988年度の売上高、営業利益の対前年度比の伸び率はそれぞれ23%、35%にもなり、まさに成長段階にあるといえる。
B社は大手の百貨店で、順調に成長を続けている。売上高は1988年度は対前年度比で10%伸び、業界の中での順位、特に、主力店舗の順位が上昇している。自ら中核をなす企業グループの事業領域の拡大もめざましい。
C社は生命保険会社であり、業界で業績の指標として用いられる総資産、収入保険料については、1988年度は対前年度比でそれぞれ36%、51%も伸び、外勤職員も順調に増えている。企業規模、外勤職員数を2倍にしようという1987年度にスタートした5ヶ年計画の最中のこともあり、高成長を続けている。
D社は大手の総合不動産業者で、1988年度の売上高、営業利益は対前年度比でそれぞれ19%、22%伸び、13期連続の増益を記録している。事業領域も拡大を続け、子会社展開の形で、ホテル、ショッピング・センター、レジャー、リゾート事業にも積極的に取り組んでいる。
E社は鉄道会社で、公益事業であるために、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。ただし、E社に限っていえば、規制の自由化の可能性があるために、近い将来の事業領域拡大の期待が高まっている。
F社は電気通信業者で、やはり公益事業であるために、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。今回の調査対象はソフトウェアの技術部門。
G社は外資系の石油輸入・精製業者で、ガソリン中心の生産体制が、重油・灯油価格抑制政策の下で有利に作用して、業界他社が業績不振の時も高業績を維持し続け、最近10年間の平均経常利益は約500億円と高水準で安定している。
H社は食品を主としたメーカーであるが、主力となっている乳製品が売上高、利益とも安定しているために、安定期にあると考えられる。
I社は農業機械の大手寡占メーカーの一つであるが、主力機種の普及率向上と、減反政策等による市場規模縮小のために、シェアは維持しているものの売上高は減少し、営業利益は改善中ながら、調査時点ではまだ赤字になっている。
J社はもともと海上土木工事中心の建設業者だったが、国内港湾整備の進行と官公庁の財政難や公害反対運動などで、海上土木工事が伸び悩んだために、陸上土木や建築工事へ進出して、総合建設業への脱皮をめざしている。建築工事は施工量が急速に増えている割には利益が薄く、部門による差異はあるものの、全体としてはまだ低迷期から完全に脱しきれているとはいえない。
以上のようなヒアリング調査の結果を、従業員の意識のレベルでも確認するために、第2段階の質問票調査では、成長期、安定期、低迷期という3グループをそのまま選択肢として、「あなたの会社の現状は次のどれに該当すると思いますか?」という質問を作成して、直接的にきいてみた。その結果、各社において過半数を占める選択肢は、ヒアリング調査の結果と一致している。ただし、J社は、過半数を占める選択肢がなく、意見が三分された状態にあったが、これは部門による違いをそのまま反映したものと考えられる。
そこで、いよいよ仮説5.3の検証に入る。ぬるま湯感については質問Q5.1:「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」を用いた。活性化については、
というYes-No形式の質問でより直接的にきいてみた(この質問の妥当性については河合・高橋(1992)を参照のこと)。この質問Q5.3に対するYes比率を「活性化比率」と定義する。各社ごとに、ぬるま湯比率と活性化比率をみてみよう。その結果は図5.7に示されるが、明らかに、成長期の企業は活性化比率が高く、ぬるま湯比率が低い。さらに、低迷期にある企業2社は、その逆となっている。成長期の4社、安定期の4社、低迷期の2社はそれぞれグループをなしていて、G社を除くと、R2=0.8575 (G社を含めたままだと R2=0.6121)とほぼ線型の関係が見いだされる。この図は仮説5.3を支持している。
図5.7 活性化比率とぬるま湯比率(JPC89調査)
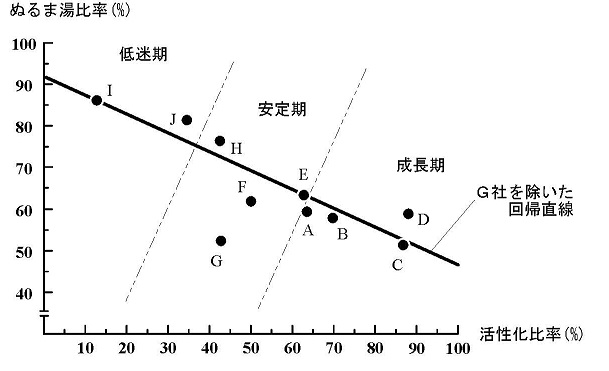
注)ぬるま湯比率を被説明変数とする回帰分析(G社を除く)
| 変数 | 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 |
|---|---|---|---|---|
| 体感温度 | -0.4535 | 0.070 | -6.490 | p <0.001 |
| 定数 | 91.9241 | 4.268 | 21.539 | p <0.001 |
さらに、ぬるま湯感と活性化との間には表5.6のクロス表に示されるような負の相関関係があり、これは0.1%水準で有意となっている。仮説5.3は、こうした相関関係が、表面的、間接的なものであり、成長性という先行変数があるための見かけ上の疑似相関であると主張しているのである。
表5.6 活性化とぬるま湯感の関係(JPC89調査)
| Q5.3 会社は 活性化して いると思う。 | Q5.1 職場の雰囲気を「ぬるま 湯」だと感じることがある。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 385 | 313 | 698 |
| No | 380 | 123 | 503 |
| 計 | 765 | 436 | 1,201 |
そこで実際に、各社ごとにぬるま湯感と活性化の相関関係をみるために3重クロス表を作ってみよう。表5.7はその3重クロス表を示している。このクロス表によると、10社のうち、A社、F社、H社の3社については、ぬるま湯感と活性化との間に有意な相関関係がみられたが、他の7社については、10%水準でも有意な相関関係は見いだせなかった。特に、C社、G社、I社、J社については、ほとんど無相関といってもよい。このことから、仮説5.3はほぼ検証されたといっていいだろう。つまり、表5.6は「活性化→ぬるま湯感」または「活性化←ぬるま湯感」という関係があるように見えるが、しかし、表5.7によれば、実はこれは大部分が成長性という先行変数があるための疑似相関であって、「活性化←成長性→ぬるま湯感」という関係があるのだということになる。したがって、成長期の企業は活性化していて低ぬるま湯感、低迷期の企業は活性化していなくて高ぬるま湯感という特徴を持ち、全体として総計すると、見かけ上、活性化とぬるま湯感の間に相関関係がみられると考えられるのである[32]。
表5.7 会社別・活性化別のぬるま湯比率(%)(JPC89調査)
| ヒアリング による分類 | Q5.3 会社は活性化していると思う。 | 相関係数 Cramer's V | χ2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yes群 | No群 | ||||
| 成長期 | A社 | 51.46 (103) | 72.88 (59) | -0.210 | 7.132** |
| B社 | 54.00 ( 50) | 66.67 (21) | -0.117 | 0.972 | |
| C社 | 52.29 (153) | 45.83 (24) | 0.044 | 0.346 | |
| D社 | 56.31 (103) | 78.57 (14) | -0.147 | 2.524 | |
| 安定期 | E社 | 58.75 ( 80) | 70.83 (48) | -0.121 | 1.885 |
| F社 | 46.77 ( 62) | 76.19 (63) | -0.302 | 1.431** | |
| G社 | 51.22 ( 41) | 52.63 (57) | -0.014 | 0.019 | |
| H社 | 56.90 ( 58) | 89.87 (79) | -0.381 | 9.891*** | |
| 低迷期 | I社 | 77.78 ( 9) | 87.50 (64) | -0.093 | 0.631 |
| J社 | 76.92 ( 39) | 83.78 (74) | -0.084 | 0.795 | |
疑似相関であるから、ぬるま湯感と活性化との間には、直接の因果関係は存在せず、ぬるま湯感を人為的に変化させても、直接的には活性化に変化は生じないはずである。そのことは実際にも確かめることができ、その良い例がG社である。G社は、1989年に社名を変更して、CIの真っ最中であり、その数年前から、実力主義による賃金、処遇の決定、新部門の設置や合理化の推進に伴う本社及び事業所の既存組織の改組などの組織の積極的な改革、改訂、そして、広報機能の充実による企業イメージの向上といった様々な経営施策の展開、実施を行っている。そのために、システム温が上昇して、ぬるま湯感が低下しているが、活性化については、今までのところ変化していない。そのことは図5.7によってはっきり示されている。安定期に分類されたG社は、回帰直線からは明らかにはずれている。つまり、活性化については確かに安定期の水準にあるが、ぬるま湯感については成長期の企業と同水準になっているのである。したがって、他社の傾向と比較して、G社は活性化についてはあまり変わらずに、ぬるま湯感だけが低下したことになる。以上の分析から、仮説5.3は検証された。
これまでは、個々の企業や産業レベルの成長性を考えてきたが、日本経済全体の成長性も、実は同じ様な効果をもたらすことになる。こうしたことは、不況時にぬるま湯比率が上昇するという事実によっても裏付けられる。不況時にぬるま湯感が強くなるという傾向は、世間一般の常識には反していると思われるが、確かな事実であり、しかも、この事実は体感温度仮説によって説明できる。図5.8はバブル不況の1992年のぬるま湯比率が、なんと74.1%にまで上昇していることと、その時に体感温度が急激に落ち込んでいることを示している。同様の傾向は、景気失速のデフレといわれた1995年にも見られ、このときのぬるま湯比率は、実に75.3%に達している[33]。
図5.8 ぬるま湯比率の推移と体感温度(JPC90〜JPC96調査)
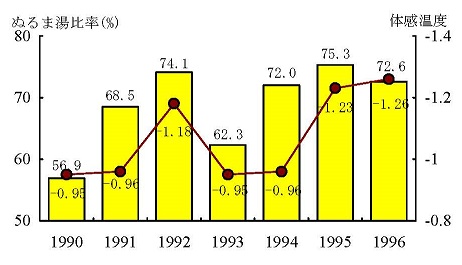
図5.9を見ると、この落ち込みは、システム温の落ち込みが原因であることがわかる。実は、こうした成長性とぬるま湯感の連動、すなわちシステム温とぬるま湯感の連動は、ある前提が成り立って初めて成立するものである。その前提とは、体温の恒常性である。これまでの調査データからすると、生物としての人間と同様に、組織人としての人間の体温にも恒温性があると考えた方が理解がしやすい。これは、個人の変化性向である体温が、個人にとってはパーソナリティーに近いものであることを暗示している。このことはやや意外な感じを受けるかもしれないが、高橋(1993a, ch.5)でより詳細に取り扱われている。既に第4章で取り上げたアトキンソン型の動機づけモデルでも、変化性向と考えられる Ms−MfM/sub> は個人ごとに定まる定数であり、パーソナリティー的特性を表すものとして扱われていた。
図5.9 体感温度の推移とシステム温・体温(JPC90〜JPC96調査)
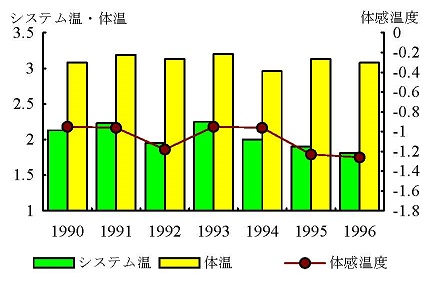
この恒温性を直接的に検証できるようなデータを示すことはまだできないが、第4.1項で取り上げたG社のように、CIによっても体温は変わらず、システム温だけが変化していたと考えられる事例や、ここで示したように、不況時に体温は変わらず、システム温だけが低下してぬるま湯感が強くなるというデータは存在している。さらに、ここで扱っている調査とは別個のものであるが、CIをはさんで1989年と1991年に標本調査を行ない、3年間にシステム温は顕著に上昇したが、体温は全くといっていいほど変わらなかったという調査データも化粧品、トイレタリー関係の企業から筆者のもとに寄せられている。したがって、心証としてはこの体温には恒温性があると思われるのである。
これまでの一連の調査を通して、システム温と体温の温度差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、それを検証することによって、ぬるま湯現象なるものをかなり解明できたと考えている。体感温度測定尺度の改良によって、ぬるま湯と感じるかどうかは、システム温と体温でほぼ予測可能になったといえるだろう。そこで、体温を縦軸、システム温を横軸にとった図5.10のような図を考えてみることにしよう。この図は「湯かげん図」と呼ばれるが、体温、システム温の平均を破線で入れ、便宜上、右上の領域を「適温」領域、左下の領域を「水風呂」領域と呼んでいる。
図5.10 湯かげん図(破線はJPC90〜JPC96調査の平均)
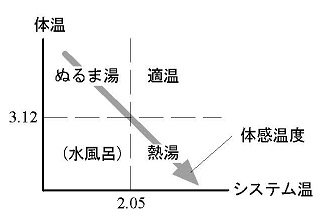
図5.10において重要なことは、本来、活性化していると呼ぶべき状態は適温の状態であり、一方、本来、活性化していないと呼ぶべき状態は水風呂の状態であり、ぬるま湯の領域はどちらとも異なるということである。つまり、調査データの分析過程で疑問を感じた通り、やはり、ぬるま湯の状態は不活性状態の典型というわけではなかったことになる。
そして、近藤(1992)が指摘するように、システム温が低いのに体温が高いぬるま湯の状態とは、外的報酬によって動機づけられる機会がないにもかかわらず、組織に対して貢献している状態である。つまり、ぬるま湯の現象とは、ブルーム型のモデルでは説明のつかない現象なのである。しかも、その貢献の内容は、現状を打破しようとするまさにチャレンジであり、アトキンソン型の内発的動機づけの内容と合致している。言い換えれば、ぬるま湯の現象が日本企業で多く観察されるということは、まぎれもなく、日本企業に勤める多くの従業員が、少なくとも動機づけの場面においては、期待効用原理の世界ではなく、未来傾斜原理の世界に住んでいるということを示しているのである。
そしてもう一つ、体感温度仮説が正しければ、組織や職場の状態をぬるま湯感や体感温度だけで判断することは危険だということもわかる。なぜなら、同じ水準の体感温度をもたらすシステム温と体温の組は一意には定まらず、システム温、体温が共に高くても、共に低くても、同じ体感温度になりうるからである。図5.10で考えれば、例えば、図の右上隅も左下隅も体感温度では0になり、差がないことになる。しかし、この両者の違いは重要かつ重大である。右上隅が組織のシステムも人も変化性向が大きく、システム・人が一体となって変化することを指向した組織であるのに対して、左下隅は組織のシステムも人も変化性向が小さく、組織のシステムが現状に甘んじることを肯定しているだけではなく、そのメンバーも現状に甘んじることが体に染み着いているために、そうしたシステムの状況に気が付いていないという危険な状態にあると考えられる。
このことは、組織や職場の状態を、その中にいるメンバーの「感じ」だけで判断してしまうことの危険性を示唆しているだけだが、さらに想像をたくましくすることもできる。例えて言えば、適温だ、いい湯だと思って風呂に長々と浸かっていると、湯の温度(システム温)は自然に下がっていってしまう。ところが、本人の体温もそれにつれて低下しているため、そのことに気付かず、いつしか平気で水風呂の中につかり、そのうち風邪をひいてしまうということが、十分に考えられるのである。これと類似のことが、1980年代前半の米国の鉄鋼、自動車などの産業が苦境に立たされた原因として「ゆでガエル現象」(boiled frog phenomenon)として指摘されている(Tichy & Devanna, 1986)。この現象はもともとがカエルが主役の古典的な生理学的反応実験のアナロジーなので、温度の高低の設定は逆になっているが、カエルを突然熱湯に入れると、カエルはすぐに飛び出すが、カエルを冷水の鍋の中に入れて、ゆっくりと熱を加えていけば、温度の変化がゆっくりなので、カエルは熱湯になっていっていることに気付かず、飛び出すことなく、鍋の中でゆで上がって死んでしまうという現象を指している。
しかし、本当にそうだろうか? 確かに図5.5のように、企業をプロットすると、企業レベルではシステム温と体温の間に正の相関があり、システム温の高い企業は体温も高いことがわかる[34]。
それでは、強くはないが、正の相関があったということは、システム温を上げれば体温も上がる、あるいは、システム温を下げれば体温も下がるということを意味しているのだろうか? 実はこの正の相関には二つの可能性が考えられる。
風呂のアナロジーで考えても「ゆでガエル現象」で考えても一見もっともらしい1のケースについては、実はいままでのところ何の証拠もない。むしろ、既に述べたように、体温には恒温性があると考えられる。2のケースについては、「熱湯」領域では、人の出入りが激しく、離職率も高いというケースが、ヒアリング調査の中では頻繁に聞かれる。そして、前章でも取り上げたCALUTE92調査では、データ的にも裏付けが取れた。どうも現時点では②のケースの方がもっともらしいと考えられる。
CALUTE92調査では、1992年11月に産業機器の大手メーカーI社の従業員の全数調査を行った際に、改良版の体感温度測定尺度を使ってデータが集められた。I社のぬるま湯比率は60.3%で、体温、システム温とともに、ほぼ平均的な水準にあった。そこで、年齢別にみてみると、まずぬるま湯比率は15〜24歳の若年層で低くなっており、特に、15〜19歳では32.4%と、全体のぬるま湯比率の半分になっている。これは図5.11の湯かげん図からも明らかなように、若年層が低体温の割には高システム温の熱湯の状態にさらされているためである。特に15〜19歳ではそのギャップは大きい。入社当初の会社や仕事に慣れるまでの一時的な現象かもしれないと思われたが、従業員のインタビュー調査などによって調べてみると、I社では、入社後3年は「I学校」と称し、徹底的に仕込むとともに、我慢するように指導しているということがわかった。入社後2〜3年で仕事に慣れるか辞めるかという見極めがつき、高卒、大卒を問わず、20歳代前半までに、合わない人は辞めていき、残った人は仕事にのめり込むようになっていくという。同期入社した者は入社5年でほぼ半減するといい、この間の推定年間離職率は12〜13%程度とみられる。体温については25歳以上になると安定しているところをみると、若年層の相対的低体温がこの間に解消されるのは、個々人の体温が上昇するというよりは、高システム温に耐えられない低体温の人が抜けていくことによって、平均としての体温が上昇するのだと考えた方が合理的だと思われる。
図5.11 産業機器メーカーIの全従業員(2128人)の年齢別湯かげん図(CALUTE92調査)
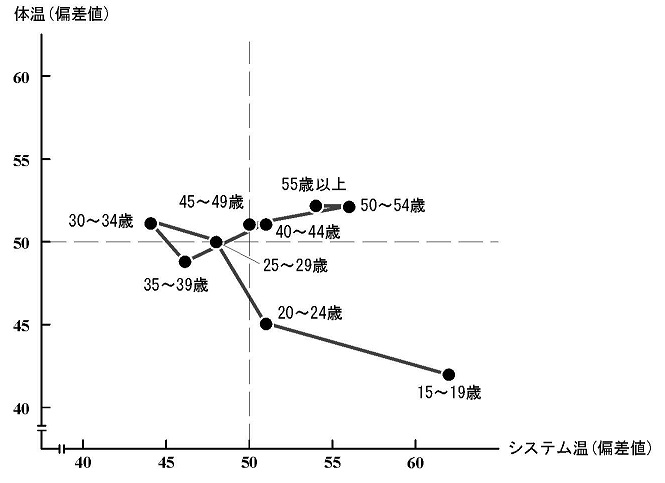
注) ぬるま湯比率60.3%, 満足比率39.8%, 入社後5年の推定年間離職率12〜13%。
実は、一連のJPC調査では、ホワイトカラーを対象としており、実質的に、本社の20歳以上の大卒・短大卒の従業員の調査となってしまっていた。そのために、こうした現象を観察することが出来なかったのである。この産業機器大手メーカーI社の事例は、こうした2のような淘汰のプロセスを組み入れた進化論的な解釈を要求される事例だと考えられる。こうした現象と協調行動の進化モデルとの関係については、近藤(1992)も指摘している。
それでは、システム温が下がったら、どうなるのだろうか? もし、外的報酬で動機づけられているのであれば、システム温が下がった途端に、働く意欲も失うことになるだろう。しかし、体温が高く内発的に動機づけられてチャレンジしていくような人間は、システム温が下がったからといって、すぐに意欲を失う理由にはならない。事実、JPC90〜JPC96調査の合併データでは、体温と自己決定度の相関係数は 0.445 (p <0.001; N=6,137)で、システム温と自己決定度の相関係数 0.263 (p <0.001; N=6,122)と比べて、高い相関を示している。つまり、システム温にかかわらず、体温の高い人は自己決定度も高く、満足を感じる可能性も高いことになる。しかも、体温には恒温性もありそうだ。システム温に影響されて辞めることもないだろう。だからこそ、企業の中にそういった人間が存在できることになり、ぬるま湯感が発生するのである。
その意味では、ぬるま湯現象は不活性状態の典型ではなかったし、そのこと自体が悪い現象というわけでもない。単に、メンバーが内発的動機づけと未来傾斜原理の世界に生きているということの現れと見ることもできる。しかし、第2章で見たような、見通し指数とパーソナリティーとしての未来傾斜指数との間の長期的に連動する関係は、システム温と体温の間にも成り立つのである。いま仮に、低システム温の状態が長く続くことを考えてみよう。そうなると、それには耐えられる低体温の人間が採用等で入って居残っていくことになり、企業レベルでの体温の平均は低下していくに違いない。そのことは長期で考えると「ぬるま湯感」の解消につながるが、それはむしろ組織状態の悪化ととらえるべきだろう。したがって、ぬるま湯感は、短期的にはどうのこうのというわけではないが、システム温が低下してきているという意味での危険信号、シグナルにはなっていると受け取るべきなのである。
[29] 岩波書店の広辞苑(1983)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす。」とされている。さらに、小学館の国語大辞典(1981)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。ぬるみ。びおんとう。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「安楽な現状に甘んじて呑気に過ごす。」とされている。
[30] このシステム温と後述する体温についての多変量解析を使った吟味については、高橋(1993, ch.1)を参照のこと。第3節で後述する改良版尺度開発時の吟味と同様の分析が行われている。
[31] 組織の活性化についてはここではこれ以上詳述しない。詳しくは高橋(1987b; 1989b)やTakahashi (1992a)を参照されたい。なおここで示された組織の活性化された状態の定義は、一般に「活性化」についてもたれているイメージと重なるものであることが調査結果からわかっている(河合・高橋, 1992; 高橋, 1993a, ch.2)。後述する質問Q5.3はその際に用いられたものである。また組織活性化とその周辺については、高橋(1995b, ch.5)に解説がある。
[32] このように、ぬるま湯感と活性化という2変数に対して、成長性という第3の変数を導入して分析することは、エラボレイションと呼ばれる。ここでは、仮説5.3から成長性を先行変数として導入し、ぬるま湯感と活性化の疑似相関を説明するので、特にエクスプラネイションとも呼ばれる(安田・海野, 1977)。
[33] こうした傾向を、同じように企業に対して業況感等を調査しているビジネス・サーベイ・ データとの関係でもおさえておこう。まず、日本銀行調査統計局が出している『短観』(企業短期経済観測調査結果報告)の業況判断DIの推移を見てみると、「主要企業」「中小企業」ともに、1991年から1992年にかけてプラスからマイナスに大幅に落ち込み、1993年には底を打つ。その後は回復傾向にあり、1996年末には「主要企業」の判断DIはようやくゼロ付近まで回復するのであるが、1994年後半から1995年にかけて「中小企業」では一旦また落ち込んでいる。しかしその落差は1991年から1992年にかけての落差の大きさに比べればかなり小さい。このように、落差の大きさはともかく、判断DIの上下動とぬるま湯比率の上下動とはほぼ一致しているように見える。しかし経済企画庁調査局の出している『法人企業動向調査報告』のBSI (Business Survey Index)については、国内景気、業界景気とも、1992年に大幅に落ち込むところまではほぼ同じだか、1994年からは大幅に増加して1995年にはプラスに転じており、ぬるま湯比率の変動とは一致しない。今期の状態が「良い」か「悪い」かを指標化している日銀の判断DIの動きは景気の動きとほぼ一致するが、BSIは前期に対する変化を指標化しているので景気動向指数のDIと同様に変化するといわれる(中村他, 1992, ch.8)。その意味では、ぬるま湯感は景気動向というより景気の状態と連動しているといってよさそうだ。
[34] このことは重要なことである。つまり、システム温は客観的に測定されたものではなく、ある体温をもった各メンバーによって主観的に測定されたものであるために、仮に、システム温の段階で、体温が既に引かれてしまっていて、体温が織り込み済みとなっていれば、システム温が疑似体感温度となっている可能性があったからである。もしそうならば、体感温度がそうであったように、システム温も体温が高いほど低下するという負の相関が見られるはずであったが、実際には企業単位でみるとシステム温と体温とは正の相関があったわけで、事実、さらに個人単位でも、JPC90〜JPC96調査の合併データ(N=6,145)で、システム温と体温の相関係数を求めると 0.114 と弱いものの正の相関があったことから(N が大きいので、p <0.001)、こうした可能性が否定され、システム温が疑似体感温度となってはいないことが確認されたことになる。
近代組織論は、1940年代から1950年代にかけて、組織メンバーの限定された合理性が、組織の意思決定過程の中でどのように克服されていくのかを解明することを基本的テーマとして発展を遂げた。そこには、ゲーム理論や決定理論の強い影響が見られるが、近代組織論では、ゲーム理論や決定理論のように決定問題を解くことではなく、組織的状況の中でいかに決定問題が形成されるのかということに関心がある。そしてそのとき組織は、限定された合理性にとって手頃な大きさに因数分解された決定問題をそれぞれ抱えた意思決定過程の連鎖としてとらえられる[35]。
こうした近代組織論の考え方を簡潔にまとめると、
ということになる。しかし、人間は合理性に閉じこもって生きているわけではないし、また生きられるわけでもない。この本がテーマにしているように、組織の中にあってさえ、大きな問題にぶつかって立ち往生したり、チャレンジしたりを繰り返していく。
実際、1970年代に入ると、素朴な意思決定論には馴染まない現実の意思決定状況を説明するための分析枠組みとして、この章で取り扱うことになるゴミ箱モデルが提唱されることになる。そこでこの章では、原点に立ち返り、組織の中の決定問題を近代組織論的に考察するところから始めて、その流れの中にゴミ箱モデルを位置付け、構造的制約がない未分割版と呼ばれる簡明なコンピュータ・シミュレーション用のプログラムを使って、シミュレーションを行ない、ゴミ箱モデルの結論を再検討する。さらに、日本企業における実態調査をもとに、シミュレーションの結論を検証するとともに、日常の組織的行動の中でゴミ箱モデル的な現象がごく普通に発生していることを確認する。30歳代の課長クラスにゴミ箱モデル的な現象が頻繁に発生しているという事実が、実は未来傾斜原理の発露であるということは、続く二つの章で明らかにされる。
第4章で考察したような個人の決定問題を想像するとわかりやすいが、いまいくつかの可能な代替的行動の案があり、そのそれぞれの行動によって引き起こされる結果がわかっていて、それらの結果を評価しうるようなある価値体系があるとしよう。このとき、その価値体系によって、望ましい代替的行動を選択するとき、「合理的」選択と呼ばれる(Simon, 1976, p.75 邦訳p.96)。
ところで、実際には、人間が一人でポツンと孤立して意思決定している例は存在しないのであり、人間は常に何らかの意味で組織に属して意思決定を行なっている。それでは、なぜ人間は組織を作って、その中で意思決定を行なっているのだろうか。その答えは、一般に、人間の「限定された合理性」(bounded rationality)に求められる。人は全知全能で無限定に合理的な存在というわけではないが、だからといって本質的に不合理でハチャメチャな存在でもない。限られた範囲内の問題であれば合理的な選択を行なうことができる。そこで、何らかの装置を使って、問題のサイズを小さくすることで、限定された合理性のサイズに合わせ、何とか合理的な選択を行なうようにすることができるはずである。こうした装置の代表的なものが組織なのである。
例えば、そもそも期待効用原理は無限定に、誰にでもいつでも適用可能なものではない。より具体的に言えば、ある一組の仮定を満たして意思決定が行なわれるときに初めて、くじの効用関数が存在し、それが賞金の期待効用の形になることを証明することが可能になるのである。それは第4章で明らかにした通りである。また主観確率も、それにさらにいくつかの追加的仮定を満たしたとき、はじめて存在が証明できる(Anscombe & Aumann, 1963; 高橋, 1993c, ch.3)。これら一連の仮定を要件として満たしたときに、はじめて一般の意思決定に期待効用原理が適用可能になるのである。
こうした仮定は、一つ一つを個別に見れば、それぞれに納得のできるものではあるが、これらすべての仮定を常時満たしていることは、われわれ現実の生身の人間にとっては容易なことではない。その意味では、このリスクのケースだけを考えてみても、決定理論においては、現実の生身の人間よりは、かなり条件の整った「人間」が想定されていると考えなくてはいけない。実は、それほどまでに条件を整えることは組織の中においてのみ可能になるのである。しかし、実際には、これまで決定理論や古典的な経済学においては、組織の存在を仮定せずに、孤立した人間のものとして「合理的」選択のモデルが作られてきた。そのため、全知的に合理的な人間モデルを想定せざるをえなくなってしまったのである。これは経済人(economic man)モデルと呼ばれ、より具体的には次のような特徴をもつ人間モデルを指している(Simon, 1957, pp.xxv-xxvi 邦文序文pp.22-23; March & Simon, 1958, p.140 邦訳pp.213-214)。
しかし、自分の行動を振り返ってみてもわかるように(例えば、高橋(1993c, pp.63-65)では、賃貸の住居を探す例を挙げている)、少なくとも、実際の人間の行動は全知的・客観的合理性に次の3点で遠く及ばないということは容易に指摘しうる(Simon, 1947, p.81; March & Simon, 1958, p.138 邦訳p.210)。
実は、実際にわれわれが問題を設定し、解くことができるのは、代替案の数がごく限られているか、あるいは、各代替案の結果やその価値、効用が簡単な形をしているものばかりなのである。明らかに、われわれには、経済人モデルが求めるような高度な問題解決能力は備わっていないし、利用可能な労力や時間にも制約がある。経済人が相手をしている問題のサイズに比べたら、人間の頭脳の能力は、はるかに小さなものにすぎないのである。
そこでサイモンが考え出したのが「経営人」(administrative man)の人間モデルである。経営人モデルは、経済人モデルと対比させると、次のような特徴をもっている(Simon, 1957, pp.xxv-xxvi 邦訳序文pp.22-23; March & Simon, 1958, p.140 邦訳pp.213-214)。
これまでの議論から、限定された合理性を考慮に入れると、経営人たる人間が、たとえなんらかの意味で合理的に意思決定できるとしても、それは人間にとってかなりお膳立ての整えられたような状況下に限られてくることが明らかになった。前項、第2.1項の合理性の限界についての指摘を逆手にとれば、次のような状況の特性が、意思決定に先立ってあらかじめ定められ、与えられているときにのみ、人間は合理的に意思決定できるにすぎないということがわかる。
つまり第4章の決定問題でいうところの (1)意思決定者の行動の集合、(2)行動によって引き起こされる結果、(3)結果の利得関数、である。リスクのケースではさらに、(4)将来起こりうる事象またはその事象の生起する確率分布についての知識もしくは仮定、も必要となってくるだろう。
この四つの状況の特性があらかじめ定められ、与えられているときにのみ、人間は合理的に行動できる(March & Simon, 1958, pp.150-151 邦訳pp.230-231)。ということは、仮に合理的意思決定者がいるとすると、その合理的意思決定者の直面している状況のこの四つの特性は、何らかのプロセスを通して、意思決定の瞬間までには、あらかじめ記述されるにちがいないということになる。そして、こうした認識から、次の二つの基本的性格を組み込んだ「合理的選択の理論」(theory of rational choice)が示される(March & Simon, 1958, pp.139-140 邦訳pp.211-213)。
この理論では、人間が組織の中に身を置くことによって、組織の中での心理学的・社会学的過程による濾過作用を受けることを肯定的に扱っている。つまり、組織は、その中に身を置く人間が直面している現実の状況にふるいをかけ、歪みを加えながら単純化を行うという濾過作用を果たす点でまさに重要なのであり(March & Simon, 1958, pp.154-155 邦訳p.236)、この状況定義が存在することによって、合理性に限界のある人間が、はじめて合理的に意思決定をすることができるのである。
ここでいう状況定義の一例としては、ヘイウッド(O. G. Haywood, Jr., 1954)が取り上げた「状況評価」(estimate of the situation)がわかりやすい。ヘイウッドは第二次世界大戦中のビスマルク海戦(Battle of the Bismarck Sea)をゲーム理論的に定式化したが、これは各種のゲーム理論のテキストでも取り上げられ、有名になった。1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争の日米開戦から、日本は東南アジア、西太平洋の広大な地域を手にしたが、翌年6月にはミッドウェー海戦で米国に敗北し、1943年1月にはガダルカナル島での消耗戦にも敗退する。そこで、連合軍の本格的反攻に備え、ニューギニア島東岸のラエ、サラモアの支援増強のため、ニューギニア島東隣のニューブリテン島にある海軍の拠点航空基地ラバウルから輸送部隊を送ることになった。このラバウルからラエへの日本軍の輸送部隊とニューギニア島南部の連合軍の航空部隊との間で、1943年(昭和18年)3月に起きた戦闘がビスマルク海戦である。
ヘイウッドの論文(Haywood, 1954)での主人公は、南西太平洋地域の連合空軍の司令官、ケネー将軍(G. C. Kenney)である。ニューギニアをめぐる戦闘は、1943年2月には重大な局面を迎えていた。諜報機関の報告では日本の軍隊と補給船団がラバウル(図6.1のニューブリテン島の北東端)に集結中であった。目的地はラエと予想された。
図6.1 ラバウル=ラエ輸送作戦
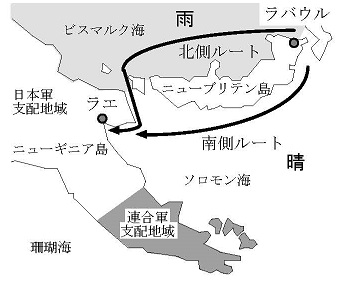
(出所) Haywood (1954, Fig. 1).
こうした状況下でのケネー司令官の決定のプロセスは、統合参謀本部によって認められた状況評価と呼ばれる5段階の分析に則って定式化される。これは、すべての軍人学校でも教えられていたものだというが、ケネー司令官は5段階状況評価を次のように進めた。
表6.1 予想される戦闘結果
| 連合軍の戦略 | 日本軍の戦略 | |
| 北側ルートで輸送 | 南側ルートで輸送 | |
| 北側ルートを 集中的に偵察 |
視界不良だが 偵察機の大量投入で 2日目には発見し 2日間の爆撃 |
晴天だが 偵察機が手薄で 2日目になって発見し 2日間の爆撃 |
| 南側ルートを 集中的に偵察 |
視界不良の上 偵察機が手薄で 3日目の朝以後に発見し 1日間の爆撃 |
晴天の上 偵察機の大量投入で 1日目に発見し 3日間の爆撃 |
こうして「北側ルートを集中的に偵察」の選択が行われ、日本軍の司令官は「北側ルートで輸送」を選択して、歴史上、ビスマルク海戦として知られる衝突となる。戦闘の結果がどうなったかについては、高橋(1995b, ch.7)、松原(1985, ch.3.2)に詳しいが、日本軍の全輸送船7隻が沈没または炎上して、連合軍側の勝利で海戦は終結する。
具体的には、他にも色々な形のものがあるだろうが、こうした「状況評価」のようなモデルがあってはじめて、経営人たる人間に合理的意思決定が可能になる。「状況評価」が軍人学校で教えられ、軍隊組織において機能するように、経営人は、組織に所属することによって、その中でのプロセスを通して、状況定義を獲得し、組織の中で機能させるのである[37]。
バーナード(Chester I. Barnard)の『経営者の役割』(The Functions of the Executive, 1938)によって創始された近代組織論(modern organization theory)は、さらにサイモン(Herbert A. Simon)の『経営行動』(Administrative Behavior, 1947)、およびマーチ(James G. March)とサイモンの『オーガニゼーションズ』(Organizations, 1958)によって精緻化された。バーナードとサイモン、マーチとの間には主張にやや隔たりがあるが、後者を中心にして考えれば、組織メンバーの限定された合理性が、組織の意思決定過程の中でどのように克服されていくのかという観点から組織現象を説明するための概念体系と理論的枠組みを確立した。限定された合理性しかもたない人間が、「合理的」に意思決定をしうるための装置として組織をとらえ、そのために組織がどのような機能を果たしているのかを明らかにしようというのである。
例えば、まず、状況定義の諸要素自体が組織の中での心理学的・社会学的過程の結果なので、人間の選択について、全体として長々とした過程の最後の瞬間の「決定」にだけ注意を向けるのではなく、それに先行する探索、分析等を含めた複雑な過程の全体に注意を向けることが必要となってくる(cf. Simon, 1977, p.40 邦訳p.54)。こうした理由から、近代組織論では、組織の分析・考察に当っては、分析の最小単位を意思決定(decision)にではなく、そこに至るまでに登場する意思決定前提(premise)に置くことになる。言い換えれば、意思決定を「諸前提から結論を引き出す過程」(Simon, 1976, p.xii 邦訳序文p.8)として扱うことにするのである。
こうして、近代組織論では状況定義を所与として分析を始めるのではなく、組織の中で状況定義がどのように形成されてくるのかということ自体に重大な関心を払うのである。状況定義の形成プロセスの分析をすることで、行動の予測も可能になる。例えば、サイモンによれば、販売部長、生産計画部長、工場長、製品デザイン担当技師の4人の架空の会話を設定すると、
などと予想することは容易であるという(Simon, 1976, pp.xviii-xix 邦訳序文p.17)。なぜなら、彼らは特定の組織的ポジションにあり、特定の種類のコミュニケーション、特定の部門目標、かつ特定の種類の圧力を経験しているからである。つまり、特定の状況定義に基づいて意思決定を行なっていることになる。したがって、さまざまな組織の中で、さまざまなパーソナリティーをもった人がそれぞれのポストについていながら、その状況定義についてはある程度特定が可能なので、彼らの行動についても大まかに予測することがある程度可能なのである。
ホール(Edward T. Hall)は、人間が自分自身と現実との間にスクリーンを設けることで、現実を構造化しているので、行動を曲がりなりにも合理的にコントロールしようとすると、その構造を知る必要があるとしているが(Hall, 1976, p.102 邦訳pp.119-120)、まさに、近代組織論のこうした議論はそのことを精緻に議論したものである。ホールによれば、人間と現実の間にスクリーンを設けることが文化の機能であるとされるが(Hall, 1976, p.85 邦訳p.102)、それは組織に所属することによって可能となるのだというのが、近代組織論の主張なのである。
本書ではこれ以上立ち入らないが、近代組織論の登場により、経営者の役割は組織を形成し、維持することだという観点から、経営学の分野において経営の管理論と組織論とが一体として論じられるようになった。その後、サイアート(Richard M. Cyert)とマーチの『企業の行動理論』(A Behavioral Theory of the Firm, 1963)は、近代組織論をもとにして、企業の行動理論を確立することを企図したが、論文集的な性格が強く、それ以降の発展もあまりみられない。そこで、この段階までの近代組織論の考え方の全体像を結論的にまとめておくと、次のようになる(高橋, 1993c)。
しかし、人間は合理性に閉じこもって生きているわけではないし、また生きられるわけでもない。この本がテーマにしているように、組織の中にあってさえ、大きな問題にぶつかって立ち往生したり、チャレンジしたりを繰り返していく。実際、マーチはその後、1970年代に入って、素朴な意思決定論には馴染まない現実の意思決定状況を説明するための分析枠組みとしてゴミ箱モデルを、コーエン(Michael D. Cohen)、オルセン(Johan P. Olsen)とともに提唱することになる(Cohen, March & Olsen, 1972)。
ゴミ箱モデル(garbage can model)は、組織的意思決定論の学説史の中では、決定理論の影響を強く受けている初期の理論の延長線上にあるものとして位置づけられている(March & Olsen, 1986)。決定理論に従えば、意思決定はあまりにも時間と情報を要求しすぎ、それは合理性に限界のある人間にはとうてい処理できないほどの過大な要求となる。そこで、近代組織論では、組織メンバーの限定された合理性が、組織の意思決定過程の中でどのように克服されていくのかを解明してみせたわけだが、しかし、それでもまだ理論と現実との乖離が埋められたわけではなかった。数学の試験問題を解くようにして問題解決が行われることは希なのである(Cohen, March & Olsen, 1972)。
例えば、問題のある選好、不明確な技術、そして流動的参加によって特徴づけられた組織化された無政府状態(organized anarchies)である。実際、人間の選択、行動が、効用関数のようなものの存在と矛盾することがあることも従来から指摘されているし、また、ある選択肢が、ある特定の結果をもたらすという比較的もっともらしい前提も、技術が不確実であいまいなままの状況下では非常に疑わしい。特に技術革新著しい現代においては、むしろ選択肢がどのような結果をもたらすか、やってみるまで、あるいは、やってみて改良、改善努力を行うまでわからないという状況の方が常態なのかもしれない。そして、意思決定、特にルーチンではない非定型の意思決定に誰が参加するのか、あるいは結果として誰の意見が入ってくるのかという点に関しても、参加者は確定的な組織メンバーにとどまらないし、かなり流動的な側面が強いのも事実である。
このような組織化された無政府状態は、大学の経営・行政において特に顕著であり、大学についての経験的観察研究によれば、そうした組織では、参加者によって、様々な種類の問題と解が勝手に作り出されては、「選択機会」に投げ入れられている。自らが示されるべき選択機会を捜し求めている「問題」、自らがその答えになるかも知れない問題を捜し求めている「解」、そして、仕事を捜し求めている意思決定者たるべき「参加者」、こういったものの単なる集まりとして組織を見た方がよいというのである。
このようにしてゴミ箱モデルが生まれる。そこでは、問題、解、参加者、選択機会の独立で外生的な流れを仮定している。したがってゴミ箱モデルでは、決定の多くが、選択機会、問題、解、参加者のタイミングの産物であり、問題、解、参加者は同時性(simultaneity)によって結び付けられると仮定され、意思決定プロセスはタイミングに影響されることになる。論理必然的秩序(a consequential order)よりも、むしろ一時的秩序(a temporal order)が重要になるのである(March & Olsen, 1986)。
実は、ゴミ箱モデルは、具体的には、コンピュータ・シミュレーションのモデルとして提示されている。そこでここでは、後ほど実際にシミュレーション用のプログラム SGCP (Single Garbage Can Program)を組むことを射程に入れて、ゴミ箱モデルの概要を説明しておこう。
ゴミ箱モデルで「ゴミ箱」にたとえられているのは選択機会である。組織的意思決定過程においては、まるでゴミ箱にゴミを投げ入れるように、各参加者が選択機会に対して、問題、解、エネルギーを独立に投げ込み、その選択機会に投げ込まれた問題の解決に必要となる一定量までエネルギーがたまったとき、あたかも、満杯になったゴミ箱が片付けられるように、当該選択機会も完結し、「決定」が行われたものとして片付けられるというのである。
そこで、コーエン=マーチ=オルセンの最初の論文(Cohen, March & Olsen, 1972)にしたがって、ゴミ箱モデルを定式化してみよう。より正確には、次のような四つの基本的な概念の再検討に基づいて、コンピュータ・シミュレーション・モデルが定式化されている。
これら四つの要素は、互いに比較的独立して、かつ外生的に組織というシステムに対して、流れ込んでいると見ることができる。そして、選択機会が決定に至る条件については、次の仮定がおかれる。
エネルギー加法性の仮定: 選択機会が決定に至るためには、各選択機会は、それに投入されている問題のエネルギー必要量の総計と同量の効果的エネルギーを必要とする。つまり、ある時点で、一つの選択機会に属している効果的エネルギーの総量が、エネルギー必要量の総量と等しいかまたはそれを超えると決定がなされる。
このようにゴミ箱モデルは、最も純粋な形では、問題、解、参加者、選択機会の独立で外生的な流れを仮定している(March & Olsen, 1986, pp.17-18 邦訳p.23)。それらは、
によって決まるある方法で結び付けられる。したがって、決定の多くが、選択機会、問題、解、参加者のタイミングの産物となる。こうすることで、ゴミ箱モデルでは、問題、解、参加者は、論理的必然によってではなく同時性(simultaneity)によって結び付けられると仮定され(March & Olsen, 1986, p.11 邦訳p.13)、意思決定過程はタイミングに左右されるのである。
特に、決定構造、アクセス構造といった構造的制約のないモデルは未分割版(unsegmented version)と呼ばれるが(March & Weissinger-Baylon, 1986)、ここでは、後でこの未分割版が重要になるので、実際のシミュレーションは未分割版に限定して行われる。一般のゴミ箱モデルでは、決定構造とアクセス構造にしたがって、それぞれ参加者のエネルギーと問題が、決定に一番近い選択機会に投げ込まれるという「エネルギー配分の仮定」と「問題配分の仮定」がさらに置かれることになるが、ここで扱われる未分割版ではその必要はない[38]。第7章では、この未分割版が重要になる。
選択機会と問題、解の関係をもう少し具体的に考えてみよう。まず選択機会は問題の存在を必ずしも意味せず、単なる選択機会である。例えば、従業員の採用時期というのは、毎年ほぼ同時期に規則的に訪れる。これは特に何か明示的な問題を伴うものではなく、たまたまそのとき手元にあった採用内定者リストが満足解として、すんなりと決定されることも多い(後述する「見過ごしによる決定」に相当する)。
ところが、多くの場合、本当の意味で問題が存在しなかったわけではない。ただその選択機会では問題が顕在化しなかっただけのことである。例えば、景気が良かったりすると売り手市場となって、時期が来たときに用意できたリストでは、採用内定者の数・質を確保できていなかったり、あるいは結果的に内定者の出身校や出身地が極端に偏っていたりする事態も起こってくる。こうして潜在的に抱えていた問題が姿を現すことになる。採用活動の態勢の問題点、当該企業の知名度の地域的アンバランス、さらには、将来の人員構成はどうあるべきなのかといった将来のヴィジョンの問題等、様々な問題が次々に提起されることになる。そして、それらの問題に対する善後策が、新たな採用内定者リストとともに解として提示されるということを何度か繰り返しながら、徐々に解決へと向かうことになるのかもしれない(後述する「問題解決による決定」に相当する)。
しかし、採用活動はもともと期限のかなりきつい活動であるから、これだけ多くの問題が噴出してくると、通常はいちいちまともにとりあっていては採用担当者はお手上げの状態となる。そこで、期限内に諸問題を解決することはもともと無理な話と、結局、問題を棚上げにしたまま、ほとぼりがさめるのを待って、あるいは社内のどこかのプロジェクト・チームに先送りされるのを待って、とりあえず今年は、手元の採用内定者リストで行こうという結論になるかもしれない(後述する「やり過ごしによる決定」に相当する)。
実は、先ほどのシミュレーションの仮定からも、全く同様に、次の3タイプの決定が起こると考えられている。
コーエン=マーチ=オルセンは、このモデルにしたがい、コンピュータ・シミュレーションを行い、通常いわれる「問題解決による決定」は一般的ではなく、特に問題の負担が大きいときには、問題の見過ごし、やり過ごしによる決定が、実は通常の決定スタイルとなることなどの知見を得ている。
以上のような知見が、実際にコンピュータ・シミュレーションの結果、未分割版のモデルでも得られるのかどうかを確認してみることにしてみよう。コーエン=マーチ=オルセンの作ったシミュレーション用プログラムはFORTRANで書かれ、同論文の最後に付録として掲載されている。しかし、決定構造やアクセス構造を組み込んでいるために複雑で長いものになっていて、プログラムの内容を理解するのが困難であるし、修正も難しい。また乱数列をデータとして与える形式をとっているために、長い期間のシミュレーションには適さない。
そこでまず、ここで行うような100万期間のシミュレーションにも耐えうるように、コンピュータ言語の乱数発生関数を使うようにし、なおかつ決定構造、アクセス構造のない未分割版を考えることで、シミュレーション・プログラムを簡単にすることを考えよう。実際、
という定式化により、シミュレーション・プログラムは非常に簡単にすることができる。そこでこうした観点から Single Garbage Can Program (SGCP)と呼ばれるプログラムを新たに作成した(高橋, 1993c)。SGCPを使った研究としては、山下(1996)のものがあるが、ここでは、決定のタイプの分類をコーエン=マーチ=オルセンの最初の論文(Cohen, March & Olsen, 1972)に忠実に従ったものに変更したプログラム(Takahashi, 1997a)を用いてシミュレーションを行った。プログラムはBASICで書かれ、章末の付録に示されている。
SGCPでは、選択機会に参加者からのエネルギー(EP)または問題(エネルギー必要量 ERP)の少なくともどちらかが投げ込まれて、はじめて選択機会が出現したと考え、カウントすることになっている(行番号280)。このモデルで問題の負荷(load)量を表す負荷係数 LC を色々変えることによって、問題の負荷量の決定スタイルに与える影響について調べてみることにしよう。いま決定回数 K=10,000回と設定しておいて(行番号350)、解係数 SC=1.00としてシミュレーションを行なってみた結果は、表6.2のようにまとめられる。
表6.2 問題の負荷と決定のタイプ(解係数 SC=1.0)
| 負荷係数 LC | 決定1回に要 した平均期間 | 決定のタイプ(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 問題解決 | 見過ごし | やり過ごし | ||
| 0.1 | 1.6318 | 59.93 | 33.33 | 6.74 |
| 0.2 | 1.7266 | 59.70 | 33.28 | 7.02 |
| 0.3 | 1.8805 | 59.30 | 33.38 | 7.32 |
| 0.4 | 2.0915 | 58.65 | 33.70 | 7.65 |
| 0.5 | 2.3975 | 58.24 | 33.82 | 7.94 |
| 0.6 | 2.9683 | 57.56 | 34.23 | 8.21 |
| 0.7 | 3.5887 | 57.27 | 34.09 | 8.64 |
| 0.8 | 4.2061 | 57.22 | 33.42 | 9.36 |
| 0.9 | 5.4675 | 56.73 | 33.38 | 9.89 |
| 1.0 | 8.0929 | 56.09 | 33.43 | 10.48 |
| 1.1 | 11.4212 | 55.65 | 33.23 | 11.12 |
| 1.2 | 15.6606 | 55.04 | 33.39 | 11.57 |
| 1.3 | 19.6435 | 54.30 | 33.54 | 12.16 |
| 1.4 | 29.8381 | 53.78 | 33.43 | 12.79 |
| 1.5 | 56.1532 | 52.41 | 34.37 | 13.22 |
同様にして、表には示さないが、解係数 SC=0.99, 0.95, 0.90, 0.80, 0.50としてそれぞれシミュレーションを行った結果もあるので、それらをもとにして図6.2を作成した。これを見ると、どの解係数の値でも問題の負荷が大きくなると、決定1回当りに要する平均期間がどんどん長くなっていくことがわかる。特に、解係数 SC=1.00 のときは、負荷係数 LC が大きくなるにしたがって、決定1回当たりに要する平均期間がなだらかに大きくなっていくことがわかる。しかし例えば、解係数を SC=0.90にすると、問題の負荷が小さいときには解係数 SC=1.00の時とほとんど同じだが、負荷係数が LC=0.5あたりから、決定1回当りに要する平均期間は大きくなりだし、ついに負荷係数 LC=0.6のとき、4463回目の決定の際に決定に至らず、100万期間でシミュレーションは打ち切られている。このように、解係数 SC=1.00以外のケースでは、負荷係数 LC が1以下でも100万期間で決定に至らず、シミュレーションは打ち切られている。
図6.2 問題の負荷と決定1回に要する平均期間
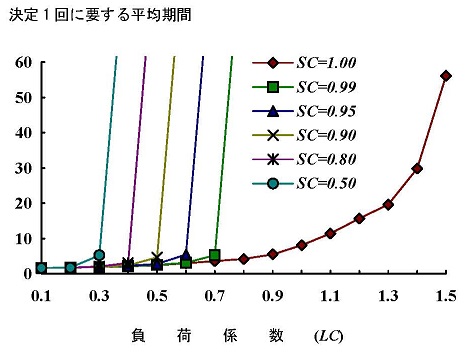
こうしたことから、解係数 SC=1.00のときに限定して、負荷係数による決定タイプの構成比率の変化を見てみることにしてみよう。解係数 SC=1.00のとき、表6.2をもとにして作成した図6.3を見ると、明らかに、負荷係数が大きくなって問題の負荷が大きくなるほど「問題解決」という決定のタイプが減り、それに代わって「やり過ごし」が増える傾向のあることがわかる。実は他の解係数の場合でも、打ち切りにならないで10,000回の決定が行われているときには、この決定タイプの構成比率は解係数が SC=1.00のときとあまり変わっていないことがわかっている。いずれにせよ、参加者のエネルギーに比べて問題の負荷量が大きくなると、結局、参加者の存在は小さなものとなり、参加者のエネルギー投入の様子にあまり関係なく、問題の去就によって意思決定が左右されるようになる様子が見てとれる。
図6.3 問題の負荷と決定のタイプの構成比率(解係数 SC=1.00)
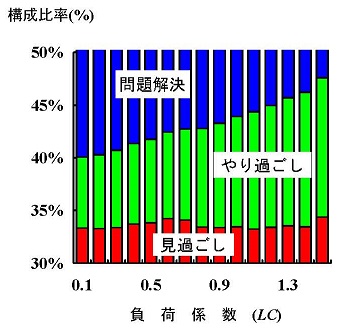
それらに比べて、「見過ごし」は負荷係数にあまり関係なく安定している。「見過ごし」はSGCPの場合、理論的には確率1/3で発生するようになっている。なぜなら「見過ごし」は選択機会の最初に EP>0かつ ERP≦0となったときに発生し、さらに EP≦0、ERP≦0のときは選択機会は出現しなかったという扱いになるので、いま
p=Pr{EP>0}, q=Pr{ERP≦0}
とすると、「見過ごし」の発生確率 P(0) は
P(0)=Pr{EP>0 かつ ERP≦0| EP>0 または ERP>0}
=Pr{EP>0 かつ ERP≦0}/Pr{EP>0 または ERP>0}
=(pq)/{1−(1−p)q}
となるからである。このプログラムでは、p=q=1/2 と設定してあるので、
P(0)=(1/4)/(3/4)=1/3
となる。実際、表6.2では「見過ごし」の発生頻度はいずれも 0.3323〜0.3437 となっている。
以上のことから、問題の負荷が大きくなると、「問題解決」による決定が減り、その分「やり過ごし」による決定が増えることが確認できた。SGCPのような未分割版のモデルの場合、結果の解釈が容易であるが、ゴミ箱モデルで問題の負荷との関係で重要なのは「やり過ごし」であり、「見過ごし」ではないことがわかる。
以上のようなゴミ箱モデルのシミュレーションから得られた知見によれば、コーエン=マーチ=オルセン(1972)が主張するほどには、問題の負荷との関係で「見過ごし」は重要ではないので、調査の対象を「やり過ごし」に絞り、日本の企業で「やり過ごし」がどれほど一般的なものなのか、そして、あいまい性下の意思決定とやり過ごしとの間にどのような関係があるのかを調べるために、まずJPC91調査が行われ、さらにJPC92調査が行われた。やり過ごしに関連して行われた1993年の調査は、次章で扱われるように、ある特定の企業A社に対象を絞ったものである。ここまでの段階で、次章で登場する「無政府度」の質問項目が確定したので、「やり過ごし」と「無政府度」は、JPC94調査、JPC95調査、JPC96調査でも調査項目となった。これらのJPC調査の方法については巻末付録を参照してほしい。いずれにせよ、こうした一連の調査データの分析は、次の章で、あいまい性の観点から系統的に行われるので、ここでは「やり過ごし」現象がどれほど一般的な現象なのかをデータにより示し、問題の負荷との関連を見るのにとどめる。
「やり過ごし」現象の分析は、次章も含めて、鍵となる次のYes-No形式の質問を中心に行なわれる。
この質問に対してYesと答えた人の比率をやり過ごし比率と定義すると、やり過ごし比率はJPC91調査では 66.3% (=597/900)、JPC92調査では 68.7% (=501/729)、JPC94調査では 55.9% (=461/824)、JPC95調査では 62.5% (=659/1055)、JPC96調査では 55.4% (=442/798)となっていた。つまり、多少の変動はあっても、過半数の人がやり過ごしを経験していることになる。5年分を合わせると、61.8% (=2660/4306) となる。さらに、この5年分の合併した年齢・職位階層別のやり過ごし比率は表6.3のようになる。つまり、やり過ごしはごく一般的な組織現象だったのである。
表6.3 年齢・職位階層別のやり過ごし比率(JPC91調査・JPC92調査・JPC94調査・JPC95調査・JPC96調査)
| 年齢 | 職位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 部長 | 2. 課長 | 3. 係長 | 4. 一般 | 全体 | |
| 1. 20-24 | 50.0( 2) | 100.0( 5) | 47.0(447) | 47.6(454) | |
| 2. 25-29 | 100.0( 7) | 77.2( 79) | 61.2(750) | 63.0(836) | |
| 3. 30-34 | 87.8( 49) | 69.8(255) | 64.3(339) | 68.3(643) | |
| 4. 35-39 | 75.0( 12) | 77.2(114) | 69.7(284) | 66.4(116) | 70.7(526) |
| 5. 40-44 | 76.7( 43) | 63.4(183) | 59.4(170) | 52.0(123) | 60.5(519) |
| 6. 45-49 | 66.0( 47) | 62.3(220) | 58.8(148) | 48.2(112) | 58.6(527) |
| 7. 50-54 | 63.2( 87) | 60.3(146) | 43.4(122) | 45.0( 60) | 53.7(415) |
| 8. 55- | 42.5( 40) | 52.0( 50) | 40.0( 30) | 63.2( 38) | 50.0(158) |
| 全体 | 63.3(229) | 65.6(771) | 63.6(1,093) | 57.1(1,985) | 60.8(4,078) |
この表によると、「30代」と「課長」クラスでのやり過ごし比率が高くなっていることがわかる。30代の課長163人中の実に 80.4% が指示をやり過ごしているうちに、その指示が立ち消えになることを経験している。やり過ごしを単にルーズさの現れだと考えていた人にとっては、この「30代」の「課長」クラスでやり過ごし比率が高く、80% にもなるということは意外なことに違いない。しかし、ゴミ箱モデルのシミュレーション結果によれば、問題の負荷が増えれば「やり過ごし」現象の頻度も増え、一般的に観察できるようになるはずなのである。したがって、このやり過ごし比率の高さは、「30代」の「課長」クラスの問題負荷の重さを表していると考えた方が理にかなっている。事実、第1段階のヒアリング調査の結果から、調査対象企業の組織の中で、一番忙しいのがこの「30代」の「課長」クラスの人たちであるということがわかっていた。これはゴミ箱モデルのシミュレーションによる知見、すなわち、問題の負担の大きいときには、問題のやり過ごしによる決定が多くなるという結論と合致しているといえる。
110 '***************************************************************************
120 '* A Single Garbage Can Model Version 2.2 Feb.1,1995 *
130 '***************************************************************************
140 '*************** Initialization ********************************************
150 I=0: RESOLUTION=0: OVERSIGHT=0: FLIGHT=0
160 LC=1 :'LC=Load Coefficient of ERP
170 SC=1 :'SC=Solution Coefficient to deflate EE
180 MAXK=10000 :'MAXK=Number of decisions to be exercised
190 '*************** Garbage Can Process ***************************************
200 J=0:TEE=0:ERC=0 :'to reset garbage can
210 I=I+1:J=J+1
220 EP=RND-0.5 :'EP=Energy from Participants EP=I[-0.5,0.5)
230 TEE=TEE*SC+EP :'TEE=Total Effective Energy
240 IF TEE<0 THEN TEE=0
250 ERP=LC*(RND-0.5) :'ERP=Energy Required by Problems ERP=LC*I[-0.5,0.5)
260 ERC=ERC+ERP :'ERC=Energy Required by Choice
270 IF ERC<0 THEN ERC=0
280 IF J=1 AND TEE=0 AND ERC=0 THEN I=I-1:GOTO 200:'Case of no entry
290 IF TEE
310 IF J=1 AND TEE>0 AND ERC=0 THEN OVERSIGHT=OVERSIGHT+1 :GOTO 340
320 IF J>1 AND TEE>0 AND ERC=0 THEN FLIGHT=FLIGHT+1 :GOTO 340
330 RESOLUTION=RESOLUTION+1
340 K=RESOLUTION+OVERSIGHT+FLIGHT :'K=number of decisions
350 IF K
370 STOP
380 RUN
[35] これからこの章で明らかにされるように、実はゲーム理論や決定理論が意味を持つのは、こうした因数分解された後の個々の意思決定過程の中だけ、つまり、意思決定者が十分に知識を持っている意思決定状況の中だけなのである。これは神取(1994, p.53)が「ゲーム理論は、比較的少数の人間が、自分達を取り巻く状況に対して十分な知識を持った上で行動する様なケースに対しては、鋭い切れ味を見せるのだが、そうでない場合にはどうもしっくり来ないというのが、多くの人の正直な感想であろう。」としていることと重ね合わせると興味深い。ただし、近年のゲーム理論の急速な進展が、旧来の素朴な意思決定論を根底から書き直す可能性を秘めていることも事実である。
[36] ここで注意を要するのは、2の満足基準は暗黙のうちに逐次的な探索過程を前提として考えられているが、正確にはその必要がないことである。実は、経済人モデルで取り上げられている最適基準の定義も、「すべての代替案」という部分に力点が置かれていると理解されるべきで、正確には、最適基準と満足基準は対照概念にはならないので注意がいる。詳しくは、高橋(1993c, ch.4)を参照のこと。
[37] ゲーム理論や決定理論が意味をもつのは、こうした状況定義の枠内だけである。実際、表6.1を確認すればわかるように、連合軍の決定「北側ルートを集中的に偵察」はマクシミン原理に則った決定であり、日本軍の決定「北側ルートで輸送」もマクシミン原理に則った決定であった。第1章で述べていた通りに、このゼロ和2人ゲームではマクシミン原理を採用することで均衡点が実現していたのである。つまり経済学的な意味では、負けた日本軍も最適戦略をとっていたことになる。このことの経営学的な意味については、高橋(1995b, ch.7)に解説がある。
[38] 決定構造、アクセス構造をもった彼らのもともとのシミュレーション・モデルでは次の二つの仮定も置いているので、参考までに挙げておこう。
エネルギー配分の仮定: 各参加者のエネルギーは、各期ではただ一つの選択に投入されているが、各参加者は自分がアクセス可能な選択機会の中でも、決定に一番近い選択機会、つまり他の参加者の投入エネルギーにより前期末のエネルギー不足分が最も小さくなっている選択機会に自分のエネルギーを投入する。
問題配分の仮定: 各問題は各期においてただ一つの選択機会に投入されており、その選択機会は、アクセス可能な選択機会の中から決定に一番近いものが選ばれる。問題間には優先順位は存在しない。
[39] 「やり過ごしによる決定」というのは意訳である。これまでは、decision making by flightは「飛ばしによる決定」と訳されることが多かったが、実際には人間が問題を飛ばしているのではなく、問題の方が自発的に飛んで行ってしまうまで、人間の方はじっとやり過ごして待っているだけなので、高橋(1992d)以来、筆者は「やり過ごしによる決定」という訳語を提案してきており、その後ほぼ定着するに至っている。
前章では、ゴミ箱モデルについて簡単にその概要を説明した後、命令、指示の「やり過ごし」の現象がどういった意味をもち、どういった条件、要因のもとで発生するものなのかを Single Garbage Can Program (SGCP)を使ってシミュレーションを行い、条件や要因の影響を吟味して理論的に考察してみた。その結果、注目すべき現象として「やり過ごし」が浮かび上がってきたのである。
以前、企業人を相手にしたセミナーの後で組織の中での意思決定について雑談をしていて、話題が命令、指示の「やり過ごし」の方に向いたとたん「組織の中にあって、上司から出された命令や指示をやり過ごしてしまうなどということはあってはならないことである。」と大きな声である大企業の部長から言われ、話題を変えたことがある。しかし、後になってから、個人的にもっと「やり過ごし」の話を聞きたいという人がやってきた。あってはならないことだとその存在すら一刀両断で切り捨ててしまう人もいれば、それでもあるのだという人もいる。そして驚いたことに、この章で扱っている調査では、やり過ごしのできない部下は無能であるとまで言い切る人さえ現れてきたのである。
従来「やり過ごし」は、やり過ごしをしてしまう人、やり過ごしをさせてしまう人といった個人のキャラクターやパーソナリティーの問題であると片付けられがちであった。確かにそういった側面は否定しきれないし、そこから「やり過ごし」に対する悪い印象も生まれてくると考えられる。しかし「やり過ごし」という組織現象の発生には、こうした個人の側だけではなく、どうやらシステムの側でも何らかの条件が関係しているらしい。そのことをゴミ箱モデルでは、あいまい性と呼んでいる。
そこでこの章では、実態調査をもとに、ゴミ箱モデルによって日本企業の意思決定様式が説明できるかどうかといった観点から、あいまい性の概念を再検討する。その結果、従来のあいまい性の3要件よりも、もっと直接的にゴミ箱モデルに結びついた新3要件が浮かび上がってくる。この新3要件の充足度を「無政府度」という指数で表現すると、無政府度が高いほどゴミ箱モデル的現象が発生していることが調査データから明らかにされる。
また、事後のヒアリング調査であいまい性以外にも特徴のあったA社については、再調査の結果、A社も含めた企業間比較では決定的に重要であった無政府度が、A社一社内部における組織単位間比較ではほとんど意味をもたず、A社にとって企業特殊的な要因である仕事の負荷量と上司の態度が決定的に重要であったことが明らかにされる。
しかし、いずれにせよ、日本企業では、上司の指示をやり過ごすことを容認する傾向がある。やり過ごしてしまうことは確かに「コスト」になるには違いないのだが、しかしこれは単なる無駄を意味するのではなく、将来の管理者や経営者を育てるためのトレーニング・コストあるいは選別コストとして暗黙のうちに容認されているケースも多いのである。未来係数が高い実際の日本企業においては、やり過ごしの現象を必ずしも「悪い」現象として決めつけず、駆逐することもしないという現実がある。これも未来傾斜原理の発露にほかならない。
ゴミ箱モデルは、前章でも紹介されているように、当初、コンピュータ・シミュレーションのモデルとして定式化され、分析が行なわれた(Cohen, March & Olsen, 1972)。その後、確率過程モデルによる分析なども試みられたが(Padgett, 1980)、現在では、そうしたモデル自体の分析よりも、むしろ現実の経営管理過程の分析に、分析枠組みとして用いられるようになっている(March & Weissinger-Baylon, 1986, ch.2)。例えば、マーチ=オルセン自らによるアメリカ、オランダ、ノルウェーの大学経営についての詳細な事例研究(March & Olsen, 1976)があるし、さらに、軍事組織の意思決定過程についても、戦時、平時を問わず、ゴミ箱モデルがもつ多くの特徴を見ることができるという研究(March & Weissinger-Baylon, 1986)がある。
経営の分野での分析枠組みとしての応用という点で注目されるのは、リン(Leonard H. Lynn)による研究(Lynn, 1982)で、新しい製鋼技術が日米両国の鉄鋼産業にいかにして導入されたのか、その経緯をゴミ箱モデルを分析枠組みとして使って描いている。そこで言っている新しい製鋼技術とは、純酸素上吹き転炉(BOF; basic oxygen furnace、LD転炉とも呼ばれる)である。これは、レンガで内張りされた炉で溶融した鉄を精錬する際に純酸素を上から吹き込む方法で、1949年にスイスの小さな製鋼会社の研究チームが実験に成功し、オーストリアのフェースト社とアルピネ社がそれぞれ1952年、1953年に実用BOF工場の稼働を始めたものである。日本では八幡製鉄が1957年、日本鋼管が1958年に導入したのに始まって、このBOFを速やかに導入したことで、1960年代に日本の鉄鋼業の国際競争力が飛躍的に伸びたといわれる。Lynnによれば、標準的な意思決定モデルは、BOFの後発組に見られる決定過程には符合するが、先発組の決定過程には当てはまらず、ゴミ箱モデルが符合していた。例えば、八幡製鉄では、生産能力を拡充しようとの決定が行われる前に、既にBOFを見いだしていたというように、問題がはっきりする以前に解が現れていた。また、日本鋼管では、技師や研究所の研究員、取締役、社長が、助言を求められる形や積極的に旗振りをする形で、さまざまな時、所でかかわっていたというように、決定センターがはっきりしなかった。そして、BOFという代替案、解は、誰かに発見されるのをじっと待っていたのではなく、BOFのプロモーターの積極的な売り込み努力に見られるように、「提案者」を積極的に探していたのである。
こうした分析枠組みとしての利用を意識して、
というような3要件の揃った状況での意思決定を、あいまい性下の意思決定(decision making under ambiguity)と呼ぶようになってきている(March & Weissinger-Baylon, 1986, p.1)。しかし、あいまい性のこの3要件、特に1、3とゴミ箱モデルのシミュレーション・モデルとの関係は必ずしも明確ではないし、説明も与えられていない。
そこでこの章では、6年にわたって行われた日本企業を対象とした実態調査(1991年: 6社907人、1992年: 7社740人、1993年: 1社539人、1994年: 8社829人、1995年: 6社1061人、1996年: 6社801人)のデータを使って、高橋(1995a)、Takahashi (1997a)をもとに、ゴミ箱モデルによって日本企業の意思決定様式が説明できるかどうかといった観点から、あいまい性の概念を再検討することにしたい。
前章のゴミ箱モデルのシミュレーションから得られた知見によれば、問題の負荷との関係で「見過ごし」はそれほど重要ではないので、調査の対象を「やり過ごし」に絞り、あいまい性下の意思決定とやり過ごしとの間にどのような関係があるのかを調べるために、まず1991年にJPC91調査が行われ、さらに1992年にはJPC92調査、1994年にはJPC94調査、1995年にはJPC95調査、1996年にはJPC96調査が追加的に企画実施された。これらのJPC調査の方法については巻末付録を参照してほしい。また1993年にも調査を行ったが、これは次節で扱われるように、ある特定の企業A社に対象を絞ったものである。
調査データの分析は鍵となるのは、前章でも質問Q6.1として登場した次のYes-No形式の質問である。
それでは、あいまい性の要件について探ってみよう。まずJPC91調査のデータを用いて、この質問Q7.1とそれ以外の74の同様の Yes-No 形式をもつ質問項目との間の相関をとり、その相関の高かった質問項目の上位10項目の質問文を相関係数の絶対値順に並べると、次のようになる[40]。
この他にも、福利厚生面の充実との間にも相関が見られたが、これについては3重クロス表を作ってみると、疑似相関であるらしいことがわかったので、このリストからは除いてある[41]。
そこで、高橋(1992d)にしたがって、さらに各変数を標準化した上で主成分分析を行なってみよう。各主成分に対する固有値は 2.568, 1.257, 0.961, 0.951, 0.902, 0.765, 0.728, 0.647, 0.634, 0.587 となり、第3主成分以下は1に満たないので、第1主成分、第2主成分だけを考えることにする。対応する固有ベクトルによって求めた重み係数は表7.1に示されているが、これによると、第1主成分は、上司の好き嫌いで評価され、上司の評価は適切さに欠けており、納得のいくまで議論が行なわれず、あいまいなままで、上司からの目標明示がないというように、「上司のあいまい性」を表していると考えられる。それに対して、第2主成分は、基準・規程・マニュアルがあるにもかかわらず、有効に利用されておらず、複数系統からの指示があり、しかも長期的展望に立った仕事というよりも短期的数字合わせに終ることも多いなど、「仕事のあいまい性」(あるいは「状況のあいまい性」)を表していると考えられる。
そこで、各社ごとに第1主成分、第2主成分の平均得点を求めて、それをもとに各社をプロットしてみると、図7.1が得られる。これによると、やり過ごし比率が81.1%と最も高かったB社は、上司のあいまい性、仕事のあいまい性ともに高かったのに対して、やり過ごし比率が60%台の3社については、A社、F社は上司のあいまい性が高く、E社は仕事のあいまい性が高いというように、ややタイプの異なっていることがわかった。
表7.1 主成分分析の結果(JPC91調査)
| やり過ごし(Q7.1)との 相関の高い上位10項目 | 固有ベクトル | |
|---|---|---|
| 第1主成分 | 第2主成分 | |
| X1 基準有効利用まだ | 0.283 | 0.480 |
| X2 機会があれば転職 | 0.215 | 0.325 |
| X3 複数系統から指示 | 0.205 | 0.453 |
| X4 短期的数字合わせ | 0.316 | 0.351 |
| X5 上司の評価は適切 | -0.374 | 0.259 |
| X6 納得いくまで議論 | -0.369 | 0.279 |
| X7 本音の議論は社外 | 0.294 | -0.293 |
| X8 上司の好嫌で評価 | 0.376 | -0.310 |
| X9 議論は実行に直結 | -0.321 | -0.059 |
| X10 上司から目標明示 | -0.354 | 0.074 |
| 固有値 | 2.568 | 1.257 |
| 各主成分での重み係数の絶対値上位4項目 |
図7.1 主成分得点による6社の位置付けとやり過ごし比率(JPC91調査)
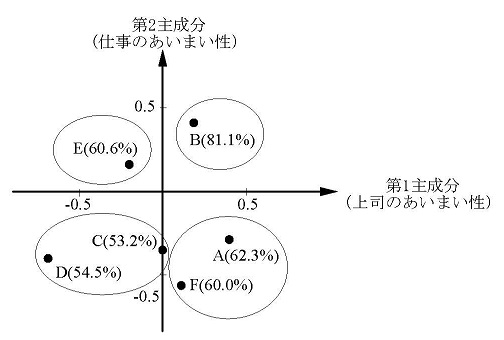
JPC91調査では、やり過しの実態を知るために、上司のあいまい性も仕事のあいまい性もともに高く、さらに6社中やり過ごし比率が81.1%と最も高かったB社について、調査の第3段階としてフォローアップのヒアリング調査を行なった。その結果、多くのやり過ごしの発生原因があげられた。それらは、あいまい性下の意思決定の3要件と密接に関連しているが、企業内におけるやり過ごしの実態を描写していて興味深い。これを「上司のあいまい性」「仕事のあいまい性」に整理すると次のようになる。
ところで、やり過ごしの質問Q7.1との相関の高かった上位10項目の中には、あいまい性の定義1、2、3との関係が比較的明瞭な (1) X1, X10, (2) X4, (3) X3のような項目もあるが、他の項目については必ずしも対応関係が明確ではない。それでも、前節では、JPC91調査のデータを用いて、これら10変数をもとに主成分分析を行い、二つの主成分を抽出している。ただし、第2主成分についてはそれなりにあいまい性との関係を指摘できるが、第1主成分についてはそうしたゴミ箱モデル的な関連づけは難しい。
こうしたことから、主成分や因子を抽出し、多少無理をしてでもあいまい性の3要件に結び付けてしまうのではなく、原点に立ち帰って、どういった条件の組織でやり過ごしが発生するのかを考えることにした(Takahashi, 1997a)。つまり、やり過ごし比率を被説明変数とするようなできるだけ少数の変数による回帰モデルを考えるのである。やり過ごしの現象の生じやすい組織を明らかにするために、個人単位のデータではなく、企業単位での各質問項目XiのYes比率を値としてとる変数 Xiを用いた分析を行うことにした。その場合、やり過ごしと相関の高かった変数が選ばれることが予想されるので、前述の10変数の中からそうした変数を選ぶこととし、これらの10の質問項目についてはJPC92調査でも調べられた。
まず10項目の中で、あいまい性の定義1、2、3との関係が比較的明瞭な (1) X1, X10、(2) X4、(3) X3のような変数を用いて、やり過ごし比率を被説明変数とする回帰分析を行ってみた。JPC91調査6社、JPC92調査7社の計13社の会社別の10項目のYes比率をデータとした分析結果は表7.2のようになり、有意なモデルにはならないことがわかった。
表7.2 やり過ごし比率とあいまい性(JPC91調査・JPC92調査の13社)
| 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) X10 上司から目標明示 | -0.6948 | 0.3151 | -2.205 | 0.0585 |
| (1) X1 基準有効利用まだ | 0.7898 | 0.2980 | 2.651 | 0.0292 |
| (2) X4 短期的数字合わせ | -0.4122 | 0.4728 | -0.872 | 0.4087 |
| (3) X3 複数系統から指示 | -0.0905 | 0.3710 | -0.244 | 0.8135 |
| 定数 | 0.9715 | 0.3176 | 3.059 | 0.0156 |
そこで、次に「あいまい性」の定義に拘らずに、やり過ごし比率を説明する回帰モデルを考えることにした。方法としては、JPC91調査6社、JPC92調査7社の計13社の会社別の10項目のYes比率をデータとして変数選択を行なった。
変数間の相関係数行列は表7.3のようになる。変数 X7 と X9 は相関が r=−0.769 と強く、共に「議論の非公式性」もしくは「議論と公式決定の分離」とでもいえるような特性を表した変数である。しかし質問 X7 については、JPC92調査の際に、企業によっては「就業時間内」と「社外」が必ずしも排反ではなく、あいまいさを残す表現となっているという指摘を受けた。変数 X7 は変数 X9 によって代替できると考えられるので、ここでの分析では変数 X7 を除いた9変数を説明変数の候補とした変数選択を行ってみよう。
表7.3 相関係数行列(JPC91調査・JPC92調査の13社)
| X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 0.365 | 0.487† | 0.623* | -0.018 | 0.135 | -0.360 | -0.505† | 0.135 | 0.183 |
| X2 | -0.047 | 0.290 | -0.369 | 0.024 | 0.067 | -0.037 | -0.332 | -0.346 | |
| X3 | 0.672* | -0.340 | -0.252 | 0.074 | -0.153 | 0.099 | 0.008 | ||
| X4 | -0.660* | 0.118 | 0.009 | -0.125 | 0.118 | -0.332 | |||
| X5 | 0.084 | -0.481† | -0.398 | 0.130 | 0.647* | ||||
| X6 | -0.491† | -0.084 | 0.585* | 0.142 | |||||
| X7 | 0.611* | -0.769** | -0.460 | ||||||
| X8 | -0.262 | -0.019 | |||||||
| X9 | 0.357 |
総当り法ですべての組合せで重回帰分析を行なって調べた結果、変数選択基準 Mallowsの Cp の値の小さいモデル(いずれも Cp の値は5を超えない)は説明変数が2〜6個のモデルに存在するので、それぞれ決定係数 R2 の大きさが一番もしくは二番目に大きい回帰モデルの決定係数、AIC、Cp を抜き出すと表7.4のようになった[42]。
表7.4 決定係数の大きな回帰モデルの変数選択基準の値(JPC91調査・JPC92調査の13社)
| 説明変数 | R2 | AIC | Cp |
|---|---|---|---|
| (1) X2, X8 | 0.6715 | 85.41 | 1.395 |
| (2) X2, X1 | 0.6001 | 87.97 | 3.221 |
| (3) X2, X8, X9 | 0.7859 | 81.85 | 0.471 |
| (4) X2, X8, X6 | 0.7146 | 85.58 | 2.293 |
| (5) X2, X8, X9, X5 | 0.8307 | 80.79 | 1.325 |
| (6) X2, X8, X9, X4 | 0.8166 | 81.84 | 1.687 |
| (7) X2, X8, X9, X5, X10 | 0.8536 | 80.91 | 2.742 |
| (8) X2, X8, X9, X5, X1 | 0.8444 | 81.70 | 2.977 |
| (9) X2, X8, X9, X5, X3, X10 | 0.8703 | 81.33 | 4.313 |
| (10) X2, X8, X9, X5, X6, X10 | 0.8628 | 82.06 | 4.506 |
Cp で選ぶと(3)ということになるし、AICで選ぶと(5)ということになるが、AICは(3)でも(5)でもさほど変わらない。モデル(5)はモデル(3)に変数 X5 を加えたものであるが、この変数 X5 の回帰係数は10%水準でも有意ではないので、表7.5のモデル(3)が最良のモデルといえるであろう。
表7.5 やり過ごし比率を被説明変数とする回帰モデル(3) (JPC91調査・JPC92調査の13社)
| 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | |
|---|---|---|---|---|
| X2 機会があれば転職 | 0.4378 | 0.1237 | 3.540 | 0.0063 |
| X8 上司の好嫌で評価 | -0.5709 | 0.1911 | -2.987 | 0.0153 |
| X9 議論は実行に直結 | -0.4149 | 0.1892 | -2.193 | 0.0560 |
| 定数 | 0.8636 | 0.1508 | 5.725 | 0.0003 |
こうして、やり過ごし比率を被説明変数とする重回帰モデルは回帰係数の符号も考えると、メンバーは、
ような組織でやり過ごし比率が高いということになる。一体、どんな組織なのだろうか。これらの3変数が、March & Weissinger-Baylon (1986)のあいまい性の3要件と合致していないことは一目瞭然である。特に(3) X8の業績主義などは常識的なあいまい性の概念にも反しているように思われる。
実はわれわれの身近に、この新3要件(1)〜(3)によく当てはまる組織がある。それは組織化された無政府状態の典型、「大学の教官組織」である。つまり、コーエン=マーチ=オルセンの発想の原点(Cohen, March & Olsen, 1972)に戻ったことになる。日本の企業を調査して見いだしたことは、この新3要件の点で「大学」に近いほど、やり過ごしの発生頻度が高いということである。しかも、原3要件が、ゴミ箱モデルの具体的定式化と結び付いていないのに比べ、この新3要件はゴミ箱モデル、特にシミュレーション・モデルの定式化と次のように直接的に結び付くという点でも興味深い。
このうち、1と2はゴミ箱モデルの中核部分である。1は参加者の出現、退出が比較的ランダムであることを示唆しており、2は問題解決以外の決定のタイプの存在を示している。3はこれまであまり指摘されていないが、仮に業績ではなく、職務態度で評価されるようになると、問題の選択機会間の移動が制限されることになる。すなわち、やり過ごしが制限されることになるのである。
ところで、表7.5からもわかるように、回帰モデル(5)と比較してみても、採用された回帰モデル(3)の回帰係数の絶対値は0.41〜0.57の間にあり、ほぼ等しいことがわかる。そこで、回帰係数が正の変数 X2 のもとになっている質問X2についてはYesならば1点、Noならば0点を与えることにし、回帰係数が負の変数 X8, X9 のもとになっている質問X8, X9についてはNoならば1点、Yesならば0点を与えることにしてダミー変数化し、その合計点を「無政府度」(degree of anarchy)と定義することにしよう(Takahashi, 1997a)。このように単純化して、回帰係数ではなく等ウェイトに変えることで、データが追加されるごとに起こる回帰係数の変動に伴う、過去のデータにまで遡った「無政府度」の計算し直しの煩わしさから解放され、長期・広範囲に渡る継続的なデータの利用が容易になる。
そこで、実際にこれまで分析に使ってきた13社と新たに追試のために調査したJPC94調査の8社、JPC95調査の6社、JPC96調査の6社の合計33社について無政府度を求め、やり過ごし比率との関係をプロットしてみると、図7.2のようになる。決定係数は0.4202 (自由度修正済み決定係数は0.4015)とあまり高いとはいえないが、平均値を原点とする直交座標の第1象限と第3象限にほとんどの企業が分布している。また、この33社について、表7.5と同様に重回帰分析してみても決定係数は0.4488(自由度修正済み決定係数は0.3917)とわずかにしか変わらないので、回帰係数ではなく等ウェイトに単純化したことの影響はほとんどないといってよい。
図7.2 無政府度とやり過ごし比率(JPC91調査・JPC92調査・JPC94調査・JPC95調査・JPC96調査の33社)
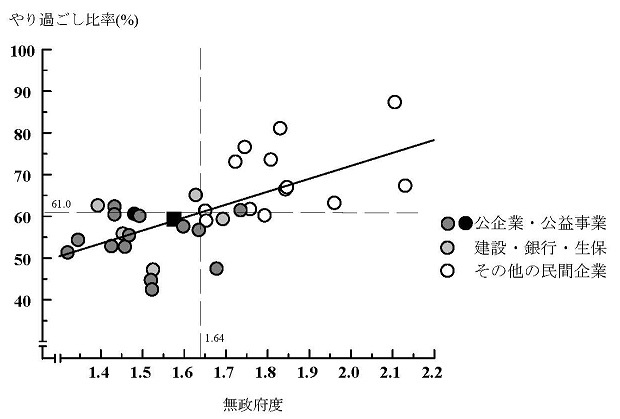
注1) ●はA社の位置を示す。■は回帰分析とは無関係だが、1993年に調べたA社の位置を示している。破線はJPC91調査・JPC92調査・JPC94調査・JPC95調査・JPC96調査の33社の平均を表している。
注2) やり過ごし比率を被説明変数とする回帰モデル
| 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | |
|---|---|---|---|---|
| 無政府度 | 31.0545 | 6.5513 | 4.740 | 0.0001 |
| 定数 | 10.0724 | 10.8194 | 0.931 | 0.3591 |
次節で取り上げるJPC91調査のA社については図7.2の中で「●」で示している。この図7.2から、公企業と公益事業は、やり過ごし比率も無政府度も低いということがわかる。言い方を変えれば、政府に近いほど無政府度も低いわけで興味深い。ちなみに、公企業と公益事業に交じっている民間企業は、2社は官庁からの受注の多い大手建設会社、残りは銀行と生命保険会社であった。
以上のことから、この新3要件に直接対応した無政府度を用いれば、やり過ごし比率についても説明することができ、「大学」らしさを表す新3要件の方が発想の原点から考えても、原3要件より自然であることがわかる。
JPC91調査のA社(図7.1)における第3段階のフォローアップのヒアリング調査を行なった結果、やり過ごしの発生原因とその機能に関して、次のような興味深い結果が得られた。
ところで、以上のようなA社でのヒアリング調査の結果、特にbの「バカ殿状況」はこれまでのゴミ箱モデルと基本的に合致していた分析とはやや異なる側面を描写している。またaの「オーバーロード状況」の意味している仕事の負荷量についてはゴミ箱モデル的な状況下、つまりあいまい性下でやり過ごしの現象が発生する要因として既に考察してきたが、実はあいまい性の要件自体には含まれていないものである。新3要件に含まれていないということは、企業間比較では重要ではなかったということになるが、おそらく、あるレベルのあいまい性をともなった一企業の内部での組織単位比較では、仕事の負荷量がやり過ごしの現象の発生を左右しているということを示していると思われる。
そこで、こうした要因が一企業内の分析で重要になってくるのかどうかを確認するために、このA社のより多くの部門を対象にした調査が1993年に追加的に企画実施された(高橋, 1995a)。JPC91調査、JPC92調査で用いた共通の質問項目にさらに追加して60項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。質問票調査はホワイトカラーの部門、具体的には1事業部門、2支店を選び、その中の全組織単位の構成員に対して全数調査を行った。総組織単位数は12、総調査対象者数は601人、組織単位当りの平均調査対象者数は50.1人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた人に対して、1993年8月25日(水曜日)に一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、8月30日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、539人から質問調査票が回収でき、回収率は89.7%となった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
そこで、さっそくこのA社のやり過ごし比率と無政府度とを求めると、やり過ごし比率は57.7% (N=534)、無政府度は1.574となった。これは既に図7.2に「■」でプロットされているが、図7.2の注にある無政府度を説明変数とした回帰モデルによるやり過ごし比率の予測値59.0%との乖離はわずかに1.3%程度で、前回の位置とも近く、A社全体のやり過ごし比率は無政府度によって説明されているといってよさそうである。しかし、A社の内部で組織単位のやり過ごし比率を無政府度で説明することは全くできない。この回帰モデルの決定係数は、わずかに 0.0010、両者の相関係数は0.0316にすぎない。
それでは、A社内部でのやり過ごし現象の発生は、フォローアップのヒアリング調査で明らかになったような「バカ殿状況」や「オーバーロード状況」によって説明することができるのだろうか。しかし実際の調査では直接的な表現で聞くことはできないので、今回のA社の調査では、次のYes-No形式の質問を用意した。
図7.3からわかるように、実はA社一社のみの内部に限定すると、各組織単位のやり過ごし比率の全分散は、このたった2変数で82.82%も説明できてしまう。ところが、このA社での調査結果を追試するために、質問A1、A2を入れて行ったJPC94調査、JPC95調査、JPC96調査では、調査対象の計20社について同様の分析をしてみると表7.6のようになり、A1、A2 を説明変数とする回帰分析の決定係数はわずかに0.1019 (自由度修正済み決定係数は -0.0038)で、有意な結果は得られなかったというよりも、ほぼ無相関であったことがわかったのである。
図7.3 A社の各組織単位のやり過ごし比率と回帰分析(1993年)
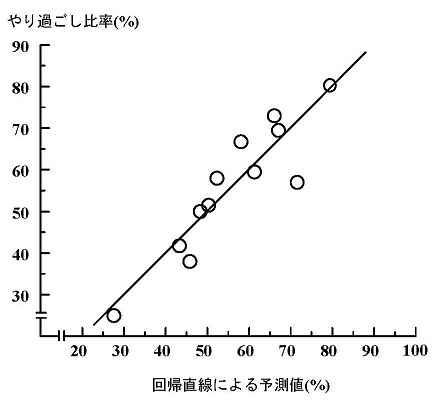
注) A社でのやり過ごし比率を被説明変数とする回帰モデル(1993年)
| 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | |
|---|---|---|---|---|
| A1 自分の意見が尊重 | -0.8083 | 0.1279 | -6.321 | 0.0001 |
| A2 仕事は正直きつい | 0.6168 | 0.2216 | 2.784 | 0.0213 |
| 定数 | 76.5477 | 11.6934 | 6.546 | 0.0001 |
表7.6 やり過ごし比率を被説明変数とする回帰モデル(JPC94調査・JPC95調査・JPC96調査の20社)
| 回帰係数 | 標準誤差 | t | 有意確率 | |
|---|---|---|---|---|
| A1 自分の意見が尊重 | -0.2028 | 0.2680 | -0.757 | 0.4596 |
| A2 仕事は正直きつい | 0.2096 | 0.2028 | 1.034 | 0.3157 |
| 定数 | 64.6243 | 21.8320 | 2.960 | 0.0088 |
つまり、A社も含めた企業間比較の場合には、未分割版のゴミ箱モデル的状況を表す無政府度が重要であったが、各企業の内部について見れば企業特殊的な要因が存在しうるのであって、A社の場合には企業内比較で明らかになったように、仕事の負荷量と上司の態度が決定的に重要だったということである。これは、あるレベルのあいまい性が存在し、ゴミ箱モデル的状況が存在すれば、実際のやり過ごしが現象として出現する引き金となる要因については、企業によってかなり特殊なものが考えられることを示唆している。
これまでの実態調査から、日本の企業では、やり過ごしの現象がごく普通に見られるということがわかった。やり過ごしが30代、特に30代の課長クラスが頻繁に経験しているということにも象徴されるように、やり過ごしは、問題の負担が大きすぎて、オーバーロード状況に陥っている組織を、あいまい性の下で、できるだけ有効に機能させるという側面をもっている。さらにそれだけではなく、A社の例からもわかるように、上司の信頼性・安定性の低さを上手に回避することで組織行動の安定化が図られていることが明らかになった。このことは、スクリーニング機能、フィルター機能ともに、やり過ごしが部下の側の能力を発揮する場としての側面をもっていることを示唆している。A社でのヒアリング結果からもわかるように、あいまい性下で仕事の過大負荷がある場合には、ゴミ箱モデルが想定しているとおりに、やり過ごしは、部下が行使すべき正当な意思決定方法なのかもしれない。
またフィルター機能は、上司の誤った意思決定を回避する際に、やり過ごしが発生していることを示している。実際、第3段階のヒアリング調査の結果、A社以外でも、たまたま現在の部長クラスの数人のキャラクター、パーソナリティーが、やり過ごしの発生に大きく影響しているらしいというケースも見つかっている。このような場合、組織運営上はやはり問題がある。
これまでの実態調査で、やり過ごしの現象がゴミ箱モデルと直結した無政府度と関係していることが明らかになったことからもわかるように、やり過ごしは人的条件を一定にしておいても、高いあいまい性(新3要件)下では論理的に自然な現象なのである。しかし、実際に発生する際には、企業特殊的な要因も働いており、A社の場合には、仕事の過大負荷や上司の低信頼性・不安定性が引き金となって発生していることも明らかになった。やり過ごし自体には、こういった組織的破綻を回避するという評価すべき機能がありながら、その引き金となる仕事の過大負担や上司の態度に大きな問題があるために、やり過ごしの現象に対する評価が分かれるのであろう。
しかし、引き金になる要因に色々と問題があることがわかっていながら、なぜ日本企業はそれを放置あるいは黙認しているのであろうか。実はこれこそが、やり過ごしの現象がごく普通に観察される直接かつ最大の理由のはずである。そこでこの章の締めくくりとして、やり過ごしには、もう一つ重要な機能が存在していることを強調しておきたい。それは人材育成という側面である。経済学的な発想からすると、やり過ごしは単なるコントロール・ロス(Williamson, 1967)やコストに過ぎない。確かに優秀な上司の指示にすべてきちんと従った方が、効率的だろう。しかし、この発想には決定的な誤りがある。それは、少なくとも日本企業では、今日の部下は10年後には何らかの形で上司を勤めることになるということである。今、上司の指示をただ忠実に、やり過ごすこともなく黙々とこなすだけの部下が、果たして10年後に良い上司となりえるのだろうか。
経験を積んだ優れた上司が、部下の力量を判断して、詳細な指示の下に、一番生産性が高くなるような仕事だけに従事させるとどうなるだろうか。これまでに調査の対象となった大手の流通業者では、4年制大学を卒業した男子従業員に、7年間も同じ売り場で単調な食品加工の仕事をさせていた例があった。この場合、店長が短期的な人件費、コスト削減圧力の中で、「熟練した職人」である彼を担当からはずす決心がつかないままに、ずるずると7年間が経過したらしい。その間、7年間も続けさせたくらいであるから、確かにその食品加工の生産性は高かったであろう。しかし、そうした環境に置かれ続けた者が、果たして幹部として成長しうるであろうか。彼の将来は一体どうなるのか。そして幹部候補として採用したがために、大卒男子に高い給料を支払い続ける会社はどうなるのだろうか。そう考えるならば、短期的には多少非効率なことが発生しても、ローテーションを行ってさまざまな経験を積ませるべきではなかったのではないだろうか(高橋, 1993a, p.122)。そのためには、やり過ごしを完全に排除してしまってはいけないのである。
実際、トレーニング的な意味合いを込めて、上司は部下がこなし切れないほどの量の仕事を与えることがある。こうすることで、部下のやり過ごしをわざと誘発させているのである。そんなとき部下は、自分で仕事に優先順位を付け、優先順位の低い仕事をやり過ごしながら、自分で仕事を管理することを期待されている。うまくやり過ごしができるようにならなければ優秀な上司にはなれない。
A社の場合にも、やり過ごしのこういった機能を十分に知った上で、部下が自分で判断して上司の指示をやり過ごすことを容認しているという反応があった。また他社では、やり過ごしの発生する状況をわざと与え、部下に実際にやり過ごしをさせることで、個々の仕事に対する優先順位の付け方や、やり過ごしの判断の仕方をチェックして部下の力量を推し量っているというケースも報告されている。つまり、やり過ごしてしまうことは確かに「コスト」になるには違いないのだが、しかしこれは単なる無駄を意味するのではなく、将来の管理者や経営者を育てるためのトレーニング・コストあるいは選別コストとして暗黙のうちに容認されているケースも多いのである。このことは注目に値する。なぜなら、このコストは、高い未来係数の下でのみ、はじめてとトレーニング・コストあるいは選別コストに化けるからである。だからこそ、長期雇用を前提としている実際の日本企業においては、やり過ごしの現象を必ずしも「悪い」現象として決めつけないという現実がある。これはまさに未来係数が高い状況下での未来傾斜原理の発露にほかならないのである。
[40] いずれも0.1%水準で有意。ここでの質問の解答は2値データになるので、クロス表の相関係数であるクラマーの V 係数(Cramer's V)が用いられた。ただし第1章でも述べたが、2×2クロス表では、クラマーの V 係数とピアソンの積率相関係数 r とは一致する(高橋, 1992c)。
[41] より具体的には、調査対象企業を公益事業とそれ以外の非公益事業とに分けた上で、それぞれクロス表を作って調べてみると、相関係数はそれぞれかなり小さくなり、しかも、非公益事業では指示のやり過ごしが多く、福利厚生面での充実が立ち後れているのに対して、公益事業では、福利厚生面でも充実しているし、指示のやり過ごしも比較的少ないということがわかった。したがって、指示のやり過ごしと福利厚生という直接的には本来無関係なはずの変数が、実はともに企業の業種、業態、市場環境と密接に結び付き、これらが先行変数となっているために、疑似相関が見られると考えられる。高橋(1992c)も参照のこと。こうしたやり過ごしと公益事業・非公益事業との関係は、後で図7.2においても確認できる。
[42] 変数選択基準 Mallowsの Cp については、Chatterjee & Price (1977, ch.9)、AICについては坂元他(1983, ch.4)を参照のこと。
既に前の二つの章で明らかにしたように、ごく簡単なコンピュータ・シミュレーションを行ってみても、やり過ごしの現象は仕事の負荷が大きい時に発生しやすいことがわかっているし、実際、やり過ごしの現象は、企業の中ではもっとも多忙な人々といわれる30代の課長・係長クラスで、仕事の負荷がきつい時に発生していることが、調査の結果わかってきた。上司の指示をやり過ごしてしまうことは確かにコストには違いない。しかしそれは正確に言えば、単なる無駄ではなく、将来の管理者や経営者を育てるためのトレーニング・コストあるいは選別コストである。そのため、長期雇用を前提としている日本企業においては、やり過ごしの現象を暗黙のうちに容認し、必ずしも「悪い」現象として決めつけないという現実もあるのである。
ところで、部下のやり過ごしを許容したとして、それが不首尾に終わったときには一体どうしたら良いのだろうか。ここからが、この章が扱おうとしているテーマである。
これについての妙案はない。はっきりしているのは、誰かが尻ぬぐいをしなければならないということである。実際、企業を調べてみると、業務の多忙感が充満している課長あるいは係長クラスでは、いわば職場の尻ぬぐい的な仕事をさせられていることが、業務の多忙感につながっていることがわかってきた。しかも尻ぬぐい的な仕事に従事している中心は、いまや公式名称としては多くの企業で姿を消しつつある「係長」に相当する職場リーダー達であった。係長クラスが上司と職場・現場に挟まれて尻ぬぐいに追われている姿は、まさに多忙そのものである。課長などの外部からも見えやすいポジションとは異なり、係長クラスの存在は、いまや係制の廃止などで、対外的には見えにくくなっている。しかし、光は当たっていなくとも、その職場リーダーとしての機能は重要である。企業がトレーニング・コストや選別コストを覚悟するのは当然としても、結局は、誰かが尻ぬぐいをしなければ、組織は回っていかないのである。
やり過ごしのように意思決定を部下に任せてみるという場面だけではない。自分で片付けた方が速くて正確であるようなルーチンに近い仕事についても、とりあえずは部下に任せてやらせてみて、仕事を覚えてもらう。それで結果的にうまくいかなかった場合には、覚悟を決めて自分が尻ぬぐいに回るのである。こうした尻ぬぐい的行動のおかげで、組織的行動やシステムが破綻をきたさずに済んでいるのである。そして、やり過ごしだけではなく、この尻ぬぐいも、高い未来係数に支えられた未来傾斜原理に則った行動なのである。
経営学では、1940〜1960年代に、組織のローワー・レベルを中心に扱ったワーク・モティベーション論やリーダーシップ論の研究が盛んに行われた。他方、経営者・管理者については、管理過程論のような経営者の仕事についての教科書的な理解の時代を経て、そこで描かれる経営者・管理者像に反駁するような形で、経営者・管理者の行動の実態についての調査研究が、管理者行動論と呼ばれ、行われてきた。管理者行動論(managerial behavior)は、現実のトップまたはミドルのマネジャーの日常的行動の実態についての地道で記述的な調査を行い、管理者の行動が、一見すると、いかに非能率的で、支離滅裂であるかを事実として提示してきたのである。
ミンツバーグ(Henry Mintzberg)のレビュー(Mintzberg, 1973)を引き継ぐ形での金井(1991)の管理者行動論の網羅的な文献レビューによると、管理者自身が事前にコード化されているメモ用紙に、活動が生じるたびに、継続的従事時間、場所、参加者などを記録するダイアリー・メソッド(diary method)と呼ばれる調査方法を用いることで、時間配分を明確にパーセンテージで示すという管理者行動論独自の貢献があったという。代表的な業績としては、スチュアート(Rosemary Stewart)による160人のイギリス人トップ、ミドル・マネジャーの調査研究(Stewart, 1967)のような注目される研究が挙げられる。そして、これを含む多くの調査研究の共通の事実発見として、次のことが明らかになってきたという(金井, 1991, p.153)。
このうち4は断片化(fragmentation)と呼ばれる。断片化の原因は、管理者が次々と生じる日常的事象や対人接触機会に対して、受動的に反応する行動様式をとっているからだとされる。ミンツバーグは、観察中ないしは観察後にカテゴリー化を行う構造化観察法によって5人の経営者を調べたが、それによると、口頭での接触のうち管理者自身の側から自ら率先して行った接触は32%にすぎなかったという(Mintzberg, 1973)。経営者でさえ自分の活動のごく一部しか積極的にコントロールできないというのである。
ところで、日本企業を研究対象として考えた場合、こうした管理者行動論の研究の中でも、すっぽりと空白域になってしまっている領域がある。それがいわゆるホワイトカラーの「係長」の仕事についての研究である。人事・労務関係の部署の係長を除いて、ほとんどの場合、係長は労働組合の組合員となっており、管理職とは扱われない。通常、「マネジメント」がつく場合には管理職を意味しているので、ミドル・マネジメントと呼ぶ場合は、係長よりは上の職位、課長、部長を指すと理解するのが普通である。かといって、係長はいわゆるヒラの従業員と同じなのかというとそうではない。しっかりと管理的な仕事をまかされているのである。実際には、課長は結構日の当たる職位である。それに比べると、係長はほとんど課長の黒子役に徹するような職位である。これからはミドルの時代だとか言われながら、不思議なことに、実は係長の話はどこにも出てこないのである。
この章で扱われる調査研究でも、当初から明確に係長をターゲットにしていたというわけではない。むしろ事実発見的にその重要性を認識させられて、調査の企画を練り直したというべきだろう。調査の結果として明らかになってきた「係長の仕事」は、その量だけを考えても、ほとんど体力任せの感がある。その質をとっても、まさに尻ぬぐい、泥かぶりの類の仕事である。当の係長自身が、そのうち異動があるからという見通しにすがって、なんとか凌いでやっているような節がある。しかし、調査過程で明らかになってきた「係長の仕事」は日本企業の人材育成と業務遂行のシステムのまさに要の仕事である。
その意味では、いまや日の当たらない仕事の典型のようになっている「係長の仕事」に光を当てるのが、この章の目的である。そのことで日本企業の人材育成と業務遂行の実態について考えてみたい。
ここでの目的とアプローチについては、管理者行動論と対比して、その違いを指摘しておく必要があるだろう。管理者行動論における管理者の記述は、実は管理者に限らず、係長やヒラの従業員にもそのまま当てはまるはずである。ここでは、ダイアリー・メソッドはとられないが、質問票調査とヒアリング調査を繰り返し実施することで、こうした一見、いかにも非能率的で、支離滅裂である現象が職位によって程度の差こそあれ、組織の中でならどこでも見られる現象であることが明らかになる。実際、調査開始当初、注目していた業務の多忙感にとって、その源泉ともいえる尻ぬぐい的な仕事の比重は、空白域になってきた係長クラスにこそ多いのだという事実発見が得られる。そして、管理者行動論では侮蔑の対象とでもいうべき、この尻ぬぐい的な仕事が、実はすべてが全く無意味なものなどではなく、それを係長クラスが中心となってこなしていること自体にも理由と意義があることを明らかにすることこそが、この章の目的なのである。
調査が企画された当初、筆者を含めて調査対象企業が抱えていた問題意識は、「業務が多忙である」といった業務の多忙感は一体どこから来るのだろうかということであった。そして、その多忙感が組織やその従業員に対してどのような影響をもたらすのかということにも関心をもっていた。こうした問題意識で調査が企画され、質問調査票も設計されたために、調査結果が得られた後で、係長クラスの多忙感の源泉についての事実発見が得られると、今度はこれを第1次調査と位置付けた上で、事実発見で得られた知見をもとにして、第2次の調査が追加的に企画実施されることになったのである。
調査は1994年にJPC94調査の一環として行われた。調査は質問調査票を作成する前のヒアリング調査と、その質問調査票を使った第1次と第2次の質問票調査、そしてそれらの調査結果を手にしてから行ったフォローアップのヒアリング調査に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、まず1994年6月に合宿形式でグループで相互にヒアリングを行い、各社2時間程度をかけて、各社の組織の概要、特徴、問題点などをできるだけ明らかにした上で、さらにそれぞれの会社、職場で多忙感をもたらす要因となっているものについて議論してみた。こうした作業を通して、多忙感をもたらすものとして、
の二つの側面について、その要因を考える必要が確認された。特に業務の質を取り上げることの必要性については、説明を要するかもしれない。これは、ヒアリングの結果、明らかになってきた事実発見によっている。すなわち、組織、職場の中で多忙感を感じる際には、単に量的に仕事が多いというだけではなく、仕事の質によってもその多忙感は左右されるものだというのである。つまり、本来の仕事だけではなく、余計なことをやらされていると感じる場合に、より多忙感を感じるのではないかというのである。こうして、業務の量と業務の質について、各社において、その実態と特徴をできるだけ具体的に浮き彫りにするような質問項目をリストアップする作業が行われ、さらに、どの会社でも質問として意味が通じるように"共通語"に翻訳する作業をしながら、質問調査票が作成された。
調査の第2段階では、この質問調査票を使って、調査対象となった8社のそれぞれでメンバーの現在又はかつて所属していた「組織単位」をいくつかピックアップして、その構成員全員を対象とする全数調査を行った。実は今回の調査では、年齢と「部長クラス」「課長クラス」「係長クラス」「一般」の四つの職位との間には、かなりはっきりした関係のあることがわかっている。図8.1でもわかるように、「一般」の75.47%は20歳代の人で占められている。同様に、「係長クラス」の55.23%は30歳代、「課長クラス」の67.31%は40歳代、「部長クラス」の実に84.21%は50歳代以上によって占められている。つまり、一般は20歳代、係長クラスは30歳代、課長クラスは40歳代、部長クラスは50歳代以上というおおまかな関係が見出せるのである。もちろん企業によっての昇進スピードの差がある。特に係長クラスは20歳代後半も14.53%いるし、40歳以上の高卒の係長クラスの存在も指摘されている。しかし、こうしたかなりはっきりとした対応関係があることから、ここでの分析は、職位によるものを取り上げることにする。当然のことながら年齢階層による分析でも同様の傾向が見出されることになるが、それでも職位による分析を中心にしたのは、ヒアリングの結果では、年齢よりも職位の方が本質的に重要であるという意見が多かったためである。
図8.1 職位別の年齢構成
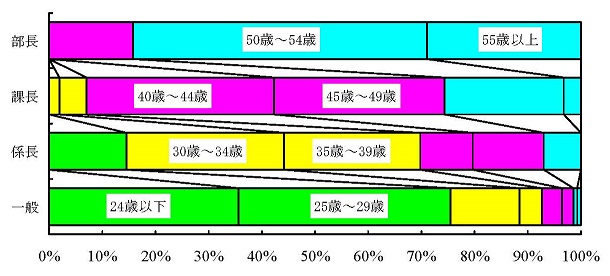
それではまず、業務の量についての調査結果から見ていくことにしよう。業務の量については、Yes(該当する)、No(違う)のどちらか近いと思われる方一つを選んで○をつけて下さいというYes-No形式で、次のような質問が用意された(順番は図8.2に合わせて並べ変えている)。
これらの質問に対する答えにはある共通した傾向があることがわかった。それは「部長クラス」「課長クラス」「係長クラス」「一般」の四つの職位カテゴリーで、それぞれYesの比率をみてみると、図8.2のように逆U字型をしていたのである。つまり、業務の量に関しては、職位が上がるにつれて増加する、あるいは減少するという単調な傾向は見られず、課長クラスと係長クラスでピークを迎えることがわかった。部長クラスではかえって業務の量は減少するのである。しかもE1の会議などについては課長クラスが高いが、E2の残業の手伝い、E5の隣のグループの手伝い、E7の休日出勤といった実労働時間的な忙しさについては、実は係長クラスが一番高いことがわかった。
図8.2 職位別に見た業務の量
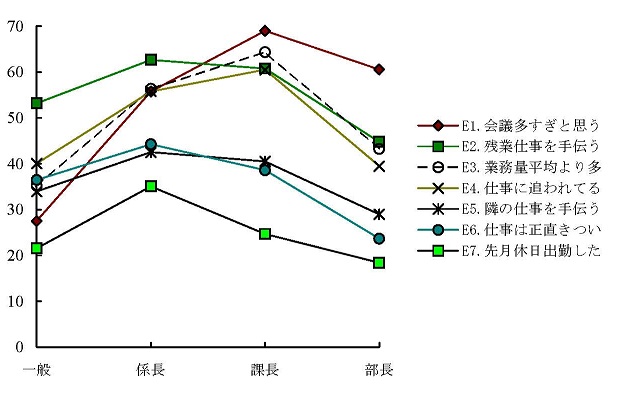
こうした職位カテゴリーで見た場合の逆U字型の傾向は、業務の質に関する次のようなYes-No形式の質問でも見出された(順番は図8.3に合わせて並べ変えている)。
F1についてはNoの比率(したがって、図8.3の凡例では「人員配置は不適切」と質問文とは逆の表現にしてある)、F2〜F5についてはYesの比率をとってみると、図8.3のように、やはり逆U字型をしていたのである。しかも今度はいずれの質問でも、係長でピークを迎えている。
図8.3 職位別に見た業務の質
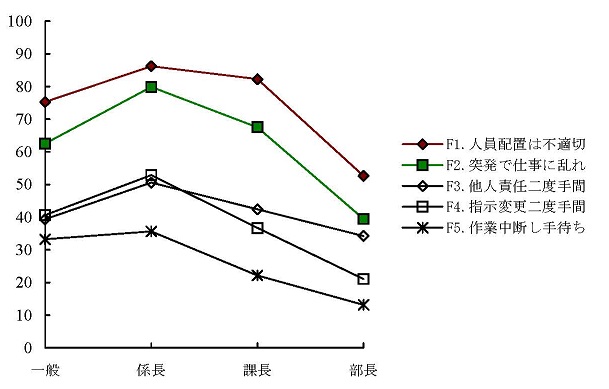
ところで、この業務の質に関する五つの質問は、各社の職場の中では具体的には、一体どのような現象を表しているのであろうか。ここまでの調査結果をもとにして、1994年10月に再度、合宿形式でグループで相互にヒアリングを行うとともにディスカッションを行った。その結果、これらの質問は「尻ぬぐい」もしくは「泥をかぶる」ような内容の仕事を指しているのではないかという点で一致した。つまり、いずれもその原因は自分の不手際や不始末などではない。上司や部下といった他人のせいなのである。しかも、困ったことに、この原因を持ち込んだ人々は基本的に自己責任で原因を解決してくれない。つまり、回答者に対して、泥をかぶって、尻ぬぐいすることを求めているのである。まさに管理者行動論における断片化、そして操り人形仮説に隠された真実の姿といっていい現象である。
しかも、ここで注目されるのは、こういった「尻ぬぐい感」が、実は係長クラスで高くなっているという事実である。このことに関しては、調査対象となったどの企業でも納得できる現象であるという結論に達した。つまり、どの企業でも、係長クラスの仕事とは、まさに尻ぬぐい的な仕事になっているというのである。
そこで、この五つの質問をもとにして「尻ぬぐい」の程度を表す指標を作ることを考えてみよう。質問F1についてはNoの比率、質問F2〜F5についてはYesの比率をとって考えていたように、質問F1についてはNoならば1点、Yesならば0点を与え、質問F2〜F5についてはYesならば1点、Noならば0点を与えてダミー変数化することにする。質問項目 Fi に対応するダミー変数を Fi で表すと、これらの変数の単純統計と相関係数行列は表8.1のようになる。
表8.1 相関係数行列 (N=817)
| 変数 | 単純統計 | 相関係数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | F1 | F2 | F3 | F4 | |
| F1 人員配置は不適切† | 0.778 | 0.416 | ||||
| F2 突発で仕事に乱れ | 0.663 | 0.473 | 0.194*** | |||
| F3 他人責任二度手間 | 0.417 | 0.493 | 0.201*** | 0.288*** | ||
| F4 指示変更二度手間 | 0.424 | 0.494 | 0.147*** | 0.202*** | 0.410*** | |
| F5 作業中断し手待ち | 0.307 | 0.462 | 0.106** | 0.211*** | 0.179*** | 0.240*** |
この五つの変数を標準化した上で主成分分析を行ってみると、各主成分の固有値は、1.895, 0.914, 0.852, 0.774, 0.564 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルは
(0.344, 0.386, 0.528, 0.503, 0.448)
となるので、各変数の標準偏差を考慮すると、各変数の重み係数はほぼ等しくなることがわかった。つまり、単純に合計して合成得点を作ってもよさそうだ。そこで、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点を「尻ぬぐい度」と定義することにしよう。定義から、尻ぬぐい度は0から5までの整数値をとることになる。
そこで、さっそくこうして定義された尻ぬぐい度と業務の量との間にどのような関係があるのかが調べられた。まず次のような質問によって、一斉に調査票を配布した1994年8月31日(水曜日)の前日の勤務パターンと出社時刻、退社時刻を調べ、これから勤務時間を求めた。
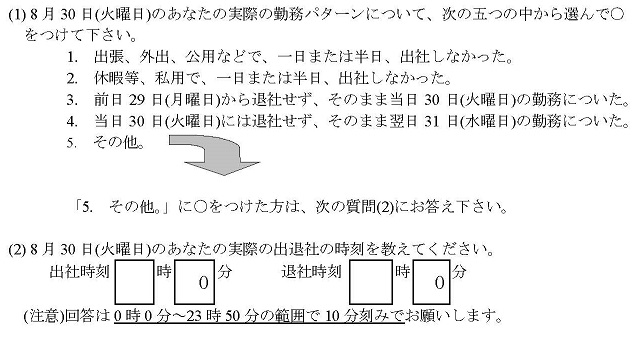
こうして求めた勤務時間をもとに、勤務時間のカテゴリーを作ると「8時間未満」23人(3.5%)、「8時間台」104人(15.7%)、「9時間台」179人(27.0%)、「10時間台」143人(21.6%)、「11時間台」88人(13.3%)、「12時間以上」125人(18.9%)といった分布となった。この各カテゴリーについて尻ぬぐい度の平均を求めると、図8.4のようになり、平均値の差の検定を行うと F = 7.10 で0.1%水準でも有意な差が見られた。このことから勤務時間が長くなるほど尻ぬぐい度が増加する傾向があることがわかった。これはいわゆる残業が尻ぬぐい的な業務によるものであることを示していると考えられる。
図8.4 勤務時間と尻ぬぐい度(F = 7.10, p <0.001)
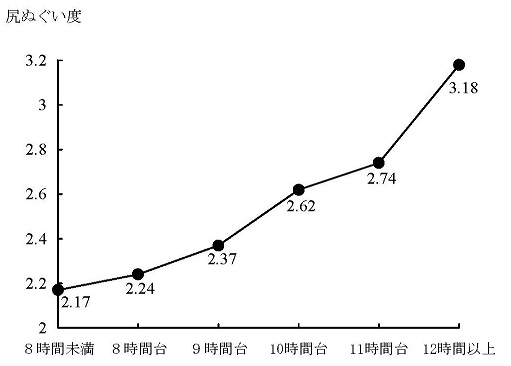
調査前日(1994年8月30日火曜日)の勤務時間(出社から退社までの時間)
同様に業務の量についての多忙感の質問と尻ぬぐい度との関係を調べると表8.2が得られるが、各質問で業務の量が多いと答えた人の方が尻ぬぐい度の平均が有意に高いことがわかる。つまり実際の勤務時間だけではなく、多忙感も尻ぬぐい度とは関係のあることもわかった。
表8.2 尻ぬぐい度と業務の量
| 業務の量を表す変数 | 尻ぬぐい度の平均 | ||
|---|---|---|---|
| Yes群 | No群 | t | |
| E1 会議多すぎと思う | 2.81 (357) | 2.42 (458) | 3.90*** |
| E2 残業仕事を手伝う | 2.70 (458) | 2.44 (358) | 2.59** |
| E3 業務量平均より多 | 2.94 (379) | 2.28 (433) | 6.65*** |
| E4 仕事に追われてる | 3.02 (396) | 2.19 (420) | 8.68*** |
| E5 隣の仕事を手伝う | 2.80 (299) | 2.47 (518) | 3.13** |
| E6 仕事は正直きつい | 2.95 (312) | 2.37 (503) | 5.83*** |
| E7 7月休日出勤した | 2.83 (204) | 2.51 (613) | 2.80** |
そして、職位別に尻ぬぐい度の平均を求めると図8.5のようになり、尻ぬぐい度も逆U字型で、係長クラスでピークになることがわかる。F = 12.76 で0.1%水準で有意な差があった。
図8.5 職位別の尻ぬぐい度 (F=12.76, p <0.001)
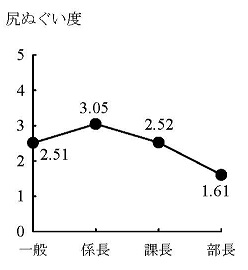
こうして、組織の中における係長クラスの果たしている役割が「尻ぬぐい」をキーワードとして明らかになってきたわけであるが、ここで、こうした考察の結論を確かめるために、同じ調査対象企業8社の今度は係長クラスに対象を絞って、1994年11月後半に、第2次質問票調査が行われた。
調査では、既に第1次調査で用いられた尻ぬぐい度を構成する質問に関連して、それぞれの質問項目で、尻ぬぐいの状況が発生したときの具体的な状況の事例を記述してもらうことにした。8社中、A社とE社については、質問調査票を用いた面接調査が行われ、他の6社については、同じ質問調査票を用いた留置法による調査が行われた。その結果得られた比較的まとまった回答を列挙してみると、次のようになる。これでかなり係長クラスの尻ぬぐいの実態がつかめるのではないだろうか。
実は調査が行われた前年の1993年末に、ハマー(Michael Hammer)とチャンピー(James Champy)の『リエンジニアリング革命』(Reengineering the Corporation, 1993)の邦訳が出版され、調査当時もリエンジニアリングのブームが続いていた。業務の多忙感を調べるという課題設定が行われたこともそうであるが、調査対象企業8社がこのような第1次、第2次に及ぶ、しつこい調査にも熱心に応じてくれたのも、こうした時代の雰囲気と無縁ではない。しかし、調査対象企業の担当者は、このような調査結果を事実として認めた上でなお、こうした尻ぬぐい的状況を変えるために、仕事のプロセスをリエンジニアリングするということに対して、全く否定的であった。
確かに、「もう少し何とかならないのか」という感想が漏れるようなシステムやプロセスの不備を示す調査結果も散見された。しかし、より重要なことは、こうした尻ぬぐい的行動のおかげで、組織的行動やシステムが破綻をきたさずに済んでいるということである。問題なのは、尻ぬぐい的行動がとられることではなく、誰も尻ぬぐいをしないときであろう。そして、何を隠そう、そもそもこうした尻ぬぐい的状況がもたらすコストを計算に入れて、システムやプロセスが作られているのである。
ところで、なぜ係長クラスが尻ぬぐい的な仕事に忙殺されているのだろうか。これには。構造的な要因が存在している。
賃金は熟練によって決まるものであって、それは経済的に説明がつくと考えているようだが、今回の調査対象企業も含めて、少なくとも筆者が接してきた大企業については、この考え方は疑わしい。実態はむしろ逆で、賃金カーブが熟練よりも先に別の事情で決まっているように感じられる。小池(1991)に対する反論を展開する野村(1993, pp.37-39)が言うように、日本の大企業では、戦後直後の労働組合による「経営民主化」「身分制撤廃」運動の結果として、ホワイトカラーとブルーカラーの間に、基本的に同じ賃金制度が適用されるようになったのであり、準戦時体制、戦時体制のもとで確立した大企業の賃金カーブが、戦後直後の生活給的賃金制度に受け継がれ、さらに春闘方式のもとで「年齢別生活費保障型」の賃金カーブが定着したのではないだろうか(これについては第3章の第3.2項を参照のこと)。これらはむしろ労働組合などによって課される「政治的な」制約条件によるものであろう。そして、この賃金カーブが課された後の企業行動こそが、実に経済的に合理的なものなのである。
野村(1993, pp.39-40)は、賃金が年齢とともに上昇するために、その上昇したコストに見合ったパフォーマンスを直接作業員にも求めるために技能育成を行うと考えられるとしているが、こうした指摘はホワイトカラーについてもそのまま当てはまっているように思える。しかも、ホワイトカラーにとってのパフォーマンス向上とは、より高い職位について、より管理的、経営的な仕事をすることによってしか達成されないのである。そこに何らかの「技能」「熟練」のようなものがあり、その育成が可能だとしても、育成に役立つOff-JT(off-the-job-training)の方法を開発することには未だ誰一人として成功していない。だから消去法的にOJT(on-the-job-training)しか残されていないのである。
このことは、ブルーカラーについても言えるようになってきたのではないだろうか。1950年代に東北地方に進出した大手家電メーカーの工場について、1991年にヒアリング調査したときには、急激な円高と人件費上昇の中で、かつては直接作業員として雇っていたはずの従業員であっても、もはや直接作業員として働かせていては全くペイしない状況が進んでいた。その結果、生産設備は協力会社に移され、そこの従業員によって生産が行われるようになる。かつての直接作業員は、その高い賃金に見合うだけの働きをするために、いまは自ら直接作業をすることはやめさせられ、協力会社の管理業務にあたらざるをえなくなっていた。しかし、生産現場における技能とは異なり、管理業務に必要な能力の育成はいたって心許ない。実際には、管理業務に耐えられずに辞めていく人が後を絶たないという。こうした状況は、同時期に調査に訪れた東北地方の数社の工場でも同じ様に聞くことが出来た。
このように、賃金カーブは保障できても、管理職としての人材育成は保証できないという現実を背景にして、もう一つの経済的に合理的な企業行動が生まれる。それが、日本の大企業ならばどこでも行われているといってもいいような職能資格制度の導入である。これによって、賃金に連動した資格等級から職位を分離したのである。職能資格制度では、原則的に対応職位は等級の下限でセットされる(楠田, 1995)。たとえば、課長は資格等級○級以上の者から選ばれるというように決められるのである。もちろんその等級に昇格したからといって、課長に昇進するとは限らない。これによって、管理職への昇進には選別を行うことにしたのである。
これは『賃金センサス』(労働省政策調査部編『賃金構造基本統計調査』)によれば、従業員規模1,000人以上の企業の25〜29歳の男子従業員に占める大卒者の比重が、1995年には59.3%にもなっているという現実を目の前にして、より重要な意味を持つ。管理職候補の大卒ホワイトカラーは、人数が増えようとも、とにかくOJTで育てて(他に方法がない)、賃金分は働いてもらえるようにしなければならない。しかし、全員が管理職になれるほどポストはないし、その能力もないだろうから、管理職になる段階で選別しなくてはならない。これが、係長クラスが尻ぬぐい的仕事に忙殺される構造的な要因なのである。
ところで、現在、多くの日本企業では「係長」は死語になりつつある。今回の調査対象企業8社でも、「係長」という名称のポストが存在している企業は皆無であった。
それでも、今回の調査対象企業8社の係長クラスを平均的に見れば、係長クラスは、
というようにまとめて、一般的には間違いはないだろうということで、8社の見解は一致した。
それでは、調査対象となった8社で、係長クラスは、実際にはどのような形で存在していたのであろうか。労働組合の組合員になっているという共通点をもってはいるものの、表8.3によると、その他の特性にはかなりの多様性をもっていることがわかる。
表8.3 係長クラスの職務権限等の比較表
| 会社 | 対外名称(a) | 年齢(b) | 職務権限 | 係長クラスへの登用 | 課長への登用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事 評定権 | 課長の 代理・ 補佐(c) | 下級者 の指導(c) | |||||
| A社 | 課長代理 主任 | 33〜37 | なし | 非公式 | 非公式 | ある段階で筆記試験を 行うなど緩やかに選別 | 選別 |
| B社 | 主任 | 36〜40 | なし | 公式 | 公式 | ほぼ年齢対応 | 選別 |
| C社 | 主任 | 28〜 | なし | 非公式 | 公式 | ほぼ年齢対応 | 選別 |
| D社 | 課長代理 | 32〜39 | あり | 公式 | 公式 | ほぼ年齢対応 | 選別 |
| E社 | 課長代理 | 30〜35 | なし | 公式 | 公式 | 過去3年の評価をもとに 形式的ではあるが審査 | ほぼ年齢対応(d) |
| F社 | 課長代理 主任 | 28〜35 | なし | 公式 | 公式 | 資格は年齢で昇格する が、任命は選別 | 選別 |
| G社 | 副主事 | 31〜36 | なし | 公式 | 公式 | ほぼ年齢対応 | 昇進時期に差 |
| H社 | 課長代理 調査役 | 32〜39 | なし | 公式 | 公式 | ほぼ年齢対応 | 昇進時期に差 |
このうち、職務権限の欄での「公式」「非公式」は、職務権限規程などで定められている場合には「公式」、定められてはいないが、実質的にそうであるものは「非公式」とした。たとえば、B社の職務権限規程では、係長クラスに相当する「主任」の職務は次のように「公式」に定められている。
「主任は上位者の命を受け所管業務を処理する。主任の主なる職務は次の通りとする。
またD社では人事評定権があることになっているが、これは同社の「権限規程」でリーダー(これが同社内での正式名称で、対外名称は「課長代理」となっている)の権限が「リーダーの権限は、課長の権限と同一とする。」と簡潔に規定されてしまっているためで、実際には、人事評定権をもっているとは言いがたい。
このように多様性があるのは、日本企業において、
という事情を反映しているため、課長の一歩手前の役職という点では一致しているものの、課長になるまでは資格等が入社時から連続性を持ってなだらかに設定され、係長クラスがそれより下のクラスから明確に峻別されていないからであろう。しかも、課の仕事が成功した場合、失敗した場合、高い評価を得たり、責任を取らされたりするのは課長であり、係長クラスは黒子として活動するのみで、表面的には見えてこない存在なのである。
また1でも示したように、ほとんどの従業員は、長期欠勤、体調不良、業務遂行能力の著しい欠如のような特殊な理由のない限り、多少の昇進時期の差はあっても、ほぼ年齢に応じて係長クラスに登用されることになっており、また経験しなくてはならないことにもなっている。
たとえばE社では、年齢的には27〜35歳の間、事務系では「主事」、技術系では「技師」と資格上、呼ばれる。この「主事・技師」資格は、標準的滞留期間8年で、若い方から順に3級、2級、1級に分けられていて、それぞれの標準滞留期間は3年、3年、2年とされている。係長的な役割は主事・技師2級者以上が担っているといえるが、対外的に肩書きが与えられるのは、同1級者になってからで、それが「課長代理」なのである。このクラスの「主事」は直接の上司として課長がいて、自らも小グループを率いてリーダーとしての役割を担っている。事務系の主事の場合には、具体的には、次のような代表的職務が挙げられている。
こうして組織上位置付けられる係長クラスは、一体どのような仕事をしているのであろうか。今回の調査対象8社の間では、係長クラスの仕事に対して、次のような特徴づけが行われた。
つまり、簡単に図式化してしまうと、図8.6のように、管理者グループと実務者グループの連結ピンの役割を果たしていることになる。係長は実務者グループの一員として、実務もこなしながら、同時に管理者グループの一員として、係員の指導と育成を行うのである。
図8.6 連結ピンとしての係長クラス
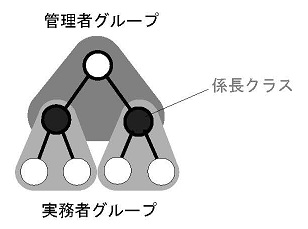
もっとも、実際の負担を考えると、リッカート(Likert, 1961)の連結ピン以上に、負担が大きいと考えられる。先ほどのD社の例を除いたとしても、残りの7社は人事評定権ないしは人事考課権はもっていないことになる。にもかかわらず、課長の代理・補佐として若手に指示命令を下し業務を遂行することを求められているわけで、人事評定権の後ろ盾なしで真の意味でのリーダーシップを求められていることになる。
その上、一係員として、係員の中でも最も高度な業務を分担するだけではない。未熟練係員の教育・指導も行わなくてはならない。人材育成の要なのである。しかも単なる教育・指導ではなくOJTである。係長は、自分でやった方が簡単だと思われるような仕事についても、とりあえずは係員にやり方を教えて、仕事をまかせる。実務を通して、下級者と日常的にもっとも接しているのが係長クラスであり、課長等の管理職の業務方針をきちんと理解しているはずなのも係長なのである。コピー、ファックスのやり方から、各種連絡事務のリコンファーム、さらには業務方針の徹底、営業推進のアドバイスに至るまで、係長は下級者の面倒を見なければならない。これがOJTの実態である。
しかし、いかにトレーニングの対象とはいえ、仕事は仕事である。もしできなかったらどうなるのか。係員が仕事を期日までに完遂する保証はどこにもないのである。もし仕事がうまくいかなかったら、結局は係長が尻ぬぐいをするしかない。この尻ぬぐいなしには、組織は動かないのである。
また、先ほどの表8.3で特徴的なのは、係長クラスへの登用はほぼ年齢対応とする企業が多かったのに対して、課長職への登用については、選別を行うか(これは当然、昇進できない人が出てくる)、もしくは昇進時期に差をつけるということである。つまり、企業にとって、係長クラスというのは、管理職登用への一種の試験期間でもあるのである。
この方式のOJTは、係長クラスに集中的に尻ぬぐいという過大な負担を要求する"教育"システムになっている。しかも大変な教育コストを要するだけでなく、教育する側の係長にもストレスを引き起こすことになる。そのストレスは選別プロセスの中で加圧される。しかし、もしそれをしなかったら、係員はいつまでたっても育たず、一人前には仕事ができないことになる。その上、係長は課長以上の管理職から降ってくる例外的な仕事についてもこなさなくてはならない。ここに多忙感の根本的な原因がある。
つまり、忙しくなる原因は自分の不手際でも不始末でもない、どう客観的に見ても上司や部下といった他人のせいなのである。しかも、上司であれ、部下であれ、忙しさを持ち込む人々には、基本的に自己責任をとらせることができない。結局は、係長クラスが泥をかぶり、尻ぬぐいをして回るしかないのである。ここに、徒労感とでもいうべき多忙感が発生するのである。これは大いなるストレスをもたらす。しかも、下級者に不手際があった場合、課長が注意を与える対象は、不手際をしでかした本人ではなく、係長クラスであることが普通であるともいわれる。
しかし、こうしたストレスに耐えられることも良い管理職になるための必須条件なのである。そのことを端的に表しているのが、「ストレス耐性」と呼ばれるものかもしれない。G社の資格要件では、係長クラスに相当する副主事は、一般職層と管理職層とに挟まれたリーダー職層と位置付けられている。G社の資格別分析評価項目では、その副主事に対して、思考判断(問題意識・課題設定、実態把握・判断、創意企画)、課題実現(業務処理・行動、交渉、ストレス耐性)、補佐指導(上司補佐、指導率先)、知識、のような能力要素が評価項目とされている。注目されるのは、課題実現の中の「ストレス耐性」で、これは「難しい事態に遭遇しても回避せずに粘り強く取り組んでいるか」どうかを見ているというのである。
しかし、いかに試されているとはいえ、こうしたストレスに半永久的にさらされるのでは、とても身が持たない。したがって、一般的に、大卒従業員の場合には、係長クラスにはある程度限定された滞留期間が設定されている。それも、気力、体力ともに充実している(というより、多少なりとも無理のきく)30歳代に設定されている。係長クラスにいる間に選別が行われるために、その結果によって違いは出るだろうが、課長等、別の職位に抜けて行くことが予定されていて、半永久的に尻ぬぐいをさせることのないような配慮がなされているのである。ある滞留期間を経て、課長等に抜けて行くという「見通し」があってこそ、はじめて、人はストレスに耐えていられるのである。未来係数が高いからこそ機能する未来傾斜原理に則った行動なのである。
まずは「まえがき」に書いておいた本書の課題をもう一度確認しておこう。
きれいで美しいゲーム理論の世界、決定理論の世界、近代組織論の世界。それは、この本の第1部、第2部、第3部のそれぞれ冒頭の章で紹介している通りである。ところが、日本に暮らすわれわれ、特に日本企業とそのメンバー達は、それらの理論から見ると一見不合理な世界に生きている。しかし、われわれの生きている世界が本当に不合理かというと、そんなはずはない。もし本当に不合理ならば、われわれの互いの行動も全く予想がつかず、社会生活など不可能で、われわれの目の前には支離滅裂でばらばらな光景が展開しているはずだからである。何か筋が通っているような気がする。はっきりとはしていないが、何かに導かれて行動しているように感じられる。それでは、われわれは一体何に導かれて行動しているのだろうか?
これが本書の課題だった。そして、それに対する私の答えは「未来の重さ」である。「未来の重さ」に導かれて行動しているからこそ、われわれの世界は破綻をきたさずに済んでいる。これがこの本の結論である。
むしろ逆に、「未来の重さ」が存在している世界では、ある意味で空間が歪んでいるために、ゲーム理論的均衡も、決定理論的期待効用原理も、近代組織論的意思決定過程も、もはやきれいな平面上で理路整然と成立するようなわけにはいかなくなる。均衡も安定ももはや説得的で魅力的なアイデアとはいえない。実際の経営の現場で、こうした理論の破綻を取り繕い、均衡や安定に代わって実際の行動に意味を与え続けてきたのが、この「未来の重さ」なのである。しかも「未来の重さ」は、単なる理屈の上だけの概念ではない。実際に、手応え、やりがい、生きがいとなって、われわれが行動する上での日常感覚の基礎をなしているものなのである。
私がこの本で主張し、伝えたかったことは、ゲーム理論、決定理論、近代組織論から見ると、一見不合理に感じられるわれわれの世界が、実は「未来の重さ」によって導かれている合理的な筋の通った世界なのだという発見である。例えば、「未来の重さ」の存在に気がついてしまえば、日本企業の行動様式はまことに理にかなったものに感じられる。
こうした「未来の重さ」はこの本の中では姿を変えて何度となく繰り返して登場してきていた。例えば、第1章から、今回の対戦と比較した次回の対戦の weight、すなわち次回の対戦が行われる確率を表す discount parameter を、敢えて割引率とは呼ばずに未来係数と呼び続けてきたが、いまこそこれを「未来の重さ(weight)」ともっと素直に呼ぶときが来たのである。未来をどこかに収束させるために、割引率を便宜的に使うことはもうやめよう。未来をどこかに収束させる必要なんかないのである。未来は無限大に発散する存在でかまわない。大きな「未来の重さ」が存在している所では、未来は残すことにこそ価値があるのである。
この本では、このように「未来の重さ」に導かれている姿を意思決定原理の形で抽出し、未来傾斜原理と呼んできた。「未来の重さ」が存在している世界では、もはや、これまでの決定理論系の意思決定原理では行動指針として説得力がなく、役に立たない。そして現実にも生き残ったのは、未来傾斜原理に則ったシステムだったのである。
そこで、今度はこの「未来の重さ」の存在を最初から明確に意識しながら、この本での議論を跡づけし、振り返っておくことにしよう。
人は、何かものごとを決める際に、意識している意識していないにかかわらず、何らかの原理・原則に則って意思決定を行なっているものである。それをここでは意思決定原理と呼ぶ。企業、組織、経営といった分野でよく知られた意思決定原理は、主に決定理論と呼ばれる分野で考えられたものがルーツになっている。そしてその決定理論自体、もともとはゲーム理論から派生して生まれたものである。
ゲーム理論では、ゼロ和2人ゲームであれば、数ある意思決定原理の中でも、マクシミン原理に導かれて均衡点に到達することができる。言い換えれば、ゼロ和2人ゲームの世界では、それを採用すれば均衡点に到達できるという意味で、マクシミン原理は説得的でありかつ魅力的な意思決定原理である。しかし、非ゼロ和2人ゲームになると、均衡点は存在するものの、もはやマクシミン原理で到達できる保証はなくなる。マクシミン原理は均衡点へのパスを指し示すものではなくなるのである。
しかも非ゼロ和ゲームでは、その均衡点自体、実際上、どれだけ意味のあるものか怪しくなってくる。例えば、ゲーム理論で考えれば、裏切り合いの共倒れで均衡するはずの囚人のジレンマ・ゲームであっても、「未来の重さ」が大きい長期間のゲームでは、実験でもシミュレーションでも協調関係が現れるようになり、均衡点は現実的には意味を失う。これはわれわれの日常感覚にも合致している。均衡に代わって進化論的な状況で用いられる集団安定の概念を使っても、均衡の時と同様に、裏切り合いの共倒れで集団安定することが理論的に証明されるのだが、実際には、やはり「未来の重さ」が大きい長期間のゲームでは、現実的に無意味であることが明らかになる。
こうして、ゼロ和ゲームでは、均衡点へのパスを指し示してくれるという点で、マクシミン原理は説得的でかつ魅力的な意思決定原理だったのに、非ゼロ和となると、マクシミン原理がもう均衡点へのパスを指し示さないどころか、「未来の重さ」が存在している世界では、均衡も安定も現実的な意味を失ってしまっているのである。もはや均衡や安定へのパスを指し示してくれるという観点から意思決定原理を評価すること自体に意味がない。しかし、もしわれわれが、どんな形であれ、筋の通った行動をとっているとすれば、そして、それに何らかの意味があるとすれば、われわれは全く異なる別の観点から見て説得的で魅力的な意思決定原理に則って意思決定を行い、行動しているはずである。
そこで、反復囚人のジレンマ・ゲームのシミュレーションの結果を検討してみると、実はシミュレーションの結果から、(1)自分からは決して裏切らない、(2)相手が裏切った後でも再び協調する、という性質をもった戦略が高得点を挙げている。この(1)(2)が示唆していることは、目先の利益や過去への復讐を選択してはいけないということである。将来の協調関係をこそ選択すべきなのである。まさに「未来の重さ」に素直に導かれるべきなのである。
しかし、よく考えてみると、これはあまりにも当たり前のことである。シミュレーションなどやってみるまでもない。いまもし、
未来傾斜型システムを採るべきだ。われわれにそう気付かせてくれるのは、「未来の重さ」が存在している時かもしれない。言い換えれば、「未来の重さ」こそが、そのことを実感させてくれる。「未来の重さ」が存在している時には、ゲーム理論や決定理論で登場してきたものとは全く別の系統のロジックや意思決定原理が機能し、生き残ってきているはずだ。この本で「未来傾斜原理」と呼んでいるものは、まさにその好例である。
未来傾斜原理とは、過去の実績や現在の損得勘定よりも、未来の実現への期待に寄り掛かって意思決定を行うという原理である。もし仮に「未来の重さ」が非常に大きければ、その未来への期待に寄り掛かり傾斜した格好で現在を凌いで行こうという行動につながることは容易に想像できる。これこそが未来傾斜原理に則った行動なのである。均衡や安定へのパスを指し示すからではなく、まさに未来そのものへのパスを指し示すという点で、未来傾斜原理は説得的である。しかも、未来傾斜原理自体は、「未来の重さ」の軽重にかかわらず、意思決定原理として機能しうる。
日本企業でごく普通に観察される意思決定原理は、この未来傾斜原理である。例えば、日本企業のもつ強い成長志向、より正確に言えば、今は多少我慢してでも利益をあげ、賃金や株主への配当を抑え、何に使うかはっきりしていない場合でさえ、とりあえずこつこつと内部留保の形で、将来の拡大投資のために貯えることは、未来傾斜原理の典型的な発露である。自分が定年退職を迎えるまで自分の会社が存続しているかどうかもわからない場合でさえ、こうして未来傾斜原理に則った意思決定が行われる。
実際、日本企業では、「未来の重さ」を表す指数の一種と考えられる見通し指数によって、職務満足も退出願望もほぼ説明が可能であることが約4,500人分の調査データから明らかになる。しかも「未来の重さ」が大きくなるほど、現在の職務満足は退出願望には結び付かなくなるという未来傾斜的な傾向も見られる。
さらに別の約23万人分の調査データでは、パーソナリティー的な「未来の重さ」を表しているはずの未来傾斜指数が、見通し指数と同様の傾向をもつことがわかったが、従業員と内定者(大学生)を対象に、見通し指数と未来傾斜指数を同時に調べてみた結果、
ということがわかった。つまり日本では、「未来の重さ」の大きい企業には、それに合ったパーソナリティーの人が集い、そしてまた「未来の重さ」を高めると考えられるのである。個人も企業も、まさに「未来の重さ」に導かれて行動している。
日本企業とその従業員との関係における「未来の重さ」の存在は、実は、日本的経営論の中で繰り返し、かつ一貫して主張されてきているものの一つである。日本企業では、雇い主は従業員を解雇あるいは一時解雇しようとはしないし、また従業員も辞めようとしないということが指摘され、終身コミットメントと呼ばれているが、このことはまさにその典型であろう。もちろん、すべての日本企業がそうだと言っているわけではない。しかし、少なくとも歴史ある大企業についてはそうだったと言っていいだろう。日本経済と日本企業の活躍の度合によって、日本的経営に対する評価が大きく振れる中でも、終身「雇用制度」はともかく、終身「コミットメント」は戦後、一貫して指摘されてきたのである。バブル崩壊後でも、依然として、日本における終身コミットメントは国際比較の点からは特徴的であることも調査結果からわかっている。そして終身コミットメントをベースに、生活費保障給型の賃金体系がとられてきたように、終身コミットメントの示唆しているこの「未来の重さ」が、日本では企業とその従業員を未来傾斜型システム採用に導いてきたのである。
「未来の重さ」はモデルの中に既に確率が組み込まれてしまっているような場合にでさえ、われわれの行動に本当の意味を与え続ける。ゲーム理論や決定理論では、確率が入ってくると、いわゆる期待効用原理で意思決定を行なうことが合理的である。それは数学的にも証明できてしまうほどきれいなもので、もちろん均衡も存在する。
しかしモデル上の確率は、期待効用を計算する際の加重平均の単なる weight にすぎない。現在価値に直して清算してしまうような未来に、本当に意味があるのだろうか。実は、確率が入ってくるような状況、より正確にいえば、「未来の重さ」が存在するような状況に置かれた途端、我々の仕事観、世界観は大きく変わってしまっているのである。リスクや不確実性のある未来だからこそ、過去の実績や現在の損得勘定よりも、今は、多少無理をしてでも未来に向かってチャレンジし、成長し、より大きな未来の実現に努力することの方が大切になるのである。まさに未来傾斜原理が機能し始める。未来は残すことにこそ意味があるのである。
事実、ワーク・モティベーションの世界では、「未来の重さ」の下では期待効用原理は色あせ、それとは入れ替わりにチャレンジの概念が大きな意味を持ち始める。「未来の重さ」が存在しているところでは、チャレンジの概念が示唆しているように、自ら成長し、そして育てることの中にこそ、未来の本当の価値があるのである。そのことは、日本企業の調査データでも、チャレンジに基礎を置いた自己決定仮説が成り立っていることから確認される。そして、そのことと表裏一体の現象であるが、日本企業では、従来の外的報酬を基礎に置いた動機づけモデルでは説明の付けられないような現象が見られる。その代表が「ぬるま湯的体質」である。
ぬるま湯感を説明するための枠組みとして「体感温度仮説」が検証され、湯温として組織のシステムの変化性向を表す指数である「システム温」と、メンバーの組織人としての変化性向を表す指数である「体温」との温度差によってぬるま湯感が説明できることがわかった。この変化性向の概念こそが、チャレンジの概念と密接に結び付いたものだったのである。そして実際問題として、企業でぬるま湯感が発生する際には、その企業のまさに成長性が発生要因として大きな位置を占めることもわかってきた。
ぬるま湯の現象が日本企業で多く観察されるということは、まぎれもなく、日本企業に勤める多くの従業員が、少なくとも動機づけの場面においては、期待効用原理の世界ではなく、未来傾斜原理の世界に住んでいるということを示している。実際、ぬるま湯の状態は期待効用理論で考えられているような外発的動機づけの存在しない状態なのに、組織に貢献している状態だったこともわかっている。「未来の重さ」が存在するところでは、チャレンジし、自ら成長し、そして育てることにこそ、本当の価値がある。期待効用的な外発的動機づけは色あせ、意味を失っていくのである。
近代組織論の考え方を簡潔にまとめると、(1)人間は限られているとはいえ、合理的に意思決定を行うことができるが、(2)それを可能にするのが組織という装置であり、これを使って環境への適応を図っている、ということになる。しかし、人間は決定理論的な合理性に閉じこもって生きているわけではないし、また生きられるわけでもない。「未来の重さ」が存在しているところでは、組織の中にあってさえ、大きな問題にぶつかって立ち往生したり、既に述べたようなチャレンジを繰り返していく。
実際、その後、素朴な意思決定論には馴染まない現実の意思決定状況を説明するための分析枠組みとして、ゴミ箱モデルが提唱されるが、このゴミ箱モデルのシミュレーションを行った結果、注目すべき現象として「やり過ごし」が浮かび上がってきた。日本企業における調査データによっても、日常の組織的行動の中で、やり過ごし現象がごく普通に発生していることが確認されている。さらに、ゴミ箱モデルと密接に関連した無政府度と呼ばれる指数の値が高いほど、やり過ごし現象が発生していることも調査データから明らかになった。
しかし、いずれにせよ、日本企業では、部下が上司の指示をやり過ごすことを必ずしも「悪い」現象として決めつけず、駆逐することもしないという現実がある。むしろ暗黙のうちに容認する傾向がある。それは「未来の重さ」が存在しているからなのである。やり過ごしてしまうことは確かに「コスト」になるには違いないのだが、しかし「未来の重さ」が存在しているところでは、将来の管理者や経営者を育てるためのトレーニング・コストあるいは選別コストであり、単なる無駄には終わらないのである。だからこそ、やり過ごしが容認されているケースが多い。現在のコストよりも、チャレンジさせ育てることに重きを置く、これも未来傾斜原理の発露にほかならない。
ところで、やり過ごしを許容したとして、それが不首尾に終わったときには一体どうしたら良いのだろうか。これについての妙案はない。企業がトレーニング・コストや選別コストを覚悟するのは当然としても、結局は、誰かが尻ぬぐいをしなければ、組織は回っていかないのである。実際、企業を調べてみると、課長あるいは係長クラスでは、いわば職場の尻ぬぐい的な仕事をさせられていることが、業務の多忙感につながっていた。尻ぬぐいをする中心は「係長」に相当する職場リーダー達である。
なぜそうなってしまうのか。彼らこそが、日本企業の人材育成の要を担っているからである。やり過ごしのように意思決定を部下に任せてみるという場面だけではない。自分で片付けた方が速くて正確であるようなルーチンに近い仕事についてさえも、とりあえずは部下に任せてやらせてみて、仕事を覚えてもらう。それで結果的にうまくいかなかった場合には、覚悟を決めて自分が尻ぬぐいに回るのである。彼らが先輩にそうしてもらったように、彼らもまた後輩を育てている。そしてその後輩が次の世代を……。「未来の重さ」の存在しないところでは、このような未来傾斜型の人材育成システムは機能しない。「未来の重さ」が尻ぬぐい的行動に意味を与えているおかげで、人材育成を組み込んだままでも、日本企業の組織的行動やシステムは破綻をきたさずに済んでいるのである。
私は企業の人の話を聞くのが大好きなのだが、中堅クラスの人のもつ危機感には大変なものがある。いま日本全体が変革期にあり、企業環境が大きく変わっている中で、うちの会社はうまくやって行けるのだろうかという危機感である。そのためには、社内にゆらぎを起こして、組織を環境適応させる必要があるという主張も多い。しかし、果たして本当にそうだろうか?
経営学の世界では、1970年代、日本でも米国でも、環境適応理論(コンティンジェンシー理論)と呼ばれるものが大流行した。そして、最適な組織構造や管理システムが市場・技術環境によって条件付けられて決まるのだという膨大な(しかし一貫性には欠ける)調査結果の山が残された。しかし、いまやそれを振り返る者はいない。別に定説にたどり着いたわけではない。環境に対する受動的な適応のアイデア自体が魅力を失ったからのように私には思える。それでは、実際の企業は何をしてきたのだろうか?
企業環境との関係で言えば、まずは環境変化を能動的にビジネス・チャンスとして生かすことである。人口、所得、技術の変化によって生み出された資源運用の機会とニーズをビジネス・チャンスとして生かすのである。そして、企業は事業活動を量的に拡大し、地域的に分散し、新しい事業分野に進出する。つまり成長する。こうして企業に新しい資源、新しい活動分野が増加すると、次には、それらを調整・評価・計画するための組織づくりが必要になるのだが、実は、組織づくりをタイムリーに行うこと自体が大変なことだったのである。
チャンドラー(Alfred D. Chandler, Jr.)はその著書『経営戦略と組織』(Strategy and Structure, 1962)の中で「組織は戦略に従う」("Structure follows strategy")という有名な命題を唱えた。ここでの戦略は正確には成長戦略の意味なのだが、 follow は成長戦略に従った組織構造をとるという意味だけではない。組織づくりが、成長戦略に伴う成長の時間的に「後に続く」の意味も込められていた。それでは、なぜ組織づくりが成長に遅れてしまうのか? チャンドラーによれば、経営者が日常業務に熱中し過ぎたり、あるいは組織づくりが経営者自身の地位や権力を脅かすと感じたりするために、組織づくりが遅れてしまうのである。しかし少なくとも、これまで成長を続け生き延びてきた大企業は、たとえ遅れをとったとしても組織づくりに成功してきたことには違いない。
例えばGMがそうだったといわれる。チャンドラーによれば、GMの創立者ウィリアム・デュラントは、米国ミシガン州フリントで保険の外交員から身を起こして馬車会社で成功すると、それを人に任せ、自分は個人事務所をニューヨークに移す。そして、倒産したフリントの自動車会社ビュイックを買い取ると、馬車会社の工場と人員を利用して、米国第1位の自動車メーカーにし、1908年、持株会社ゼネラル・モーターズ(General Motors; GM)を設立する。それから2年弱の間に、ビュイックだけでなく、オールズ・モーター製作所、キャディラックなど自動車会社10社、さらに部品・アクセサリー会社等と、ただひたすらに買いあさる。しかし組織づくりをしなかったために、1910年のちょっとした景気後退で、部品業者や労働者に支払う資金にも不足し、不良在庫を抱えて、経営権はデュラントから銀行団へと移ってしまった。
銀行団は、外への拡張よりも組織づくりに強い関心を持った。まずGM傘下の多くの子会社を整理統合し、本社機構をニューヨークからデトロイトに移し、主な傘下会社の社長で構成する幹部連絡会議を設立した。さらに、本社の全社的な管理を補佐する資材部、会計部、生産部の三つの常設部門を設置し、傘下会社間の資材連絡会議を設けた。
しかし、デュポン家から多額の資金援助を受け、自動車会社シボレーを買収したデュラントが1916年にGMに復帰して社長に就任すると、組織づくりはまた忘れ去られ、本社資材部や幹部連絡会議、資材連絡会議は廃止、個人事務所と会社の小規模な財務部門はまたもやニューヨークに移ってしまった。彼は既存の自動車工場の生産台数を増やし、会社を買収し続ける。その間、1917年にGMは持株会社から事業会社へと法律上、変更されたものの、この拡張期を通して、デュラントは依然として組織づくりには何の関心も示さなかった。
第一次世界大戦が終わって、1919年から20年前半まではGMの大拡張の年となり、工場と設備に巨費を投じ、多数の部品会社を買収した。同時に各事業所長は勝手に資材を確保し、在庫を積み増す。しかし自動車市場は崩壊し、1920年10月末には納入請求書や賃金など当面の支払いにも事欠く事業所長が続出する。この危機でGMの株価は急落、デュラントはついに11月20日、社長を辞任する。その10日後、ピエール・デュポンが社長に就任すると、年内には、GMの子会社の社長をしていたアルフレッド・スローンのGMの組織改革案を承認、ただちにこれを実施し、スローンをGMの副社長にした。
この組織改革により、各事業部は自動車、アクセサリー、部品、雑製品の四つのグループに分けられ、それぞれのグループを担当する本社幹部が置かれた。そしてこれに専門スタッフをつけて、多数の現業事業部を調整、評価し、目標と政策を策定する総合本社を作り出した。こうして1921年はGMの組織づくりの年となり、雑多な自動車関係の事業の寄せ集めにすぎなかったGMは、一つのまとまった組織へと変態を遂げ始める。さらに、シボレー、オールズ、オークランド、ビュイック、キャディラックという順に低価格車から最高級車まで製品系列を合理的に秩序付け、自動車事業部間での競争を減らして調整を可能にした。また、1920年危機の原因が過剰在庫であったことから、4ヶ月先までの販売見通しを各事業部に出させて、総合本社がこの見通しを承認してはじめて各事業部が必要な資材を購入できることにした。こうして、1925年にはGMの組織が完成する。自動車市場でのGMのシェアは1924年の18.8%から、1927年には43.3%に上昇し、1929年の大恐慌で新車需要が急激に減ったときでさえも、GMの利益にはほとんど影響しなかったのである。
経営で一番大切なのは、苦しい時、危機的状況に陥った時、どのようにそれを乗り切るかである。スローンの組織改革案のような完成度の高いものでなくてもよい。しかし、どんな形であれ、経営者が未来を指し示し、見通しを与えることが、危機的状況を乗り切るための必須条件である。
藤本=ティッド(1993)のトヨタの事例は興味深い。1937年、豊田自動織機は自動車部を分離してトヨタ自動車工業株式会社を設立し、翌1938年には月産2000台規模の挙母工場が完成したが、さあこれからという時に日中戦争が勃発し、第二次世界大戦、そして1945年8月の終戦を迎えることになる。9月にはトヨタはGHQの許可を得て、1930年代に購入した古い機械を利用する形でトラックの生産を再開したが、終戦直後、米国の量産工場の生産性はトヨタの約10倍もあったという。ところがこんな状況下で、豊田喜一郎は、3年以内に米国の生産性に追い付くという途方もない大胆な目標を打ち出す(実は、生産量といわずに生産性といったところに、最適チャレンジを与えるという経営者の妙がある)。実は技術者の間では、米国企業との力の格差はもっとあると思われていたというから、10倍と言ってしまうこと自体がホラのようなものだが、案の定さすがに3年ではこの目標は達成できなかった。しかしトヨタは1955年まで10年かかって米国の自動車メーカーの生産性に追い付く。
このように途方もない無茶な目標でも、しかるべき人がしかるべき時に宣言すれば、そしてある程度の長期にわたって変更撤回されなければ、目標は人々の迷いを取り払い、人々を元気づけ、人々を方向づける。その際、それが最適であるかどうかはあまり重要な問題ではない。見通しが立つこと自体に、経営的観点からはある種の意義が存在する。
ワイク(Karl E. Weick, 1987)は、次のような面白い話を紹介している。それはある軍事演習でのこと。ハンガリー人の小隊を率いる若い少尉は、アルプス山脈の凍てつく荒野に偵察隊を送り出した。ところが、その直後から雪が降り始める。雪は二日間降り続き、送り出した偵察隊は戻ってこない。安否が心配されたが、三日目になって偵察隊は帰ってきた。彼らがいうには「われわれは道に迷ったとわかって、もうこれで終わりだと思いました。するとそのとき隊員の1人がポケットに地図を見つけたのです。その地図のおかげで冷静になれました。われわれはテントを張って吹雪を耐え抜きました。それからその地図で方位、位置を確かめながらここに着いたわけです。」少尉がこの命の恩人となった地図を手にとってじっくり見ると、驚いたことに、それはアルプス山脈の地図ではなく、ピレネー山脈の地図だったのである。
つまり、道に迷ったときにはどんな地図でも役に立つ可能性があるし、混乱しているときにはどんな見通しでも役に立つ可能性がある。企業が危機に直面した場合を想像してみるといい。激変する環境に、組織の中まで混乱の渦に飲み込まれようとしているまさにそのとき、誰かが(多分、経営者が)混乱の渦の直中にあって、毅然と立ちはだかり、進むべき道を指し示してパニックを静めなければ、組織はそのまま崩壊に至るのである。
それは外部環境に適応するためにパニックになって右往左往するよりは、むしろ外部環境との間には一線を画して毅然として自ら予測し、自らの優先順位に基づいて自律的に行動することで、自らの能力や優位性を有効に発揮していこうという姿勢である。それは変温動物としてではなく恒温動物として、しかも服を着込むことも冷暖房をすることもできる知的動物としての生き方の延長線上にあるといっていいのではないだろうか。
そのためには本当の意味での経営者が必要なのだ。ナイト(Frank H. Knight)は、その著書『危険・不確実性及び利潤』(Risk, Uncertainty and Profit, 1921)の中で、優れた経営的能力の意味を次のように指摘した。他人を有効に統制する力。何をなすべきか決定する知的能力。しかし何より重要なことは、自らの判断と力に対する確信の程度や自らの所信に基づいて行動し「冒険する」気質である。つまり確信と冒険心に富んだ経営者が危険を引受け、疑い深く臆病な一般の社員に対して、安定的な契約的収入を保証する。その見返りとして、経営者は、変動するが、額も大きい利潤を受け取ることになるというのである。ゆらぎを起こすことではなく、確信に満ちてゆるがぬことこそが経営者の最初の仕事なのである。そのおかげで、社員は混乱に陥ることなく、計画的で秩序ある行動をとることが可能になる。
経営者の仕事が、確信に満ちてゆるがぬことだとして、なぜそれが必要になるのだろうか。実は、従業員に見通しを与え、明るい未来を指し示すことは、「未来の重さ」を従業員に体感させることにつながるからである。「未来の重さ」に導かれた未来傾斜型の企業こそが、その場限りの「今」の充実感、快楽を求める刹那主義型システムとの競争に生き残ってこられたからである。
それでは、この節の最初の問いに戻ろう。実際に生き残ってきた企業は一体何をしてきたのか?
要約して言えば、あらゆる環境変化をビジネス・チャンスとして生かして成長することに邁進する一方で、組織づくりを怠らず、苦しい時でも凌いできたのである。つまり未来傾斜原理に則って行動してきたのである。そして、それを可能にしたのは、「未来の重さ」だった。確信に満ちてゆるがず、見通しを与え続けた経営者だけが、その「未来の重さ」を従業員の手のひらにずっしりと体感させることに成功し、そのことを可能にしてきたのである。まさに未来を残す仕事をしてきたのである。
1986年に初めての調査を行って以来、日本生産性本部(Japan Productivity Center)経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの参加者の所属企業を対象にした調査を年1回のペースで「組織活性化のための従業員意識調査」として行ってきた。1993年度からは社会経済生産性本部(Japan Productivity Center for Socio-Economic Development)経営アカデミー『組織革新』コースと改称しているが、本書では、これらの一連の調査を「JPC調査」と総称している。
1987年に「ぬるま湯的体質」をテーマにした調査を初めて行って以来、ぬるま湯的体質に関する質問は何らかの形で取り上げられてきている。JPC調査の開始当初は、調査方法の点で試行錯誤を重ねていたが、ここでは主要な質問項目と調査方法を確定した1990年の調査以降の調査の方法を中心にまとめておくことにする。「組織活性化のための従業員意識調査」の具体的な実施方法などについては、高橋(1992c, ch.6)に詳しい。
JPC調査の1987〜1996年各年の調査は、JPC87調査、JPC88調査、JPC89調査、JPC90調査、JPC91調査、JPC92調査、JPC93調査、JPC94調査、JPC95調査、JPC96調査と呼ばれるが、基本的にはほぼ同じ手続き、手順に従って行われた。特に主要な質問項目と調査方法を確定したJPC90調査以降は、極力、調査方法を固定するように努めている。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査、そしてその調査結果を手にしてから行なったフォローアップのヒアリング調査の3段階に分けて行われる。
第1段階のヒアリング調査では、毎年6月頃に、合宿形式で集中的に1社平均2時間程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われる。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつと筆者からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、問題意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行い、この過程でリストに挙げられた様々な質問項目を最終的に筆者が整理して、これをYes-No形式の質問にまとめるのである。JPC96調査では、選択肢の「Yes-No」は「はい・いいえ」に切り替わっているが、基本的な形式に変更はない。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行う。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の組織単位を選ぶ。「組織単位」という概念はJPC90調査から明示的に用いられるようになったが、いわゆる「職場」にほぼ対応している。それまで職場を設定する際に、漠然とではあるが、暗黙のうちに使っていた基準を整理して、(1)組織図上で同一の上司を持つ職場もしくは職場の集合で、(2)組織単位が複数の「機能区分」(事務・スタッフ部門、技術・製造部門、研究・開発部門)にまたがらないように注意しながら、(3)正社員の人員規模が50人程度になるように、設定するという基準にまとめ、この基準を一応の目安にして「組織単位」として明確に定義したのである。ただし、(3)の基準よりは(2)の基準を優先したので、「50人」にこだわると組織単位が複数の機能区分にまたがってしまうような場合には、人員規模を小さくして組織単位を設定している。
こうして設定された組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行うのである(高橋, 1992c, ch.1; ch.6)。このような方法によって調査対象に選ばれた人に対して、毎年8月25日から9月5日までの間のある水曜日に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、翌週の月曜日までに回収するという形で、留置法によって質問票調査が行われる。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行うことになっている。
JPC調査の1987〜1996年各年の調査、つまりJPC87調査〜JPC96調査の実施状況の詳細については、表A.1、表A.2を参照のこと。この他、本書の中で用いられた指数の各年の平均、標準偏差については、改良版体感温度測定尺度(JPC90〜JPC96調査)は表A.3、自己決定度・見通し指数・満足比率(JPC90〜JPC96調査)は表A.4、無政府度・尻ぬぐい度(JPC94〜JPC96調査)は表A.5に示してある。
表A.1 JPC調査の実施状況
| 質問票調査実施日 | 質問 項目数* | 会社数 | 組織 単位数 | 配布数 | 回収数 | 回収率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配布(水曜日) | 回収(月曜日) | |||||||
| JPC87調査 | 8月26日 | 9月 7日 | 50 | 11 | 39 | 690 | 580 | 84.1% |
| JPC88調査 | 8月31日 | 9月 5日 | 60 | 8 | 37 | 770 | 626 | 81.3% |
| JPC89調査 | 8月30日 | 9月 4日 | 134 | 10 | 73 | 1,392 | 1,228 | 88.2% |
| JPC90調査 | 9月 5日 | 9月10日 | 75 | 9 | 39 | 959 | 853 | 88.9% |
| JPC91調査 | 8月28日 | 9月 2日 | 75 | 6 | 30 | 1,017 | 907 | 89.2% |
| JPC92調査 | 9月 2日 | 9月 7日 | 45 | 7 | 27 | 847 | 740 | 87.4% |
| JPC93調査 | 8月25日 | 8月30日 | 60 | 6 | 33 | 1,275 | 1,160 | 91.0% |
| JPC94調査 | 8月31日 | 9月 5日 | 60 | 8 | 39 | 885 | 829 | 93.7% |
| JPC95調査 | 8月30日 | 9月 4日 | 64 | 6 | 41 | 1,187 | 1,061 | 89.4% |
| JPC96調査 | 9月 4日 | 9月 9日 | 62 | 6 | 37 | 844 | 801 | 94.9% |
| JPC90〜JPC96調査小計(改良版で実施) | 48 | 246 | 7,014 | 6,351 | 90.5% | |||
| JPC87〜JPC96調査計 | 77 | 395 | 9,866 | 8,785 | 89.0% | |||
表A.2 JPC調査の対象の概況
| 男子比率 | 管理者比率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| JPC87調査 | 70.8% | 22.6% | 35.0 |
| JPC88調査† | 99.2% | 100.0% | 42.3 |
| JPC89調査 | 78.6% | 16.2% | 35.4 |
| JPC90調査 | 80.8% | 23.3% | 34.9 |
| JPC91調査 | 87.2% | 29.0% | 36.6 |
| JPC92調査 | 76.4% | 25.1% | 35.5 |
| JPC93調査 | 86.8% | 18.1% | 38.0 |
| JPC94調査 | 72.0% | 24.6% | 35.7 |
| JPC95調査 | 77.2% | 23.8% | 37.3 |
| JPC96調査 | 86.8% | 16.8% | 39.4 |
表A.3 改良版体感温度測定尺度の平均(JPC90〜JPC96調査)
| システム温 | 体温 | ぬるま湯比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 平均 | 標準偏差 | N | 平均 | 標準偏差 | N | % | |
| JPC90調査 | 830 | 2.13 | 1.41 | 831 | 3.08 | 1.49 | 849 | 56.9 |
| JPC91調査 | 888 | 2.23 | 1.52 | 893 | 3.19 | 1.30 | 903 | 68.5 |
| JPC92調査 | 721 | 1.95 | 1.47 | 723 | 3.13 | 1.34 | 730 | 74.1 |
| JPC93調査 | 1,137 | 2.25 | 1.56 | 1,139 | 3.20 | 1.28 | 1,157 | 62.3 |
| JPC94調査 | 815 | 2.00 | 1.52 | 810 | 2.96 | 1.37 | 825 | 72.0 |
| JPC95調査 | 1,051 | 1.90 | 1.52 | 1,051 | 3.13 | 1.38 | 1,058 | 75.3 |
| JPC96調査 | 788 | 1.81 | 1.49 | 786 | 3.08 | 1.33 | 799 | 72.6 |
| 全体 | 6,230 | 2.05 | 1.51 | 6,233 | 3.12 | 1.36 | 6,321 | 68.6 |
表A.4 自己決定度・見通し指数・満足比率の平均(JPC90〜JPC96調査)
| 自己決定度 | 見通し指数 | 満足比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 平均 | 標準偏差 | N | 平均 | 標準偏差 | N | % | |
| JPC90調査 | 831 | 2.72 | 1.66 | - | - | - | 850 | 46.9 |
| JPC91調査 | 889 | 3.22 | 1.46 | - | - | - | 904 | 50.6 |
| JPC92調査 | 716 | 2.77 | 1.46 | 710 | 2.08 | 1.40 | 738 | 46.1 |
| JPC93調査 | 1,123 | 2.83 | 1.53 | 1,133 | 2.21 | 1.40 | 1,155 | 48.7 |
| JPC94調査 | 816 | 2.72 | 1.52 | 805 | 2.12 | 1.44 | 824 | 48.4 |
| JPC95調査 | 1,051 | 2.86 | 1.52 | 1,040 | 2.16 | 1.46 | 1,059 | 49.4 |
| JPC96調査 | 784 | 2.93 | 1.56 | 784 | 2.41 | 1.51 | 796 | 48.0 |
| 全体 | 6,210 | 2.87 | 1.54 | 4,472 | 2.20 | 1.45 | 6,326 | 48.4 |
表A.5 無政府度・尻ぬぐい度の平均(JPC94〜JPC96調査)
| 無政府度 | 尻ぬぐい度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 平均 | 標準偏差 | N | 平均 | 標準偏差 | |
| JPC94調査 | 815 | 1.69 | 0.79 | 817 | 2.59 | 1.44 |
| JPC95調査 | 1,044 | 1.60 | 0.80 | 1,054 | 2.73 | 1.52 |
| JPC96調査 | 786 | 1.50 | 0.82 | 790 | 3.15 | 1.47 |
| 全体 | 2,645 | 1.60 | 0.81 | 2,661 | 2.81 | 1.50 |
「まえがき」にも書いたが、数年前、近代組織論の体系をその源流である決定理論、さらにゲーム理論にまで遡って位置付けてみようという意図から、私は『組織の中の決定理論』(朝倉書店, 1993年)という本を書いた。本書はある意味ではその本の続編であるといえなくもない。しかし、そこから出発してこの本に到達するまで、私は随分と知的な冒険と執拗な調査を繰り返してきたように思う。それでも足らずに、私は用心深く、この本の基本的なアイデアとコンセプトを『できる社員は「やり過ごす」』(ネスコ/文藝春秋, 1996年)という一般向けの啓蒙書の中に織り込んで、一般の読者からの反応も探ってみるた。その結果を見て、ようやく私は自分の出した結論に確信がもてるようになってきたのである。
ところで、『できる社員は「やり過ごす」』を執筆し、出版するに当たって、私は密かに三つの仮説を立てていた。そのうちの二つは「(1)日本企業、特に大企業に勤める多くの日本人にとって、ここに書いてあることは当たり前のことであって、くどくど説明される必要もなく直感的に理解できる内容のはずである。(2)にもかかわらず、すべての日本人にとってそうだというわけではない。欧米流の近代経済学や経営学などを通して欧米の感性を身につけた人やバリバリの外資系企業に勤めるかなりの部分の人にとっては、感覚的に受け入れがたい違和感があるはずである。」というものである。
特に、私の原稿を読んで「それって当たり前の話ですよね」と感想をもらす(1)を絵に描いたような編集の人に対しては、(2)の部分を強調して、その意義を説明した。実際、これまでのところ、その本に関しては、この仮説通りの反応が得られており、全く正反対の二種類の反応があったのである(ただし、(1)が圧倒的な多数派だが……)。つまり、仮説(1)(2)は立証されたということになる。
残されたもう一つの仮説は、「(3)日本の大企業は、大企業になったから、ここに書いてあるような現象が観察されるようになったのではなく、ここに書いてあるような現象が発生するようなシステムをもっていたからこそ、大企業に成長してきたのである。」というものである。その根拠はこの本の中で、より正確な形で述べてきたつもりだが、この仮説の方はどうなるだろうか。多分、この仮説も立証されるだろう。ただし、それにはさらにあと数十年、あるいはそれ以上の時間がかかるかもしれない。
本書は「われわれは一体何に導かれて行動しているのだろうか?」という問に答えるために、既発表論文をまとめる作業から始められたが、草稿の段階で何度も全体構成を変更し、そのたびに大幅な内容の入れ替えと加除とを繰り返したために、いまやほとんどその原形をとどめていない。調査データも最新のものに入れ替えてしまっている。かろうじて、部分的に節レベルでの対応関係が残っているところがあるが、基本的に書き下ろしだと考えていただいた方がいいだろう。
この本は、実に多くの方々に支えられて成り立っている。すべての方のお名前を挙げることはできないし、挙げるとかえってご迷惑をおかけすることになるので、はぶかせていだくが、本書が基礎にしている調査データの大部分は、(財)社会経済生産性本部において、経営アカデミー(JPC調査)、経営開発部(CALUTE調査)およびメンタル・ヘルス研究所(JMI調査)のご協力の下に得られたものである。特にJPC87〜JPC96調査は本書のバックボーンをなし、この10年間毎年行われ、今なお継続中の繰り返し調査である。こうした一連の調査を物心両面で支えていただいた同本部の木村滋、原賢一、杉浦修一、佐々木昌彦、新井一夫、そして根本忠一の各氏には、心から感謝申し上げたい。この他の調査に際しては、(財)吉田秀雄記念事業財団(CC&C調査)、(財)高年齢者雇用開発協会(人事モデル調査)、東京大学経済学部附属日本産業経済研究施設(IT調査)の研究助成を受けることができた。また(財)東京大学出版会の黒田拓也氏には草稿段階で建設的なコメントをいただき、おかげで本書の構成を思い切ってすっきりさせることができた。この場をお借りして御礼申し上げたい。
最後に、あらかじめ予想される読者からの質問に対して、私なりに現時点での回答を記しておこう。この本は日本企業に勤める日本人サラリーマンの意思決定原理について書かれたものである。それでは、なぜ「日本的」と言えるのか? 他の国との比較は行なっているのか?
経営学の分野では、本書第3章でも取り上げているように、かつてホフステッド(Geert Hofstede)が、多国籍企業IBMで1967年〜1973年に40ヶ国のIBMの営業部門、管理部門の延べ約7万人分のデータを集めて分析し、空前絶後の調査研究と言われた。それによると、「日本」は収入を重視し、上司や協働はあまり重視しないという傾向が40ヶ国中で突出して一番強いという調査結果も出ている。しかし、これでは世間一般の常識にも反しているように思えるが、どうだろうか。調査データがある以上、確かに日本IBMはそういう企業なのかもしれないが(個人的には違うように思えるが)、統計屋的な常識からすれば、これは調査設計のミスというべきだろう。
とはいうものの、本書第3章にその一部が紹介されているように、最近、自分でも国際比較調査に着手してみて、国際比較は正直言って難しいと感じる。本書で取り上げている「終身関係」を確認するような作業は、いわば事実の精度を高める作業なのでなんとかなる。しかしこうした特殊な場合を除いて、出てきた統計数字が一体何を意味しているのか、その数字だけを見ていてはよくわからないのである。
そのことは拙著『経営統計入門』(東京大学出版会, 1992年)でも既に指摘している通りで、別に国際比較調査に限ったことではない。しかし国際比較調査では、どうしても統計数字を拠り所として、その差異をことさら強調することで、国、文化を特徴づけるアプローチにはまってしまう。そのため、なおのこと怪しい。意地悪な見方をすれば、ホフステッドの研究も、計量的な分析を覆っているのは、ローマ帝国まで登場するような延々とした「こじつけ」話にすぎない。多分、データに合わせて、どんな話でもしてくれるのだろうと思えてしまう。しかし、そんなものが科学の名に値するものだとは思えない。私には「国際比較」データの幻想に酔っているだけのように見える。それに学問的な価値がないとは思わないが、自省の念もこめて言わせてもらえば、かくして「学問的な業績」は量産され、垂れ流され、そして消費されていくのだ。
実は、社会心理学的な実験も含めて、言語や文化を超えて、ある統一した切り口の「国際比較」データなるものが、単体では独立に存在しえないのではないかと私は直感している。例えば、日本では、職務満足を感じている人の割合が他の国と比べても低いというのは昔から比較的よく知られた事実だが、だからといって日本人が不幸か(Fortune, 1997年1月13日号 p.92 では "unhappy" と形容している)といえば、それは全然違う問題である。日本では、今の仕事に満足してしまっていていいのかという「美学」の問題も絡んでくる。それに、「未来の重さ」が存在するところでは、そうでないところと比べて、もともと今の満足にはさほどの重要性はなく、チャレンジする気持ちの方が大切にされてもいる。それはこの本の中で指摘してきた通りである。つまり、個々のデータはそれぞれの国、文化の全体像の中で理解しなくてはならないのだ。
私自身はこの本のもとになっている日本企業に関する研究を進めていた段階で、一つの選択をしたように思う。一気に「世界」「国際」という名の巨大な泥の城を作り上げるのではなく、まずは一個一個レンガを焼き固めて、「日本」という名のレンガ作りの塔を土台から積み上げていく作業に、今、私はようやくとりかかったばかりなのである。確かな事実と理屈で固めようとすると、レンガ作りは時間ばかりがかかる大変な作業だが、そのうち手慣れてくれば、「アメリカ」をはじめとする他の名の塔も作れるようになるかもしれない。いずれにせよ、見比べることができるようになるのは、複数の塔が積み上がってきて、それぞれの塔の全体像がおぼろげながらにでも見えるようになってきた後の話である。
正直言うと、私は、未来傾斜原理と「未来の重さ」で、ようやく日本企業に勤める日本人サラリーマンの普通の日常感覚と価値観を説明する糸口をつかんだという感じはしている。しかし、それ以上のものではない。日本だけのものだという経験的証拠もまだないし、おそらくどこの国でも、成功して成長を遂げた企業は大同小異ではないかという予感もしている。
作業は始まったばかり。とにかく、急がず、あわてず、私に時間をください。
同じ言葉を謝罪と祈願の念を込めて、妻敦子と息子伸之にも。
1997年4月
高橋伸夫