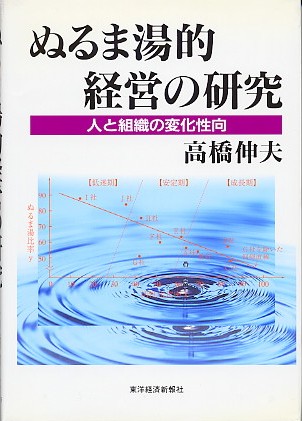
本書は日本企業の「ぬるま湯的体質」の解明に挑戦している。この純和風な上にあいまいな概念との悪戦苦闘の中で、「変化性向」という概念を創り出した。変化性向とは、現状を打破し変化をもたらそうとする傾向を指している。人の側の変化性向と経営・組織の側の変化性向を考えることで、どうやらぬるま湯感と職務満足感の発生メカニズムを体系的に説明し、かつ測定する道を探り当てたような感触を今はもっている。
しかし、一つの問題をある程度解決すると今度は別の問題という具合に、新しい問題が次々と浮び上がってきてしまう。最初の問題である「日本企業の中でぬるま湯感はどうして生じるのか?」から始まって、「なぜぬるま湯的体質が企業から問題視されるのか?」「ぬるま湯感を他の要因から予測できないか?」あるいは、ぬるま湯感と職務満足感が共存しているということがわかっているが、「職務満足はどこから来て、なぜぬるま湯感と共存しうるのか?」「ぬるま湯的体質と生産性、職務遂行とはどんな関係にあるのか?」そして、こうした問題に逐一答えていく中で、当初は黒子的存在であった個人の変化性向の重要性が次第に浮き彫りになってくる。個人の変化性向を考えることで、色々な経営現象に説明が付けられるのである。それでは、その「個人の変化性向が企業によってかなり異なるのはなぜか?」
こうした一連の研究課題に対して、本書の第1〜6章がそれぞれ当てられている。第6章冒頭で、こうした内容を「変化性向の枠組み」としてまとめ、要約しているので、本書の全体像を確認、整理するために、あるいは手短に知るためには便利であろう。結果的に、「ぬるま湯的体質」というきわめて日本的なイシューの解明にも、経営学というディシプリンの主要な知見を総動員することになりそうな気配である。
このように、新しい研究課題に次々とぶつかるたびに、理論を考え、調査を企画、実施し、データによって仮説を検証するという作業を5年間繰り返してきた。この間に本書が直接利用している分だけでも「組織活性化のための従業員意識調査」としてのべ44社、4,194人分のデータが集められた。その概要については巻末付録にもまとめてある。その他にも、予備調査として行なったものや、一連の「組織活性化のための従業員意識調査」とは別の機会に行なったヒアリング調査などもあったが、調査手順の違いなどもあって、それらについてはほんの一部しか触れていない。
本書は調査データで検証しながら議論を進めるために、常識的に理解可能な範囲での統計的手法はどうしても使用せざるをえない。しかし多変量解析手法を必要とするような分析は、すべて各章の付録に押し込めたので、読者がその部分を読み飛ばしたとしても本書の理解に差し支えないはずである。本書は基本的には統計学の知識がなくても理解できるようになっている。
それでもその常識的に理解可能な範囲での統計分析をよりしっかり理解したいという読者は、手元にあるごく初歩的な統計学テキスト、あるいは拙著『経営統計入門−SASによる組織分析−』東京大学出版会を参照してほしい。同書は「組織活性化のための従業員意識調査」を例として、実際の調査の仕方も含めて、統計的な分析の基礎を懇切丁寧に解説している。統計パッケージSASを用いた集計・分析も初心者向けに詳述してあるので、本書にあるような調査を実際に自分でやってみたいという読者にも大いに参考になろう。
なお、本書はもともと既発表の論文をまとめる形で書き始められたが、結果的には大幅な書き直しのために、ほとんど原形をとどめないようになってしまった。そのため、対応関係もすっきりしないが、一応、読者の便宜を図って巻末の参考文献リストでの初出年をあげておくと:第1章(1989c)(1990b)、第2章(1990a)(1992b)、第3章(1992c)、第4・5章(1990c)、第6章(1992a)、ということになろうか。
本書がもとにしている調査データの収集の機会と場を与えてくれた財団法人日本生産性本部経営アカデミーにはこの場をお借りして御礼を申し上げたい。特に同本部の新井一夫氏には一連の調査のはじめから親身になって協力していただいた。また本書は原稿の段階で、同本部の経営アカデミーで行なわれた実際の企業人を相手とした講義で何度かテキストとして使用しているし、筆者の勤務する東京大学教養学部教養学科及び同大学院総合文化研究科の授業や非常勤講師を勤める筑波大学大学院経営政策科学研究科の授業でもその原稿を教材として使用してきた。いずれの機会でも授業に参加してくれた皆さんからは貴重な質問、意見を聞くことができたことを感謝したい。本書1冊でどの程度それにこたえられたであろうか。そして東洋経済新報社の足達堅三氏には、編集、校正のみならず、本書の内容を的確に理解された上で、執筆上のヒントまで与えていただいたことに感謝申し上げたい。
最後になるが、本書の執筆のために、夏休みの予定の大半をあきらめてくれた妻敦子と息子伸之に心から感謝したい。
1992年11月
高橋伸夫
本書は純和風の概念である「ぬるま湯的体質」の解明に挑戦している。この問題はやがて、企業業績や職務満足、職務遂行、さらには組織の成り立ちそのものといった組織と経営の問題にも深く広くかかわりをもってくることになるが、この章ではとりあえず、「組織の活性化していない状態」の典型として、日本企業の「ぬるま湯的体質」について探ることにしよう。ぬるま湯の現象はどのような状態のとき発生しているのだろうか? そして、ぬるま湯的体質は組織の活性化にどのような意味をもっているのだろうか?
こうした問題を解明するために、1987年〜1991年の5年間に5回の「組織活性化のための従業員意識調査」を行ない、のべ44社、4,194人分の質問票調査のデータが分析されてきた(詳しくは巻末の付録Aを参照されたい)。こうした一連の調査と分析作業が進められてきた結果、ぬるま湯感と活性化の関係を「変化性向」の概念を基にして体系的に説明するための枠組みが考え出された。この章は、その枠組みを提示し、それを調査データに基づいて検証することを目的としている。なお、この章では、ぬるま湯的体質の解明のために、1987年に実施された調査(以下「1987年調査」と略記)、1988年に実施された調査(以下「1988年調査」と略記)の2回の調査結果を取り上げているが、そのうち1987年調査ではA社〜K社、1988年調査ではA社〜H社と独立別個にラベルを付けることにする。
「ぬるま湯」現象とはどういった組織現象、特に職場内や個人の意欲上の現象を表しているのであろうか。また、ぬるま湯感と職務満足等との間にはどのような関係があるのだろうか。企業のぬるま湯的体質は、組織の活性化していない状態の典型であると、とりあえずは考えているが、本当に、そう考えてしまってよいのであろうか。こうした一連の問題意識に基づいて、ぬるま湯感についての事実発見を主目的として、1987年調査が企画された。
1987年調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1987年度の参加者の所属企業11社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1987年6月12・13の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの11人と筆者の計12人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、ぬるま湯現象を典型とする組織の不活性状態を表していると思われる職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、「個人の仕事に対する姿勢に関する」25の質問項目と、「職場に関する」25の質問項目の計50項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場を構成する正社員に対して、原則として、全数調査を行った。(全数調査の意味、意義、あるいは標本調査ではなく全数調査を行なう理由については、統計学の解説になってしまうので、本書では省略する。興味のある読者は、高橋(1992d, ch.1; ch.6)に解説されているので、それを参照されたい。本書で取り上げられている5回の「組織活性化のための従業員意識調査」はいずれも全数調査である。なお本書では、全数調査では本来意味のない有意性検定の結果を併記するようにしているが、これは判断材料となりうる数字については貪欲でありたいという姿勢の現れと理解されたい。)
各社において選ばれた職場数は1ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数にも25人から154人まで開きがあるが、総職場数は39ヶ所、総調査対象者数は690人、職場当りの平均調査対象者数は17.7人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた11社690人に対して、1987年8月26日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月7日(月曜日)までに回収するという形のいわゆる留置法で質問票調査が行われた。その結果、580人から質問調査票が回収できた。回収率は84.1%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
使用した質問調査票は、ぬるま湯現象を典型とする組織の活性化していない状態を表すと思われる、もしくは、逆に活性化した状態を表すと思われる前述の計50のYes-No形式の質問項目の他に、個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。
そこで、この1987年調査のデータを基にして、ぬるま湯現象について考察していくことにしよう。ぬるま湯現象を典型とする組織の活性化していない状態を表すと思われる前述の50のYes-No形式の質問項目のうち、ぬるま湯感についての、いわば鍵となる質問:
Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。について最初にみてみよう。この質問に対しては、55.4% (316人)がYes、44.6% (254人)がNoと答えている。つまり、調査対象となった人のほぼ半数がぬるま湯感を感じていることになる。
ぬるま湯感を感じているかどうかというこの質問Q1については、会社別には「統計的に意味のある」(以下これを単に「有意な」ということにする)相関が見られたが、性別、年齢階層別、既婚・未婚別、学歴別、職種別、職位別には有意な相関は見られなかった。また、このぬるま湯感と他の質問項目との間の相関係数をみてみると、「職場に関する」質問項目との相関が高いが、「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問項目との相関が全般的に低いという特徴のあることもわかった。このことから、ぬるま湯感は、その人の個人的特性というよりも、会社・職場の特性との関係が深いということがわかった。
しかし、いかに「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問とはいえ、組織の不活性状態を表すと考えていた質問項目との間で相関があまりないということは、組織の不活性状態の代表的な現象としてぬるま湯現象を位置付けることに対して疑問を抱かせる。少なくとも「典型的」とはいえないのではないだろうか。
この疑問は、調査の第1段階のヒアリングで、組織のメンバーの活性化の重要な指標と見ていた職務満足に関するYes-No形式の質問:
Q2. 自分の仕事に充実感を感じている。との相関をみていくと、よりはっきりしてくる。この質問に対し、62.0% (355人)の人がYes、38.0% (218人)の人がNoと答え、ほぼ6割の人が仕事に充実感を感じていると答えている。しかし、この仕事の充実感はぬるま湯感とは異なり、会社別に有意な相関があるだけではなく、性別にみれば男性の方が、年齢階層別にみれば高い年齢階層の方が、既婚・未婚別にみれば既婚者の方が、学歴別にみれば高学歴の方が、職位別にみれば高い地位の方が、より仕事の充実感を感じているという有意な相関がみられるのである。しかも、この仕事の充実感は、「職場に関する」質問項目、「個人の仕事に対する姿勢に関する」質問項目との相関がともに高いという特徴のあることもわかった。つまり、われわれが調査開始当時に抱いていた活性化のイメージとかなりよく合っているということがわかったのである。
実は、この充実感についての質問Q2は、ぬるま湯感と有意な相関のあった、数少ない個人の仕事に対する姿勢に関する質問の一つで、なおかつその中では一番相関係数の大きいものだったのである。しかし、クロス表の形で示すと表1.1のようになり、ぬるま湯感と仕事の充実感の間には有意な負の相関関係があるものの、仕事に充実感を感じている人のほぼ半数がぬるま湯感も同時に感じており、仕事の充実感とぬるま湯感との間にはかなりの重なりが存在していることもわかる。(クロス表の詳しい見方、及び相関係数の一種であるCramer's V、独立性のχ2検定については、高橋(1992d, ch.5)を参照されたい。ここではそうした予備知識がなくても、素直に表1.1を読んでもらえばいい。なお、Cramer's V いわゆる V 係数は、本来、非負であるが、ここで適用されている2×2クロス表では、負の相関があるときには、慣習的にマイナスの符号を付けることが多い。したがって、このとき量的データで一般に用いられる相関係数(Pearsonの積率相関係数)とも等しい値をとることになる。本書も、2×2クロス表については、この慣習にしたがうことにする。)
表1.1 ぬるま湯感と充実感(1987年調査)
| Q2. 自分の仕事 に充実感を感じ ている。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま 湯」だと感じることがある。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 175 (49.9) | 176 (50.1) | 351 (100.0) |
| No | 138 (64.2) | 77 (35.8) | 215 (100.0) |
| 計 | 313 | 253 | 566 |
しかも、会社別に、ぬるま湯感を感じている比率と、仕事の充実感を感じている比率を求め、会社をプロットしてみると、図1.1が得られ、この両者の間には、全体的にはやはり負の相関関係があるものの、C社については、こうした傾向からはずれる特性を示していることがわかった。このC社は、71.7%がぬるま湯だと感じていて、その比率は11社中もっとも高くなっているが、一方、仕事に充実感を感じている者も72.9%もいて、この比率も11社中3番目に高い会社なのである。つまり、C社においては、まさに仕事の充実感とぬるま湯感が共存していることになる。
図1.1 会社別ぬるま湯感・充実感散布図(1987年調査)
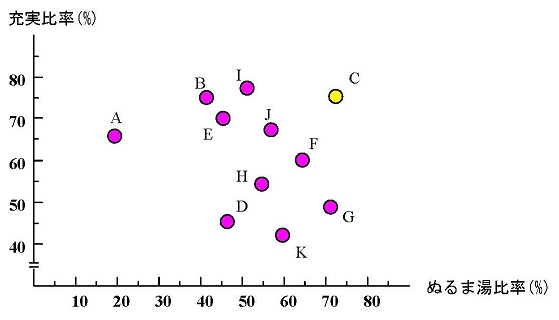
このように述べると、C社だけが特殊な会社であるかのような印象を与えかねないが、実は同様の散布図に、会社ではなく、今度は職場をプロットしてみると、なんのことはない、ぬるま湯感と仕事の充実感の共存する職場が、C社に限らず、かなり存在していることもわかっている。つまり、表1.1の示す通りに、ぬるま湯感と仕事の充実感とが共存していることは、ごくありふれた現象だったのである。このことが偶然の産物ではなかったことは、後の調査でもほとんど同じ結果が得られたことで確認されている(第4章の表4.1を見られたい)。
以上の調査結果から、ぬるま湯現象を組織の不活性状態における典型的現象として単純に割り切って考えることは、かえって不自然に思われる。つまり、ぬるま湯現象とはどういう現象であるのかを、安易に組織の不活性状態や、職務不満足の状態と結び付けてしまわずに、きちんとした枠組みに基づいて相互に関係づけを行った上で説明する必要が出てきたのである。(なおここでは、「職務満足感」と「仕事の充実感」とを区別せずに用いて記述しているが、本質的にはやや問題があるかもしれない。しかし、職務満足は多元的概念で、しかも、それがどんな次元から構成されているのかについては、多くの研究者の間で必ずしも意見の一致はないとされている(坂下, 1985, p.140)こともあり、ここでは、とりあえず質問Q2で職務満足を測定することにする。もっとも第4章の4.1節でも明らかになるように、本質的にはともかく、実際上にはほとんど問題はないといってよい。)
そこで、原点に戻って考えてみることにしよう。職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じるということはどういう現象なのであろうか。岩波書店の『広辞苑』第3版(1983)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす。」とされている。さらに、小学館の『国語大辞典』(1981)によると、「ぬるまゆ(微温湯)」とは、「温度の低い湯。ぬるい湯。ぬるみ。びおんとう。」とされ、「ぬるまゆにつかる」とは「安楽な現状に甘んじて呑気に過ごす。」とされている。
それでは、風呂のアナロジーで考えるときに、職場のぬるま湯感を表す際の「温度」とは何を意味しているのだろうか。またそれは何によって測定できるものなのだろうか。この研究では、そのヒントを「ぬるまゆにつかる」の意味の中に求めた。つまり、現状に甘んじることなく変化を求める傾向、現状を打破して変化しようとする傾向、これを変化性向(propensity to change)と呼び、ここでは、組織としての変化性向をまず考え、変化性向が大きければ、「温度」が高く、熱いと感じ、逆に、変化性向が小さければ、「温度」が低く、ぬるいと感じると考えるのである。
そこで、前述の50の質問項目のうち、データ分析の結果等も参考にしながら、基本的には論理的に考えて、組織のシステムとしての変化性向を表すものと考えられる「あなたの職場に関する」質問のなかから、次の五つの質問を選び出した:
S1. 仕事上の個人の業績、貢献の高い人は、昇進、昇格あるいは昇給などを確実に果たしている。
S2. 仕事上の前向きの失敗は問わないと言う雰囲気がある。
S3. 職場の上司は、その上の上司を動かす力があると思う。
S4. 今までの仕事の進め方は、今後、変わりそうにない。(−)
S5. 年次さえ来れば、ある程度まで昇進できると皆思っている。(−)
この五つの質問のうち、S1、S2、S3については、Yesと答えた方が、変化性向が大きいと考えられる。他方、S4、S5については(−)でも示してあるように、逆にNoと答えた方が、変化性向が大きいと考えられる。そこで、この五つの質問に対する回答を、S1、S2、S3についてはYesと答えた比率、S4、S5についてはNoと答えた比率について会社別にまとめると、表1.2が得られる。この表からもわかるように、この五つの質問については、いずれも会社別のクロス表に1%水準、もしくは0.1%水準で有意な関連がみられた。
表1.2 システムの変化性向とシステム温(1987年調査)
| 会社 | N | S1 1. YES | S2 1. YES | S3 1. YES | S4 2. NO | S5 2. NO | システム温 SINDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A社 | 19 | 89.47 | 84.21 | 84.21 | 52.63 | 89.47 | 4.00 |
| 2. B社 | 27 | 37.04 | 85.19 | 55.56 | 66.67 | 74.07 | 3.19 |
| 3. C社 | 55 | 63.64 | 56.36 | 63.64 | 43.64 | 45.45 | 2.73 |
| 4. D社 | 18 | 66.67 | 61.11 | 50.00 | 5.56 | 66.67 | 2.50 |
| 5. E社 | 96 | 68.75 | 81.25 | 80.21 | 62.50 | 79.17 | 3.72 |
| 6. F社 | 78 | 37.18 | 64.10 | 65.38 | 41.03 | 28.21 | 2.36 |
| 7. G社 | 65 | 60.00 | 70.77 | 61.54 | 44.62 | 49.23 | 2.86 |
| 8. H社 | 53 | 69.81 | 75.47 | 60.38 | 47.17 | 39.62 | 2.92 |
| 9. I社 | 26 | 53.85 | 92.31 | 92.31 | 88.46 | 65.38 | 3.92 |
| 10. J社 | 40 | 45.00 | 82.50 | 82.50 | 57.50 | 47.50 | 3.15 |
| 11. K社 | 48 | 52.08 | 68.75 | 39.58 | 58.33 | 62.50 | 2.81 |
| 全体 | 525 | 57.52 | 73.33 | 66.86 | 52.00 | 55.43 | 3.05 |
| χ2 | 38.93*** | 26.40** | 44.47*** | 44.45*** | 70.55*** | F =8.80*** | |
この五つの質問を基にして、各個人について、S1、S2、S3についてはYesならば1点、Noならば0点を与え、S4、S5についてはYesならば0点、Noならば1点を与える。このように、二つのカテゴリーのうちどちらかに属することを0か1で表すように定義した変数をダミー変数と呼ぶが、こうして各質問の回答をダミー変数化した上で、これらの5問の合計点をSINDEXと定義し、これをシステム温(system temperature)と呼び、これによって、組織のシステムとしての変化性向をみることにした。
システム温は本来、組織のメンバーがつかっている湯の温度を表しているものであるが、湯温という用語を用いると、システムの温度ではなく、回答者の周囲の人々の温度を表しているかのような誤解を与えるので、ここではあえてシステム温という用語を用いることにする。システム温は0、1、2、3、4、5の値をとることになる。
そこで、前述の質問Q1で、職場の雰囲気をぬるま湯と感じている人を「ぬるま湯」群と呼び、そうではない人を「非ぬるま湯」群と呼ぶことにしよう。このシステム温とぬるま湯感の関係をみるために、両群の間で、システム温についての平均値の差の検定を行ってみた。(平均値の差の検定について詳しくは、高橋(1992d, ch.3)を参照のこと。ここでは2群の平均値の間に差があったとき、それが統計的に意味のある「有意な」差であるか、それとも統計的にはよく起こりうる誤差の範囲内の無意味な差であるのかを調べる手法であると理解されたい。) すると、全体での平均は3.05であったが(N =525)、予想通り、「ぬるま湯」群のシステム温の方が2.72 (N =292)と、「非ぬるま湯群」の3.46 (N =233)よりも0.1%水準で有意に低く(t =−6.61)、システム温が低いことが確かめられたのである。
以上のことから、システム温によって、個人のぬるま湯感を説明する試みは、有望そうである。それでは、このシステム温を使うことで、会社別にみたときのぬるま湯感を説明できるであろうか。つまり企業のぬるま湯的体質を説明することができるであろうか。会社別のシステム温については、既に、表1.2に示してあるが、各社のシステム温の平均には0.1%水準で有意な差がみられるものの、11社中で最高の71.7%の人がぬるま湯感を感じている前述のC社のシステム温が、この表1.2では2.73になっていて、確かに全体の平均よりは低くなっているものの、システム温が特に低いというわけではない。したがって、ぬるま湯感を説明するためには、システム温だけではまだ不十分と考えた方が良いようである。また組織のシステム的側面に着目するだけでは、C社のような職務満足の高い会社で、なぜぬるま湯感が強いのかを説明することができないということも明らかである。そこで、ぬるま湯感を説明するための新たな枠組みが必要となるのである。
組織のシステムの変化性向であるシステム温だけを基にしてぬるま湯感を説明することは、C社のようなケースには不十分であるということがわかった。それでは、その代わりにどのような説明が考えられるだろうか。そこでC社のもつ特徴について、もう一度思い起こしてみよう。C社は71.7%がぬるま湯と感じていて、ぬるま湯感が11社中で最も高かった一方で、仕事に充実感を感じているものも72.9%と11社中3番目に高かった会社である。そのことを考え合わせると、ぬるま湯感には、単に、組織のシステム側の要因だけではなく、人の側にも原因がありそうである。そこで、次のように考え、仮説を立ててみることにしよう。
生物としての人間の体温は、誰でも約36〜37℃でほぼ一定している。だから、システム温という湯の温度を考えて、ぬるま湯感を説明することを自然に思いついたのである。しかし、組織人としての人間の体温は、果して、誰でも、いつでも一定なのであろうか。つまり、C社のメンバーのような仕事の充実感の高い人は、実は組織人としての体温も高いのではないだろうか。そして、「ぬるい」と感じるか「熱い」と感じるかということは、組織人としての体温をベースとした体感温度の問題なのではないだろうか。
ここで「体温」とは、組織のメンバーの組織人としての変化性向であり、組織のメンバーが現状を打破して、変化をもたらそうとする意欲がどの程度あるのかを表す指数と考えられる。一方、「システム温」とは、既に定義したように、組織のシステムとしての変化性向であり、組織のシステムがメンバーの変化を受け止め、あるいは促す仕組み、制度にどの程度なっているのかを表す指数であった。そこで、組織人としての変化性向として BINDEX を定義し、これを体温(body temperature)と呼び、この体温とシステム温との温度差で、ぬるま湯感を説明することを考えよう。つまり、思いきって単純化をして、体感温度を
のように定義し、ぬるま湯感がこの「体感温度」(effective temperature または bodily sensation temperature)によって説明できると考え、次のような仮説を立てる。
仮説1 (体感温度仮説). 職場の雰囲気をぬるいと感じる人の方が、熱いと感じる人よりも体感温度が低く、ぬるいと感じる人と熱いと感じる人の分布は、図1.2のようになる。図1.2 体感温度仮説
(A)システム温・体温と体感温度 (B)体感温度による相対度数折れ線
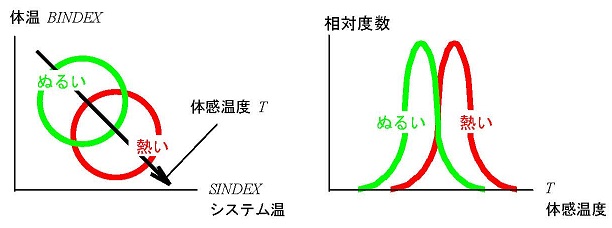
実は、ここで用いる体感温度算出式は、システム温と体温が「同一単位」で測定されているということを暗黙のうちに前提としているが、この前提については、章末付録において、多変量解析によるデータの分析によって、吟味が行われることになる。興味のある読者は章末付録を読むとわかるが、多変量解析を用いた吟味の結果、こうした前提が置いてあっても、実際上は問題がないということがわかっている。そこでここでは、調査データを基にして、この体感温度仮説を検証することを考えてみよう。
体感温度仮説を検証するためには体温について定めなくてはいけない。そこでまず、システム温と同様にして、データ分析の結果等も参考にしながら、基本的には論理的に考えて、今度は「あなたの仕事に対する姿勢に関する」質問の中から、組織人としての変化性向を表す質問項目と考えられる次の五つの質問を選び出した:
B1. 自分の仕事については、人並の仕事のやり方では満足せずに、常に問題意識をもって取り組み、改善するように心がけている。
B2. 今の職場では、業績を残すよりも、大きな問題やミスを起こさないようにしたい。(−)
B3. 自分の仕事に関する業務知識、専門知識を修得しようと常日頃から心がけている。
B4. 新しい仕事をどんどんやりたい。
B5. できれば人よりも早く昇進したいと思っている。
このうち、(−)で示してあるように、B2についてはNo、他のB1、B3、B4、B5についてはYesと答えた方が変化性向が大きいと考えられる。
そこで、SINDEX と同様にして、この五つの質問を基にして、各個人について、B2についてはYesならば0点、Noならば1点、他のB1、B3、B4、B5についてはYesならば1点、Noならば0点として点数を与え、ダミー変数化した上で、この五つの質問について点数を合計したものを体温(BINDEX )と呼び、定義し、これによって、組織人としての変化性向をみることにした。体温(BINDEX )はシステム温(SINDEX )と同様に0、1、2、3、4、5の値をとることになる。ぬるま湯感と個人の仕事に対する姿勢に関する質問との間に、あまり相関が高くなかったことを反映して、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の体温の平均値は、それぞれ3.46 (N =292)、3.56 (N =233)となり、両群の間に有意な差はみられなかった(t =0.68)。全体での平均は3.60であった(N =525)。
この五つの質問に対する回答と体温BINDEX を会社別にまとめると表1.3が得られる。この五つの質問のうち、B1、B2については会社別のクロス表に有意な関連がみられたが、他の三つについては5%水準で有意な関連は見いだされなかった。しかし、各社について体温BINDEX の平均を求めると、平均については0.1%水準で有意な差がみられる。これによると、予想された通りC社はやはり体温の平均値も4.04と高く、これは充実感と同様に、11社中3番目に高い値になっている。
表1.3 組織人としての変化性向と体温・体感温度(1987年調査)
| 会社 | N | B1 1. YES | B2 2. NO | B3 1. YES | B4 1. YES | B5 1. YES | 体温 BINDEX | 体感温度 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A社 | 19 | 94.74 | 78.95 | 94.74 | 89.47 | 47.37 | 4.05 | -0.05 |
| 2. B社 | 27 | 70.37 | 74.07 | 85.19 | 85.19 | 37.04 | 3.52 | -0.33 |
| 3. C社 | 55 | 92.73 | 60.00 | 92.73 | 92.73 | 65.45 | 4.04 | -1.31 |
| 4. D社 | 18 | 83.33 | 44.44 | 88.89 | 83.33 | 44.44 | 3.44 | -0.94 |
| 5. E社 | 96 | 84.38 | 56.25 | 86.46 | 88.54 | 52.08 | 3.68 | 0.04 |
| 6. F社 | 78 | 70.51 | 41.03 | 79.49 | 83.33 | 48.72 | 3.23 | -0.87 |
| 7. G社 | 65 | 75.38 | 36.92 | 84.62 | 93.85 | 53.85 | 3.45 | -0.58 |
| 8. H社 | 53 | 58.49 | 58.49 | 84.91 | 77.36 | 47.17 | 3.26 | -0.34 |
| 9. I社 | 26 | 96.15 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 65.38 | 4.54 | -0.62 |
| 10. J社 | 40 | 90.00 | 47.50 | 97.50 | 90.00 | 72.50 | 3.98 | -0.83 |
| 11. K社 | 48 | 58.33 | 52.08 | 79.17 | 87.50 | 47.92 | 3.25 | -0.44 |
| 全体 | 525 | 77.71 | 54.29 | 86.86 | 88.00 | 53.33 | 3.6 | -0.55 |
| χ2 | 46.81*** | 40.28*** | 17.40+ | 14.91 | 16.50+ | F =4.07*** | F =3.34*** | |
そこで、仮説の検証にとりかかることにしよう。ただし、仮説では、「ぬるい」と感じる人と「熱い」と感じる人という分類を用いているが、今回の調査では質問Q1しか使うことができないので、「ぬるま湯」「非ぬるま湯」という分類しか用いることができない。このため「非ぬるま湯」の中に、「熱い」と感じる人だけではなく、「適温」だと感じている人なども入ってきて、仮説1の図1.2 (A)(B)の「ぬるい」「熱い」ほどには「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群がきれいに分れないことが考えられる。
図1.3 体温・システム温散布図(1987年調査)
(A)全体
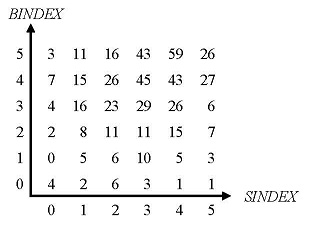
Cramer's V =0.146 (χ2=56.021***)
(B)「ぬるま湯」群 (C)「非ぬるま湯」群
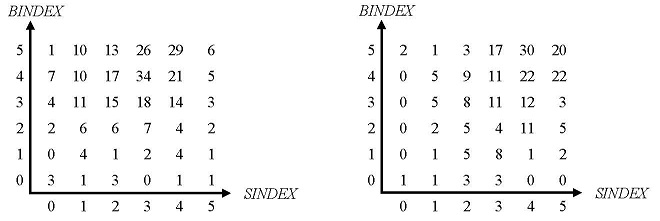
Cramer's V =0.158 (χ2=36.470+ ) Cramer's V =0.219 (χ2=55.980***)
このことは実際、データによって確かめられる。体温を縦軸、システム温を横軸とする散布図にメンバーをプロットしてみよう。その結果は、図1.3の(A)(B)(C)のようになった。傾向としては、「ぬるま湯」群が左上に厚く分布しているように、仮説通りの傾向が現れている。ただし、やはり、図1.2(A)ほどにはきれいに分れていない。事実、図1.3(C)の実際の「非ぬるま湯」群の分布は仮説の中で「熱い」としていた右下の位置だけではなく、右上隅にも分布していて、分布の中心はむしろこの右上隅の方である。右上隅はシステム温も体温も高い状態、すなわち、組織のシステムも人も変化性向が大きく、システム、人が一体となって変化することを指向した組織であることを意味した領域である。まさに「適温」の状態といってよいだろう。つまり、図1.3(C)の分布は「非ぬるま湯」群の大部分がいわば「適温」に分類すべきメンバーであったことを示唆しているのである。
このように、「熱い」の代わりに「非ぬるま湯」を使わなくてはならず、しかも「非ぬるま湯」群の中心は「熱い」というより、むしろ「適温」であったという事実発見があったにもかかわらず、体感温度仮説は期待通りに検証される。まず、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群とで、体感温度 T に差が認められるかどうかをみてみることにしてみよう。T =SINDEX −BINDEX と定義しているので、体感温度 T は-5から5までの整数値をとることになる。体感温度を計算して求めると、全体での平均は−0.55 (N =525)となった。「ぬるま湯」群の体感温度は−0.91 (N =292)、「非ぬるま湯」群の体感温度は−0.09 (N =233)と両群では、体感温度の平均値に0.1%水準で有意な差があり(t =−5.79)、仮説通りに、「ぬるま湯」群の体感温度の方が「非ぬるま湯」群の体感温度よりも低いことがわかった。
以上のことは、表1.4のように、「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群両者の分布を相対度数でみるとより明確になる。この表1.4をもとにして相対度数折れ線を描くと図1.4のようになり、体感温度仮説の図1.2(B)とほぼ同じ図が得られる。ただし、やはり図1.2(B)ほどには、はっきりと両群の分布は分れてはいない。ところで、図1.4は図1.2(B)と対応させる都合上、相対度数折れ線になっているが、相対度数ではなく度数で折れ線を描くと、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の度数折れ線の交差する点が体感温度−1と0の間にあることが、表1.4からもわかる。そこで、判別の境界を整数にとれば、T ≦−1ならば「ぬるま湯」、T ≧0ならば「非ぬるま湯」と判別するとき、誤判別は200人、誤判別率38.1%と最小になる。
表1.4 ぬるま湯感と体感温度の分布(1987年調査)
| 質問Q1 | 体感温度 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」群 | 1 | 17 | 27 | 56 | 84 | 58 | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 292 |
| 2. No 「非ぬるま湯」群 | 2 | 1 | 8 | 31 | 51 | 60 | 44 | 25 | 9 | 2 | 0 | 233 |
| 計 | 3 | 18 | 35 | 87 | 135 | 118 | 72 | 37 | 15 | 4 | 1 | 525 |
図1.4 相対度数折れ線(1987年調査)
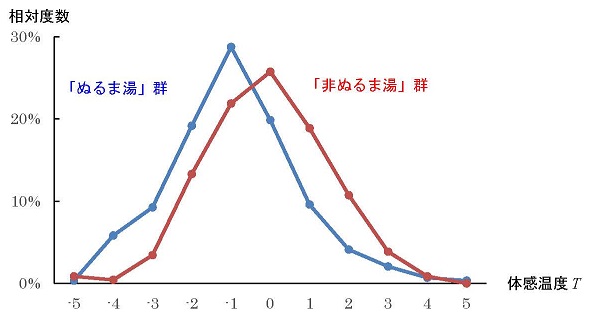
ところで、この散布図や体感温度を使うと、問題のC社は相対的にどのように位置づけられるであろうか。会社別に体感温度の平均値を求めたものは既に表1.3に示してあるが、0.1%水準で会社によって体感温度の平均値に有意な差のあることがわかる。その中で、ぬるま湯感を感じているメンバーの比率が最も高かったC社の体感温度は、期待された通り−1.31と一番低くなっている。また会社をシステム温、体温の平均値で散布図にプロットしてみると、図1.5のようになり、C社だけが予想された「ぬるま湯」領域にプロットされる。以上のことから、システム温と体温を使えば、C社も含めて企業のぬるま湯感をかなり説明することができるということがわかる。
図1.5 会社別散布図(1987年調査;破線は平均値)
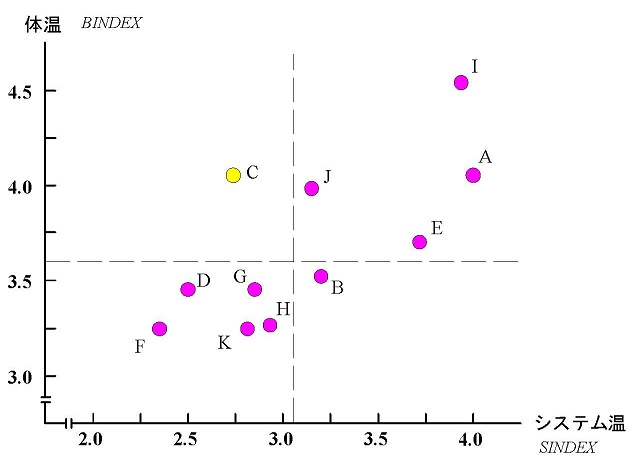
これまでは1987年調査から得られた事実発見などをもとにして、職務満足と体温、システム温についての枠組みについて考察してきた。そこで、1987年調査によって、一応、裏付けられたとはいうものの、体感温度仮説が一度限りの偶然ではなく、より一般的に妥当性をもつものであるかどうかを確認するために、1988年調査が企画、実施された。この1988年調査は中間管理職を対象として行われた。
実は、1987年調査のような通常の調査でも、職位については調べているが、中間管理職に関する限りは、この形式的な肩書による比較は企業間比較の場合、適切ではない。というのは、中間管理職が管理職と非管理職の境界に接しているためで、日本では比較的転職が少なく、生え抜きの人が連続的に昇進していくことが事情を複雑にしている。同じ肩書が同じ会社の中で管理職と非管理職のどちらにも使用されているケースすらある。
異なる会社間ともなると、肩書の比較がほとんど意味をもたないほど、肩書の重さも意味も各会社が「独自に」与えているのが実情である。そこには、誰にでも納得可能な社会常識は存在しない。例えば、企業によっては、「課長」でも社内的には管理職として扱われておらず、組合員のままの人もいる一方で、現在は肩書も直属の部下ももっていなくても、非組合員でかつ社内的に管理職として認知されているようなケースも珍しくはない。
こうした事情から、中間管理職の識別をするには、それぞれの会社の内部事情に精通した上で、細心の注意が必要になってくる。そこで、この調査では、最低限、非組合員であるという条件をつけた上で、各社で社内的に中間管理職として認知、周知されている従業員ということで、「中間管理職」を定義し、実態に即して、各社の社内での認定、抽出作業を行うことにした。このようにして、この調査では、形式的な肩書による分類では得られない中間管理職の実態、実像に迫ることを意図している。
1988年調査で調査対象となったのは、1987年調査と同様に、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの今度は1988年度の参加者の所属企業8社である。調査は1987年調査と同様の手順を踏んで、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1988年6月17・18の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この質問票調査に参加する会社の各社1人ずつの8人と質問票調査には参加しなかった会社の2人、そして筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、職場内の現象、個人の仕事に対する意識の状態をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、個人の仕事に対する姿勢に関する25の質問項目と、職場に関する25の質問項目の計50項目のリストを作成した。これに1987年調査でシステム温、体温を算出するために用いた個人の仕事に対する姿勢に関する5つの質問項目と、職場に関する5つの質問項目をそれぞれに加えて、30問ずつの計60問の質問項目リストを作成した。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。前述のように1987年調査とは異なり、調査対象者は中間管理職に限定している。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場の中間管理者に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は2ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数には30人から190人まで開きがあるが、総職場数は37ヶ所、総調査対象者数は770人、職場当りの平均調査対象者数は20.8人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた8社770人に対して、1988年8月31日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月5日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。
その結果、626人から質問調査票が回収できた。回収率は81.3%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。使用した質問調査票は、前述の60のYes-No形式の質問項目の他に、1987年調査と同様の個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。
1988年調査では、1987年調査と同じぬるま湯感についての質問Q1「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」に対しては、69.7% (434人)がYes、30.3% (189人)がNoと答えている。これは、1987年調査でYesが55.4%、Noが44.6%と調査対象となった人のほぼ半数がぬるま湯感を感じていたことと比べると、ぬるま湯感を感じている人が7割という高レベルになっている。このように中間管理職にぬるま湯感が高いことは、後述するように、体感温度仮説によってうまく説明することができるので、ここでは、ぬるま湯感を感じている比率の高いデータとなっていることに注意しながら、さっそく1987年調査と同じ質問項目を用いて、システム温、体温を求めてみることにしよう。
システム温 SINDEX、体温 BINDEX、体感温度 T を計算して求めてみると、全体の平均はそれぞれ、3.06、4.09、−1.03 (N =609)となった。「ぬるま湯」群でそれぞれ2.90、4.09、−1.19 (N =422)、「非ぬるま湯」群でそれぞれ3.43、4.10、−0.66 (N =187)となる。両群の間で平均値の差の検定を行うと、システム温については0.1%水準で有意(t =−4.85)、体感温度についても0.1%水準で有意(t =−4.11)だったが、体温については有意な差はみられなかった (t =−0.09)。このように、体感温度の平均値に有意な差があり、体感温度仮説の通りに、「ぬるま湯」群の体感温度の方が「非ぬるま湯」群の体感温度よりも低いことがわかった。
さらに、1987年調査と同様に、体温を縦軸、システム温を横軸とする散布図にメンバーをプロットしてみると、その結果は、図1.6の(A)(B)(C)のようになった。相対的な傾向としては、仮説に近い傾向が現れている。ただし、1987年調査と同様に、やはり、図1.2(A)ほどにはきれいに分れてはいない。図1.6(C)の分布は、「非ぬるま湯」群の分布の中心が右上隅になっていて、いわば「適温」に分類すべきメンバーが中心になっていることを示唆している。
図1.6 体温・システム温散布図(1988年調査)
(A)全体
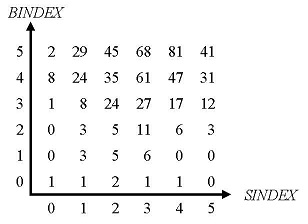
Cramer's V =0.111 (χ2=37.736*)
(B)「ぬるま湯」群 (C)「非ぬるま湯」群
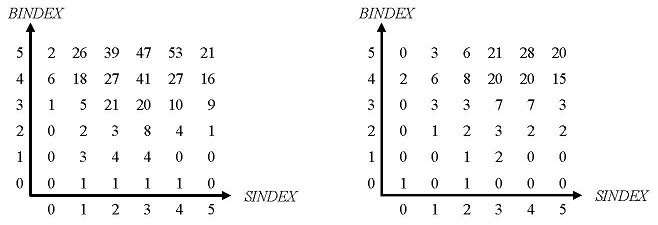
Cramer's V =0.158 (χ2=26.066) Cramer's V =0.226 (χ2=47.774***)
表1.5 ぬるま湯感と体感温度の分布(1988年調査)
| 質問Q1 | 体感温度 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」群 | 2 | 32 | 58 | 79 | 117 | 74 | 39 | 18 | 2 | 1 | 0 | 422 |
| 2. No 「非ぬるま湯」群 | 0 | 5 | 12 | 32 | 52 | 50 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 187 |
| 計 | 2 | 37 | 70 | 111 | 169 | 124 | 65 | 26 | 4 | 1 | 0 | 609 |
図1.7 相対度数折れ線(1988年調査)
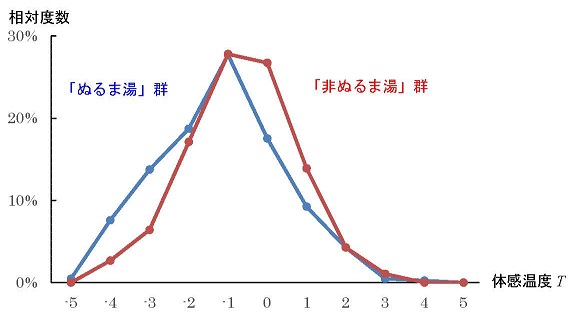
また、「ぬるま湯」群、「非ぬるま湯」群両者の分布を相対度数でみると表1.5のようになり、これをもとにして相対度数折れ線を描くと図1.7のようになる。1988年調査では、「ぬるま湯」群が7割を占め、「非ぬるま湯」群が3割程度しかいない上に、体温が上限にはりついて、両群では体温にほとんど差がなく、相対度数では図1.2(B)ほどには、はっきりと両群の分布は分れてはいない。このため、仮に1987年調査の際と同一の基準で、T ≦−1ならば「ぬるま湯」と判別し、T ≧0ならば「非ぬるま湯」と判別してみると、このとき、誤判別は235人、誤判別率は38.6%となっている。これは1987年調査の誤判別率38.1%とほとんど同水準であり、体感温度による判別は安定していることがわかる。
ところで1988年調査では、なぜこのように高水準のぬるま湯感が存在するのだろうか。1987年調査と比較しても1988年調査のぬるま湯感は高水準である。解明の糸口は1988年調査の体温の高さにある。1987年調査のデータと比較すると、1988年調査のデータは体温の分布が4と5に偏りすぎていることが、図1.6(A)からわかる。体温5が43.7%、体温4が33.8%とこの両者だけで77.5%も占めている。このことは1988年調査が中間管理職だけを対象としていることに起因していると考えられる。つまり、ヒアリング段階から十分に予想されていたことであったが、中間管理職が一般に現状を打破しようという意欲を強くもっているという事実が、高体温に反映されていると考えられるのである。したがって、中間管理職を対象とした1988年調査では、体温はほぼ上限に張り付いてしまったために、差がほとんど出なくなり、図1.6の(B)(C)をみても、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の違いは、システム温の違いだけのようにみえる。
しかし、この図1.6に示されるような1988年調査だけに限定すれば、システム温だけでぬるま湯感の説明をつけることは可能なのだが、1987年調査との比較において、なぜこのように高水準のぬるま湯感が存在するのかということを説明することができない。実際、1988年調査のシステム温の平均値は3.06で、1987年調査のシステム温の平均値3.05とほとんど同じであり、システム温だけで1988年調査での中間管理職の高水準のぬるま湯感を説明することはできないのである。
ところが、体感温度仮説によれば、1987年、1988年の2回の調査で、システム温の平均はほぼ同じなのに、1988年調査の体温の平均が4.09と、1987年調査の3.60を大きく上回っていたために、1988年調査の中間管理職の場合には、その体温の高さゆえに体感温度が低下し、その結果、ほぼ7割がぬるま湯感を感じることになってしまったと説明することができる。
会社別の体感温度の平均値は表1.6に示されるが、0.1%水準で会社によって体感温度の平均値に有意な差があり、その中で、ぬるま湯感を感じているメンバーの比率が87.5%と群を抜いて最も高かったH社の体感温度はやはり群を抜いて一番低くなっている。また会社別にシステム温、体温の平均値を求め、散布図に会社をプロットしてみると、図1.8のようになる。
表1.6 システム温・体温・体感温度(1988年調査)
| 会社 | N | システム温 SINDEX | 体温 BINDEX | 体感温度 T |
|---|---|---|---|---|
| 1. A社 | 46 | 3.02 | 3.96 | -0.93 |
| 2. B社 | 111 | 3.35 | 4.25 | -0.90 |
| 3. C社 | 71 | 3.24 | 3.96 | -0.72 |
| 4. D社 | 56 | 3.43 | 3.91 | -0.48 |
| 5. E社 | 108 | 3.35 | 4.03 | -0.68 |
| 6. F社 | 142 | 2.77 | 4.25 | -1.48 |
| 7. G社 | 52 | 2.58 | 4.04 | -1.46 |
| 8. H社 | 23 | 1.87 | 3.87 | -2.00 |
| 全体 | 609 | 3.06 | 4.09 | -0.55 |
| F | 8.08*** | 1.52 | 6.26*** | |
1.8 会社別散布図(1988年調査;破線は平均値)
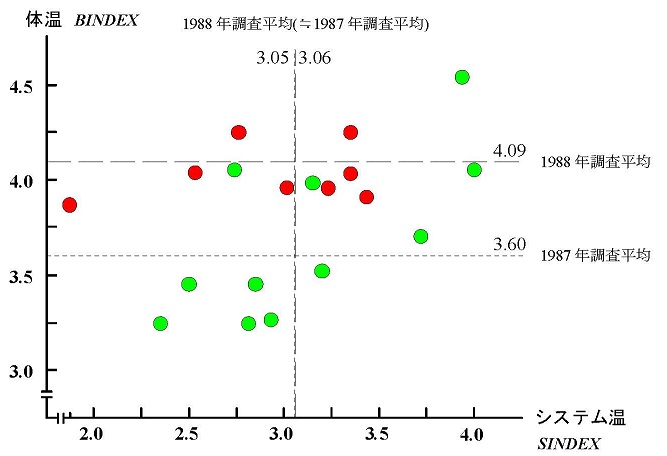
ただし、1988年調査のデータは、体温でほとんど差がないために、体温は「ぬるま湯」群「非ぬるま湯」群との間で有意な差がなかっただけではなく、会社別にみても有意な差がなかった。しかも、どの会社においても体温のレベルは高く、このことは1987年調査データによる図1.5と比較すると明白である。すでに述べたように、1987年調査データと比較すると、全体でのシステム温の平均値は3.05と3.06とほとんど同じなのに対して、全体の体温の平均値は、1987年調査の3.60と1988年調査の4.09とでは大きく異なる。このことは、中間管理職だからといって、システム温の評価は変わるものではないが、体温についてはレベルが高くなるために、体温4、5とほとんど上限に張り付いてしまい、会社によっての差がなくなってしまうという興味深い事実を物語っていると考えられる。
ちなみに、図1.8に1987年調査の体温の平均値線も破線で書き込んでみると、8社とも1987年調査の体温の平均値線よりも上の領域に入ってしまうことがわかる。前述のぬるま湯感を感じているメンバーの比率が87.5%と群を抜いて最も高かったH社も、予想された「ぬるい」領域にプロットされることになる。
以上のことから、中間管理職のように体温が高い調査対象の場合であっても、体感温度仮説によって、ぬるま湯感を説明できることが確認された。ところで、なぜ中間管理職は体温が高いのであろうか。これには次の二つの可能性が考えられる。
どちらが妥当性のあるものなのか、あるいはケース・バイ・ケースで起こり得るものなのかは、この段階では判断がつかない。このことは後の研究課題となってくる。
この章では、実際の調査を通して、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、それを検証するという作業を通して、ぬるま湯現象をかなり解明できたと考えている。
しかし、もし体感温度仮説が正しいとすると、ぬるま湯感だけで組織や職場の状態を判断することには問題があることになるので注意が必要である。つまり、組織や職場の状態を体感温度だけで判断することには盲点があるのである。なぜなら、体感温度はシステム温と体温の温度差なので、同じ水準の体感温度をもたらすシステム温(SINDEX )と体温(BINDEX )の組は一意には定まらず、システム温、体温が共に高くても、共に低くても、同じ体感温度になりうるからである。
このことを図1.9を使って示せば、等体感温度曲線は、体感温度を表す右下がりの直線への垂直な直線となるはずである。したがって、例えば、図の右上隅(システム温5、体温5)も左下隅(システム温0、体温0)も体感温度では、システム温−体温なので0になり、差がないことになる。しかし、この両者をともに「適温」と呼んでもよいのだろうか。両者の違いは重要かつ重大である。確かに右上隅は組織のシステムも人も変化性向が大きく、システム・人が一体となって変化することを指向した状態で適温と呼ぶのにふさわしいのに対して、左下隅は組織のシステムも人も変化性向が小さく、組織のシステムが現状に甘んじることを肯定しているだけではなく、そのメンバーも現状に甘んじることが体に染み着いているために、そうしたシステムの状況に気が付いていないという危険な状態にあると考えられる。
図1.9 体感温度の落し穴
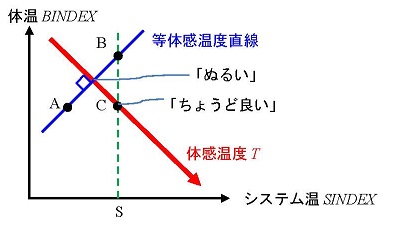
このことは、組織や職場の状態を、その中にいるメンバーの「感じ」だけで判断してしまうことの危険性を示唆している。メンバー自身が「適温」だと思っていても、その実態はシステムも人も変化性向の低い状態になってしまっているかもしれないのである。例えて言えば、適温だ、いい湯だと思って風呂に長々と浸かっていると、湯(システム)の温度は自然に下がっていってしまう。しかるに、本人の体温もそれにつれて低下しているのでそのことに気付かず、いつしか平気で水風呂の中につかり、そのうち風邪をひいてしまうということが十分に考えられるのである。したがって、体感温度だけによって、組織や職場の状態を判断できないということは、体感温度の盲点であるとともに、体感温度仮説の重要な含意でもあるのである。
これと類似の現象が、経営学の領域で、Tichy & Devanna (1986, p.44 邦訳p.59) によって「ゆでガエル現象」(boiled frog phenomenon)として指摘されている。この現象はもともとがカエルが主役の古典的な生理学的反応実験に由来するものの例えなので温度の高低の設定は逆になっているが、カエルを突然熱湯に入れると、カエルはすぐに飛び出すが、カエルを冷水の鍋の中に入れて、ゆっくりと熱を加えていけば、温度の変化がゆっくりなので、カエルは熱湯になっていっていることに気付かず、飛び出すことなく、鍋の中でゆで上がって死んでしまうという現象を指している。米国の鉄鋼、自動車などの産業はこの現象の犠牲者だったというのである。本研究での体感温度仮説においては、体感温度の概念を定義、操作化することで、こうした指摘を単なる教訓話としてではなく、論理として議論の対象として提示することに、ある程度成功していると考えることができる。
体感温度仮説によれば、同じぬるま湯感、つまり、同じ低体感温度であっても、システム温が低いというケースだけではなく、1987年調査のC社の例のように、システム温はとりたてて低いというわけではないのに、体温が高いために、低体感温度になってしまうというケースも含まれうることには改めて注意する必要がある。例えば、図1.9に示されるように、同じ体感温度になるA点とB点とを比較してみよう。同程度のぬるま湯感をもたらすにもかかわらず、高システム温・高体温のB点の方が望ましい状態だということができるだろう。しかも、このB点をC点と比べた場合には、体感温度の危険性がより明らかになる。すなわち、組織外部の諸要因によって、どうしてもシステムの変化性向が低く抑えられてしまっているような企業の場合には、同じシステム温Sであるならば、ちょうど良いとかんじているC点よりは、ぬるいと感じているB点の方が、体温が高く、ゆでガエル現象の例えを待つまでもなく、この方がむしろ健全だということができるのである。
以上のことから、実は体感温度(T )よりも、この体温(BINDEX )を縦軸、システム温(SINDEX )を横軸にとった図の上での位置の方が重要ではないかということになる。一般には図1.10のようになるが、これを「湯かげん図」と呼んでいる。既に試験的にこの湯かげん図を用い、会社単位で職場間の比較を行ったケース研究が、1987年調査の調査対象企業の担当者自らの手によって試みられていて、そこでは、図1.10に体温、システム温の平均を破線で入れたものが使用されている。これらの一連のケース研究では、便宜上、右上の領域を「適温」領域と呼んでいるが、左下の領域については、前述の体感温度の盲点に関する風呂の例えからもわかるように、「適温」と呼ぶべきではなく、「水風呂」領域等、別の名称で呼ぶべきであろう。
図1.10 湯かげん図
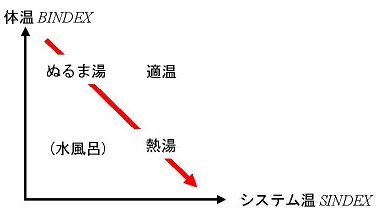
湯かげん図において重要なことは、活性化していると呼ぶべき状態が「適温」の状態であることは確からしいが、他方、本来、活性化していないと呼ぶべき状態は「水風呂」の状態であって、「ぬるま湯」と感じている領域はどちらとも異なるということである。つまり、調査データの分析過程で疑問を感じた通り、やはり、ぬるま湯の状態は不活性状態の典型というわけではなかったことになる。
ところで、「熱湯」の読み方について注意をしておくと、もともと風呂のアナロジーで考えているので、「熱湯」は「あつゆ」と読むべきであろう。「ねっとう」と読むと煮えたっている湯になってしまい、とても入浴することなどできないからである。しかし、「ねっとう」ではなく「あつゆ」と読んだとしても、システム温が体温をはるかに上回る熱湯の状態や、組織も人も冷え切ってしまった水風呂の状態というのは、短期的にはありえても、定常状態としてはありえないのではないだろうか。ゆでガエル現象でも、カエルはゆで上がって死んでしまうのである。実際、図1.3や図1.6で、「非ぬるま湯」群の大部分が適温領域に分布し、水風呂領域や熱湯領域にはあまり分布していなかったという事実は、この予想を裏付けるものといえる。ただし、ぬるま湯の状態はどうなのであろうか。図1.3や図1.6でみても、ぬるま湯領域には十分に分布している。ぬるま湯的体質が問題になることを考え合わせると、ぬるま湯領域はまさにぬくぬくと過ごしやすい領域なのかも知れない。
図1.3、図1.6からも明らかなように、システム温と体温との間には強くはないが正の相関があり、システム温が高いと答えた人は、体温も高い傾向がある。さらに、図1.5のように、企業をプロットすると、企業レベルでもシステム温と体温との間には正の相関のあり、システム温の高い企業は体温も高いことがわかる。このことは重要なことである。つまり、システム温は客観的に測定されたものではなく、ある体温をもった各メンバーによって主観的に測定されたものであるために、システム温の段階で、体温が既に引かれてしまっていて、体温が織り込み済みとなり、システム温が疑似体感温度となっている可能性があったからである。もしそうならば、体感温度のように、体感温度のようにシステム温も体温が高いほど低下するという負の相関が見られるはずであったが、実際にはシステム温と体温とは正の相関があったわけで、こうした可能性が否定され、システム温が疑似体感温度となってはいないことが確認されたことになる。
それでは、強くはないが、正の相関があったということは、システム温を上げれば体温も上がる、あるいは、システム温を下げれば体温も下がるということを意味しているのだろうか? このことは、なぜ中間管理職は体温が高いのかという問題に対する二つの可能性とも密接に関係している。実はこの正の相関には二つの可能性が考えられる。
風呂のアナロジーで考えると一見もっともらしい1のケースについては、いままでのところ証拠はなく、真偽のほどは不明である。2のケースについては、「熱湯」領域にある企業では、人の出入りが激しく、離職率も高いというケースが、ヒアリング調査の中で見いだされている。どうも現時点では2のケースの方がもっともらしいと考えられる。
実際の入浴でも、湯船の中で熱くも冷たくもない不感温度は体温に近い36℃前後と言われるが、例えば、東京都衛生局は1951年に公衆浴場の浴槽温度で常に、42℃以上と定めている。もともと入浴温度自体が習慣、体調などで個人差があり、一概には論じえないが、昔から日本人は熱い湯を好んできたと言われる。しかし、東京で銭湯に外国人の客が増え、特に東南アジア系の人が熱い湯を苦手としていたり、シャワー志向の日本の若者も熱い湯を好まず、東京都衛生局が公衆浴場の浴槽温度を常に42℃以上と定めた都条例の見直しに着手していると言われる(朝日新聞1990年11月6日付)。この段階で単純化して言ってしまえば、ぬるま湯的体質、特に体温と湯温の関係については、先ほどの1のような一回限りの入浴のアナロジーではなく、2のような長期にわたるその人の入浴行動における湯温の好みのアナロジーの方がより正しい理解と言えるのではないだろうか。
それでは、システム温が下がれば、体温は下がるのだろうか? これについても否定的である。多くの企業で、システム温が下がっても、体温はかなりの期間、そのまま維持されていると考えた方が良いだろう。そのために、ぬるま湯的状況が発生していると考えた方が考えやすいのである。次の章で取り上げられるように、ぬるま湯感と成長性の関係を考えると、ぬるま湯感は、システム温が知らず知らずのうちに低下してきているという意味での危険信号、シグナルになっていると考えた方がよいのである。
システム温が上がるにせよ、下がるにせよ、どうも体温には恒常性があるようである。生物としての人間と同様に、組織人としての人間にも恒温性があるらしい。これは、個人の変化性向である体温が、個人にとってはパーソナリティーに近いものであることを暗示している。このことはやや意外な感じを受けるかもしれないが、第5章でより詳細に取り扱われる。ここでは、とりあえず次の仮説を立てておくことにしよう。
仮説2 (恒温仮説). システム温の変動にかかわらず、個人の体温は安定的である。この仮説を直接的に検証できるようなデータを示すことはまだできないが、次の章で取り上げられるように、CIによっても体温は変わらず、システム温だけが変化していたと考えられる事例が存在している。さらに、本書で扱っている調査とは別個のものであるが、CIをはさんで1989年と1991年に標本調査を行ない、3年間にシステム温は顕著に上昇したが、体温は全くといっていいほど変わらなかったという調査データも化粧品、トイレタリー関係の企業から筆者のもとに寄せられている。したがって、心証としてはこの仮説2の妥当性は検証可能と思われる。
この第1章では、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、ぬるま湯感を説明することに一応成功したといっていいだろう。しかし、既にあちこちで述べてきたように、いくつかの問題がまだ解明されないままに残っている。これを整理しておこう。
こうした大きく分けて五つの問題に答えるために、この後の五つの章が用意されている。1については第2章、2については第3章、3については第4章、4については第5章、5については第6章で、それぞれ解明を試みることにする。
この第1章では、システム温、体温、したがって体感温度も、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加減算したものになっている。そこで、この付録では、多変量解析によるデータの分析結果も考慮した上で、等ウェイトで実用上問題がないかどうかを検討・吟味してみることにしよう。そのことで、同時に、体感温度仮説の妥当性について多変量解析の角度からも吟味してみることにする。
システム温を算出する基となった質問S1、S2、S3、S4、S5について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.565, 0.969, 0.958, 0.772, 0.735となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は
SPRIN1=0.429S1+0.541S2+0.531S3+0.424S4+0.247S5
となり、S5に対する重み係数が小さめではあるが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができそうである。
同様に、体温を算出する基となった質問B1、B2、B3、B4、B5について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、2.050, 0.847, 0.769, 0.741, 0.592となり、第1主成分だけが1をはるかに超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は
BPRIN1=0.489B1+0.425B2+0.479B3+0.437B4+0.399B5
となり、各質問項目に対する重み係数はSPRIN1以上にほぼ一定したものになっている。
以上のことから、主成分分析によって、もとの変数群のバラツキを最も良く表現するような合成変数SPRIN1, BPRIN1を求めて、それを基にしてぬるま湯感の分析を行ったとしても、等ウェイトの場合とそれほど異なる結果になるとは考えにくい。
実際、システム温、体温、体感温度を以上の第1主成分の重み係数を使って計算し直すと、全体の平均はそれぞれ、1.36、1.62、−0.27となった。さらに、「ぬるま湯」群でそれぞれ、1.22、1.64、−0.41 (N =292)、「非ぬるま湯」群でそれぞれ、1.52、1.60、−0.08 (N =233)となる。両群の間での平均値の差の検定を行うと、等ウェイトの場合と同様に、システム温については0.1%水準で有意(t =−5.87)、体感温度についても0.1%水準で有意(t =−5.29)だったが、体温については有意な差はみられなかった(t =0.65)。また、会社別にSPRIN1, BPRIN1の平均値をとって散布図として会社をプロットしてみても、2本の平均値線によって区切られた四つの領域に属する会社の構成は変わらず、やはり等ウェイトの場合と同様な結果が得られる。したがって、本研究では等ウェイトにして体感温度の算出式を考えたが、主成分分析を行って求めた場合でも、これとほぼ同様の結果をもたらすことがわかった。
次に、システム温の算出に用いたS1、S2、S3、S4、S5の質問の5問、体温の算出に用いたB1、B2、B3、B4、B5の質問の5問の計10問を基にして、質問Q1の「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。
u=−1.125+0.589S1+0.153S2+0.401S3+0.414S4+0.956S5
−0.144B1−0.230B2+0.150B3−0.237B4−0.094B5
この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。
システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はS2、S5で多少ばらついているが、符号はすべて正である。他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はB3を除いてすべて負となっており、その大きさもほぼ一定していると考えてよさそうである。このように、質問S系には正、質問B系にはほぼ負という係数の符号が得られたことで、「体感温度=システム温−体温」によってぬるま湯感をとらえようとした本研究での試みが、かなり的を得たものであったことが、判別分析の結果からも確認されたと考えられる。
実際に、この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表1.7のようになっているが、誤判別は187人、誤判別率は35.6%となっていて、誤判別率は低いとはいえない。システム温、体温を等ウェイトで求めたときの誤判別200人、誤判別率38.1%でも、この判別分析の結果と比較すると大差なく、本研究での方法が多少なりとも有効なものであったことがわかる。
以上のことから、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題なく、1987年調査のデータで見る限り、多変量解析の結果ともかなりよく符合するものであることが明らかになった。このことと同時に、体感温度仮説の妥当性もある程度確認された。
表1.7 判別結果の比較(1987年調査)
| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 182 (62.3) | 110 (37.7) | 292 | 185 (63.3) | 107 (36.6) | 292 |
| 2. No 「非ぬるま湯」 | 77 (33.1) | 156 (66.9) | 233 | 77 (39.9) | 156 (60.1) | 233 |
| 計 | 259 | 266 | 525 | 278 | 247 | 525 |
| 誤判別数=187 誤判別率=35.6% | 誤判別数=200 誤判別率=38.1% | |||||
1987年調査の時と同様に、システム温、体温、したがって体感温度も、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加算した等ウェイト算出式で算出してしまって、実用上問題がないかどうかを、多変量解析によるデータの分析結果も考慮した上で、検討・吟味してみることにする。
システム温・体温の主成分分析を1987年調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった1987年調査の質問S1、S2、S3、S4、S5に対応する同じ質問項目について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.501, 1.081, 0.905, 0.808, 0.704 となり、第1、2主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は
SPRIN1=0.509S1+0.554S2+0.560S3+0.335S4+0.087S5
となり、S5に対する重み係数が小さいが、その他の質問項目に対する重み係数はほぼ一定しているとみることができそうである。
同様に、体温を算出する基となった1987年調査の質問B1、B2、B3、B4、B5に対応する同じ質問項目について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.660, 0.962, 0.899, 0.820, 0.660 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は
BPRIN1=0.541B1+0.360B2+0.446B3+0.490B4+0.372B5
となり、各質問項目に対する重み係数はSPRIN1以上にほぼ一定したものになっている。
1987年調査と1988年調査の主成分分析の結果を比較してみると、主成分分析による重み係数は、計算の元になっているデータによって影響を受けやすいものであることもわかる。したがって、むしろ、この程度の重み係数の軽重は等ウェイトとみなしていてもかまわない許容範囲の中にあると考えた方が良いと思われる。1987年調査での結論と同様に、もとの変数群のバラツキを最も良く表現するような合成変数 SPRIN1, BPRIN1 を考えて、それを基にしてぬるま湯感の分析を行ったとしても、等ウェイトの場合とそれほど異なる結果になるとは考えにくい。
次に、1987年調査と同様に「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。
u=−1.303+0.225S1+0.365S2+0.118S3+0.178S4+0.928S5
−0.033B1−0.112B2+0.287B3+0.288B4−0.358B5
この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。1988年調査では体温が一様に高く、体温4、5に77.5%も集中して分布しているために、質問B系では「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群の差があまりでない。したがって、質問B系の各質問項目は判別という点では重要な役割を果たしてはいないので、質問B系の各質問項目の重み係数はかなり不安定なものになっていると考えた方がよい。
そのことを念頭において線形判別関数をみると、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数は、S5については大きくなっているが、符号はすべて正である。他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数はB3、B4を除いて負となっており、1987年調査のときほどにはきれいに現れてはいないものの、質問S系には正、質問B系にのみ負の符号の係数が存在していることは、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした本研究での試みが、ある程度は、的を得たものであったことが、判別分析の結果からも確認されたことになる。それと同時に、判別分析の重み係数が標本の特性に大きく影響を受けやすいものであることもわかった。
この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表1.8のようになっているが、誤判別は240人、誤判別率は39.4%となっていて、システム温、体温を等ウェイトで求めたときの誤判別235人、誤判別率38.6%よりも、むしろ悪くなっている。ただし、1988年調査のデータは、「非ぬるま湯」が30.3%しかいなかった偏ったデータだったため、すべてを「ぬるま湯」と判別した場合に誤判別率30.3%となり、誤判別率が低くなるので、全体での誤判別率を比較することは、1987年調査ほどには意味はないということには注意がいる。事実、表1.8をより詳細に検討すると、体感温度による判別の方が、「非ぬるま湯」についての判別が甘くなっていることがわかるが、いずれにせよ、体感温度による判別が判別分析の結果と比較しても大差のないものであることが明らかになった。
表1.8 判別結果の比較(1988年調査)
| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 244(57.8) | 178(42.2) | 422 | 288(68.2) | 134(31.8) | 422 |
| 2. No 「非ぬるま湯」 | 62(33.2) | 125(66.8) | 187 | 101(54.0) | 86(46.0) | 187 |
| 計 | 306 | 303 | 609 | 389 | 220 | 609 |
| 誤判別数=240 誤判別率=39.4% | 誤判別数=235 誤判別率=38.6% | |||||
以上のことから、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していることは、実用上は問題がなく、1987年調査、1988年調査ともに、かなりよく符合するものであることが明らかになった。それとともに、体感温度仮説の妥当性も確認されたといえるだろう。
ただし、以上の多変量解析を使った吟味は、採用されている10の質問項目が完全に満足のいくものであることを示すものではない。率直にいうと、その中にやや問題のある質問項目も含まれていることも示唆している。この章で採用されている質問項目リストは、第3章で、ぬるま湯比率を説明するという観点から大幅に改訂されることになる。本書の第2部で使用されるのは、この大幅改訂版の質問項目リストである。詳しくは第3章を参照のこと。
この章では、なぜ「ぬるま湯」現象が問題なのか、より具体的には、「ぬるま湯」現象と企業の業績、特に成長性との間にはどのような関係があるのか、ということを考察することにしよう。こうした作業を通して、なぜ、ぬるま湯的体質が企業から問題視されるのか、そして、なぜ、ぬるま湯的体質が「組織の活性化していない状態」の典型という発想が生まれるのかを明らかにして行きたい。
「ぬるま湯」現象については、第1章でまとめられたような一連の研究で、そして、組織の活性化については、既に高橋(1987c)で、それぞれの現象についての分析の枠組みと測定手法についての提案がなされ、ヒアリングと質問票調査によって得られたデータを基にした検討が行われている。高橋(1989f)はこれら一連の研究成果を結び付けることによって理論的な推論を行い、組織の活性化された状態とぬるま湯現象という、一連の研究の中で概念的にはまったく独立の現象として扱われていた二つの現象をつなぐ予想を「あとがき」の形で提示して締めくくっている。この予想は次のように仮説の形に整理することが出来る。
仮説3 (成長性先行仮説). (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、また活性化された状態が比較的容易に達成されうるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。組織の活性化された状態とぬるま湯現象は、もともと概念的には独立であり、直接的には因果関係の存在しない現象である。にもかかわらず、この仮説3によれば、
というように、両者には成長性という共通の先行変数があるため、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。この章は、この仮説を検証することを目的としている。そこで、まずは、この仮説に到達するに至った道筋を、高橋(1989f)に従って簡単に考察し、その後、この仮説を検証するために新たに企画され、1989年に実施された調査(以下「1989年調査」と略記)の結果からこの仮説3の妥当性を検証してみることにしよう。
なお、この章では、第1章でも取り上げられた1987年調査、1988年調査に加えて、1989年調査の計3回の調査データが用いられているが、そのうち、企業別のデータが扱われる1989年調査では第1章とは独立別個にA社〜J社とラベルを付けることにする。
「組織の活性化」という用語は、1970年代半ば頃からしばしば用いられるようになったが、主に組織開発の分野で日本にある考え方や技法などをすべて包括しているあいまいな概念であるといわれる(馬場, 1989)。実際、活性化にしろ、活力にしろ、ひろく使われている用語にもかかわらず、企業や組織に関して用いられる場合には、必ずしもその真意は明確ではない。例えば、通産省産業政策局 (1984) のレポートでは「活力ある企業活動」を「企業が市場ニーズに対応して、新製品の開発、製品の高品質・低価格・早納期を積極的に実現していくこと」と定義している (p.6)。こうして定義すると、これはコンティンジェンシー理論にみられる環境適応のアイデア(例えば、Lawrence & Lorsch (1967)、加護野(1980)、岸田(1985))と似ているようにも見える。
しかし、活性化の場合には、実際には、コンティンジェンシー理論のように、環境の様々な状態に対して、「それぞれの状態に適した組織の活性化」が考えられるわけではない。一般には、環境の状態が等しければ、より高い業績を挙げる組織の状態が普遍的に存在することを想定し、その状態を「活性化された状態」と考えているのである。すなわち、活性化された状態とは環境の状態にかかわらず、良い状態であり、環境の状態との組み合わせで善し悪しが決まるという性質のものではない。その上、必ずしも高業績に結び付いたものでもない。
活性化された状態とは、先程の通産省のレポートの定義で言えば、「積極的に実現していく」ということに重点が置かれた概念である。組織の活性化された状態(activated state)とは「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」ではないだろうか。この定義は、Barnard (1938, p.82 邦訳p.85)の組織成立の必要十分条件「組織は、(1)相互に意思を伝達できる人々がおり、(2)それらの人々は行為を貢献しようとする意欲をもって、(3)共通目的の達成をめざすときに成立する。」とも基本的に合致している。ちなみに、「組織の活性化」はもともと外来語ではないので、英語の原語は存在しないが、Takahashi (1992b)やKawai (1992)はこれに"organizational activation"という英訳語をあてている。
もともと、組織の活性化された状態をこのように定義しようという基本的なアイデアは、数理的な組織設計論(Takahashi, 1983; 1986a; 1987a; 1987b; 1987c; 1988)から得られたものである。これら一連の数理的組織設計論の研究、特に、Takahashi (1987c; 1988)では、課業の選択過程が逐次決定問題として定式化されるような組織についての組織設計問題を経営学及び経営組織論の概念的枠組みに基づいて考察している。組織構造は課業の割り当てシステムとして、管理システムは環境の観測過程における伝達システムとして定義された上で、組織形態はこの組織構造と管理システムとの組で表現され、課業の逐次決定モデルの一部を構成することになる。このとき組織設計問題とは、最も低い損失・コストで課業を決定し、実行しうるという意味での「効率的な組織形態」を求めることである。統計的決定理論の議論を適用すると、Davis & Lawrence (1977)の主張やBurns & Stalker (1961)の主張を支持する諸命題が得られるが、これらの諸命題は、実際に日本企業を対象として行なった実証研究(高橋, 1985; Takahashi, 1986; 1987a; 1987c; 1988)によっても支持されている。
ところで、このような数理モデルを用いて構築された理論は、その常として、いくつかの仮定の上に成り立っている。これらの仮定のうちのいくつかは、理論の一般性を制限するという点で厄介なものであるが、同時に、組織設計の制約条件として実質的に意味をもつものであることが、実際の日本企業の調査研究が進むにしたがって、しだいに明らかになってきた。それが、組織の活性化された状態の定義にある三つの条件なのである。
このような数理モデルと仮定の関係をふまえれば、数理的な組織設計論は、効率的組織形態が環境、特に環境の不確実性に依存していることを示しているが、こうした組織設計問題に対する解答は、ある一定の仮定の下でのみ意味をもっているということができる。そして、これらの仮定を満たす組織、すなわち活性化された状態にある組織は、環境の不確実性に応じて組織形態を選択しうる組織ということになる。効率的組織構造や効率的管理システムが環境の不確実性に依存していたとしても、活性化された状態にある組織は、組織設計問題の解がひとたび得られれば、その効率的な組織形態を選択することができるのである。つまり、環境の不確実性に応じて、常に「効率的」な組織でいることができる。コンティンジェンシー理論が主張するように、組織化に唯一最善の方法は存在しないが、状況に応じて最善の組織化の方法を選ぶことを可能にするような組織の類は存在する。それが活性化された状態にある組織なのである。
いまの話を組織特性という視点から整理してみよう。組織の特性は大きく二つの種類に分けて考えることができる。一つは長期的な特性で、組織設計の場合には所与と考えられている人的特性あるいは組織風土のような固定的なものである。これはトップが変えようと思っても、なかなか一朝一夕には変えられない。もう一つは短期的な特性であり、組織形態のように、トップが変えようと思えば変えることができる、いわば可変的な特性である。
この区分は、第1章の体感温度仮説の議論における体温とシステム温にそれぞれ対応させて考えるとわかりやすい。個人の体温は仮説2の恒温仮説のように、システム温の変動にかかわらず安定的であるのに対して、システム温の方はトップの経営施策や組織改編などによって高めることが可能である。仮に1.5節(3)での議論の通り、システム温が上昇すると、それに耐えられない低体温の人が組織を離れていくとすれば、人材の頭数の維持、確保を第一と考えたとき、メンバーの体温はシステム温を上げる際の制約条件となる。したがって、当然、高システム温をともなう組織形態を採用する際にも制約条件となるわけで、人的特性のような固定的で長い時間をかけないと変えられない特性は、組織形態のような可変的な組織特性を変える場合には、主に制約条件として作用することになる。
コンティンジェンシー理論では、通常、組織形態と環境(特にその不確実性)との間の適合性が論じられるが、Morse & Lorsch (1970)のように、人間の問題の重要性を主張したごく一部の例外を除くと、組織メンバーの人的特性にはほとんど注意が払われてこなかった(岸田, 1985, p.105)。しかし、組織形態と環境との間の適合性のみをみるのではなく、どの組織形態をとりうるのかについては人間的な要因を明確に制約条件として考慮すべきである。このことがまさに数理的組織設計論の示唆する重要な観点である。つまり、図2.1にあるように、単なる環境適応ではなく、人間的制約条件のもとでの環境適応の組織設計を考えるということが、組織設計論のより正確な姿なのである。
図2.1 組織の特性と変化性向
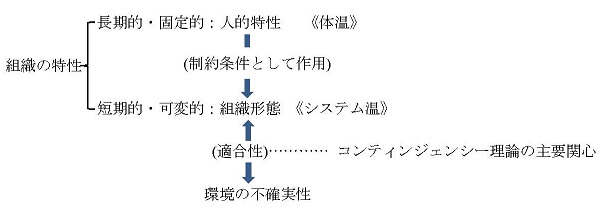
組織が活性化され、「組織のメンバーが、①相互に意思を伝達し合いながら、②組織と共有している目的・価値を、③能動的に実現していこうとする状態」にある組織は、少なくともTakahashi (1987c; 1988)で考えられている組織形態の選択に関しては、その人間的制約条件をクリアーしている。こうして活性化された状態にある組織は、環境に応じて、「効率的」な組織形態を選択していくことができるということが数理的な組織設計論によって示唆されているのである。
このような活性化された状態にある組織を考えることで、業績と活性化とが必ずしも結び付いたものではないということをより明解に議論することができる。いま、もし人間的制約条件の下での選択可能な組織形態の中に、効率的組織形態がたまたま属していれば、その組織は、活性化された状態となっていなくても、効率的な組織形態をとることができ、それは高業績につながるのである。つまり、活性化された状態は高業績の十分条件ではあるが、必要条件ではないのである。
こうした数理的組織設計論を背景とした組織の活性化された状態の評価、測定手法は、I I図法(I-I chart method)として既に開発され、その有用性も確認されている(高橋, 1987d; Takahashi, 1992b)。その概要については、章末付録の解説を参照のこと。
ところで、ここで提示されたような組織の活性化された状態の定義は、一般にもたれている「活性化」のイメージとどの程度重なるものであろうか。このことについて、第1章でも取り上げられた1987年調査、1988年調査のデータを再利用して調べてみることにしよう。
1987年調査では、次のような質問を設定しておいた:
Q3.あなたは、あなたの会社は活性化していると考えますか?さらに、1988年調査では、質問をYes-No形式に改めて、
Q3'.自分の会社は活性化していると思う。という質問を設定しておいた。これらの質問を除く1987年調査での50問、1988年調査での89問の計139問のYes-No形式の質問と質問Q3、Q3'との間で2×2クロス表を作り、それらのうち相関の高い質問項目として、便宜的に相関係数であるV 係数(Cramer's V )の絶対値が0.3以上のものを拾いあげてみると、1987年調査では0問、1988年調査では6問になった。それを、組織の活性化された状態の定義である「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」に対応させると、
といったように対応が付けられる。( )内は有効オブザーべーション数を示している。
以上のことから、「活性化」のイメージは組織の活性化された状態の定義とほぼ重なっていることがわかった。逆にいえば、組織が活性化された状態にあるかどうかは、前述のYes-No形式の質問Q3'を使っても、直接的にきくことができると考えられる。
それでは、組織の活性化とぬるま湯感が、なぜいま問題になっているのかという観点から、ここで提示した枠組みに基づいて、改めて考えてみることにしよう。
いま、成長期にある企業について考えてみよう。もし、企業が高成長を続けているのであれば、その組織のほとんどの特性、変数は、単調に大きく増加、もしくは単調に大きく減少といったように、単調に、しかも大きく変化することになるだろう。つまり、十分な成長性は企業、組織の内部に単調性と高い変化率をもたらすのである。このことは重要である。一つには、組織自体の変化率が大きいことから、組織が現状に留まることは、したくてもできず、組織のシステムとしての変化性向も大きなものとならざるをえない。そのため、仮説2の恒温仮説のいうように、メンバーの体温が安定しているのであれば、ぬるま湯感は自然と低く抑えられることになる。
もう一つには、単調性があれば、企業全体の方向性や戦略が明確に分らなくとも、メンバーは自らが向かうべき進路を、企業全体の方向性に反しない範囲で知ることができる。つまり、メンバーは全体のことを知らなくとも、自分の回りのごく狭い世界(これはMarch & Simon (1958)の状況定義にあたる)を構成する変数の過去から現在への動きを知っているだけで、単純に、その延長線上に進むべき未来像を描くことができる。これは組織の活性化された状態の定義である「組織のメンバーが、(1)相互に意思を伝達し合いながら、(2)組織と共有している目的・価値を、(3)能動的に実現していこうとする状態」のうちの(2)が容易に達成されることを意味している。さらに、高成長のもたらす活気が③をも可能にし、比較的容易に「活性化された状態」が達成されうることになる。
ところが、企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、こうした事態は一変する。単調性はあちらこちらで屈折し、混迷へと急速に推移する。企業全体の方向性や戦略が明確に打ち出されなければ、そして、それが、メンバーの間にきちんと浸透しなければ、メンバーは自らの向かうべき方向を見失う。自分がいま何をなすべきかを見失うのである。暗闇の中では、人は積極的に動くことができない。こうして、活性化された状態は失われてしまう。
しかも、組織自身の変化率が低下しているので、何か人為的に変化性向を高める努力をしない限りは、組織のシステムとしての変化性向も低迷することになる。たとえ、自分が能動的、積極的に動き、変化を求めたくとも、組織、職場のシステムがそれを受け止め、促すような状況にはなってはいないために、低システム温のもとで、体感温度仮説の筋書き通りに、ぬるま湯感もまた進むことになるのである。
以上のようなことから、組織の活性化された状態とぬるま湯現象は、概念的には独立の、直接的には因果関係の存在しない現象であるにもかかわらず、成長性という先行変数があるために、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。したがって、前述の仮説3が立てられることになる。仮説3を再掲しておこう。
仮説3 (成長性先行仮説). (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、また活性化された状態が比較的容易に達成されうるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。さて、そこでこの仮説3を検証するために、1989年調査が企画、実施された。対象となった企業は、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1989年度の参加者の所属企業10社である。調査は、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。第1段階として、まず、1989年6月9・10の両日に合宿形式で集中的に、1社平均80分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答が行われた。さらに、この各社1人ずつの10人と筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かヒアリングを行い、各社の特性を浮き彫りにする作業が行われた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選んで、その職場の構成員に対して、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は5ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数にも93人から198人まで開きがあるが、10社全体で、総職場数は73ヶ所、総調査対象者数は1,392人、職場当りの平均調査対象者数は19.1人となっている。1989年8月30日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月4日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、1,228人から質問調査票が回収できた。回収率は88.2%であった。回収された質問票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
仮説の検証のためには、あらかじめ、成長段階上に各社を相対的に位置付けておく必要がある。第1段階のヒアリング調査の結果、次のようにヒアリング対象者自身によって相互の比較、位置付けが行われ、10社が成長段階に沿って順序をつけられて並べられた。さらにその上で、10社を次のように3グループに分けた。
A社は1970年に日米の自動車メーカーの共同出資によって設立された自動車部品メーカーであるが、設立以来、順調に成長を続け、納入先も拡大して、売上高、販売台数ともに伸び、工場も次々と増設されている。1988年度の売上高、営業利益の対前年度比の伸び率はそれぞれ23%、35%にもなり、まさに成長段階にあるといえる。
B社は大手の百貨店であるが、順調に成長を続けている。売上高は1988年度は対前年度比で10%伸びている。業界の中での売上高の順位、特に、主力店舗のランキングも上昇している。しかしそれにもまして、むしろ百貨店単独というより、自ら中核をなす企業グループとしての事業領域の拡大がめざましい。
C社は生命保険会社である。生命保険会社の場合は、普通の企業でいえば利益に相当する剰余金は安定的にコントロールされるために、業績の指標にはならない。指標として用いられる総資産、収入保険料の点では、1988年度は対前年度比でそれぞれ36%、51%も伸びている。その業績の基礎となっている外勤職員も順調に増えている。企業規模、外勤職員数を2倍にしようという1987年度にスタートした5ヶ年計画の最中のこともあり、高成長を続けている。
D社は大手の総合不動産業者である。売上高、営業利益ともに順調に伸びており、1988年度は対前年度比でそれぞれ19%、22%伸び、13期連続の増益を記録している。事業領域も拡大を続け、子会社展開の形で、企業グループとして、ホテル、ショッピング・センター、レジャー、リゾート事業にも積極的に取り組んでいる。
E社は鉄道会社である。公益事業であるために、その点では、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。ただし、E社に限っていえば、規制の自由化の可能性があるために、近い将来の事業領域拡大の期待が高まっているが、まだ実現には至っていない。
F社は電気通信業者である。E社と同様に公益事業であるために、売上高、利益とも安定的にコントロールされている。ただし、今回の調査はソフトウェアの技術部門に限定している。
G社は米国の国際石油資本を大株主とする外資系の石油輸入・精製業者である。近年の好景気と原油安、円高を反映して、石油業界全体として需要が堅調ということもあるが、それだけではなく、ガソリン中心の生産体制が、重油・灯油価格抑制政策の下で有利に作用して、業界他社が業績不振に苦しむ中でも高業績を維持し続け、最近10年間の平均経常利益でみても約500億円と業績は業界他社と比べ高水準で安定している。
H社は食品を主としたメーカーであるが、主力となっている乳製品が売上高、利益とも安定しているために、安定期にあると考えられる。
I社は農業機械の大手寡占メーカーの一つであるが、主力機種の普及率が向上してしまっている上に、国の減反政策をはじめとする農業政策のあおりを受けて、市場のパイ自体が縮小を続け、シェアは維持しているものの売上高は減少している。営業利益は改善しつつはあるが、調査時点ではまだ赤字になっている。
J社はもともと海上土木工事を中心とした建設業者であった。しかし、国内の港湾は整備が進んでしまっている上に、依存度が約7割と高い官公庁の財政難や公害反対運動などが影響し、海上土木工事は伸び悩んでいる。このため、陸上土木や建築工事への進出により総合建設業(ゼネコン)への脱皮をめざしている。現在のところ、進出したての建築工事は施工量が急速に増えている割には利益が薄く、他方、本来の海上土木工事の方はパイ自体が小さくなったため、部門による差異はあるものの、全体としてはまだ低迷期から完全に脱しきれているとはいえない。
以上のようなヒアリング調査の結果を、従業員の意識のレベルでも確認するために、第2段階の質問票調査では、成長期、安定期、低迷期という3グループをそのまま選択肢として、次のような質問を作成して、直接的にきいてみた。
Q4. あなたの会社の現状は次のどれに該当すると思いますか?その結果は、表2.1のようになった。各社における過半数を占める選択肢はヒアリング調査と一致しており、ヒアリング調査の結果を明確に裏付けているといっていいだろう。その中でただ1社、J社については、過半数を占める選択肢がなく、意見が三分された状態にあるが、これは部門による違いをそのまま反映したものと考えられる。
表2.1 成長段階についての回答(1989年調査)
| ヒアリング による分類 | 従業員の回答 (Q4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成長期 | 安定期 | 低迷期 | 計 | ||
| 成長期 | A社 | 153 (93.9) | 10 (6.1) | 0 (0.0) | 163 |
| B社 | 56 (68.3) | 9 (11.0) | 17 (20.7) | 82 | |
| C社 | 146 (82.5) | 30 (17.0) | 1 (0.6) | 177 | |
| D社 | 70 (59.8) | 47 (40.2) | 0 (0.0) | 117 | |
| 安定期 | E社 | 50 (39.4) | 71 (55.9) | 6 (4.7) | 127 |
| F社 | 48 (37.8) | 65 (51.2) | 14 (11.0) | 127 | |
| G社 | 6 (5.8) | 71 (68.9) | 26 (25.2) | 103 | |
| H社 | 27 (19.6) | 105 (76.1) | 6 (4.4) | 138 | |
| 低迷期 | I社 | 2 (2.7) | 1 (1.4) | 69 (95.8) | 72 |
| J社 | 35 (31.0) | 49 (43.4) | 29 (25.7) | 113 | |
| 全体 | 593 (48.6) | 458 (37.6) | 168 (13.8) | 1219 | |
こうした結果をふまえて、いよいよ仮説の検証に入る。この作業に使われる活性化とぬるま湯感についての質問についてみてみよう。ぬるま湯感については、第1章で取り上げたぬるま湯感についての質問
Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。を用いた。これには、63.8% (771人)がYes、36.2% (438人)がNoと答えている。
活性化については、前述の質問Q3'の「自分の」の部分だけを削った質問
Q3". 会社は活性化していると思う。というYes-No形式の質問で直接的にきいてみることにした。これには58.2%(709人)がYes、41.8%(510人)がNoと答えている。こうした方法をとる理由は、まず、活性化についてできるだけ簡単に1変数で取り扱いたいということ。もう一つの理由は、2.2節(3)で述べたが、1987年調査や1988年調査のデータから、この質問に対する回答が、組織の活性化された状態の定義とかなり合致したイメージをもっていたということである。
そこで、各社において、質問Q3"で、Yesつまり活性化していると答えた人の比率を「活性化比率」と定義し、質問Q1でYesつまりぬるま湯を感じると答えた人の比率を「ぬるま湯比率」と定義しておこう。わかりやすいように、この二つの比率を使って、各社のこの二つの質問に対する回答をみてみよう。その結果は表2.2に示されるが、この二つの質問に対する回答は会社間で0.1%水準で有意な違いがみられる。
表2.2 会社別の活性化比率とぬるま湯比率(1989年調査)
| ヒアリング による分類 | 活性化比率 | ぬるま湯比率 | |
|---|---|---|---|
| 成長期 | A社 | 63.2 (163) | 59.3 (162) |
| B社 | 69.5 (82) | 57.8 (71) | |
| C社 | 86.5 (178) | 51.1 (178) | |
| D社 | 88.0 (117) | 59.0 (117) | |
| 安定期 | E社 | 62.5 (128) | 63.6 (129) |
| F社 | 50.0 (126) | 61.9 (126) | |
| G社 | 42.6 (101) | 52.5 (101) | |
| H社 | 42.3 (137) | 76.3 (139) | |
| 低迷期 | I社 | 12.3 (73) | 86.3 (73) |
| J社 | 34.2 (114) | 81.4 (113) | |
| 全体 | 58.2 (1219) | 63.8 (1209) | |
| Cramer's V | 0.431 | 0.227 | |
| χ2 | 226.27*** | 62.45*** | |
明らかに、成長期の企業は活性化比率が高く、成長期にあるA社〜D社がこの活性化比率の上位4位までを占めている。さらに、低迷期にある企業2社はぬるま湯比率が飛び抜けて高く、80%以上となっている。この表2.2は仮説3を支持している。実は、1987年〜1989年の3回の調査を行ってきた中で、このようにはっきりと低迷期と判断される企業が調査対象に含まれていたのは、この1989年調査だけであった。1989年調査が、1988年調査のように中間管理職に対象を限定したわけでもないのに、ぬるま湯比率が63.8%と比較的高く、1987年調査と1988年調査のちょうど中間あたりの値になっている背景には、こうした低迷期の企業が含まれていたことも一因になっていたと考えられる。
さらに、仮説3が正しければ、ぬるま湯感と活性化との間には疑似相関が見られるはずだが、実際に、ぬるま湯感と活性化との間には表2.3のクロス表に示されるような相関がみられる。これによると、両者には負の相関関係があり、これは0.1%水準で有意となっている。仮説3は、こうした相関関係が、表面的、間接的なものであり、成長性という先行変数があるために、見かけ上の疑似相関があるということを主張しているのである。
表2.3 活性化とぬるま湯感の関係(1989年調査)
| Q3". 会社は活性化 していると思う。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」 だと感じることがある。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 385 | 313 | 698 |
| No | 380 | 123 | 503 |
| 計 | 765 | 436 | 1201 |
そこで、そのことを確かめるために、各社ごとにぬるま湯感と活性化の相関関係を示した3重クロス表を作ってみよう。表2.4はその3重クロス表を示している。このクロス表によると、10社のうち、A社、F社、H社の3社については、ぬるま湯感と活性化との間に有意な相関関係がみられたが、他の7社については、10%水準でも有意な相関関係は見いだせなかった。相関係数の大きさで見ても、全体での相関と同程度、もしくはそれ以上の相関係数が見いだせたのは、A社、F社、H社の3社だけであった。特に、C社、G社、I社、J社については、ほとんど無相関といってもよい。このことから、仮説3はほぼ検証されたといっていいだろう。
表2.4 会社別・活性化別のぬるま湯比率(1989年調査)
| ヒアリング による分類 | Q3".会社は活性化していると思う。 | 相関係数 Cramer's V | χ2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yes群 | No群 | ||||
| 成長期 | A社 | 51.46(103) | 72.88(59) | -0.210 | 7.132** |
| B社 | 54.00(50) | 66.67(21) | -0.117 | 0.972 | |
| C社 | 52.29(153) | 45.83(24) | 0.044 | 0.346 | |
| D社 | 56.31(103) | 78.57(14) | -0.147 | 2.524 | |
| 安定期 | E社 | 58.75(80) | 70.83(48) | -0.121 | 1.885 |
| F社 | 46.77(62) | 76.19(63) | -0.302 | 1.431** | |
| G社 | 51.22(41) | 52.63(57) | -0.014 | 0.019 | |
| H社 | 56.90(58) | 89.87(79) | -0.381 | 9.891*** | |
| 低迷期 | I社 | 77.78(9) | 87.50(64) | -0.093 | 0.631 |
| J社 | 76.92(39) | 83.78(74) | -0.084 | 0.795 | |
つまり、図式化すると、さきほどの表2.3のクロス表は
というように、活性化しているほど、ぬるま湯感が減少しているように、あるいは、ぬるま湯感が減少するほど活性化しているように見える。しかし、表2.4の3重クロス表によれば、実は、これは大部分が「成長性」という先行変数があるための疑似相関であって、
という関係があるのだということになる。したがって、成長期の企業は活性化していて低ぬるま湯感、低迷期の企業は活性化していなくて高ぬるま湯感という特徴を持ち、全体として総計すると、見かけ上、活性化とぬるま湯感の間に相関関係がみられると考えられるのである。
このように、ぬるま湯感と活性化という2変数に対して、成長性という第3の変数を導入して、分析することは、エラボレイション(elaboration)と呼ばれる。ここでの場合は、仮説3から成長性を先行変数として導入し、ぬるま湯感と活性化の疑似相関を説明するので、特にエクスプラネイション(explanation)とも呼ばれる(安田・海野, 1977)。
したがって、疑似相関であるから、ぬるま湯比率と活性化比率との間には、直接の因果関係は存在せず、ぬるま湯比率を人為的に変化させても、直接的には活性化比率に変化は生じないはずである。そのことは実際にも確かめることができ、その良い例がG社である。G社は、調査年の1989年に社名を変更して、調査時点ではCIの真っ最中であった。しかも実際には、その数年前から、実力主義による賃金・処遇の決定、新部門の設置や合理化の推進に伴う本社及び事業所の既存組織の改組などの組織の積極的な改革、改訂、そして、広報機能の充実による企業イメージの向上といった様々な経営施策の展開、実施を行っている。
このような場合、第1章の仮説2の恒温仮説が正しく、個人の体温が比較的安定しているならば、CIなどによってシステム温が上昇したときには、ぬるま湯感が低下することになる。しかし活性化については、それほど短期間には成果のあがるものではない。そのことは図2.2によってはっきり示されている。図2.2は表2.2をグラフ化したものであるが、これによると、成長期の4社、安定期の4社、低迷期の2社はそれぞれグループをなしていて、さらに、G社を除くと、決定係数R2は0.8575(G社を含めたままだと0.6121)とほぼ線型の関係が見いだされる。しかし、安定期に分類されたG社は、その線型の関係からははずれている。つまり、活性化比率については確かに安定期の水準にあるが、ぬるま湯比率については成長期の企業と同水準になっているのである。したがって、G社については、他社の傾向と比較して、活性化比率についてはあまり変わらずに、ぬるま湯比率だけが低下したということがはっきり示されているのである。以上の分析の諸結果から、仮説3は検証された。
図2.2 活性化比率とぬるま湯比率(1989年調査)
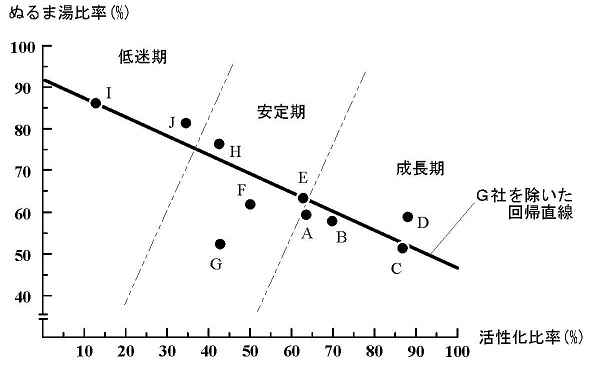
注) G社を除いた回帰直線は次のようになる。
y = 91.92 − 0.4535x
(21.539***)(−6.490***)
R2=0.8575 (F =42.117***)
これまでの分析によって、冒頭に掲げた仮説3は検証され、活性化とぬるま湯感が、企業の成長性によって結び付けて考えられることが明らかになった。しかし、前章でも述べたように、ぬるま湯の状態は確かに「適温」の状態ではなかったが、不活性の典型である「水風呂」とも違っていた。活性化あるいは不活性化とぬるま湯感の重なりは、常態として存在しているといっていいだろう。そのことは、どの企業にとってもいえることである。
2.2節でも触れたように、「組織の活性化」という用語は1970年代半ば頃からしばしば用いられるようになったといわれるが、これは、日本が高度成長期から安定成長期に移行して、たとえ成長するにしても、それまでの戦後の経済復興期や高度成長期のような単純な成長ではなく、分社化や企業グループ形成、さらにはリストラクチャリングといった複雑な様相を呈するようになってから、「組織の活性化」が叫ばれるようになったと考えることもできる。そして、こうした活性化の必要性が叫ばれる状況に軌を一にして、ぬるま湯感も進行していたと考えられるのである。
実は、これまで扱ってきた調査の過程で、組織の活性化について、ヒアリングをして印象に残ったことがある。それは、企業全体の戦略や方針をトップが明確に示して欲しい、そして、それをきちんとブレークダウンして、組織の下部まで浸透させることが重要なのだということが必ず意見として出されるのである。よく考えてみると、企業、組織は成長しなくても、明確に全体の方向性が打ち出されれば、活性化することは可能なのである。高成長期には何もしなくとも、組織内に単調性が生まれ、活性化することは容易だったわけだが、低成長期にであっても、意図的に、一体化すべき方向性、つまり、目的、価値を明確に打ち出し、メンバーに積極的に動けるような状況を作り出すことで、活性化を導くことはできるのである。
その意味では、ヒアリングの中で戦略、方針の明示を渇望しているということは、偶然ではなく、まさに本稿で明らかにされたような意味での組織活性化を渇望して、本能的に求めた施策であると考えることができる。その意味で、高橋(1989a; 1989b)が明らかにしたNTTの新規事業開発の事例は、民営化プロセスの中で、子会社戦略を180度転換させ、基本原則を確立することで、別会社を舞台にした新規事業展開の戦略、方針と「民営化」の具体像を明示することに成功した事例だといえるのである。
第1章の仮説2の恒温仮説のいうように、体温はかなりの期間、安定的に維持されること、そして、それに比べシステム温はより容易に変動しうるもののようだということがG社の事例によっても示されている。しかも、システム温は企業の成長性とかなりの程度連動するものであり、そのために、活性化との間にも疑似相関が見られたのである。したがって、ぬるま湯感の発生や活性化の必要性の強調は、その企業の成長性が衰え始めることで、システムの変化性向、すなわちシステム温が低下して、同時に、メンバーが方向性を見失い始めているという意味での危険信号、シグナルになっていると考えられるのである。
この付録では、Takahashi (1992b)を基にして、組織のメンバーの組織人特性に焦点を当てた組織分析の手法としてI I図法(I-I chart method)を概説する。すなわち、組織の活性化された状態の定義のうち、特に、組織人特性を規定している(2)(3)を取り上げ、(2)の組織と目的・価値を共有している程度を表すものとして一体化度指数を、(3)能動的に思考している程度に関連して無関心度指数を設定し、その上で、この二つの指数を座標軸にした図が、組織の活性化分析の手法としてのI I図である。
Barnard (1938, pp.167-170 邦訳p.175-178)はおのおのの組織メンバーには「無関心圏」(zone of indifference) が存在し、その圏内では命令の内容は意識的に反問することなく受容しうるのだと考えた。つまり、代替案レベルでは無関心圏が存在し、命令を受けた者は無関心圏内にある代替案に対しては無差別で、それが何であるのかについて比較的無関心に、命令を受け入れるのである。この考え方は Simon (1976) にも「受諾圏」(zone of acceptance または area of acceptance)という概念で受け継がれている。無関心圏がより大きいということは、上司の命令に対して忠実で従順である範囲がより広いということを意味しているのだが、反面、その範囲の中では受動的であるために、組織の中で受け身でいることが多いことも意味している。つまり、無関心圏の大きさは、受動的か能動的かといったメンバーの特性にかかわってくることになる。そこで、無関心圏の大きさを表す指数として無関心度指数(indifference index)を考えた。すなわち、組織メンバーの課業・処遇等に本質的に重大な影響を及ぼすはずの経営諸施策等に対して、どの程度まで無関心でいられるのかをこの指数で表した。
次に一体化についてであるが、ある人が意思決定を行うにあたって、特定の集団にとっての結果の観点からいくつかの代替案を評価するとき、その人はその集団に自身を一体化している(Simon, 1976, p.205 邦訳p.260)という。言い換えれば、メンバーが組織と目的や価値を共有しているとき、そのメンバーは組織に自身を一体化している状態にあるといえる。そこで、一体化の程度を表す指数として一体化度指数(identification index)を考えた。無関心度指数のときと同じ質問を用いて、組織メンバーの課業・処遇等に重大な影響を及ぼすはずの経営諸施策等に対して、個人の立場からの評価と、会社の立場からの評価がどの程度一致しているのかをこの指数で表した。
より具体的には、各経営施策等の採用・実施状況について文章を完成させながら答える次のような一般的形式の質問を作成し、無関心度指数と一体化度指数の算出に用いた。
「経営施策名 は(1.行われている 2.行われていない)が、そのことによって、私は(3.働きがいを感じている 4.働きがいとは関係ない 5.働きがいを感じなくなった)。また、会社の活性化には(6.寄与している 7.関係がない 8.悪影響を及ぼしている)。」
下線部の経営施策名としては14種の経営施策等が用いられたが、そのうち二つの指数の算出には、組織メンバーの課業・処遇等に本質的に重大な影響を及ぼすはずの(1)異部門間でのジョブ・ローテーション、(2)引っ越しを必要とするような距離での転勤、(3)専門職制度、(4)年功序列・能力主義人事、(5)労働組合の活動、の五つの経営施策等の採用・実施状況についての質問の回答が用いられた。
無関心度指数は、五つの質問のうち「4.働きがいとは関係ない」と答えた質問の数で定義した。一体化度指数は、五つの質問のうち、次のどれかのケースに該当する質問の数で定義した。
したがって、無関心度指数、一体化度指数ともに、0から5までの整数値をとることになる。
いま一体化度指数、無関心度指数をそれぞれ縦軸、横軸にとったグラフをI I図(I-I chart; Identification-Indifference chart)と呼ぶことにする。前述のような一体化の現象と無関心圏のもつ意味から、I I図によってメンバーの組織人としての性格づけができる。一体化度指数の高低と無関心度指数の高低の組み合わせから、図2.3に示されるように、次のような四つのタイプに類型化して考えることができる。
図2.3 I I図によるメンバーの類型化
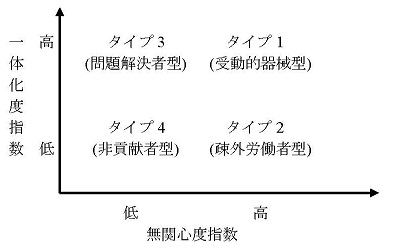
タイプ1 (受動的器械(passive instrument)型): 無関心度が高く、かつ一体化度が高い組織メンバーである。組織の要請・命令に忠実で、指示を受けて仕事を遂行する。組織と一体化して、目的・価値を共有しているので、動機づけはあまり問題にならない。
タイプ2 (疎外労働者(alienated worker)型): 無関心度は高いが、一体化度は低いメンバーである。命令には従うが、一体化の程度が低いために、個人的な目的・価値と組織の目的・価値が一致していない。つまり、表面的に命令にしたがっているのである。そのために、目的・価値の対立から、権力現象とか勤労意欲が組織内の行動の説明に重要となっていて、動機づけが中心的な課題となる。目的・価値の点では組織と一線を画しているが、行動の点では命令にしたがっているので、まさにビジネスライクに行動していることになり、よくいわれる公務員タイプ、官僚タイプに相当すると思われる。
タイプ3 (問題解決者(problem solver)型): 無関心度は低いが、一体化度が高いメンバーである。メンバーは無関心圏が狭いので、命令・指示の忠実な受け手というよりは、組織と共有している目的・価値に基づいて、組織の立場から自ら問題意識をもって、主体的に問題解決を図り、意思決定を行おうとする者である。
タイプ4 (非貢献者(non-contributor)型): 無関心度も一体化度も低いメンバーであり、個人的な目的・価値と組織の目的・価値が一致していない上に、命令にも従順ではなく、組織的な行動を期待できない者である。実質的には組織のメンバーとはいえない。
組織の活性化された状態の定義から、タイプ3の問題解決者型のメンバーが多ければ、組織は活性化された状態にあるということができる。つまり、組織にとっては、組織と一体化したメンバーによって、組織的行動を維持しつつ、メンバー各自の合理性を限界にまで最大限に発揮して、合理的に問題解決を図り、意思決定を行ってくれることを、前提にできるのであれば、あとは環境の不確実性に応じて、組織形態を適宜変更することで、コストダウンを図ることが、組織全体の能力、生産性を高めるという点から望ましいのである(Takahashi, 1992b)。『広辞苑』第3版(1983)によると、「活性化」とは「沈滞していた機能が活発に働くようになること。また、そのようにすること。」とあるが、組織の活性化された状態の定義は、まさに組織の本来持てる機能、力が活発に発揮されるような状態を人間的制約条件の観点から記述したものなのである。組織活性化とは組織メンバーを健全な問題解決者として覚醒させることを指しているといっていいだろう。
ところで、タイプ4は非貢献者型であり、実際には、このタイプのメンバーの多い組織は組織的行動がとれずに、存続が難しくなる。それ以前の問題として、そのような傾向をもった者をメンバーとして企業が受け入れるとは考えにくい。したがって、仮に、無関心度指数と一体化度指数が正しく設定されているとすると、次のような仮説を立てることができる。
仮説A1. 無関心度指数も一体化度指数も共に低いようなタイプ4の者は、実際の企業の組織には少ない。いま、タイプ1のメンバーを中心とした組織をタイプ1の組織、同様にタイプ2、タイプ3のメンバーを中心とした組織を、それぞれタイプ2の組織、タイプ3の組織と呼ぶことにしよう。仮説A1から、タイプ4の組織は考えないことにする。タイプ1・2・3のいずれかに組織特性を特定することで、理論的に組織がもつべき特徴が決まってくるので、数理的組織設計論の議論も用いると、(1)ピラミッド組織で、しかも社員は従順で、トップの設けた目標に全社一丸となって向かう傾向があるならば「タイプ1」。(2)ピラミッド組織で、しかも社員はトップダウンの命令には従うが、ビジネスライクで、セクショナリズムの傾向が強いならば「タイプ2」。(3)マトリックス組織ならば「タイプ3」。というように、実際の組織をその組織特性から予想して「タイプ1・2・3」に分類することができる(ここで、「 」は予想される組織特性であることを示している)。したがって、無関心度指数と一体化度指数が正しく測定されているならば、次の仮説にあるような関係が見いだされるはずである。
仮説A2. 「タイプ1・2・3」に予想類別された組織の間には、I I図上で、図2.3で示されたような相対的位置関係がある。こうして立てられた仮説A1、仮説A2ともに1986年に実施された調査によって検証され(Takahashi, 1992b)、無関心度指数と一体化度指数が正しく設定されているということが確認されている。
これまでは、2回の調査を通じて、体感温度仮説の検証を行ってきた。その結果、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明するという体感温度仮説の妥当性がデータにより裏付けられるとともに、一つの重要な事実発見、すなわち「非ぬるま湯」群の大部分が、実は「熱湯」ではなく、「適温」と呼ぶべき領域に属していたことがわかった。そこで、この章では、こうした事実発見をふまえて、「ぬるい」対「熱い」という対立図式を体感温度によって説明するのではなく、質問Q1:「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」に対して、Yesすなわち「ぬるま湯」と感じることがあると答えた人の比率、つまり「ぬるま湯比率」を体感温度で説明することを考えよう。あわせて、体感温度測定のための質問項目の改善を行うことにする。
そのために、まず、第1章で立てた仮説1の体感温度仮説の次のようなぬるま湯比率版を考える。
仮説4 (ぬるま湯比率に関する体感温度仮説). ぬるま湯と感じる人の比率をぬるま湯比率と呼ぶと、体感温度が高くなるほどぬるま湯比率は低下する。ところで、この仮説2を検証するには、1987年調査、1988年調査の質問項目はあまり適しているとはいえない。つまり、単調性のあるきれいな関係が出てこないのである。この原因は、1987年調査を実施してしまった後でシステム温や体温といった変化性向の概念に合いそうな質問項目を選んだために、採用された10の質問項目の中にやや問題のある質問項目も含まざるをえなかったことにある。具体的には、次のような問題点を指摘することができる。
以上のことから、第1章の仮説1の体感温度仮説の検証という点に限れば、一応、許容範囲内とはいえるものの、改善の余地は十分にあるといっていいだろう。ぬるま湯比率を説明するという観点から、改めて質問項目リストの吟味をする必要がある。
そのために、まずこれまでの質問票調査によって集積されたデータと経験をもとにして、質問項目の収集・整理が行われ、それを基にした質問調査票の設計を行い、1990年に予備調査と本調査の2回の調査を行って、質問項目リストの改善を図った。さらに追試として、1991年に調査を行い、質問項目リストの再吟味を行った。
予備調査では、その第1段階として、日本生産性本部経営アカデミー『人間能力と組織開発コース』を舞台にして、それまで既に1987年、1988年、1989年と行われていた組織活性化に関する調査において使用した質問調査票から、Yes-No質問項目を中心に候補となる質問項目を選抜した。その際の選抜基準は次のように設定した。
ここで、選抜基準1は誰が答えても明らかにYes、または明らかにNoとなる質問項目は除くという基準である。選抜基準2、3は会社間で回答に違いの出る質問項目を選ぶという基準で、2と3で有意水準の基準が異なるのは、1989年調査の回収数1,228人(回収率88.2%)が、1987年調査の580人(回収率84.1%)、1988年調査の626人(回収率81.3%)と比べて約2倍になっているためである。実は、χ2の性質として、相関係数の大きさが同じクロス集計表でも、オブザーべーション数が約2倍の1989年調査ではχ2の値も約2倍になってしまい、その分だけ有意になりやすい。1987年調査、1988年調査の5%水準で有意なχ2の値はほぼ14程度なので、自由度(この場合、自由度=調査対象会社数−1)の違いも考慮して、0.1%水準で有意なものにほぼ相当すると考えた。したがって、2、3の真意としては、1987年調査、1988年調査で5%水準で有意になった程度の「相関」の大きさの質問項目を1989年調査でも選抜したいので、その目安として、0.1%水準を採用したということである。
3回の調査の中で、全く同一の質問を2回以上使ったこともあるが、そうした場合には1種類として数えることにすると、以上の選抜の結果、186種の質問項目が候補として残された。この186種の質問項目の中から、さらに第2段階として、「組織活性化度の測定手法の開発」のための調査用に、100種類の質問項目が選ばれた。ただし、Yes、Noの比率が80%まではいかないものの偏りの大きい質問項目などに対しては、修正を加えている。(巻末の付録B参照のこと)。
このようにして、質問項目として選択された100の質問項目の中から、さらに、体温、システム温に対応する質問項目を絞り込むために、1990年に本調査に先だって予備調査が企画、実施された。この予備調査の結果、内容については、高橋(1990c)に詳しいが、ここでは、本調査の参考になる範囲にとどめて、予備調査の結果の概要について述べる。
予備調査で調査対象になったのは、事務・スタッフ部門、技術・製造部門、研究・開発部門を揃ってもっている、いわゆるメーカー2社である。販売部門については、子会社化されていたために、ここでは調査対象とはしなかった。この予備調査では、各社の主力となる一つの単位事業を選択し、この単位事業に対して、組織単位の設定を行った。
ここで、「組織単位」とは、従来「職場」として漠然ととらえていたものを、1990年予備・本調査を機により明確に定義したもので、
という基準を一応の目安にして設定した。この「組織単位」の概念は1990年本調査でも用いられることになる。こうして、正社員の人員規模50人程度のホワイト・カラーの組織単位が設定された。ただし、3の基準よりは2の基準を優先したので、「50人」にこだわると組織単位が複数の機能区分にまたがってしまうような場合には、人員規模を小さくして組織単位を設定している。その上で、これらの組織単位について、それを構成する個人全員を対象とした質問票による全数調査が、1990年3月に行われた。2社合計で、19の組織単位が選ばれ、671人に質問調査票が配布され、564人から回収できた。回収率は84.1%であった。
得られたデータに基づいて、体温、システム温、その他に次章で後述されるような変数を構成する質問項目をもとにして主成分分析を行ってみた。各質問項目はYes-No形式になっているので、Yesならば1点、Noならば0点といったようにダミー変数化した上で、各変数について、主成分分析を行っている。それとともに、体感温度仮説の検証も行われ、体感温度仮説はこの1990年予備調査のデータにより検証されている(高橋, 1990c)。この予備調査の結果を参考にして、質問項目のリストが絞られた。こうして得られた35項目からなる質問項目リストをもとにして、1990年本調査が企画された。
1990年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1990年度の参加者の所属企業9社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1990年6月15・16の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの9人と筆者の計10人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、予備調査の結果として絞られた35の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これはそれまでの3回の調査とほぼ同じ方法で行われた。つまり、まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、1990年予備調査の際に定義されたような「組織単位」を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には31人から245人まで開きがあるが、総組織単位数は39ヶ所、総調査対象者数は959人、組織単位当りの平均調査対象者数は24.6人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた9社959人に対して、1990年9月5日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月10日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、853人から質問調査票が回収できた。回収率は88.9%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
こうして得られたデータを基にして、論理的にシステム温、体温を表す質問項目と考えられるものの中から、さらに章末の付録でも取り上げられているような主成分分析、判別分析の結果を検討しながら絞り込みを行って、システム温、体温の2変数に対応して、次の各5問が選ばれた:
システム温1987年調査・1988年調査で採用されていた質問項目のうち、システム温については、この3.2節のはじめに問題点を指摘しておいた質問項目については結果的に除くことにした。代わりに、S7〜S9をまったく新たに加え、さらにS6についても、1987年調査・1988年調査当時の質問文S2よりも説明的な表現に改めた。体温についても、体温の平均を下げる必要もあって、全面的に見直しを行い、B1以外は質問項目を入れ替えることにした。これらの10の質問項目のうち、(−)で示してあるように、システム温の質問S6、S8、体温の質問B9については、Yesならば0点、Noならば1点、他の7質問項目については、Yesならば1点、Noならば0点を与えて、ダミー変数化した上で、各変数に対応する5問の合計点をシステム温、体温の値として定義することにした。
システム温の平均は2.13、標準偏差は1.41 (N =830)、体温の平均は3.08、標準偏差は1.49 (N =831)となり、システム温、体温とも0〜5の値をとることができるということを考えると、ほぼ適切な水準といえる。多変量解析を用いた体感温度算出式の吟味については、章末の付録を参照されたい。
そこで、いよいよ仮説4の検証にとりかかることにしよう。表3.1は第1章の表1.4、表1.5と同様に、
Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。という同じ質問を使って、ぬるま湯感と体感温度のクロス集計表であるが、仮説4では、ぬるま湯比率が問題になっているので、行ではなく、列で、つまり縦方向に百分率をとっていることに注意されたい。この表3.1から明らかなように、仮説4の通り、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率は単調に低下していく。この様子は、図3.1にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。図3.1では、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率が単調に低下していく様子がよくわかる。ただし、ここで注意を要するのは、体感温度T =4、T =5のところで、急にぬるま湯比率が落ちていることである。これは、T =4は8人、T =5に至ってはわずかに1人しかいないために、例えばT =5のときは、ぬるま湯比率は0%か100%しかとれないというように、とりうる値のキメが粗くなるために起こる現象と考えられる。そこで、T =4、T =5を除いて、試みに、最小2乗法で残りの9個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図3.1の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は0.9836となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この回帰直線によれば、体感温度0でぬるま湯比率はほぼ50%となり、ぬるま湯と感じるかどうかはほぼ半々となる。そして、体感温度が1高くなるごとに、ぬるま湯比率はほぼ6〜7%低下することになる。この図によって、体感温度のもつ意味はより明確に理解されるだろう。つまり、体感温度を測定することができれば、ある体感温度をもった人がどの程度の確率でぬるま湯感を感じるかを予測することができるのである。
表3.1 体感温度とぬるま湯比率(1990年本調査)
| 質問Q1 | 体感温度=システム温−体温 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| 1. Yes | 14 | 34 | 68 | 98 | 98 | 82 | 46 | 18 | 3 | 1 | 0 | 462 |
| 2. No | 3 | 12 | 31 | 51 | 80 | 69 | 61 | 31 | 8 | 7 | 1 | 354 |
| 計 | 17 | 46 | 99 | 149 | 178 | 151 | 107 | 49 | 11 | 8 | 1 | 816 |
| ぬるま湯比率(%) | 82.4 | 73.9 | 68.7 | 65.8 | 55.1 | 54.3 | 43.0 | 36.7 | 27.3 | 12.5 | 0.0 | 56.6 |
図3.1 ぬるま湯比率(1990年本調査)
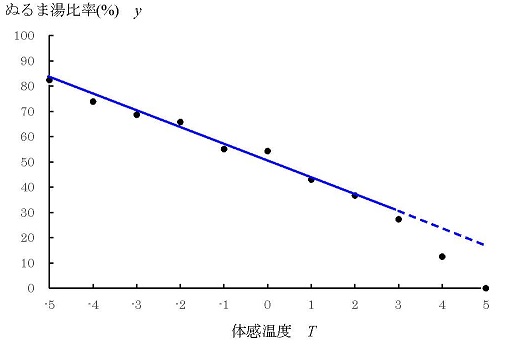
注) 直線は、該当者が少ないT =4,5を除いて、最小2乗法によって求めたもので、
y = 49.77 − 6.58T
(55.959***)(-20.488***)
R2=0.9812 (F =418.376***)
(+ p <0.1; * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001)
ところで、ぬるま湯比率を用いれば、オリジナル版の体感温度仮説である第1章の仮説1の図1.2(A)は別の表現をすることもできる。つまり、「高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率が高く、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯感が低い」というようにぬるま湯比率には差が出るはずである。そこで、システム温、体温の平均2.13、3.08を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように、二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、ぬるま湯比率を求めてみると、表3.2のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとにぬるま湯比率を求めてみたのである。これからわかるように、高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率は69.8%と7割にもなっているのに対して、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯比率は41.7%と4割にすぎない。また分散分析を行ってみると、低体温より高体温、高システム温より低システム温の方がぬるま湯比率が有意に高いこともわかり、オリジナル版の体感温度仮説である仮説1の図1.2(A)もぬるま湯比率で検証することができる。なお、分散分析は繰り返し数が不揃いなので、要因に階層構造を考えて、部分モデルに基づく平方和を求めたType Ⅱの平方和を用いている。
表3.2 ぬるま湯比率(1990年本調査)
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 69.8 (192) | 46.7 (169) | 59.0 (361) |
| 低 (0〜3) | 61.2 (304) | 41.7 (151) | 54.7 (455) |
| 全体 | 64.5 (496) | 44.4 (320) | 56.6 (816) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 4.29* |
| システム温 | 36.19*** |
| 体温×システム温 | 0.26 |
1990年本調査で行った体感温度仮説の検証を追試するために、1991年調査が企画実施された。
1991年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1991年度の参加者の所属企業6社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1991年6月14・15の両日に、合宿形式で集中的に1社平均120分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの6人と筆者の計7人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、1990年本調査で用いた10の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これは1990年本調査と同じ方法で行われた。つまり、まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、1990年本調査と同様に「組織単位」を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には90人から358人まで開きがあるが、総組織単位数は30ヶ所、総調査対象者数は1,017人、組織単位当りの平均調査対象者数は33.9人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた6社1,017人に対して、1991年8月28日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月2日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、907人から質問調査票が回収できた。回収率は89.2%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
システム温の平均は2.23、標準偏差は1.52 (N =888)、体温の平均は3.19、標準偏差は1.30 (N =893)となり、システム温、体温とも0〜5の値をとることができるということを考えると、ほぼ適切な水準といえる。1990年本調査のシステム温の平均2.13、標準偏差1.41 (N =830)、体温の平均3.08、標準偏差1.49 (N =831)と比較すると、システム温、体温ともにほぼ0.1高い水準になっている。多変量解析を用いた体感温度算出式の吟味については、章末の付録を参照されたい。
そこで、いよいよ仮説4の検証にとりかかることにしよう。表3.3は表3.1と同様に、ぬるま湯感と体感温度のクロス集計表である。この表3.3から明らかなように、仮説4の通り、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率は単調に低下していく。この様子は、図3.2にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。図3.2では、体感温度が高くなるにしたがって、ぬるま湯比率が単調に低下していく様子がよくわかる。ただし、1990年本調査と同様に、体感温度T =4のところで、急にぬるま湯比率が落ちている(T =5は一人もいない)。これはT =4は9人しかいないために、1990年本調査と同様にとりうる値のキメが粗くなるために起こる現象と考えられる。そこで、T =4を除いて、試みに、最小2乗法で残りの9個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図3.2の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は0.9549となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この回帰直線によれば、体感温度0でぬるま湯比率はほぼ64%となり、体感温度が1高くなるごとに、ぬるま湯比率はほぼ6%低下することになる。
表3.3 体感温度とぬるま湯比率(1991年調査)
| 質問Q1 | 体感温度=システム温−体温 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| 1. Yes | 17 | 52 | 84 | 133 | 121 | 101 | 60 | 26 | 9 | 1 | 0 | 604 |
| 2. No | 1 | 8 | 20 | 34 | 55 | 59 | 53 | 27 | 8 | 8 | 0 | 273 |
| 計 | 18 | 60 | 104 | 167 | 176 | 160 | 113 | 53 | 17 | 9 | 0 | 877 |
| ぬるま湯比率(%) | 94.4 | 86.7 | 80.8 | 79.6 | 68.8 | 63.1 | 53.1 | 49.1 | 52.9 | 11.1 | − | 68.9 |
図3.2 ぬるま湯比率(1991年調査)
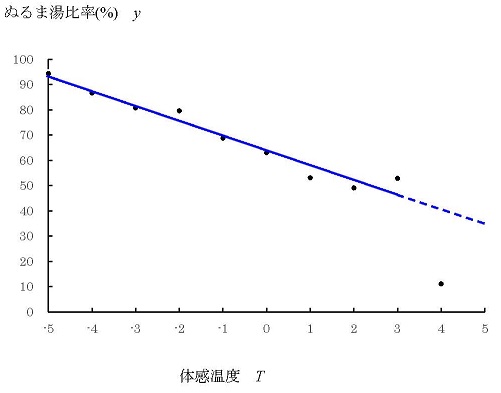
注) 直線は、該当者が少ないT =4, 5を除いて、最小2乗法によって求めたもので、
y = 63.99 − 5.85T
(48.128***)(−12.173***)
R2=0.9549 (F =148.173***)
さらに1990年本調査と同様に、ぬるま湯比率を用いてオリジナル版の体感温度仮説である第1章の仮説1の図1.2(A)の検証も行ってみた。システム温、体温の平均2.23、3.19を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように、二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、ぬるま湯比率を求めてみると、表3.4のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとにぬるま湯比率を求めてみたのである。これからわかるように、高体温・低システム温の領域ではぬるま湯比率は実に80.9%と8割を超えているのに対して、低体温・高システム温の領域ではぬるま湯比率は56.1%にすぎない。また分散分析を行ってみると、高システム温より低システム温の方がぬるま湯比率が有意に高いこともわかった。体温については、低体温より高体温の方がぬるま湯比率は高いものの有意な差にはなっていないが、オリジナル版の体感温度仮説である仮説1の図1.2(A)も1990年本調査同様にぬるま湯比率で検証することができる。なお分散分析には、さきほどの1990年本調査のデータのときと同様にType Ⅱの平方和を用いている。
表3.4 ぬるま湯比率(1991年調査)
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 80.9 (209) | 60.8 (143) | 72.7(352) |
| 低 (0〜3) | 78.4 (283) | 56.1 (173) | 70.0(456) |
| 全体 | 79.5 (492) | 58.2 (316) | 71.2(808) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 1.14 |
| システム温 | 44.86*** |
| 体温×システム温 | 0.13 |
3.2節でも述べたように、システム温、体温に対応する各5問は、1990年本調査において、システム温、体温、したがって体感温度を、その算出式における各質問項目(これは、Yes-No形式の質問を0-1形式にダミー変数化してある)を等しいウェイト1で単純に加算した等ウェイト算出式で算出してしまっても、実用上問題が起こらないように、多変量解析によるデータの分析結果を検討しながら選んだものである。そこで、確認のため、まず1990年本調査のデータを用いて、主成分分析、判別分析の結果を検討・吟味してみることにしよう。
まず、システム温・体温の主成分分析を1987年調査・1988年調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった質問項目S1、S6〜S9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.696, 1.104, 0.844, 0.712, 0.645 となり、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は
SPRIN1=0.455S1+0.452S6+0.489S7+0.405S8+0.431S9
となり、従来の質問項目に比べても、重み係数はほぼ一定しているといっていいだろう。
同様に、体温を算出する基となった質問項目B1、B6〜B9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.960, 0.980, 0.820, 0.659, 0.581 となり、第1主成分だけが約2で1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は
BPRIN1=0.515B1+0.499B6+0.509B7+0.351B8+0.322B9
となり、B1、B6、B7と比べて、B8、B9の重み係数が小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。
次に、1987年調査や1988年調査と同様に、同じ質問Q1「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」を使って、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群に分け、両群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。
u =−0.414+0.097S1+0.263S6+0.653S7+0.514S8+0.711S9
−0.254B1−0.311B6−0.022B7−0.138B8−0.191B9
この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。線形判別関数をみると、係数の大きさにはかなりのばらつきがあるものの、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて正であり、他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて負となっており、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした体感温度仮説を符号の点で明確に支持したものになっている。
この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表5のようになっているが、誤判別は310人、誤判別率は38.0%となっていて、システム温、体温を等ウェイトにして、体感温度0以下を「ぬるま湯」、正ならば「非ぬるま湯」と判別して求めたときの誤判別314人、誤判別率38.5%と比べてもほとんど改善されないことがわかる。このことから、等ウェイトで求めた体感温度による判別が、判別分析によって求めたウェイトによる判別の結果と比較しても遜色のないものであることが明らかになった。
表3.5 判別結果の比較(1990年本調査)
| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 284 (61.5) | 178 (38.5) | 462 | 394 (85.3) | 68 (14.7) | 462 |
| 2. No 「非ぬるま湯」 | 132 (37.3) | 222 (62.7) | 354 | 246 (69.5) | 108(30.5) | 354 |
| 計 | 416 | 400 | 816 | 640 | 176 | 816 |
| 誤判別数=310 誤判別率=38.0% | 誤判別数=314 誤判別率=38.5% | |||||
以上のことから、このようにして選ばれたシステム温、体温に対応する各5問については、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題がなく、かなりよく符合するものであることが確認された。
既に述べたように、システム温、体温に対応する各5問は、1990年本調査において、多変量解析によるデータの分析結果を検討しながら選んだものである。そこで、さらに確認のため、1991年調査のデータを用いて、主成分分析、判別分析の結果を検討・吟味してみることにしよう。
まず、システム温・体温の主成分分析を1990年本調査と同様に行ってみよう。システム温を算出する基となった質問項目S1、S6〜S9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.961, 0.912, 0.868, 0.642, 0.617 となり、第1主成分だけが1を超え、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分SPRIN1は
SPRIN1=0.375S1+0.454S6+0.522S7+0.470S8+0.399S9
となり、重み係数はほぼ一定しているといっていいだろう。
同様に、体温を算出する基となった質問項目B1、B6〜B9について主成分分析を行ってみると、各主成分に対応する固有値は、1.636, 0.966, 0.926, 0.764, 0.708 となり、第1主成分だけが1を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけをみることにする。第1主成分に対応する固有ベクトルから、各質問項目に対する重み係数を求めると、第1主成分BPRIN1は
BPRIN1=0.520B1+0.471B6+0.523B7+0.401B8+0.270B9>BR>
となり、やはりB1、B6、B7と比べて、B8、B9の重み係数が小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。
次に、1990年本調査と同様に、同じ質問「職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。」を使って、「ぬるま湯」群と「非ぬるま湯」群に分け、両群の判別分析を行ってみた。その結果得られた線形判別関数は次のようになった。
u =−0.602+0.333S1+0.098S6+0.968S7+0.389S8+0.779S9
−0.424B1−0.332B6−0.196B7−0.090B8+0.204B9
この線形判別関数を基にしてuを計算し、u <0のとき「ぬるま湯」、u >0のとき「非ぬるま湯」と判別するとよいことになる。線形判別関数をみると、係数の大きさにはかなりのばらつきがあるものの、システム温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はすべて正であり、他方、体温を計算するのに用いた各質問項目に対応している係数の符号はB9を除いてすべて負となっており、「体感温度=システム温−体温」でぬるま湯感をとらえようとした体感温度仮説を符号の点で明確に支持したものになっている。
この線形判別関数を用いたときの判別の結果は表3.6のようになっているが、誤判別は308人、誤判別率は35.1%となっている。システム温、体温を等ウェイトにして、1990年本調査のときと同じ基準を用いて、体感温度0以下を「ぬるま湯」、正ならば「非ぬるま湯」と判別して求めたときの誤判別273人、誤判別率31.1%と比べても改善されないことがわかる。このことから、等ウェイトで求めた体感温度による判別が、判別分析によって求めたウェイトによる判別の結果と比較しても遜色のないものであることが明らかになった。
表3.6 判別結果の比較(1991年調査)
| 質問Q1 | 判別分析による判別結果 | 体感温度による判別結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yes | 2. No | 計 | 1. Yes | 2. No | 計 | |
| 1. Yes 「ぬるま湯」 | 378 (62.6) | 226 (37.4) | 604 | 508 (84.1) | 96 (15.9) | 604 |
| 2. No 「非ぬるま湯」 | 82 (30.0) | 191 (70.0) | 273 | 177 (64.8) | 96 (35.2) | 273 |
| 計 | 460 | 417 | 877 | 685 | 192 | 877 |
| 誤判別数=308 誤判別率=35.1% | 誤判別数=273 誤判別率=31.1% | |||||
以上のことから、1990年本調査と同様に、多変量解析の結果、体感温度の算出式を等ウェイトに設定していても、実用上は問題がなく、かなりよく符合するものであることが確認された。
第1章では、1987年調査のデータから、職務満足感とぬるま湯感の共存が指摘されている。実は、1990年本調査でもまったく同様に、職務満足感とぬるま湯感の共存を確認することができる。そのことをまず見てみよう。1990年本調査では、ぬるま湯感については第1章の質問Q1と同じ質問、職務満足感については第1章の質問Q2をよりストレートな表現に変えて、それぞれ次のようなYes-No形式の質問を用意した:
Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま湯」だと感じることがある。質問Q1のぬるま湯感については、56.9%(483人)の人がYes、43.1%(366人)の人がNoと答えている。これは1987年調査とほとんど同じ構成比率である。これに対して、質問Q2'の職務満足感については、46.9%(399人)の人がYes、53.1%(451人)の人がNoと答えている。この二つの質問への回答について、その関連を調べてみると、クロス表は表4.1のようになった。この表の行方向(横方向)の百分率は、1987年調査のときのクロス表(第1章の表1.1)とほとんど同じ比率を示している。つまり、ぬるま湯感と職務満足感との間には負の相関関係があるものの、やはり職務満足感を感じている人の半数(1987年調査で49.9%、1990年本調査でも50.1%)がぬるま湯感を同時に感じているのである。
表4.1 ぬるま湯感と職務満足感(1990年本調査)
| Q2'. 現在の職務に 満足感を感じる。 | Q1. 職場の雰囲気を「ぬるま 湯」だと感じることがある。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 200 (50.1) | 199 (49.9) | 399 (100.0) |
| No | 281 (62.7) | 167 (37.3) | 448 (100.0) |
| 計 | 481 | 366 | 847 |
このように1987年調査と同様に、1990年本調査でも、ぬるま湯感と職務満足感との間には、かなりの重なりが存在していたことから、職務満足感とぬるま湯感の共存はごく普通に見られる現象と考えてよさそうである。この章では、なぜ、職務満足感とぬるま湯感が共存しうるのかを考えるために、そもそも職務満足はどこから来るのか、そして、それはシステム温、体温といった変化性向とどのような関係にあるのかを、これまでの主要な事実発見と学説を取り込み、第3章で取り上げられた1990年本調査と1991年調査のデータを使って検証を行いながら、解きほぐしていくことにする。これらの2回の調査は、体感温度測定のための質問項目の改善とともに、この章でこれから展開される諸仮説の検証も目的として行なわれたものである。
まずそれでは、職務満足は、一体どこから来るのかについて考えてみよう。そのヒントがHerzbergの動機づけ衛生理論(motivation-hygiene theory)として知られるものにある。Herzbergらは、米国ピッツバーグ(Pittsburgh)市の企業9社の技術者と会計担当者、約200人を対象にした横断的調査を行い、その面接調査の結果得られた事実発見に基づいて、この理論を提唱している。この面接調査では、彼らの職務について、例外的に良い感じをもった時、あるいは例外的に悪い感じをもった時を思い出してもらい、その時にどんな事象が起こったのかを詳細に話してもらうという方法がとられた(Herzberg et al., 1959, ch.3, pp.141-142)。その結果、次のような事実発見が得られたという(Herzberg et al., 1959, p.80)。
したがってHerzberg et al.(1959, pp.113-114)は、これらの2組の要因は二つの分離したテーマを有していると考えた。つまり、職務満足をもたらす1の満足要因(satisfier)は自分の行っている職務そのものと関係していると考えられるが、職務不満足をもたらす2の不満足要因(dissatisfier)は自分の職務ではなく、それを遂行する際の環境、条件と関係しているというのである。そして、1の満足要因は動機づけ要因(motivators)と呼ばれ、2の不満足要因は、もっぱら職務不満足を予防するための環境的要因なので、衛生要因 (factors of hygiene)と呼ばれることになる。これが動機づけ衛生理論の概要である。
この動機づけ衛生理論に対して、その後、Herzberg自身のものも含め、多くの追跡研究 (follow-up studies)が行われ、Herzberg (1966, chs.7-8)で多数紹介されている。そのうち、復元調査だけでも9研究が取り上げられており、もともとの調査も入れて、17母集団に対する10研究で、重複しているものも入れて100以上の要因が調べられ、そのうち、動機づけ衛生理論の予想と違う結果になったのはわずか3%にも満たないことが紹介されている (Herzberg, 1966, p.125 邦訳p.141)。以上のことから、Herzbergの動機づけ衛生理論はかなり真憑性が高いと考えるべきであろう。
動機づけ衛生理論の真憑性が高いとすると、給与や作業条件という従来動機づけの中心に考えられていたものが、実は衛生要因にすぎなかったということになる。それに代わって見いだされた動機づけ要因が、自分の行っている職務そのものとの関係を表しているということは、一体何を意味しているのだろうか。Herzberg et al.(1959, p.114)は、動機づけ要因は、仕事において自らの先天的潜在能力に応じて、現実の制限の内で、創造的でユニークな個人として自分の資質を十分に発揮したいという自己実現(self-actualization)の個人的欲求を満たすからこそ満足要因になるのだと主張している。こうしたことを明らかにしてくれるのが、内発的動機づけの理論である。これには変化性向の概念が密接な関係をもってくる。
内発的に動機づけられた活動とは、当該の活動以外には明白な報酬がまったくないような活動のことである。見た目には、つまり外的には何も報酬がないのに、その人がその活動それ自体から喜びを引き出しているようなとき、そう呼ばれる。その活動が外的報酬に導いてくれるからその活動に従事するのではない。外的報酬という目的のための手段になっているからではなく、その活動それ自体が目的となって、その活動に従事しているような活動を内発的に動機づけられた活動というのである(Deci, 1975, p.23 邦訳p.25)。
動機づけというと、給与等の外的報酬にのみ目が行きがちであるが、実は内発的動機づけと外的報酬による動機づけとは付加的関係にはないということが、多数の実験研究から実証されている(Deci, 1975, ch.5.)。これらの実験では、内発的動機づけの測度として、
Deci (1975, p.61 邦訳p.68)はこの内発的動機づけ(intrinsic motivation)を考察し、「内発的に動機づけられた行動は、人がそれに従事することにより、自己を有能(competent)で自己決定的(self-determining)であると感知することのできるような行動」であると定義した。後に第5章でも触れるが、Atkinson (1957)の考えた達成動機づけも、環境との関係において自らが有能で自己決定的であることを感じたいという基本的な動機づけから分化したものであり、内発的動機づけの一つの特殊ケースとなる(Deci, 1975, p.107 邦訳p.120)。このように、有能さと自己決定の感覚への欲求は、自己とその環境との相互作用の結果として、特定のいくつかの欲求へと分化していくことになる(Deci, 1975, p.62 邦訳p.70)。言い換えれば、最初に有能さと自己決定の感覚への欲求が存在するのである。 このことはMaslowの考えた自己実現の位置づけとは全く異なる。Maslow(1943)は人間の欲求を
ところが、有能さと自己決定に対する内発的欲求は、出生時から既に存在しているのであり(Deci, 1975, pp.82-84 邦訳pp.92-94)、Maslowによる自己実現の欲求の位置づけとはその位置づけが根本的に異なっている。このことには十分な注意が必要である。もっとも、Maslowの欲求段階説に対しては、これまで数多くのさまざまな検証が試みられているものの、その試みはことごとく失敗していると言われる(Wahba & Bridwell, 1976)。Maslow自身もその主張を実質的にトーンダウンさせているので(Maslow, 1970, ch.4)、Maslowの考えた自己実現の位置づけにこだわる必要はないといえる。
このように有能さと自己決定の感覚への欲求は出生時から既に存在し、後にいくつかの欲求へと分化していくことにもなる根源的な欲求である。このうち有能さ(competence)の概念はWhite(1959)によるもので、日常的用法よりも広義に、生物学的意味で有機体がその環境と効果的に相互に作用する能力を指している。Whiteは広範な文献サーベイを行い、見る、つかむ、はう、歩く、考える、目新しいものや場所を探求する、環境に効果的な変化を生み出すといった行動は、それによって、動物や子供がその環境との間に効果的に相互に作用することを学習するプロセスを構成するという共通の生物学的意味をもっていると考えた。この共通の性質を指すために、有能さという用語が選ばれたのである。
つまり、自己の環境を処理し、効果的な「変化」を生み出すことができたとき、有能さを感じるのであり、DeciはWhiteの定義したこの有能さという用語を選ぶことで、変化性向の概念を考察していたことになる。人は自己の環境を自分で処理し、効果的な「変化」を生み出すことができるときに、有能であると感じるのであり、それはまさに自己決定的であると感じていることにほかならない(Deci, 1975, p.61 邦訳p.68)。そして、そうした有能さと自己決定(self-determination)の感覚に対する一般的欲求(Deci, 1975, p.62 邦訳p.70)こそが、個人の「変化性向」すなわち体温なのである。もちろん本書では、個人の変化性向の大きさを測定しようとする試みからスタートしていることからもわかる通り、変化性向には個人差があることを前提としているが、この変化性向がある程度の大きさでは存在しているために、人は、
命題D1 (Deci, 1975, Proposition II を修正). もし、ある人の有能さと自己決定の感覚が高くなれば、彼の満足感は増加する。逆に、もし、有能さと自己決定の感覚が低くなれば、彼の満足感は減少する。
つまり、人には有能で自己決定的である感覚に対する一般的な欲求である変化性向があるために、内発的に動機づけられた行動をとり、その結果、有能さと自己決定の感覚が高められれば、満足感を得ることになるのである。したがって命題D1は、既に述べたようなHerzbergの事実発見、すなわち、達成、達成に対する承認、仕事そのもの、責任、昇進が満足要因であるということに基本的に合致している。つまり、Herzbergの職務満足における動機づけ要因とは、有能さと自己決定の感覚に関するものだったのである。
それに対して、Herzbergの衛生要因の示唆するところは、職務を行っている環境が、個人の変化性向(すなわち体温)の発現である自己決定を阻害し(すなわち低システム温)、自己決定が低レベルに抑えられてしまうならば、職務不満足をもたらすということである。そのような状況下では、もし仮にシステム温が高く、自己決定を促進していたならば、自己決定度は向上し、その結果として職務満足がもたらされたかもしれない。Deciは内発的動機づけに及ぼすこうした外的報酬の効果に関して、「認知的評価理論」(cognitive evaluation theory)を提唱した。この理論は前述の命題D1と次の命題に要約される。
命題D2 (Deci, 1975, Propositions I and III を修正). あらゆる外的報酬は二つの側面をもっている。すなわち、(1)それを提供することで、受け手の行動を統制し、特定の活動に従事させ続けることをねらいとしている統制的(controlling)側面と、(2)報酬の受け手に彼もしくは彼女が自己決定的で有能であることを伝える情報的(informational)側面である。(a)もし受け手にとって統制的側面がより顕現的であれば、自己決定の感覚が弱まり、外的報酬を獲得するために活動に従事していると知覚し始める。(b)もし情報的側面がより顕現的であれば、自己決定と有能さの感覚が強まる。
この命題D2は、外的報酬がまさに「外的」存在であるということを指摘している点が重要なのである。既に命題D1で述べたように、有能さと自己決定の感覚は、常に内発的動機づけに結び付き、満足感を高める。内発的に動機づけられた活動とは、その活動が金銭や賞賛や食物などの外的報酬(external rewards)に導いてくれるという手段として有用だという理由からではなく、活動それ自体が目的なのであり(Deci, 1975, p.23 邦訳p.25)、彼が報酬に浴していると見いだすようなある種の内的状態(internal states)をその活動自体がもたらすから、その活動に従事しているのである(Deci, 1975, p.24 邦訳p.26)。このように、内的な情緒的状態が報酬となっているケースでは、報酬を満足と分けることができない。両者はむしろ同義と考えるべきである。なぜなら、内的報酬では、ある目標の達成が報酬となっているというよりは、目標の達成によってもたらされる内的状態すなわち満足それ自体が報酬だからである(Deci, 1975, pp.117-118 邦訳p.133)。
それに対して、金銭や賞賛のような外的報酬のケースでは、たとえ満足をもたらすとしても、満足は報酬の後にくることになる。命題D2の(a)は、そのように満足を後に押しやってしまうために、外的報酬が内発的動機づけを制約する大きな顕現性(salience)とインパクトをもっているということを主張している。したがって、この認知的評価理論によれば、業績を条件として与えられる報酬(contingent rewards)は、確かに個人を外的に動機づけるために有効ではあるが、しかしその一方で、その統制的側面が機能すればするほど、人間は内的な情緒的状態を報酬とは考えず、外的報酬の獲得のために働くようになる。つまり、内発的動機づけは低下することになる。外的報酬が内発的動機づけに対してプラスに機能するかどうかは、外的報酬の種類からではなく、それがメンバーの変化性向を受け止め、あるいは促す程度を表すシステム温的観点から評価するしかないといえそうである。
以上のことをまとめると、変化性向の定義から考えて、個人の変化性向である体温が高いほど、結果として生じる個人の自己決定の度合は高くなるはずである。そして、仮に同じ体温レベルだとしても、個人の組織内環境であるシステムがメンバーの変化性向を受け止め、あるいは促す程度を表す変化性向、つまりシステム温が高いほど、個人の自己決定の度合は高くなり、自己決定の感覚も高くなるはずだと考えられる。ただし、Herzbergの動機づけ衛生理論が示唆する通り、システム温は衛生要因的な役割を果たすにすぎず、それ自体が直接、自己決定の感覚をもたらすわけではないことには注意がいる。そこで、ここでは、変化性向との関係から、個人の変化性向の結果として生じる自己決定の感覚に的を絞って、自己決定度を連結点にして、変化性向と職務満足を結び付ける自己決定度仮説を、命題D1から立てることにする。
仮説5 (自己決定度仮説). (a)個人の変化性向である体温が高いほど、そして組織のシステムとしての変化性向であるシステム温が高いほど、組織の中での個人の自己決定の感覚は高くなる。(b)この自己決定の感覚が高いほど、職務満足感は高くなる。仮説5の検証を行うためには、自己決定の感覚がなんらかの形で測定されなければならない。第3章で改良版のシステム温、体温を定義したときと同様に、1990年本調査で得られたデータを基にして、論理的にこれらを表す質問項目と考えられるものの中から、さらに章末の付録でも取り上げられているような主成分分析の結果を検討しながら絞り込みを行って、次の5問が選ばれた。
D1. トップの経営方針と自分の仕事との関係を考えながら仕事をしている。これらの質問に、Yesならば1点、Noならば0点を与えて、ダミー変数化した5問を単純に加えた合計点を自己決定度(DINDEX )として定義することにしよう。自己決定度は、システム温、体温と同様に0〜5の値をとることができる。この自己決定度を使って、1990年本調査、1991年調査によって得られたデータを基にして、仮説5の検証を行なってみよう。自己決定度は、1990年本調査では平均2.72、標準偏差1.66 (N =831)となった。1991年調査では平均3.22、標準偏差1.46 (N =889)となり、1990年本調査と比べて平均が0.5高くなっている。体温、システム温、自己決定度の3変数間の相関係数は表4.2のようになっている。
表4.2 主要変数間の相関係数行列
(A)1990年本調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温 (SINDEX ) | 自己決定度 (DINDEX ) | |
|---|---|---|---|
| 体温 (BINDEX ) | 1.000*** (831) | 0.230*** (818) | 0.535*** (820) |
| システム温 (SINDEX ) | 0.230*** (818) | 1.000*** (830) | 0.321*** (817) |
| 自己決定度 (DINDEX ) | 0.535*** (820) | 0.321*** (817) | 1.000*** (831) |
(B)1991年調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温 (SINDEX ) | 自己決定度 (DINDEX ) | |
|---|---|---|---|
| 体温 (BINDEX ) | 1.000*** (893) | 0.152*** (877) | 0.486*** (879) |
| システム温 (SINDEX ) | 0.152*** (877) | 1.000*** (888) | 0.311*** (875) |
| 自己決定度 (DINDEX ) | 0.486*** (879) | 0.311*** (875) | 1.000*** (889) |
それではさっそく仮説5(a)の検証を行ってみよう。体温が高いほど、そしてシステム温が高いほど、自己決定度が高くなるかどうかを調べるために、自己決定度(DINDEX )を被説明変数とし、既に第3章で定義している改良版の体温(BINDEX )、システム温(SINDEX )を説明変数として回帰分析を行ってみた。その結果は、
1990年本調査 DINDEX = 0.558 + 0.535 BINDEX+0.248 SINDEX
(4.633***)(16.368***) (7.125***)
R2=0.3272 (F=195.810***)
1991年調査 DINDEX = 1.125 + 0.499 BINDEX+0.231 SINDEX
(9.434***)(15.506***) (8.350***)
R2=0.2922 (F=178.379***)
となった。自己決定度の平均が1991年調査の方が0.5高いことを反映して、定数項にはその分の違いが認められるが、回帰係数の値は安定している。回帰係数の下の( )内はt 値を表しているが、このDINDEX のBINDEX、SINDEX への回帰式から、体温、システム温の回帰係数はともに有意で、しかも正なので、体温が高いほど、そして、システム温が高いほど、自己決定度は高くなるという仮説5(a)の関係が確かめられた。
さらに、第3章でもやったように、1990年本調査のデータを使い、システム温、体温の平均2.13、3.08を境にして、それぞれ「低システム温」(システム温0〜2)、「高システム温」(システム温3〜5)、そして「低体温」(体温0〜3)、「高体温」(体温4〜5)というように二分してカテゴリーを作り、組み合わせてできる四つのセルのそれぞれについて、自己決定度の平均を求めてみると、表4.3(A)のようになった。つまり、湯かげん図の各領域ごとに、自己決定度の平均を求めたのである。この表からわかるように、高体温・高システム温の領域では、自己決定度の平均は3.96とほとんど4にもなるが(自己決定度は最高5までしかとれない)、低体温・低システム温の領域では自己決定度の平均は1.92と、その半分にも達しない。また、分散分析を行ってみると、低体温より高体温、低システム温より高システム温の方が自己決定度が有意に高いこともわかる。また1991年調査のデータを使って、追試として同じ分析を行ったが、表4.3(B)のように同様な結果が得られている。以上のことから仮説5(a)は検証された。なお、分散分析は、繰り返し数が不揃いなので、要因に階層構造を考えて、部分モデルに基づく平方和を求めたType Ⅱの平方和を用いている。
表4.3 自己決定度
(A)1990年本調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 3.27 (191) | 3.96 (165) | 3.59 (356) |
| 低 (0〜3) | 1.92 (304) | 2.33 (148) | 2.06 (452) |
| 全体 | 2.44 (495) | 3.19 (313) | 2.73 (808) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 200.80*** |
| システム温 | 26.92*** |
| 体温×システム温 | 1.85 |
(B)1991年調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 3.51 (206) | 4.06 (141) | 3.73(347) |
| 低 (0〜3) | 2.46 (280) | 3.16 (173) | 2.73(453) |
| 全体 | 2.91 (486) | 3.56 (314) | 3.16(800) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 109.88*** |
| システム温 | 42.66*** |
| 体温×システム温 | 0.62 |
次に、仮説5(b)の検証を行ってみよう。これはまず、職務満足に関する前述の質問Q2'を用いて、Yesつまり現在の職務に満足を感じていると回答した者の比率を「満足比率」と定義し、これが、自己決定度が高くなるにつれて、どのように変化していくのかを調べてみればよい。表4.4は職務満足と自己決定度のクロス集計表であるが、この表から明らかなように、1990年本調査、1991年調査ともに、仮説5(b)の通り、自己決定度が高くなるにしたがって、満足比率は増加していく。この様子は、図4.1にあるようにグラフ化してみるとよりはっきりする。試みに、最小2乗法でそれぞれ6個の点にあてはまりのよい直線を求めてみると、図4.1の注にあるような回帰直線となる。決定係数R2は1990年本調査で0.9830、1991年調査で0.9407となり、かなりあてはまりがよいと考えてよいだろう。この直線によると、1990年本調査、1991年調査ともに、自己決定度3で満足比率はほぼ50%となり、職務満足を感じるかどうかほぼ半々になる。そして、自己決定度が1上がるごとに、満足比率はほぼ10%上昇するのである。このことで、仮説5(b)は検証された。また自己決定度が測定できれば、ある自己決定度の人が、どの程度の確率で職務満足感を感じるかを予測することもできる。
表4.4 自己決定度と満足比率
(A)1990年本調査
| Q2'. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 自己決定度(DINDEX ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| 1. Yes | 20 | 42 | 50 | 71 | 94 | 113 | 390 |
| 2. No | 78 | 90 | 93 | 70 | 63 | 44 | 438 |
| 計 | 98 | 132 | 143 | 141 | 157 | 157 | 828 |
| 満足比率(%) | 20.4 | 31.8 | 35.0 | 50.4 | 59.9 | 72.0 | 47.1 |
(B)1991年調査
| Q2'. 現在の職務に 満足感を感じる。 | 自己決定度(DINDEX ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | |
| 1. Yes | 6 | 29 | 40 | 97 | 133 | 140 | 445 |
| 2. No | 35 | 61 | 99 | 92 | 86 | 68 | 441 |
| 計 | 41 | 90 | 139 | 189 | 219 | 208 | 886 |
| 満足比率(%) | 14.6 | 32.2 | 28.8 | 51.3 | 60.7 | 67.3 | 50.2 |
図4.1 自己決定度と満足比率
(A)1990年本調査
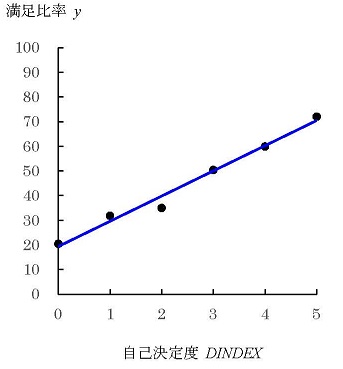
注) 直線は最小2乗法によって求めた
y = 19.37 + 10.22 DINDEX
( 9.508***)(15.191***)
R2=0.9830 (F=230.779***)
(B)1991年調査
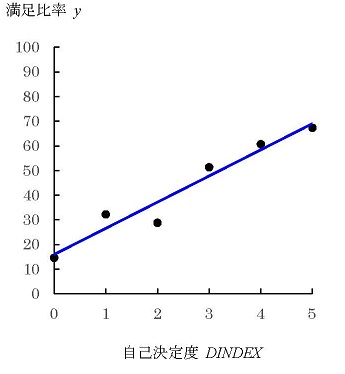
注) 直線は最小2乗法によって求めた
y = 15.95 + 10.61 DINDEX
( 3.953*) ( 7.965**)
R2=0.9407 (F=63.444**)
以上のように、仮説5は(a)(b)ともに検証されたが、(a)と(b)とを組み合わせると、体温が高いほど、そしてシステム温が高いほど、職務満足も高くなるという関係を導くことができる。そこで、先ほどの仮説5(a)の検証のときと同様にして、湯かげん図の各領域ごとに満足比率を求めてみると、表4.5のようになった。これからわかるように、1990年本調査(表4.5(A))では、高体温・高システム温の領域では、満足比率は74.0%にもなるのに、低体温・低システム温の領域では29.1%と3割にも満たない満足比率になってしまう。1991年調査(表4.5(B))でも、高体温・高システム温の領域では、満足比率は62.4%になるのに、低体温・低システム温の領域では38.9%という満足比率になってしまう。分散分析を行ってみても、低体温より高体温、低システム温より高システム温の方が、満足比率が有意に高いことがわかった。
表4.5 満足比率
(A)1990年本調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 45.3 (192) | 74.0 (169) | 58.7 (361) |
| 低 (0〜3) | 29.1 (306) | 54.0 (150) | 37.3 (456) |
| 全体 | 35.3 (498) | 64.6 (319) | 46.8 (817) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 27.96*** |
| システム温 | 61.08*** |
| 体温×システム温 | 0.30 |
(B)1991年調査
| 体温 (BINDEX ) | システム温(SINDEX ) | ||
|---|---|---|---|
| 低 (0〜2) | 高 (3〜5) | 全体 | |
| 高 (4〜5) | 45.9 (209) | 62.4 (141) | 52.6 (350) |
| 低 (0〜3) | 38.9 (283) | 55.2 (172) | 45.1 (455) |
| 全体 | 41.9 (492) | 58.5 (313) | 48.3 (805) |
| 因子 | F 値 |
|---|---|
| 体温 | 4.11* |
| システム温 | 21.18*** |
| 体温×システム温 | 0.00 |
こうしたことから、仮説5の自己決定度仮説によって、なぜ職務満足感とぬるま湯感が共存しうるのかということを説明できる。体感温度仮説によれば(第1章の図1.2(A))、高体温・低システム温は高いぬるま湯感をもたらし、逆に低体温・高システム温は低いぬるま湯感をもたらすことになる。つまり、仮にぬるま湯感の高低で二分すれば、図4.2(A)のように、左上半分の領域がぬるま湯感の高い高ぬるま湯感領域、右下半分の領域がぬるま湯感の低い低ぬるま湯感領域となる。ところが一方、自己決定度仮説によれば、高体温・高システム温は高い職務満足をもたらすのである。つまり、仮に職務満足感の高低で二分すれば、図4.2(B)のように、右上半分の領域が高職務満足感領域、左下半分の領域が低職務満足感領域となるのである。
もし、高ぬるま湯感領域と高職務満足感領域が湯かげん図で対極に位置しているのであれば、職務満足感とぬるま湯感の重なりはかなり低いレベルにとどまるはずである。ところが、実際には、図4.2(C)のように、高ぬるま湯感領域と高職務満足感領域は、湯かげん図上でかなり重なってしまう。その結果、高ぬるま湯感でかつ高職務満足感の領域ができてしまうことになる。しかも、図4.3(A)(B)でもわかるように、1990年本調査、1991年調査とも、境界線の引き方で変動はあるものの、この高ぬるま湯感でかつ高職務満足感の領域に十分な度数が存在しているのである。以上のことから、実際の企業でも職務満足感とぬるま湯感とが共存しているメンバーがかなり多いと考えられる。
図4.2 ぬるま湯感と職務満足感との湯かげん図上での領域の重なり
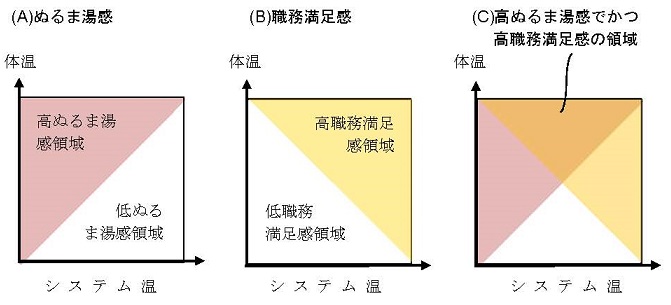
図4.3 湯かげん図上での実際の分布
(A)1990年本調査(N =818) (B)1991年調査(N =877)
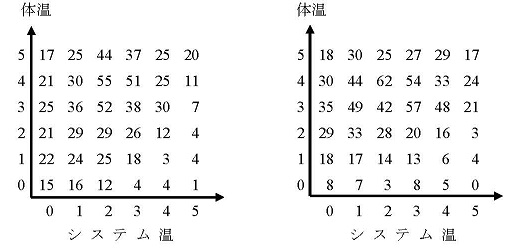
Cramer's V=0.122 (χ2=60.904***) Cramer's V=0.103 (χ2=46.172** )
以上の諸考察から、図4.4のような関係が得られる。これを「変化性向の枠組み」と呼ぶことにしよう。点線になっている関係については、次の第5章で取り扱われる。
図4.4 変化性向の枠組み
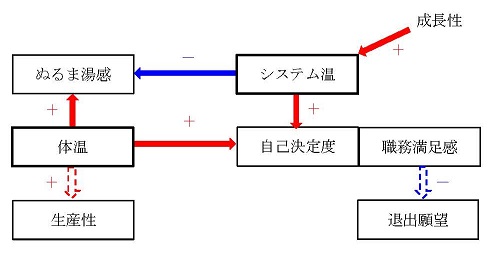
この変化性向の枠組みの中で、ぬるま湯感に対する体温、システム温の+−の影響は、体感温度仮説が正しければ論理的に明かであるが、一応直接的に検証するために、ぬるま湯と感じる(Yes)ならば1、感じない(No)ならば0をとるダミー変数(y )を被説明変数とし、体温(BINDEX )、システム温(SINDEX )を説明変数とする回帰分析を行ってみよう。1990年本調査、1991年調査のデータを用いた分析の結果はそれぞれ
1990年本調査 y = 0.658 + 0.535 BINDEX−0.098 SINDEX
(15.580***) (3.334***) (−8.029***)
R2=0.0759 (F=33.412***)
1991年調査 y = 0.803 + 0.031 BINDEX−0.095 SINDEX
(18.805***) (2.675** ) (−9.636***)
R2=0.0974 (F=47.173***)
となった。この回帰式から、体温、システム温の回帰係数はともに有意で、2回の調査で安定した値をとっていることがわかる。しかも体温については+、システム温については−であり、体温が高いほど、そして、システム温が低いほどぬるま湯と感じるという関係のあることが確かめられた。
この図4.4によって、変化性向である体温、システム温といった概念を鍵にして、ぬるま湯感と職務満足感の発生メカニズムと、両感覚の重なりのメカニズムが統一的に明らかにされる。ところで、本書で提唱している変化性向の枠組みのうち、体温対システム温という図式の部分は、Herzbergの動機づけ衛生理論における動機づけ要因対衛生要因という図式や、Deciの内発的動機づけの理論における内的報酬対外的報酬という図式と基本的に類似の構造をしているということにすぐ気が付くだろう。いずれも個人の内にある変化性向とそれに対する個人のまわりの環境の条件という2変数を問題にしている。違いは、HerzbergやDeciの主要関心が職務満足の方、すなわち変化性向の枠組みでいうと2変数の足算の方つまり右下の方向に向いていたのに対して、もともと体感温度仮説では2変数の引算の方つまり左上の方向に向いていたことにあったのである。
また図4.4ではまだ点線になっている体温と生産性、職務満足と退出願望の関係については、次の章で考察される。実は、次の章でも述べられるが、職務満足と生産性との間には一貫した明確な相関が見られないということが、これまでに行なわれてきた多くの研究データによって明らかにされている。しかしこの図4.4のような関係が明らかになれば、職務満足と生産性との間に明確な相関が見られないのは、システム温が影響を及ぼしているからだと説明することが可能になる。
ダミー変数化した五つの質問項目D1〜D5について主成分分析を行ってみよう。1990年本調査のデータを用いると、各主成分に対応する固有値は、2.258、0.919、0.682、0.644、0.498となり、第1主成分だけが2を超えていて、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなって、1にも満たなくなっている。したがって、この第1主成分だけを見ることにし、第1主成分に対応する固有ベクトルを求めてみると、第1主成分DPRIN1は
1990年本調査 DPRIN1=0.464D1+0.479D2+0.476D3+0.379D4+0.430D5
となり、D4の重み係数がやや小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。
さらに1991年調査のデータを用いて追試してみると、各主成分に対応する固有値は、1.942、1.035、0.794、0.689、0.539となり、第2主成分以下は固有値の値が急に小さくなっている。したがって、この第1主成分だけを見ることにし、第1主成分に対応する固有ベクトルを求めてみると、第1主成分DPRIN1は
1991年調査 DPRIN1=0.433D1+0.498D2+0.507D3+0.320D4+0.453D5
となり、やはりD4の重み係数がやや小さいが、各質問項目に対する重み係数はほぼ一定したものになっていると考えてよさそうだ。
この章で明らかにしたいのは、前章の図4.4の「変化性向の枠組み」のうちまだ点線で示されている次の二つの仮説である。
仮説6 (退出仮説). 職務満足が低いときに、「組織を退出したい」という願望が知覚される。この二つの仮説によって、前章の最後に半ば予告的に掲げた「変化性向の枠組み」が完結することになる。ここで重要なのは、この二つの仮説を組み合わせても、職務満足と生産性は理論的には直結しないということである。それは図4.4の変化性向の枠組みを見ても明らかであるが、両者の間の関係にはシステムの変化性向であるシステム温の存在が重要な役割を果たしていることになる。そして、そのシステム温がうまく機能しているかどうかが、実は本書のメイン・テーマであるぬるま湯感によって検知されていたのである。
かつては、この二つの仮説に別々に現れる職務満足と生産性が、直接的に関係づけて議論されることが多かった。職務満足と生産性の関係については、ワーク・モティベーション(仕事への意欲)の研究の分野でかなりの研究がなされてきている。そこでは、生産性 (productivity)あるいはより広く「職務遂行」(job performance)が重要な概念となっている。ワーク・モティベーションの分野で、職務満足(job satisfaction)との関係で用いられる職務遂行という用語は、中性的というよりポジティブに優れた職務遂行や高い生産性の意味で使用されることがある(二村, 1977)。これは、従業員の欲求の満足化による生産性増大運動ともいえる人間関係論(Vroom, 1964, p.181 邦訳p.209)以来、職務満足と職務遂行との間に有意な関係を見いだすことに多くの努力がなされてきていることに由来している。(人間関係論については5.5節で後述する。)
しかし例えば、Likert (1961, p.14 邦訳p.22)はミシガン大学の社会調査研究所 (Institute of Social Research)での各種研究を踏まえて、高生産性の部署の従業員の会社に対する満足度は低生産性の部署の従業員と違わず、職務満足は自動的に高い生産性には結び付かないが、他方で、職務満足は低い欠勤率と低い転職率には結び付いているとデータを示しながら結論づけている。実際、こうした事実は他にも多くの研究によって指摘されている。
Vroom (1964, p.186 邦訳p.215)は、Brayfield & Crockett (1955)の文献レビューもふまえた上で、職務満足と職務遂行との相関についての20の研究をレビューの上、まとめて、欠勤、離職、生産性との関係について次のように結論づけている:
1、2は「負の関係」というと回りくどいが、要するに、職務に対する不満足が離職や欠勤という組織を退出する行動と結び付くようだということである。それに対して、3は職務満足と生産性の相関関係自体に疑問があることを意味している。これはどうしてなのであろうか。
そのためには、まず最初に、組織のメンバーが行う次の2種類の意思決定について明確に区別しておく必要がある:
1は、March & Simon (1958) では参加の意思決定(decision to participate)と呼ばれていたが、5.2節で触れる組織均衡の理論でも明らかにされるように、この意思決定の内容は「これから新規に、ある組織に参加するか否か」というよりは「既に参加している組織にさらに参加し続けるか否か」というものである。したがって、ここでは誤解を招かぬように、「退出の意思決定」と呼ぶことにする。
2の生産の意思決定は、March & Simon (1958)では、「組織によって要求された率 (rate)で生産活動を行うかどうか」という表現になっているが、5.4節で後述するように、こうした表現自体が、現在では生産の意思決定を表すものとしては適切ではないと考えられるので、ここでは「効率的に」という、より大ざっぱな表現に改めている。どちらにせよ、生産の意思決定で問題にしているのは「率」であり、「参加するか、退出するか」とは、本質的には別の問題である。まぎらわしいものに、Barnardの組織の能率(efficiency)の概念があるが、これはそのシステムの均衡を維持するに足るだけの有効な誘因を提供する能力(capacity)とされているので(Barnard, 1938, p.93 邦訳p.97)、本質的に、組織均衡及び退出の意思決定に関するもので、生産の意思決定や組織の生産性とは別の概念なので注意が必要である。
いずれにせよ、March & Simon (1958, p.48 邦訳pp.74-75)が主張するように、この1と2の意思決定は、異なる行動の集合を喚起するのであり、両者の間には重要で本質的な差異がある。したがって、両者を区別して考えなければ、離職や欠勤の問題と生産性の問題を論じる際に、議論に混乱が生じることになる。両者を区別した上で、前述のVroomの結論1、2、3を解釈すれば、次のようになるだろう:退出の意思決定に由来する欠勤・離職といった行動と職務満足との間には相関があるという事実が見い出されてきたのであるが、肝心の生産の意思決定についての研究の結果は、こうした予想とは異なるものであった。
これはきわめて重大な事実発見である。実は人間関係論には、もともと「幸福な労働者は能率的かつ生産的労働者である」という仮説があるとされ、職務満足は、人間関係論等において独立変数として位置づけがなされていたわけだが、ここにきて、多くの調査研究の結果、この人間関係論的仮説に疑問が投げかけられたのである。つまり、職務満足は離職や欠勤といった退出の意思決定に関する変数との間には関係がありそうであるが、肝心の生産性に関する生産の意思決定との間の関係についてはどうも疑問があるというのである。
そこで、職務満足が職務遂行を生むというこの人間関係論的仮説に対して、米国では1950年代中頃から疑問がもたれ始め、これに代わって、逆に、職務遂行が職務満足を生むというモデルが採用されていき、1970年頃には確立されたものになっていたといわれている(二村, 1977)。その代表的なモデルは、Lawler & Porter (1967)によるもので、彼らは職務満足データの解釈のための新しい理論的モデルを考え出した。このモデルは、職務遂行と職務満足との間に、第3の変数である報酬(rewards)を入れて、関係づけることが可能であると主張するものである。つまり、(1)高い職務遂行はある場合には報酬を生み出し、さらに、(2)報酬は職務満足を引き起こす、と考えるのである。このように、その間に報酬という変数を挟んでいるので、職務満足と職務遂行との結び付きは弱まり、両者の相関が低くなることを説明できるとしている。しかし、職務遂行の種類ごとにモデルが別々に作られているわけではないので、このタイプのモデルでも、職務満足との相関が退出の意思決定と生産の意思決定との間では異なっているという事実を説明することは本質的に出来ない。
そこで、この章では、退出の意思決定と生産の意思決定を明確に区別した上で、まず退出の意思決定について次の5.2節で考察し、次に生産の意思決定については5.3節以降で考察することにしよう。
退出の意思決定、つまりMarch & Simon (1958)のいうところの組織への参加の意思決定は組織均衡(organizational equilibrium)の理論によって扱われている。組織の均衡の概念は、もともとBarnardのアイデアをもとにして(ただし、Barnardは「能率」という用語を主に用い、「均衡」という用語はあまり用いていないが)、Simon (1976)が発展させたものであり(Simon, 1976, p.111 邦訳p.159)、個人の組織からの退出の意思決定を考察する際の重要な概念である。組織均衡の理論は基本的に動機づけの理論であるが、この理論の骨格は次のように整理することができる(March & Simon, 1958, p.84 邦訳p.128):
ここで「参加者」というのはMarch & Simonの用語であって、Barnardは「貢献者」(contributors)と呼び、従業員の他に、投資家、供給業者、顧客も含めて考えていた(例えば、Barnard (1938, p.77 邦訳pp.79-80))。したがって、組織均衡の概念は、通常、われわれが組織の「構成員」(members)と呼んでいる人々だけでなく、他の種類の「参加者」にまで適用範囲を拡大していくことが可能な概念であるということには注意がいる(March & Simon, 1958, p.83 邦訳p.127)。ただし、ここでの関心は組織のメンバーに限定される。
ところで、組織均衡概念の核心部分である4については、同義反復的に解釈する必要がある。つまり、4の意味は、より正確には「各参加者が組織を去るか否かについて無差別になるとき、誘因の効用と貢献の効用とのバランスがとれていると考えよう」ということである。なぜなら、各参加者が組織を去るか否かという事象を誘因・貢献によって説明、予測しようとするためには、誘因・貢献効用スケール(inducement-contribution utility scale)を各参加者が組織を去るか否かという事象から独立かつ客観的に設定することが必要となるが、実際にはこれは困難だからである。
直感的には、このスケールを満足スケール(satisfaction scale)で代替することができると思えるかもしれない。しかし、実は、満足スケールによって誘因・貢献スケールを代替してしまうことには論理的に問題がある。一例をあげれば、満足スケールのゼロ点は、参加者が「不満足」の程度を語り始める点であるのに対して、誘因・貢献効用スケールのゼロ点は、参加者が組織を退出するか否かについて無差別になる点である。この二つのゼロ点が一致する必然性はない。むしろ一般的には同じではないだろう。「不満足」を感じている参加者みんなが組織を退出するかというとそうではない。組織を退出するのは、不満足感をもっている参加者の一部に過ぎないのである(March & Simon, 1958, pp.85-86 邦訳p.131)。
それでは、この違いをどのように説明したらよいだろうか。大まかにいえば、満足スケールは組織を移動する願望にだけ関係しているのに対して、誘因・貢献スケールは移動する願望に加えて、知覚された移動の容易さとも関係しているのである(March & Simon, 1958, p.86 邦訳p.132)。より正確にいえば、
以上の諸関係は図5.1のようにまとめられる。
図5.1 退出の意思決定の諸要因(このうち青い太字の部分が仮説6の退出仮説を表す。)
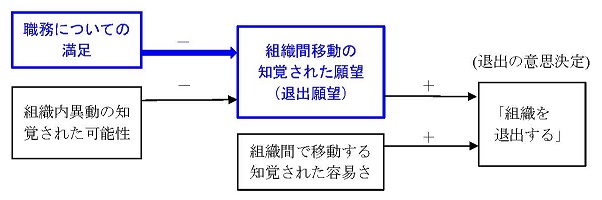
満足スケールと誘因・貢献スケールの違いについての以上の議論に注意を払えば、米国のように組織間を移動する知覚された容易さがある程度存在する社会では、1にある組織間を移動する知覚された願望が、退出の意思決定にストレートに結び付くであろう。そのために、職務満足と欠勤、離職が相関するであろうことは容易に推測できる。しかし、日本は米国に比べれば、組織間を移動する知覚された容易さは低いレベルにあると考えられている。事実、坂下(1985, pp.205-206)の日本企業を対象とした調査研究によると、職務満足と欠勤率・離職率との間には有意な相関関係は見いだせなかったとされる。
そこで、実際に図5.1のような関係を検証するためには、その一部である2の部分に相当する図5.1の青い太字部分だけを扱うことにしよう。すなわち、退出の意思決定の結果としての離職や欠勤といった実際の行動のレベルではなく、その一歩手前の組織間を移動する知覚された願望、つまり「退出願望」のレベルで、職務満足との間により直接的に次のような仮説にしておけばよい(cf. March & Simon, 1958, pp.50-51 邦訳p.78)。
仮説6 (退出仮説). 職務満足が低いときに、「組織を退出したい」という願望が知覚される。既に述べたように、米国では、欠勤、離職と職務満足との間に負の相関があることは何度もデータ的に確認され、広く認められているといっていいだろう。日本においても、欠勤、離職といった実際の意思決定や行動のレベルの事象ではなく、仮説6にあるような組織を退出したいという願望について調べるのであれば、比較的容易に確認、検証することができる。それには、次のような質問を使って調べれば良い。
Q5. チャンスがあれば転職したいと思う。つまり、「転職願望」を調べるのである。既に3.2節で調査の方法について述べている1990年本調査では、この質問について、ちょうど50.0%(423人)の人がYes、50.0%(423人)の人がNoと答えている。職務満足については、前章の質問Q2'と同じ、
Q2'. 現在の職務に満足感を感じる。を使うことにして、1990年本調査でのデータを用いて二つの質問の間でクロス表をつくってみると表5.1のようになった。このクロス表からもわかるように、職務満足と転職願望との間には負の相関関係があり、職務満足を感じている人はその6割が転職を考えていないが、逆に職務満足を感じていない人はその6割が転職を考えているのである。
表5.1 職務満足と転職願望(1990年本調査)
| Q2'.現在の職務に 満足感を感じる。 | Q5.チャンスがあれば 転職したいと思う。 | ||
|---|---|---|---|
| Yes | No | 計 | |
| Yes | 153 (38.5) | 244 (61.5) | 397 (100.0) |
| No | 268 (60.0) | 179 (40.0) | 447 (100.0) |
| 計 | 421 | 423 | 844 |
このように、組織を退出したいという願望については、職務満足との間に負の相関が見い出せ、仮説6が検証された。したがって、これまでの米国での調査研究が明らかにしてきたことを考え合わせても、退出願望については、職務満足との間に負の相関関係があると結論してよさそうである。
前の5.2節では、退出の意思決定と職務満足の関係について考察してきた。この両者の関係については、データ的にもほぼ確認されているといっていいだろう。残るは生産の意思決定である。そこでこの節では、この生産の意思決定について、まずは動機づけに関する代表的な2モデルを参考にして、(1)外的報酬による動機づけを扱うVroomに代表されるモデル(これをここではV型モデルと呼ぼう)、(2)内発的動機づけを扱うAtkinsonに代表されるモデル(これをここではA型モデルと呼ぼう)、を定式化して比較検討しながら考察してみることにしよう。
VroomやAtkinsonのモデルは認知的モデル(cognitive model)とも呼ばれ、人間が複数の代替的行為コースの中から行う選択が、行動と同時に生起する心理学的事象と法則的に関連していると仮定している。選択はそうした諸力の相対的強度に依存するものと考えるのである。この考え方は、基本的に決定理論(decision theory)の考え方と類似したものである。そこでまず、Vroom (1964, pp.14-18 邦訳pp.15-20)も参考にしながら、ここで扱う認知的モデルを構成する共通で主要な3概念を決定理論と関係づけて、まとめておこう。
ある人が得る特定の結果(outcome) x は、彼が選択する行為(action) a に依存するだけではなく、彼には制御できない事象である自然の状態(state of nature) u にも依存している。したがって、決定理論では、結果は x =(u, a) のように自然の状態と行為の組で表現される。ある自然の状態が生起するだろうという確信の度合は、決定理論では主観確率(subjective probability)と呼ばれるが、心理学者は主観確率という用語だけではなく、例えば、VroomやAtkinsonは期待(expectancy)といった用語を用いて主観確率を表している。主観確率は当然のことながら0から1までの値をとる。また、自然の状態 u に主観確率 p (u) が付与されれば、ある行為 a を選択した際に起こりうる結果 x =(u, a) についても主観確率を付与することができる。
人はいくつかの結果の間で、選好(preference)をもっていることが仮定されている。すなわち、結果の間には、一方が他方よりも選好されるというような選好関係が存在していると仮定される。決定理論ではこうした選好を表現するのに、数量化された効用(utility)の概念ややはり数量化された負の効用である損失(loss)の概念を用いているが、心理学者は効用といった用語だけではなく、多くの異なった用語を用いてきた。例えば、Vroomの誘意性(valence)やAtkinsonの誘因価(incentive value)といった用語も、すべて効用のような結果への情動志向(affective orientation)を指しているとされる。効用は正から負までの広範囲の値をとりうると仮定される。
選択を行う際に、効用と主観確率がどのように結びつくのかを特定化するために、決定理論では効用の期待値として(主観的)期待効用を考える。そして、最大の期待効用をもたらす行為を選択すると考えるのである。しかし、こうした行為を選択せしめるような仮説的な力(force)を効用と主観確率を用いて数学的に記述するには多くの可能な方法がある。例えば、Vroomは、実質的には期待効用の場合と同じ選択をもたらすことにはなるものの、期待効用の単調増加関数を考えていたし、Atkinsonは期待効用と類似のいわば「満足」の期待値を考えていた。
以上のような3概念の共通性を念頭に置いた上で、V型モデルとA型モデルの比較を行なってみよう。
Vroom (1964)のモデルは期待理論(expectancy theory)とも呼ばれ、ある特定の行為を行わせようとする動機づけに関心を向けた。ここでは、Vroomにしたがって、外的報酬による動機づけを期待理論のモデルで定式化してみよう。そこでまず、第1次と第2次の2種類の結果(outcome)を考えてみる。V1j を第1次の結果 j の誘意性(valence)、j =1, ..., m、とし、V2k を第2次の結果 k の誘意性、k =1, ..., n、とする。ここで、ある行為によって引き起こされる第1次の結果の複合体とは、いわゆる行為の目標に相当している。一方、第2次の結果は外的報酬に相当したものであると考えられる(Deci, 1975, p.119 邦訳p.134)。この第1次、第2次の結果の誘意性の間には次のような関係があるとされる。
命題V1 (Vroom, 1964, Proposition 1を修正). ある人にとって、ある第1次の結果の誘意性は、すべての第2次の結果の誘意性とその第2次の結果の獲得に対する第1次の結果の手段性についての彼または彼女の認識の積の代数和の単調増加関数で表され、
V1j =gj (Σk =1n Ijk V2k), j=1, ..., m
ただし、gj' >0 。Ijk は第2次の結果 k の獲得に対する第1次の結果 j の手段性(instrumentality)で、−1≦ Ijk ≦1 とする。
実は、Vroom(1964)自身は第1次の結果と第2次の結果の誘意性を区別していないが、両者を区別しておかないと、誘意性の間にはこの命題Ⅴ1の関係式が与えられているために、誘意性は、その連立方程式を代数的に解くことによって求められるべきものであるということになりかねない。こうした混乱を回避するために、ここでは第1次の結果と第2次の結果とを区別しておく。Vroom理論の解説や解釈も実質的におおむねこの区別を行っている。
こうして命題V1によって得られる第1次の結果の誘意性(すなわち行為の目標が達成されたときにもたらされるであろう効用)と、これらの結果が生起するだろうという確信の度合、つまり、Vroomが期待と呼んだ主観確率をもとにして、個人がある行為を遂行するように作用する力が定式化される。
命題V2 (Vroom, 1964, Proposition 2を修正). ある人に行為 i (i=1, ..., l )を遂行するように作用する力(force) Fi は、すべての第1次の結果の誘意性と、その行為がこういったすべての結果の獲得をもたらすとの主観確率の積の代数和の単調増加関数で表され、
Fi =fi (Σj=1m pi ( j) V1j), i =1, ..., l
ただし、fi' >0。pi ( j)は行為 i が第1次の結果 j をもたらすとの主観確率で、0≦pi ( j)≦1とする。
ここで fi は単調増加関数であるから、結局、期待効用
Σj=1m pi ( j) V1j
が大きくなるほど、「ある行為を遂行するように作用する力」もまた大きくなるわけである。つまり、最大期待効用をもたらす行為iを遂行するように、最大の力 Fi が作用する。したがって、結果的に最大期待効用をもたらす行為 i が選択されることになる。
次に、Atkinson (1957)の達成動機づけのモデルにしたがって、動機づけを定式化してみよう。まず、Isj を目標 j の成功の誘因価(incentive value of success)とし、Ifj を目標 j の失敗の誘因価(incentive value of failure)とする。ここで、成功の誘因価とは人が目標 j を達成した際に感じるプライドで、その目標が達成困難なほど高い誘因価をもつ。他方、失敗の誘因価とは失敗に伴う恥や困惑といった不快の情緒であり、負の値をとるが、その目標の達成が容易であったほど、失敗したときのダメージはひどく、失敗の誘因価の絶対値は大きくなる。
また、Ms を成功への動機(motive to approach success)とし、Mf を失敗回避動機(motive to avoid failure)とする。両方とも比較的安定したパーソナリティー的特性で、その値は各個人については状況にかかわらず定数であると考えられる。
以上のことから、目標 j の達成状況に接近したり回避したりする合成的モティベーション (resultant motivation) Rj は
Rj =p( j)Ms Isj +(1−p( j)) Mf Ifj (1)
と表される。ただし、ここで、p( j) は目標 j の成功の主観確率であり、目標 j の成功の容易性を表している。他方、1−p( j) は目標 j の成功の困難性と考えられる。
Atkinsonは誘因価のもっている意味から、誘因価 Isj や Ifj がこの目標 j の成功の困難性、容易性の線型な関数になると仮定した。そして、その線型な関数という関係をさらに単純化して、誘因価と目標 j の成功の確率 p( j) との間に次のような関係を仮定している。
Isj =1−p( j) Ifj =−p( j)
この関係を用いれば、合成的モティベーションを表す(1)式は
Rj =(Ms−Mf ) p( j) (1−p( j)) (2)
となり、成功への動機と失敗回避動機という二つのパーソナリティー的特性を表す定数と目標 j の成功の確率によって、合成的モティベーションが決まることになる。
この(2)式の中の個人ごとに定まる定数である Ms−Mf は、チャレンジの際の成功への動機から失敗回避動機を引いたものであり、まさに個人の変化性向、つまり体温を表していると考えることができる。したがって、このA型モデルで記述されるような動機づけにおいては、モティベーションの大きさの決定に、パーソナリティー的特性としての個人の変化性向の大きさが重要な役割を果たしているのである。
またA型のモデルでは、誘因価と成功の確率の間に特定の関係を仮定したことで、「目標達成」ということのもたらす満足は、目標達成それ自体にのみ関係し、目標達成以外には明白な報酬がまったくないことになる。このことは、V型のモデルと比べて際だった特徴になっている。4.2節でも述べたように、内発的に動機づけられた活動とは、当該活動の他には明白な報酬がまったくないような活動のことであるから、このA型モデルではまさに内発的動機づけだけが問題になっていることになる。
外的報酬による動機づけを考えたV型のモデルでは、もし同じ外的報酬 k をもたらすパスに、容易なパスと困難なパスの二つのパスがあるときには、人は容易なパス、すなわち、確率 pi ( j) と手段性 Ijk の大きいパスを選ぶことになるだろう。なぜなら、外的報酬の期待値が高くなるからである。しかし、内発的な動機づけを考えたA型のモデルでは、より困難なパスを選ぶかもしれない。なぜなら、合成的モティベーションを表す(2)式の Rj の式からも明らかなように、個人の変化性向である体温が正、つまり、Ms−Mf >0 ならば、p( j)=1/2 のときに最大の内的報酬が得られるからである。したがって、外的報酬による動機づけは、目標成功の困難性が低いほど大きくなるが、他方、内発的動機づけは、目標の困難性が一定の最適水準に高まるまで増大するのである(Deci, 1975, p.117 邦訳p.132)。
つまり、A型のモデルでは、個人がより困難なことにチャレンジするように動機づけられるのに対して、V型のモデルではできるだけ容易な道へと向かってしまう。どうもV型のモデルで効率的に生産活動を行なうような動機づけを考えるのは難しそうである。実際、V型のモデルでは、職務誘意性は作業者が外的報酬を獲得できる程度の仕事をする確率とは関係するかもしれないが、たいていの場合、作業者の潜在的可能性をはるかに下回る業績レベルで十分に外的報酬を獲得できるので、その場合、とても効率的に生産活動を行っているとはいいがたい。
実は、既に、Vroom自身が広範な調査研究のサーベイの結果、生産の意思決定にとって本質的に重要なのは、内発的動機づけであると、次のように発見をまとめていた(Vroom, 1964, ch.8):
そして、これらの発見は、職務遂行が目的達成の手段であるばかりでなく、目的そのものでもあることを示しており、個人は職務遂行に対する外的に媒介された結果とは無関係に、効率的遂行からは満足を引き出し、非効率的遂行からは不満足を引き出すことを示唆しているとした(Vroom, 1964, pp.266-267 邦訳pp.304-305)。つまり、生産の意思決定、及び生産性は、内発的動機づけと関係が深そうだというのである。
このうち2、3は、自己決定度の高い方が遂行レベルも高いということを示している。ところが、Deciの命題D1によっても、そしてわれわれの自己決定度仮説(第4章仮説5)によっても、高い自己決定度は高い職務満足をもたらすことから、もし仮に2、3が正しければ、自己決定度を先行変数としての職務満足と生産性との間の疑似相関がなくてはいけないということになってしまう(疑似相関については第2章での説明を参照のこと)。つまり、
ところが、既にVroom自身が指摘していた通り、職務満足と生産性との間に明確な相関関係がない。このことを整合的に説明するにはどうしたらよいだろう。
実はこのことは、1が個人の変化性向である体温に応じて、遂行レベルが変動することを示していると考えれば説明がつく。既に見たように、A型のモデルでは個人の体温が内発的動機づけを決定づけている。体温が生産性を決定づけているとは考えられないだろうか。実は次のように、変化性向である体温を媒介させ、自己決定度の段階ではなく、その前の体温の段階で遂行レベルに影響を与えていると考えることで、2、3の事実関係もうまく説明することができるのである。
これで図4.4の変化性向の枠組みのうちの生産性に関する部分が見えてきたことになる。つまり、②③の指摘は、自己決定度と生産性の直接の相関関係を示しているものではなく、実は、体温を先行変数として、自己決定度と生産性との間でみられる疑似相関を指摘していると考えるべきである。しかも、自己決定度に対しては、システム温も影響を与えることから、その生産性との疑似相関はより弱いものになってしまうし、問題となっている職務満足と生産性との相関関係はさらに弱まり、明確な相関関係が見られなくなると考えられる。
以上のようなことから、次のような仮説を立てることにしよう。
仮説7 (生産性仮説). 体温の高い組織ほど生産性が高い。このようにして、前章4.4節で予告的に提示された「変化性向の枠組み」が完結して示されることになる。この高体温が高い生産性と直接的に結び付くという考え方は、事実関係を説明するには有力である。しかし、残念ながら、組織の生産性と変化性向との関係についてのデータを我々はまだ持ち合わせていない。そこで、この章の残りでは、経営の分野でこれまで蓄積されてきた事例研究や事実発見をもとにして、生産性仮説の妥当性について吟味、検討してみることにしよう。
今日の近代経営管理の源流の一つで、20世紀初頭において米国を中心として展開された科学的管理(scientific management)についてまず考えてみることにしよう。Taylorは、当時の米国、英国で工員が故意に仕事をのろのろとゆっくりやって、一日分の仕事量が増えないようにすることが、ほとんどすべての工場に共通した現象であり、この怠業 (soldiering)を除去することこそが、労使の繁栄をもたらすことになると主張している (Taylor, 1911, pp.13-15 邦訳pp.230-231)。そして、怠業は二つの原因からきているのであり、一つは人間の本能として楽をしたがるからで、これを自然的怠業(natural soldiering)と呼んだ。もう一つの原因は、当時、精を出して働いて出来高を増したばっかりに工賃単価が引き下げられたりするような事態が繰り返されたことで、自分たちの利益や仲間との関係に色々思慮をめぐらして怠業するのだとし、これを組織的怠業(systematic soldiering)と呼んだのである(Taylor, 1911, p.19 邦訳p.235)。
Taylorは、この組織的怠業に対処するために、科学的管理を提唱している。時間研究 (time study)やGilbreth夫妻によって始められた動作研究(motion study)により、科学的に課業を設定し、この課業を指図通りの時間内に正しくなし終えたときには、普通の賃金より30%から100%の割増賃金をもらうようにして(Taylor, 1911, p.27 邦訳p.252)、精を出して働いて出来高を増したばっかりに工賃単価が引き下げられたりするような事態を防ぐとともに、目分量式(rule of thumb)の非能率な動作をやめて、科学をもってして、最も速くて最も良い方法へと代えていくことを主張したのである(Taylor, 1911, pp.23-25 邦訳pp.239-241)。
しかし、こうした試みは、近年必ずしもうまく機能していない。このような一種の能率給型の外的報酬を利用して、V型の動機づけモデルで生産性の改善を考えるには、ある水準の「効率的遂行」が報酬獲得につながり、誘意性をもたらすように遂行レベルを設定することが必要になる。しかし、それで効率的に生産しているといえるのだろうか。A型の内発的動機づけのモデルでは、遂行自体が目的になっているので、ある意味では、効率向上それ自体が内的報酬となりうる。ところが、V型の外的報酬による動機づけの場合には、遂行がそれ自体目的なのではなく、あくまでも誘意性獲得のための手段である以上、効率や生産性の「向上」それ自体が満足をもたらすことにはならない。それは、単に事前に設定された「効率的とされるある水準以上の遂行」が外的報酬を経由して満足をもたらすのにすぎないのである。もちろん、Taylor自身はその水準の設定に工夫をしたのではあるが、多くの場合、誘意性獲得に必要な遂行レベルは作業者の潜在的可能性を下回って設定されているだろうから、V型のモデルで考えると、外的報酬のみによる動機づけの場合には、常に組織内に未利用のスラック(ゆるみ、たるみ)の存在する可能性を残していることになる。既に述べたように、V型のモデルでは、できるだけ容易な道へと向かってしまうのである。遂行は設定された遂行レベル以下でなければよいのであって、メンバーは設定された遂行レベル以下でも以上でもなく、遂行を行うことになる。
それどころか、むしろ変化に対する態度(attitude to change)には悪影響を与えてしまう。Woodward (1965, pp.47-49 邦訳pp.57-59)は、能率給ではなくて、時間単位の給与をもらっていることが、製造工程や製造方法の変化に抵抗がないことの要因だと指摘している。給与が生産性に連動するがゆえに、一時的にではあれ生産性の低下する製造工程や製造方法の変化に抵抗することになるのである。つまり、短期的に業績が報酬に連動する能率給システムは、仕事の内容の変化よりも、むしろ外的報酬の変化に眼を向けさせる結果になる可能性がある(cf.命題D2)。能率給システムが必要となるような状況もあるだろうが、従業員を動機づける最も満足すべき手段であるかどうかには疑いがあり(Deci, 1975, p.226 邦訳p.236)、外的報酬を使用するべきかどうかは外的報酬による動機づけの増加が内発的動機づけの低下よりも大きいかどうかによって決まってくるのである(Deci, 1975, p.225 邦訳p.256)。
Taylorの主張は、生産管理、労務管理が職場の工員や経験工まかせの成行管理になっていた19世紀末から20世紀初頭の時代背景から出てきたものである。だからこそ、Taylor (1911, p.26 邦訳p.241)は科学的法則に従って仕事が行われるためには、管理者が工員まかせにせずにもっと責任分担をして、この科学を発達させ、部下として働いている工員を指導、援助し、その結果に対して、大部分の責任を負わなければならないとしたのである。
そして、事実、その後、工業化が進み、企業の管理組織や手段が整備されてくるにつれて、製品の開発・設計、製造方法、生産計画、作業方法、作業手順の決定や改善・修正、作業集団の編成、負荷の決定や配分などのおよそ生産にかかわる諸々の技術的・管理的問題は、経営者、管理者、技術者、コンサルタントなどの専門家に掌握され、現場の作業者はこうした問題から隔離されていくのである(島田, 1988, pp.97-98)。
島田(1988, ch.3)は、自動車産業において、米国の日系進出工場を米国企業の工場と比較して、日米の自動車産業の生産技術の三つの相違点を挙げている。すなわち、科学的管理の影響が色濃く残る米国の自動車産業では
といったような特徴をもっているのに対して、日本企業はこれとはかなり対照的である。まず1については、製品や部品の標準化は米国と同様であるが、労働については、米国のように細密な区分を行わず、職種区分が大まかに緩やかにつくられ、各人の担当する職務内容は弾力的に変化しうるように構成されている。
さらに、2については、逆に、中間在庫削減の強調が行われている。中間在庫の削減は、それが可能ならば、それ自体、在庫コストを節約するという直接的で大きなメリットがあるが、それだけではなく、うまくいけば、中間在庫を減らすことが、生産システムに伏在する問題点を発見し、これを解決しようとする心理的な効果をもたらし、欠陥率、不良率が低下し、品質が向上し、欠陥品の廃棄・修繕コストを節約するメリットがある。
また3については、日本企業は小ロット生産を特徴としている。小ロット生産は、作りすぎと中間在庫を低く抑える。また不良や欠陥が発生した場合でも、ロットが小さいだけに影響範囲は小さく、その発生原因も追求しやすいために、品質向上効果がある。ただし、機械の段取り替えには時間がかかるので、小ロット生産を経済的に実現するためには、段取り時間を短縮することが必要になってくる。
言い換えるならば、米国の生産方式は、現場の労働者と機械設備(ハードウェア)や生産システム(ソフトウェア)との相互作用を最小にするように技術体系が構成されている(島田, 1988, p.110)のに対して、上述の日本の生産方式は、そのシステムがうまく機能すれば、効率的かつ高品質の生産を推進するように作用するが、システムがうまく機能するかどうかは、現場における人間の働きに大きく依存しているのである。人々が必要な知識と技能を身に付け、現場の変化に弾力的に適応しつつ、生産や改善活動に意欲的に参加するならば、この仕組みは効果的に機能するが、その条件が満たされなければ、この生産システムはうまく機能しなくなる。島田(1988, ch.4)はこうした人的役割を
といったような例によって示した上で、このような人間的要素のさまざまな役割に共通している重要な機能は、トヨタで「改善」と呼んでいる人々の意識的な働き、つまり「つねに事態をより良くしていこうという自律的な自己革新的機能」(島田, 1988, p.143)であると述べている。この改善で重要なのは、自分の良心にしたがって仕事をする態度であり、その際には、自分の今期実績と過去の実績との比較や他人の実績との比較が当人の評価の基準となる。すなわち、向上心と競争心が改善活動の基礎となる(門田, 1991, pp.367-368)。こうした人的役割を期待する基礎となっているものこそ、まさに個人の変化性向、つまり体温の概念と一致するものである。ということは、日本の生産方式は高体温を前提にしており、その高体温が高生産性に結び付く一つのあり方を示す例となっているといえるのである。
実は、Taylor (1911, pp.34-35 邦訳pp.248-249)は、当時の通常の管理の中では最良のものとして、工員にできるだけ自発的に仕事をさせ、その代わり特別の誘因を与えるという、自発性と誘因の管理(management of initiative and incentive)を挙げ、科学的管理と対照区別して論じていた。そして、この「旧式」の管理では、成功は工員の自発性に依存しているのであり、成功するのはまれなケースだと断じている(Taylor, 1911, pp.35-36邦訳p.249)。確かに、成功は工員の自発性に依存している。しかし、米国の日系進出工場の特徴は、Taylorがまれなケースだと切り捨ててしまった事態が、実際に起こり得たということであろう。まさに科学的管理から自発性と誘因の管理への原点回帰である。
成功が工員の変化性向すなわち体温に依存しているというTaylorの指摘は、この章の後半の議論の帰結、すなわち生産性仮説と基本的に合致している。しかし、なぜTaylorは変化性向が低いと断言するのだろうか。これは、Taylorが前述のように自然的怠業を考えていたことと無縁ではないだろう。つまり、楽なゆっくりした歩調で仕事をしようとする傾向があることに疑いはないのであり、なみなみならぬエネルギーと活力と野心とをもち、せっせと働く人は例外にすぎないと考えていたのである(Taylor, 1911, p.19 邦訳p.235)。
このTaylorの科学的管理は典型的な例だが、McGregorは、経営者が決定を下し、措置をするからには、必ずその背後に人間の性質・行動に関してなんらかの考え方があると考えた。当時、組織に関するたいていの文献や経営施策で暗黙のうちに了解されているものとして、
をあげ、こうした一連の考えを「X理論」(Theory X)と名付けた(McGreger, 1960, pp.33-34 邦訳pp.38-39)。Taylorの考え方は、まさにX理論の系列に属するものである。
他方、人間行動に関する知識が蓄積されてきたことを手がかりに、当時、人事管理の新理論が生まれてきたが、McGregorはこの考え方を「Y理論」(Theory Y)と呼んだ。Y理論は次のような人間の特性を仮定している(McGreger, 1960, pp.47-48 邦訳pp.54-55):
このようにY理論はX理論の暗黙の仮定を否定したものである。そして、McGregor (1960, p.49 邦訳p.56)はX理論から導かれた「階層原理」(scalar principle)にしたがった命令、統制による経営に反対し、Y理論に基づいた経営を主張する。X理論は個人の変化性向を低いものとする暗黙の仮定に基づく考え方であるが、その仮定が正しくないことは、これまでの議論から明らかであろう。個人差はあっても、変化性向は根源的な欲求なのである。X理論は何か問題を引き起こすはずである。実際、X理論の系列に属する科学的管理においては、既に当時から、Taylor自身が、科学的管理の下では工員を単なる自動機械、でくのぼうにしてしまうという印象がある(Taylor, 1911, p.125 邦訳p.322)とか、科学的管理では、工員が自分で新しいより良い作業方法を工夫する誘因が少ないようだ(Taylor, 1911, pp.127-128 邦訳p.323)と認めている。
それでは、なぜ一部ではあってもX理論が信じられているのであろうか。Morse & Reimer (1956)の実験によると、四つの部門に所属した約200人の事務員に対して、そのうち二つの部門については、意思決定を行う階層レベルを引き下げ、一般の事務員に意思決定をより行なわせる監督方式をとる自律的プログラム(autonomy program)を実施した。対照的に、残りの二つの部門については、意思決定を行う階層レベルを引き上げる階層統制的プログラム(hierarchically-controlled program)を実施した。
後者の階層統制的プログラムでは、実験した1年くらいの間は自律的プログラム以上に生産性が向上している。このことが、管理方式やリーダーシップのタイプの選択を誤らせることになる。ところが、実はその生産性が向上している間に、態度の方は次第に非好意的になってきて、自己実現感や職務満足が低下してくることになる。それに対して、前者の自律的プログラムでは、生産性の向上と同時に、態度の方もますます好意的になり、自己実現感や職務満足も向上してくる。
階層統制的プログラムが職務満足を低下させるとするならば、やがて重大な結果を招くことになる。5.2節の退出仮説が示すように、職務満足の低下はやがては退出の意思決定を促し、せっかく、コストをかけて採用、訓練し、効率的に機能するように組織化した有能な要員を失う結果になるからである。事実、階層統制的プログラムの下では実験期間中に既にその兆候は現れていたとされている。階層統制的プログラムにおける生産性の向上は、その組織の人的資産を犠牲にして得られたものだといえそうである。短期的な生産性に目を奪われれば、X理論や階層原則の誘惑に負けてしまうのである。
この節及びこの章の最後に、生産性向上のための教訓を指摘しておこう。
米国シカゴ市にあるウェスタン・エレクトリック社(Western Electric Company)のホーソーン(Hawthorne)工場で、1924年から1932年まで行われた一連の実験、いわゆるホーソーン実験(Hawthorne experiments)は、その成果をもとにして、人間関係論(human relations)が展開されるきっかけとなったものとして有名である。
人間関係論とは何なのか。一般的には、作業者の作業能率が工場の照明度や休憩時間などの物理的環境条件よりも、彼らの心理的・情緒的なものに依存するところが大きく、職場という公式組織の中に自然発生する非公式集団の影響力が大きいことを強調する学説であると理解されているといってよいだろう。これだけの質、量の実験結果が、われわれの議論に対して、どのような意味をもっているのかを検討してみよう。
Roethlisberger (1942, ch.2)によると、ホーソーン実験は1924年の照明実験をもって開始されたといわれる。この実験では、作業者を2群に分け、さまざまな照明度の下で作業させる試験群(test group)とできる限り一定の照明度の下で作業を続けさせた統制群(control group)とを比較することで、照明の質と量が従業員の作業能率の上にどのような影響を及ぼすのかを調べる目的で行われた。
その結果、例えば、試験群の照明度を3段階で徐々に高めていったが、両群とも生産量はほぼ同量増加したし、試験群の照明度を下げても、やはり両群とも生産率は上昇した。つまり、一連の照明実験で、両群の間には生産高で重要な相違はなく、同じ様に変化していたのである。ということは、照明度と作業能率との間にはなんの相関関係もないということになる。しかし、この段階では、まだこの結論を下してしまうことをいさぎよしとしなかったので、作業者の生産能率に影響する他の変数をもっとよく統制した状態で、新たな実験を計画すべきだということになったといわれる。
そこで、1927年4月から1932年半ばにかけて継電器組立作業(relay assembly)実験が行われたわけであるが、この実験について、Mayo (1933, ch.3)とRoethlisberger (1942, ch.2)をもとにして、主要な事実発見をまとめてみよう。
この実験では、5人の女子作業者を他の作業者から隔離された作業室に移し、適当な期間を置いて彼女たちの作業条件にさまざまな変化を導入し、これらの変化が生産高にどのような影響を及ぼすのかを調べる実験が5年間23期間にわたって行われ、文書にして数トンという資料が集積されたという。しかし、物理的環境上の変化を生産高と関係づけようとするあらゆる試みは、有意な相関関係を一つも見いだすことができず、ものの見事に失敗に終ってしまった。ところが別の興味深い事実発見があったのである。
実験の最初の1年半ぐらいの間、休憩時間のとり方や作業時間の短縮、特別の軽食の提供といった作業条件の改善につれて、生産能率が徐々に上昇していった。しかし、実験の第12期(1928年9月から12週間)に、これらの作業者にとって優遇的な条件は12週間廃止され、作業条件をすべて調査当初の第3期(第1〜2期は作業実験室への移動前後のいわば準備期間だった)の状態に戻し、悪化させたにもかかわらず、生産高は12週間の間依然として極めて高い水準を保ち続け、それまでのいかなる期間の生産高をも超えたのである。そして、その後、1929年6月末まで31週間継続された第13期には、休憩及び茶菓を復活し、生産量はこれまでのうち最高のものとなったのである。そして、第7期、第10期、第13期は、同じ労働時間、同じ労働条件だったにもかかわらず、これら3期間の生産高は上昇傾向をとり続けたのである。つまり、生産高は継続的に上昇傾向を示し、それは休憩についての変化ともまったく無関係に存在していた。その間、女子作業者の満足感は注目に値するほど高まった。そして、女子作業者の欠勤率は約80%も減少したのである。
これに対するRoethlisberger (1942, ch.2)による説明は、研究者たちが実験に対する被験者たちの完全な協力を得ようと努めた結果、工場で通常行われていた作業習慣はすべて変えられてしまったほどで、女子作業者の協力的態度、および生産能率向上の原因は、実はここに求められねばならないというものであった。例えば、
Roethlisbergerは、なぜこれらの要因が、高生産性、高満足、低欠勤率をもたらしたのか、については何も説明を与えていない。しかし、変化性向の枠組みを使うと説明が可能になる。明らかに、作業慣習が変えられたことにより、変化性向の大きい作業慣習が導入されている。つまり、システム温が上昇したのである。自己決定度仮説(第4章仮説5)の(a)が示すように、たとえ同じ体温であっても、システム温が上昇すれば、自己決定度は増大する。そのことで、1、3にみられるように、被験者の自己決定度は増大し、2のように承認による有能さの感覚も増大して、自己決定度仮説(b)の通り、職務満足感が高くなったと考えられる。その結果、退出仮説(この章の仮説6)が示すように欠勤率も低下したと考えられる。
それでは生産性はどうして向上したのであろうか。変化性向の枠組みには入っていないが、ひょっとしてシステム温の上昇が体温の上昇をもたらしたのだろうか。実はそうではないという指摘が、Carey (1967)によってなされている。Careyはホーソーン実験を厳しく批判し、誤った解釈が随所に見られると指摘している。その一つが、生産性の増加がなぜもたらされたのかという点についてのものである。Careyによれば、実験の途中で、5人中2人の反抗的な作業者が解雇され、代わって経済的な問題で仕事を必要とした生産的で経験のある2人の女性が入ってきて、彼女らの努力と刺激が集団の生産性に増加をもたらしたのだとするのである。
5人の作業者が実験の全過程を通じて固定されていたものではないことは、Mayo (1933, ch.3)によっても明言されており、実験の最初の年である1927年で5人中作業者番号1番と2番の2人が脱落し、1928年1月に始まる第8期からは、その者たちと同程度ないしはそれ以上の技能をもつ他の2人の者が、同じ番号を引き継いで、これに代わって最後まで仕事を継続したことが述べられている。さらに、作業者番号5番のもう1人も、1929年の半ばにホーソーン工場をやめたが、1年後、再びこのグループの職に復帰しており、その間は別の作業者が実験に参加していたことも述べられている。そして、作業者番号1番〜5番の平均毎時生産量が、1927年〜1932年にわたってグラフで示されている。確かに作業者番号1番と2番は交替直後から生産量がはね上がっている。Careyの指摘も十分にありうるといっていいだろう。同じ労働時間、労働条件の第7期、第10期、第13期について比較して、生産高が上昇傾向をとり続けているといっても、実際にはそのうちの第7期と第10期・第13期とでは被験者が5人中2人もより生産的な作業者に交替していたのである。
もしCareyの指摘が正しければ、ホーソーン実験は貴重な教訓をもたらしてくれたことになる。まず、生産性は個人個人によってもともとかなり異なっているようだということ。そして、組織の生産性を上げるのに効果的な方法の一つは、生産性の低い人を減らし、生産性の高い人を増やすことだということである。つまり、個々人の生産性を上げるのではなく、組織として生産性の平均を上げる方法である。仮説7の生産性仮説からすると、この二つの教訓の中の「生産性」は本来「体温」としておくべきものであろう。
それでは、組織としての体温の平均が、組織によってかなり差が出てきてしまうのはなぜなのだろうか。それが次の第6章のテーマである。
当初、「ぬるま湯」現象は、組織の活性化していない状態の典型であると考えられていた。しかし、ぬるま湯感と職務満足感の間には、確かに有意な負の相関関係があるものの、職務満足感を感じている人のほぼ半数がぬるま湯感も同時に感じており、職務満足感とぬるま湯感との間にはかなりの重なりが存在している事実が判明した。
もともと「ぬるまゆにつかる」とは「現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす」あるいは「安楽な現状に甘んじて呑気に過ごす」意味であるとされている。そこで、現状に甘んじることなく変化を求める傾向、現状を打破して変化しようとする傾向、これを変化性向と呼び、つかっているお湯の温度に対応するものとして、組織のシステムとしての変化性向である「システム温」を考えた。このシステム温が高ければ、「温度」が高く、熱いと感じ、逆に、システム温が低ければ、「温度」が低く、ぬるいと感じるのではないかと考えたが、調査データは、ぬるま湯感を説明するためには、システム温だけではまだ不十分であることを示していた。
そこで、「ぬるい」と感じるか「熱い」と感じるかということは、組織人としての「体温」をベースとした体感温度の問題なのではないだろうかと考えたわけである。ここで体温とは、組織のメンバーの組織人としての変化性向である。この体温とシステム温との温度差で、ぬるま湯感を説明することを考えたのが、体感温度仮説である。
仮説1 (体感温度仮説). 体感温度をシステム温と体温を使って、企業のぬるま湯的体質をかなり説明することができるということが1987年調査のデータによって検証されている。さらに中間管理職を対象とした1988年調査でも、体感温度仮説によって、ぬるま湯感を説明できることが確認された。また1988年調査では、1987年調査と比較して、高水準のぬるま湯感が存在していたが、両調査のシステム温の平均はほとんど同じであり、システム温だけによって1988年調査での中間管理職の高水準のぬるま湯感を説明することはできない。しかし、体感温度仮説によれば、1988年調査の体温の平均が、1987年調査の平均を大きく上回っていたために、その体温の高さゆえに体感温度が低下し、その結果、ぬるま湯感が高水準になっていると説明することができるのである。
体感温度仮説が正しければ、体感温度はシステム温と体温の温度差なので、システム温、体温が共に高くても、共に低くても、同じ体感温度になってしまう。したがって、組織や職場の状態をその中にいるメンバーの「感じ」だけで判断してしまうことは危険だということになる。メンバー自身が「適温」だと思っていても、その実態はシステムも人も変化性向の低い状態になってしまっているかもしれない。経営学の領域でいう「ゆでガエル現象」である。体感温度仮説においては、体感温度の概念を定義、操作化することで、こうした指摘を単なる教訓話としてではなく、論理として議論の対象として提示することに、ある程度成功していると考えることができる。
湯かげん図において重要なことは、活性化していると呼ぶべき状態が「適温」の状態であることは確からしいが、他方、本来、活性化していないと呼ぶべき状態は「水風呂」の状態であって、「ぬるま湯」と感じている領域はどちらとも異なるということである。つまり、ぬるま湯の状態は不活性状態の典型というわけではなかったことになる。
こうして、システム温と体温の差によってぬるま湯感を説明する体感温度仮説を立て、ぬるま湯感を説明することに一応成功したが、いくつかの問題がまだ解明されないままに残っている。こうした問題に答えるために、この後の作業が続けられた。
なぜ、ぬるま湯的体質が企業から問題視されるのだろうか。そして、本当は違うのに、なぜ、ぬるま湯的体質が「組織が活性化していない状態」の典型という発想が生まれるのであろうか。そのことを明らかにするために、次の仮説が検討された。
仮説3 (成長性先行仮説). (a)成長期にある企業はぬるま湯感が低く抑えられていて、また活性化された状態が比較的容易に達成されうるのだが、(b)企業が低成長もしくは低迷に陥ってしまえば、活性化された状態は失われやすく、ぬるま湯感も進みやすい。つまり、組織の活性化された状態とぬるま湯現象は、概念的には独立の、直接的には因果関係の存在しない現象であるにもかかわらず、
というように、成長性という先行変数があるため、見かけ上は疑似相関があるだろうと予想するのである。
1989年調査によると、実際,ぬるま湯比率と活性化比率との間には負の有意な相関関係がある。つまり、活性化しているほど、ぬるま湯感が減少しているように、あるいは、ぬるま湯感が減少するほど活性化しているように見える。しかし、各社ごとにぬるま湯感と活性化の相関関係をみるために3重クロス表を作ってみると、こうした相関関係が、表面的、間接的なものであり、成長性という先行変数があるために、見かけ上の疑似相関であることが明らかになった。したがって、成長期の企業は活性化していて低ぬるま湯感、低迷期の企業は活性化していなくて高ぬるま湯感という特徴を持ち、全体として総計すると、見かけ上、活性化とぬるま湯感の間に相関関係がみられると考えられるのである。
疑似相関であるから、ぬるま湯感と活性化との間には、直接の因果関係は存在せず、ぬるま湯感を人為的に変化させても、直接的には活性化に変化は生じないはずである。そのことは実際にも確かめることができ、その良い例がG社で、調査年に社名を変更して、CIの真っ最中であり、そのために、システム温が上昇して、ぬるま湯感が低下しているが、活性化については、今までのところ変化していないことがはっきり示される。
もし企業が高成長を続けているのであれば、その組織自体の変化率が大きいことから、組織が現状に留まることは、したくてもできず、組織のシステムとしての変化性向も大きなものとならざるをえない。そのため、ぬるま湯感は自然と低く抑えられることになる。したがって、成長性仮説が明らかになったことで、ぬるま湯感の発生は、その企業の成長性が鈍化し、衰え始めることで、システムの変化性向すなわちシステム温が低下してきているという意味での危険信号、シグナルになっていると考えられるのである。
体感温度仮説の検証を行った際に、一つの重要な事実発見、すなわち「非ぬるま湯」群の大部分が、実は「熱湯」ではなく、「適温」と呼ぶべき領域に属していたことがわかった。そこで、第3章では、こうした事実発見をふまえて、「ぬるい」対「熱い」という対立図式を体感温度によって説明するのではなく、ぬるま湯比率を体感温度で説明することを考え、次のような体感温度仮説のぬるま湯比率版を考えた。
仮説4 (ぬるま湯比率に関する体感温度仮説). ぬるま湯と感じる人の比率をぬるま湯比率と呼ぶと、体感温度が高くなるほどぬるま湯比率は低下する。これまでの質問票調査によって集積されたデータと経験をもとにして、質問項目の収集、整理が行われ、それを基にした質問調査票の設計を行い、1990年に予備調査と本調査の2回の調査を行って、質問項目リストの改善を図った。さらに追試として、1991年に調査を行い、質問項目リストの再吟味を行った。その結果、体感温度の測定はより信頼できるものになったことがわかった。
なぜ、職務満足感とぬるま湯感は共存するのであろうか。そもそも、職務満足はどこから来て、システム温、体温といった変化性向とはどのような関係があるのだろうか。職務満足については、内発的動機づけを考えることがもっともらしい。
内発的に動機づけられた活動とは、当該の活動以外には明白な報酬がまったくないような活動のことである。見た目には、つまり外的には何も報酬がないのに、その人がその活動それ自体から喜びを引き出しているようなとき、そう呼ばれる。言い換えれば、その活動が外的報酬に導いてくれるという、目的のための手段になっているという理由からではなく、その活動それ自体が目的となって、その活動に従事しているような活動を内発的に動機づけられた活動というのである。
内発的に動機づけられた行動は、人がそれに従事することにより、自己を有能で自己決定的であると感知することのできるような行動である。人間にはもともと有能さと自己決定の感覚への欲求があり、それが自己とその環境との相互作用の結果として、特定のいくつかの欲求へと分化していくのである。ここでの「有能さ」という用語は、自己の環境を処理し、効果的な変化を生み出すことのできる人の能力または力量を指しており、言い換えれば、有能さという用語を選ぶことで、変化性向の概念を考察していることになる。人は自己の環境を自分で処理し、効果的な変化を生み出すことができるときに、有能で自己決定的であると感じるのである。もちろん本書では、変化性向の大きさを測定しようとする試みからスタートしていることからもわかる通り、変化性向には個人差があることを前提としているが、この変化性向がある程度の大きさでは存在しているために、内発的に動機づけられた行動をとり、その結果、有能さと自己決定の感覚が高められれば、満足感を得ることになるのである。
変化性向の定義から考えて、個人の変化性向である体温が高いほど、そして、個人の組織内環境であるシステムの変化性向、つまりシステム温が高いほど、個人の自己決定の度合は高くなり、自己決定の感覚も高くなるはずだと考えられる。そこで、変化性向との関係から、自己決定の感覚に的を絞って、自己決定度を連結点にして、変化性向と職務満足を結び付ける自己決定度仮説を立てた。
仮説5 (自己決定度仮説). (a)個人の変化性向である体温が高いほど、そして組織のシステムとしての変化性向であるシステム温が高いほど、組織の中での個人の自己決定の感覚は高くなる。(b)この自己決定の感覚が高いほど、職務満足は高くなる。ただし、システム温は衛生要因的な役割を果たすにすぎず、それ自体が直接、自己決定の感覚をもたらすわけではないことには注意がいる。 1990年本調査、1991年調査のデータはともにこの仮説を支持している。この自己決定度仮説によって、なぜ職務満足感とぬるま湯感が共存しうるのかということを説明できる。体感温度仮説によれば、高体温・低システム温は高いぬるま湯感をもたらし、一方、自己決定度仮説によれば、高体温・高システム温は高い職務満足をもたらす。したがって、高ぬるま湯感領域と高職務満足感領域は、湯かげん図上で重なり、高ぬるま湯感・高職務満足感領域ができてしまうのである。
ぬるま湯感やシステム温、体温といった変化性向は、組織の生産性や職務遂行との間にどのような関係をもっているのであろうか。米国では、退出の意思決定に由来する欠勤、離職といった行動と職務満足との間に相関があることは広く認められている。次の退出願望と職務満足に関する仮説は、1990年本調査のデータでも容易に検証される。
仮説6 (退出仮説). 職務満足が低いときに、「組織を退出したい」という願望が知覚される。それに対して、職務満足と生産性の相関には疑問のあることが、これまでに指摘されている。これはどうしてなのであろうか。内発的動機づけのモデルでは、個人がより困難なことにチャレンジし、より効率的に生産活動を行うように動機づけられることを説明できる。しかもこのとき、個人の変化性向である体温が内発的動機づけを決定づけて、高い体温が高い生産性につながるのである。自己決定度仮説が示すように、体温とシステム温が高いほど自己決定度も高まるので、次のように変化性向を媒介させることで、事実関係をうまく説明することができる。
体温を先行変数として、自己決定度と生産性との間で疑似相関があると考えられる。しかし、自己決定度に対しては、システム温も影響を与えることから、その生産性との疑似相関はより弱いものになってしまうし、問題の職務満足と生産性との相関関係はさらに弱まり、明確な相関関係が見られなくなっていることも十分に考えられる。そして、こうした図式の中でシステム温がうまく機能しているかどうかということが、実は、本書のメイン・テーマであるぬるま湯感によって検知されていたのである。
高体温が高い生産性と直接的に結び付くという考え方は、事実関係を説明するには有力である。しかし、残念ながら、組織の生産性と変化性向との関係についてのデータを我々はまだ持ち合わせていない。そこで、経営の分野でこれまで蓄積されてきた事例研究や事実発見をもとにして、次の仮説が立てられる。
仮説7 (生産性仮説). 体温の高い組織ほど生産性が高い。以上の諸考察から、図6.1のような関係が組み立てられる(図4.4の再掲)。これが「変化性向の枠組み」である。職務満足の理論では、主要関心は二つの変化性向の足算つまり右下の方向に向いていたのに対して、もともと体感温度仮説では、二つの変化性向の引算つまり左上の方向に向いていたことになる。この変化性向の枠組みによって、ぬるま湯感と職務満足感の発生と共存のメカニズムが統一的に明らかにされるとともに、生産性や職務遂行との関係も明らかになる。
図6.1 変化性向の枠組み
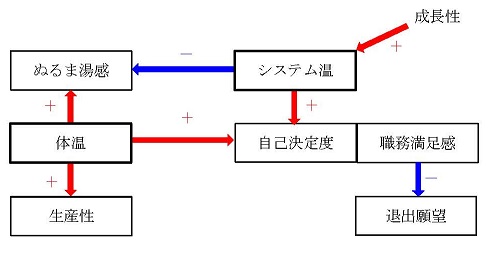
ところで、実はこれまで整理してきた仮説の中に次の仮説2が入っていなかったことに気の付いた読者もいただろう。
仮説2 (恒温仮説). システム温の変動にかかわらず、個人の体温は安定的である。いくつかの経験的証拠、状況証拠からすると、この仮説は正しいようなのだが、それならば、なぜ企業によって体温の違いができるのであろうか。そして、体温とシステム温の間に正の相関が見られるのはなぜだろうか。そこで次節からは、本書及びこの章の締めくくりとして、システム温と体温の概念を膨らませて、より一般化し、単に大きさや量だけではなく、内容や質も考えることで、組織のロジックと「人質」という概念をそれぞれ考え出し、システム温と連動した体温形成のメカニズムについての一つの解答を述べることにしたい。
組織がもっている目標の種類、用いる管理の型、従業員間関係、上司部下間の関係、そういったものの基礎にある諸価値などが、組織によって劇的に異なっているとしばしば指摘されてきた(e.g., Schein, 1978)。いわゆる組織風土(organizational climate)の存在である。本書で取り上げてきた「組織活性化のための従業員意識調査」でも、その調査過程からやはり同様な組織間差異の存在を確認してきた。例えば、1990年本調査では、次のようなYes-No形式の質問
Q6. 失敗をしながらでも業績を挙げていくよりは、失敗をしないで過ごした方が評価されると思う。に対して、表6.1のような明らかに会社別に異なる回答を得ている(1987〜1989年調査とは独立別個にA〜I社とラベルを付けている)。
表6.1 1990年本調査の質問に対するYes比率(網掛けは最高と最低を示す)
| 質問 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | F社 | G社 | H社 | I社 | 全体 | χ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 | 57.1 (196) | 30.1 (83) | 78.0 (50) | 84.6 (91) | 62.1 (87) | 50.5 (109) | 58.4 (113) | 58.3 (24) | 61.5 (91) | 59.0 (844) | 64.933*** |
| Q7 | 33.2 (193) | 22.5 (80) | 24.0 (50) | 12.1 (91) | 22.9 (83) | 42.2 (102) | 31.3 (112) | 78.3 (23) | 22.1 (86) | 29.1 (820) | 55.792*** |
| Q8 | 77.6 (196) | 63.9 (83) | 92.0 (50) | 80.4 (92) | 71.6 (88) | 35.1 (111) | 85.8 (113) | 83.3 (24) | 80.7 (88) | 72.8 (845) | 110.954*** |
| Q9 | 30.9 (194) | 24.7 (85) | 72.0 (50) | 40.7 (91) | 31.8 (88) | 13.8 (109) | 21.1 (114) | 16.7 (24) | 39.6 (91) | 30.9 (846) | 70.885*** |
こうした一般的に知られている経験的事実をふまえて、McGregor (1960, ch.10)は「経営風土」(managerial climate; 邦訳では残念ながら「経営環境」と訳されてしまっている)の概念を開発した。組織の中での直接の上司や他の主要な人々の日々の行動が、基本的に重要な経営に関する彼らの仮定(assumptions)について何かを伝達しており、こうして多くの行動に微妙に現れる態度が心理的風土(psychological climate)を造り出しているというのである(McGregor, 1960, pp.133-134 邦訳pp.154-155)。Litwin & Stringer (1968)によると、この心理的風土についての最初の明確な研究は、1930年代のKurt Lewinの研究まで遡るとされるが、組織風土のごく一般的な定義としては、例えば、Forehand & Gilmer (1964)による定義がわかりやすい。すなわち、ある一つの組織を記述する特性で、
の集合が組織風土であると定義している。
しかし、ここでは組織風土の全容を解明するつもりはない。関心のあるのは、この1〜3の条件を満たし、かつ組織にとって本質的に重要な基本的ロジックの部分である。より具体的にいえば、さきほどの質問Q6〜Q9やシステム温の算出に用いた質問、特に改良版のS1、S6〜S9が問うているのは、その組織の中では、何が良くて、何が悪いのか、あるいは、何が評価され、何が評価されないのかといった、その組織の中で生きていくのに基本的に前提として知っていなくてはならない評価基準、評価の仕方である。このように、その組織のメンバーの価値前提を構成する基本的ロジックを「組織のロジック」と呼ぶことにしよう。これは本書でこれまで、その大きさを測定することに関心を向けてきたシステム温、つまりシステムの変化性向の実体とでもいうべきものである。より形式的に述べれば、組織のロジックとは、組織内のメンバーの行動ないしはその結果に対して、その組織という社会がもっている優先順位、社会的選考順序のことである。それはとりもなおさず、その組織のメンバーが、組織としての行動の一端を担うために、その自らが担当する意思決定の価値前提としてもっておくべきものである。
まずそこで、価値前提という概念について、Simon (1976)をもとに整理しておこう。事実的命題(factual propositions)であれば、観察しうる世界とその動き方についての記述であり、その真偽を検証することができる。しかし、意思決定は事実的命題以上のなにものかである。意思決定は一つの将来の事態を他よりも選好し、その選択した事態を目指して行動するという性質をもっている。つまり、意思決定は事実的内容とともに、「べきである(ought)」、「よい(good)」、「好ましい(preferable)」のような倫理的な用語 (ethical term)によって表される倫理的内容を有している。あらゆる意思決定は、「事実的」と「価値的」と呼ばれる2種類の要素を含んでいるのである(Simon, 1976, pp.45-46 邦訳pp.56-58)。言い換えれば、意思決定の過程は次の二つの主要な部分に細分化できる。つまり、(1)手段−目的連鎖の中での中間的価値の体系化とそれらの相対的重要性の評価を含む部分と、(2)この価値体系の観点から、可能な行為を比較する部分である(Simon, 1976, p.53 邦訳p.65)。そして、(1)に対応して、手段−目的連鎖の中で決定が最終目的の選択につながる限り、これらの決定を「価値判断」(value judgments)と呼び、他方(2)に対応して、決定がこうした目的の実行をともなっている限り、それらを「事実判断」(factual judgments)と呼んでいる(Simon, 1976, pp.4-5 邦訳p.7)。
合理的な意思決定は、二つの異なった種類の意思決定前提、すなわち、価値前提(value premises)と事実前提(factual premises)から引き出された結論と考えることができる。価値前提と事実前提の与えられ方と、それによる意思決定のあり方には、次のような3通りのケースが考えられる(cf. Simon, 1976, pp.223-224 邦訳p.283)。
したがって、3の事態を避けるために、価値前提の共有はメンバーに自由裁量を与える際の重要な前提条件となるのである。このことは数理的な組織設計モデルを扱う際にも、同様にいえることであり、Takahashi (1987c;1988)では、価値前提の共有を仮定することで、はじめて権限委譲を検討に値する選択肢として扱うことが可能になっている。
他方、このことは、共有すべき情報の種類を限定しているという点でも、極めて重要である。もし、すべてのメンバーがすべての情報を共有していなければならないのであれば、組織が多くの人間で構成されている積極的意味はない。情報・意思決定という点では一人のメンバーしかいないのと同じことだからである。組織を限定された合理性しかもたない人間が合理的に意思決定しうるための装置であると考えれば(高橋, 1989d)、組織の中に存在する情報には、共有すべき情報もあれば、共有すべきではない情報もあるはずである。前述の①②③のケースを比較してわかるように、おそらく事実前提の多くは共有する必要のないものであろう。そして、価値前提のかなりの部分は共有しておく必要のあるものであろう。その中でも、組織のロジックは、共有すべき価値前提の最低限必要な部分を構成していると考えられる。その組織の一員として行動するということは、この組織のロジックを理解し、それに則って行動するということだからである。
以上のようなことから、組織のロジックに着目することで、ある種の組織行動を説明することができる。例えば、若杉(1989)は、欧米企業との比較で、日本企業が、基礎研究については外国の成果に依存し、自らは基礎研究よりも応用研究や開発段階に特化しているという事実を説明するために、次のような二つの「組織原理」を指摘している。一つは、キャリア・パスに関するものである。日本企業では、研究開発に従事する者は、研究開発のサポート業務に従事する入社〜20歳代後半の教育時代を経て、30歳代前半に一人前の技術者に成長し、35歳前後〜40歳前後には研究開発部門の第一線またはしばしば生産・販売部門の管理者になる。そして、それ以降は第一線の研究開発業務から離れ、管理職へ移行するというような、かなりはっきりしたらせん階段状の昇進プロセスが存在するという。つまり、日本企業では、優秀な技術者を生産、企画、販売等の部門の責任者として、より高い地位に昇進させ、処遇する方法が一般的で、一貫して研究開発に従事させるというような欧米で見られるキャリア・パスが必ずしも確立されていない。いったん、このような日本企業型のキャリア・パスが与件として認知され与えられてしまえば、自らのキャリア・パスが開けている生産・販売部門での評価、業績につながる研究目標に関心が向くのは当然で、そのことが、自己のキャリア・パスを有利なものにするという意識が働くことになる。
もう一つは、研究開発費の配分原理である。研究開発費は、研究開発部門に硬直的に配分されるのではなく、経常的な研究経費を除けば、その他の事業部や本社の意思が強く反映され、企業全体の収益にどれだけの寄与をすることが期待されるかで決められる。つまり、研究開発費は、応用研究や商品開発のようにかなり具体的で、はっきりした目的やテーマをもつものが評価され、重点的に研究開発費を配分されやすい仕組みになっているというのである。したがって、以上のようなキャリア・パスと研究費配分の際の評価システムという組織のロジックが、日本企業の研究開発従事者の研究開発行動を規定していると結論づけているのである。
キャリア・パスに象徴されるように、組織のメンバーにとって実用的で詳細な企業のロジックは、多くの場合、全社的かつ系統的な人事情報と、部分的に一部のメンバーと共有された時間空間情報を基礎的なデータとして、個人レベルで帰納的に導き出されるようである。多くの企業にとっては、「出世コース」やキャリア・パスの軽重、ポストの軽重、昇進スピードのもっている意味、さらに、自分の知る範囲で、特定のポストの人が、具体的にどのような経歴、個性、業績をもっているかということが、組織形態(組織構造や管理システムなど)に関する情報と重ね合わされることで、何が評価され、何が評価されないのかという組織のロジックを特定する際に重要な意味をもってくる。ただし、ここで注意が必要なのは、それがいわゆる「報酬システム」ではないということである。報酬システムは確かに組織のロジックを反映しているが、大事なのは目に見えているシステムの方ではなく、その根底に横たわっているロジックの方なのである。それはむしろシステムというよりも企業コンセプトのようなものに近い。
例えば、筆者がヒアリング調査をしたことのある民間警備会社は、創業者の明確な企業コンセプトに基づいて創業され、それ以来セキュリティ事業を中心としたサービス、商品を次々と開発、普及し、創業から4年後の安全のオンライン化を目指したSPアラームシステムの実用化までに現在の企業コンセプトがほぼ確立したと言われる。これ以後、企業コンセプトの維持に莫大な量のエネルギーが投入されているという。もちろんサービスのシステム化、マニュアル化も行われているが、それ以上にこの会社の従業員はこの企業コンセプトの布教、伝道者として行動してきている。組織の創設者と初期の基本メンバーの価値および態度が後の会社の方針の源になることが多いので、組織のロジックはこうした人達のパーソナリティーおよび経歴に基づくものかもしれない(cf.Schein, 1978, ch.1)。
いずれにせよ、もし、同じ能力をもったメンバーが二人同時に入社したならば、より早く、より的確に、この組織のロジックに気づき、それを体得したメンバーが、より早くその組織の一員として適切な行動をするようになり、そして、当然のことながらそれは評価され、早く昇進していくことになる。これは日本企業の中において、ごく一般的に観察され、報告される経験的事実である。なかには「2階級上で何を考えているかを考えて行動しろ」というように、組織のロジックの体得を積極的に促しているような事例もある。こうした組織のロジックを的確に体得した者が早く昇進し、より高いポストにつくことで、組織のロジックは比較的正確に継承され、安定的にその組織の中に保持されていくことになると考えられる。
March & Simon (1958, p.65 邦訳p.100) が指摘するように、個人の諸目的(goals)は、組織にとって所与の存在ではない。①組織のメンバーを新規に採用する手続き (recruitment procedures)や②組織内の実践(organizational practices)によって、メンバーの目的を操作することができると考えられるからである。つまり、最初からその組織のロジックに馴染めそうな人々をメンバーとして採用し、その上で、さらに採用後の実践によって、組織のロジックを体得させることができるというのである。
Schein (1978, chs.8-9)はこのことをさらに詳細に、募集・選抜過程からキャリア初期までの間に、個人と組織のそれぞれの側で様々な判断が行われると分析している。個人と組織が相互に受容するためには、まず個人の側では、自分自身を試す機会があること、自分にやれて、十分にやりがいがあって、満足できる仕事があること、自分は価値があるとみなされていること、そしてこの組織に投資し続けるに足るほど自分のパーソナリティーと価値体系に合致していることが判定されなければならない。他方、組織の側では、その新従業員の勤務スタイル、態度、価値、およびパーソナリティーが組織に適合すること、そして組織に対して貢献するに足るだけの才能があることが判定されなければならない。双方がともに満足すると、個人と組織は相互に受容し、「心理的契約」(psychological contract)が形成される。これは、実際の条件が暗黙のままでどこにも記されていない点で心理的であるが、どちらか一方が期待に応えられなければ、モティベーション低下や異動、解雇という事態に至るという点で契約のように機能する。心理的契約は組織が提供するやりがいのある仕事、納得のいく労働条件、給与・諸手当等の報酬、昇進などのキャリア前進の見込みという形での組織における未来、そして、これらと引き換えに個人が提供する努力、貢献を明かにするのである。
さらに、Schein (1978, p.125 邦訳p.143)によれば、初期キャリアは新従業員と雇用する組織との間の相互発見(mutual discovery)の時とみることができる。継続的な試行と新しい職務挑戦(new job challenges)を通して、それぞれがもう一方をよりよく学ぶ。そして、新従業員は徐々に、自己認識(self-knowledge)を獲得し、よりはっきりした職業上の自己概念(occupational self-concept)を開発する。この自己概念は、
の3部分をもち、これらが一緒になって、人のキャリア・アンカー(career anchor)が作り上げられるというのである。キャリア・アンカーは、もし失敗しそうな環境、あるいは自分の欲求が満たされないか自分の価値が危うくなる環境に入るならば、何かもっとしっくりくるものに引き戻されるという意味で「錨」(いかり=anchor)として機能する。キャリア・アンカーは個人のキャリア全体にわたって安定し続けると考えられ、個人のキャリアを導き、安定させるように機能する。
Schein (1978, chs.10-11)は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology: MIT)の経営大学院Sloan Schoolの男性の同窓生44人を卒業10〜12年後に面接調査し、その結果として、内発的動機づけのときに登場した有能さ(competence)という概念も使いながら、次の五つのキャリア・アンカーによって、人の特性をグループ化している。
このようにみてくると、これまで「体温」として単にその大きさのみに関心を払ってきた個人の変化性向にも、実は、発揮されやすい分野や向けられている方向といった特性もありそうである。そこで、変化性向の大きさや量だけではなく、その内容や質まで含めて、組織のロジックとの関係を考えてみよう。
こうした採用による選別とその後の実践による補正により、各組織内では、その組織のロジックにあった人格やキャリア・アンカーをもったメンバーが多数を占めることになる。実際、1987〜1991年に5回の調査を行い、企業単位のヒアリング調査と各社での個人単位のアンケート調査を繰り返した結果として、一つの強烈な印象が残った。それは、企業によってそもそも人の質・種類が違うのではないかと思えるほど、人的特性が企業間で異質だということである。この多分キャリア・アンカーを中心として形成されていると思われる人材の質、性質を本書では「人質」(じんしつ)と呼び、「 」つきで用いることにする。人質は通常「ひとじち」と読むが、「人質」という用語を選んだことには次のような意味も込められている。
加護野・小林(1989)は、その企業にしかない技術の修得、仲間との協働のノウハウ、企業についての知識、人的なネットワークの形成というものが、その企業に勤める限りにおいて意味のある資源で、それを「企業特異的熟練」と呼び、当該企業に勤務し続ける限りにおいて、その価値を正当に評価してもらうことが出来ると考えている。そして、この熟練を形成するための時間とエネルギーの拠出が企業にとられた一種の人質となり、それが従業員にとっての退出障壁を形成するというのである。しかし、熟練の再学習に、移動をあきらめさせるほど多くの時間とエネルギーを要するとは考えにくい。むしろ決定的に重要なのは、特定の組織のロジックに適した「人質」の存在である。キャリア・アンカーのように、ひとたび形成されてしまった「人質」の変更は、おそらく企業の側にも人の側にも移動をあきらめさせるだけに十分な時間とエネルギーを要するはずである。つまり、「人質」(じんしつ)は人質(ひとじち)として機能することになるのである。
日本企業の採用活動は、人事部が中心であるということが、ほぼ共通する特徴として指摘されているが、極端な言い方をすると、採用の際には、各部門で必要とされているスキルよりもパーソナリティー、より正確に言えば、その企業のロジックへの適性の方が重視されていると考えることができるのである。このことは、国際比較した場合にはより際立った特徴となる。米国に進出した日本の自動車メーカー、例えばホンダでは、注意深い人材選考で、仕事に対する考え方や態度に焦点をおいて、詳細で綿密な選考を行い、ホンダ流のチームワークを理解でき、それを担える人材集めに努力を傾注していたと現地従業員の印象の中で指摘されている(島田, 1988, ch.2)。要するに、ロジックに合った「人質」を注意深く選考していたと考えられるのである。
このように、ある特定の組織のロジックの存在が、ある特定の範囲の「人質」をもたらすという側面があると同時に、逆に、ある特定の組織のロジックはそもそもある特定の「人質」を前提、仮定して組み立てられているのだという側面もあることに注意しておく必要がある。例えば、本書で取り上げた「組織活性化のための従業員意識調査」でも何行かが調査対象となった都市銀行のように、比較的良質でしかも同質的な4年制大学卒の男子を中心にした企業の場合は、一方の極である。こうした高水準で同質的な企業の場合、人事部によって、ジョブ・ローテーションによるスパイラル的人事が行われ、ゼネラリスト志向の強い評価、人事が行われることになる。しかも、メンバーも転勤等を厭わずに、こうした人事ローテーションにのっかっている。
しかし、こうした様式は一般的には当てはまるわけではない。いわゆる大企業と呼ばれる企業の中にも、人員規模こそ大きいものの、これほどには良質の4年制大学卒の男子を揃えるわけにはいかない企業も多いのである。例えば、1990年本調査の対象となった加工組立型のメーカー2社の場合、いわゆる賃加工業としてのコスト意識から、人件費、労賃の抑制のために、若年の低コスト労働力志向が強く働いている。そして、同時に、工程管理を行うための技術管理能力をもった少数の大学卒業の技術者、熟練工も必要としている。ところが、適応性の高い優秀な技術者は少なく、能力にもバラつきがあるために、人的資源に互換性がない。したがって、人事部を中心にした中央集権的なジョブ・ローテーションは一般的には不可能である。
実際、こうした企業では、管理職が優秀な人材を抱え込んでしまうケースも多い。そのため、ヨコの人事異動は部門間の「トレード」の形で行われることになる。つまり、たとえ人事部から優秀な人材を出せと言われても、一番優秀な人材は残しておいて、2番目以降からトレードに出されるようなことが起こる。その意味では、トレードに出される人材は、本当の意味での中核的なメンバーではなく、トレード要員としてのメンバーと考えられるケースが多くなる。そうした事情があるからこそ、「社内公募」制度が必要になるのである。しかも、たとえ、異動を行っても組織がきちんと機能せず、所属が変わったのに、仕事がその人について回ることも多い。つまり、組織図が形式的になり、実質的意味を失うこともあるのである。また多くの場合、仕事関係は非公式な人間関係の上で成り立つことになり公式の上長への組織上の関係は、事後報告で済まされることも多くなる。このように、前述の都市銀行などとは、まったく組織のロジックが異なるのである。
「人質」の組織のロジックへ与える影響を考えるという点では、1990年の予備調査の対象となった大手精密機械メーカーの生産子会社の例も興味深い。この会社は1973年に仙台市近郊に設立されたが、東北地方への進出を考えた理由は、親会社がもともと関東中心に工場展開をしている企業であったのと人材獲得の容易さであったといわれる。加工組立型である同社の場合、人的集約産業として直接作業員の数が必要になってくる。東北地方では、兼業農家、高卒の若い女子、男子などの層で、単に人件費が安いというだけではなく、首都圏と同じ賃金でより優秀な人材が集められる。東北地方の中で特に仙台市近郊が選ばれたのは、将来的には仙台港からの輸出もしたいとの期待と、周辺に、東北大学をはじめとする理工系学部をもった大学や宮城高専などがあり、技術スタッフを獲得する可能性を考えてのことだったといわれる。
ところが、高卒の女子作業員が、首都圏とは違う行動パターンをもっていることが次第にわかってきた。核家族化の進んだ首都圏では、女子作業員は結婚、出産を経てほぼ退職していくのに、地方の農村地帯では自宅があり、両親も同居もしくはそばに住んでいて、子供も預けられるために、地場産業と比べて賃金が割高な同社を退職せず、結婚、出産を経て年齢が高くなってもそのまま辞めずに残っていくのである。つまり、確かに、採用時には優秀で割安であった女子作業員が、次第に、優秀かもしれないが割高な女子作業員になってきたのである。このことは、賃加工業としては由々しき事態である。人件費が高くなってくれば、付加価値の高い製品で勝負するしかないので、そうした高付加価値製品の生産に対応できるだけの技術スタッフが必要になってくる。こうなってみると、周辺に、東北大学をはじめとする理工系学部をもった大学や宮城高専などがある仙台市近郊を選択しておいてよかったということになる。同社は製品の高付加価値化を進めていくことになるのである。こうして、当初考えもしなかった価値観をもったメンバーを知らずに選別せずに採用してしまったような場合には、組織のロジックは「人質」に合わせた変更を迫られることになるのである。
このように、ある特定の組織のロジックが、そもそもある特定の「人質」を前提・仮定して組み立てられているということは、組織のもつ重要な機能を示唆している。複数の個人の選好順序から一つの社会的選好順序を作り出す社会的厚生関数については、Arrow (1963)の一般可能性定理が明らかにしたように、民主的決定のもつべき諸条件を満たす社会的厚生関数は存在しないことがわかっている。つまり、個人選好の無制約性、パレート最適性、無関係対象からの独立性を満足させる決定方式は、必然的に独裁性をもち、ただ一人の人の選好順序が(他の構成員の選好にかかわらず)常に社会的選好順序として採用されることになってしまうのである。
しかし、こうした事態を通常われわれがあまり意識しないで済んでいるのは、われわれが自ら選んで自分の「人質」にあったロジックをもった組織に所属し、そして組織もそのロジックに合った「人質」を選択しているために、一つの組織内では「人質」が同質的になっているからだと思われる。つまり、そうした一つの組織の中に限定すれば、少なくとも個人選好の無制約性は配慮しなくとも済むようになっているために、一般可能性定理は成立しないのである。実際にはもっと強烈に、異なる選好順序をもとにして、組織の社会的選好順序を決めるのではなく、既に決められているある範囲の社会的選好順序に同意しうる選好順序をもつ人だけが集まってくるのだと考えられる。それがメンバーの意思決定の価値前提であり、より限定的には組織のロジックなのである。
「人質」が同質的であることの意義は、まず評価の容易さである。同質的であるからこそ、数値で評価したり、あるいは順序付けて評価することが可能になるのである。異質なものを一列に並べて、序列を付けたとしても、その序列は評価としてはほとんど意味がない。このような場合、さまざまな観点からさまざまな根拠に基づく評価が並存するのが自然である(佐伯, 1980, ch.8)。しかし、同質的な「人質」をもった組織がその「人質」と適合したロジックをもっている場合、あることが良いという評価基準が明確にされることで、それだけを狙った行動が喚起され、組織内部での熾烈な内部競争を引き起こすことになる。加護野・小林(1989)は日本の企業では従業員は組織の一員としての連帯意識を強くもっていると同時に、お互いにしのぎを削る競争者でもあり、いわゆる優良企業ほどこの内部競争は明瞭であり、顕在化していることを指摘しているが、これは優良企業ほど、組織のロジックの共有化と「人質」の同質化に成功しているということによって説明することが出来る。
ただし実際には、大企業で現業部門と間接部門(管理部門)がそれぞれ十分大きいような場合には、組織のロジックの共有化や「人質」の同質化がまた別の問題を引き起こすこともある。この点では、1987年調査の対象となったある鉄道会社の例が興味深い。この会社では、現業部門の一番上のポスト、例えば駅長は本社の管理部門の課長の下のポストになっている。現業部門では、駅長になることが昇進の目標になっているという一つの閉じた部門のロジックが出来上がっているので、現業部門のメンバーが、本社の管理部門との比較をしてしまいモラール上の問題が起きるということはない。問題があるとすれば、むしろこの会社の本社が鉄道以外にも事業を多角化しているにもかかわらず、本社の管理部門のメンバーは入社直後から現業部門での数年の実務経験を経て、管理部門に配属されるために、現業部門のロジックをそのまま受け継いでいることにある。例えば、評価制度については、大きな業績を残したかどうかよりも、失敗があったかどうかが重要視される傾向があり、一度の失敗がその後の評価に後々まで継続的に影響することが多いといわれている。また、計画的な異動は最近始めようとしているところで、同一部署に長く在籍する者が比較的多く、仕事の進め方も従来からのやり方を自然と継続・踏襲することが多くなっている。そして、昇進制度においては、評価が中程度の者が高い評価の者と同時に昇進することが多く、抜擢人事のようなこともほとんどないといってよい。査定の上下による昇給、賞与の金額差も比較的小さいといわれる。これは鉄道事業の現業部門のロジックといっていいだろう。この会社のような組織のロジックと実際の事業とのミスマッチのケースでは、多くのメンバーがぬるま湯感を訴えることになる。つまり、ぬるま湯比率の高いような組織では、特定の部門で、組織のロジックと「人質」が最初から構造的にミスマッチを起こしているようなケースも考えられるのである。
ぬるま湯現象は、不活性状態の典型的現象ではない。職務満足と共存しうることもわかっている。むしろそのぬるま湯感が体温の高いことを反映しているのであれば、生産性も高く、特に問題はないようにさえ思える。しかし、ぬるま湯状況を不活性化の典型と考えがちなのは決して根拠のないことではない。企業の成長性が低下してくることによってシステム温が低下して、ぬるま湯感が発生するからである。あるいは、組織のロジックと「人質」との構造的なミスマッチによっても発生するので、この場合には「人質」は活かしきれていないことになる。いずれも危険信号だと受け取るべきであろう。
しかも、たとえ、各個人の体温がパーソナリティーに近く、安定したものであっても、長期にわたって考えると、低システム温は低平均体温をもたらす。それは、各個人のレベルで体温を低下させるのではなく、低システム温に合った低体温の人間が採用によって入ってくるようになるからである。そのような人々は、もはや「ぬるま湯」とは感じない。「適温」だと感じるだろう。体感温度の問題だからである。これは状況の悪化を意味している。組織の平均体温の低下は、生産性や職務満足を着実に蝕んでいくのである。だからこそ、さしあたって直接、実害が伴わないからといって、「ぬるま湯感」というシグナルを見逃したり、放置したりしてはいけないのである。
仮に、本書で立てられた諸仮説が正しければ、ぬるま湯現象を巡る諸概念、諸変数の関係はこのようにまとめられるわけである。読者は、こうした枠組みから、具体的にどういった方策をとるべきなのかという示唆を期待しているだろう。しかし、現段階では、現象の理論的解明とその検証が中心であって、具体策については何も触れられてはいない。それでも何か……と求められれば、私は感想めいた私見として、次のように述べたい。
人的資源こそが、一番手間暇、コストのかかる資産である。そして、人には強弱の差こそあれ、変化性向があり、変化を求めている。ところが、体温の安定性からもわかるように、人は急には、そして大幅には変われない。だから高体温の人ばかりを集め、彼らのためにも組織のシステム温を高くしておかなくてはいけないなどと主張するつもりは毛頭ない。変化性向のような一面的な量的尺度だけを考えても、体温とシステム温のつりあいをとることは重要である。それを実際には質や内容まで考え、「人質」や組織のロジックまで考慮に入れた上で、まさに「適材適所」を図ることを考えなくてはならないのである。それを可能にするために大切なことは、
というように、個人と組織の両方に自由な判断と意思決定を保障することではないだろうか。この2原則に関して、できるだけ制約を付けず、その選択の自由度と機会とを保障しうるシステムをもった(これこそ平等な)社会・企業とその構成員が、結局は人的資源のパフォーマンスの点で優り、勝ち残っていくことになるだろう。そして、そのようにして勝ち残った一群では、体温とシステム温とは強い正の相関を示すはずである。
その意味では、本書で取り扱った「組織活性化のための従業員意識調査」の対象企業の多くは、調査データ上は体温とシステム温の正の相関を示しているので、全体的には今のところうまくいっているという一つの証になっているのかもしれない。ただし、各々の企業で、体温とシステム温のふつりあいから発生してくる「ぬるま湯感」は、こうしたシステムがきしんでいるシグナルであるということを忘れてはならない。
1987年に「ぬるま湯的体質」をテーマにした調査を初めて行って以来、5年間にわたって、ほぼ年1回のペースで、ぬるま湯的体質を何らかの形で取り上げた「組織活性化のための従業員意識調査」を行ってきた。この一連の調査のデータは本文中の随所で何度か繰り返して利用されているので、巻末付録として、ここに調査の方法をまとめておくことにする。「組織活性化のための従業員意識調査」の具体的な実施方法などについては、高橋 (1992d, ch.6)に詳しいので参照されたい。
まず5回の調査の目的、配布・回収状況については、表A.1、表A.2の通りであった。ただし、1990年予備調査については、本文中で、その調査データを利用しなかったので、ここでは割愛してある。
表A.1 調査の目的
| 調査の名称 | 主な引用章 | 調査の目的 |
|---|---|---|
| (1)1987年調査 | 第1章 | ぬるま湯感の調査 |
| (2)1988年調査 | 第1章 | ぬるま湯感の調査: 追試 |
| (3)1989年調査 | 第2章 | 成長性とぬるま湯感の関係の調査 |
| (4)1990年本調査 | 第3・4章 | 変化性向測定尺度の改良と職務満足の調査 |
| (5)1991年調査 | 第3・4章 | 変化性向測定尺度の改良と職務満足の調査: 追試 |
表A.2 配布・回収状況一覧
| 調査の名称 | 会社数 | 配布数 | 回収数 | 回収率 | 配布〜回収期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)1987年調査 | 11 | 690 | 580 | 84.10% | 1987.8.26〜9. 7 |
| (2)1988年調査 | 8 | 770 | 626 | 81.30% | 1988.8.31〜9. 5 |
| (3)1989年調査 | 10 | 1,392 | 1,228 | 88.20% | 1989.8.30〜9. 4 |
| (4)1990年本調査 | 9 | 959 | 853 | 88.90% | 1990.9. 5〜9.10 |
| (5)1991年調査 | 6 | 1,017 | 907 | 89.20% | 1991.8.28〜9. 2 |
| 計 | 44 | 4,828 | 4,194 | 86.90% |
各年の調査は、基本的にはほぼ同じ手続き、手順に従って行われた。調査対象は、日本生産性本部経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの参加者の所属企業である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われる。
第1段階のヒアリング調査では、毎年6月頃に、合宿形式で集中的に1社平均1時間以上をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われる。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつと筆者からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、問題意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行い、この過程でリストに挙げられた様々な質問項目を最終的に筆者が整理して、これをYes-No形式の質問にまとめるのである。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行う。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の組織単位を選ぶ。「組織単位」という概念は1990年本調査から明示的に用いられるようになったが、それまでの調査での「職場」にほぼ対応している。それまで職場を設定する際に、漠然とではあるが、暗黙のうちに使っていた基準を整理して
こうして設定された組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行うのである。全数調査の意味、意義、あるいは標本調査ではなく全数調査を行なう理由については、統計学の解説になってしまうので、本書では省略する。興味のある読者は、高橋(1992d, ch.1; ch.6)に解説されているので、それを参照されたい。
このような方法によって調査対象に選ばれた人に対して、毎年8月から9月にかけてのある水曜日に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、翌週の月曜日までに回収するという形で、留置法によって質問票調査が行われる。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行うことになっている。
正確には、この2段階の調査の後に、非公開の第3段階があり、質問調査票の集計結果、統計数字を前にして、グループで各社および全体について相互に何回かのヒアリングを行い、統計数字の背景にある実態の把握、各社でのフォローアップ・ヒアリング、うち数社についての事例研究などが次々と誘発されていくことになる。しかし、この段階で収集されたデータや事例は、グループの外には漏らさないことを前提にして収集されるものなので、この第3段階の調査データについては、筆者も論文等では特別の事前了解、許可がない限りは触れないことになっている。したがって、本書に記述されているものは、原則として第1段階、第2段階での調査データということになる。
以下に、各年の調査方法のより細部について、本文中より抜粋してまとめておく。
1987年調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1987年度の参加者の所属企業11社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1987年6月12・13の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの11人と筆者の計12人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、ぬるま湯現象を典型とする組織の不活性状態を表していると思われる職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、個人の仕事に対する姿勢に関する25の質問項目と、職場に関する25の質問項目の計50項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場を構成する正社員に対して、原則として、全数調査を行った。
各社において選ばれた職場数は1ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数数にも25人から154人まで開きがあるが、総職場数は39ヶ所、総調査対象者数は690人、職場当りの平均調査対象者数は17.7人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた11社690人に対して、1987年8月26日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月7日(月曜日)までに回収するという形のいわゆる留置法で、質問票調査が行われた。その結果、580人から質問調査票が回収できた。回収率は84.1%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
使用した質問調査票は、ぬるま湯現象を典型とする組織の活性化していない状態を表すと思われる、もしくは、逆に活性化した状態を表すと思われる前述の質問Ⅳ、Ⅴの計50のYes-No形式の質問項目の他に、個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。
1988年調査は中間管理職を対象として行われた。実は、1987年調査のような通常の調査でも、職位については調べているが、中間管理職に関する限りは、この形式的な肩書による比較は企業間比較の場合、適切ではない。というのは、企業によっては、「課長」でも一般に組合員であったり、肩書はなくても非組合員で、社内的に管理職として認知されているようなケースも珍しくはないからである。こうした事情から、中間管理職の識別には細心の注意が必要になってくる。そこで、この調査では、最低限、非組合員であるという条件をつけた上で、各社で社内的に中間管理職として認知、周知されている従業員ということで、「中間管理職」を定義し、実際にも、各社の社内での認定、抽出作業を行うことにした。その意味では、形式的な肩書による分類では得られない中間管理職の実態、実像に迫ることを意図している。
1988年調査で調査対象となったのは、1987年調査と同様に、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの今度は1988年度の参加者の所属企業8社である。調査は1987年調査と同様の手順を踏んで、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1988年6月17・18の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この質問票調査に参加する会社の各社1人ずつの8人と質問票調査には参加しなかった会社の2人、そして筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、職場内の現象、個人の仕事に対する意識の状態をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目がリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、個人の仕事に対する姿勢に関する25の質問項目と、職場に関する25の質問項目の計50項目のリストを作成した。これに1987年調査でシステム温、体温を算出するために用いた個人の仕事に対する姿勢に関する5つの質問項目と、職場に関する5つの質問項目をそれぞれに加えて、30問ずつの計60問の質問項目リストを作成した。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。1987年調査とは異なり、調査対象者は中間管理職に限定することにした。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選び、その職場の中間管理者に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は2ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数には30人から190人まで開きがあるが、総職場数は37ヶ所、総調査対象者数は770人、職場当りの平均調査対象者数は20.8人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた8社770人に対して、1988年8月31日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月5日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。
その結果、626人から質問調査票が回収できた。回収率は81.3%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。使用した質問調査票は、前述の60のYes-No形式の質問項目の他に、1987年調査と同様の個人属性に関する質問や一般的質問を含めたものである。
1989年調査で対象となった企業は、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1989年度の参加者の所属企業10社である。調査は、質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。第1段階として、まず、1989年6月9・10の両日に合宿形式で集中的に、1社平均80分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答が行われた。さらに、この各社1人ずつの10人と筆者の計11人からなるグループで、相互に何回かヒアリングを行い、各社の特性を浮き彫りにする作業が行われた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、一つまたは複数の「職場」を選んで、その職場の構成員に対して、全数調査を行った。各社において選ばれた職場数は5ヶ所から9ヶ所まで幅があるので、各社の調査対象者数にも93人から198人まで開きがあるが、10社全体で、総職場数は73ヶ所、総調査対象者数は1392人、職場当りの平均調査対象者数は19.1人となっている。1989年8月30日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月4日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、1228人から質問調査票が回収できた。回収率は88.2%であった。回収された質問票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
1990年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1990年度の参加者の所属企業9社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1990年6月15・16の両日に、合宿形式で集中的に1社平均70分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの9人と筆者の計10人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、予備調査の結果として絞られた35の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これはそれまでの3回の調査とほぼ同じ方法で行われたが、この年から、従来「職場」として漠然ととらえていたものを「組織単位」として明確に定義することにした。各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、 (1)で述べたように、組織単位を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には31人から245人まで開きがあるが、総組織単位数は39ヶ所、総調査対象者数は959人、組織単位当りの平均調査対象者数は24.6人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた9社959人に対して、1990年9月5日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月10日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、853人から質問調査票が回収できた。回収率は88.9%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
1991年本調査で調査対象となったのは、日本生産性本部の経営アカデミー『人間能力と組織開発』コースの1991年度の参加者の所属企業6社である。調査は質問調査票の質問を作成する前のヒアリング調査と、質問調査票を使った質問票調査の2段階に分けて行われた。
第1段階のヒアリング調査では、1991年6月14・15の両日に、合宿形式で集中的に1社平均120分程度をかけて、各社の会社の概要、組織的特徴、問題点、社風などを中心にして、報告、質疑応答等が行われた。さらに、そこで出された問題意識を基にして、この各社1人ずつの6人と筆者の計7人からなるグループで、相互に何回かのヒアリングを行い、1990年本調査で用いた10の質問項目のリストを包含する形で、会社・職場内の現象、個人の仕事に対する意識をできるだけ具体的にリストアップしていく作業を行った。この過程で、様々な質問項目が新たにリストに挙げられたが、最終的には筆者がそれらを整理する形で、計75項目のリストを作成し、これをYes-No形式の質問にまとめた。
調査の第2段階では、各社の職場単位での質問票調査を行った。これは1990年本調査と同じ方法で行われた。つまり、まず、各社のヒアリング対象者の所属する、もしくはそれに比較的近いホワイトカラーの部門を選び、さらにその中において、1990年本調査と同様に「組織単位」を一つまたは複数選び、その組織単位の構成員に対して、原則として、全数調査を行った。各社において選ばれた組織単位数は3から9まで幅があるので、各社の調査対象者数には90人から358人まで開きがあるが、総組織単位数は30ヶ所、総調査対象者数は1,017人、組織単位当りの平均調査対象者数は33.9人となっている。このような方法によって調査対象に選ばれた6社1,017人に対して、1991年8月28日(水曜日)に各社一斉に質問調査票が配布され、記入してもらった上で、9月2日(月曜日)までに回収するという形で、質問票調査が行われた。その結果、907人から質問調査票が回収できた。回収率は89.2%であった。回収された質問調査票は、あらかじめ決められた指示に従って、各社の担当者によって点検された上で、筆者がクリーニングを行った。
ここでは、第3章での体感温度測定尺度の改良に関連して、それまでの調査結果を踏まえて作成された「組織活性化度の測定手法の開発」のための質問調査票と、それに付随した調査結果、単純集計を掲載する。この質問調査票作りの作業は、その第一段階として、日本生産性本部経営アカデミー「人間能力と組織開発コース」を舞台にして、既に1987年、1988年、1989年に行われた組織活性化に関する調査において使用した質問調査票から、Yes-No質問項目を中心に候補となる質問項目を選抜した。その際の選抜基準は
ここで、1は誰が答えても明らかにYes、または明らかにNoとなる質問項目は除くという基準。2、3は会社間で回答に違いの出る質問項目を選ぶという基準。2、3で有意水準の基準が異なるのは、1989年調査の回収数1,228人(回収率88.2%)が、1987年調査の580人(回収率84.1%)、1988年調査の626人(回収率81.3%)と比べて約2倍になっているためである。実は、χ2の性質として、相関係数の大きさが同じクロス集計表でも、オブザーべーション数が約2倍の1989年調査ではχ2の値も約2倍になってしまい、その分だけ有意になりやすいためである。1987年調査、1988年調査の5%水準で有意なχ2の値はほぼ14程度なので、自由度(この場合、自由度=調査対象会社数−1)の違いも考慮して、0.1%水準で有意なものにほぼ相当すると考えた。したがって、3の真意としては、1987年調査、1988年調査で5%水準で有意になった程度の「相関」の大きさの質問項目を1989年調査でも選抜したいので、その目安として、0.1%水準を採用したということである。
3回の調査の中で、全く同一の質問を2回以上使ったこともあるが、そうした場合には1種類として数えることにすると、以上の選抜の結果、186種の質問項目が候補として残された。この186種の質問項目の中から、さらに第2段階として、「組織活性化度の測定手法の開発」のための調査用として、以下に示すような100種類の質問項目が最終的に選ばれた。ただし、Yes、Noの比率が80%まではいかないものの偏りの大きい質問項目などに対しては、新たに改訂・追加したものを選んでいる。 こうして作成された質問調査票を用いて行われた1990年予備調査についても、その集計結果を併記しているが、調査対象が2社のみだったために、χ2検定については行わず、単純集計だけを記している。
【質問項目に付された記号】
| # | …… | もともとはYes-No形式の質問ではなかったもの。 |
| ( ) | …… | 類似した質問。 |
| χ2 | …… | 当該質問のYes、Noと会社によるクロス集計表のχ2。検定の結果は*印で表示。 |
| (* p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001) | ||